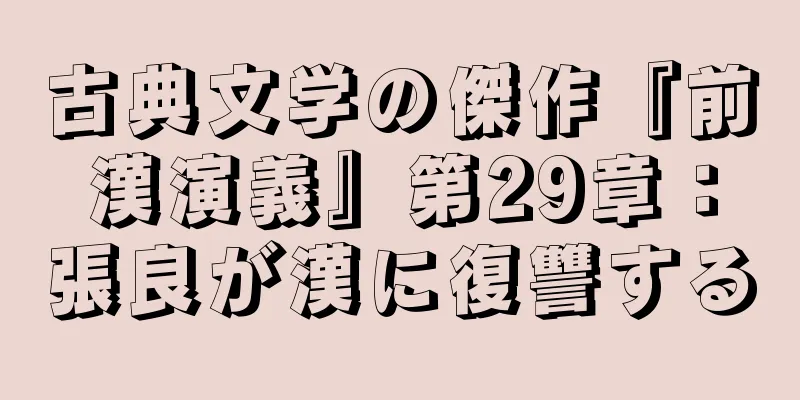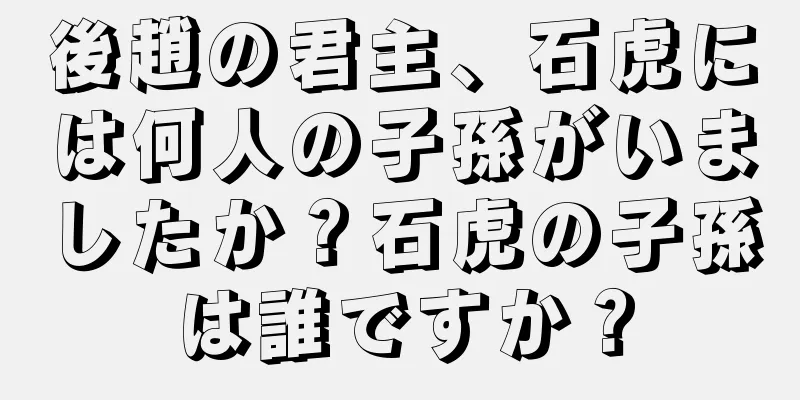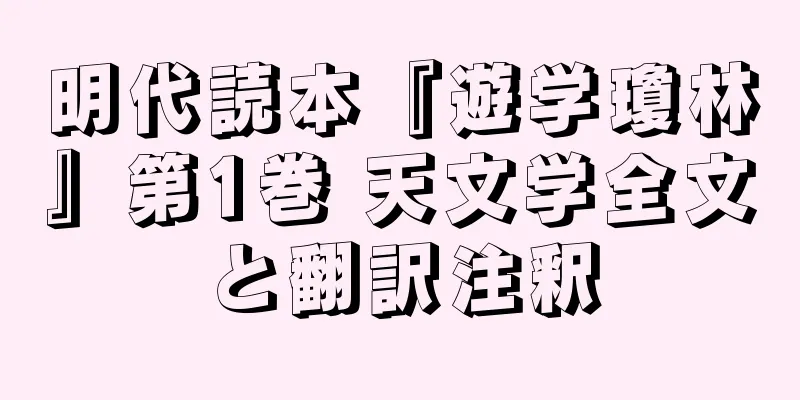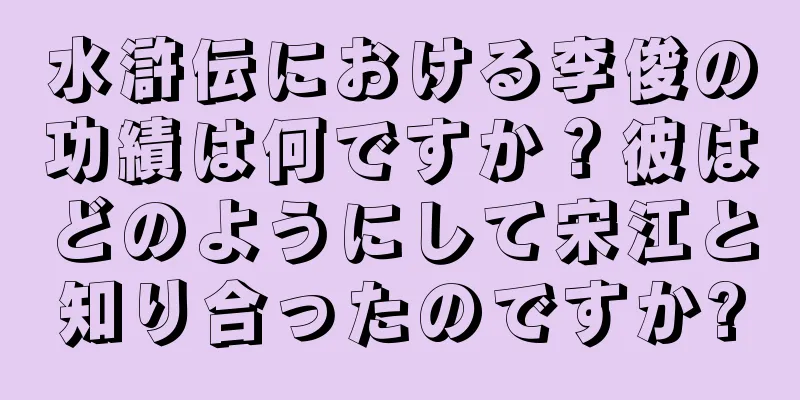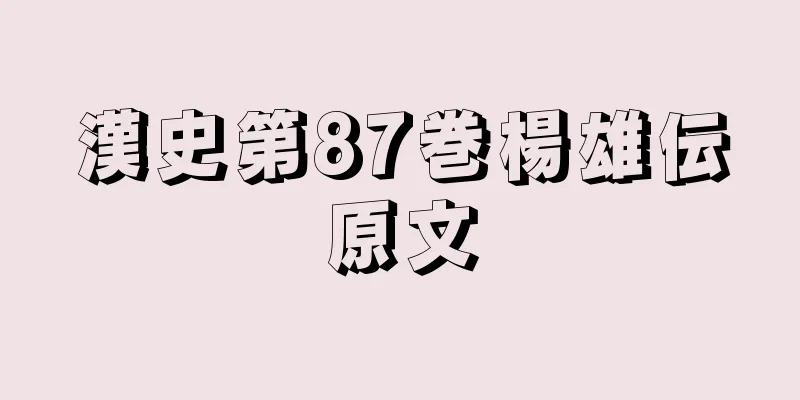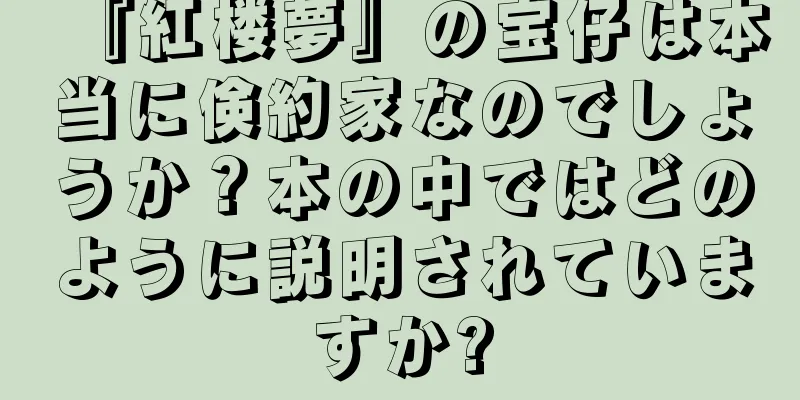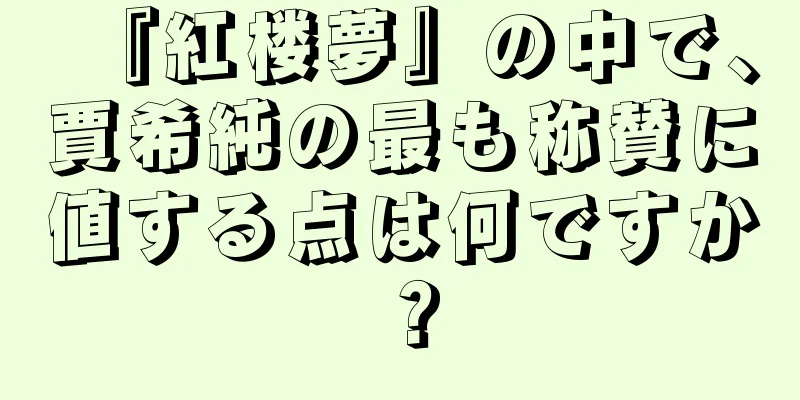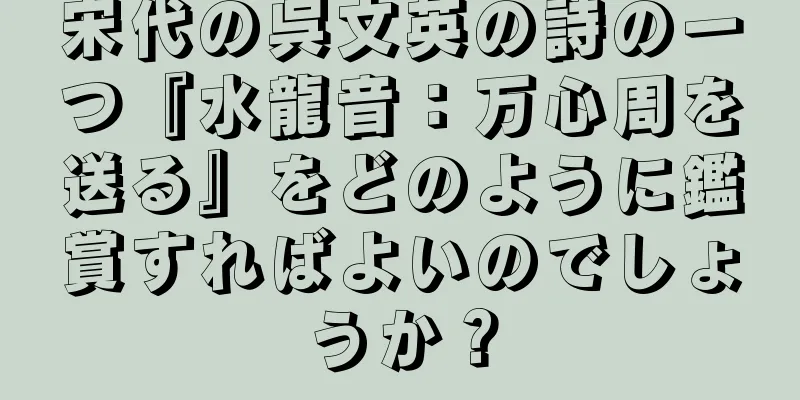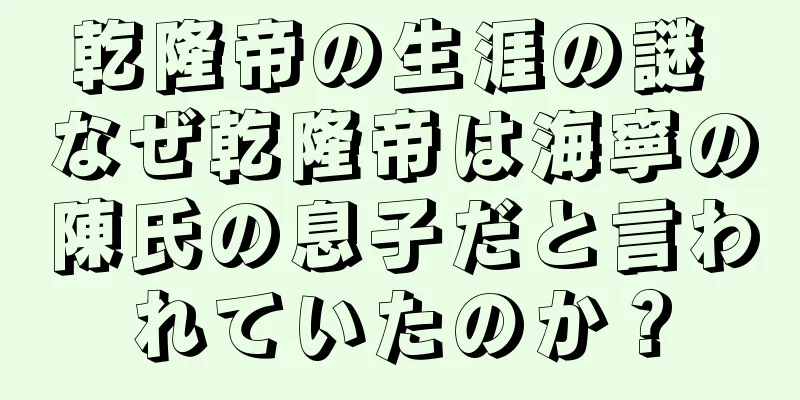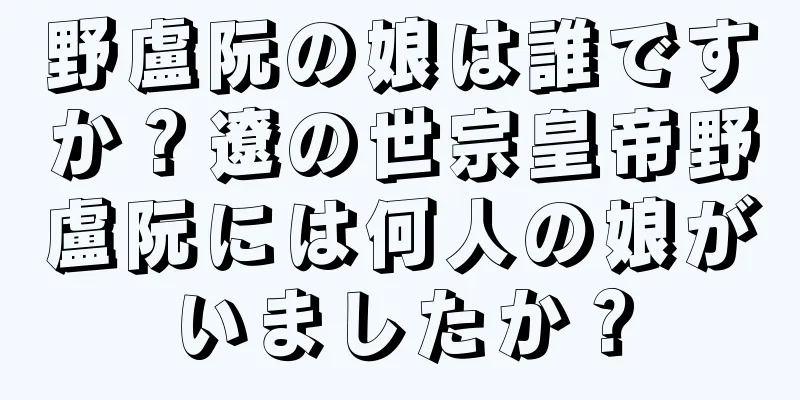戴樹倫の「辺境の歌二番」:去って二度と戻らなかった勇敢な男を歌う
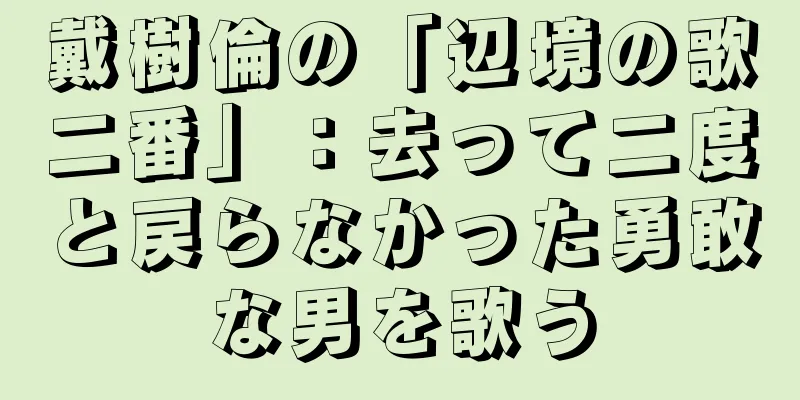
|
戴叔倫(732年頃 - 789年頃)は唐代の詩人で、字は有公(慈公ともいう)で、潤州金壇(現在の江蘇省常州市金壇区)の出身である。彼は若い頃、肖英師に師事した。彼は新城の知事、東陽の知事、福州の知事、栄冠の軍知事を務めた。彼は晩年、道教の僧侶になることを願う嘆願書を提出した。彼の詩の多くは隠遁生活やゆったりとした気分を表現しているが、「女農」や「屯田慈」では人々の生活の苦難も反映されている。彼は詩論において、「詩人の風景は藍田の暖かい太陽や、良質の玉から立ち上る煙のようなもので、目には見えるが目の前に置かれることはない」と主張した。それでは、次の興味深い歴史編集者が戴樹倫の「辺境の二つの歌、第2部」をお届けしますので、見てみましょう! フロンティアの二つの歌、第2部 戴叔倫(唐代) 殷山には漢の旗が掲げられ、胡の子馬一頭も帰還を許されなかった。 私は一生祖国に奉仕したいと思っていますが、なぜ玉門峠に行く必要があるのでしょうか? 戴樹倫の『辺境の歌』は2つの詩から成り、どちらも7字四行詩である。これは2番目です。この歌は最初の歌「辺境の歌:将軍はよく降伏文書を受け取る」よりずっと簡単です。そこには「生きて玉門関に入る」という暗示が含まれています。 「生きて玉門関に入る」という言葉は、もともと定遠侯の班超の言葉です。これは、班超が30年以上西域の使節を務めていたことを意味します。彼は年老いて故郷に帰りたいと思い、手紙に「酒泉県に入ることは望めませんが、生きて玉門関に入ることを望んでいます」と書きました。潘超氏は30年間西部地域に駐在し、国と国民のために尽力してきた。故郷を懐かしみ、老後に帰国したいと願うのも無理はない。しかし戴樹倫の意見では、潘超の愛国心は十分ではなかった。彼は「生きて玉門関に入る」ことを提案すべきではなかったし、「生きて玉門関に入る」ことを提案する必要もなかった。彼はただ祖国に奉仕することに集中すべきだったのだ。戴樹倫の愛国心は素晴らしいし、最善を尽くすという決意も良いが、実際の班超の例に当てはめると、それほど人道的ではない。この暗示を知ると、詩全体の意味が明らかになります。最初の連句は、漢軍が敵に対抗するために重装兵を派遣し、胡軍の兵士を一人たりとも逃がさなかったことを語っています。そして、前述の物語が起こります。玉門関に戻るのではなく、国のために国境に平和をもたらすために死ぬ必要があるという信念を持って胡兵士を打ち負かします。 戴の詩は、先代の開拓詩と同じスタイルで、英雄的な志を表明しており、その多くは、決して帰らない戦士の英雄的な精神を歌っています。時代の特徴に対する分析、判断、および関連する命題については、やや抽象的です。上記の詩が唐代中期の戴の詩として注釈されておらず、他の時代の詩であると気軽に言われているのであれば、疑問を呈することは難しいでしょう。 |
<<: 陳涛の「隴渓行四詩集 その2」:この詩はあまりにも悲しくて涙が出てくる
>>: 高石の『辺境で笛を聴く』:郷愁は微妙で意味深く、人々にいつまでも噛み締めさせる
推薦する
孫子の『算経』で「韓信の視兵」と呼ばれる算数の問題は何ですか?
淮安の民間伝説には「韓信が軍を視察する」という話があり、それに続いて「韓信が軍を視察する、多ければ多...
水滸伝で傑珍はどんな経験をしたのでしょうか?なぜ彼は天岡スターズに選ばれたのでしょうか?
双頭の蛇「傑真」の紹介桀震は『水滸伝』に登場する涼山の英雄108人のうち34人目であり、双頭の蛇の異...
程浩の「春の日の折々の詩」:詩人の青春と故郷黄陂への郷愁
程昊(1032年2月28日 - 1085年7月9日)は、号を伯春、号を明道といい、通称「明道氏」と呼...
荘景和碩公主の実の母親は誰ですか?荘景和碩公主の夫は誰ですか?
荘景和碩公主の実の母親は誰ですか?荘景和碩公主の夫は誰ですか?荘景和碩公主(1781-1811)は、...
春秋戦国時代以降、官僚が商売をする話はあまり聞かなくなったのはなぜでしょうか。
役人が商売をしてはいけないというルールは、ほとんどの人にとって馴染みのあるルールでしょう。しかし、こ...
「2月2日龍が頭を上げる」とはどういう意味ですか?ドラゴンを家に招き入れる4つの方法
「二月二日は龍が頭を上げる」とよく言われますが、これはどういう意味でしょうか?実は、龍が頭を上げると...
水滸伝で、涼山の英雄のうち誰が虎と戦ったでしょうか?結果はどうですか?
『水滸伝』には、梁山泊の英雄108名が登場します。これらの英雄たちは、性格的に類似点がありますが、非...
『リトル・ピーチ・レッド 川辺の水灯籠』の執筆背景を教えてください。どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】春の橋には何千もの光が輝き、その光は10マイル先まで輝き、舞う鳳凰と飛ぶ鳳凰の姿は壮観...
古代の月餅はどんな感じだったのでしょうか?昔の月餅は美味しかったのでしょうか?
古代の月餅はどんな感じだったのでしょうか?古代の月餅は美味しかったのでしょうか?Interestin...
明末から清初期の偉大な学者顧延武はなぜ科挙制度を批判したのでしょうか?
私たちは皆、子供の頃から「人は皆、自分の国の運命に対して責任を負っている」という格言を聞いてきたと思...
『紅楼夢』で、希仁は自分と宝玉との関係をどのように見ているのでしょうか?
希仁は『紅楼夢』の登場人物です。彼女は金陵十二美女の一人で、宝玉の部屋の四人の侍女の長です。次回はI...
「湘飛元:民柵と酒旗」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
項飛の苦情:他人の塀にワインの旗を立てる馬志遠(元代)人々の家の塀にはワインの旗が垂れ下がり、冷たい...
古代では「ベッド」は何に使われていたのでしょうか?魏晋南北朝時代の「便」の代用品!
今日は、Interesting History の編集者が、古代の「ベッド」は何に使われていたのかを...
軍事著作「百戦百策」第9巻「囮戦」全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
唐代の詩の鑑賞:七つの田園詩、第 5 番。この詩ではどのような芸術技法が使用されていますか。
唐代の王維作『七田歌集 第五番』。以下、Interesting History編集部が詳しく紹介しま...