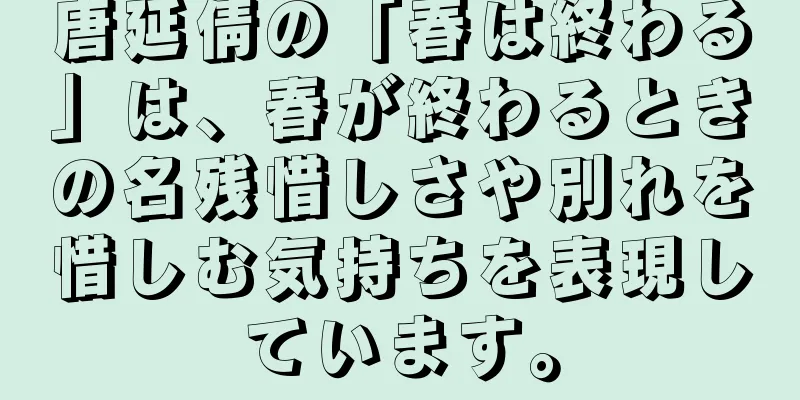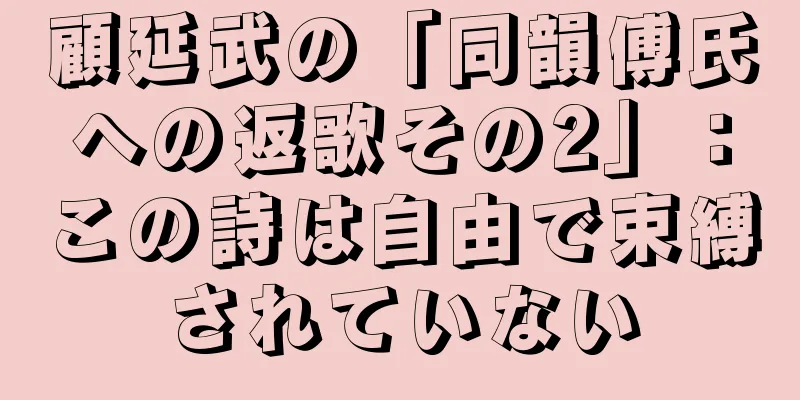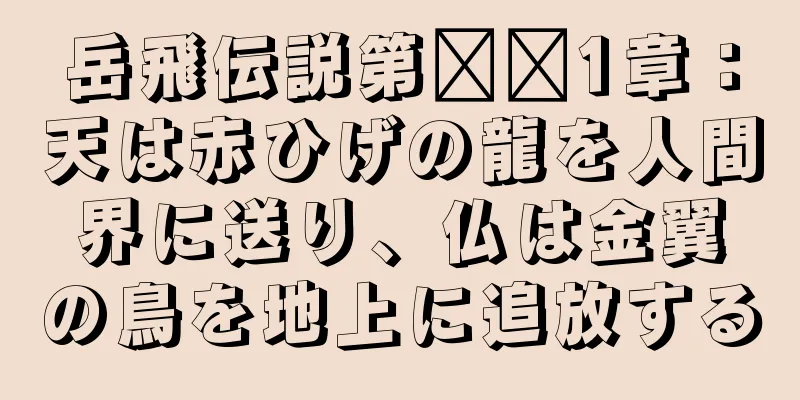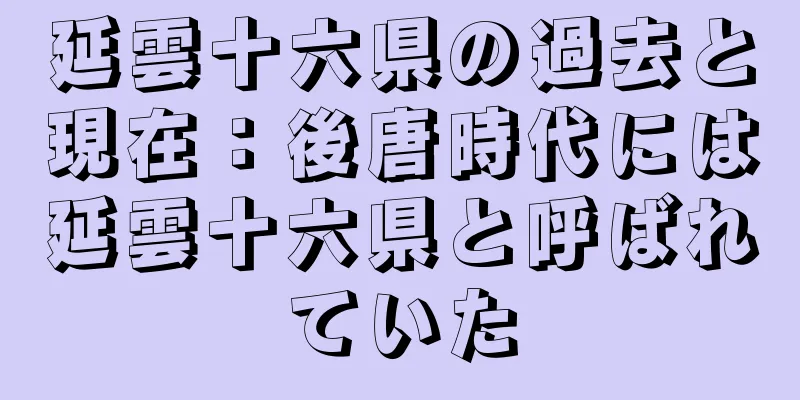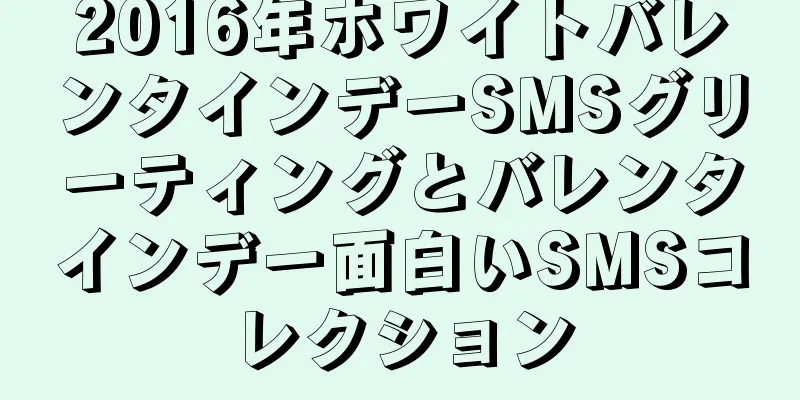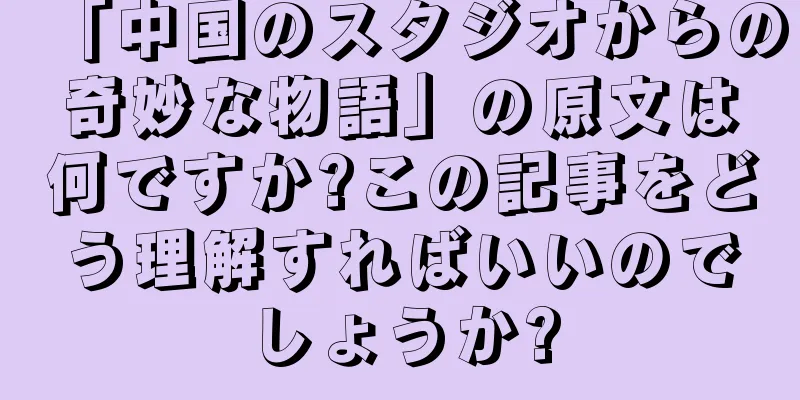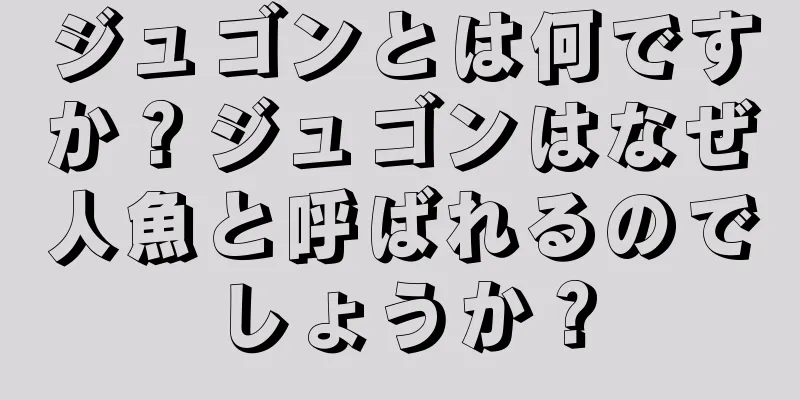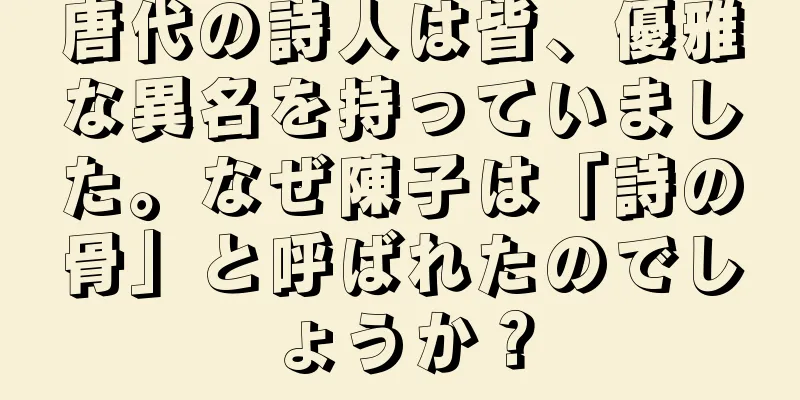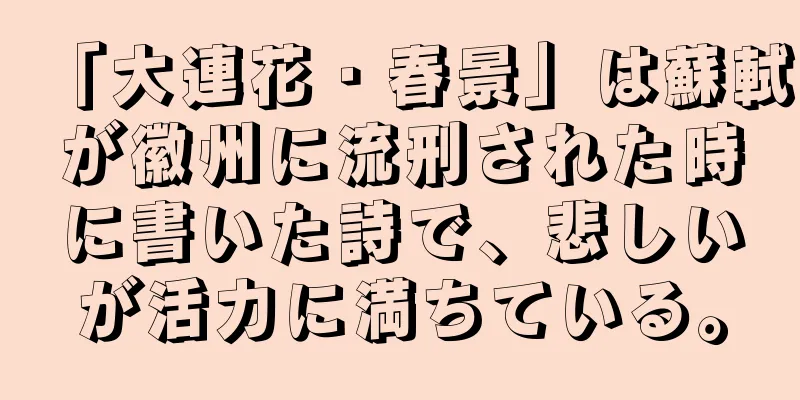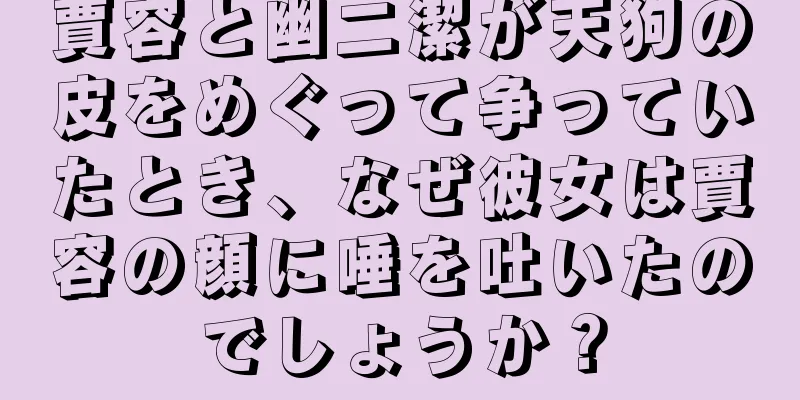南宋時代の詩人楊延政の詩集「水歌:斜陽に向かい酒を飲む」を鑑賞
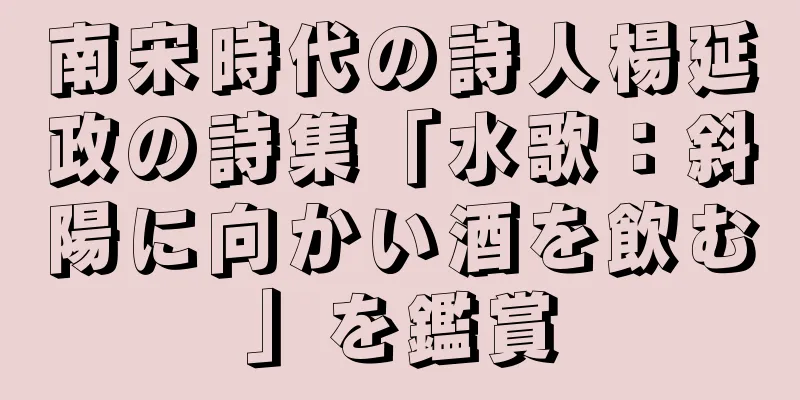
|
以下、面白歴史編集長が楊延正の『水条閣頭・斜日に向かって酒を飲む』の原文と評価をご紹介します。ご興味のある読者と面白歴史編集長は一緒にご覧ください。 水の旋律の歌:夕日を眺めながらワインを飲む (宋代)楊延政 沈む夕日を眺めながらワインを飲み、静かに西風に問いかける。紅の用途は何ですか?蓮を染めるのに使われます。夕暮れの広大な川を眺めていると、渡り鳥を着陸させる場所もなく、果てしない悲しみを感じます。空は手すりの角にあり、人々は半分酔っていて半分目覚めた状態でそれに寄りかかっています。 浙江省の南から北、西から東まで数千マイル。私の人生は仮住まいのようなものです。それでも、三道の菊が恋しいです。私を漁師にするために五湖で船を貸してくれる中州の英雄は誰ですか?故郷を振り返って、この考えに急いで飛びつかないでください。 注記 水旋律歌:琴曲の名称で、「元徽曲」「開歌」「太成遊」「水釣歌」「花帆年女」「花帆」とも呼ばれる。茅龐の『元会曲・九金増宋評』を基準とし、95語の二重韻文で構成され、前半は9つの文と4つのレベルの韻があり、後半は10の文と4つのレベルの韻がある。 ハイビスカス:蓮です。ここでは秋の蓮を指します。梁昭明王の『芙蓉歌』には「夏に香り高く咲き、晩秋に鮮やかに咲く」とある。 胡 (hú): 古代の容量の単位で、10 斗が 1 胡に相当し、後に 1 胡あたり 5 斗に変更されました。 「万湖」は悲しみが大きすぎることの比喩です。 「空はそこにある」という2つの文章は、私が半分酔っていて半分目覚めている状態で手すりに寄りかかって外を眺めていて、手すりの角から一筋の天窓が見えるという意味です。 如意:人生の短さの比喩。 三道菊図:趙斉の『三府覚略・道明』では、漢代に蒋旭が官職を辞して故郷に戻り、家に閉じこもり、庭前の竹の下に三道(小道)を開き、秋忠と楊忠とだけ交流したと記されている。後に、この隠者の住居は「三道」と呼ばれるようになった。陶謙の「帰郷」:「三道は寂れているが、松と菊はまだそこにあります。」これは意味の言い換えであり、田舎に戻ることを示しています。 中州:黄河の中流と下流。 五湖:太湖周辺の地域。これは湖や海での隔離を意味します。 祖国: 中原を指します。 方言翻訳 私はワイングラスを持ち、西風に問いかけるかのように静かに沈む夕日を眺めた。ルージュはなぜ蓮をあんなに赤くするのでしょうか?広大な川を眺めていると、別れの悲しみが尽きず、飛び交う野鳥の休む場所もない。手すりの隅からは一筋の太陽の光だけが覗いていて、半分酔っていて半分目覚めている男が手すりに寄りかかっていた。 彼は全国を旅し、浙江省の西部と東部を訪問した。人生は短すぎる。私はまだ小道の生垣のそばの菊の間を散歩したい。中原の英雄で、私に船を貸して五つの湖を渡らせて漁師にさせてくれる人は誰なのだろうか。この滅びた故郷を振り返って、田園地帯の田舎に急いで戻らないでください。 感謝 秋への郷愁がよく表れた詩です。 彼は金朝に対する抵抗を強く主張した愛国者であったが、統治者の非抵抗政策により、彼の優れた才能と高い志を発揮することはできなかった。この詩は、彼自身の人生経験を語ることによって、国と国民に対する愛国的な熱意と関心を表現しています。それはまさに、時代に対して感傷的になり、不満を感じている彼の心理的活動を反映したものです。この詩の主な雰囲気は悲しみと悲哀ですが、作者は完全に落ち込んで立ち直れないわけではありません。この詩は全体の構想と文章構成が独特で、大胆で憂鬱でありながら、優雅で優美で、芸術的にも独特の特徴を持っています。 詩の前半は、自分の才能や野望を実現できないことに対する悲哀と憂鬱を表現しています。最初の 2 行は、詩人の悲しみを控えめに表現しています。太陽は西に沈み、詩人はワイングラスを手に持ち、風の中に立って何かを考えており、突然奇妙な質問をします。沈む太陽は、風景を描写し、時間を示すことに加えて、時間の経過を書き、時間の浪費や青春の喪失感を暗示するという想像上の意味も持っています。 「一言も言わずに西風に尋ねる」とは、質問は心からのものだが、声には出さないという意味です。質問は西風についてですが、これは秋の季節を示すだけでなく、前の文の「斜陽」と同じ意味を持っています。これら 2 つの文は相反するものであるため、人々はそれに気づきません。次の2つの文「Rouge」は、当然ながら質問の内容です。 「ハイビスカス」とは蓮のことで、ここでは秋の蓮を指します。梁昭明王の『芙蓉歌』には「夏に香り高く咲き、晩秋に鮮やかに咲く」とある。花は真っ赤なので、詩人は西風に尋ねます。「なぜ秋の蓮を染めるのに紅を絵の具として使うのですか?」東風が春の花の主であるように、西風も秋の花の主です。少なくともここで詩人はそう考えています。この質問は当然ながら不条理で不合理です。なぜこの質問をするのですか? 詩人が川辺に来ると、秋の川が真っ赤でまばゆいばかりの蓮の花で満ちているのが見えました。それは詩人のその時の気分とは大きく異なっていました。それで詩人は心の中でつぶやき、このような奇妙な考えを思いつきました。ちょうど春が来るのを悲しんでいる人が、花が咲いたことを責め、鳥が鳴いたことを責めるように。これは詩人の悲しみをひそかに表現した斬新な書き方で、とても憂鬱です。 「夕河千里を眺めて」という文は、蓮華を見たときにすでに河のそばにいたことを述べており、省略がなく、「夕」という言葉が「斜陽」に応答しているという前の文を完結している。この広大な川は、「果てしない別れの悲しみを運び、渡り鳥が降り立つ場所もない」という、悲しみについて書くという主題を浮き彫りにしています。昔の文人は悲しみを表現するのにさまざまな方法を持っていました。李游は「東に流れる湧き水の川」(于梅人)を比喩として使いました。何卓は「タバコの川、街中が花穂でいっぱい、梅が黄色いときに雨が降る」(清源庵)を比喩として使いました。李清昭は「二つの川に小舟が浮かんでいて、何も運べない」(武陵春)を比喩として使いました。彼らは皆、斬新な発想とユニークな概念を持っていました。ここで詩人は于鑫の「私の心の一寸に一万胡の悲しみがあることを誰が知っているだろうか」(『悲歌』より)という一節を言い換え、「一万胡」を使って悲しみは測れるが網羅的ではないことを表現し、抽象的で無形の悲しみを具体的で鮮明なものに変え、比喩を適切で鮮明なものにしている。続く「どこにも」という一文は、悲しみの深さを改めて表現し、悲しみの感情を強めています。「川は別れの悲しみで満たされ、鳥さえも止まる場所がなく、ましてや人間はいない。悲しみは果てしなく、そこからどれほど悲しく荒涼としているかが想像できます。」この文は、上記の 2 つの文の比喩的な比較に基づいて悲しみに重厚な感触を加え、完全に表現します。上記の7つの文は4つの層に分かれており、叶わなかった志の悲しみを表現しています。 薄い文字から濃い文字、明るい文字、そして最後に濃い文字へと、層ごとに段階的にレンダリングされます。この光と闇、明るさと暗さの対比の中で、憂鬱さがより強く鮮明に現れます。当時、詩人はすでに34歳で、まだ平民でした。世界を運営する才能に恵まれているのに、それを発揮する場がないというのは、実に悲しいことです。 「国のために死ぬ覚悟はあるが、戦場がない」という悲壮感と憂鬱感が余すところなく表現され、クライマックスを迎えます。そこで詩人は自由に書いた後、軽い書き方で口調を穏やかにします。 「空は柵の角にあり、男は半分酔って半分目覚めた状態で柵に寄りかかっている」:夕暮れは広大で、柵の角には一筋の天窓しか見えず、柵に寄りかかっていると悲しみから逃れるのは難しい。 「酔いしれず」とは、酔っているわけでも酔っていないわけでもなく、酔っているようでいてまだしらふの状態を指します。酒を飲んで悲しみを忘れ(酔う)、それから世界を観察する(目覚める)という組み合わせです。蘇東坡が『江澄子』の詩で言った「夢の中でははっきりしているが、酔っていると目が覚める」という言葉に似ています。詩人が酔うのは、落ち込んで心配しているからであり、眠らないのは、心の中で恨みを感じていて、野望が達成されていないからである。この二つの文章は、前半で別れの悲しみを醸し出すだけでなく、後半で心理的な葛藤を引き起こします。構造は多彩で、感情はよく整理されており、視覚的なイメージは気楽で愛国心のある人物の素晴らしい姿を表現しています。 詩の後半では、詩人は文体を変え、国に奉仕することと田舎に戻ることの間の心理的矛盾を描くことに焦点を当てています。開けたり閉じたり、リラックスしたり手放したり。まず、移行部の3行は、前の部分のテーマを引き継いでおり、詩人は異国の地を旅し、風雨に晒され、さまよい、漂流するという人生の歩みを描写しています。次に、人生は一時的な滞在のようなものだという気持ちを表現し、陶淵明の「田舎に帰る」の詩的な意味を言い換えて「三道は寂れているが、松と菊はまだそこにあります」と田舎への思いを表現しています。そして彼は怒りながら質問を続け、こう尋ねた。「この国の英雄は誰ですか?」答えは明白だ。私以外にこの国の英雄は誰ですか?そして英雄はどこでその技能を使えるのですか?詩人はどうしようもなく言った。「川や湖を巡るのにボートを貸してください」。私は范芬博士の例に倣って、釣りをする隠者になりたいです。退職後の気分が繊細かつ心のこもった方法で表現されており、非常に充実した表現となっています。 これらの詩節は、詩人が人生におけるさまざまな挫折や、実現されなかった野望や理想によってやつれ、挫折し、無力になったことを真に反映している。詩「水の歌 多井楼に登る」には「国のために尽くす術もなく、頭が真っ白になるのは残念だ」「河上の月を頼りに、カモメに想いを託す」という一節があり、こうした思いが率直に表れている。この考えは当時の愛国心ある愛国者たちの間では一般的かつ典型的なものでした。これに応えて辛其記が歌った歌詞の中には、「旅に疲れて、川へ出て、この手で何千ものオレンジの頭を植えたい」というものがある。心の底からのため息と憤りがこみ上げ、苦しみと痛みに満ちている。最後の 2 つの文には、語調に休止があります。国と故郷を離れ、田舎に引っ込んでいくという感情の奔流が押し寄せてきたとき、突然、堰堤が下ろされた。詩人の祖国への誠実な決意が力強く表現され、故郷の山河に対する限りない愛着が表現され、全てを捨て去りたいが迷い続ける詩人の心情と、誠実で忠実な性格が生き生きと再現されている。これは屈原の愛国心「突然故郷を見渡すと、召使は馬のことを悲しんで、馬は体を丸めて振り返ったが、動けなかった」(李托)と一致している。 |
推薦する
南宋は金王朝と対峙していたにもかかわらず、なぜ北宋よりも100年以上も長く続いたのでしょうか。
趙匡胤によって建国されて以来、北宋は北方の遊牧民からの軍事的脅威に直面してきた。その中で、契丹と西夏...
明代志農(選集):程英の芸術智慧篇全文と翻訳
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
「彭公安」第62章:キングコングは、窮地に陥った女性、于秋祥を救うために寺を訪れ、命をかけて泥棒たちを叱責する
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
劉瑜は高い戦闘能力を有していただけでなく、いくつかの軍隊編成を考案しました。
南朝の初代皇帝である劉裕は、南朝時代で最も軍事力の強い皇帝であると言える。生涯を通じて軍事上の功績が...
トゥファ・リルには何人兄弟がいますか?トゥファ・リルの兄弟は誰ですか?
吐法礼禄固(?-402)は、河西出身の鮮卑人で、十六国時代の南涼の君主であった。吐法五固の弟であり、...
史公の事件簿 第70話 順天県が到着し、楊歌舞が出発する
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
斉における管仲の改革
「土地の質に応じて税を徴収する」とは、土地の質と生産量に応じて田をいくつかの等級に分け、等級に応じて...
易張紅は本当に存在するのか?ハーレムの側室を罰する古代の刑法の秘密を解明する
『真歓伝』で華妃が夏妃に授けた「易章紅」に感銘を受けた友人は多いと思います。では、易章紅は本当に歴史...
第75章: 孫武が戦闘隊形で梅吉を殺害、蔡昭侯が呉に人質として降伏
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
秀雲亭第48章:湖畔亭で幽霊を語る江月珍がピアノを弾く
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
『紅楼夢』の母娘、チュニャンと母のポジは、どのようにお互いを愛し、憎んでいるのでしょうか?
母と娘の間には、愛し合い殺し合うという別の種類の関係もあります。 Interesting Histo...
水滸伝の潘喬雲とは誰ですか?彼女はなぜ楊雄を裏切ったのか?
潘喬雲は小説『水滸伝』の登場人物で、肉屋の潘公の娘である。 Interesting History ...
『西遊記』では、天宮で桃の節句が開かれましたが、孫悟空は招待されませんでした。なぜでしょうか?
桃の宴は、中国の神話や伝説に登場する天国での盛大な祝賀儀式です。次のInteresting Hist...
「十二塔」:桂正塔・財宝と食料、そして金銀の損失
『十二塔』は、明代末期から清代初期の作家・劇作家である李毓が章立てで書いた中国語の短編集です。12巻...
蘇軾の『青年旅記:潤州で書き、遠く離れた男に送った詩』:夫婦の深い愛情が表れている
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...