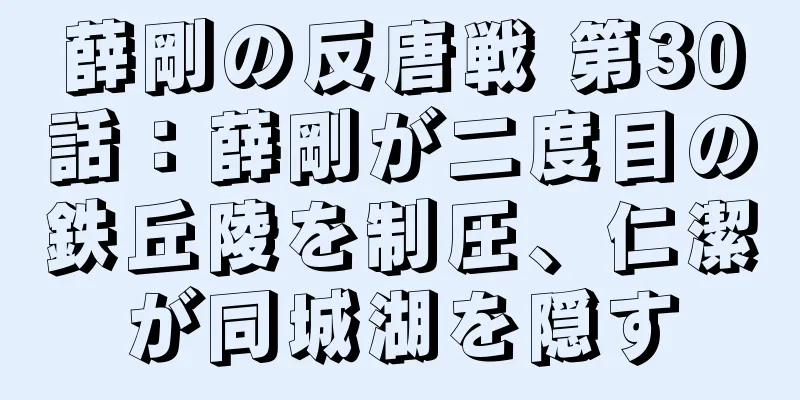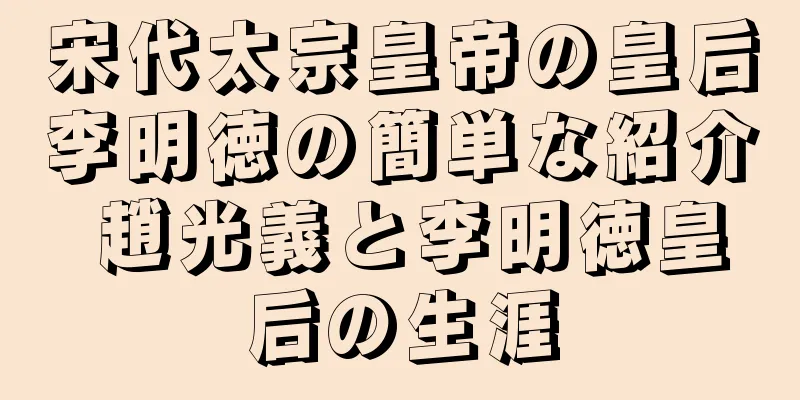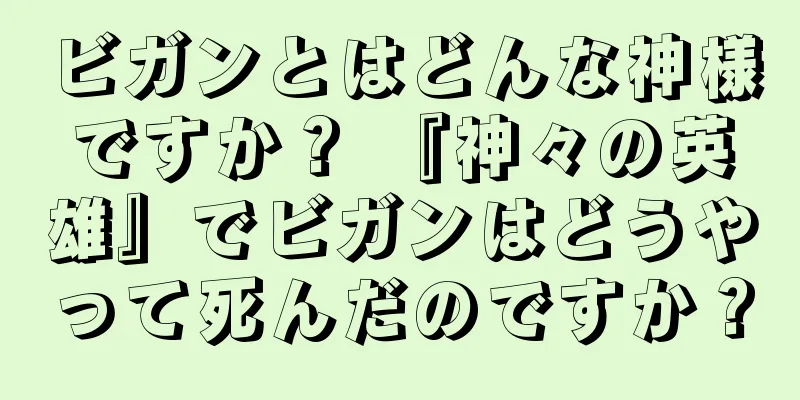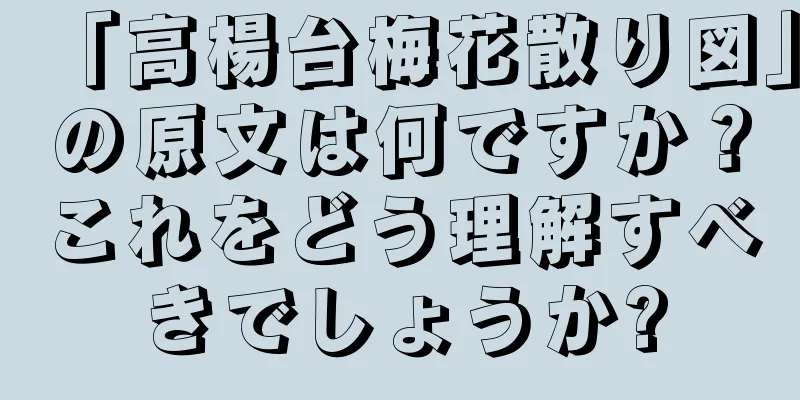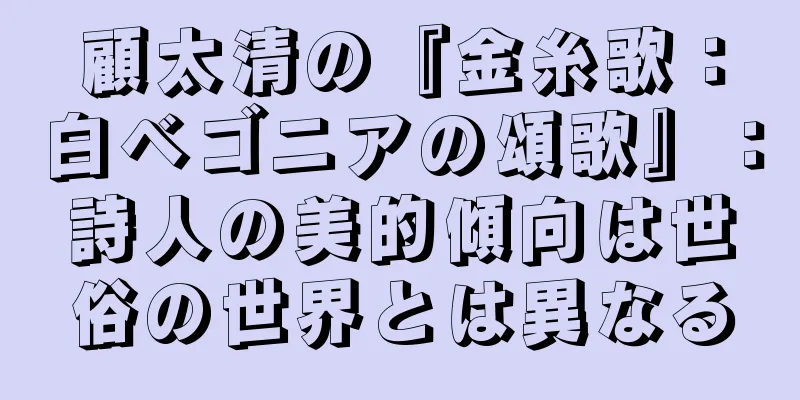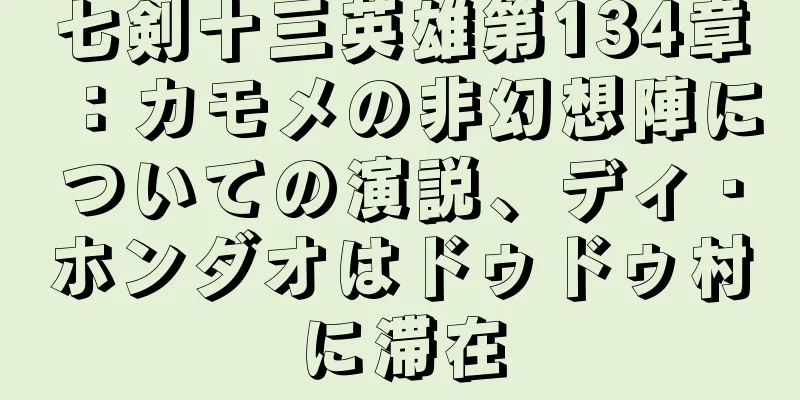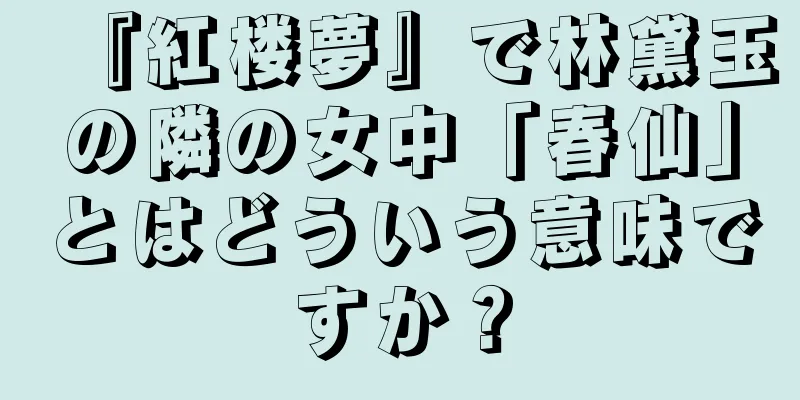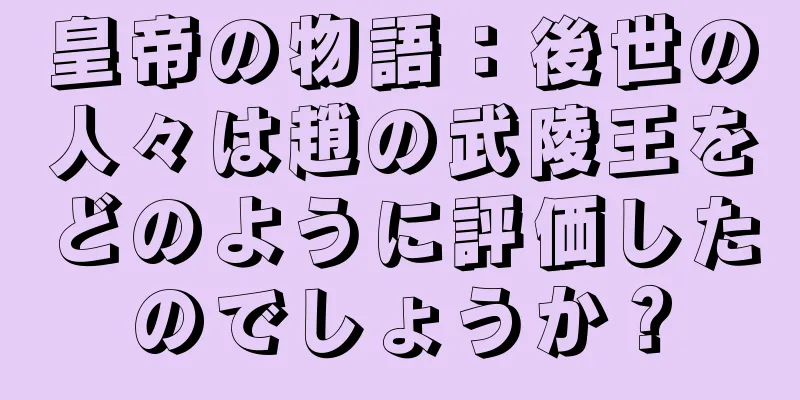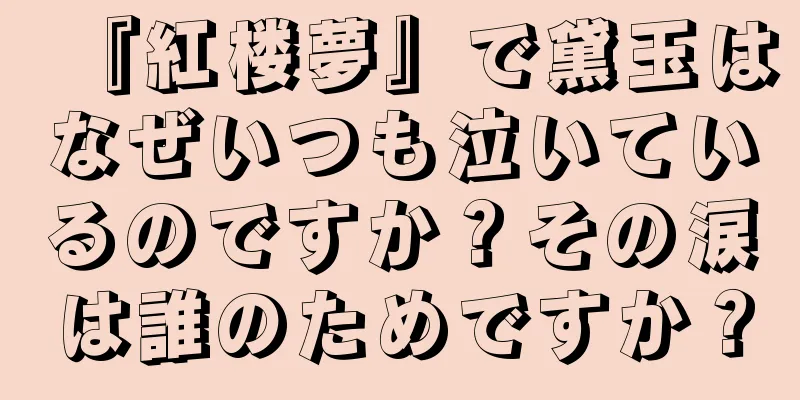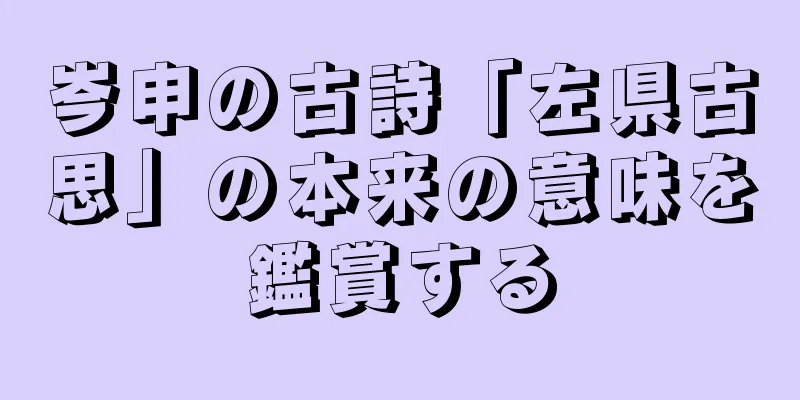古典文学の傑作『太平楽』:「臨界」編第12巻
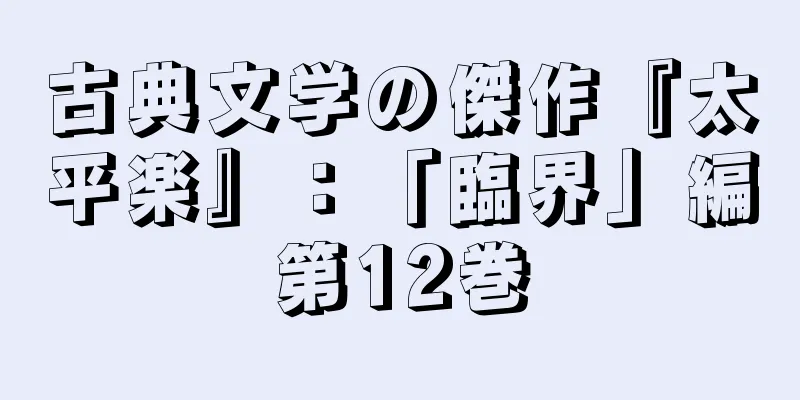
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、Scales and Shells Volume 12 の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう。 ○寒天 『漢武内伝』には、西王母が「仙人は薬を授け、深海には玉魚がいる」と言ったとある。 ○スギナ 「神易経」はこう言った。「北の荒野に石の湖があり、そこには長さ7~8フィートの横向きの魚が住んでいる。形は蛇の頭に似ているが、目は赤い。」昼間は湖の中にいて、夜になると人間の姿に変身します。トゲが刺さらず、煮ても調理できず、黒梅を27分間煮るだけで調理されます。それを食べると悪い病気を防ぐことができます。 (玄奘経には「横公魚は殺せないが、黒梅を加えることでその気を滅することができる」とある。) ○魚 『魏武帝の四季食則』には、毛魚は女性のように髪があり、白くて太っていて、鱗がなく、滇池で採れると書かれている。 ○ ナマズ 『魏武帝の四季食則』には「ガマの鱗は粥のようで、邊県のものだ」とある。 ○インドの魚 『臨海奇事記』には、このアザラシには鱗がなく、形は「玉溪」(誤発音)に似ていると書かれている。額にはアザラシのような四角い模様が4つある。死ぬ運命にある大きな魚はすべて最初に封印されるべきです。 郭延之の『書正記』には、城陽県南梁瑞には堯の母である清都の墓の前に池があり、魚の額に印があり、頬魚と呼ばれている、とある。寺に報告しなければ捕まることはない。 左寺の『武度賦』には「印龟鱕(音樊。)〈鱼昔〉」とある。 ○ キグチニベ 『呉書』には、薛宗が碑文に次のように記している。「膠州の太守朱福は、多くの村人を長官に任命し、人々に黄ニベ一匹と米一ブッシェルを支払うよう強制した。」 劉新奇の『膠州記』には、武寧県の秋の9月に、黄ニベがウズラに変わったと書かれている。 『南草事記』には、9月中旬、短くて細い黄色のニベが秋風でウズラに変わり、魚は団子状になる、とある。役人はこれを捕まえて焼いて食べ、味は濃厚で美味しい。 『南中八県記』には「黄ニベは川に生息する。形はボラによく似ており、骨はタマネギのようで食べられる」とある。 郭易公の『広志』には、「腕骨のある黄色いニベは、銭県の白道県で産出する」とある。 ○魚を送る 沈懐遠の『南越記』には、次のように記されている。「冲魚は長さ3インチで、白い魚のように見える。洪水を乗り越えるために、船によく付着する。」一つは魚を運ぶことです。 『臨海水土記』には、ジドゥ魚は長さ3インチで、白い魚のように見えると記されている。 ○じゅんゆ 沈懐遠の『南月志』にはこう書かれている。「王魚は長さが3インチで、背中に筆筒のような骨があり、大きなものは槍のようだ。」小魚や亀に遭遇すると、腹を切り裂いてしまいます。 ○アンコウ 『臨海奇事記』には、アンコウには鱗がなく、琵琶のような形をしていると書かれている。 沈懐遠の『南月志』には、アンコウには鱗がなく、長さが2フィート、形が琵琶に似ていることからその名が付けられたと書かれている。 任芳の『奇事記』にはこう記されている。「海の魚は千年経つとメカジキに変わる。」レーユはアンコウとも呼ばれ、琵琶に似た形をしており、歌うのが好きなことからその名が付けられました。 左寺の『武度甫』には「人魚と琵琶」とある。 曹丕の『楊杜甫』にはこうあります。「魚とは琵琶とイカである。」 ○ まばらな歯の魚 『衛武四季食則』には、鯵の味は豚肉や魚に似ており、東シナ海から来たものであると記されている。 潘越の『蒼海頌』には「目は近く、歯はまばらだ」とある。 ○魚 『衛武四季食則』には、半魚の頭には真珠のような石があり、北海から来ると書かれている。 郭易公の『光志』にはこう記されている。「半嶼の頭には真珠のような玉石がある。」 ○ イエローバード 『臨海奇聞』には、黄鳥魚は8月に黄色い鳥に変身し、10月に魚となって海に戻ることが多いと記されている。 「風徒記」によると、6月には南東から長い風が吹き、一般に黄鳥風と呼ばれています。その時、海の魚が黄色い鳥に変わることからこの名前が付けられました。 ○ アゲハチョウ 『臨海奇事記』には、ツバメ魚は体長5インチで、雨の日には10フィート以上も飛ぶことができると書かれている。 ○カイトフィッシュ 『臨海奇事記』には、凧魚は凧に似ているが、尾も足もないと書かれている。雨の日でも数フィートの高さまで飛ぶことができます。 ○ 赤魚 豫歓の『衛略』にはこう記されている。文帝が退位を受け入れようとしたとき、露の入った大釜の中に赤い魚が泳いでいた。 ○クロダイ 王子年世一路は言った。「夏群は水を制御しようとしたが失敗し、豫江に沈み、そこで千フィートの大きさの黒い魚に変わった。」その後、彼は川と海の間に横たわって亡くなった。後世の聖人たちは、黒い魚を神格化された生き物とみなし、「黒い」種と「魚」の種を組み合わせて「鮌」の種を形成しました。 ○ シャオフィッシュ 『臨海水土記』には「韶魚は凧魚のような形をしている」とある。 ○イカ 『臨海水土記』には、人魚は凧魚のような形をしていると書かれている。 ○ ウェルフィッシュ 『臨海奇事記』にはこう記されている。「井魚の頭には二本の角がある。」 ○ミラーフィッシュ 『臨海奇事記』には、鏡魚は鏡のような形をしており、肉が少ないと記されている。 ○ツヤツヤの魚 『臨海奇事記』にはこう記されている。「蝋魚とも呼ばれる蝋光魚」黄色くて美しく、ろうそくのように輝くことからキャンドルと呼ばれています。 沈懐遠の『南月志』には、「蝋魚は蝋魚と呼ばれる。色が鮮やかで美しいので蝋魚と呼ばれる。夜に光る」とある。 『霊標六易』にはこう書かれている。黄蝋魚は川や湖に横たわる魚で、頭と口が長く、背中の鱗は金色である。南部の人々は、おいしいが有毒なこの肉を焼いて食べます。また、揚げたり、乾燥させたりもします。夜にはろうそくのような光があります。 ○〈ユー・チェン〉魚 『臨海奇事記』には、「玉塵」という魚は指ほどの大きさで、長さは7~8インチだが、背骨があり、スープを作るのに適していると書かれている。大きなものは竹竿ほどの大きさで、太陽の光に当てるとろうそくのようになり、非常に明るくなります。 ○わんゆ魚 『臨海奇事記』には、万魚は3月に川で生まれ、切ると長さが1インチになる、とある。 10月中旬、董は海に戻って死に、その香りが水面に漂った。時が来れば、月は生まれ変わります。 『永嘉地理志』には「石塘水の河口には万魚類が多い」とある。 ○サンドブロワー 『臨海奇事記』には、「吹砂は長さ3インチで、背中にトゲがあり、人に当たると刺す」とある。 ○フーニエンフィッシュ 『臨海水土記』には「伏年魚は砂を吹く魚のようだ」とある。 ○ゴールデンオニダルマ 「南月記」はこう言った。「金石魚は丸い形をしており、7インチの皿のようだ。」 ○ メイドフィッシュ 『臨海奇事記』には、メスの魚の口は腹に近く、その形は女性の靴に似ていると書かれている。 ○ スレイブフィッシュ 『臨海水土記』にはこう記されている。「ウミウシは体長1フィートで、靴のような形をしている。」 ○{ウォユ}(発音はwo)魚 『臨海水土記』には「{倭魚}はナマズに似ており、長さは3フィートである」と記されている。 ○ 銅魚 『臨海奇事記』には、この銅魚は長さ5インチで鯉に似ていると記されている。 ○陶器の魚 『臨海水土記』には、タオ魚は長さ3フィートで、タン(「シェン」と発音)魚に似ていると記されている。 ○イシダイ 『臨海水土記』には「オコゼ、コオロギ、六つの昆虫は一つである」とある。 別名:オニダルマオコゼ、ワーム。 (コオロギと呼ばれる魚です。体長は1フィート以上あります。縞模様はトラの縞模様のようです。一般的にコオロギと呼ばれています。ぼんやりしているときにコオロギと呼ばれます。その後、陸に上がって交尾します。その子孫は食べられません。) ○ ヒトデ 『臨海水土記』には、星形の魚が凧魚に似ており、背中に指ほどの大きさの白い飾りが2つあることからこの名が付けられたと記されている。 ○〈フィッシュパーティー〉魚 沈懐源の『南ベトナム』には、「玉堂」という魚は「玉富」や「玉比」に似ていると書かれている。 (ビと発音します。) この尾状植物には、桐の木のトゲのようなトゲがあります。 ○イカ 『臨海水土記』には、魿魚は〈魚公〉魚に似ていると書かれている。 「奇妙な事の記録」にはこう記されている。「南部の魚のほとんどは脂がのって美味しくないが、ナマズだけが最高だ。」大きいものは長さが2フィートあり、焼くと特に香りがよく、おいしいです。 『霊標六易』には、魿魚は白身魚に似ているが、体はやや短く、尾は垂れ下がっていないと書かれている。清遠江にはこの魚がたくさんいますが、海にはいません。広東省の人々はこれを刺身にして食べることが多いが、魚臭くなく、おいしく、他の魚の尾よりも美味しい。 ○ ウィーバーフィッシュ 『臨海水土記』には、ウィーバーフィッシュは歩く魚のように見え、他の魚よりも味が良いと書かれている。 沈懐遠の『南月志』にはこう書かれている。「編んでいる魚は本物の魚のようで、背中は緑色だ。」 ○〈魚〉ニシン 『臨海水土記』には、「魚隹」という魚は「魚隹」という魚に形が似ていて、川で遊び、定まった場所がないと書かれている。 ○トゥヌ 『臨海水土記』には、トゥヌ魚は虎のような頭を持ち、人を刺すことができる棘を持っていると記されている。 ○花嫁魚 『臨海水土記』には、花嫁魚は〈玉瓜〉魚に似ており、長さは10フィートであると記されている。 ○鯛 『臨海水土記』にはこう記されている。「ウニは魚に似ており、豚の頭を持ち、長さは9フィートです。」 郭普の『河詩』にはこうある。「魚類には川イルカとウニがいる。」 曹丕の『楊都頌』にはこうある。「ラッコ、クジラ、チョウザメがたくさんいる。」 ○ くんあわび 『臨海水土記』には「崑アワビは海豹に似ている」とある。 ○遠くの魚 『臨海水土記』には「遠くまで潜る魚で、臥魚に似ている」とある。 (千元は魚の名前で、臥魚に似ています。) ○ ヒキガエル 『臨海水土記』には、ヒキガエル魚は凧魚のような色をしており、頭はヒキガエルのようで、尾は凧のようだと書かれている。 ○タートル(シュアンと発音) 『臨海水土記』にはこう記されている。「亀の体長は5インチです。」 ○ ラットフィッシュ 沈懐遠の『南月志』には、ネズミ魚の頭はネズミのようだと書かれている。 『臨海奇事記』には、ネズミ魚は体長7インチで、頭はネズミのようだと記されている。 ○ボウフィッシュ 『臨海水土記』にはこう記されている。「弓魚は体長3インチで、イモリに似ている。」 ○〈魚の赤ちゃん〉〈魚の一匹〉魚 『臨海水土記』には「玉英」「玉益」という魚、長さ1フィートと記されている。 ○ キビ 『臨海水土記』には、キビ魚は長さ3フィートで「魚」に似ていると記されている。 ○〈魚蔵〉(さかなくら) 『臨海水土記』には、「玉倉」という魚の肋骨の下には焼肉ほどの大きさの大きな肉片がある、と記されている。 『霊標六易』には、「玉蒼」という魚は鯛に形が似ているが、頭が突出していて、背中が丸くて細いと書かれている。身は非常に厚く、魚は脂肪が固まったように白く、背骨は1本だけです。生姜とネギ、炒ったもち米と一緒に調理します。骨が柔らかくなり、食べたものを捨てることがなくなります。俗に「寝ている魚を犬が叩く」とも言われます。 (犬にとってはお皿の下の骨を見つけるのが難しいため、犬が眠っている魚を叩いてしまったと言われています。) ○魚の餌やり 「南月記」曰く:尾のある魚は有毒で、亀魚とも呼ばれる。 ○地元の食材を使った魚料理 『臨海水土記』には、土混じりの魚は体長7インチで、白と黒の斑点がある、と記されている。 ○ガオユ 『奇異の記録』にはこう記されている。「ガオ魚はマスに似ている。」このトカゲは、通常3月か2月に水上でトカゲと交尾するが、この時期にはメスはいるがオスはいない。そして胎児を食べ、人間を殺す。 ○ 魯(魚) 『奇異記』には、葦(葦帥)はウナギに似ているが、筋が細かく、油っぽくてふっくらとして美味で、大きな葦管のようだと書かれている。もともと地中に生えていて、湧き水とともに湧き上がる植物で、通称は「露浮(ゆふ)」といいます。 沈懐遠の『南月志』には、葦魚は山や谷に生息し、地中の洞窟に潜り込み、泉があるときに現れると書かれている。現在、それは鹿嶺から南の南州まで存在しています。普通の人はそれをソースだと思っている。 ○ ワニ 『奇妙な事物の記録』には、冬になると、何千万匹ものこの魚が大きな洞窟の中に一緒に隠れ、その上には白い霧が漂っていると書かれている。あるいはワニの巣穴では、ワニの皮膚は漆のように黒く、数マイル離れた木の洞に忍び込むことができ、風に乗って木の洞に入り、コウモリに変身することができます。肉はとても美味しいです。 ○くん魚 『茅詩』の「鶏鳴き」には、「古い籠が梁の上にあり、その籠で捕らえられた魚は鯛と昆である」とある。 「エルヤ」曰く:クンは魚卵です。 (魚の息子は一般的にクンと呼ばれます。) 別名:鱦、小魚。 (sheng と発音します。yun とも発音します。東洋の大工は、未熟な魚の卵を「sheng」と呼びます。) ○海くん魚 『王子年世一路』にはこうある。「黒河は北極である。」水は濃くて黒く流れず、上には黒い雲が浮かんでいます。長さ1000フィート、クジラのような形をした黒いクンがおり、南シナ海まで飛んだり泳いだりすることが多い。 『荘子』にはこうある。「北海に魚がいて、その名は坤といい、その大きさは不明だが、長さは何千里にもなる。」 蒋愍の詩にはこうある。「大亀は蓬莱をまとい、大坤は天地を動かす。」突然、雲が降り雨が降り、3つの植物は悲しくなりました。 孫芳の荘子賛歌にはこうある。「大小はみな同じ馬に乗っているが、物事の変化には予測できない報いがある。」坤は長い鱗を脱ぎ捨て、鵬は空に昇って飛び立ちます。翼を広げて風を集め、上を見上げて大空へ舞い上がります。 袁洪の『北伐譜』には、魚は水を頼りに坤となり、山の木は松となるとある。 ○ ウールフィッシュ 「呂氏春秋」はこう言った。「最も美しい魚は東シナ海のボラです。」 張衡の『西都賦』には「坤と禹の巣」とある。 (クンは魚卵、ウールは小魚を意味します。) ○赤魚 劉易清の『冥界記』には、石興の雲水の源泉に温泉がある、と書かれている。霜や雪が降ると、上空の蒸気は数十フィートの高さになります。春には小さな赤い魚が泳いでいることが多いのですが、誰も捕まえません。 ○ ゴドウフィッシュ 毛氏書にはこう書かれている。「古い籠は梁の上にあり、その中には鯛とボラが入っている。」 (男やもめの魚) 『孔子』はこう言った。魏の男が川で釣りをし、荷車いっぱいになるほど大きな男やもめを捕まえた。彼は言った。「鯛の餌を置いたが、寡夫は見もせず通り過ぎた。次に豚の半身を置いたが、それを飲み込んだ。」 鍾思は言った。「寡夫は餌を欲しがって死ぬが、学者は世間の給料や財産を欲しがる。」 ○ 本物の魚 沈懐遠の『南月志』にはこうある。「本物の魚、織機の魚のようだ。」 『臨海水土記』には「玉真」という魚、通称は「有魚」と記されている。 ○チキンフィッシュ 『霊標六易』には、鶏魚は鶏のような口を持ち、肉は柔らかく、鱗がなく、尾は長く尖っていると書かれている。風と波があると、ボラのように風に乗って海上の船に乗って飛びます。 ○ 竹魚 『霊標六易』には、竹魚は川や小川で採れる魚で、蛇の頭のような形をしており、大きくて骨が少なく、色は濃い青色で、鱗の下に赤い点があり、遊ぶのが楽しいと書かれている。時にはスープにして食べることもあり、脂っこくて美味しいです。 ○ サバヒー 『霊標山奇記』には、泉邑山の南西に盤龍山があり、山頂には乳頭洞があり、斜に川が流れており、霊水渓と呼ばれている、と記されている。 (現在は貴州省霊川県)川には魚がいて、どれも尾が長く、足が4本、腹が赤く、自由に泳いでいます。漁師たちはそれを捕まえる勇気がない。 (二亜曰く:イモリはボラに似ていて、足が4本あり、泣いている子供のような声を出す。この魚は現在も尚州の渓流に生息しており、ボラと呼ばれている。) ○{勝利の魚} 魚 『臨海水土記』には次のように記されている。「{生魚} ボラに似た魚で、長さは 2 フィート。」 |
<<: 野盧朱の『天祥台賦』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
推薦する
「武夷山にて」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
武夷山謝芳徳(宋代)夢を見ないまま10年が経ち、私はついに故郷に戻り、緑の山々と荒々しい水のほとりに...
明代読本『遊学瓊林』第3巻 宮殿全文と翻訳注釈
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...
『酒泉子 長易観潮』を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
酒泉子・昌益 潮を見る潘朗(宋代)町中の人々が競って川を眺めながら潮を眺めていたことを私はいつまでも...
「降伏都市の夜、笛の音を聞く」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】慧楽峰の前の砂は雪のようで、首江城の外の月は霜のようです。 (慧楽峰は慧楽峰とも呼ばれ...
秦の始皇帝は暴君だったと言う人が多いでしょうが、功績のある役人を殺したことがあるでしょうか?
秦の始皇帝について話すとき、多くの人が彼は暴君であり無能だったと言うだろうと思います。実際、最も典型...
宋代の有名な詩人、顔書:「桓希舎:時は有限」の翻訳と鑑賞
本日は、『Interesting History』編集者が Yan Shu の『Huanxisha:...
「農桑料理」野菜とレタス全文と翻訳ノート
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
唐の中宗皇帝の娘である永台公主李献恵は永台公主の実母である。
李献慧(684-701)、号は献慧、唐の皇帝中宗の娘の中で6番目であった。彼女は衛皇后の三番目の娘と...
悲しい春の詩の古典作品:王安国の「清平楽春節祝賀」鑑賞
以下、Interesting History 編集者が、王安国の『清平楽春節祝賀会』の原文と評価をお...
雲錦はどのように作られるのですか?雲錦を作るのに使われる機械は何ですか?
Yunjin 生産の 4 番目のステップは、機械を作ることです。機械製作工程は、錦織の種類や規格に応...
孫悟空は仏陀になった後、自分の最初の選択がいかに愚かであったかを悟った。
「壁にぶつかるまで引き返すな」という古いことわざがあります。明らかに、『西遊記』の孫悟空はこのような...
神話:韓鍾離の呂洞賓に対する十の試練と呂洞賓の不死の物語
神話の物語:韓鍾離が呂洞賓を10回試す:八仙人の一人である呂洞賓は、幼い頃からすでに古典や歴史に精通...
私の国の歴史上、最も簡単に間違って発音された 12 の川は何ですか?
多くの場合、地名や人名に使用される文字の多くは異なっており、そのため認識されなかったり、誤って使用さ...
『淮河入水四行詩』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
淮河に入るときの四行詩楊万里(宋代)船は洪沢の砂浜を出発し、淮河に到着した人々は不幸だった。サンガン...
古代中国の歴史家はどの王朝に最初に誕生したのでしょうか?夏王朝に遡る
多くの友人は、古代中国の歴史家がどの王朝から始まったのか興味を持っています。実際、中国のすべての王朝...