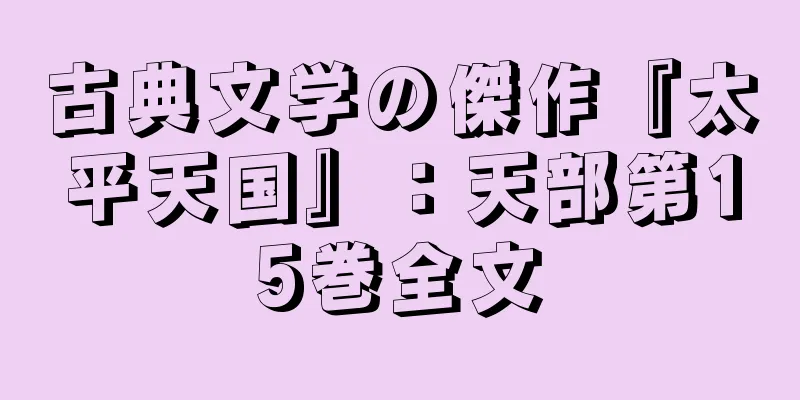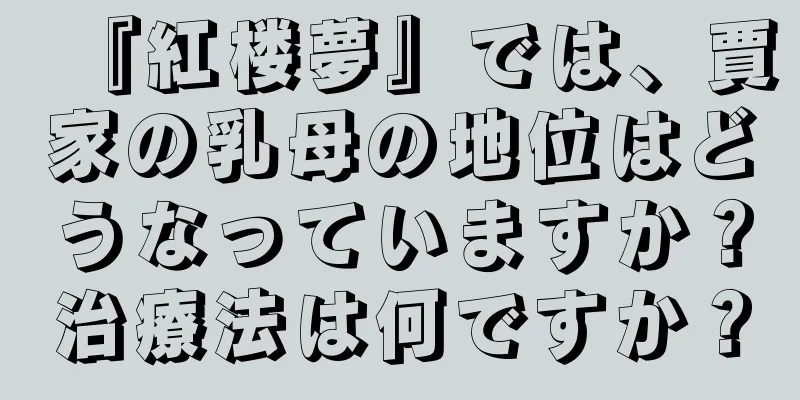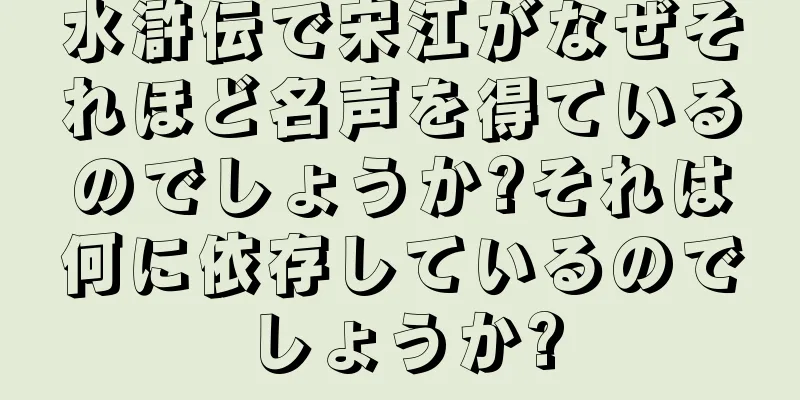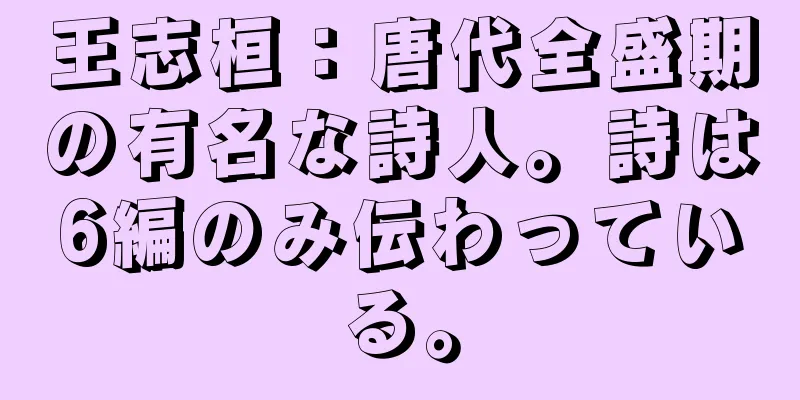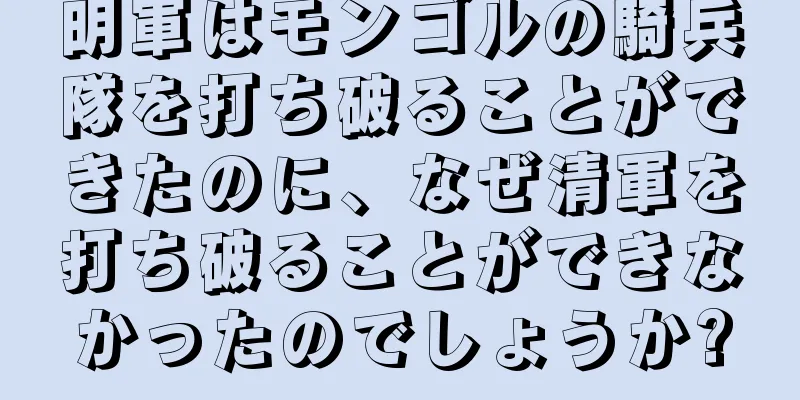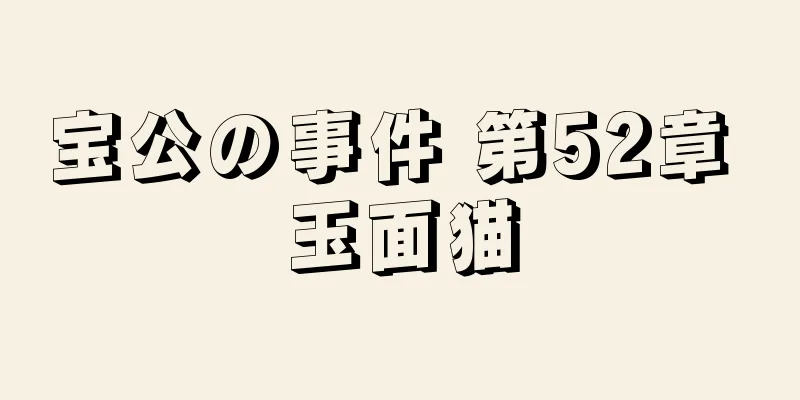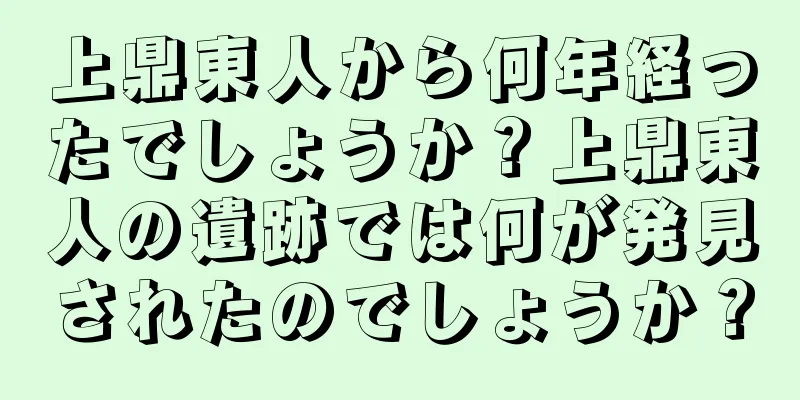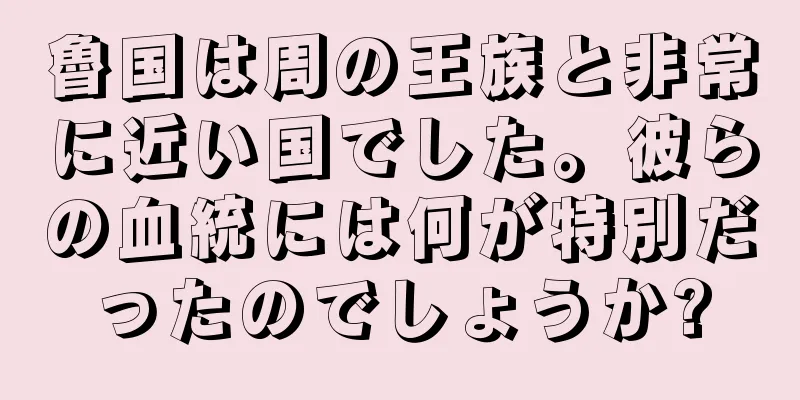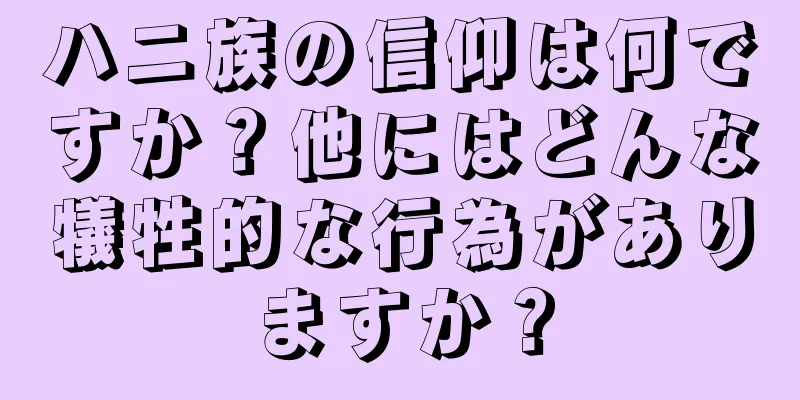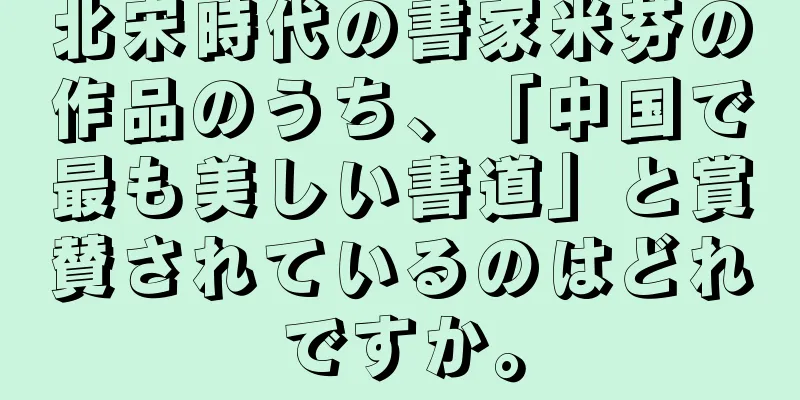清朝の老人保健に関する論文「老老衡厳」第1巻:食事全文
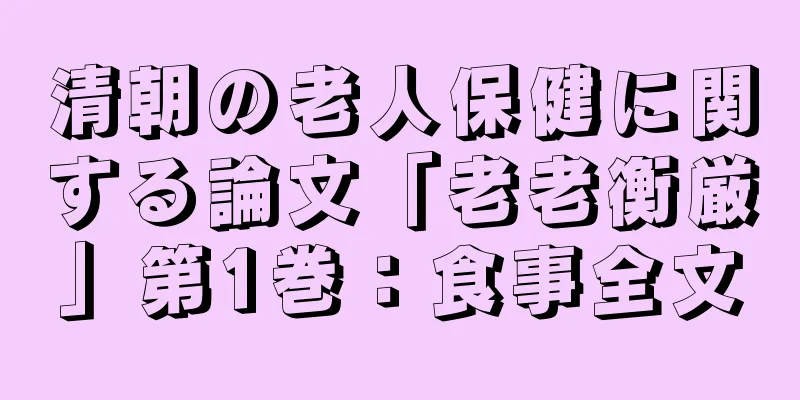
|
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれを高く評価し、還暦の贈り物としてふさわしい良書と評した。最も優れた版は、清朝の乾隆38年に曹廷東自身が印刷した版である。それでは、次の興味深い歴史編集者が第1巻「ダイエット」の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 『内規録』には、「一般的に、春は酸味を増し、夏は苦味を増し、秋は辛味を増し、冬は塩味を増し、なめらかで甘味をバランスさせる」とあります。(注:酸味、苦味、辛味、塩味は、木、火、金、水の要素に属します。)季節の味をさらに加えて気を養いましょう。四季すべてがなめらかで甘い味わいに調和され、大地の住まいを象徴しています。孫思邈は「春は酸味が少なく甘味が強く、夏は苦味が少なく辛味が強く、秋は辛味が少なく酸味が強く、冬は塩味が少なく苦味が強く、四季を通じて甘味が少なく塩味が強くなる」と語った。「内澤」は繁栄に乗じることを目指しており、孫の意図は衰退を支えることである。つまり、季節に関係なく、5つの味のいずれも過剰に摂取すべきではないということです。 『包朴子』には「酸味が多すぎると脾臓を傷め、苦味が多すぎると肺を傷め、辛味が多すぎると肝臓を傷め、塩味が多すぎると心臓を傷め、甘味が多すぎると腎臓を傷める」とある。この5つの味は5つの内臓を克服する、これが五行の自然の法則である。傷ついたと言われている人は、その時すぐにはそれを感じない。 すべての食べ物は塩辛いはずですが、少し塩を加えると味が薄くなります。食べ物が薄味であれば、その食べ物の本当の味と性質が得られます。塩辛い食べ物をたくさん食べると、喉が渇きます。塩辛い食べ物は水に属し、体を潤すのに、なぜ喉が渇くのでしょうか。黄帝内経には、「血と塩辛い食べ物が出会うと凝固し、凝固すると血が乾く」と書かれています。意味がはっきりしないようです。西洋水法には、「木を燃やして灰にして塩水を得るようなものだ」と書かれています。塩辛い食べ物は火によって生成されるため、塩水は凍らないことがわかります。物事は極端に変わると思います。火が極端になると塩辛くなり、塩辛さが極端になると渇きになります。また、「干」の卦の陽線は水に火が含まれていることを表すので、腎臓には実際の火があります。 『内規記』には「ナツメヤシ、栗、麦芽、蜂蜜で甘くし、スミレ、イバラ、アマランサス、ニレ、兎、菖蒲、桑、キンモクセイで滑りを良くし、脂や軟膏で滑らかにする」とある。甘くすると脾臓を喜ばせ、滑りを良くすると脾臓の陽を鎮め、軟膏は脾臓の陰に効くと思う。この3つの言葉は、すべて脾臓を指している。古人は、老人を介護し、脾臓を整え、薬として服用する方法を採用した。 『包朴子』には「熱い食べ物は骨を傷つけ、冷たい食べ物は肺を傷つけ、熱い食べ物は唇を火傷させず、冷たい食べ物は歯を凍らせてはならない」とある。また「熱い食べ物と冷たい食べ物を一緒に食べるときは、最初に熱い食べ物を食べてから冷たい食べ物を食べるのが良い」とも書かれている。食べ物の熱さや冷たさはその時に自然に判断されるべきだと思うが、冷たすぎるよりは熱すぎる方が良い。夏は陰が内側に隠れているため、熱い食べ物を食べると軽い発汗を誘発することがあります。 「内規」には「夏に汗をかかない者は秋に強風に悩まされる」とある。汗は気から変化したもので、外部と内部の詰まりを取り除くという考えである。 『養生記』には「春に肝臓を食べてはいけない、夏に心臓を食べてはいけない、秋に肺を食べてはいけない、冬に腎臓を食べてはいけない、四季に脾臓を食べてはいけない。それがピークのとき、物の死気を怒らせてはいけない、なぜなら生きているものを食べる理由がないからだ」と書いてある。この理論は厳格すぎる。『豫書衛志』には「春に肺を食べてはいけない、夏に腎臓を食べてはいけない、秋に心臓を食べてはいけない、冬に脾臓を食べてはいけない、四季に肝臓を食べてはいけない」と書いてある。つまり、自分が抑えているものを食べてはいけないということだ。この理論はまだ受け入れられる。 夏至を過ぎて秋分の前は、外の暑さが増す一方で、内なる陰が表れ始める時期です。脾胃の調子を整え、脂っこい食べ物を避けることが最も重要です。 『黄帝内経』には、「濃いものは陰、薄いものは陽である。濃いものは排出し、薄いものは通過する。また、果物、野菜、生の食べ物や冷たい食べ物にも注意する。胃は温かいものを好み、温かいものは発散し、冷たいものは凝固する。凝固すると、まず胃が傷つき、脾臓が機能しなくなる」とある。『百胡同』には、「胃は脾臓の住処であり、脾臓は胃から気を受け取る。正午前後、脾臓は生命に満ち、正午以降は死気で満たされる。仏教徒には、死気を避けるために正午以降は食べないという格言がある」とある。『黄帝内経』には、「正午は陽気が高く、日没時は陽気が弱まる。 「そうすれば、朝食をしっかり食べて、午後は食べる量を減らし、夕方には空腹感を感じることができます。」 穎玖(姓:穎)の『三老詩』という詩に、「中年の老人が前に出て演説し、腹を量って食べるのを控えた」とある。腹を量るという言葉が一番素晴らしい。多くても少なくても、他人には分からない。自分で判断しなければならない。倹約したいなら、今日も明日も倹約すべきです。倹約するより倹約する方が良いです。もう一つの古い詩には、「もっと食べて、もっと食べなさい」とあります。高齢者にとっては、食べ物の量を減らさなければ十分です。食べ物の量を増やすと、胃を悪くします。しかも、頑張るとどうしても無理やり感が出てしまいます。あと1食増やせたとしても、その後食べ続けることができなくなります。何の意味があるのでしょうか? 極度に空腹なときには食べないでください。食べ過ぎないでください。極度に喉が渇いているときには飲まないでください。飲み過ぎないでください。腹部が空でない限り、崇和の気は皮膚と骨髄に浸透します。 「包朴子」には「一度に大量に食べるよりも、少量ずつ頻繁に食べる」とあり、同じ考えが示されています。一般的に、食事は少なめに食べる方が良いです。なぜなら、脾臓が食べ物を消化して精気に変えることを助けるからです。逆に、栄養価の高い食べ物でも食べ過ぎると害を及ぼす可能性があるため、少なめに食べると脾臓を落ち着かせることができると言われています。 『董維経』には「空腹すぎると脾臓が傷み、満腹すぎると気力が損なわれる」とある。脾臓は食物に依存しているため、空腹になると脾臓は機能できず弱くなる。気は脾臓を流れるため、満腹になると脾臓が満腹になり、気が停滞する。したがって、脾臓を養うためには空腹のときに食べるべきであり、気(エネルギー)を養うためには食べ物が脾臓を満たすのではない。 『華佗の食物論』には、「食物には三つの変化がある。一つは火による変化で、これは調理するときである。一つは口による変化で、これはよく噛むときである。そして一つは胃による変化で、これは胃に入って消化されるときである。」とある。老齢期の人々は食物の変化を火に頼ることしかできず、簡単にすりつぶされて代謝されるため、精子の損失が増えることになる。市販の干し肉に石を溶かす成分を加えると腐敗が早まります。火葬もされていますが、胃の気を弱める恐れがあるので、頻繁に食べないようにしましょう。 陸や海の幸は貴重で美味しいのですが、他の食品と混ぜるのは避けるべきです。五つの味を混ぜると、お互いに衝突し、必ず胃の不調を引き起こします。 『道徳経』には「五つの味は口の中を清らかにする」とある。清らかとは失うことであり、口の中の正常な味が失われることを意味する。それぞれの食べ物が美味しく、口と胃の両方に合うように、別々の食事で食べる方が良いです。 食後に歯の間に残った残留物は、歯にとって最も刺激となります。柳の木で串を彫り、特に虎のひげなど、徹底的に取り除きます。その後、濃いお茶を淹れて冷めたら、口をゆすいで残留物を洗い流します。魏荘の詩には「瓶から溢れ出る水は絹のように白く、口でうがいをすると泉の音がする」とあり、蘇東坡は「歯が苦くなる」と言った。甘いものを食べたら、口をすすいだほうがいいです。成人になる前に歯が抜ける人を見ると、口の中の甘い味が歯を保つため、やがて虫が寄生して「隠れ虫」になるのだと考えます[ni4]。公孫尼子はこう言った。「甘いものを食べるのは肉体には良いが、骨には有害だ。」歯は腎臓の骨である。 |
<<: 紅楼夢の小湘亭は大観園の中でどのような存在なのでしょうか?
>>: 老老衡延、清朝時代の高齢者の健康維持に関する論文:第1巻:食品
推薦する
王志桓の古詩「コウノトリの塔に登る」の本来の意味を理解する
コウノトリタワーに登る太陽は山の向こうに沈み、黄河は海に流れ込みます。もっと遠くを見たいなら、もっと...
「三雑詩その3」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】黄龍砦の兵士たちは何年も解散していないと聞きました。漢族の陣営で育った閨房の月はなんと...
戦国時代後期の作品『韓非子』:論争の全文とその翻訳と注釈
『韓非子』は、戦国時代後期の朝鮮法家の巨匠、韓非の著作です。この本には55章が現存しており、合計約1...
Xinling Junはどこの国出身ですか?趙を救うために印章を盗んだ新霊公の物語
Xinling Junはどこの国出身ですか?魏無忌、辛霊公(紀元前243年頃?-)は、魏の昭王の末息...
陳衛松はどの流派の詩を代表するのでしょうか?彼の代表作は何ですか?
陳衛松は、愛称は白文としても知られ、中国の清朝末期の有名な詩人でした。彼の詩は才能に溢れ、作品は広く...
蘇軾の『南湘子:梅の花と楊元素』:この詩には素晴らしい相補性がある
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
『紅楼夢』の賈家の人の中で、賈宝玉を嫌っているのは誰ですか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。次はInteresting Historyの編集者が詳...
「蒼藍絶」のラブストーリーでは、李潔は丹寅よりずっと幸運だ
今年の夏は、肖蘭花と東方青蒼の登場でとても特別なようです。于淑心と王河迪は、最もルックスが良く、最も...
ソクラテスの名言100選!これらの有名な引用文のうちどれを知っていますか?
今日は、Interesting Historyの編集者がソクラテスの名言100選についての記事をお届...
もし『紅楼夢』で刺繍の入った小袋を見たのが賈夫人だったら、結末は違ったのでしょうか?
『紅楼夢』では、第73帖から第75帖にかけて大観園探索の様子が詳しく描かれています。 Interes...
古典文学の傑作『太平天国』:封建主義第3巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で賈家は春節をどのように祝いましたか?ルールとエチケットは複雑で厳粛である
『紅楼夢』の賈家が春節を祝う物語を本当に知っていますか?今日は『おもしろ歴史』編集者が新しい解釈をお...
王長齢の古詩「入軍」の本来の意味を理解する
王朝: 唐著者: 王長玲オリジナル青海から流れてくる長い雲が雪を頂いた山々を暗く覆い、寂しい街は遠く...
趙雲が長阪坡で主君を救出するために単騎で出向いたとき、曹操はなぜ背後から矢を射てはならないと命じたのでしょうか。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
太平広記・巻106・報復・劉一懐の原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...