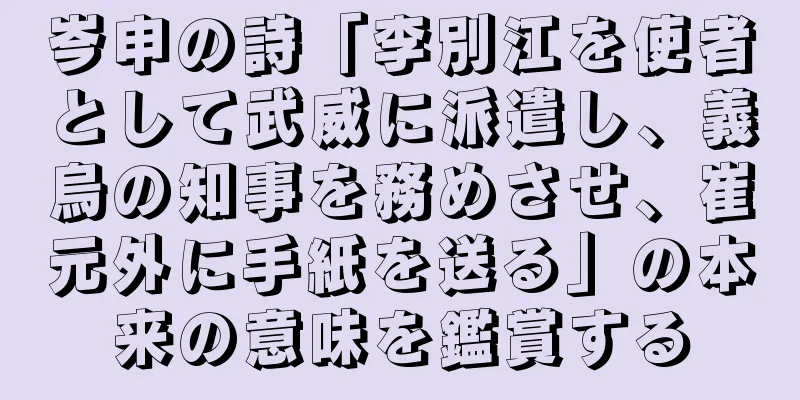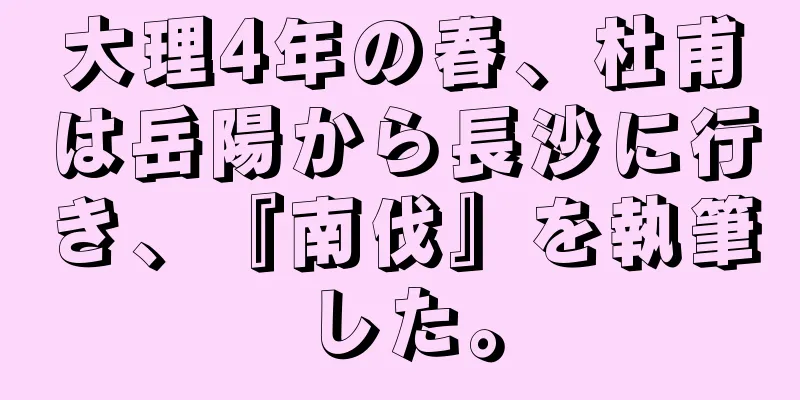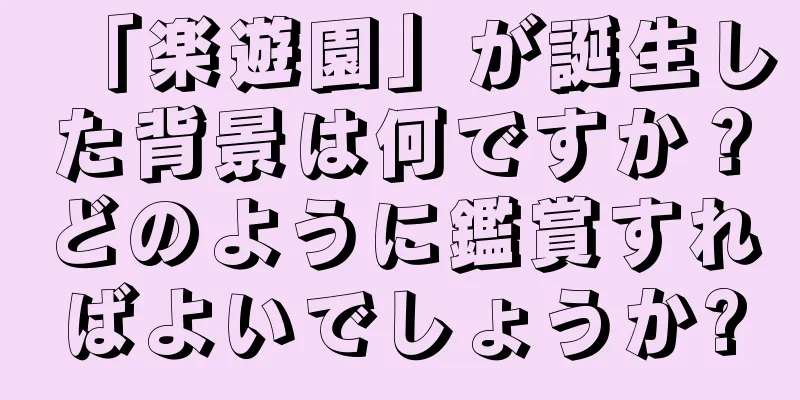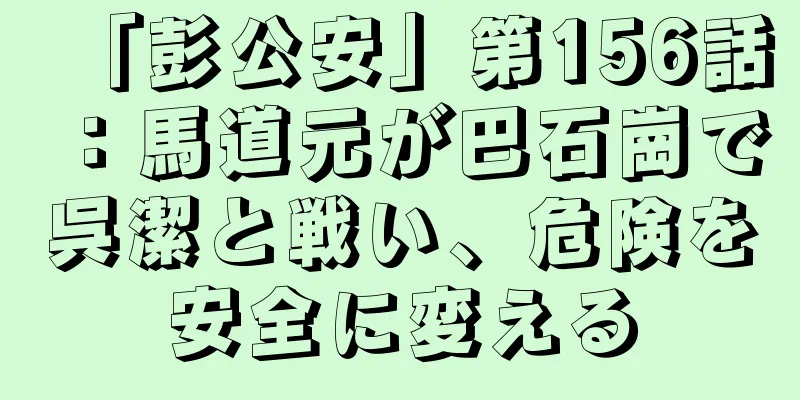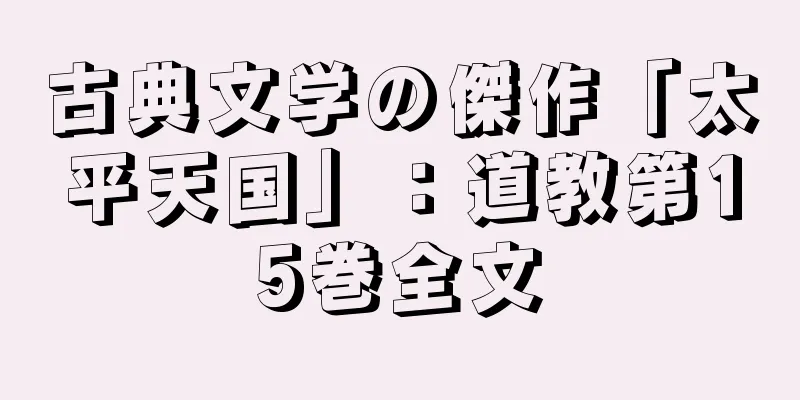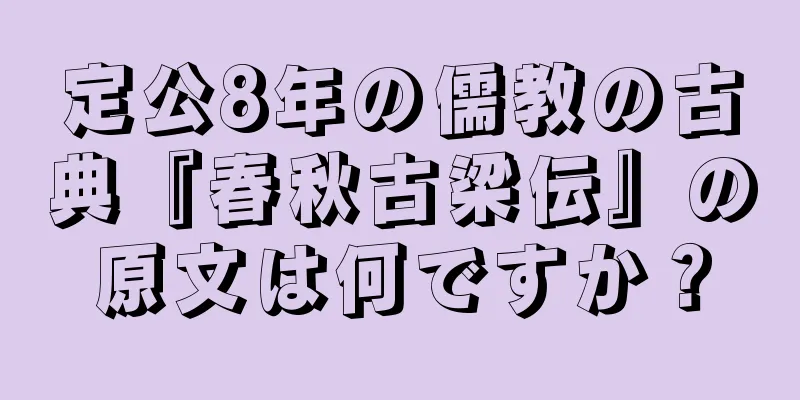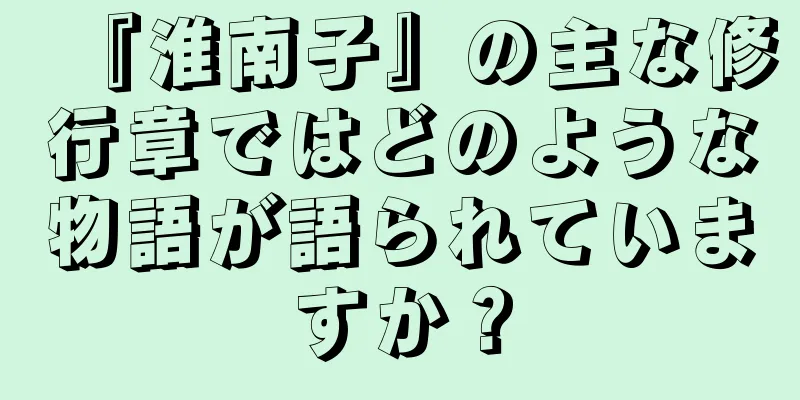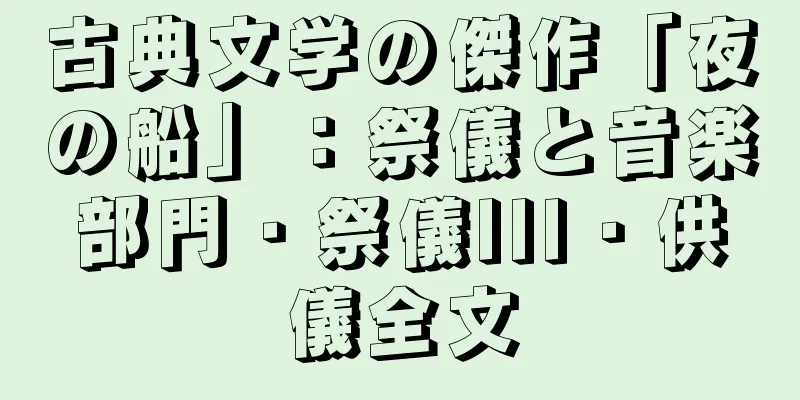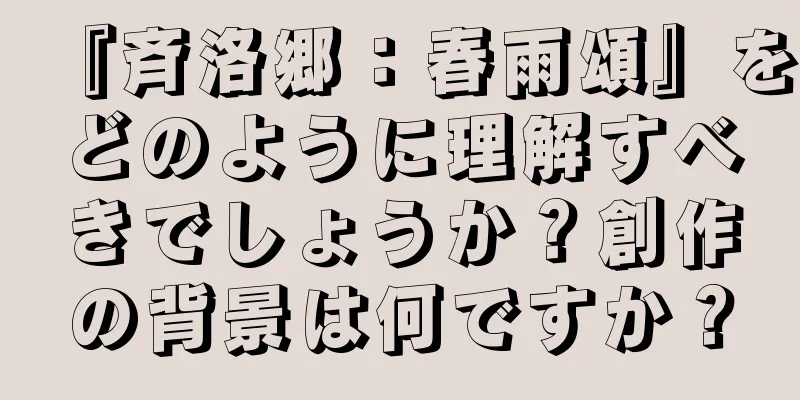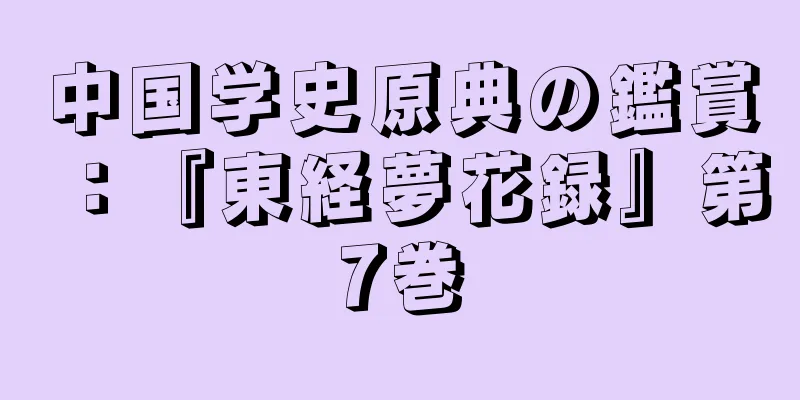清朝の老人保健に関する論文『老老衡眼』第3巻:靴
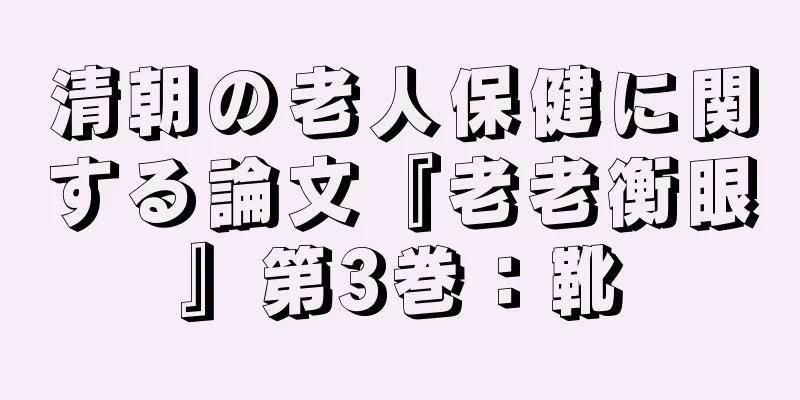
|
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれを高く評価し、還暦の贈り物としてふさわしい良書と評した。最も優れた版は、清朝の乾隆38年に曹廷東自身が印刷した版である。それでは、次の興味深い歴史編集者が第3巻の靴の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 靴はシューズと同じで、スリッパとも呼ばれます。 『古今記』には「靴底は木で作れば、乾いた天気でも泥や濡れを恐れることはない」とある。『廃農記』には「舄という字はもともと鹊という字から来ており、舄のイメージはカササギから取ったものである。歩くときに方向を知るべきだという意味で、今では一般的に鞋と呼んでいる」とある。靴が足に合うかどうかは、すべて靴底次第だ。靴底は平らでなければならない。少しでも曲がっていると、つま先に邪魔になる。甲は好きなように作ることができる。李白はかつて「飛雲靴」を作った。これは黒い絹で作られ、雲の部分は白い紗で表現されており、これもまた彼の独創的な作品である。 ベースにはブランケットを使用するのが最適です。ブランケットなら、暑い夏でも足の裏が熱くならずに履くことができます。お店で売っている布や紙のベースはあまりしっかりしていないので、手作りの布のベースも良いです。作り方:一番下の層を外側にして、キルトを薄く敷き、布で包み、針で縫います。地面が柔らかく、足音も静かでとても満足です。 底が薄すぎて湿気が入りやすいです。ただし、晴れた乾燥した日に着用すると軽くて柔らかいので、薄手のものでも問題ありません。厚すぎると、着用時に硬くて重すぎます。唐代の僧侶である清公の詩に「老人の足はもはや靴を履くほど強くない」という一節がある。下に革のトレーを敷く人もいますが、革は滑りやすく、ナツメの果肉でこするとベタベタになります。使わない方が無難です。 『世武紀源』はこう言っています。「草を「莖」と呼び、皮を「魯」と呼びます。今、外国のハラバの靴底は純皮で作られており、中国大陸で多く売られており、そのデザインは非常に優雅です。」梅雨の時期は湿気が多いので、家の中で着ることはできますが、雨具ではありません。しかし、硬くて重い性質があり、高齢者には適していません。 靴は適切な幅と締め付け感が必要です。長距離を移動する場合にのみ、より速く、より便利に移動できます。高齢者の家の家具は、足や靴を忘れて安定して快適に過ごせるように、広々としている必要があります。 『南華経』には「足の楽を忘れる」とある。昔の人は靴にベルトを使っていましたが、幅が広ければベルトで結ぶのも問題ありませんでした。元代の『車服規』によれば、「靴には二本の紐がある」とあり、紐は靴を結ぶために使われます。 冬に足が冷たくなったら、火を使って温めないでください。靴を脱いであぐらをかいて座るのが足を温める最良の方法です。綿の靴も作るべきです。1つのスタイルは靴の口に2つの耳があり、足を覆うようにしています。もう1つのスタイルは半ブーツのようなもので、革の裏地が付いています。幅が広いほど暖かいです。甲の上に縫い目がなく、小さなボタンで留めるので、脱ぎ履きが簡単です。 陳橋草履はとても軽いですが、靴底が薄くてゆったりしており、湿気を通しやすいので、夏に一時的に履くことができます。ヤシには節があります。ヤシは湿気に弱くなく、雨の日に最適です。黄尚古の詩には「老人は桐の帽子をかぶり、棕櫚の靴を履いている」とあり、張安国の詩には「靴底は棕櫚の葉とガマの縄を編んで作られ、軽くて涼しく、強くて密度が高く安定していて、足にぴったり合う」とある。どちらも真実の記録である。 靴の中には、純綿で作られたものもあります。綿を細長く撚り、染め、甲革と靴底をすべて綿で編み上げます。スタイルは粗野ですが、柔らかくて温かみがあり、他のスタイルよりも優れています。寝室での着用に最適で、あぐらをかいて座るときにも快適です。蘇東坡の詩には「あぐらをかいて座るのは楽だ」とある。本草書には、「もち米の茎を使ってブーツや靴を作り、足を温め、冷えや湿気を取り除く」とも記されている。 暑い夏にお風呂から出たばかりで足がまだ濡れているときは、スリッパを履くといいでしょう。両サイドにかかとがなく、つま先にもゆとりがあるスタイルです。しばらく履いた後は、足が冷えないように靴下を履くことをおすすめします。 |
<<: 『前漢民話』第61話はどんな物語を語っているのでしょうか?
>>: 「紅楼夢」では、林黛玉にとって賈邸に行くことより良い選択肢はあるのでしょうか?
推薦する
天皇が記念碑にコメントした内容の秘密を暴露?康熙帝は多くのことを「知っていた」
はじめに:皇帝が記念品を鑑賞した際に何と書いたかご存じですか?最近、南京江寧織物博物館は、康熙帝が鑑...
明王朝が衰退した理由は何だったのでしょうか?結局、皇帝と腐敗した役人たちは国政を運営する意図がなかったことが判明した。
明王朝が衰退した理由を知らない人は多い。明王朝時代には自然災害や反乱が頻発したため、明王朝は不運だっ...
武則天という名前の由来は何ですか?
はじめに:武則天はよく使われる名前であり、武昭は彼女が皇帝になった後に名乗った名前です。彼女の名前は...
陶淵明の「劉柴桑への返事」:田舎暮らしの喜びを詩で表現
陶淵明(365年頃 - 427年)は、字は元良であったが、晩年に名前を銭、字を淵明と改めた。彼のあだ...
歴史上の慧娘とは誰ですか?彼女の存在の意味は何でしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国古典四大傑作の一つです。Interesting ...
胡家将軍第15章:呉巴山大浪が盗賊に遭遇、王金蓮が男児を出産
『胡氏将軍伝』は清代の小説で、『胡氏全伝』、『胡氏子孫全伝』、『紫金鞭物語』、『金鞭』とも呼ばれてい...
日中共同声明を読み解く:なぜ「侵略」という言葉がなかったのか
田中角栄首相と大平正芳外務大臣を北京空港で迎え、上海虹橋空港で見送るまで、1972年の日中国交回復交...
孫悟空は自らを「天に等しい大聖人」と称したのでしょうか?仏典を手に入れるための旅の途中で、なぜ人々は名前を変えないのでしょうか?
今日、Interesting Historyの編集者は、孫悟空に「天に等しい大聖人」という称号を与え...
北斉の軍神、高長公が蘭陵王に関する歴史的出来事を振り返る
はじめに:蘭陵王は文武両道で賢く勇敢な北朝時代の有名な将軍でした。彼は「勇敢で戦闘が得意」と言う人も...
秦克清はなぜ自殺を選んだのか?彼女の寝室にある品物に隠された意味は何でしょうか?
秦克清の死はずっと未解決の謎だった。この本には彼女の死の本当の原因を明らかにする多くの詳細が記されて...
清朝の衣装:清朝のアクセサリー
清朝時代の装飾品には、さまざまな種類とスタイルがありました。それらは形が小さく、翡翠、瑠璃、金象嵌の...
「それぞれ自分のやりたいことをやる」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「各自が自分のやりたいことをやる」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語...
『神々の封神演義』の雷震子は、体が聖人になった後、なぜ天国に行けなかったのでしょうか?
『神授』の雷震子は、体が聖人になった後、なぜ天国に行けなかったのでしょうか? これは多くの読者が知り...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源61巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
楊寛の紹介:南梁の有名な将軍、楊寛はどのように亡くなったのでしょうか?
楊寛(495-549)、号は祖心、台山梁府(現在の山東省泰安県南東部)の人。南梁末期の有名な将軍。彼...