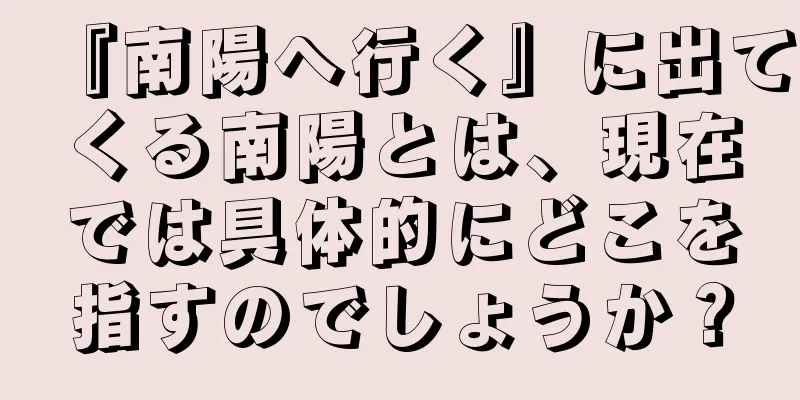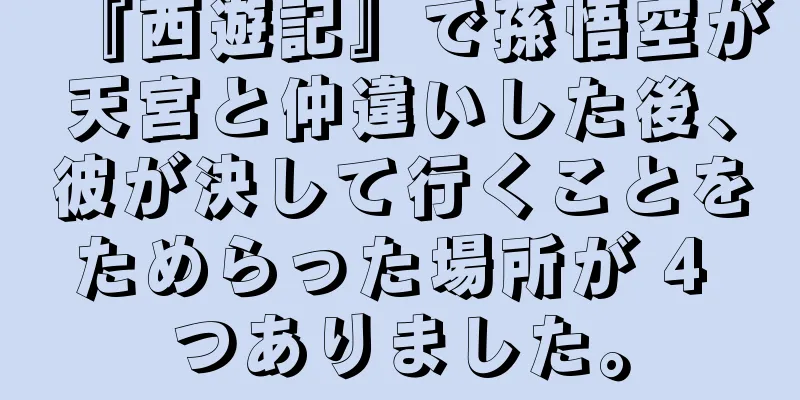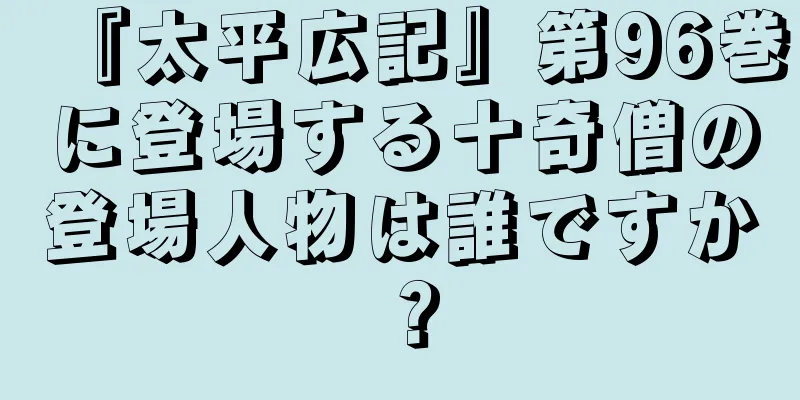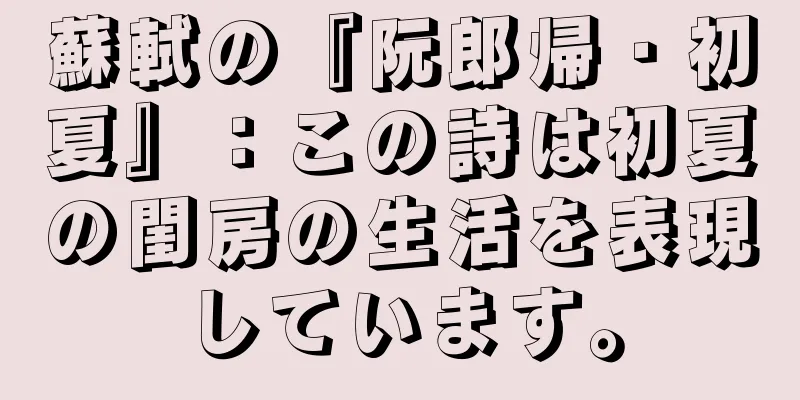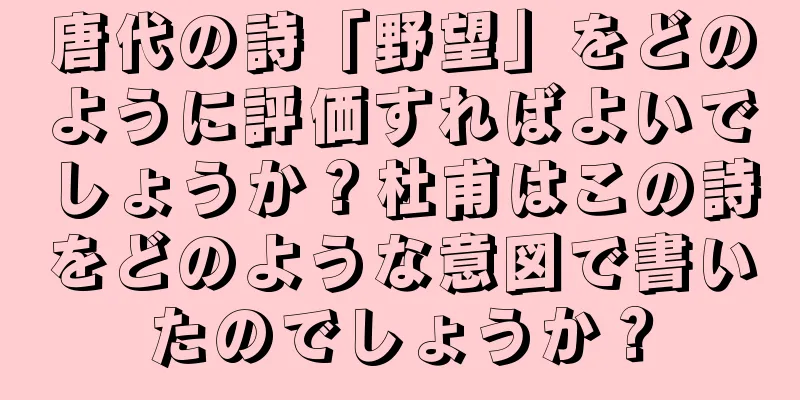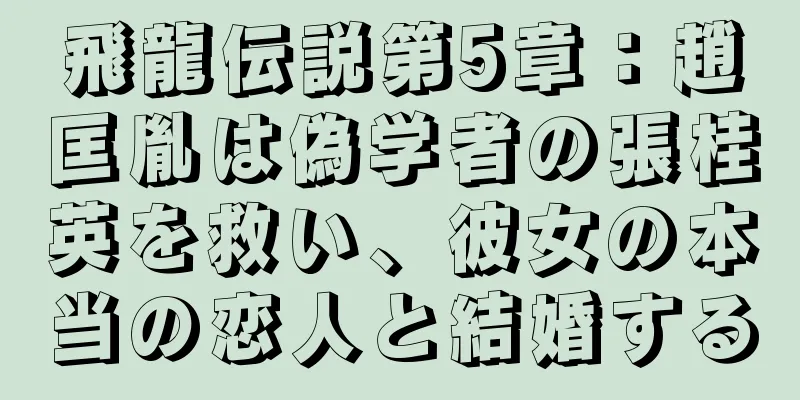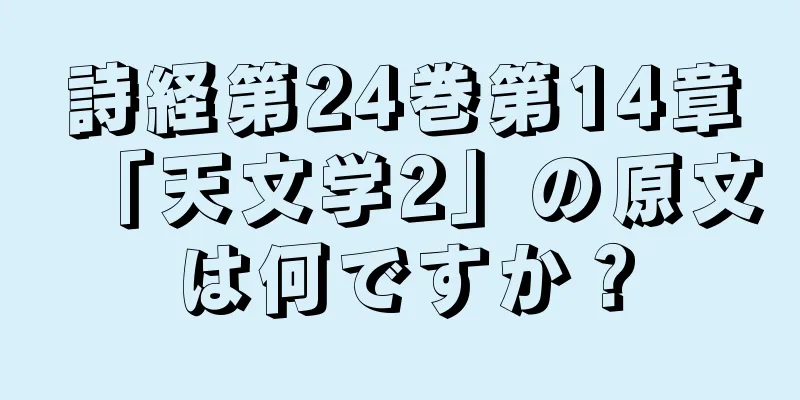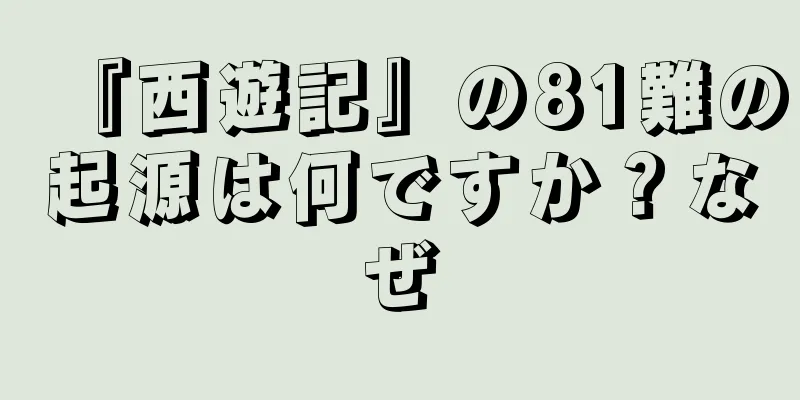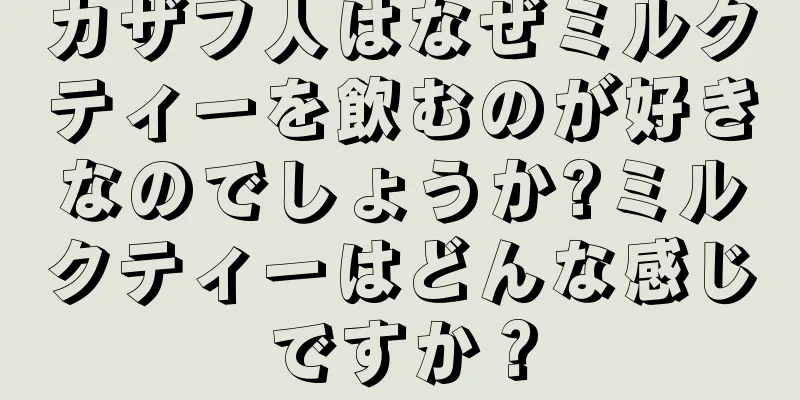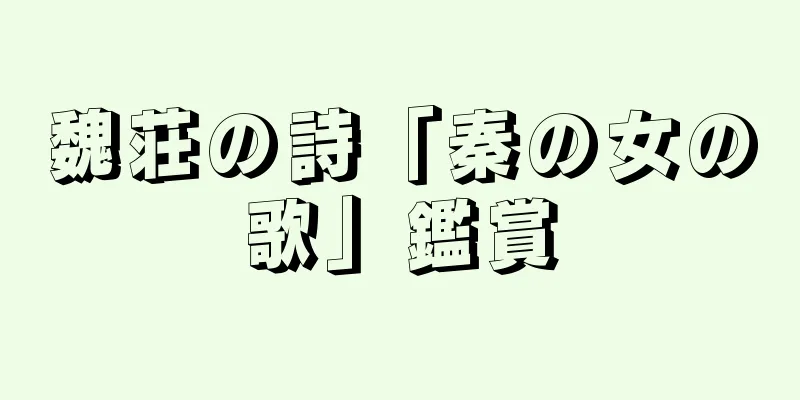維新の三偉人の一人、西郷隆盛の紹介 西郷隆盛はいかにして亡くなったのか?
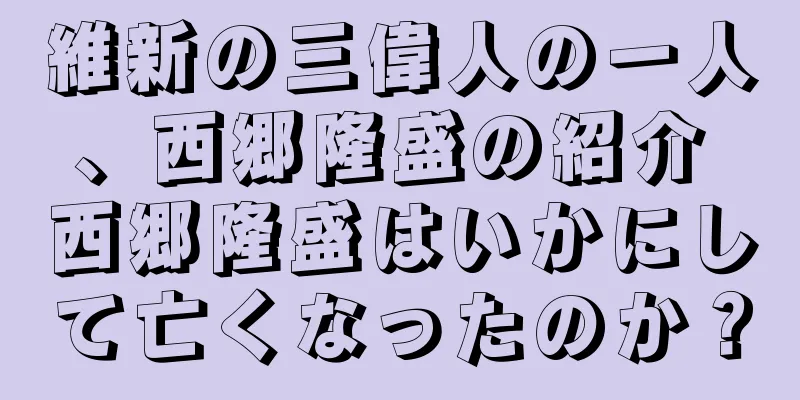
|
日本の江戸時代後期(幕末)に活躍した政治家であり、明治維新の指導者。通称は吉之助、別名は南州。彼は薩摩藩の下級武士の家に生まれた。木戸孝允、大久保利通とともに「維新の三英傑」の一人として知られる。 西郷隆盛(さいごう たかもり、1828年1月23日 - 1877年9月24日)は、日本の江戸時代後期の薩摩藩出身の武士、軍人、政治家である。初期には討幕運動に携わっていたが、維新後は外国侵略と進出を主張し、支持した。朝鮮征伐を主張し反対されたため辞職し、鹿児島に戻り私塾という軍事政治学校を設立した。その後、政府に対して武装蜂起し西南戦争で敗死した。 少年時代 1828年1月23日(文政11年12月7日)、西郷隆盛は薩摩藩鹿児島城下の下加治屋町山で生まれました。彼は御所執事西郷九郎隆盛の長男でした。天保11年(1841年)、成人の儀礼を行い、名を高栄吉之助と改め、下鍛冶屋郷の青年組織である二歳組に加わった。 彼は幼少の頃から厳しい武士の訓練を受け、それによって武士の精神を養い、忠誠、孝行、博愛、正義といった強い封建時代の武士の道徳観念を身につけました。 1844年、彼は郡書記官の補佐を務めた。その後、彼は合計10年間郡書記官を務めた。維新の三傑の一人である大久保利通とともに伊藤重右衛門から陽明思想と朱熹思想を学び、福昌寺の無山和尚から禅を学んだ。迫田郡奉行は飢饉を理由に年貢の減額を藩に求めたが却下され、怒って辞職したが、そのことは忘れられない印象を残した。没落寸前の下級武士階級の出身で、下級役人として長く勤めた経験から、下級武士階級に対する理解と共感、幕末の政治腐敗に対する認識を身につけ、決意をもって改革の道を歩み始めた。島津斉彬が薩摩藩主となった後、西郷隆盛率いる「節忠組」は農民の負担軽減について天皇に手紙を出した。彼の政治思想は島津斉彬に高く評価された。 公武融合 28歳のとき、西郷は薩摩藩主島津斉彬の側近となった。藩政改革による富国強兵の理念に感化され、藤田東湖や橋本左内といった勤王派の影響を受け、天皇に仕えて幕政改革を決意した。嘉永7年(1854年)、島津斉彬に従って江戸に出、3年間江戸に住んだ。斉彬らが提唱した公卿と将軍が協力する「公武合体」運動に積極的に参加し、次第に改革者として名を馳せた。 1858年、島津斉彬の急病により、島津忠義が藩主となり、実権は父の島津久光が握ることとなった。西郷は京都と江戸を行き来しながら、天皇を擁護する活動を続け、幕府の最高官僚である井伊直弼の排除を企てた。井伊は「安政の大獄」を設けて、天皇を支持する者たちを残酷に弾圧した。西郷と月城は都から脱出し、難を逃れた。二人は相次いで鹿児島に戻ったが、突然薩摩藩から脱藩を命じられた。王を支える状況は絶望的であると感じた彼らは絶望し、船が錦江湾に着くと、互いに抱き合って海に飛び込んで自殺した。二人が救出されたとき、月昭はすでに亡くなっており、西郷も瀕死の状態だった。島津久光により奄美大島に流刑となった。 1862年、西郷隆盛は既に藩内で実権を握っていた大久保利通の協力を得て薩摩藩に復帰した。処分が解除された後は尊攘派の一員として活動するようになった。久光はもともと、西郷の名声を利用して上洛し天皇を擁立し「政軍一体化」を進めるという自らの計画を実現しようと考えていた。西郷は久光に十分な名声と地位がないと考え、これに反対した。実際、西郷の新たな政治理念である「尊皇攘夷」は藩主の「公武合体」と矛盾しており、西郷は過激派の武士と接触した。久光は激怒し、彼を徳之島に流刑にし、2ヵ月後に死刑囚が流刑される沖永良部島の監獄に移送した。 しかし、彼は再び島に追放された。獄中で過ごした2年間、西郷は多くの苦難を経験しましたが、儒教の書物を多く読み、天皇に忠誠を尽くす決意を固めました。 明治維新 1864年、討幕派の勢力の増大と藩士たちの要求により、久光は西郷の召還を命じ、薩摩藩の陸海軍の実権を握る重責を西郷に託した。西郷は久光の顧問としてスタートしたが、後に勤皇・倒幕派に加わった。西郷は大久保利通と緊密に協力して薩摩藩の政治改革を遂行した。 1864年7月、幕府は長州藩士による禁門の変を鎮圧した。京都の西郷は久光の命令に従い、鎮圧活動に参加し、戦闘で負傷したため、賞賛された。 9月、西郷は大阪で勝海舟と会い、二人を知り、お互いに深い理解を深めた。この出会いは西郷の視野を広げ、幕府の腐敗と衰退を実感させ、考え方を変えた。この頃の西郷は、まだ「薩摩主体」の現地意識を持っていたため、その行動は非常に躊躇いがちであった。 9月に幕府が長州征伐の軍を編成すると、西郷は依然として自藩の利益を理由に遠征軍に参加し、指揮を執った。幕府が第二次長州征伐を組織したとき、西郷は既に諸大名が連合して幕府と戦うという自らの提案を実行に移していた。彼は幕府の再三の命令や督促にもかかわらず、断固として出兵を拒否し、その後の同盟に確固たる信頼の基盤を築いた。 1866年7月、将軍徳川家茂が亡くなり、徳川慶喜が後を継ぎました。 12月、倒幕派を常に鎮圧してきた孝明天皇が崩御し、幼少の明治天皇が即位した。討幕派は朝廷内の情勢を利用し、武力倒幕の準備を始めた。坂本龍馬の仲介のもと、薩摩藩と長州藩は「薩長同盟」を結成し、薩摩藩と土佐藩も同盟を組んだ。 「西南の豪族」は朝廷の権力を掌握し、共同して幕府を攻撃した。西郷らはイギリスとの「薩英同盟」も結び、イギリスからの武器購入や資金援助を期待したが、イギリスの侵略的意図を警戒していた。 1867年9月、西郷と大久保は岩倉ら公卿らを通じて、天皇の名で「倒幕の密勅」を発布する準備を進めた。 10月14日、薩摩藩と長州藩は「倒幕の密約」を受け取り、配備が整うと西郷、大久保らの倒幕派はクーデターを起こし、「王政復古」を布告した。将軍制度の廃止が宣言され、徳川慶喜は「即刻辞職し所領を明け渡す」よう求められた。討幕派は即日新政府を組織し、西郷、大久保らが新政府の実権を握った。 徳川慶喜に代表される旧幕府軍は歴史の舞台から退くことを拒み、優勢な軍勢を組織して反撃に出た。これが歴史上戊辰戦争として知られている。 1868年1月、京都南部の鳥羽・伏見地域で幕府軍と官軍の間で大規模な軍事衝突が勃発した。効果的な指揮と兵士たちの勇敢さ、そして民衆の支持のおかげで、官軍は自分たちの3倍の規模を持つ幕府軍を打ち破り、勝利を収めました。西郷は新政府により陸海軍の総大将に任命され、討幕軍は京都から出撃して江戸を包囲した。江戸城を守っていた勝海舟は、国内外の情勢を慶喜に説明し、慶喜に降伏の決意を促した。西郷は幕府に7つの降伏条件を提示し、勝海舟に会うために江戸へ向かった。最終的に幕府の降伏協定が締結され、歴史上「江戸無血開城」として知られることになった。 8月以降、西郷は官軍を率いて関東・東北地方で戦い、幕府残党を制圧して次々と勝利を収めた。西郷は凱旋帰国後、その優れた軍功により褒賞を受けた。西郷は明治維新と戊辰戦争での功績により2000石の禄を与えられ、諸藩士の中でも最高位かつ最も寛大な人物となった。 西郷は、下級武士の利益を害する明治政府の政策に不満を抱き、中央政府を離れ地方に戻った。西郷は、明治維新後の下級武士たちの悲惨な運命に同情し、多くの高級官僚たちの名誉と富の追求と浪費に耐えられず、彼らが「利益」のために「義」を忘れていると非難した。こうした国内問題で西郷は大久保らと対立した。西郷、大久保らの間では対立もあったが、彼らは皆、近代国家を建設し、日本を半植民地危機から解放するためには、封建的分離主義的状況を排除し、中央集権的な国家権力を確立する必要があることを認識していた。 1871年以降、彼らはこの目標の下に団結し、廃藩置県の改革の遂行に全力を尽くしました。 1872年7月、西郷は陸軍元帥兼近衛軍総督に任命された。翌年7月、政府は封建的な土地所有を変革し、近代的な土地制度を確立するために地租改革を実施するため、「地租改革条例」など5つの文書を公布した。政府はまた、政治、経済、軍事の分野で数多くのブルジョア改革を実施した。西郷はこれらの改革を主導し、また参加した。改革の内容に特別な貢献をしたわけではないが、軍を指揮し、武力を後ろ盾として改革が順調に進むよう尽力したことは、西郷ならではの貢献であったといえる。 西郷、大久保、木戸は幕府の打倒における役割と貢献により「維新の英雄」として称賛された。 南西戦争 1873年、明治政府の改革により、武士は次第に力を失い、特に下級武士は次第に生計を立てるすべがなくなっていった。徴兵令が施行されると、下級武士は公式に軍事力を失ったと宣言された。下級武士の力を取り戻そうと、西郷隆盛は「朝鮮出兵」と「台湾出兵」を発動し、朝鮮大使に志願した。大久保利通ら明治政府高官は欧米視察から戻ったばかりで、明治政府は内政に注力すべきと考え、西郷の提案を拒否した。西郷は怒って辞職し、1874年(明治7年)薩摩に戻った。 (大久保利通は外国の侵略に反対していたわけではない。日本の国力と世界の他の国々の国力の差が大きいことを知っていたので、国内統治に重点を置き、それを先送りにした。文明開化運動によって国力が若干高まっていた朝鮮の後ろ盾である清朝を倒すどころか、朝鮮を征服するにも日本の国力は十分ではなかった。)西郷は辞職して故郷の薩摩に戻り、武士の道を広める「私塾」を設立した。 武士問題はますます深刻になり、日本各地の不満を持った武士たちが次々と反乱を起こした。より大規模な戦争としては、1874年に江藤新平が九州佐賀県で起こした佐賀の乱がある。事件が解決した後、日本政府は武士たち、特に最も抵抗意識の強かった薩摩武士たちをなだめようとした。同年(清朝同治13年)、台湾で琉球難民が原住民に殺害されたため、日本は台湾に軍隊を派遣した(中国側は牡丹事件と呼んだ)。日本政府は西郷隆盛の弟、西郷譲道を特別に中将に昇進させ、台湾原住民事務局長に任命し、3,000人以上の軍隊を率いて台湾南部の原住民族を攻撃した。日本は軍事的には敗北したが、アメリカの支援と清政府の腐敗と無能さに頼り、清政府が賠償金として銀50万両を要求した後、日本軍は台湾島から撤退した。 結果として、貴族階級の問題は解決されなかった。 1877年、薩摩藩の恨み深い武士たちが鹿児島の政府軍の火薬庫を襲撃し、西南戦争が始まった。当時、西郷隆盛は鹿児島にいなかった。彼はその知らせを聞いてため息をついたが、それでも士族を率いて鹿児島に戻った。彼は「政府を問う」という名目で軍を率いて北上し、熊本城で政府軍と激戦を繰り広げた。結局、政府軍は薩軍を破り、西郷隆盛は鹿児島へ撤退した。彼は負傷し、部下が後を継いだ。これが日本最後の内戦の終結となった。 1877年、西郷隆盛は官職を剥奪されたが、国民の同情は強く、明治天皇も遺憾の意を表明した。黒田清隆の尽力により、1889年に大日本帝国憲法が公布されると恩赦が与えられ、死後三位に叙せられた。 西郷隆盛率いる下級武士の蜂起は、零細生産者と小ブルジョアジーの利益を代表しており、ブルジョアジーの民権派や急進派と密接な関係を持っていた。彼は資本主義の発展を主張し、大地主やブルジョアジーに反対し、強い国家主義的感情を持っていた。西南戦争の失敗後、天皇が統制し支配する封建軍国主義国家が樹立され、日本の資本主義革命は終焉を迎えた。実は西郷隆盛自身も大陸政策の支持者であり、当時の歴史的潮流は列強が植民地を分割することであったため、誰が権力を握っても日本の攻撃的な性質は変わらないはずであった。 |
<<: 維新の三偉人の一人、大久保利通の紹介 大久保利通はいかにして亡くなったのか?
>>: 明治維新の先駆者、坂本龍馬の紹介 坂本龍馬はどのように亡くなったのか
推薦する
「曲玉観・龍首雲飛」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
屈原玉関・龍首の飛雲劉勇(宋代)龍頭の上に雲が流れ、川のほとりに太陽が沈み、手すりに長く寄りかかって...
王室の称号の起源: 古代中国の女王はなぜ自分たちを「艾佳」と呼んだのか?
古代中国の王室のさまざまな称号の起源: 古代の王には多くの称号があり、それぞれの称号には起源がありま...
古代の詩「東城は高くて長い」の内容は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
東城は高くて長い [漢代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見て...
宝仔と鳳傑の誕生日のお祝いの違いは何ですか?ジアの意図は何ですか?
宝仔と鳳潔の誕生日のお祝いの違いをご存知ですか?知らなくても大丈夫です。Interesting Hi...
張燕の「月下の笛:一万里の孤独な雲」:この詩は悲しく、悲痛で、作者の内なる声を反映しているはずだ
張炎(1248年 - 1320年頃)は、字を叔霞といい、玉田、楽暁翁とも呼ばれた。彼は臨安(現在の浙...
燕は戦国時代の七大国の中で最も弱かったのに、なぜ最古と言われるのでしょうか?
春秋時代(紀元前770年 - 紀元前476年、紀元前453年説、紀元前403年説)の長期にわたる覇権...
南宋文芸詩奇譚集第8巻『易堅志全文』
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
皇帝は軍事力をしっかりと掌握するために、辺境地域の将軍たちにどのような制限を設けるのでしょうか?
五代十国時代でも、春秋時代でも、属国間の争いの最も根本的な理由は、その地域で元々君主に従属していた兄...
張暁祥の「臨江仙:梅の花が一番美しいのはどこ?」この詩は梅の花を鑑賞することで愛国心を表現している。
張孝祥(1132-1170)は、名を安国、通称を玉虎居士といい、溧陽呉江(現在の安徽省河県呉江鎮)の...
陸兆霖の「弟を四川に送る」:詩全体が深く激しい感情に満ちており、起伏がある。
呂兆林(?-?)、雅号は盛之、号は有有子、渝州樊陽(現在の河北省涛州市)の人であり、唐代の詩人である...
『易堅志』第一巻の主人公は誰ですか?
九人の聖人と幽霊YongiaのXue Jixuanは、Zuosiの秋にHuiyanの息子でした。数イ...
『紅楼夢』で林黛玉さんは普段どんな服装をしていますか?
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。知らなくても大丈夫です。Interesting Hi...
『紅楼夢』で中秋節を祝う際に、どんな奇妙なことが起こったのでしょうか?なぜ賈震は驚いたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
太平広記・巻99・釈証・慧寧の原文の内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
太平広記・第84巻・奇人・陸俊の原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...