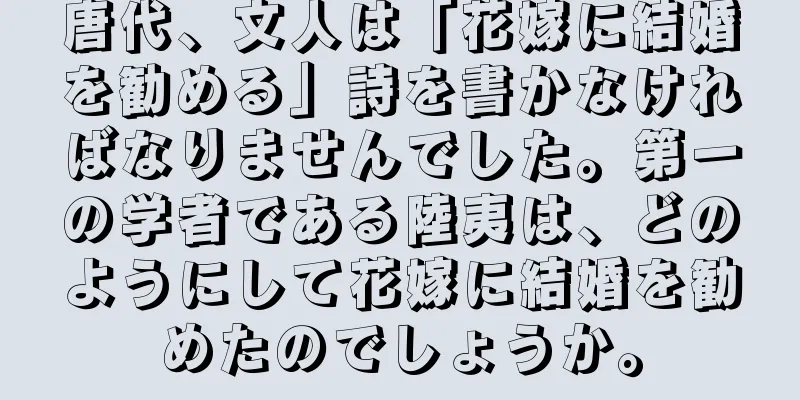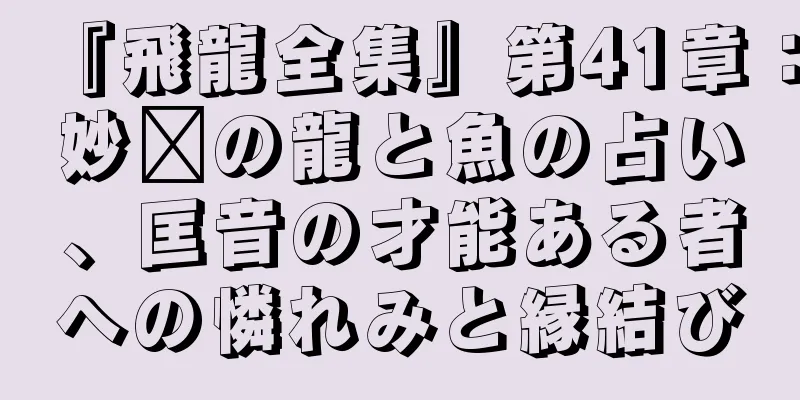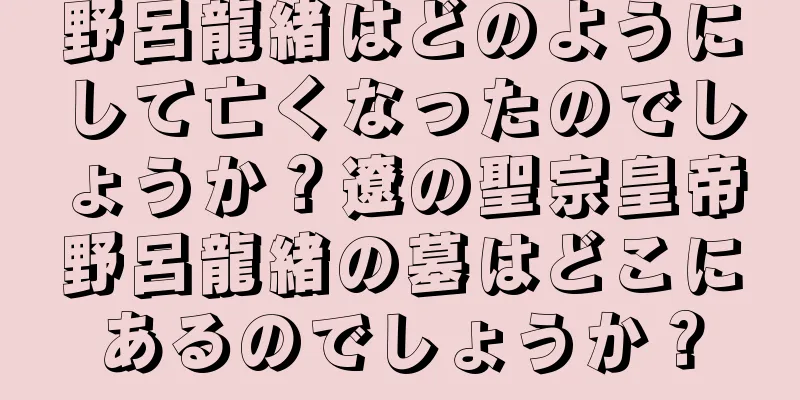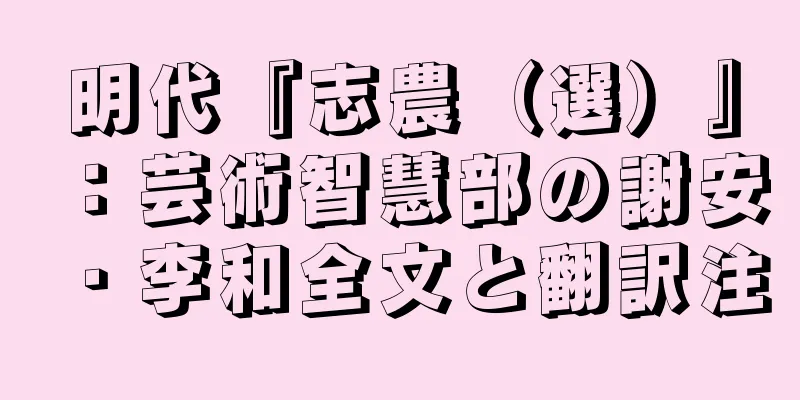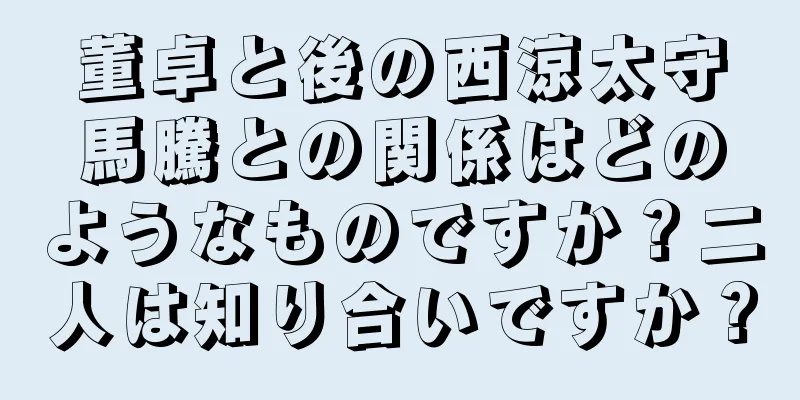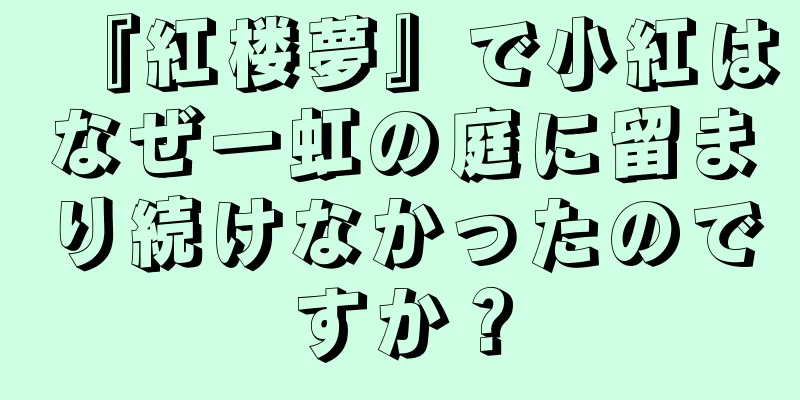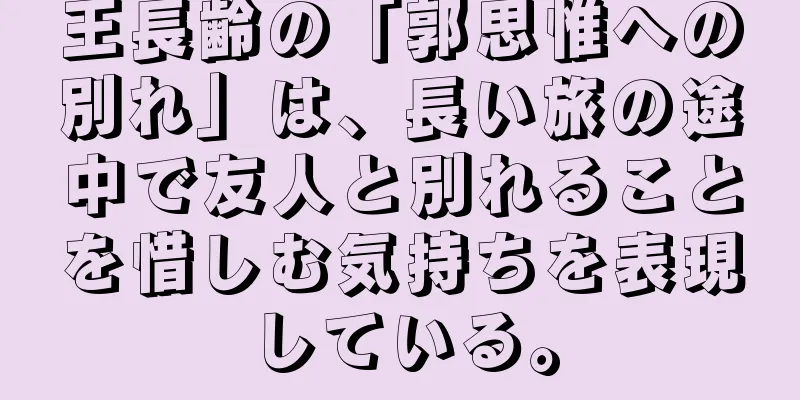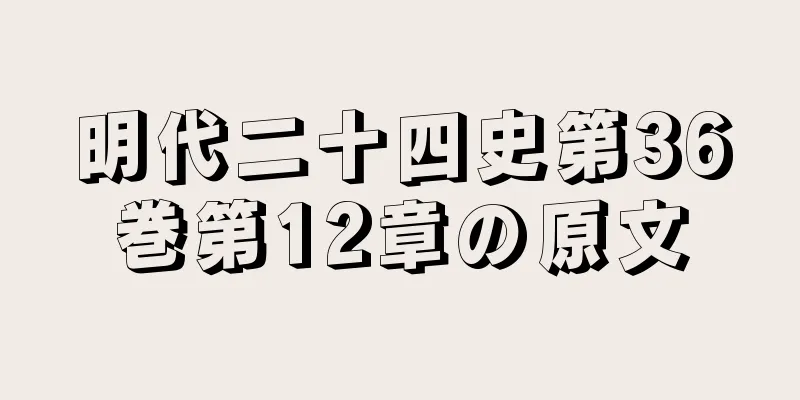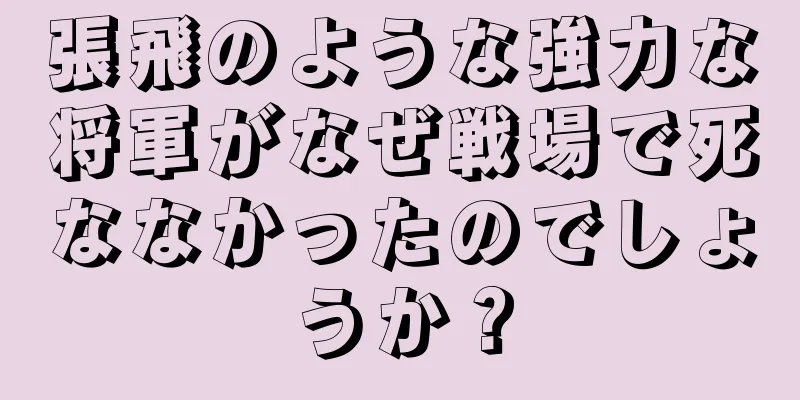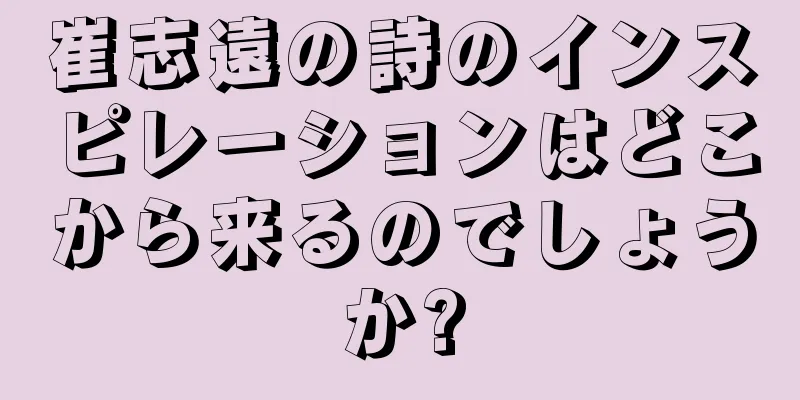明治維新の先駆者、坂本龍馬の紹介 坂本龍馬はどのように亡くなったのか
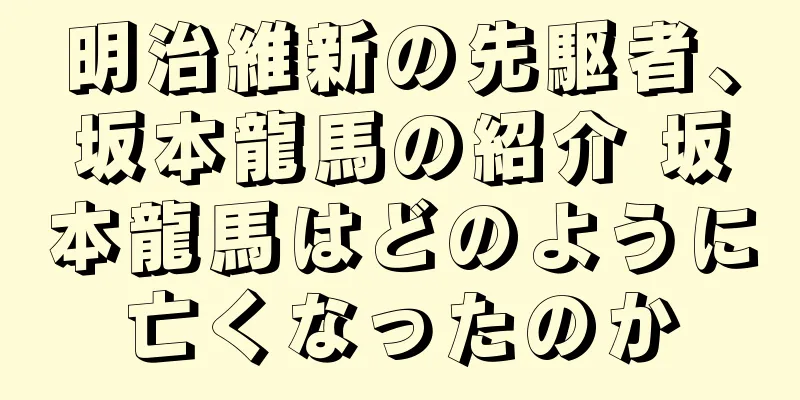
|
坂本龍馬は、日本の明治維新期の改革者であり、討幕改革運動の活動家、思想家でした。土佐藩士であったが、二度の脱藩を経て維新派となり、薩長両藩の軍事同盟成立の立役者の一人となった。後藤象二郎に提唱した朝廷への政権返還を重視し、天皇を中心とした新しい国家体制の樹立を構想した「船中八策」は、その後の維新政府の重要な指針ともなった。 龍馬誕生 戦国時代の歴史に詳しい人なら、明智光秀の領地の中心が坂本城だったことを覚えているはずです。坂本姓はこれに由来する。明智光秀の娘婿・明智秀満(左馬助)は坂本城天守閣に放火したが、死なずに土佐長岡郡に逃れたと伝えられる。四代目八兵衛は居酒屋「才田屋」を開業し、六代目八郎兵衛は武士の身分を得た。八郎兵衛藩主直益は坂本龍馬(本名直宗)の祖父である。 坂本龍馬は、1836年11月15日(天保6年1月3日)、土佐藩高知城下町(現在の高知市本町筋1丁目)の裕福な武士の家に生まれました。先祖は酒屋「才田屋」を営み、酒を売っていたが、後に金で買った武士階級の最下層である士族の身分を得た(土佐藩の士族は主に上級の軍曹階級と下級の伍長階級に分かれ、軍曹と伍長の間には様々な差別待遇があり、伍長階級は長らく軍曹階級に抑圧されていた)。 父は坂本弥兵衛直明、母は幸。母親が妊娠していたとき、お腹の中に雲や龍、駆ける馬が飛んでいる夢を見て、その子を龍馬と名付けたと言われています。坂本家の末っ子で、兄(こんぺい)と姉(ちづる、えい、おとめ)が3人いる。したがって、龍馬は他のほとんどの明治維新論者とは異なっていました。第一に、彼は身分が低く、単なる田舎紳士であり、第二に、非常に裕福でした(斎藤屋は土佐最大の商人の一人でした)。 剣士 坂本龍馬が生まれた当時は、幕府が終わり、西洋資本主義の侵略が起こり、日本は未曾有の国家的危機の時代でした。この頃、日本の識者たちは国防意識が強く、日本を守るために武士たちは再び武術、特に剣術の稽古を始め、剣術は再び復活し、日本各地の剣術道場も再び栄え始めました。坂本も10代の頃は例外ではなく、自宅近くの小栗流の剣士、日根野弁治の剣術道場で剣術を学んだ。下級武士の子弟たちが、何の束縛もなく、自由な雰囲気を漂わせながらここに集まっていた。 1853年、19歳の時に坂本は江戸に出て、京橋桶町の北辰一刀派の千葉定吉の剣術道場に入り、剣術の腕を磨きました。彼は、忠誠と孝行を忘れず、修行を第一とし、物質に惑わされて金を無駄にせず、ポルノに耽って国事を忘れず、技能の習得に集中するという父の訓戒を心に留めていた。 2年後、ついに師範の秘伝書を取得し、千葉定吉剣道場に戸籍を移し、江戸に定住した。 1857年、土佐藩主山本中谷が江戸で武芸大会を開催した。大会には数十名の剣士が参加し、坂本駒之助と島田駒之助が優勝した。 当時、剣術堂は武術の訓練の場であると同時に、政治の学校でもありました。各藩の若者たちが国情や外敵への対処法などを議論していました。彼らは自らの理論を検証するために、各国(藩)に出向いて情報収集を行い、議論の材料として江戸に戻った。土佐藩の武市水山、長州藩の高杉晋作、桂小五郎らもそのような若者であった。文久元年(1861年)、水山武市は江戸の藩邸で土佐勤王党を組織し、土佐に戻って組織を拡大した。200名以上が参加し、坂本もその一人であった。 1862年1月、坂本は土佐勤王党の指導者である武市瑞山の代理として長州に行き、長州勤王党の指導者である久坂玄瑞と会談して国内の状況を尋ねた。 3月に帰藩後、断固として脱藩した。 当時、領地から逃げ出すことは重罪であり、本人が処刑されるだけでなく、家族も巻き込まれることになりました。坂本が藩から逃げたため、妹の乙女は離婚を余儀なくされ、坂本に名刀を贈った妹の栄は自殺し、兄の全平は大金を費やしてようやく坂本を助けた。土佐藩を脱藩後、職業革命家となったが、厳しい人生の試練が彼を待っていた。 幕末に脱藩した者たちにとって、富と名声への強い欲望を抱き、武力による倒幕運動「天術会の乱」を起こした先駆者である吉村虎太郎のように、反乱を起こすことしか道はなかった。しかし坂本が脱藩したのは名声のためではなく、反動勢力が渦巻く土佐藩の束縛から逃れ、思想と行動の自由を得るためであった。そのため、坂本は脱藩後、吉村虎太郎に従わず、九州を巡り、大坂を経由して江戸に出て、幕臣の勝海舟と会い、航海術を学んだ。水山武市は、藩から脱出した彼の英断を讃える歌を詠んだ。 肝臓と胆嚢が強く力強く、奇跡的なアイデアが自然に浮かぶでしょう。 私の飛行能力と潜水能力を知っている人はいますか?私はドラゴンの名を恥じません。 ドラゴンの足跡 文久3年(1863年)8月18日の政変により、三条実ら急進派七卿は勢力を失い、勤皇攘夷派は京都から追放された。土佐藩の保守派山本長門は水山武市率いる勤王党を弾圧し、武市は捕らえられ自害した。これは武市氏が天皇、将軍、大名への忠誠という封建主義の思想から脱却できなかった結果であった。坂本は薩摩藩と協力し、水山武市の「一藩忠臣」を超え、薩長藩間の武器や船舶の売買、輸送を専門とする亀山商事を設立した。 坂本は生涯老子を崇拝し、自らを「天然堂」と称した。彼は老子からニヒリズム、つまり自分自身を空虚なものとみなす教えを受け入れた。坂本が最も注目したのは、老子の「自然に回帰し、人間の存在は無や空虚の中にのみ意味を持つ」という思想だった。 この無欲・自己否定の精神は、具体的には「他人から評価されたくない」「他人の評価に同調しない」という形で現れます。師匠の勝海舟が「行為は我にあり、評価は他人にあり、私には関係ない」と言った通りです。坂本は慶応3年(1867年)に後藤象二郎に『船中八策』を披露した際、それが自分の考えだと自慢することはなかった。そのため、山内道々の寵臣であった後藤が提案した際には、それを土佐藩の領有論とみなし、さらにそれを幕府への大政奉還の提案へと発展させた。後藤とともに王政復古運動に参加し、「五箇条の御誓文」を起草した福岡孝もこのことは知らなかった。後になって、「船中八策」が坂本龍馬の考えた策だったと知ったのである。これは坂本の先見の明のある考えだ。後藤がそれを完全に自分の創作物として捉えなければ、山内堂は受け入れないだろう。これは、他人に判断されることを望まずに、考えを自由に表現した結果です。 坂本龍馬の思想の進歩は、偏狭な「忠君一門」を捨て、尊王攘夷という単純な考えから脱却した点にある。攘夷でも建国でもなく、この二つの概念を超えて緑の大海原に目を向けた。つまり富国強兵こそが目下の急務であった。そのため、1862年に彼が江戸へ行ったのは、建国論者の勝海舟を殺すためではなく、勝海舟から影響を受け、教育を受けるためでした。なぜなら、勝海舟は2年前に咸臨丸でアメリカを訪れ、近代資本主義国の政治、経済、社会について学んでいたからです。 時代を先取り 日本人の心の中の坂本龍馬のイメージは、過去にとらわれず常に時代の先を行く人物です。小さな例は、かつてトーサ・キノ党のメンバーであるヒガキ・ナオジに言った:「私は将来、より柔軟で実用的であるコダチが好きだ。坂本リョーマがカツシュシュの見習いになった後、ナオジは再び龍馬に会うために銃を持ってきました、そして、リョーマは「国際法に関する本」のコピーを取り出しました:「ピストルは敵を殺すことができますが、この本は日本を復活させることができます!」サカモトは、紳士が時代を迎えていると言いました。 船上での8つの戦略 坂本龍馬は勝海舟の庇護のもと、神戸海軍兵学校(海軍兵学校や商船大学に相当)に入学し、同校の塾長となった。しかし、1864年、勝海舟は弟子の一部が倒幕軍として池田屋事件に参加したため解任され、1865年に海軍操練所は閉鎖された。 そこで坂本龍馬と伝習所の生徒たちは長崎に亀山商事を設立し、薩摩藩と長州藩への武器の輸送と輸入を専門に行うようになりました。商社設立の目的は生計を立てることであったが、坂本にとって幕府を倒すことは政治闘争というよりも経済闘争であった。つまり、有力な藩は幕府が独占していた貿易を掌握し、幕藩体制を解体し、新たな政府を編成しなければならなかったのである。 1867年、亀山商店を母体として坂本龍馬を隊長として海援隊が結成され、その傘下に文官、武官、装備官、輜重官、医官などで構成され、土佐藩の商工会議所となった。そのため、土佐藩も坂本の脱走罪を赦免した。 坂本にとって、海援祭は単に土佐藩の利益のために設けられたものではなく、大政奉還後の新体制のもとで確立された日本国家の政策指針を凝縮し象徴するものであった。坂本龍一の思いはすべて海援隊に託され、後に岩倉具視に「世界の海援隊」と評した。 海援祭の第一条は、「我が藩内外を問わず海事に関心のある者は、誰でも入隊できる。この隊の目的は、我が藩の交通、商業、開発、投機等の援助を行うことである。今後は、出身を問わず、隊員は本人の希望に基づいて選抜される。」と定めている。こうして海援隊は、いわゆる封建制度からの脱却者、自由民の集団となり、身分にとらわれない組織でもあった。この側面は、幕藩体制の階級社会に対抗するだけでなく、階層的アイデンティティのない社会組織を生み出しました。これは明治維新で樹立された幕府とは程遠く、坂本龍馬の理想は跡形もなく消え去った。 薩摩藩と長州藩は国政の主導権をめぐって対立していたが、坂本龍馬の仲介により、慶応2年1月、長州の木戸孝允と薩摩の西郷隆盛、小松武田らは京都で「薩長同盟」を結成し、一致して討幕勢力を結集して武力倒幕の準備を進めた。しかし、武力で幕府を倒せば、必然的に外国が内紛に乗じて侵略してくるでしょう。日本の独立を確保し、列強が中国に対して行ったように日本の領土を荒廃させることを防ぐためには、内戦を避けなければなりません。後藤象二郎は坂本龍馬の洞察力に感謝し、どんな秘密があるのか尋ねた。 徳川家に権力を朝廷に返還させるという秘密の計画があった。 「何?」と後藤も呆れたが、すぐに「そうだな、そうだったら薩長両藩は蜂起せず、戦争も避けられるし、同時にイギリスやフランスも落胆するだろう」と思った。しかし、おそらく親幕派も黙ってはいないだろう。 「徳川慶喜を再び大臣に任せることもできる。 「それは大した違いではないでしょうか?」 「いいえ、貴族、公爵、王子、武士、平民を問わず、世界中の才能のある人々はすべて議会や国政に参加すべきです。 ” 後藤は、内乱を避け、列強が危機に乗じるのを防ぐという坂本の優れた戦略をようやく理解した。また、薩摩藩と長州藩という2つの強力な藩の考えを実行に移し、同時に幕府が致命的な損害を受けるのを防ぎ、土佐藩がより優れた指導的役割を果たせるようにした。これは一石二鳥の戦略であるだけでなく、一石四鳥の戦略でもあります。 「分かりました。やってみましょう!いや、これしかないのです。明日、藩船『夕顔丸』が北京に着きます。一緒に来てください。船上であなたの言葉を文書にまとめ直したいのです。」後藤象二郎は言った。 「夕顔丸」では、海援隊の文官であった岡建が坂本龍馬の考えを記録したが、これは「船中八策」として知られるようになった。(1)政権の返還、(2)上下院の設置、(3)全国から人材の登用、(4)条約改正に広く世論を取り入れること、(5)法典の改訂、(6)海軍の増強、(7)首都防衛のための近衛兵の設置、(8)金銀の相場を外国並みにすること、などである。 この新政権の骨子は、4ヵ月後に「王政復古」として実現され、1868年の「五箇条の御誓文」へと発展した。すなわち、(1) 光興会議において、すべての事柄を世論で決定する、(2) 官吏、将軍は団結して古典の理論を推進する、(3) 官吏、武官、庶民は皆、自分の志を追求できる、(4) 古い慣習を廃止し、正義を確立する、(5) 皇帝の基盤を強化するために、世間の知識を求める、というものである。 坂本龍馬の偉大さは、尊皇派と幕府派、建国派と攘夷派に分裂した国論の中で、革命の目的を達成するための戦略を立て、革命後の政治体制の骨組みを描いたことにあります。しかし、後藤は大政奉還を果たした功績で藩主山内堂から褒賞を受けており、これが坂本の独自の考えであったことを知ったのは明治になってからであった。さらに、坂本龍一の「船中八策」は、もともとは非常に具体的なものでしたが、後に「五つの誓い」に発展したときには非常に抽象的なものになりました。封建制の時代に、彼の民主的な政治思想は泡沫となった。 明治維新後、この二つの「八策」に基づいて新政府の組織計画が完成しました。これは坂本龍馬の思想がいかに優れていたか、また洞察力がいかに並外れていたかを物語っています。しかし、龍馬の歴史的役割は不自然に誇張されていると指摘する学者もいる。『船中八策』の原文は、勝海舟の弟子で上田藩士の佐久間象山と赤松小三郎が書いたものであり、『新政府大綱八策』を完成させたのは龍馬ではなく後藤象二郎だった。誰が正しくて、誰が間違っているのかはまだ不明です。 暗殺の謎 1867 年 11 月 15 日の夜は、北風が吹き荒れ、天候は非常に寒く、人々は歩くときでもジョギングをしなければならなかった。 京都四条河原町の土佐藩士行きつけの醤油店「近江屋」の2階で、坂本龍馬と来航中の陸援隊大尉・中岡慎太郎(江戸時代後期の志士、1838年生まれ、1867年死去)が口論していた。その日の二人の議論は、坂本が平和的進化を主張し、中岡が武力による幕府転覆を主張したため、特に白熱したものとなった。 「石川(中岡慎太郎の偽名)、包丁を隣に置いたら、誰も何をすればいいか分からない。包丁から離れたところで議論した方がいいんじゃない?」坂本は中岡に提案した。 「わかった、やろう!」と中岡は答えた。そこで、衝突を避けるために、二人の男はナイフを手の届かない階下の部屋に置いた。これが二人の死のきっかけとなった。 「寒いし、お腹も空いた。今日は誕生日だし、お酒を飲もう。鳳凰、チキンを買ってきて」坂本は中岡に言った。夜の9時頃、召使の鳳基が鶏肉を買いに出かけました。 。やがて階下に誰かが訪ねてきて、坂本を介抱していた山田藤吉が玄関のドアを開けると、そこには仮面をつけた二人の武者が立っていた。彼らは丁寧に「坂本さんいらっしゃいますか?十津川剛士です。いらっしゃったらぜひお会いしたいです」と言い、名刺を見せた。藤吉は坂本と中岡に友人が多いことを知っていたので、何の疑いもなく名刺を受け取り、二人を家の中に案内した。藤吉が二階に上がろうとしたちょうどその時、後から付いてきた刺客に斬られ、血を流して地面に倒れた。 二人の暗殺者は風のようにまっすぐに階段を駆け上がり、家の中に入っていった。一人の刺客が前に座っていた中岡を背後から切りつけ、もう一人の刺客が火鉢の前に座っていた坂本の額を切りつけた。負傷した坂本さんは、床に置いてあった愛刀「吉行」を取ろうと振り向いたところ、さらに肩を2回刺された。刺客が再び襲い掛かろうとした時、坂本はまだ抜刀していなかった刀でそれを防いだ。刃は切断され、刺客は刀で坂本の額を切りつけた。血が壁に掛かった「椿」の巻物に飛び散り、脳髄が流れ出た。坂本は「頭が割れた」「石川、ダオダオ…」と叫び、気を失った。 中岡は坂本が自分の別名「石川」を呼ぶのを聞いたが、長刀が書画衝立の背後にあったため、信長の短刀で刺客と戦わざるを得なかった。予想外に、刺客にさらに数度刺され、地面に倒れた。二人の暗殺者は「もう十分だ、十分だ」と言って立ち去った。 刺客が立ち去った後、坂本は突然生き返り、刀を抜いて、顔に血がにじむ中岡に「お前の手はまだ使えるか」と尋ねた。彼は提灯を手に階段に登り、下を向いて家族を呼んだ。階下には大量の血が流れていた。 30分も経たないうちに、フェンジさんは買ってきた鶏肉を持って戻ってきて、その悲惨な光景を見てショックで気絶した。坂本はその夜(享年33歳)、六箇所に重傷を負った藤吉は翌夜(享年25歳)、中岡はその2日後(17日)(享年30歳)に死亡した。 18日午後2時、北京の陸海軍救護隊員と土佐藩士らの護衛の下、棺3基が近江屋から東山麓の霊山墓地に運ばれ埋葬された。 実際のところ、暗殺者が誰であるかはおろか、その真意すら謎である。龍馬は争いを平和的に解決し、幕府に権力を明け渡しさせる思想を持っていたが、中岡慎太郎は武力による倒幕を主張した。二人はそれぞれ亀山社中から改編された「海援隊」と慎太郎の「陸援隊」を率い、倒幕を企てる諸藩間の連絡役として活躍した。 「海上援助」と「陸上援助」は相互に依存しています。中岡慎太郎が亀山社中にヒントを得て陸援隊を創設したが、坂本龍馬が亀山社中を改編して海援隊を作ったが、実は海援隊は陸援隊の模倣であった。それに比べると、海援隊は商人部隊、龍馬は論客、陸援隊は軍隊、そして慎太郎は間違いなく戦士です。 「龍馬の主な目的は金儲け、慎太郎の主な目的は維新」という議論は単なるデタラメだが、中岡慎太郎の明治維新における役割は龍馬に劣らず、幕府からは龍馬以上に嫌われていた。 そのため、近江屋事件では、暗殺者の標的は龍馬ではなく慎太郎であり、かわいそうな龍馬はただ巻き込まれただけであるという世論が長い間続いていた。明治維新後、新政府の龍馬の積極的な擁立や、龍馬を讃える様々な文学・芸術作品の出現と普及により、坂本龍馬の評価はますます高まり、形勢は逆転し、龍馬が暗殺の主たる標的とされ、中岡慎太郎が不運な存在となった。 暗殺者の主な標的が誰であったかは不明であるため、暗殺者の出自は歴史上の謎となっている。一般的には3つの可能性があります: 1. 暗殺者は京都三界グループのメンバーです。この組織は新選組に似ており、どちらも京都の治安維持のために幕府によって設立された準警察組織であり、その上位機関も京都守護職です。違いは、新選組の主要メンバーが下級武士と浪人の集団であったのに対し、三階組の主要メンバーは幕府直属の上級武士であったことです。明治維新後、三井組組員の今井信夫と渡辺篤の自白によれば、暗殺者は同組の佐々木喜三郎(新政組の清河八郎殺害事件を覚えている人ならこの名前はお馴染みだろう)、首謀者は坂本龍馬の師匠である勝海舟、もしくは海舟と同格の幕府高官であった可能性が高い。 しかし、佐々木喜三郎が1868年の討幕戦争で重傷を負って死亡したことを証明する証拠はない。しかし、今井信夫と渡辺篤は近江屋事件に直接関与したり計画したりしたわけではなく、事件の詳細についてはほとんど何も知らず、噂に基づいて佐々木喜三郎に不利な証言をしただけである。目撃者はいるが、信頼できない。 第二に、暗殺者は新選組から来ます。この推測の根拠は前項で挙げたので、これ以上述べる必要はないが、問題は、証言を行った霊廟守衛らが新選組に対して深い憎悪を抱いており、故意に新選組に罪をなすりつけようとしていた可能性が高いということである。 近江屋事件のわずか3日後、近藤勇は伊東甲子太郎を妾の家に酒を飲みに誘い、酔わせた。そして帰る途中、突然大石鍬次郎ら新選組隊士数名が通りから飛び出し、甲子太郎を斬り殺した。これが「油小路事件」である。それだけでなく、新選組の残忍さはさらに増し、伊東甲子太郎の遺体を路上にさらして待ち伏せし、遺体を引き取りに来た霊廟守衛の主要メンバー7人をいきなり襲撃し、3人を切り殺した。 なぜ彼らはそんなに残酷なのでしょうか? それは、新選組の規則によれば、組を脱退することは裏切りとみなされ、抜け出す方法はただ一つ、つまり死ぬことだからです。後に殺害された3人のうち、藤堂平助は新選組第8番隊隊長であり、服部武雄と茂内有之助も新選組の元隊士であった。新選組は敵を殺すよりも仲間を殺す方が残酷だったのだ! したがって、近江屋事件の犯人は新選組の霊廟警備隊であると主張する人たちは、完全には信頼できない。 第三に、これはすべて薩摩藩の陰謀です。かつては志を同じくする同志であった薩摩と坂本龍馬だが、幕府と対峙するために武力を用いるか政治的強制を用いるかという点で、両者の考え方は次第に乖離していった。さらに、龍馬が山本友康の徳川慶喜への大政奉還の建議を支持したことは、薩摩側からは敵に弾薬を供給する卑劣な行為とみなされた。そのため、暗殺者は薩摩藩に雇われたのではないか、あるいは薩摩藩が龍馬の居場所を幕府に密かに漏らしたのではないかという説もある。真実はおそらく歴史の雑草と煙の中に永遠に埋もれ、追跡することは不可能となるだろう。 |
<<: 維新の三偉人の一人、西郷隆盛の紹介 西郷隆盛はいかにして亡くなったのか?
推薦する
東漢の有名な将軍、殷式の息子は誰ですか?殷式の子孫は誰ですか?
殷史(?-59年)、礼名は慈伯。彼は南陽州新野県(現在の河南省新野市)に生まれた。光烈皇后尹麗華の異...
これは、亡き妻を偲んで那藍星徳が書いた詩です。
本日は、Interesting History の編集者が Nalan Xingde の物語をお届け...
『紅楼夢』で宝玉は金伝児をどのようにからかったのですか?王夫人の反応はどうでしたか?
古典小説『紅楼夢』の男性主人公、賈宝玉は、賈一族では一般的に宝師と呼ばれています。次回は、Inter...
七剣士と十三英雄の第85章:易知梅が魏光達を銃弾で撃ち、徐明高が王文龍を槍で刺す
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
古典文学の傑作『太平楽』:「譜章」第2巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
戴明石と同城文学院 戴明石の作品は何ですか?
戴明石は順治・康熙年間の文学者で、当時の偉大な文学者でした。『南山選集』などの著作があります。戴明石...
「田舎の四季雑感」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
四季折々の田舎の雑感(1つ選択) 【宋代・范成大】穀物の雨は絹と塵のようだ。ボトルの中のワックスを沸...
「絵画のように遠くの山を通る縄」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
絵のように美しい山々を通るロープ那蘭興徳(清朝)遠くの山々は絵のように美しい。短い服と馬。落ち葉のざ...
岳飛伝説第35章:九公山への穀物輸送は盗賊に遭遇し、ファン家村は鹿のために戦い、花嫁を募集した
『岳飛全伝』は清代に銭才が編纂し、金鋒が改訂した長編英雄伝小説である。最も古い刊行版は『岳飛全伝』の...
『西遊記』の続編で白蓮花はどうやって悪に転じたのでしょうか?何が良いか、何が悪いかは、単に見方の問題です。
西遊記の続編で白蓮花はなぜ悪に転じたのか?何が善で何が悪かは、単に視点の違いによるものだ!興味のある...
『襄陽城を登る』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
襄陽城に登るドゥ・シェンヤン3 年目の秋には旅人が到着し、街は四方八方に開かれます。楚山は大地を横切...
清朝時代の鄭板橋の息子への教育物語
鄭板橋は清朝時代の有名な書家、画家、詩人でした。彼の書画はいずれも高い評価を受けており、三大奇観とし...
明朝の皇帝のほとんどは若くして亡くなったのに、大臣たちは50歳を超えて生きたのはなぜでしょうか?
明王朝は中国の歴史上、唐王朝ほど栄華を誇ってはいませんが、漢民族が建国した最後の王朝です。明王朝の2...
呉涛の有名な詩の一節を鑑賞する:旅人の春服は試着され、桃の花はすべて散り、野生の梅は酸っぱい
生没年不明の呉涛は、徳紹と号し、崇仁(現在の江西省)の出身である。彼は宋代高宗の紹興時代の有名な隠者...
8原則症候群鑑別の8つの原則は何を指していますか?
八原則症候群鑑別の8つの原則とは何でしょうか?八原則症候群鑑別は、病気の症状を分析して識別することで...