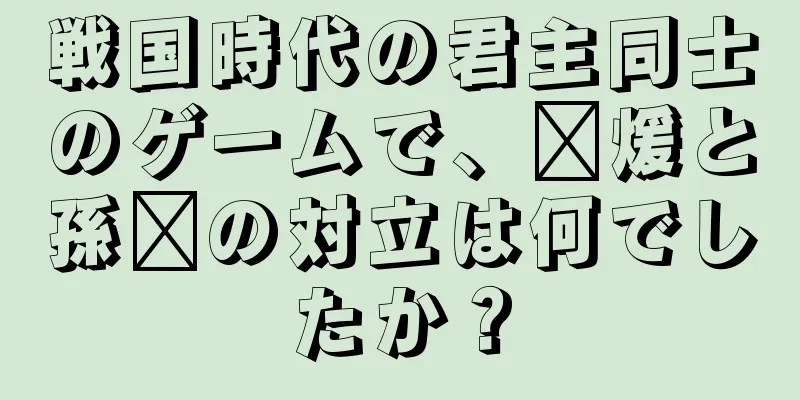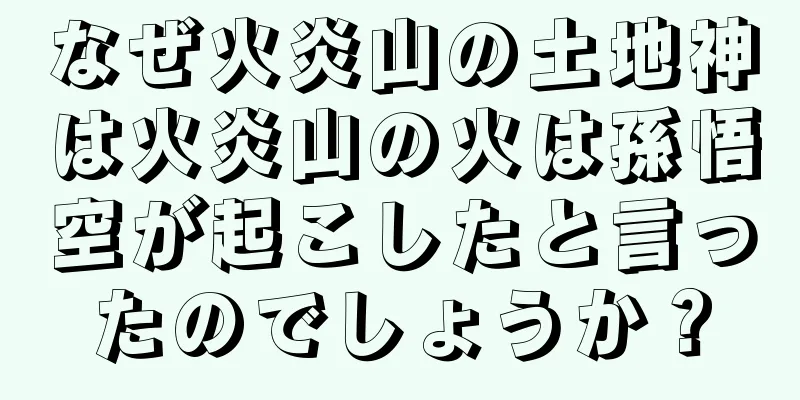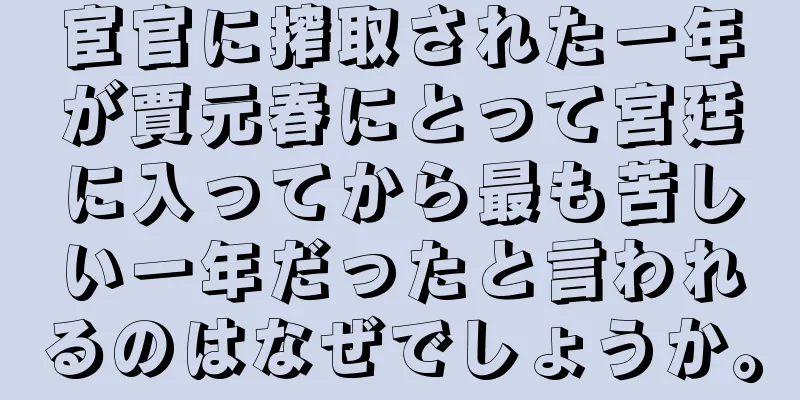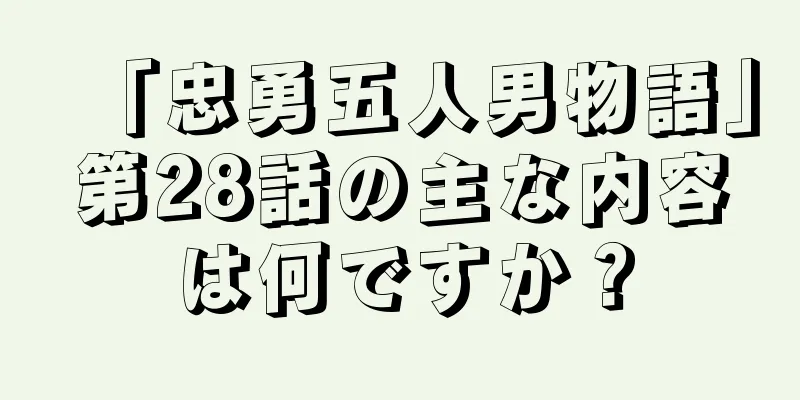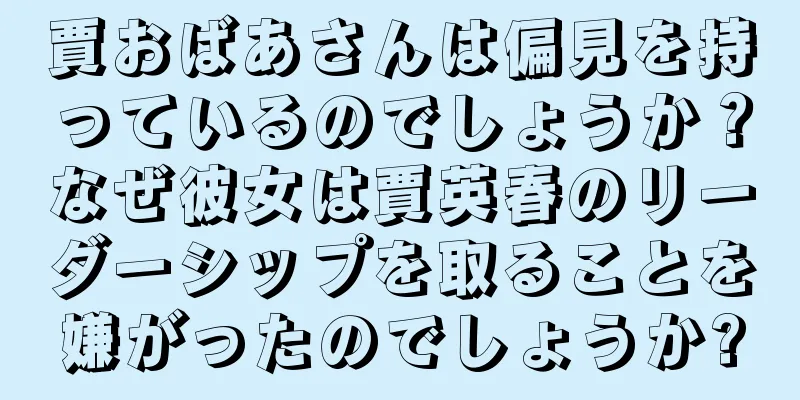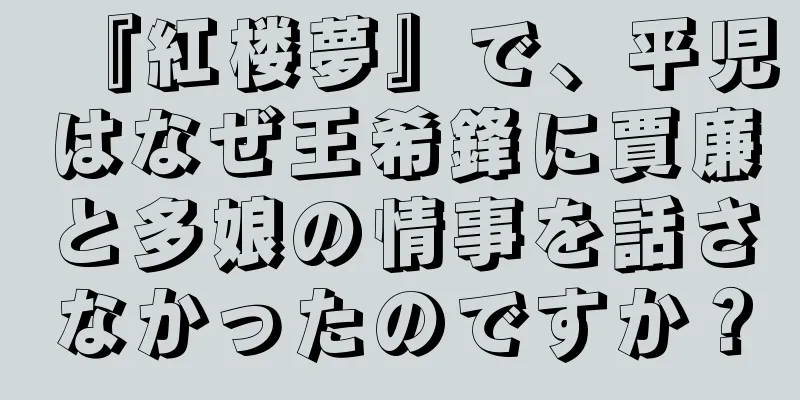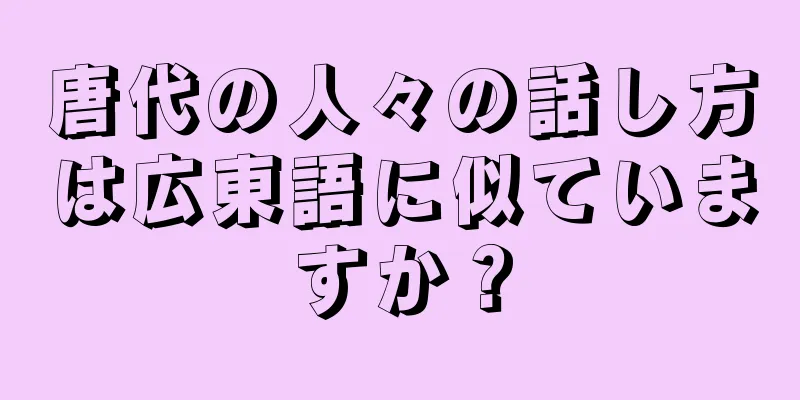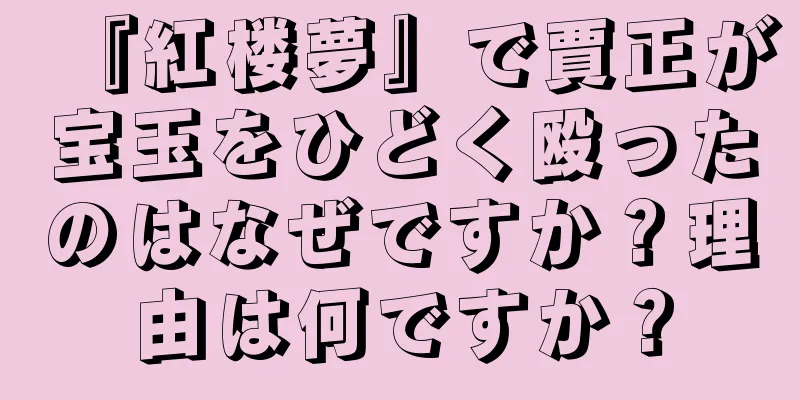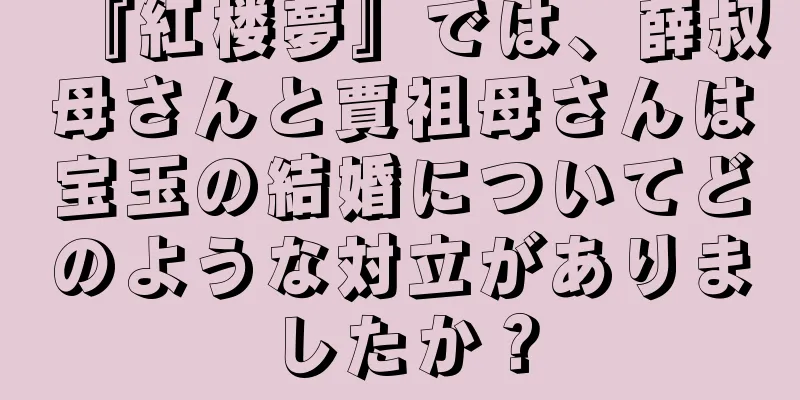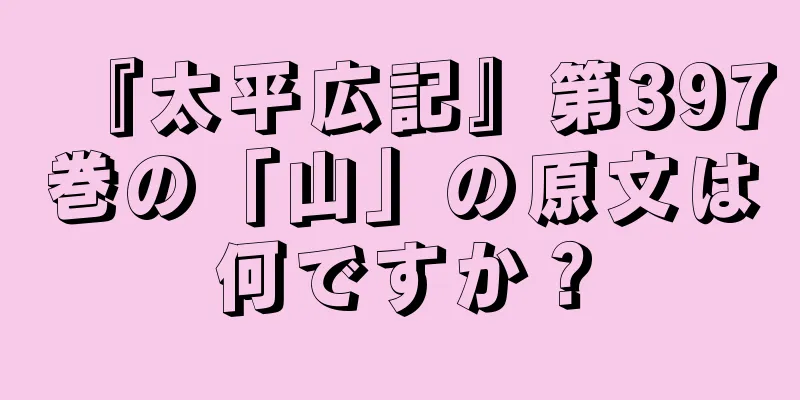なぜ菊が日本の皇室のシンボルとなったのでしょうか?
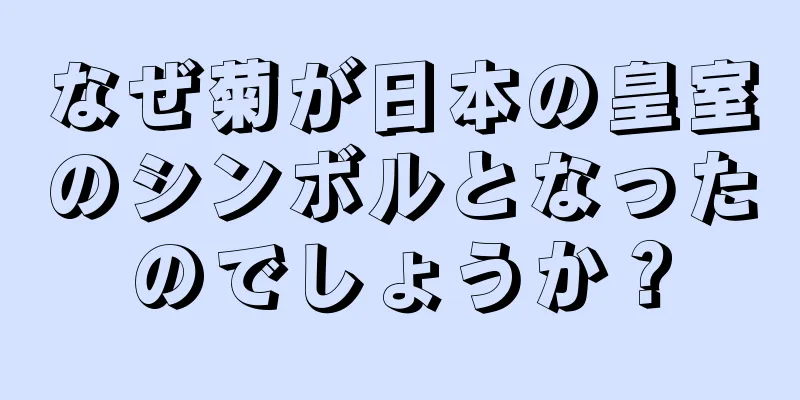
|
中国では、菊は厳粛な雰囲気と結び付けられることが多いようです。日本の皇室はなぜ菊が好きなのでしょうか。ベネディクトの『菊と剣』をより深く理解するなど、歴史や文化に詳しくなれば、皇室と菊の問題はもはや驚くことではなくなります。穏やかで美しい「菊」は日本の皇室の家紋であり、猛々しく果敢な「刀」は武士道文化の象徴です。 「菊」と「刀」を使って、日本人の矛盾した性格、つまり日本文化の二面性(美を愛するが軍国主義的、礼儀を重んじるが攻撃的、新奇なものを好むが頑固、従順だが従わないなど)を明らかにするのは、実は理にかなっている。 菊が日本の皇室のシンボルである理由についてはさまざまな意見があります。おそらく、今日の王族は、学者の机の上にある分厚い論文に十分精通していないのかもしれない。 ある理論はより一般的ですが、それを裏付ける証拠はあまりありません。 8世紀末、日本は平安京(現在の京都)に首都を移し、日本の歴史の転換点となる平安時代が始まりました。この頃、中国と日本の交流が深まり、中国から日本へ菊が伝わりました。当時、菊は珍しく貴重なものであり、日本の皇族は当然ながら菊を最も容易に鑑賞し入手することができた人々であった。菊の美しさに驚き、菊は高貴な花だと思い、菊を愛する傾向が生まれるかもしれません。 平安時代、王侯貴族や文人達は菊の美しさを強く主張してきました。旧暦9月9日の中国の重陽の節句も日本では「復活」し、菊の節句に変わりました。この日、文武両道の大臣が皇帝に敬意を表し、皇帝と大臣は一緒に菊を愛で、菊酒を飲みます。天皇の菊に対する愛はそれだけではない。10月には、残っている菊のために宴会を開き、大臣全員を招いて菊の終わりの儀式を「祝う」と言われている。したがって、日本の皇室の紋章に菊が刻まれたのはこのときであり、その後の天皇もその伝統に従った可能性がある。つまり、約1000年前のこの季節に「菊の紋章」が制定されたことになります。 皇室の紋章がなぜ「十六弁八重菊」なのかについては、当時の皇帝の在位期間がちょうど16年だったため採用されたという説もあると日本華僑報がかつて記事を掲載したこともあったが、結局のところ歴史上に明確な答えはなく、一概に判断するのは難しい。しかし、8層で16枚の花びらが外側に咲いているのは、王室のスタイルを表現するためであることは明らかです。 「十六弁八重菊」は明治初期まで皇室の紋章として使われていました。その後、新たな規定が設けられ、王子などの王族の家紋には「十六花八重外菊文」の使用が禁止され、王子の家紋は「十四花一重内菊文」、つまり「一層のみに十四枚の花弁があり、内側を向いた菊文」と定められた。 16本の菊は天皇の永遠の繁栄と尊厳の永続を祈るためにのみ使われます。 秦の始皇帝に関するもう一つの伝説があります。当時、秦の始皇帝は徐福に12人の貴族の少年少女を乗せた大きな船で中国を出航させ、不老不死の霊薬を求めて海外へ航海させました。代わりに彼らが持ってきた品物の中には、中国特産の菊も含まれていた。その後、船は嵐に遭い、無人島に流れ着きました。そこで人々は生活し、子孫を残し、菊を植えました。この地が後の日本となりました。 どちらの記述が真実であろうと、日本の皇室と菊にはつながりがある。明治維新以降、菊は皇室の装飾として徐々に社会に広まり、国花となる傾向がありました。明治中期には、一部の神社や寺院で菊の文様を装飾として使うことが許されるようになりました。 20世紀初頭、日本の対外侵略と拡張の時代には、天皇への忠誠心と愛国心の思想を促進するために、日本の武器や軍艦に金色の菊の模様が刻まれ、日本兵を鼓舞しました。 日本には国章がないため、現在でも海外にある日本大使館や領事館の玄関には皇室の紋章が使われています。日本のパスポートの表面にも「十六弁八重菊図柄」が描かれており、50円札の裏面にも菊の図柄が描かれている。また、人型の竹の骨に生菊を挿して作った「菊人像」もあります。日本人は文化的なことが大好きで、毎年旧暦の9月になると菊園に行き、菊を鑑賞したり、菊人形展を鑑賞したりすることが今でも人気です。 日本の皇室はなぜ桜を「トーテム」として使わなかったのかと疑問に思う人もいるでしょう。実は、日本には国花が 2 つあります。桜は大衆を、菊は王室を象徴します。しかし、今日では、日本人の間で菊を愛し、育てることは非常に一般的であり、菊酒や菊茶も一般に知られています。現在、日本では菊の品種改良が進み、驚異的なスピードで発展しており、優れた品種は中国にも輸出されているほどです。 |
>>: 孔子はなぜ女性を差別したのでしょうか?孔子は女性を差別しますか?
推薦する
唐代の詩「蘇甫」をどのように鑑賞すればよいでしょうか?杜甫はこの詩をどのような意図で書いたのでしょうか?
唐代の蘇軾、杜甫については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!秋は幕府の...
済公全伝第52章:髭男が済公を慧英楼に招き、盗賊と出会う
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
「柳橋からの夕景」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ウィローブリッジの夕景陸游(宋代)小さな池で魚が跳ねる音を聞きながら、森の中で鶴が戻ってくるのを待ち...
王維の古詩「祖先を偲ぶ劉子胥」の本来の意味を理解する
古代詩「祖先劉子胥を悼む」時代: 唐代著者: 王偉悪い時期の後には良い時期が来るとよく聞きますが、残...
第15章:孫娘子が危機に瀕した英山を救い、神王が川辺で自らを犠牲にする
『海公小紅謠全伝』は、清代の李春芳が著した伝記である。『海公大紅謠全伝』の続編であり、海睿の晩年72...
古典文学の傑作『太平楽』:礼部第5巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
海公大紅誦全集 第27章:高潔な王妃が重慶で恩恵を受ける
『海公大紅袍全伝』は、清代の中国語で書かれた全60章からなる長編歴史ロマンス小説です。題名は「金一寨...
沈月『范安成に別れを告げる』:この詩は文体がシンプルで、精神が力強く、不自然なところがない。
沈月は音楽に精通し、周勇らとともに四声八失の理論を創始し、平、商、曲、汝の四声を相互に調整する方法を...
古宇の起源は何ですか?
古宇の起源は何ですか?穀雨節の起源について、『淮南子』によると、蒼頡の文字の創造は天地を揺るがす出来...
「奇源」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
漆庭王維(唐代)古代人は傲慢な役人ではなかったが、世俗的な事柄についての知識が欠けていた。たまに小役...
古代の人々はカボチャをどのように食べていたのでしょうか?なぜカボチャと呼ばれるのでしょうか?
カボチャの起源に非常に興味がある人のために、Interesting Historyの編集者が参考にな...
侯夫人の「春梅二首」はどのような感情を表現しているのでしょうか?
侯夫人の「春梅二首」にどんな感情が表現されているか知りたいですか?侯夫人は隋の煬帝の治世に宮廷女官を...
『紅楼夢』の趙叔母の正体は何ですか?彼女と丹春との関係は?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が趙叔母さんに...
曹魏は軍事力が強かったとはいえ、文化をどの程度重視していたのでしょうか?
三国時代の文化や文学といえば、そのほとんどは魏の時代から来ています。曹魏は軍事力が強かったが、文化も...
『清代名人逸話』文学芸術部門第1巻の登場人物は誰ですか?
◎李雪木『樫の葉』李雪木は本名を白といい、武公の出身である。 「関中の三里」とは、中南山に住んでいた...