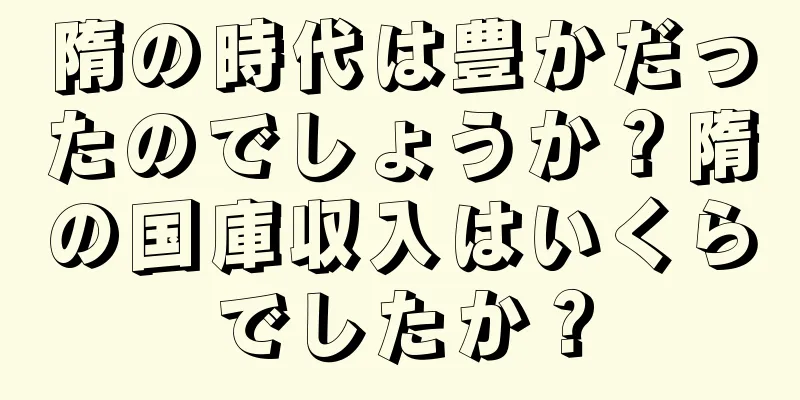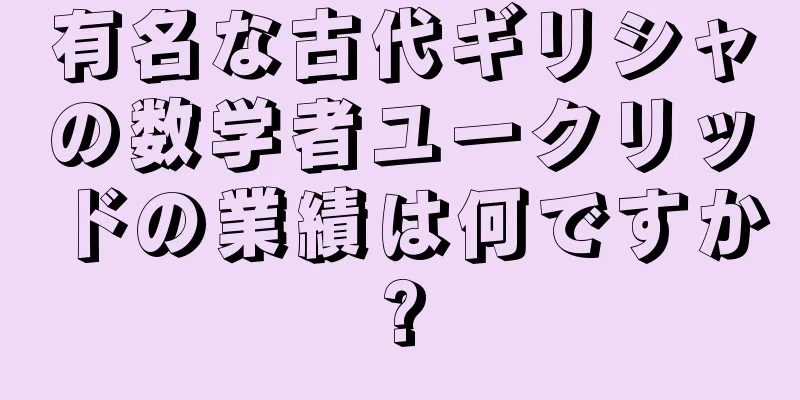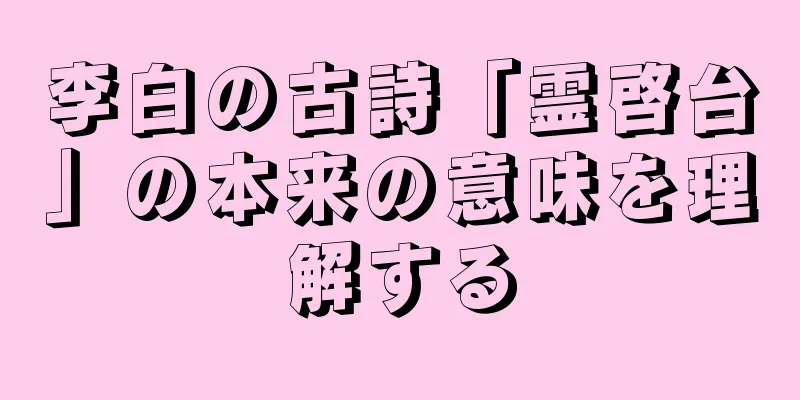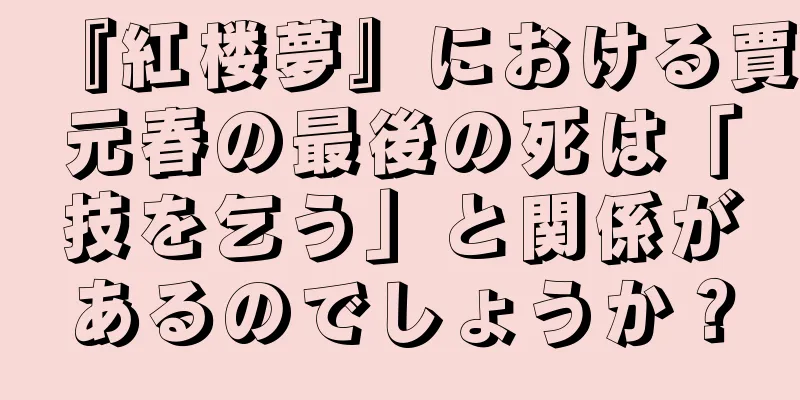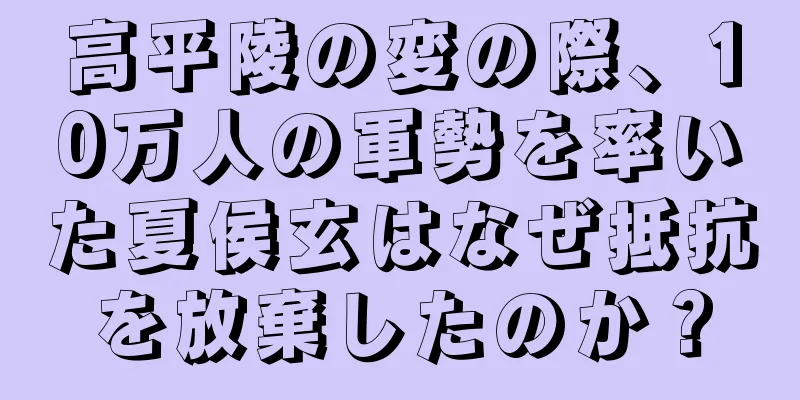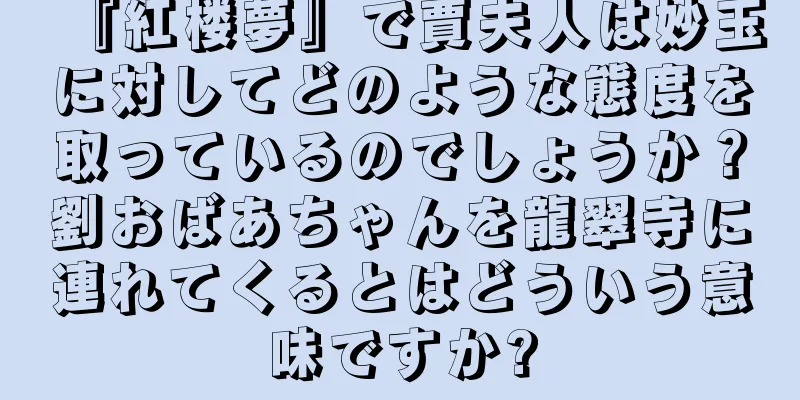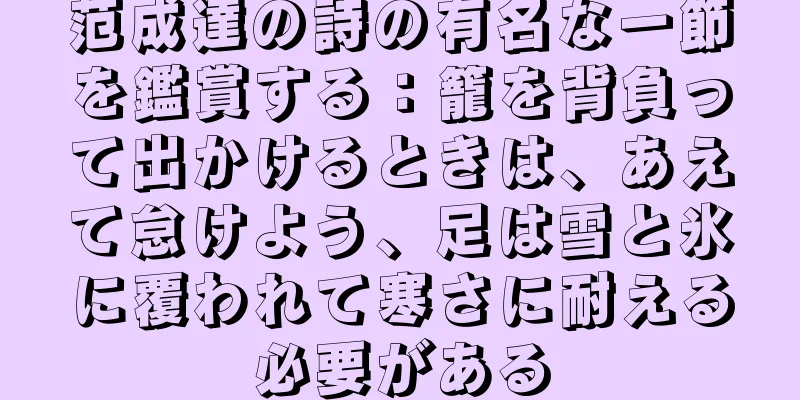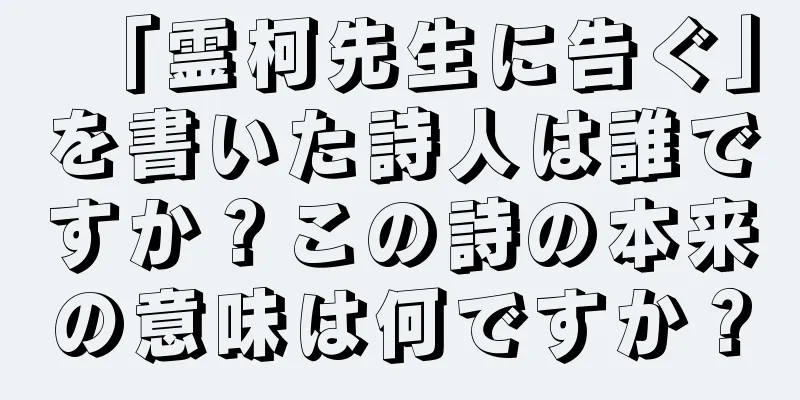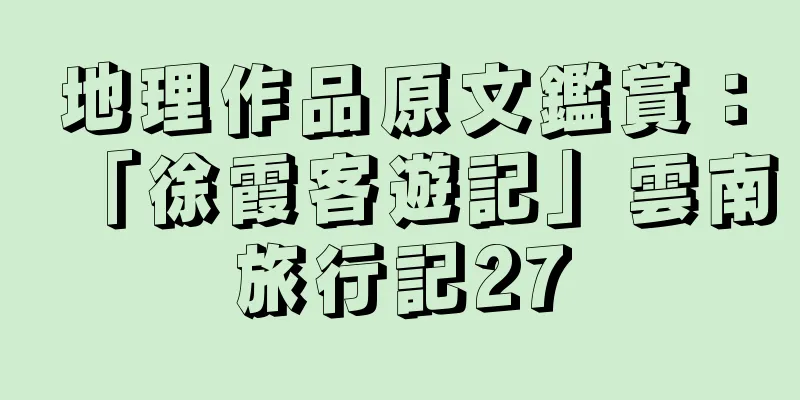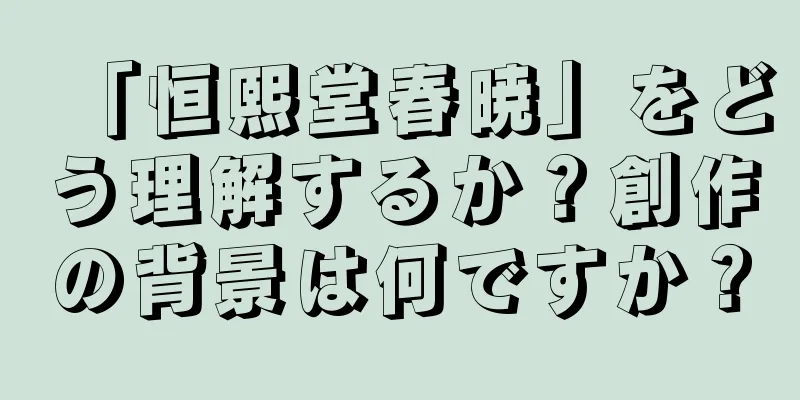明らかに:岳毅と有名な戦国武将田丹の最終的な結末は何でしたか?
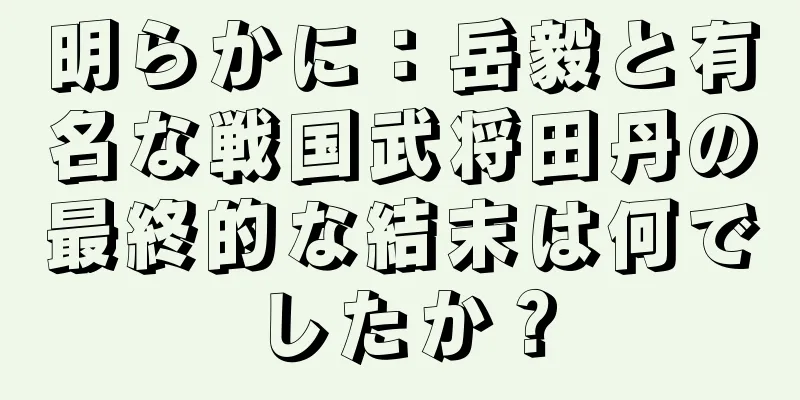
|
楽毅はもともと魏の出身で、誰もが転職を好んだ戦国時代に、燕昭王の高給政策に応じるため、諸国から来た朱馨、鄒延らとともにやって来た。燕の昭王は彼に重責を託し、第二の宰相に任命した。その後、岳邇は燕国の復讐を助けるために、各国と同盟を組み、属国連合軍を率いて斉国を攻撃しました。その結果、斉軍は次々と敗退し、岳邇率いる燕軍は止められず、斉の首都臨淄を占領しました。燕の昭王は彼を昌国の君主に任命し、斉の残りの都市を攻撃し続けるよう命じた。楽毅は斉の70以上の都市を一挙に占領し、占領されなかったのは莞と即墨の2都市のみであった。しかし、この二つの都市は斉国の最後の拠点として機能し、4年間征服されなかった。 そこで、ある者は燕昭王の前で楽毅を悪く言い、楽毅は今や反逆の心を持ち、莒と即墨を捕らえなかったのは斉の民の心を掴み、将来斉王となるためだと言った。燕昭王は歴史上比較的有名な君主であり、臣下全員を招いて盛大な宴会を開き、宴会で讒言した人物を殺害し、斉の最前線にいた楽毅に多くの贈り物を与えて、彼を斉王にしようとした。そこで楽毅は恐れて断りました。彼は深く感動し、燕国に忠誠を誓いました。危機は去りました。しかしすぐに燕の昭王は亡くなり、その息子の恵王が王位に就きました。恵王は皇太子の頃は岳嬪をあまり好きではなかったが、燕王になった今、斉の田丹の諜報活動に引っかかり、岳嬪が本当に斉王になりたがっていると考え、斉潔を岳嬪の代わりに任命し、岳嬪を帰国させた。楽毅は燕国に戻ると恵王に殺されるのではないかと恐れ、趙国に逃げた。趙国は楽毅を王竹鈞と名付け、楽毅は結局趙国で亡くなった。 田丹(ティアンダン)は、生没年不詳。姓は桂、氏名は田、名は丹。臨淄の出身で、戦国時代の田斉王家の遠縁。斉の首都臨淄で市場官(市場を担当する小官)を務めた。斉国が危機に瀕したとき、田丹は即墨を守り、火牛の陣形で燕軍を破り、70余りの城を奪還した。その功績により宰相に任命され、安平公の称号を与えられた。その後趙国に赴き将軍を務め、死後安平城に埋葬された。 田丹は斉の出身で、岳懿が軍を率いて斉を攻撃したときに名声を博した有名な将軍でした。燕軍が斉の安平県を攻撃したとき、彼は一族の者たちに車の車軸を鉄で巻かせ、城門からの脱出を成功させて名声を得た。即墨に逃れた後は将軍として擁立されたが、偶然にも燕恵王が即位したため、燕国を疎外する防諜策を講じたため、燕恵王は楽毅を疑うようになり、楽毅は趙国に逃れた。このとき、田丹の軍事的才能は十分に発揮され、最大限に発揮されました。彼はまず一連の手段を用いて斉軍を団結させて燕軍に抵抗し、次に火牛陣で燕軍を破り、岳毅に代わって燕の将軍となった斉傑を殺害し、斉に占領されていた70以上の城を一気に奪還した。最後に斉の閔王の息子である斉の襄王を臨淄に迎え入れた。田旦は斉国を再興し、斉の襄王は田旦を安平卿に任命した。 |
<<: 明らかに:戦国時代の田丹と秦の白起、どちらがより強いのか?
>>: 斉の襄王の息子である田堅は、宋国がいかにして滅亡したかを明かす。
推薦する
古代の皇居では何をすればいいのでしょうか?古代で最も人気のあるゲームのトップ10のランキング!
古代の宮殿では何をしていたのでしょうか?古代で最も人気のあるゲームトップ10!次の興味深い歴史編集者...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 白秋蓮』のあらすじは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「白秋蓮」の原文直隷に穆生という名の男がいた。あだ名は善公。...
『紅楼夢』で、黛玉は賈屋敷に入った後、なぜ宝玉と一緒に住んでいたのですか?誰が手配したんですか?
黛玉が賈府に入った話は、紅楼物語の正式な始まりとされています。Interesting History...
ヤン・ルイの「ボシュアンズ:ほこりに恋していない」:これは優しくも力強い告白だ
顔睿(やん るい、生没年不詳)、原姓は周、号は幽芳、漢民族、生没年不詳、南宋中期の女性詩人。彼女は貧...
皇帝物語:漢の恵帝・劉嬰とはどんな人物だったのか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
清家の愚かな叔父である王占の簡単な紹介は、西晋の王占がなぜ狂気と愚かさを装ったのかを明らかにする。
魏晋の時代には、優雅で名高い人物が多く、その中には奇人も少なくなかった。王占もその一人だった。彼は非...
古典文学の傑作『太平記毓覧』:布絹部第六巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
宋代の朝廷会議制度はどのようなものだったのでしょうか?裁判停止制度はいつから施行されるのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が宋代の朝廷会議制度がどのようなものであったかをお伝えします。皆さんのお役...
唐宋の八大師の中で、なぜ宋の人が唐の人より4人多いのでしょうか?
古代文学の頂点には唐詩と宋詩が並んで位置しています。また、唐宋代には優れた文章が多く生まれ、これらの...
「天剣龍剣」では、3人の少林寺僧侶が3人のペルシャの使節である馮雲月を倒すことができるのでしょうか?
金先生の小説はすべて関連していて、本に登場するほとんどすべての達人には、互いに比較できる議論があるこ...
「小桃花雑詩」を書いた詩人は誰ですか?この歌の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】杏の花が咲く時期は天気が晴れることがなく、観光客の熱意が台無しになってしまいました。赤...
東周紀伝第150章:毛角は秦王に忠告するために服を脱ぎ、李牧は桓騎から城を守る
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
張僧有の絵画はなぜ人気があるのでしょうか?張僧有はどの歴史的時代に生きたのですか?
こうした特殊な歴史的背景のもとで、張僧有の絵画があらゆる階層、あらゆる階級の人々から広く評価され、当...
『新世界物語』第89章には誰の言葉と行為が記録されていますか?
『十朔新于』は、魏晋の逸話小説の集大成です。では、『十朔新于・談話・第89号』には誰の言葉と行為が記...
有名な哲学書『荘子』外篇北遊記(5)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...