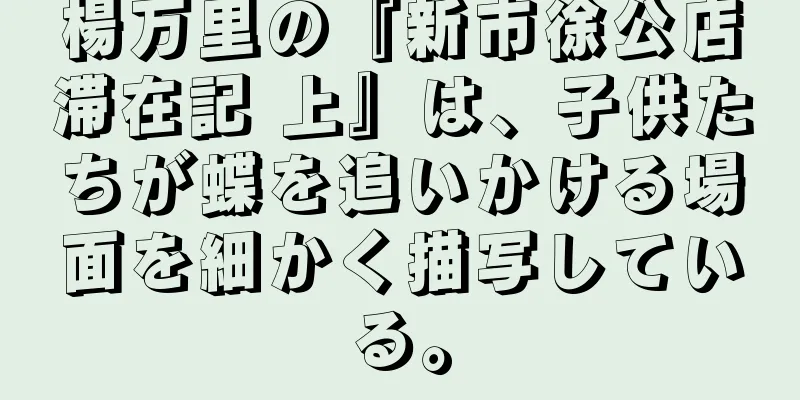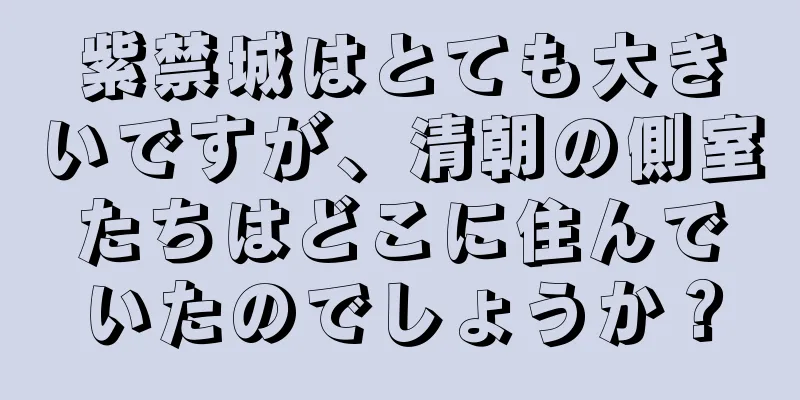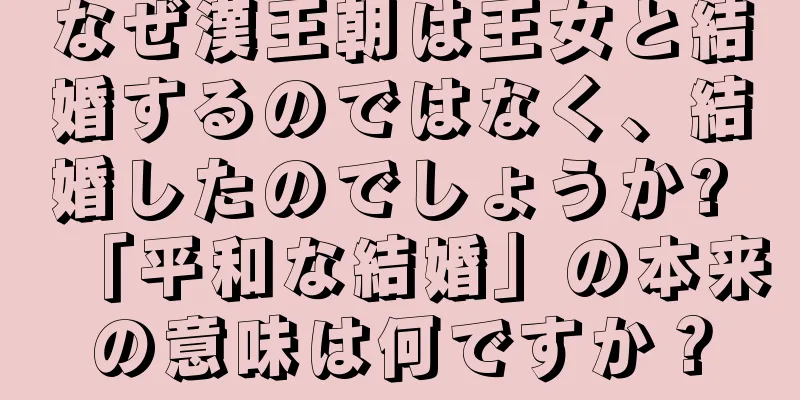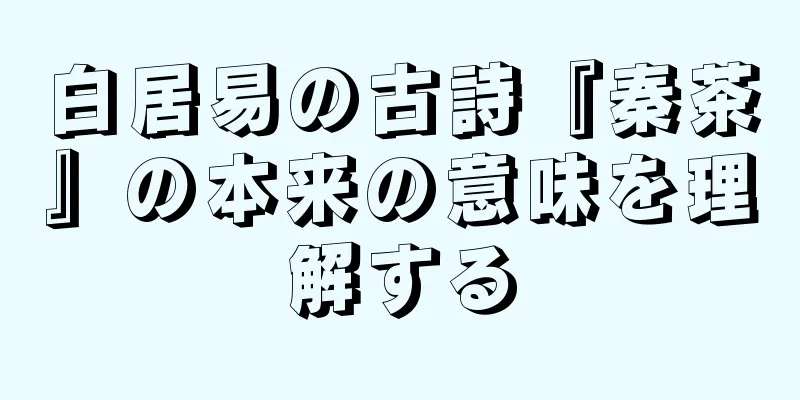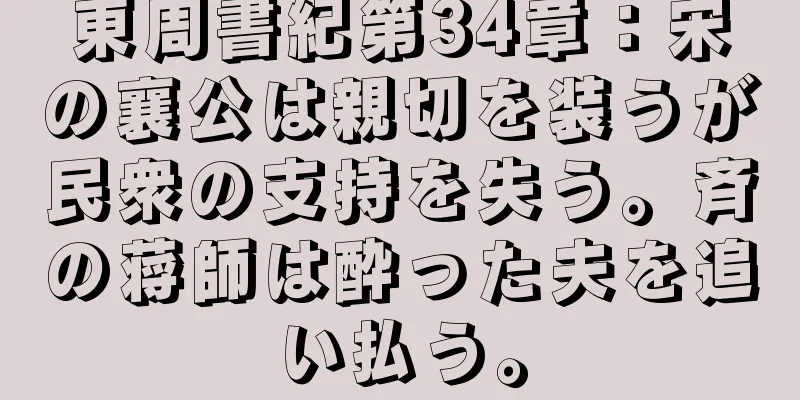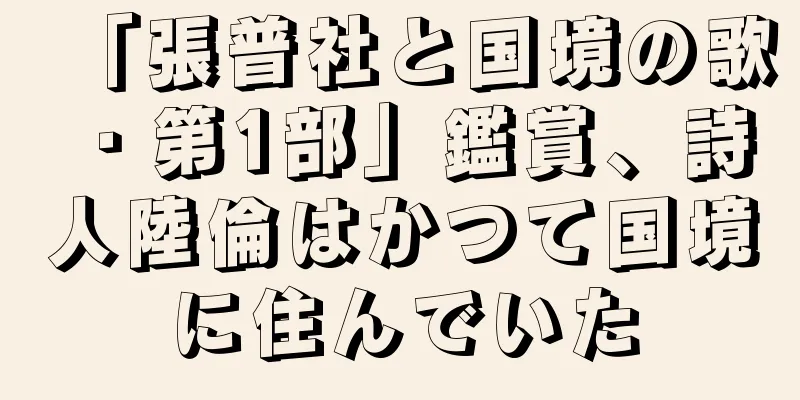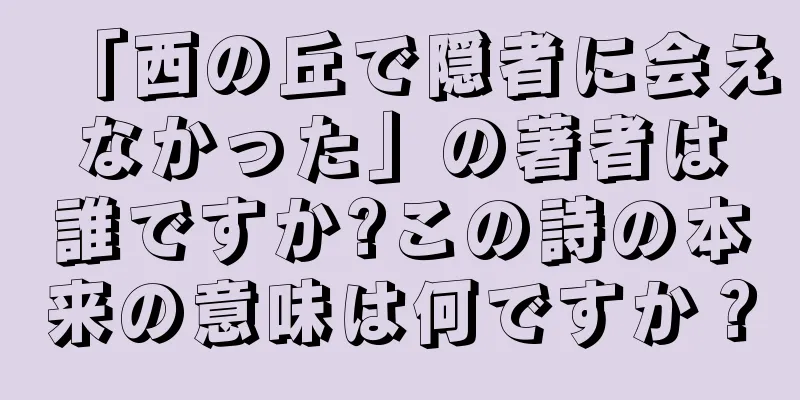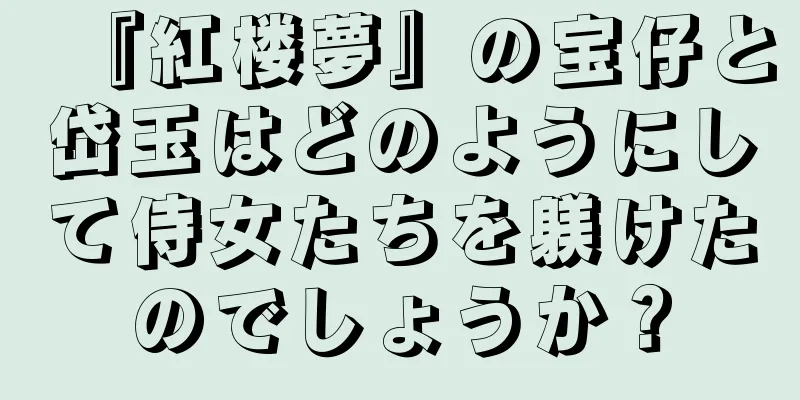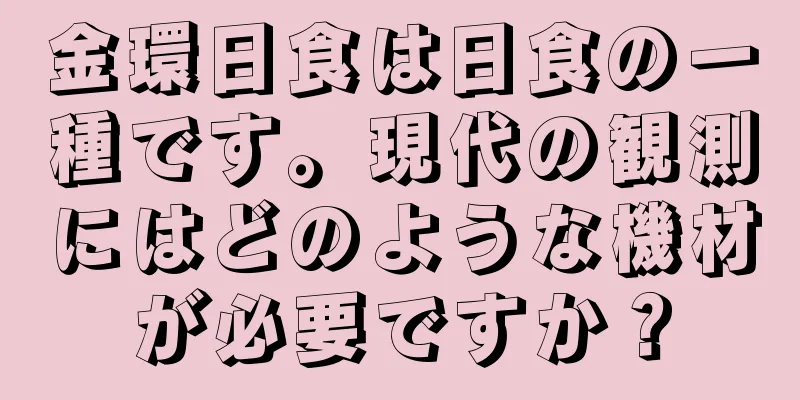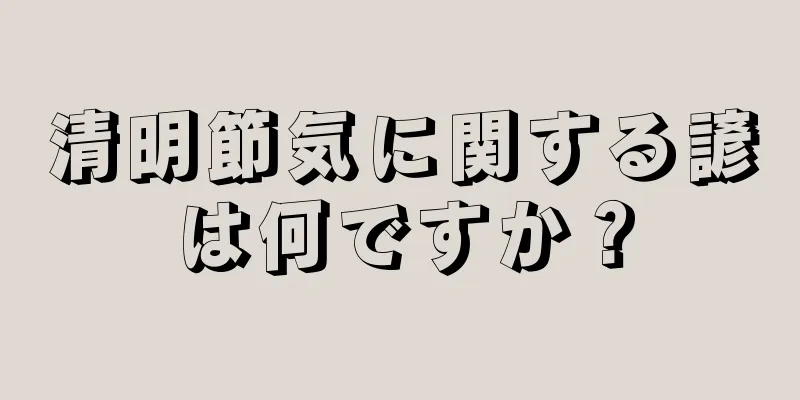明代の中国哲学者、王守仁の引用と学術書簡の簡単な紹介:「川西録」
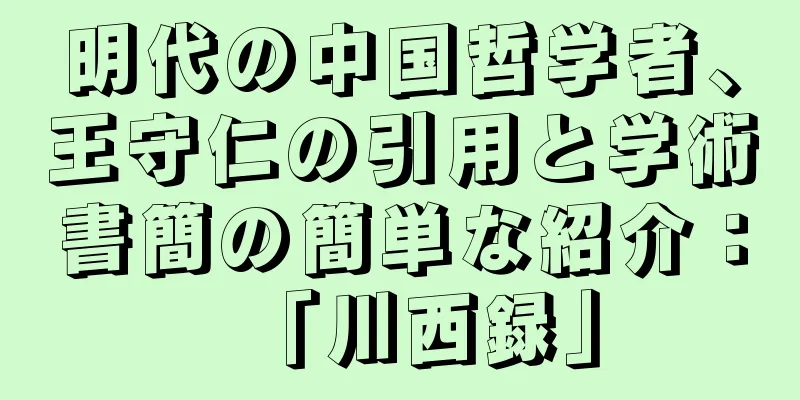
|
『実生指南』は、明代の中国哲学者であり、宋明代の中央儒学の代表者である王守人による引用と学術書簡を集めたものです。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 「川西」という言葉は、『論語』の「川不西湖」という一文に由来しています。 『実生訓』には王陽明の主要な哲学思想が収められており、王陽明の思想や心の哲学の発展を研究するための重要な資料となっています。 『実生訓』には王陽明の主要な哲学思想が収められており、王陽明の思想や心の哲学の発展を研究するための重要な資料となっています。第一巻は王陽明自身が校閲したもので、第二巻の書簡は王陽明自身が書いたもので、晩年の著作である。第三巻は王陽明自身の校閲ではないが、晩年の思想をより詳しく解説し、王陽明が提唱した「四つの文」を記録している。 「心は理なり」はもともと陸九源の命題であり、『実生訓』で詳しく述べられています。王陽明は朱熹の修身法を、心の外に理を求め、天の理や至善にかなう外的な事柄や対象を求めるものだと批判した。 王陽明は、「最高の善は心の本質である」と「心は理である。この心は利己的な欲望に邪魔されず、天の道理であり、外部から何かを加える必要はない」と信じていました。彼はこれを、社会の倫理規範の基礎が人間の心の最高の善にあることを強調するために述べました。 この原則に基づくと、彼の『大学』の解釈は朱子の解釈とは大きく異なります。 朱熹は、『大学』における「事物の探究と知識の拡張」は、学生が外部の対象を理解することを通じて、最終的に人間の心の「全体的な目的」を理解することを要求すると信じていました。 王陽明は、「格武」の「格」は「心の中の不義を除き、本質の義を保つ」という意味であると信じていました。 「意図の本質は知識であり、意図があるところに目的がある。」 「知識」とは人間の心に本来備わっているものであり、外部の物体を理解することによって得られるものではありません。この知識が「良心」です。彼の見解では、物事を調査し、その原理を探求するという朱熹の理論は、まさに心と理性を二つに分けることである。 このことから、王陽明の「心は原理である」という命題は、主に彼の修身理論に役立っていることがわかります。良心を追求する理論は、心は理性であるという陸九源の考えを発展させたものである。心は理性であるという王陽明の考えは、私たちの一般的な意味でも存在論的な意味を持っています。 しかし、存在論的な観点から研究することに重点を置くと、王陽明の修身理論におけるその根本的な意義を無視することになります。 知識と行為の問題は『実生訓』で論じられた重要な問題であり、朱子以来の宋明の朱子学におけるこの問題の議論に関する王陽明のさらなる研究も反映している。 彼はこう言いました。「心の外で真理を求めることが、知識と行為が二つの側面である理由です。自分の心の中で真理を求めることが、知識と行為の統一を説く賢者の教えです。」 「知識と行為の統一」とは、知識と行為が同じものの二つの側面であることを意味します。 王陽明の「心は理なり」「良心を養う」「知行合一」はいずれも、自己認識と道徳の優位性を強調している。 彼は言った。「知識は理性の精神的な部分です。その優勢性から見れば心と呼ばれ、その才能から見れば性と呼ばれます。」人間の心は行為の善悪を知ることができ、意識的に善を行うことができます。これは本心の「明確な認識」であり、程浩の思想の発展です。 『実践生活指南』では、人間の心の「空虚で霊的で澄んだ意識」について多くの議論がなされています。王陽明の「心外に理なし」などの理論を十分かつ正しく理解したいのであれば、彼の議論を深く研究することが非常に重要です。 人間の心の本質は理性であり、人々はこの道徳意識を意識的に実現することができるので、外部の対象物を通じて心の理性を理解する必要はありません。外部の対象物の理性は、人間の心の現れに過ぎません。真理を学ぶ目的は、外的な事柄を理解することではなく、自分の心から利己的な欲望の覆いを取り除くことです。人間の心の明確な認識については、程浩と朱熹の両者が論じました。 『実生訓』を読むときは、王陽明と彼らとのつながりと違いを理解する必要があります。 王陽明の上記の思想は、人間の本性の善良さについての存在論的な説明を提供し、歴史的な意義を持っていることを認めるべきである。しかし、彼の理論は人間の悪の原因について十分な研究を行っていないことも認識する必要があります。彼の教義は明代の下層階級に影響を与えたが、広く受け入れられたとは言えない。 王陽明はまた、「頭のよい人」と「頭の悪い人」は異なる扱いを受けるべきだと気づいていたが、彼の考えは頭のよい人にのみ当てはまる。これが、後世の人々が彼を「禅に近い」と批判した理由である。これも彼が朱熹に劣る点である。王陽明のこの欠点は現代の学者の注目を集め始めているが、梁淑明を除く現代の新儒学の巨匠たちの間では、これに十分な注意を払っていなかった。 『実生訓』は、王陽明の学問に関する質疑応答や手紙を集めたものです。儒教の簡潔かつ代表的な哲学書です。この本は、王陽明の思想を詳しく説明しているだけでなく、彼の弁証法的な教授法や、生き生きとして比喩的で、しばしば機知に富んだ言語芸術も反映しています。 『実生訓録』には王学派の重要な思想がすべて含まれています。 第一巻は、知行合一の観点、心は理であり、心以外に理はなく、心以外に対象はなく、志は対象であり、対象の探究は誠意の努力であると説いている。聖人の学問は心身の学問であり、肝心なのは理解と実践であり、単なる知識として扱われ、口先だけで語られるべきではないと強調している。 真ん中の巻には8通の手紙が入っています。彼は、認識と行為の統一と事物探究の理論に関する質問に答えるだけでなく、王一派の思想の根本的な内容、意義、善意についても論じました。また、「良心に達する」という一般的な考え方を説明すると同時に、王一派の思想の目的についても明快に説明しました。さらに、存在論に対する疑問に答え、各人の具体的な状況に基づいて実践の要点を指摘しました。陽明の教育思想を詳述した短いエッセイも2編収録されています。 第二巻の主な内容は良心を養うことである。陽明は、その熟達した修身の技巧を結合して、存在と技巧の統一、街中に聖人がいるという見解を提唱した。特に目を引くのは、王学体系を完成する「四文教」である。 |
<<: 明代の劇作家、唐仙祖:臨川四夢の一つ、邯鄲の物語の簡単な紹介
>>: 杜牧の書道作品「張昊浩の詩」をどのように評価しますか?
推薦する
黄庭堅の『胡一老の宣安訪問の碑文』:作者は高貴な気持ちを表現した
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
周王朝は何年間続きましたか?周王朝皇帝の一覧と簡単な紹介
周王朝は何年間続きましたか?周王朝は中国の歴史において商王朝の後に続いた王朝です。西周王朝(紀元前1...
五王国の王になるというのはどういう意味ですか?
五国相承とは、中国の戦国時代中期に、5つの主要な属国が互いの君主制を承認した事件であり、周の皇帝の権...
『詩経』の逸話:冒頭の章は実は周の文王の恋愛物語?
周の文王に対する人々の認識は、主に広く流布している『風神演義』を通してである。『風神』は古代のSFや...
儒教の古典『春秋古梁伝』の成功5年の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
パンケーキの発明のあまり知られていない歴史:諸葛亮が調理中の煙を避けるために発明した
諸葛亮の故郷への貢献諸葛亮は臨沂で生まれ、故郷に貢献しなかったと考える人たちもおり、彼らは諸葛亮を揶...
東漢の名将である傅俊と雲台二十八将軍の一人である傅俊の生涯について簡単に紹介します。
傅俊(?-31)、号は紫微、潘川県襄城の人。もともと襄城の村長であったが、劉秀が反乱を起こした後、劉...
王昭君が前漢の結婚相手として選ばれたのはなぜですか?外国の王子同士の結婚の中で、王昭君が最も有名なのはなぜでしょうか?
本日、『Interesting History』の編集者は、西漢に嫁いだ数多くの王女の中でも何世紀に...
なぜ夏金貴が薛家を衰退させる上で重要な役割を果たしたと言われているのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
火の神である朱容に関する5つの伝説
神話に登場する古代皇帝である朱容は、赤帝として知られ、火によって姿を変え、後世からは火の神として崇め...
周王朝の結婚制度はどのようなものだったのでしょうか?周王朝の結婚制度の紹介
周知のように、周王朝の結婚式は中国の結婚式の原型であり、その後の漢代の結婚式は周王朝の結婚式に基づい...
頤和園の40景の一つである万芳安和の特徴は何ですか?
周知のように、頤和園は長江南岸のいくつかの有名な庭園や名勝地を集約しただけでなく、西洋式庭園建築も取...
『紅楼夢』で、王希峰はなぜ幽二潔を死に追いやるほど残酷だったのでしょうか?
王希峰は『紅楼夢』の登場人物。賈廉の妻、王夫人の姪であり、金陵十二美女の一人。次回はInterest...
宋代の詩「内心に送る」を鑑賞して、孔平忠は詩の中でどのような感情を表現したのでしょうか?
宋代の孔平忠の手紙では、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう!道中の...
『紅楼夢』では、賈家の使用人たちは非常に快適な生活を送っていました。彼らは解雇されることを恐れていなかったのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...