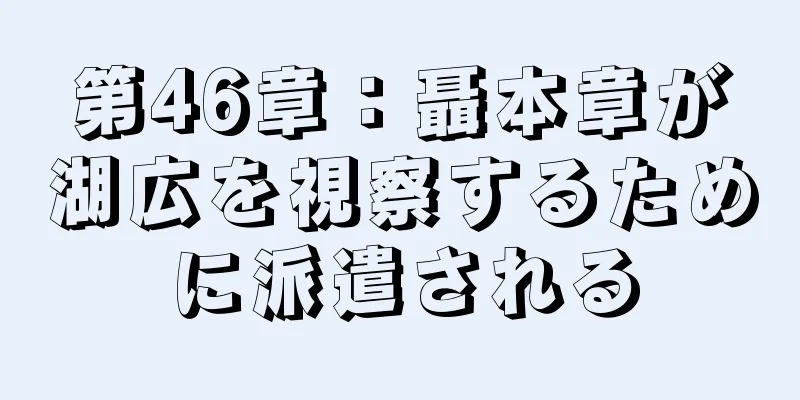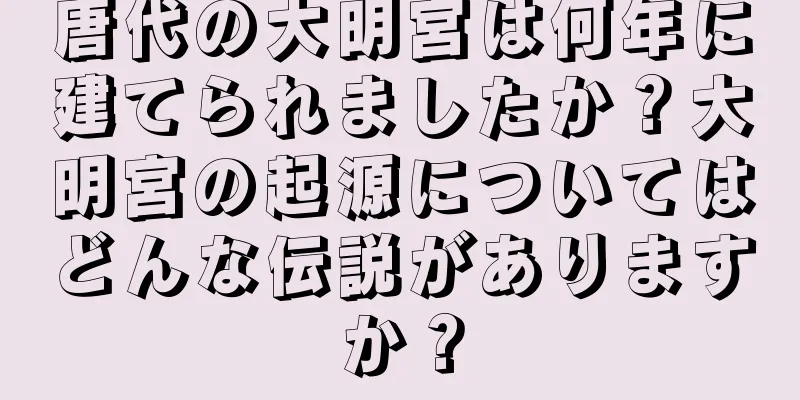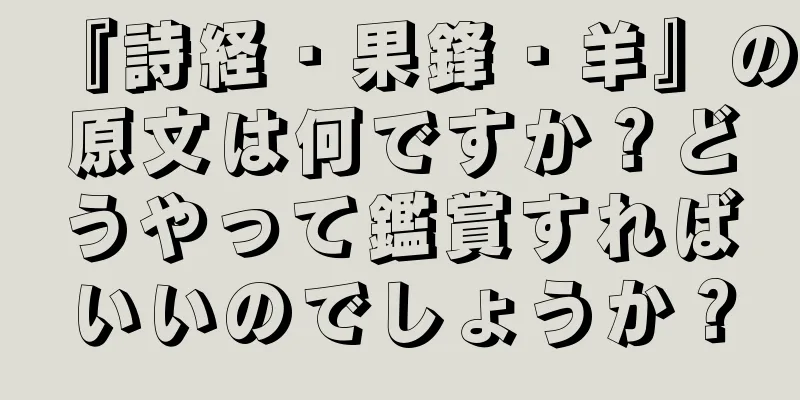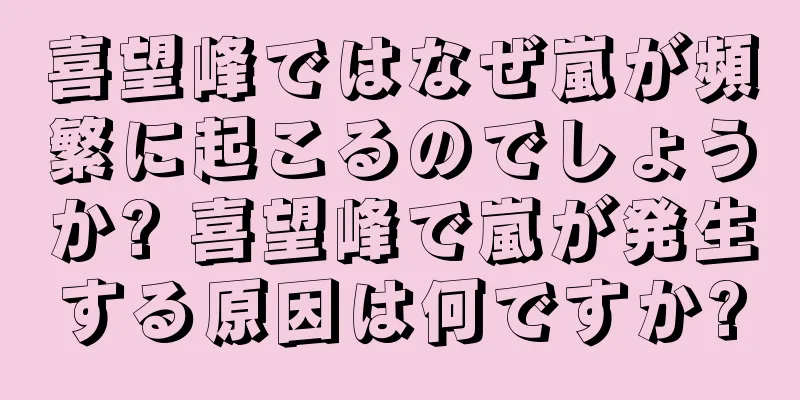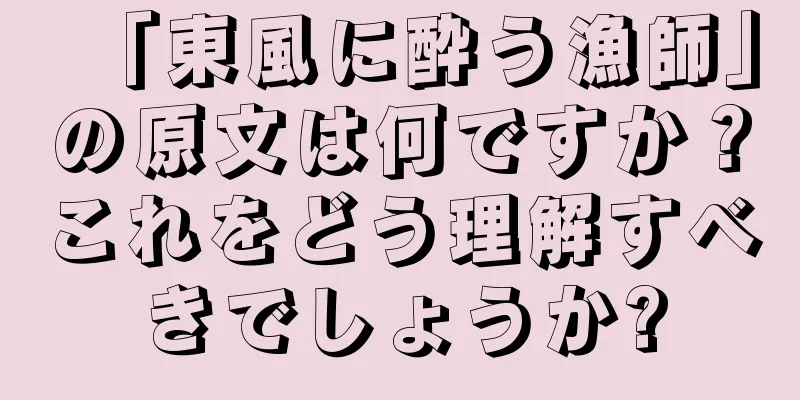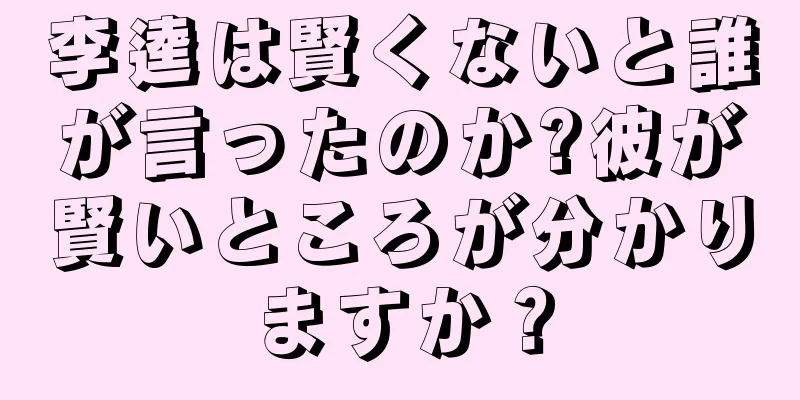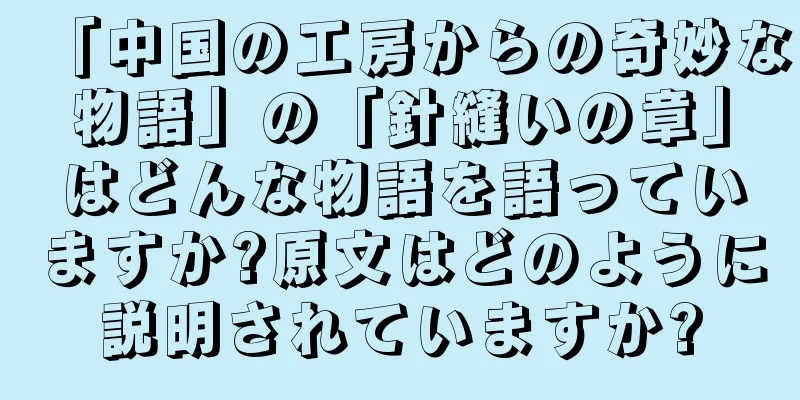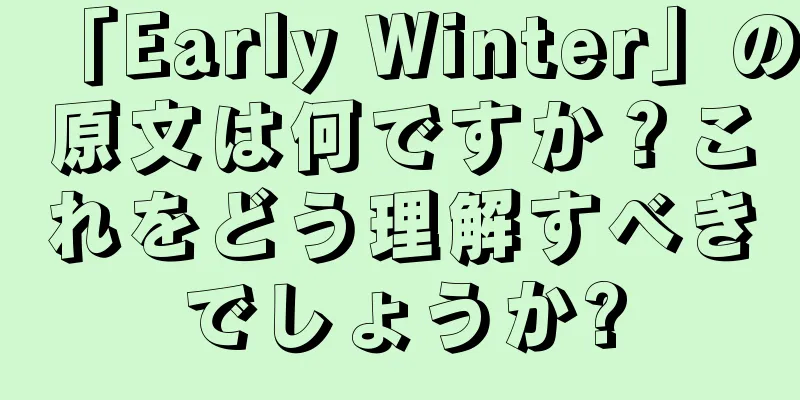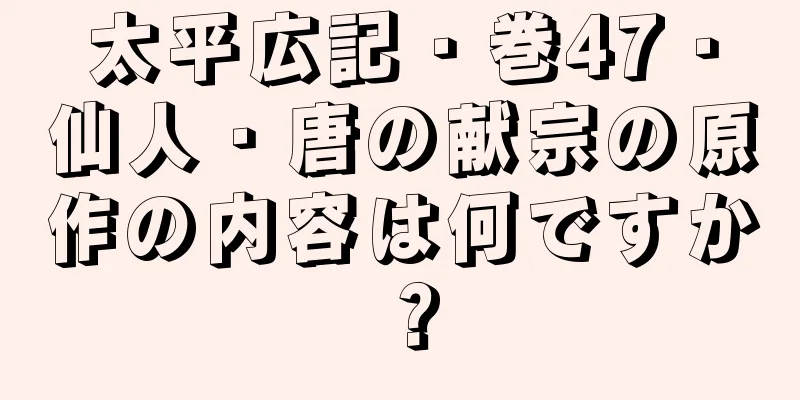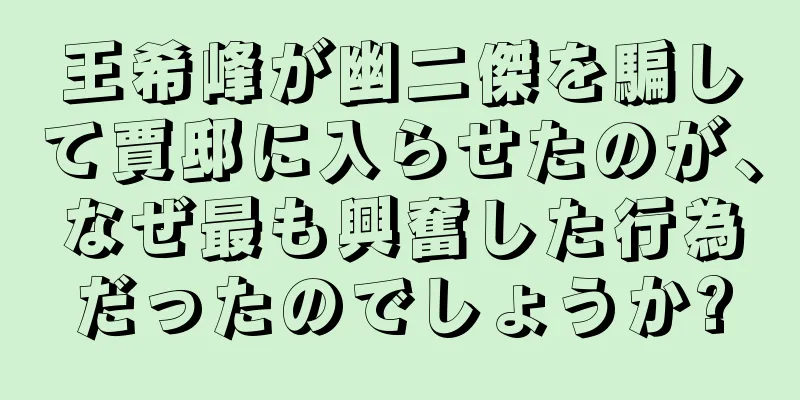『徐霞客旅行記 江油遊記十三篇』の原作の内容は何ですか?
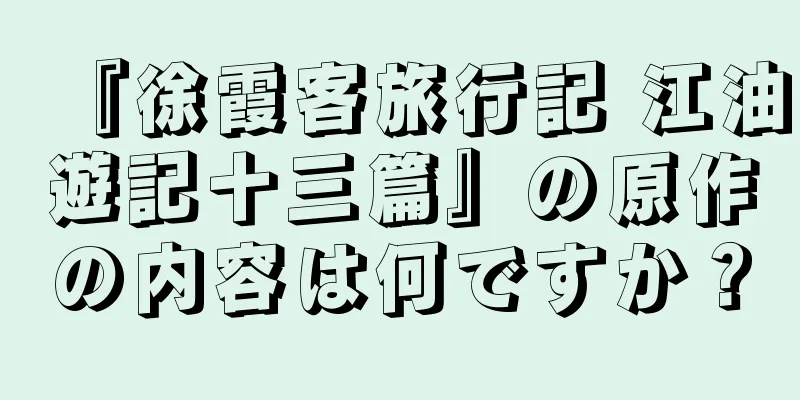
|
定州旧暦1637年1月1日、私は例外的に晴れた日に目覚めました。場所を尋ねると、鶴山から西に20マイルの廬江、北に120マイルの武公だと言いました。そこで彼は、景文と3人の部下に荷物を持って廬江に行くように命じ、私と顧普は布団を担いでまっすぐ北の山中へ向かいました。山はそれほど高くないですが、土はとても赤いです。 5マイル登り、小さな小川を渡り、さらに5マイル登ると山の上のLiujiaに到着します。北の后堂寺に到着し、小さな尾根を越えると、平らな畑と広大な水田が見え始めます。それから私たちは小川に沿って北東に5マイル進み、北西に向きを変えて小川を遡り山へ向かいました。この渓流は鶴山の北東から流れてくる水で、流れがとても強い。私が雍城から西へ向かったとき、この渓流に南から流れ込む大きな水は見なかった。山の上の六家の東から雍城の下流に流れ込む水のはずだ。青塘嶺を北上し西に下っていくと、もう一つの平坦な谷、十二塘が見つかりました。渓流に沿って西へ遡ると龍門坑に入ります。渓流の水は二つの山峡の間の岩壁を突き破り、三つまたは四つの池に流れ落ちます。一番下の池はインクのように濃い青色で、その上の二つの崖の岩は互いに向かって突き出ていました。この地域に入ると平らな場所があり、そこが鶴山寺です。寺院の南側は鶴山五老峰に面しており、寺院は鶴山の北側の支流から聳え立つ山に寄りかかっている。寺院の背後の山には二重の岩が高くそびえている。蓋和山は寺院の西側にある主山であり、南からそびえる五老山の峰が最も高くそびえています。全体像を写真に撮ってみると、「後ろには2人の子供が寄りかかっており、前には5人の老人がお辞儀をしている」と書いてあります。2つの山は、何山と5人の老人を指します。趙澳には、あまり深くないと言われている羅漢洞があります。寺の僧侶である楽安が、集めた線香を寄進し、羅漢と五長老が訪れるためにそこに残しました。私は武術で成功することを切望しており、明日はそれができないかもしれないと心配しています。そのため、あなたには帰り道に残って探索してほしいと頼みます。それから私は楽安を離れ、北の十寮に向かいます。尾根の長さは 10 マイルです。尾根を登ると、寺院の後ろの山の頂上を西に見ることができます。まるで互いにささやきあっているかのように、並んで立っている 2 組の山頂が見えます。尾根を北上すると、山は再び谷となり、東の峡谷から水が流れ出る。谷間には家屋が多く建ち並び、鉄の道と呼ばれている。その後、北の尾根を越えて5マイルほど下ると、雁塘という別の平野に着きます。そこの水は尾根の西側から鉄井に沿って南に流れています。雁塘から北に5マイル進むと、双頂としても知られる済公堡に到着します。尾根は非常に高く、尾根の南の水は鉄井から東に流れ、尾根の北の水は陳山と北渓から南翔に流れ出ています。鶏公の北は安府の境界です。山を5マイルほど下って陳山に到着しました。すでに暗くなっていたので、李さんと全さんが泊まる場所を見つけました。その老人は70歳で、深い山中に住むまさに隠者です。 2日目の朝食後、北へ向かいます。南から来た水は東の坡山に流れ、北から来た水もここで東に流れ、道は北へ遡ります。陳山は東西に高い山々が連なり、南北は海に面して谷を形成している。四方の山々は空洞で、谷のようである。上部は日差しを遮り、下部は険しく険しい。人間の世界には全く似ていない。 5マイル、山頂まで曲がりくねった道。東に曲がると、廟山澳(長衝嶺とも呼ばれる)という山の北側の尾根に沿って進みます。その西側には喬家山という峰があり、岩がゴツゴツと高くそびえ、頂上はまるで衝立のよう、あるいは人が立っているようで、すべての山の中で一番素晴らしく、最も美しい山です。北に3マイルほど行くと、川の左側に突き出た石の崖があります。その上には、翼が前後に飛ぶように水平と垂直に横たわる純粋な石があります。水は、頂上の基部から数十フィートにわたって流れ落ちています。しかし道は右に進み、崖の側面は密生した草に覆われて下を見ることはできず、聞こえるのは空気を打ち鳴らし谷を揺らす音だけである。ここまで下りると、山峡の田んぼや谷が見え、さらに2マイル進むと、3、4軒の家が見えます。これが魯子龍河です。南西の山峡から流れてくる小川が、南から長冲河と合流し、北へ流れていきます。川の北側には、峠のように丘が流れを遮っています。川は西に向きを変え、丘を北に回り、その後北西へ流れます。道は小川から始まり、北の丘を通過します。さらに 5 マイル進むと平州に着きます。ここで山は南北の 2 つの境界に広がり、太上塘前と呼ばれます。魯子龍河は西から東に向きを変えて大きな川となり、東の楊西から流れてくる平田河と合流します。 〕そこで彼らは川を渡り、北に向かい、3マイル後に妙山に着いた。そして再び山峡に入り、3マイル後に二坡尾根の麓に着いた。そこで彼らは、荷物を肩に担いでいる男を見つけた。 5マイルほど進み、北の尾根を下っていくと、平らな野原とシバドゥと呼ばれる谷に着きます。さらに3マイル離れたところに、西から東へ流れる大きな川があります。その水源は千山洞の北にあり、ここを流れています。その川には平田橋が架かっています。 】平田橋を渡り、北へ向宮嶺へ向かいます。ここからまっすぐ登って翠尾や雲崖を眺めることができます。 5 マイルほど進むと、東から来る道があります。その道はさらに 10 マイルまっすぐに上り、尾根の頂上まで曲がりくねって続きます。太陽は鍋のように焼けつくように熱く、喉が渇いていますが、水は見つかりません。しばらくして、彼は道の下からゴボゴボという音を聞きました。彼は茂みの中に泉を見つけ、そこから水を飲みました。谷間の集落は孟家坊、第19都と呼ばれていました。広場の西側には、湘宮嶺の人々が登りたいと願う非常に険しい山頂があり、北東は湘鹿峰に面しており、武公の南端にあたります。 〕まだ午後だったし、この先の道も悪そうだと思ったので、体力を温存して一泊することにしました。店主の姓は王で、母親は90歳です。 3日目、朝食後出発。次第に雲が集まり、4つの山には雲がありませんでした。 3マイルほど歩いた後、西に曲がり、山に沿って北へ進むと、東の湘鹿峰の麓から流れ出る大きな川が見えます。これが湘杵湾です。さらに1マイルほど丘を下って歩くと、3、4軒の家がありました。山をさらに1マイル登り、2つの尾根を越えると、鶴家坊に到着します。西霧から下る道があり、それは千山への道です。水は西から東に流れ、湘鹿峰の大河となります。北澳から上る道があり、それは九龍への道です。主な道は東の大河を上って嘉中を通ることです。 2マイル先で小川を渡り、南の崖に沿って歩きます。さらに1マイル進むと、小川の北側に茅葺き屋根の小屋が見えます。これが三仙宮です。ここから、私たちは崇岡山を3マイルほどゆっくりと登り、湘鹿峰に到着しました。 【崖の谷間には小さな川が流れていて、北に向かって大きな川に流れ込んでいます。見上げると、山頂の雲がだんだん明るくなってきました。急いで登ると、突然小雨が降ってきました。 〕2マイルほど歩いて、私たちは済雲岩に到着しました。霧雨が降って服が濡れたので、済雲寺に入って少し休憩しました。この寺院は葛仙翁が住んでいた場所です。道士たちは、柱が1本しかなくまだ完成していない本堂で新年を祝うために集まりました。遺跡は香炉の向かい側に高くそびえ、北は武公に面し、その前には東武から流れ出て西に向吉湾を流れる大河があり、神秘的な城郭でもある。雨はしばらく止み、山頂に行けそうな小川を見つけたので、西の九龍まで行き、雨の中半マイル歩き、老水橋を渡り、五公の南麓に沿って歩き、ついに牛新嶺に到着しました。 5マイルほど離れた、奇岩を過ぎた尾根の上にお寺があります。雨が強くなるにつれ、道六さんはもらったお金を返し、バッグを置き去りにした。碁盤の上の道は北に5マイルまっすぐに伸び、石柱風洞を通り、さらに5マイル進むと山頂に着きます。これが登山の主要道路で、小さな山道が深い峡谷に沿って東に伸びており、これが観音崖への道です。私は両方を体験したかったので、山頂の九龍への小道を通りましたが、道士は済雲まで下りて鶴家坊の幹線道路を通りたいと言っていたので、私たちは出発しました。それから私は雨の中、小道を東に向かって歩きました。ここから先は、山の枝が山頂から谷へと下っていきます。突き出ているのが丘、凹んでいるのが峡谷です。道はそれらの腰に沿って進み、丘に出会うと登り、峡谷に出会うと下ります。チェス盤から二番目の峡谷を抜けると、頂上の側面に高さ10フィートを超える石が立っており、とても優雅に見えます。渓谷には突き出た崖と密集した木々があり、とても不思議な光景ですが、曲がりくねった道は密集した草に遮られ、足を踏み入れる場所がありません。次に、三峡を東に進み、丘のふもとの渓谷を渡り、南に向かい、香炉の東側まで直進します。その後、川の水は東と西に分かれ、西は済雲から平田に流れ、東は観音断崖から江口に流れました。どちらも安府の北東部にある川です。それで私たちはさらに二つの峡谷を越えました。北を見ると、峡谷は鬱蒼とした木々と険しい崖で覆われています。時折、崖の上に滝のような白い雲が見えます。しかし、不思議なことに雲は動いていません。よく見ると、すべて凍りついています。そのとき、この場所は標高が高くて寒い、この国の低地とは違うのだと気づきました。私は小刻みに歩きましたが、雨の中では何も気づきませんでした。第三稜線の真ん中にある観音崖までは合計5マイルです。観音崖は百法寺としても知られ、白雲禅師によって建てられ、その後弟子たちによって拡張され、隠されました。牛山堂は武公の東南隅に位置し、人里離れた場所にあります。もともとは山牛などの野獣の巣窟であったため、牛山堂と名付けられました。丁白雲が白いオウムのような禅宗の小屋を建てたため、百法仏殿と名付けられました。目の前には広い池がありますが、これも高い山々に囲まれていて、なかなか辿り着くことができません。その前には基山と呼ばれる尖った峰があり、香炉の東側にも尖った峰があります。この場所には寺院はありますが、崖はありません。崖は目の前の山の峡谷にある岩で、決まった名前はありません。お寺の前後には竹林が生い茂り、正面には河口までまっすぐ下る道、背後には山頂へ続く東の道があります。その時は服も靴もびしょ濡れだったので、急いで着替えて、続けるつもりはありませんでした。昼食後、突然雨が止んだので、私たちは別れを告げて寺院の東側に隠れました。 2マイルほど登ったところで、突然、南西から厚い雲が私に向かって流れてくるのが見えました。湘魯と鶏山は突然見えなくなり、だんだん暗くなってきました。私は振り返って、全力を尽くして登ろうとしました。さらに 1 マイル進むと、寺院の後ろの山の頂上に到着しました。そこは濃い霧で覆われていました。下を見ると、白い雲と尾根の丘や峡谷が見えましたが、私たちには何も影響はありませんでした。幸いにも、霧は雨を止めました。さらに2マイル進むと、山頂の茅葺き小屋に到着しました。小屋には荷物を抱えた道教の信者が2人いました。すぐ上には三石巻殿があるが、近くからは見えない。道士は彼を中に入れ、お辞儀をしてから、茅葺き小屋に戻りました。その夜は風が激しく吹き、北西に変わったと思ったが、幸い風は止んだ。しかし朝になってもまだ風は強かった。 【武公山脈は東から西にスクリーンのように広がっています。南には翔魯峰があり、翔魯の西には孟家峰があり、東には冀峰があります。 3つの山頂はすべて急峻です。香炉は高く吊り下げられており、格子戸のように武宮の南側に開いています。頂上には四方に通じる道がある。南からは、鳳東石柱から奇盤と済雲に下り、向公嶺を通り平田十八鎮を抜ける。これが山に入るための幹線道路である。南東からは、観音断崖から江口に下り、安府に至る。北東からは、雷大石から2マイル、さらに1マイルが萍郷の境界で、山口から萍郷に至る。北西からは、九龍から幽県に至る。南西からは、九龍から千山に下り、茶陵州に至る。これが四つの境界である。 〕 4日目、まだ霧が晴れていないと聞き、長い間じっと横たわっていました。朝食後、霧が突然現れて消えた。私は風穴の石柱を見つけられることを期待しながら、正しい道を下って行きました。 3マイルほどまっすぐ下っていくと、両側に茅葺きの山々の稜線が徐々に見えてきますが、絶壁や峰の奇観はありません。遠くに翔魯峰の頂上が時々見え隠れしますが、山の中腹には相変わらず濃い霧が漂っています。鳳洞の石柱はまだ二、三マイル下にあり、見つけるのが難しいのではないかと心配しました。また、道士が飾っただけなので、たとえ見つけたとしても、特に意味はないだろうとも思いました。そこで、山頂に戻り、茅葺き小屋でもう一度食事をしました。それから私たちは山の尾根に沿って西へ歩きました。最初は雨がちらほら降っていましたが、次第に晴れてきました。 3マイルほど下って尾根を越えると、突然霧の中から中央峰の北側に、上は空を、下は地面を貫く断崖が見える。それがいわゆる千フィート断崖である。何百もの崖が曲がりくねって立ち並び、高さも地形もさまざまです。門、宮殿、幕、塔のように北に傾斜し、渓谷の底までまっすぐ落ち込んでいます。地面には木々が密生し、苔が生い茂っています。しかし、霧はまだ時々辺りを覆っていました。人がその側に来ると、霧は突然晴れ、最初は檻のようだったので、袖で服を隠さなければなりませんでした。その後霧が晴れると、巧みに笑顔で歓迎するふりをしました。蓋武宮坪は東峰、西峰、中央峰の3つの峰から構成されています。最も高い中央峰は純粋な石でできています。南側は依然として険しく、北側は非常に険しく、断崖絶壁になっています。この道を通らずに右の道を通れば、この道を通っても霧は晴れない。武功に特別な勝利はないと言える。全長3マイル、中尾根の西を通り、2つの尾根を越える。狭い道はわずか5フィートです。ここの海の北側は断崖絶壁で、特に北側は険しく底なし、奇妙な突起が多く、尾根の二重の断崖は扉のように裂け、下側は深い峡谷に通じています。 〕この通路からは北側の崖にある景勝地をすべて訪れることができるのですが、残念ながら山が高すぎて道が塞がれているため、誰もそこへは行けません。それから西へ行き、下り、そして再び登ります。そこがウェストピークです。この山は、中峰のようなごつごつした岩がないことを除けば、東峰と何ら変わりありません。さらに5マイル進むと、Yezhuwaを通過します。西峰の端には4、5人が入れるほどの突き出た崖があり、二仙洞と呼ばれています。頂上に金鶏洞があると聞いたのですが、誰も行ったことがありません。 [すると山は二つに分かれ、その間に道が通った。 〕さらに西に4マイル行くと九龍寺に着きます。寺は武公の西側に位置し、この地点では高い山々が突然谷に開け、中央に平らな峡谷があります。水は峡谷橋から西に流れ、崖を下ります。寺の時代に寧周禅師によって開かれました。白雲禅師が開いた観音崖とともに、東西両側に寺が建てられました。しかし、観音断崖は開けていて見晴らしが良いのに対し、九龍断崖は人里離れた神秘的な場所に開けており、九龍断崖ほど秘密めいた状況ではないことは確かです。地形から判断すると、九龍峰は頂上よりわずかに低いものの、その高さは観音断崖よりはるかに高い。寺の僧侶たちは東と西の二つの宿舎に分かれており、昔は南昌王がここの山に来たこともあり、今も寺は良好な状態を保っています。西寮の僧侶が一晩泊まっていました。霧が徐々に晴れてきたので、私は彼を強制的に立ち去らせました。寺院を出て、西口橋を渡ると、小川は南に流れます。それから私たちは西の尾根を越えて、小さな小川を渡りました。二つの小川は合流して南の谷に流れ落ちました。 〕川は東に流れ、道は西に流れ、両方とも南にまっすぐに落ちています。 5マイル離れたところに紫の竹林があります。僧侶の宿舎は危険な急流のそばの竹林の中に建てられています。静かで爽やかで、絶妙な青の素晴らしい場所でもあります。山から眺めると、まだ濃い霧に包まれていますが、下るにつれて次第に晴れ、水は断崖の間を流れ、激しい峡谷と断崖のような勢いをしています。ルタイまであと10マイル。ルートによって、川の右側から行く人もいれば、左側から行く人もいたが、全員が雷鳴と降りしきる雪に囲まれていた。しかし、崖は急峻で危険で、竹や木が密集していたため、下を見ることは不可能でした。川を渡ると、水は再び平らであることがわかりました。峡谷を抜けてルタイに到着すると、平野と谷が見え、その間を激しい流れが押し寄せ、歩く場所の地面を濡らします。先日、湘宮嶺を越えたのですが、一滴の水も見つかりませんでした。ここの土地はあそこよりも高く、岩山が曲がりくねって、豊かな湖を形成しています。武公の東側の山々は、枝分かれの多い尾根で形成されており、武公の西側の山々は、多くの峰と岩の断崖で形成されています。土壌と岩が異なるため、乾燥度と湿潤度も異なります。嘉渓には4、5家族が輪になって立ち、泊まる場所を探していたが、全員が大晦日のパーティーを開くことで断った。私が道端をぶらぶら歩いていると、一団の人々が東の村から西の家へやって来て、宴会を開いているのが見えました。私たちの中の一人の若者が、私が泊まる場所がないのを見て、家々を回って泊まる場所を探し、それからイーストビレッジのタン家に連れて行って宴会を開いてくれました。私はそこに滞在することができました。私たちはその日30マイル旅しました。 5日目の朝食後も、山頂はまだ霧に覆われていました。それから私たちは尾根を越えて南東に向かい、5マイルほど歩いて平らな野原に到着しました。そこがダビでした。この地域にはいくつかの世帯が住んでおり、それぞれ独自の谷を持っています。北東から小さな川が流れてきて、それが鶴家坊の流れです。北からは盧台川が流れてきて、北西からは沙盤頭川が流れてきて、それらはすべて陳前口で合流して流れ出ています。 【二つの山は門のようであり、道はそれに沿っている。 〕出口は東の海に面した石八渡の平田です。大北の水は北から陳前へ流れ、上北の水は西から車江へ流れ、二つの川は合流して前山の下の平野を東へ流れます。このルートは車江から西渓に沿って進み、5マイル進むと七北に到着し、その後再び山の中へ戻ります。川の南側を渡った後、私たちは再びメンロウリッジを登りました。リッジを5マイル越えると、再び川に出会いました。平武からさらに2マイル進むと、川の真ん中に峰があります。その北と南に川があり、峰の前で合流します。そこが越渓の上流です。道は山頂の南側の渓流から入り、南にはかなり急峻な石蘭嶼があります。竹高嶺をさらに3マイル上ると、嶺の北側の水は安府に流れ、嶺の南側の水は永新に流れます。その後、尾根に沿ってさらに2マイル進み、尾根を下りて南東にさらに2マイル歩きます。石の洞窟の北を過ぎると、南西の小さな丘を登ります。丘の上の岩は色が湿っていて、形がごつごつしています。岩の割れ目から下を見ると、4つの円に囲まれた洞窟があり、隙間に扉があります。内部には青い穴があり、奥には深い洞窟があります。洞窟の名前はストーンシティです。 【洞窟の外には4つの岩壁があり、東側の岩壁には隙間があり、庵が寄りかかっている。寺院は北を向いており、左側に洞窟があり、扉は北東を向いていますが、僧侶によって扉が閉められており、誰も入ることができません。私は岩の上に身を乗り出して呼びかけ、長い時間をかけてようやく誰かを見つけました。私は僧侶に食事を用意するように頼み、それから石門寺に行くつもりで洞窟に入りました。 【階段を下りていくと、陽県の張公洞門によく似ていますが、規模が大きいです。洞窟の高さは張公の洞窟と同じだが、深さと幅は2倍ある。丘の1つは水平で、内側と外側の2つのレベルに分かれています。外側のレベルの入り口には、プラットフォームのような巨大な石があります。プラットフォーム上には二つの石筍が立っていました。左右の北側の崖には、竹の子の2倍ほどもある石柱が立っており、とても古いものらしく、石の底から高くそびえ立ち、洞窟の頂上まで達しています。側面に隙間があり、これを利用して柱の周りを回転させることができます。柱の根元が立ち上がるところには、まるで皿に埋め込まれたかのように石の輪があります。その横に支洞があります。再び北へ進むと、もう一つの大きな柱があります。下の部分は蓮の花のように積み重なって柱になっています。上の部分は宝塔のようで、上には天蓋があります。側面には人が向きを変えられる隙間もあります。柱の左側にももう一つ穴があり、枝の穴はさらにドーム状になっています。 〕夕食後、外に出ると、彼らはとても奇妙な洞窟を目にしました。彼らはたいまつを探しましたが見つからず、召使いのグーと一緒に再び中に入って、注意深く探しました。外に出たときすでに暗かったので、彼は寺の中に留まりました。 石城洞は元々石朗と呼ばれていましたが、南皮の劉元慶が洞窟の入り口の石窟に静蘭を築き、樹林と改名しました。現在では、洞窟の外側の石の絶壁が城壁のように見えるため、石城とも呼ばれています。 |
<<: 『徐霞客旅行記 江油遊記十四篇』の原作の内容は何ですか?
>>: 賈宝玉が里香園で飲んでいたとき、なぜ林黛玉は李馬に立ち向かったのですか?
推薦する
『星の王子さま』の名言集: 『星の王子さま』の最も名言30選
以前読んだ『星の王子さま』をもう一度見直してみましょう。この本はDoubanのTOP250リストで1...
「湖口から廬山の滝を眺める」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
廬山の滝を望む湖口張九齢(唐代)巨大な泉が流れ落ち、紫色の霧が遠くまで広がります。 (ホンイー:レッ...
武則天の墓の神秘的な秘密:乾陵は1300年間無傷のままだった(写真)
武則天の墓の謎:なぜ何万人もが武則天の墓を発掘できないのか?世界で最も発掘が難しい皇帝の墓はどこかと...
『射雁英雄の帰還』で呉三娘はどのように死んだのですか?呉三娘の結末は?
呉三娘は『射雁英雄の帰還』の登場人物。呉三童の妻であり、呉敦如と呉秀文の母。呉三童のために薬を飲んだ...
北宋代の女性詩人・衛旻の詩集「菩薩人 沈む夕日に隠れた渓山」を鑑賞
以下に、Interesting History の編集者が、魏夫人の『菩薩人・河山落日図』の原文と評...
第14章:李元帥は北進を命じられ、皇帝の検閲官カンは率直な追悼文を書く
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
ヨン・タオの「ティ・ジュンシャン」:詩全体はジュンシャンの反射のリアルな描写で始まる
雍涛(834年頃生きた)は、郭君としても知られ、成都(現在の四川省成都市)出身の唐代末期の詩人である...
古代の恋愛物語の一つ:徐仙と白蛇の愛はどのように始まったのでしょうか?
『白蛇伝』は、西湖の船上で一目惚れして結婚した白姫と徐仙の二人の物語です。次は興味深い歴史エディター...
関羽は華雄を簡単に殺すことができたのだから、もしそれが河北の四柱だったらどうなるだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
なぜ裴延は『青雁』を書いたために武則天によって死刑を宣告されたのですか? 「グリーングース」という言葉はどういう意味ですか?
今日、「Interesting History」の編集者は、なぜ裴彦が「青雁」を書いたために武則天に...
唐の粛宗皇帝の母である李隆基の元献皇后の生涯と簡単な紹介
元献皇后は、姓は楊、本名は不明で、洪農華陰に生まれました。中国唐代の唐皇帝玄宗の側室であり、唐皇帝粛...
龍門石窟の蓮華洞の特徴は何ですか?ロータス洞窟の紹介
龍門石窟の蓮華洞の特徴は何ですか?蓮華洞は西暦525年から527年の間に建てられ、洞窟の頂上に彫られ...
曹爽の弾圧に直面して、司馬懿はどのように耐えて時を待ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清代初期の詩人、那蘭星徳:「迪蓮花・楚才」の文学的評価
本日は、Interesting Historyの編集者が『十里蓮花・楚才』の文学的評価をお届けします...
三国志の歴史上の出来事 三国志の主要な歴史上の出来事の紹介
三国時代三国時代(西暦220年~280年)は、中国の後漢と西晋の間の歴史的時代であり、主に曹魏、蜀漢...