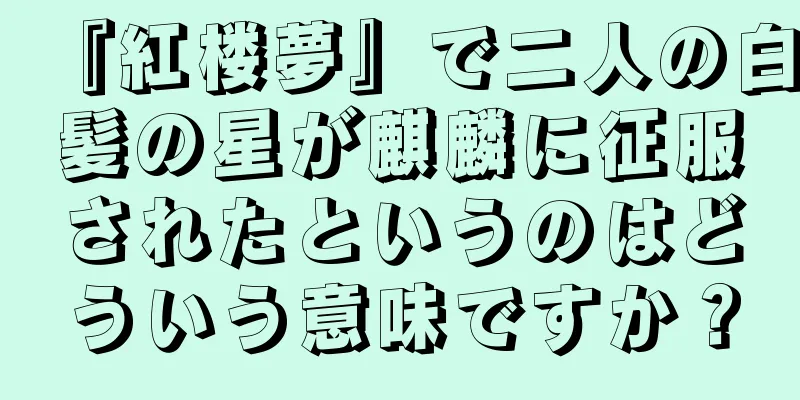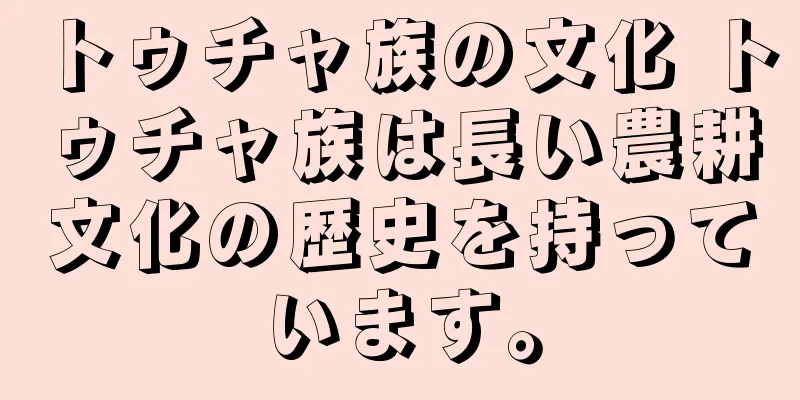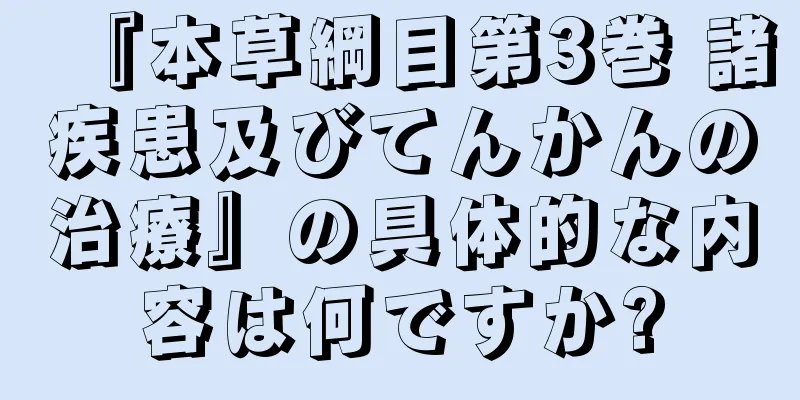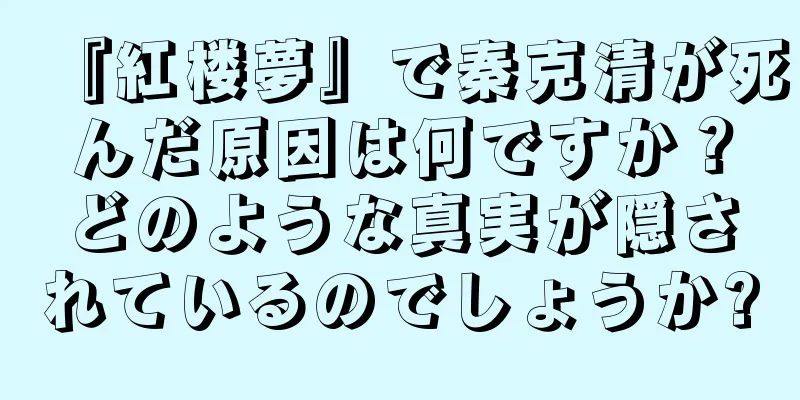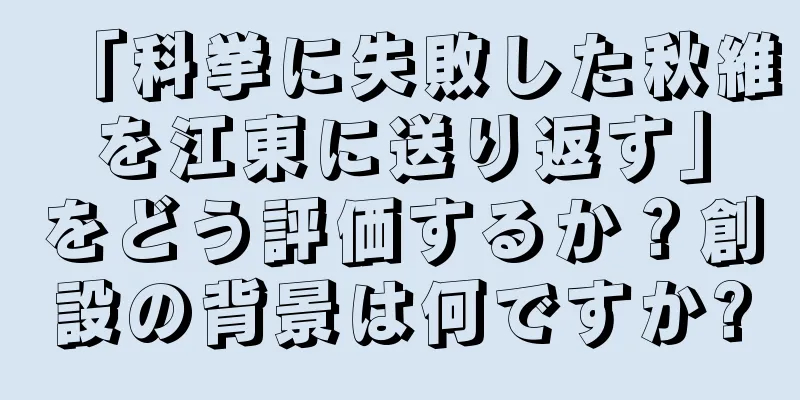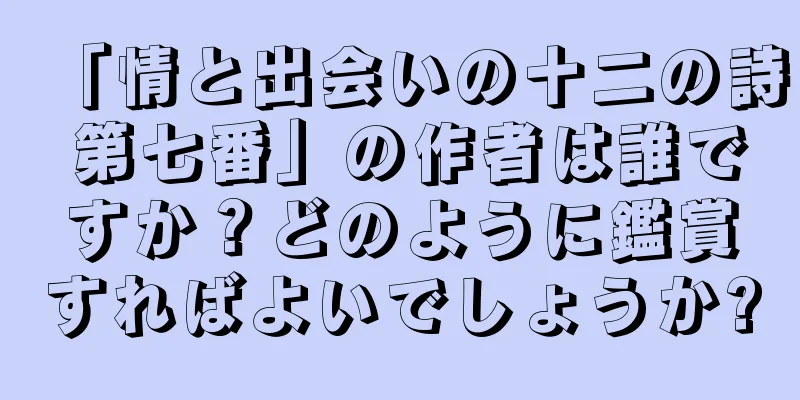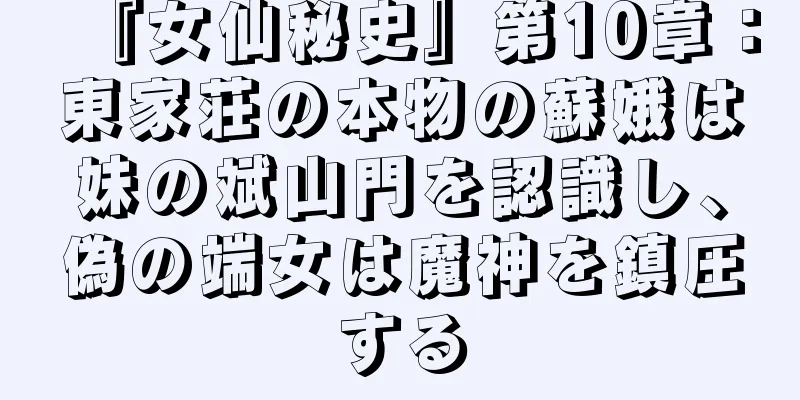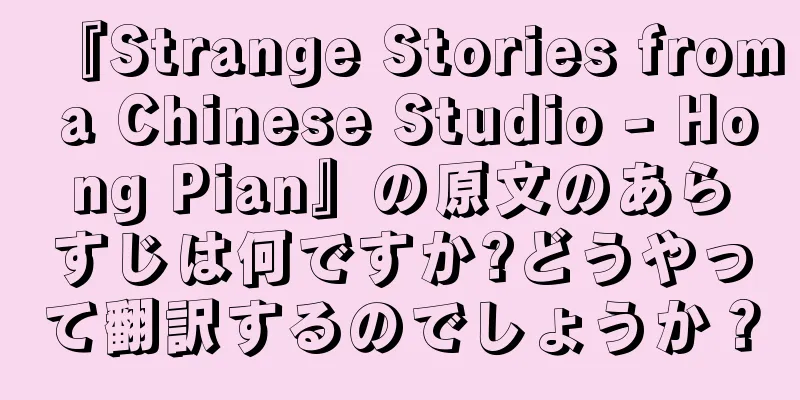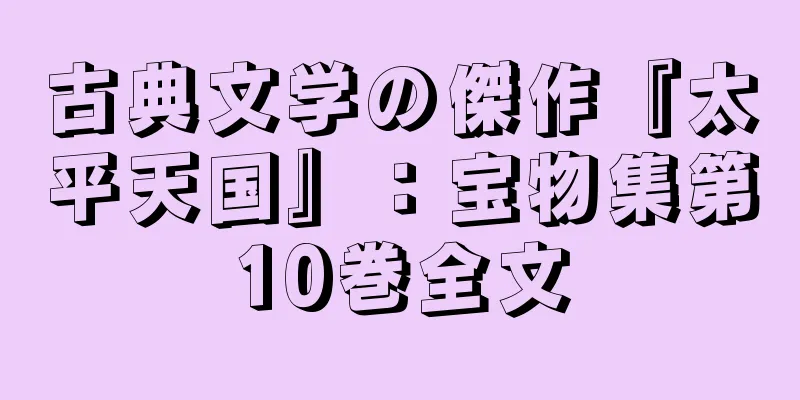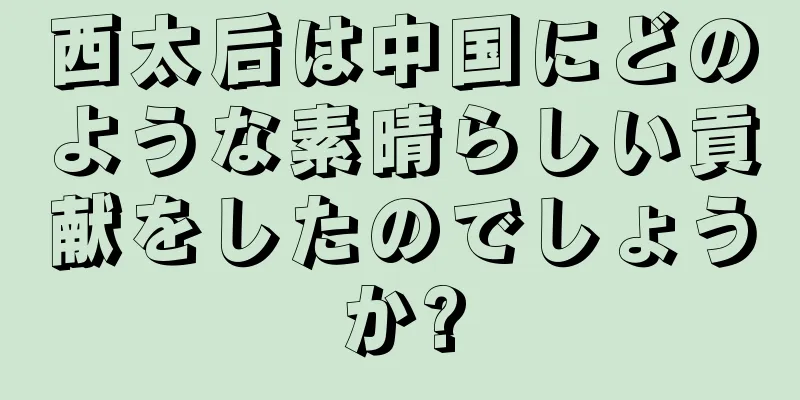老子の『道徳経』第 54 章とその続き
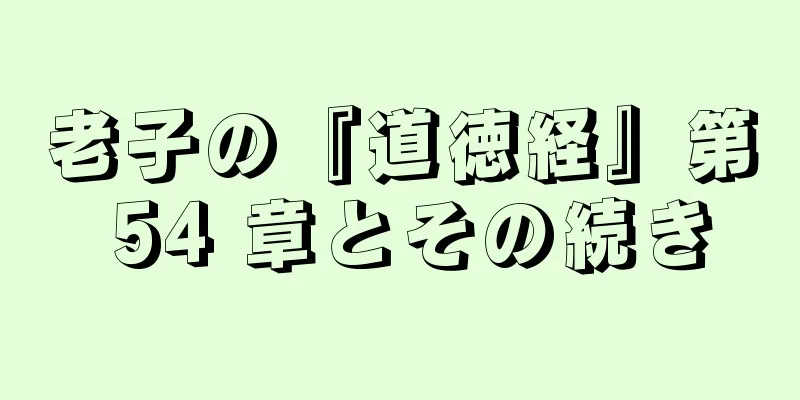
|
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古代中国で秦以前の哲学者が分裂する前に書かれた作品であり、道教の哲学思想の重要な源泉です。 『道徳経』は2部に分かれています。原典では上段を『徳経』、下段を『道経』と呼び、章は設けられていません。後に、最初の37章を『道経』、38章以降を『徳経』と改められ、81章に分かれています。そこで今日は、Interesting History の編集者が老子の『道徳経』第 54 章をお届けします。見てみましょう! [オリジナル] 剣に長けた者は決して武器を抜かず、武器を持つことに長けた者は決して手放さず、その子孫は彼らに供物を捧げ続けるであろう。それを自分自身で修めれば、その徳は真実となる。それを家庭で修めれば、その徳は豊かになる。それを村で修めれば、その徳は長続きする。それを国家で修めれば、その徳は豊かになる。それを世界で修めれば、その徳は普遍的となる。したがって、自分の体を通して自分自身を観察し、家族を通して家族を観察し、村を通して村を観察し、国を通して州を観察し、世界を通して世界を観察してください。世界がこんな風になっていることをどうして知っているのでしょうか? それはこのためです。 [翻訳] 築くのに優れたものは根こそぎにされず、保つのに優れたものは奪われない。子孫がこの道理に従い、守ることができれば、代々途切れることはない。人がこの原理を自分自身に適用すれば、その人の徳は真実で純粋になります。この原理を家族に適用すれば、その人の徳は豊かで十分になります。この原理を故郷に適用すれば、その人の徳は尊敬されます。この原理を国に適用すれば、その人の徳は豊かで偉大になります。この原理を世界に適用すれば、その人の徳は無限で普遍的になります。 したがって、自分自身の修身の道を用いて他人を観察し、自分の家族を用いて他の家族を観察し反省し、自分の故郷を用いて他の故郷を観察し反省し、世界を平定する道を用いて世界を観察し反省しなさい。世界の状況がこのようになっていることを私がどうやって知ったかと言うと、それは私が上記の方法と原則を使ったからです。 [注記] 1. 保持する: 保持する、固定する、しっかりとする。 2. 子孫は死者に対して、止めるため、断つため、終わらせるための犠牲を捧げ続けます。この文の意味は、「すべての世代が「よく建てる」と「よく抱く」という原則を遵守できれば、未来の世代の香は決して尽きることはない」ということです。 3. 長い:尊敬。 4. バン:ある本では「国」が使われています。 5. したがって、自分の体で観察し、家族で家族を観察し、故郷で故郷を観察します。自分自身で他人を観察し反映し、自分の家族で他の家族を観察し、自分の故郷で他の故郷を観察し反映します。 [拡張読書1] 王弼の『道徳経』の注釈 良い建築物は壊れない、 まず根を強くし、次に枝を育てれば、抜け落ちることはありません。 しっかりと握っている人は離しません。 欲張らず、最善を尽くせば、孤立することはありません。 子孫たちは彼に犠牲を捧げ続けています。 子孫はこの犠牲を捧げる方法を絶え間なく伝えていくでしょう。 自分自身の中でそれを培えば、あなたの徳は本物となり、家族の中でそれを培えば、あなたの徳は豊かになります。 自分自身を扱うように他人を扱いなさい。身体を養えば誠実になり、家族を養えば豊かさを得られます。練習を諦めなければ、得られる恩恵はもっと大きくなります。 村で修めばその徳は長続きし、田舎で修めばその徳は豊かになり、世界で修めばその徳は普遍的となる。だから、自分の目で自分を観察し、自分の目で家族を観察し、自分の目で故郷を観察し、自分の目で国を観察しなさい。それはすべて同じです。 世界の視点から世界を眺める。 人々の視点から世の中のあり方を観察しなさい。世の中の道は、好ましいか好ましくないか、良いか悪いか、すべて人間の道と同じです。 世界がこんな風になっていることをどうして知っているのでしょうか? それはこのためです。 上記はそういうことです。どうやって世界を知るのでしょうか? 外に求めるのではなく、自分自身を吟味することによって世界を知るのです。これが、家を離れずに世界を知るということなのです。 【拡張読書2】蘇哲の『老子解説』 しっかりと築き上げる者は根こそぎにされず、しっかりと保持する者は手放さず、その子孫は彼らに犠牲を捧げ続けるでしょう。 この世に、何かを建てても引き抜かれず、何かを握っても離されない人がいるだろうか。聖人だけが天地の理を知り、物事の虚偽を吟味し、物質を捨てて修行する。彼らの徳は豊かである。実際、彼らには建てるものは何もないが、彼らが建てたものは引き抜かれず、実際、彼らには握るものは何もないが、彼らが握ったものは離されない。そのため、彼らの子孫でさえ、彼らに供物を捧げ続けている。 身体を修めば徳は真実となり、家庭を修めば徳は残る。故郷を修めば徳は長続きし、国を修めば徳は豊かになり、世界を修めば徳は普遍となる。 一度自分自身を修養すれば、自分の影響力を自分以外のものにも広げ、全世界を統治するところまで到達することができます。 したがって、自分の体を通して自分自身を観察し、家族を通して家族を観察し、故郷を通して故郷を観察し、国を通して国を観察し、世界を通して世界を観察しなさい。世の中がこうなっているとどうしてわかるのでしょうか? それは、このためです。 天地の外にあるものは庶民には見えませんが、その原理は推測することができます。自己修養の最高段階は、自分を通して自分を観察し、家族を通して家族を観察し、郷を通して郷を観察し、国を通して国を観察することです。これはすべて私の手の届く範囲と知識の範囲内です。しかし、聖人が自分を通して自分を観察するのではなく、世界を通して世界を観察することをどうやって知るのでしょうか?自己は自己によって観察できますが、世界は世界によって観察できないことはあり得ますか?それでは、世界がこのようになっていることをどうやって知るのでしょうか?それはこれによるものです。言葉は自分の体を通して理解することもできます。 |
推薦する
重陽の節句の風習は何ですか?重陽の節句を祝う習慣は、地域によってどのような違いがあるのでしょうか?
以下は、重陽の節句についてInteresting Historyの編集者がお届けする記事です。ご興味...
『紅楼夢』で賈舒が元陽に無理やり結婚を迫った後、賈祖母は何をしましたか?
『紅楼夢』の中でメイドについて語るなら、当然元陽から始めるべきでしょう。これについて言えば、皆さんも...
七剣十三英雄第20章:梅の花が金山で弟を救い、狄紅は師匠に助けを求めて千里を旅する
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
曹操の名詩を鑑賞する:洛陽の城壁を見て、魏子は悲しんでいる
魏の武帝、曹操(155年 - 220年3月15日)は、雅号を孟徳、あだ名を阿満、吉理といい、沛国桥県...
『紅楼夢』で金川が罰せられたとき、宝玉は何をしていたのですか?彼を助けてあげたらどうですか?
賈宝玉は『紅楼夢』の中で最も複雑な登場人物の一人です。次は『おもしろ歴史』編集者が歴史物語をお届けし...
法家の代表である韓非子の思想命題の紹介:法に従って国を治める
法家の代表である韓非が唱えた「法によって国を治める」という考えは、秦の始皇帝が六国を統一し中原を支配...
太平広記・第82巻・奇人・李子謀をどう理解するか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
「武士の都への帰途に白雪を送る歌」は岑申の作で、辺境の軍営で都へ帰る使節に別れを告げる心温まる情景を描いている。
高史とともに「高實」と呼ばれた坤深は、唐代の辺境詩人です。坤深は長年辺境に住み、辺境の風景、軍隊生活...
なぜ尚官婉児はこれほど多くの権力者たちの間を動き回りながら無敵であり続けたのでしょうか?
どうして尚官婉児がこれほど多くの権力者の中で無敵であり続けたのか知りたいですか?次の興味深い歴史編集...
徐州の戦いで、高順はなぜ夏侯惇との決闘でわずか40~50ラウンドで負けたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
顧太清の『金糸歌:白ベゴニアの頌歌』:詩人の美的傾向は世俗の世界とは異なる
顧太清(1799年2月9日 - 1877年12月7日)、名は淳、字は梅仙。彼の本姓はシリン・ジョロで...
宋代の有名な将軍、武林の略歴。武林はどのようにして亡くなったのでしょうか?
武林(1102-1167)は、徳順軍竜干(現在の甘粛省景寧)の出身で、唐青と呼ばれていました。武潔の...
唐の乱を引き起こした安禄山は1年も経たずに亡くなりました。なぜ安史の乱は6年間も続いたのでしょうか?
正確に言うと、安史の乱は8年間続いたわけではなく、合計7年2か月続きました。しかし、安禄山は757年...
軍事著作「百戦百策」第8巻:全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
趙雲が長阪坡で主君を救出するために単騎で出向いたとき、曹操はなぜ背後から矢を射てはならないと命じたのでしょうか。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...