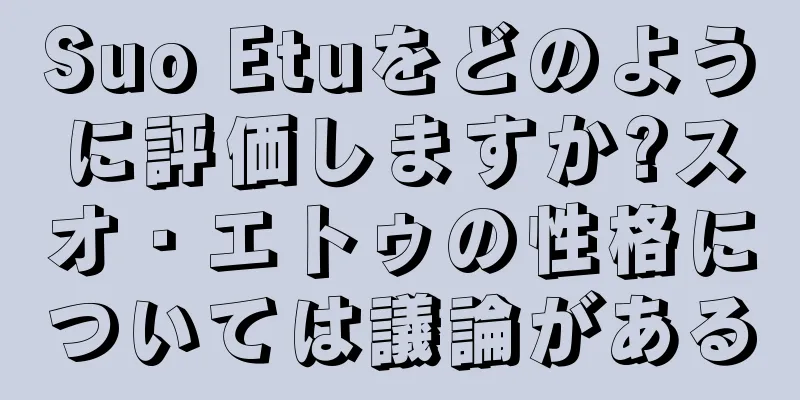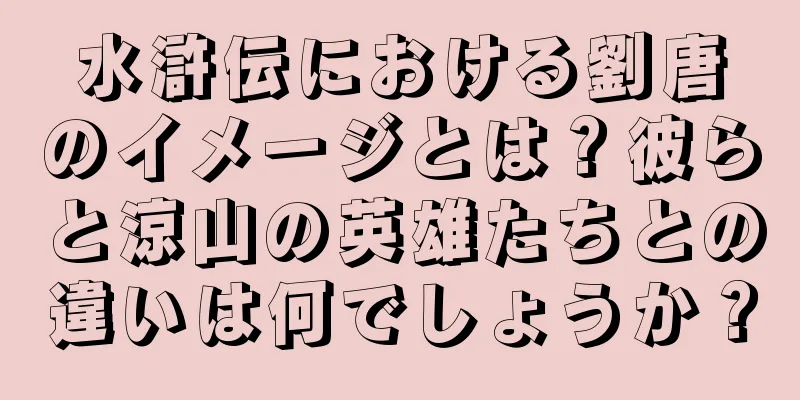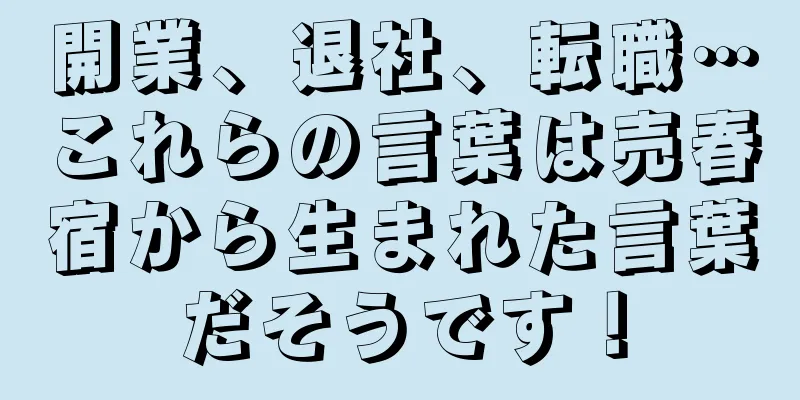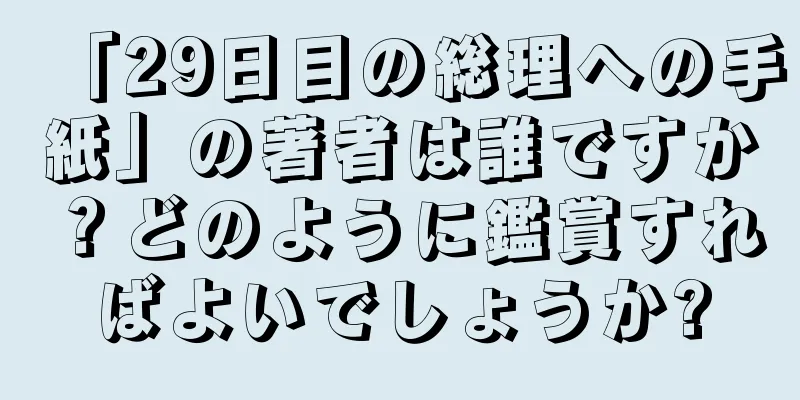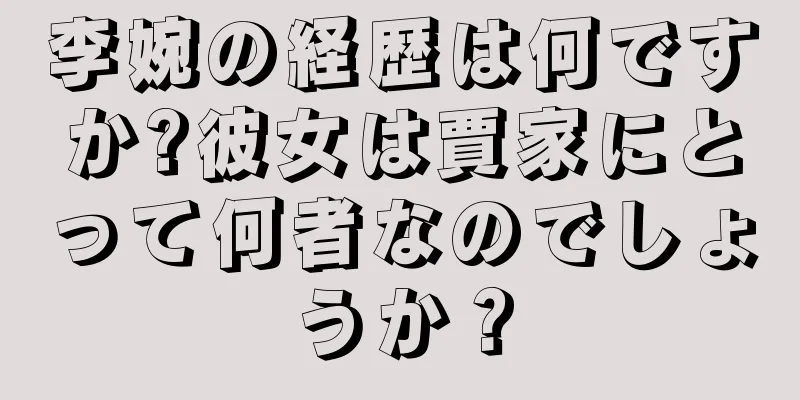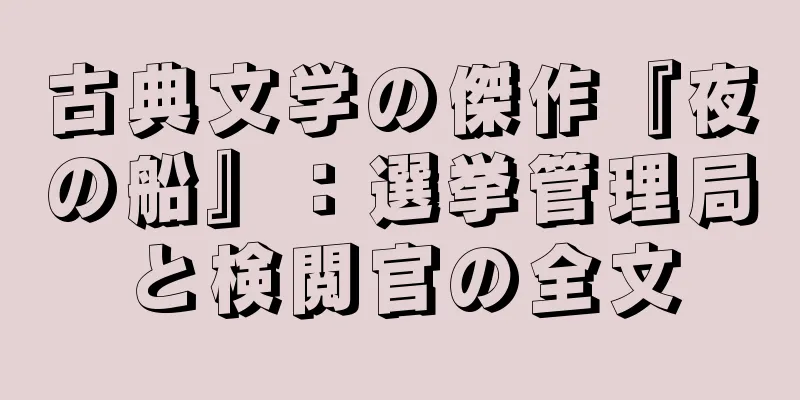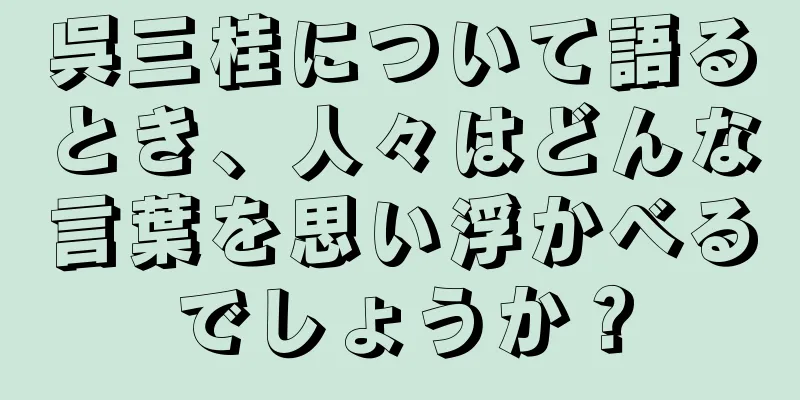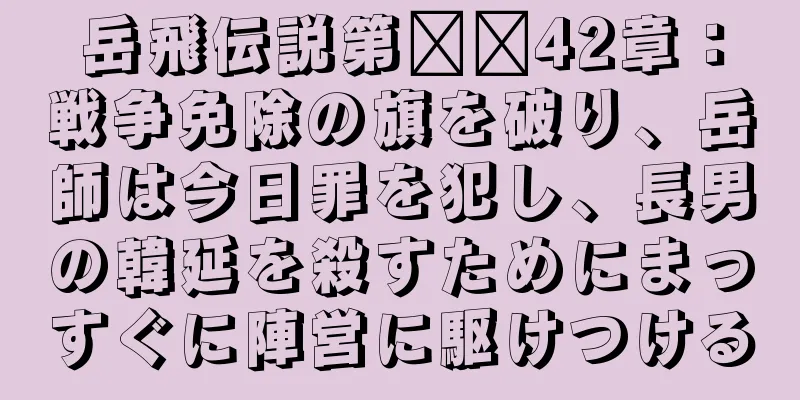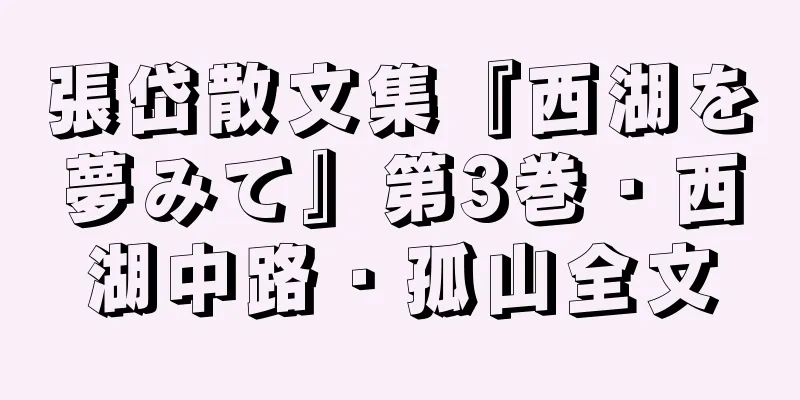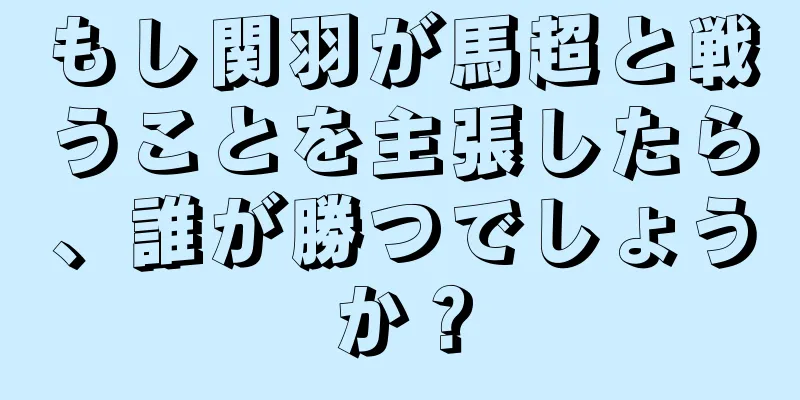古典文学の傑作『太平天国』:果実編第12巻全文
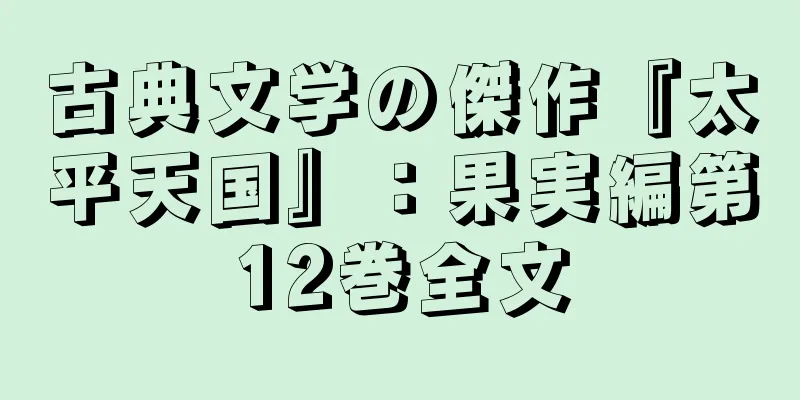
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が果物部門第12巻の詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! ○スイートバナナ 『晋の宮殿と亭の名』には、華林園、バナナの木が2本あると記されている。 『南蛮記』には、南召の住民は食器を持っていないので、バナナの葉を土台として使っていると書かれている。 『光志』によれば、バナナの漬物、または甘いバナナの茎は、蓮根のようなもので、二重の皮で包まれており、ボウルほどの大きさである。葉は幅2フィート、長さ10フィートです。種には角があります。種子の長さは6~7インチ、あるいは3~4インチです。まるで抱き合うかのように、2匹ずつ一列に並んで生まれます。皮を剥くと、黄白色でブドウのような味がして、とても食べ応えがあります。根はサトイモほどの大きさで、大きさは一粒で、色は緑色です。その茎は絹のようにほどけ、葛に編まれるため、葛と呼ばれます。シャキシャキして美味しいのですが、色は黄白色で葛色ほど良くありません。交直を離れて建安へ行きます。 『南方奇聞』にはこう記されている。「甘蕉は草の一種で、見た目は木のようだ。」大きな植物は周囲が 1 メートル以上、葉の長さは 10 フィート、または 7 ~ 8 フィート、幅は 1 ~ 2 フィート以上になります。花は大きく、ワイングラスのような形をしており、ハイビスカスのような色をしており、茎の先端に咲きます。種子は100個以上あり、大きいものは「ファング」と呼ばれます。根はサトイモのかけらのようで、大きいものは車輪のハブほどの大きさです。果実は花の後に続き、それぞれの花には 6 個の種子があり、順番に続きます。果物は一緒に実らず、花は一緒に散りません。この膠には3種類あります。1種類は親指ほどの大きさの種があり、羊の角のように長くて尖っていて、羊角バナナと呼ばれ、最も甘い味がします。1種類は鶏卵ほどの大きさの種があり、牛乳のようで、羊角バナナより少し味が劣ります。もう1種類はカップルほどの大きさで、長さ6〜7インチ、四角形で、甘さが少なく、最も弱いです。茎はサトイモに似ており、灰と混ぜて糸紡ぎに利用することができます。 『奇事記』には、バナナの葉はゴザほどの大きさで、茎はタロイモのようだとある。鍋で煮て絹にし、紡いで織ることができる。女性職人がガーゼにするが、職人は触らない。内部はニンニク白鳥の頭のような形をしており、大きさはハマグリほどです。本物の部屋なので、一部屋に何十個も置いてあります。実際、その皮膚は火のように赤く、日時計を投げ込むと黒くなります。皮を剥いて、蜂蜜のような味がする肉を食べます。 4、5個食べると満腹になり、歯の間にも風味が残ります。別名は甘嬌。 顧慧の『広州記』には、次のように記されている。「甘芭蕉の根と葉は五花石の根と葉と変わらない。南方の土壌は暖かく、霜が降りないため、花と葉は一年中咲いている。熟しているかどうかにかかわらず、苦い。」 「南部植物の説明」には、次のように書かれています。バナナの木の種子は、芽が山積みになっていて甘く、蜂蜜の保存にも使えます。 『名山紀行』には、赤岩山の水と岩の間にはバナナの木しかなく、そのいくつかは高さ10メートルにも達すると書かれている。 卞景宗の『甘焦賛』にはこうある。「青々と茂り、木のようだが、その質は木のものではない。」 ○ フーリウ 『呉路地理』には、石興に富六蔓があり、木に生えていて、辛い味がする。ビンロウと一緒に食べることもできる、とある。 『書紀』にはこう記されている。「富六樹の根は箸ほどの大きさで、柳の根のようだ。」また、鮮やかな赤や紅色をしており、生死を占う日時計としても使われるハマグリがあり、燃やして灰にすると牡蠣粉と呼ばれます。まずビンロウの実を口に入れ、1インチ長く口に含み、少量の古本灰を加えて一緒に噛むと、胸の中の悪い気を取り除くことができます。 『奇異の記録』にはこう記されている。「古代の本会は男性の李会であった。」フリュウとビンロウジュと一緒に摂ると、気分が良くなります。檳榔果は檳榔に似ています。檳榔果と檳榔果は、世界中で遠く離れた場所で育ちます。両者は非常に異なりますが、互いに補い合っています。「檳榔果と檳榔果は悩みを忘れさせてくれる」と言われています。 『膠州記』には、伏流には3種類あると書かれている。一つは火伏流と呼ばれ、根は香りがよくおいしい。一つは南伏流と呼ばれ、葉は緑色で辛い。そしてもう一つは伏流騰と呼ばれ、これも辛い。 『広志』によれば、フユボダイジュは木の周りに生え、その花と実はクラゲで、ソースにすることができる。 左寺の『武度頌』にはこうあります。「石の帆と水の松、東風がそれを支える。」 ○太郎 『朔文』には、斉の人々はタロイモを「ジュ」と呼んでいたとある。 『孝行の書』には、真冬にプレアデス星団でサトイモが収穫されるとある。 (ソン・ジュンのメモには「ジュもタロイモだ」とある。) 「Guangya」によると、Jieru は水芋であり、黒芋とも呼ばれます。 『漢書』には、汝南県に紅渓という大きな池があったとある。翟方瑾が宰相だったが、秦がそれを征服した。県民は不満を訴え、子どもの歌はこう歌った。「池を壊したのは誰?翟子薇。彼は私に豆とタロイモのスープを食べさせてくれた。」 『漢書』には、秦が趙を破ったとき、卓一族を移住させたと書かれている。彼らは言った。「岷山の肥沃な田んぼには、死ぬまで飢えることのないフクロウがいると聞いた。そこで遠くへ移住させようと思い、臨瓊に連れてきた。臨瓊には百人の召使いがいた。」 崔洪の『春秋十六国史・蜀記』には、次のように記されている。「李雄が成都を征服したとき、人々は飢えに苦しんでいたので、李雄は人々を率いて李で穀物を集め、野生のタロイモを掘って食べた。」 『南朝史孝義伝』には、毓陽出身の仙于文宗が7歳のときに父親を亡くしたと記されている。父はサトイモを植えている最中に亡くなりました。翌年サトイモの季節が来ると、私はサトイモを思って泣きました。そして、一生そうし続けました。 『范勝之書』には、地区ごとにサトイモを植える方法が記載されている。地区ごとにサトイモ3石が収穫できる。 『汝南名人伝』には、趙公という名の袁安が銀平の市長に任命されたと記されている。当時は飢饉で、野菜を食料と交換する家賃だけでは足りなかったため、安は「民は飢えていて貧しいのに、どうして穀物を食べ続けられるだろうか」と言って、代わりにタロイモを届けることを許可しました。安はまず自らタロイモを差し出し、役人たちは皆それに従いました。 『汝南名人伝』には、薛保貴の先祖は孟策で稲とサトイモを栽培したとある。彼らは米を供物に使い、サトイモを飢えの際の餌とした。道にふけり、礼儀作法を語り、神秘的であり、何もしない。 『仙人伝』にはこう記されている。梁の宰相に酔っぱらいがいた。彼は民にもっとタロイモを栽培するように命じた。3年後、大飢饉が起こったが、彼の言ったとおりになり、梁の民は死ななかった。 『鳳土記』にはこうあります。「タロイモはつる植物のように成長し、その根は鶏やアヒルの卵のようだ。」 『華陽国志』にはこう記されている。「何遂、字は済也、蜀の邊の人。」母が亡くなり、見送りに帰る途中、役人はお腹が空いていたので、道端の人から芋を取って絹で縛り、支払うお金を確保しました。人々は互いに言った。「漢青は無事だと聞いた。人々は穀物を奪い、代金を支払うよう命じた。」 「Bowuzhi」は言う:野生のタロイモを食べることは人間にとって有害です。タロイモは植えてから3年間収穫しないとまた生えてきて食べられなくなってしまいます。 『広志』には、芋には14種類あると書かれている。カワセミ芋ほどの大きさの王芋、車輪芋、側巨芋、端芋などがある。これら4種類のタロイモは、瓶ほどの大きさで、種が少なく、傘のような葉を持ち、色は黄色、茎は紫色で、長さは10フィート以上あり、熟しやすく、風味が長持ちします。これらは最高のタロイモであり、茎はスープを作るのに使用できます。枝に生えるサトイモもあり、大きいものは2~3リットルの大きさになります。黄色い鶏タロイモもあります。百果サトイモがあり、収穫量は1ムーあたり100ブッシェルです。 7月に熟すサトイモがあります。九角形のサトイモがありますが、とても醜いです。孟空里芋、青里芋、草里芋などがあり、種は食べられませんが、茎は漬物にすることができます。野嶼県産の百種芋もあります。喰い芋があり、他の種がなく、家族は永遠に繁栄します。 『本草綱目』には「タロイモ、土菌、八月色」とある。 左寺の『舒都譜』にはこう書かれている。「瓜と里芋の畑がある。」 ○リン 「Er Ya」曰く:ヒシはシダ植物です。 (郭普は言った。「私は今死にかけています。」) 『大評伝』には「枳耶水栗」とある。 (巨野は魯の広大な荒野、沼地、そして現在の蜀の山陽である。) 『周書』には、冬にはヒシの実とレンコンを食べると書かれている。 『周礼 天官 第二部』には、籠番の役目は籠にヒシの実を入れることだとある。 『国語』には、屈道は蓮を愛したとある。屈道は病気のとき、一族の長老たちを召集して配下にした。(屈道は楚の大臣で、一族の長老たちは家臣だった。)屈道は言った。「私に供物を捧げるときには、必ず蓮を捧げなさい!」吉兆が訪れたとき、一族の長老たちは蓮を勧めようとしたが、屈堅は彼に立ち去るように命じた。(屈堅は屈道の息子の子牧だった。)屈道は言った。「先生は、個人的な欲望で国のルールに干渉しません。」 『韓書・則天武后』には、渤海の太守であった龔遂が、秋から冬にかけて、クサノオウやヒシノキなどの果物をもっと備蓄するようにと人々に勧めたと記されている。 謝成の『後漢書』には、袁洪の父は彭城の宰相であった。彼が亡くなったとき、洪は葬儀を迎えるために郡に赴いた。彼は空腹のときはヒシやクサを食べ、喉が渇くと泥水を飲んだと書かれている。 『梁書』には、襄東王の真熙司馬であった于洪が西へ赴き、任務を報告したと記されている。途中で食糧が不足したため、途中で色とりどりのヒシの実を摘み、ヒシの実ご飯を作って兵士たちに分け与えた。洪都が住んでいた場所には、後世の人々は蓮根一つさえ見つけることができない。彼らはまた、瓊島で何百匹ものマカクザルを捕獲し、ジャーキーにして食料や酒として提供した。 『淮南子』には、楚の霊王が樟花台を建てたが、斉舒は民の恨みを買って毗王を立てた。民は彼を避け、彼はヒシを食べ、水を飲み、石で作った枕で死んだとある。 『呂氏春秋』は次のように語っている。李叔は莆の閔公に仕えていた。彼は自分が無知であると考え、海上に住み、夏にはヒシを食べ、冬には栗を食べた。 杜書の『杜倫』にはこうある。「浮き草が浮くのは、ヒシの浮くのと似ている。ヒシは根を張っているが、浮き草は波に浮かぶ。」だからこそ、堯と舜は賢い言葉が徳を汚すと嘆き、孔子は紫が赤の色を奪うと憎んだのです。 「風蘇堂」はこう言った。「宮殿は東の井戸のような形をしており、火を防ぐ蓮と睡蓮が彫られている。」 『羅浮山記』には、遂寧県宣桂園にヒシの実があり、とても美味しいと書かれている。 『広志』によれば、巨業格スイヒシの実は普通のスイヒシの実より大きい。淮河と漢江の南では、凶作の年にはヒシの実が野菜として使われます。 樊王の『寺院への供儀』には、秋の最初の月に、ヒシの実とクサノオウで供儀が行われたと記されている。 「楚辞」は言う:私は蓮の葉で服を作り、蓮の花でスカートを作ります。 左寺の『舒都論』にはこうある。「肥沃な土地には、緑のヒシと赤い蓮がある。」 潘越の『西伐頌』には、鴨が跳ね、雁が飛び、ヒシの実やクサノオウを食べるとある。 郭普の『河歌』にはこうある。「突然夕方を忘れて、夜に家に帰り、色とりどりの睡蓮を詠唱し、船の側面を叩いた。」 曹植の『九悲』には、言葉は色とりどりの蓮の葉と美しい花で結ばれているとある。 孫褚の『温曲建文』には、「盆の上の材料には、ヒシの実と蓮の葉が含まれています」と書かれている。楚には池がたくさんあり、そこにはヒシや蓮が生育しています。父はそれに依存して自分の感情を抑圧していました。住職は、子供を育てる儀式を無法地帯に破壊し、死者を生きているかのように扱う意味も失わせ、本来の願いを奪ってしまった。ジアンは、このことにどう耐えればよいのだろうか。 ○ ゴルゴン 「周礼書 天官 第二部」のトン人の仕事は、籠の中身とヒシの実を加えることです。 『漢書』にはこう記されている。公遂が渤海の太守だったとき、冬にはヒシやクワの実を備蓄するように民に勧めた。 『淮南子』はこう言った。「タヌキの頭はネズミを治せるが、鶏の頭は瘻孔を治せる。」 (発音は「ロウ」。ネズミは人を噛むが、アライグマは治す。瘻孔は首の腫れ。莢頭は枯れた日時計草で、幽州では「燕頭」と呼ばれている。これも瘻孔を治す。) 崔葭の『古今記』には、「芡」は鶏の頭を意味し、ガチョウの頭や芰とも呼ばれる、とある。葉は蓮に似ていますが、より大きく、茹でたような斑点があります。果実にはトゲがあり、中身は真珠のようで、空腹を癒し、喉の渇きを癒す効果がある。 「方言」によると、「{艹职},芡,」は鶏の頭です。北燕では艹职と呼ばれ、清緒、淮、泗の間の地域は芡と呼ばれていました。 「シュオウェン」曰く:ゴルゴンは鶏の頭である。 『光牙』曰く:楚南部の河川や湖沼では鶏頭、雁頭と呼ばれている。 『本草綱目』には、茯苓(別名ヤンシ)は雷沢に生育すると記されている。 劉旭の『玄元賦』にはこうある。「香り高い森は密集し、紅竹はまばらだ。」まるで錦を刺繍したかのような、ヒシと蓮が満開です。 ○ロータス 「二亜」は言った。「蓮は睡蓮で、その実は蓮の実(蓮は莢のこと)、その中の種子はハトムギの実です。」 (心の中で苦しんでいる人。) 『茅石月塵万丘沢北』にはこうある。「湖のほとりにはガマと蓮の花が咲いている。」そこには、大きな巻き毛を持つ美しい男性がいました。 『史記』には、亀は千歳で蓮の葉の上を泳いでいるとある。 『呉代外国記』には、大秦国には蓮根などの果物があったと記されている。 『宋其居朱』は次のように伝えている。宣嘉18年、役人が報告した。揚州知事の王軍は、州政府の後ろの池に2つの蓮の花が並んで生えていて、2つの枝が分かれていると説明した。 16年後、華林の知事である呉勇は次のように書き記しました。「同じ茎に2つの蓮が咲き、花池湖に咲いています。」 また太史2年8月、豫州の禅湖で、同じ茎を持つ一対の蓮の花が咲き、実を結んだとも言われています。さらに6年後、東宮の玄奘池で1つの花芽から2つの蓮の花が咲きました。 『三国志』には、斉王が鄴に帰還すると、高麗と新羅は共に使者を派遣して貢物を納めたと記されている。以前、徐州の蓮は一本の茎と二枚の花びらがあり、占いでは「異なる木々が枝を繋ぎ、遠くから人がやって来る」と言われました。これが答えです。 『北斉書』には、後主武平年間、太守崔吉叔の家の池の蓮の茎が胡人の顔の形に似ていて、鮮卑の帽子をかぶっていたと書かれている。突然、吉叔は邪悪になった。 『三国志』には、周が斉を征服した後、斉の若き君主、胡王母らは皆長安に戻ったとある。最初、呉成の死後、「千銭で果樹園を買ったが、そこには蓮の木があった。札が破れていて、蓮の種はなくなっていた」という噂が流れた。その噂はとても悲しいものだったが、それが現実になった。 また、高維が寵愛していた側室の馮淑妃の名前は小蓮だったとも言われている。 『後唐書』には、この王朝の老軍監督張承業は権力と高貴な地位を占めていたと記されている。人々は肩を並べて頭を下げて彼に仕えたが、馬羽だけは狡猾で彼を侮辱した。客や同僚が宴会に集まると、成業はいつも珍しくてエキゾチックな果物を彼らの前に並べた。客は誰もいつもの果物より先に食べようとせず、先に来た人が食べ物を全部食べてしまった。程野はシェフに密かに警告した。「馬建が次に来たら、食事の前に乾燥した蓮の実をいくつか置いてください!」 于が到着し、ちらっと見て、食べられないことに気づきました。別の日、彼はブーツの中に鉄のハンマーを入れて、それを叩きました。チェンイエは笑って言った。「食べ物を変えてあげて、私の訴訟を台無しにしないで!」 夏侯小若の『芙蓉譜』にはこうある。「緑の部屋と緑の葉、紫の装飾と赤い花。」黄色いカタツムリは丸くて、ひげが垂れ下がっています。タッセルには金歯が飾られ、白い真珠が散りばめられています。 孫褚の『蓮花譜』にはこうあります。「星のように集まり、互いに支え合う。」それは、暗い夜に映る暗い空のように明るく、鄧林を飛ぶ若い鳳凰のように魅力的です。 『岳府歌』にはこうあります。「長江の南には美しい蓮があり、蓮の葉はとても青々としている。」 ○ レンコン 「二亜」曰く:蓮は睡蓮であり、その根は蓮根である。 『呉代外国記』には、大秦国には蓮根などの果物があったと記されている。 『斉書』には、雍明年間、巴東の襄王が逃亡中の劉毅らを殺害したと記されている。武帝はこれを聞いて、臣下に「子襄が謀反を起こした」と言った。戴僧景は大声で「巴東だけではなく、すべての王が謀反を起こすべきだ!」と言った。武帝が理由を尋ねると、蘇は「王は無実だが、しばらく投獄されているのだ!占い師に相談して蓮根とジュースを一杯もらった。占い師がここにいなければ、一日中喉の渇きに耐えることになるだろう」と言った。 「 『唐史』には蘇州がレンコンを献上したと記されており、その中で最も優れたものは「山溝」と呼ばれた。蓮の名前だからという説もあれば、虫に葉が傷つけられたからという説、根を長く伸ばすためにわざと葉が傷つけられたからという説もあります。近くには蓮の葉が何枚も生えていて、蓮の実の中に花が咲いているのもとても不思議です。 司馬相如の『子胥賦』には、ヒシの実とレンコンを噛むとある。 夏侯占の『芙蓉譜』には、神秘の泉でヒシの実と蓮の根を噛むとある。 謝条の詩にはこうある。「秋の蓮根は軽い絹に砕ける。」 |
<<: 『紅楼夢』の王夫人はなぜ林黛玉を嫁にせず、薛宝才を選んだのでしょうか?
推薦する
世界で最も多くの土地を失った 5 か国のうち、最も多くの土地を失った国はどこですか?
5. ドイツドイツは二度の世界大戦の後、大きな損失を被った。西では、ドイツとフランスの間で係争となっ...
『古跡五首詩集 第五』をどう鑑賞するか?著者は誰ですか?
歴史遺物に関する五つの詩 第5回杜甫(唐代)諸葛亮の名は天下に知られ、高潔で清廉な臣下としての彼の肖...
『紅楼夢』で王夫人は王希峰に対してどのような態度を取っているのでしょうか?
王希峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。これについて言及されるたび...
春の夢:紅楼夢における幻想的な性的夢の謎を解明する
夢は不思議な現象であり、夢を見るという経験はすべての人が共有しています。夢の心理学的説明は、睡眠中の...
「清平楽」は宋代の風俗を高度に再現している。大臣の不格好な帯は一体どうしたのか?
今日は、Interesting Historyの編集者が宋代の関連文化をお届けし、皆様のお役に立てれ...
チャン族はなぜジャガイモの餅を使って客をもてなすのでしょうか?
チャン族の食生活の特徴は、彼らの生活習慣や環境に深く関係しています。一般的に言えば、チャン族の食材の...
『三朝北孟慧編』第79巻の原文には何が記録されているか?
景康時代、巻五十四。それは景康二年二月六日に始まり、辛魏十一月十一日に終わりました。大元帥府は国王を...
「幽霊と神」は中国の歴史にどのような影響を与えているのでしょうか?なぜ「魔術」が権力を掌握する手段となり得るのか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が古代の「魔...
第15章: 雍医師が武智を殺害しようと企み、魯の荘公が前史の戦いで戦う
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
秀雲閣第27章:竜王との戦い連江は復讐のために貝娘ウーゼを募集することに失敗する
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
『紅楼夢』に登場する3杯のお茶にはどんな意味があるのでしょうか?
『紅楼夢』は、章立ての形式をとった古代中国の長編小説であり、中国の四大古典小説の一つです。今日は、お...
李青昭の「永遠の喜び - 夕日が金を溶かす」:祖国への深い思いと過去と現在への感情を表現している
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
東周書紀第28章:李克が独裁者を二度殺害し、穆公が晋の反乱を鎮圧した
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
『山水鎮魔物語』第14章:聖叔母宮の張り子の虎が金山を守り、張鸞が樹井園で梅児と出会う
『山水討魔伝』は、羅貫中が書き、後に馮夢龍が補った、神と魔を扱った小説で、中国の有名な古典小説の一つ...
不潔和尚の妻は誰ですか?僧侶ブジェの妻である口のきけないおばあちゃんの紹介
金庸の小説『微笑矜持』の登場人物。醜いが、武術の腕は抜群。僧侶の不潔の妻で、娘のイーリンがいる。小説...