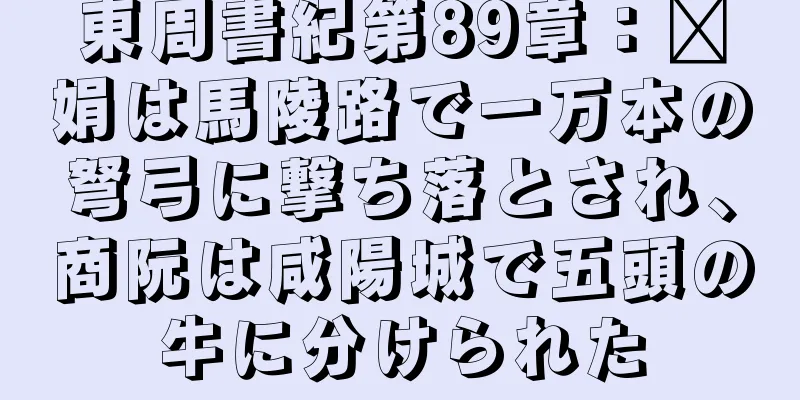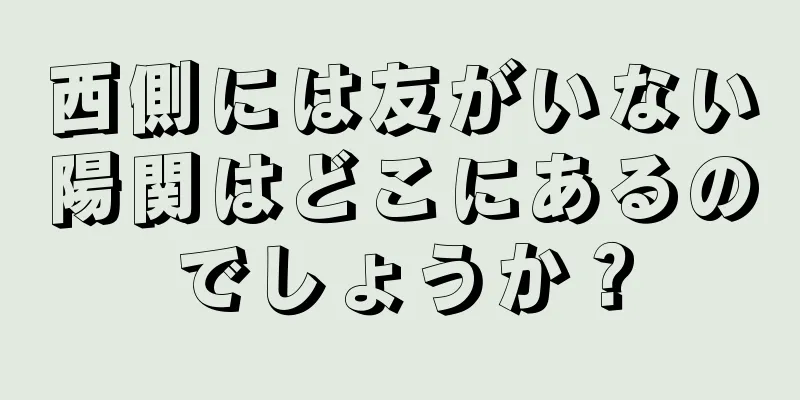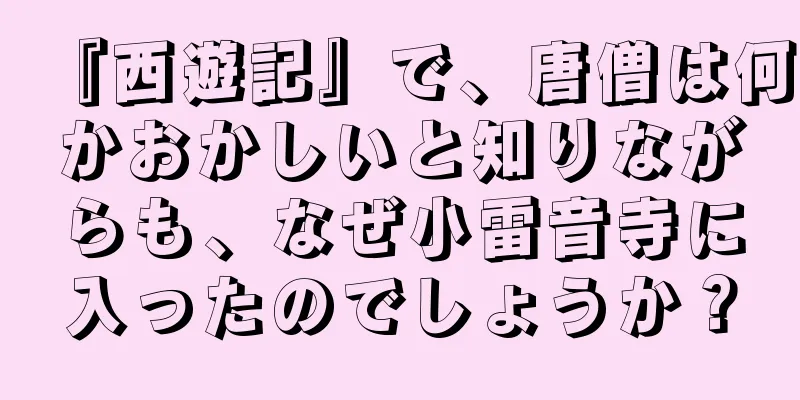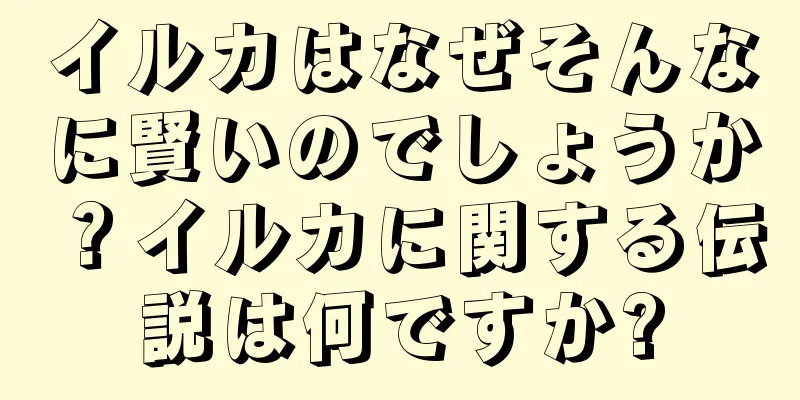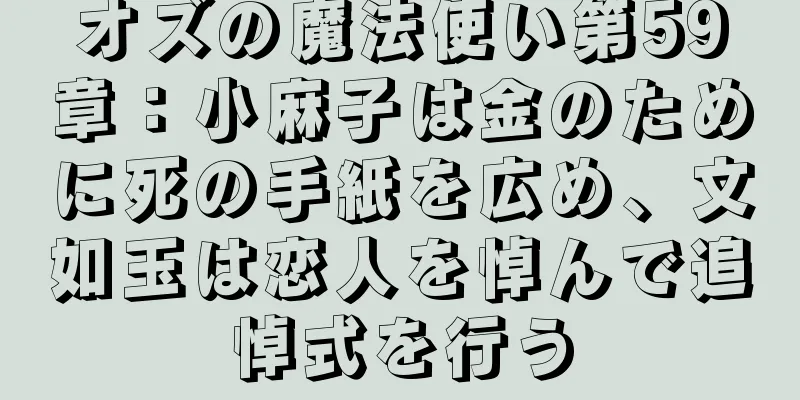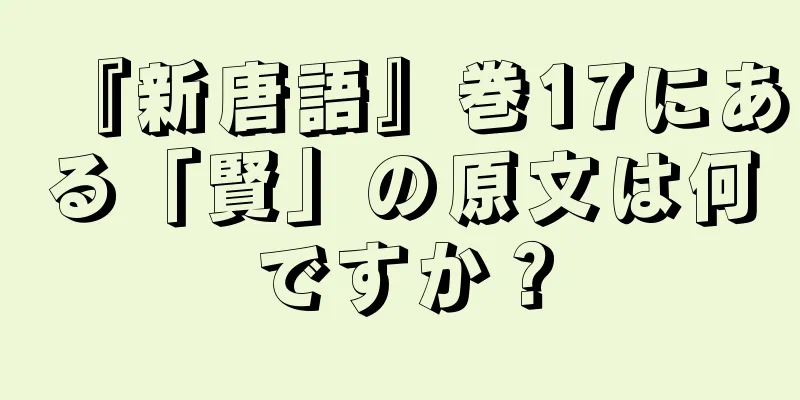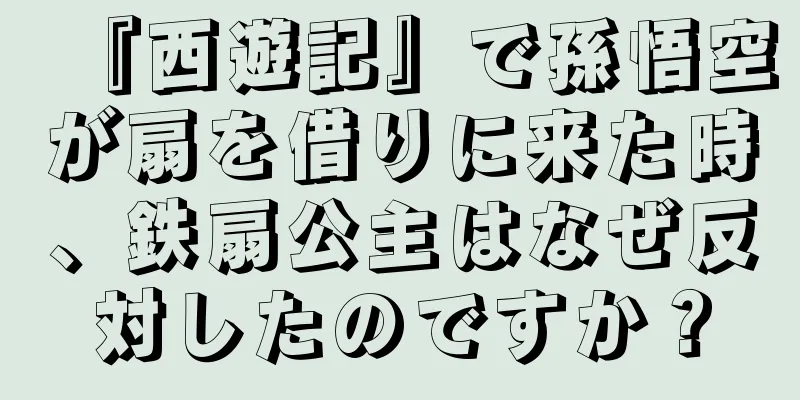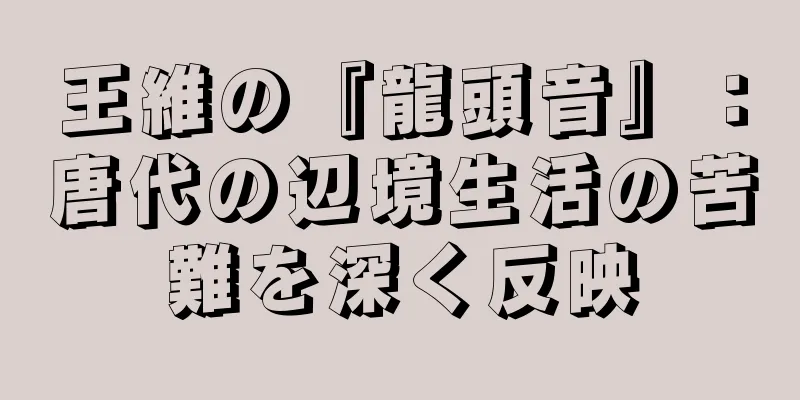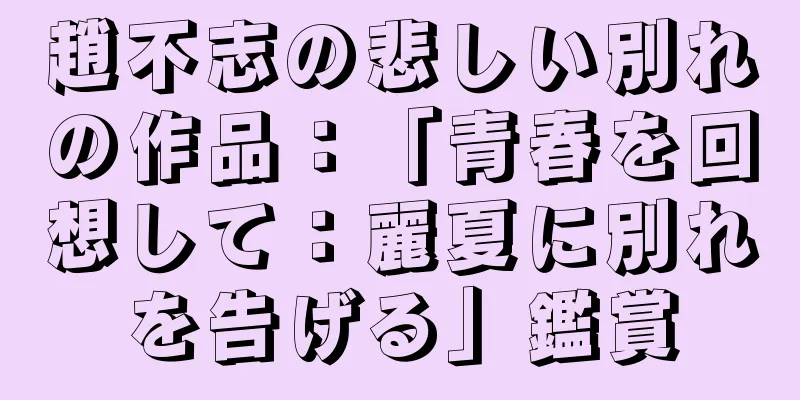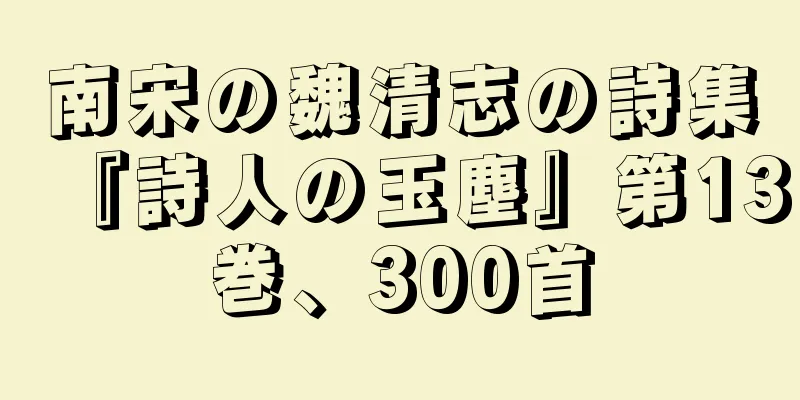宋代における司法制度の確立:犬の首切りでは死刑の見直しは不可能
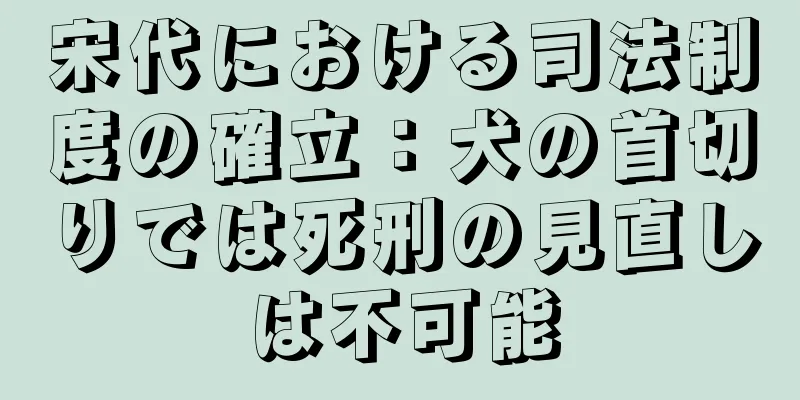
|
宋代のすべての制度設計は、「事件の発生を防ぎ、不正を規制する」(防止の対象には文武両道の役人、王族、さらには君主自身も含まれていた)という一つの原則に従っており、司法制度も例外ではなかった。宋代は裁判官が法律を濫用したり誤った判決を下したりすることを防ぐために、非常に複雑で厳格な裁判手続きを策定した。その「強姦防止」対策の徹底ぶりは、歴代の王朝に例を見ないほどだった。今日でも、この手続きは「煩雑」すぎると思われるかもしれない。ドラマ「鮑法師」を見ると、劇中の鮑法師が裁判の際、非常に注意深く観察していることがわかります。法廷で事件について明確に質問し、「法廷で判決を待ちます」と叫びます。厳格かつ正義感あふれる態度で判決を言い渡した後、再び「虎頭のギロチンが待っています」と叫びます。しかし実際には、そのような尋問と裁判のシナリオは宋代には決して起こらなかったでしょう。もし鮑正が本当にこのように判決を下したならば、それは司法手続きに対する重大な違反となり、彼は処罰されるだろう。 宋代の国家裁判所を例に、当時の刑事裁判の全過程を再現してみましょう。宋代には、各州に西里朝と周朝という 2 つの裁判所が設立されました。2 つの裁判所は並行しており、専任の司法官が配置されていました。刑事事件が公判手続きに入ると、州裁判所は「別件審理・別審理」の司法制度を開始しなければならない。つまり、罪を審理する裁判官(刑務所裁判官)と量刑を判定する裁判官(司法裁判官)は同一人物ではなく、事件に利害関係のない2人でなければならない。宋人は「刑務所の役人が尋問し、司法の役人が検査と裁判を行い、それぞれが独自の責任を持ち、腐敗を防ぐ」と信じていました。 尋問の過程で、裁判官は「告訴に基づいて尋問する」という原則に従う必要がある。『宋代刑法』には、「すべての尋問は告訴に基づいて行われなければならない。告訴以外の罪状を追求する場合は、故意の告発で起訴する」と規定されている。これは、裁判官が尋問する犯罪は起訴状に記載されている罪状に限定されなければならないことを意味する。起訴状に罪状がない場合、裁判官は容疑者を単独で尋問することはできない。そうでなければ、裁判官は「故意の告発」で起訴される。古代では自白が重視され、拷問も許されていた。しかし、宋代には拷問の使用が厳しく制限され、証拠と検査が重視されるようになった。疑いがないことが証明された者には、拷問で自白を引き出す必要はなく、「状況に応じて判断する」ことができた。高齢者、未成年者、障害者、妊婦、出産直後の女性は拷問を受けることは許されなかった。刑罰を執行する際に法律に違反した裁判官は責任を問われることになる。 裁判が終了し、検察と裁判所が量刑を決定する前に、別の裁判官が被告人に質問し、自白を確認する「記録・尋問」の手続きが行われる。取調官が刑務所の取調官と同学年や同校出身であるなど利害関係がある場合には、取調官は忌避しなければなりません。尋問の過程で、事件に誤りがあり、尋問者がそれを発見して訂正できなかった場合、尋問者は処罰されます。訂正できた場合は、報酬が与えられます。尋問が正しければ、事件は「検察・司法」手続きに移送される。裁判官は、取調べで得られた犯罪事実に基づいて適用可能な法令を特定し、判決の法的根拠として上司に提供します。検察側が事件に誤りを発見した場合、裁判官にもそれを訂正する権利がある。 注目すべき点は、尋問、記録、起訴の全過程において、三人の裁判官は独立しており、互いに協議することは許されなかったということだ。宋代の法律では、「尋問官、検察官、尋問官が会った場合、それぞれ80回のむち打ち刑に処せられる」と規定されていた。 検察と裁判所の後の次のステップは判決手続きです。まず、尋問官、検事、検察官以外の裁判官が「判決案」と呼ばれる判決文を起草し、「評決」を行います。これは、現在の「合議制」に似たもので、事件を担当する裁判官全員が共同で評決し、責任を示すために署名するものです。将来、事件の審理に誤りがあったことが判明した場合、署名した裁判官は連帯責任を負うことになります。最後に、州の最高責任者が最終判決を下し、事件を終結させる。規定によれば、判決文は犯罪者に読み上げられ、刑罰を受け入れるかどうか尋ねられなければならない。これは囚人にもう一度控訴する機会を与えることと同じである。 予期せぬ事態がなければ、事件は省レベルの刑事部または中央刑事部に提出され、審査段階に入ることができる。ここでは詳細には触れません。尋問中、判決中、あるいは処刑前であっても、囚人には自白を変える権利があることも付け加えておくべきである。自白が撤回されると、別の裁判官を組織するか(元の裁判官は自ら辞任する)、別の裁判所に移送して(宋代に一国に二つの裁判所を設けた意義が反映されている)、手続き通りに全てを繰り返さなければならない。これを「翻訳と検証」と呼びます。宋代の法律では、囚人は「再審・再検査」を受ける機会が3回と定められていた。南宋代には5回に変更されたが、実際には法定回数の制限を超え、何度も再審・再検査を受けるケースもあった。孝宗の春熙年間、南康軍にアリアンという女性がいた。彼女は共謀して夫を殺害した罪で告発され、斬首刑の判決を受けた。しかし、アリアンは「考えを変え、10人の官吏に尋問された」。彼女は10回近く考えを変えた。裁判は9年続いたが、アリアンは判決を受け入れなかった。最終的に、裁判官は「疑わしい罪は最も軽い刑罰で処罰すべき」という原則に基づいて、アリアンの命を助けた。 公平に言えば、宋代の厳格な司法手続きも今日の観点から注目に値する。もちろん、どんなに厳格な制度でも実際の運用においては妥協の余地があることは否定できない(そうでなければ冤罪は起きない)が、この制度の背後にある「事件を未然に防ぎ、紆余曲折にルールを作ろう」という立法精神と「無実の人間を放っておくよりは殺した方がまし」という司法原則は、明らかに評価に値する。 |
<<: 歴史書では学べない14の事実!全ての宦官が去勢されるわけではない。
>>: 梁暁民インタビュー:かつて繁栄していた清朝の塩商はなぜ衰退したのか?
推薦する
易経の卦「上は火、下は沼、卦」とはどういう意味ですか?
易経の卦「上は火、下は沼、卦」とはどういう意味ですか?卦です。小さなことは縁起が良い。意味は「奎瓜、...
陳平の物語とは何ですか?陳平の逸話は何ですか?
陳平(紀元前178年?-)は漢人で、楊武市虎幽郷(現在の河南省元陽市)の出身で、前漢の建国の英雄の一...
古代人はなぜ同じ姓を持つ人々との結婚を禁じたのでしょうか?同じ姓の人が結婚しない理由を説明してください
「同姓同名同士の結婚禁止」とは、同姓の男性と女性同士が結婚できないことを意味します。秦以前の時代から...
劉秀は伝説の男です。彼はどのようにして真実の愛を追い求めたのでしょうか?
東漢の始皇帝である劉秀は伝説的な人物でした。彼は軍事戦略に長けており、敵が彼を過小評価するほどハンサ...
宋代は違法建築の問題をどのように解決したのでしょうか?宋代にも違法建築があった
唐代の長安から北宋代の開封まで、中国の大都市は市場前システムから街路レベルの市場システムへと進化しま...
宋江の個人的なボディーガードは李逵ではなく、別の人物だった。
ご存知の通り、宋江は『水滸伝』の108人の英雄の中でトップの英雄です。主人公の李逵は彼の最初の刺客と...
武則天の死後、なぜ武三思は李唐王家によって粛清されなかったのか?
武則天について語るとき、武則天の甥である武三思について触れなければなりません。ご存知の通り、武則天の...
『紅楼夢』で大観園に大混乱を巻き起こした英児はどれほど陰謀を企んでいたのか?
「主君と召使は似たり寄ったり」ということわざにあるように、「紅楼夢」で大観園で大混乱を引き起こした英...
第96章: 演劇での演技
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
「都使を迎える」をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
北京への特使岑神(唐代)故郷の東の方を眺めると、その道は長く、袖は涙で濡れている。私たちは馬上で会い...
羅貫中の『三国志演義』には架空の要素が含まれていますか?
陳寿の『三国志』は曹操、劉備、関羽、諸葛亮など三国時代の人物の非常に生き生きとした伝記を記しているが...
後唐代第25章:白宝が巧みに龍門陣を組み、唐の皇帝が英雄的な戦士たちを賞賛する
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、『唐物語』と略され、『唐代前編』、『唐代物語』、『唐代全物語...
那藍星徳の「臨江仙・絹のような雨、水面の塵雲のよう」:私の心は悲しみで満たされ、すべての文章が私を悲しくさせる
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
宋代の于国宝の詩「松風、春は花を買って過ごした」をどのように評価すべきでしょうか?
馮如宋・易春張飛が花を買う、宋代于国宝、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見...
「女仙の非公式歴史」第86章:ヤオ師匠の邪悪な計画は完全に砲撃に依存しており、レイ将軍の神力はすぐに雲の旗を表示します
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...