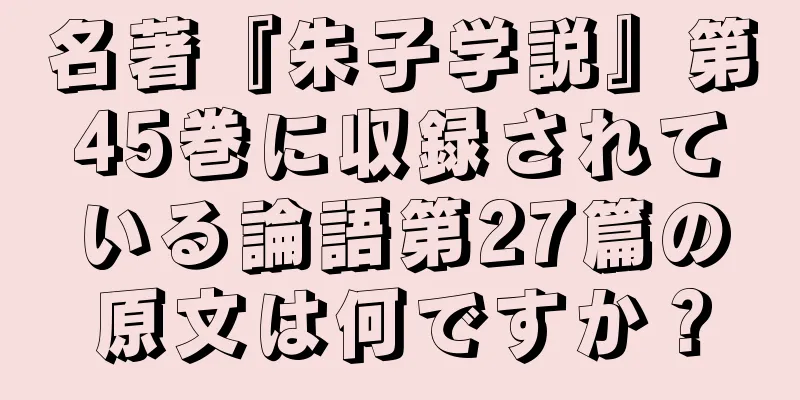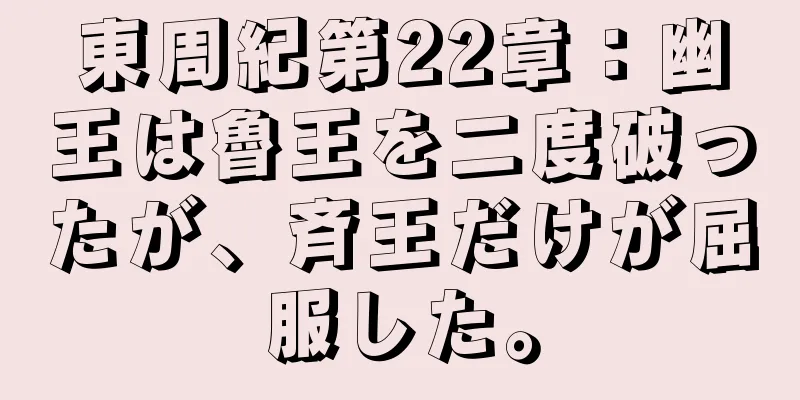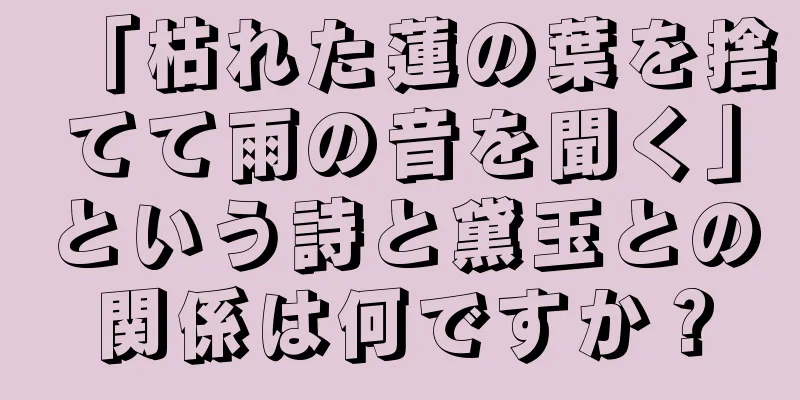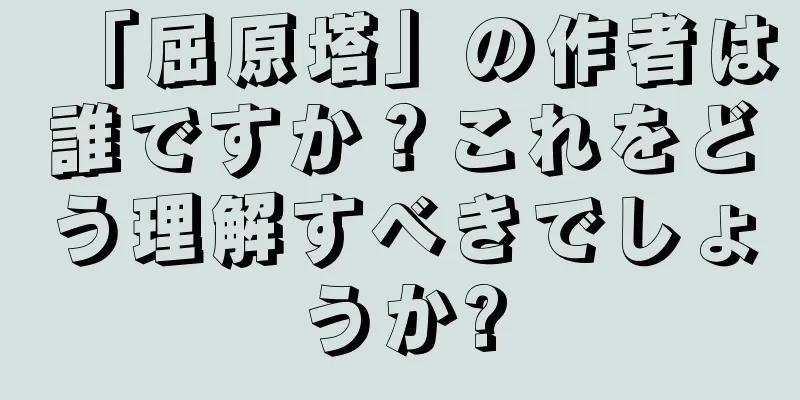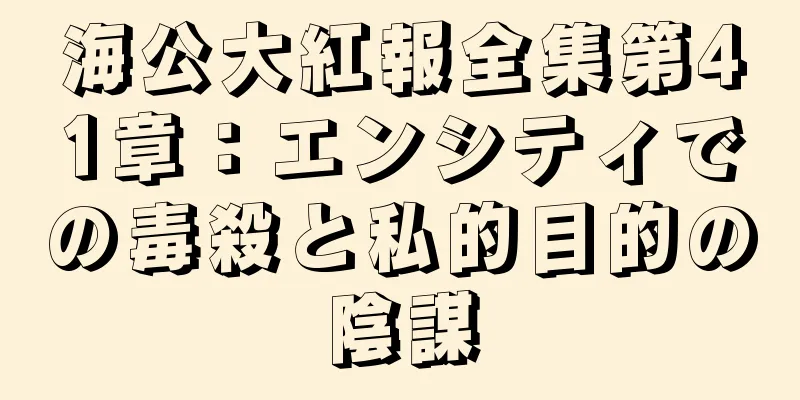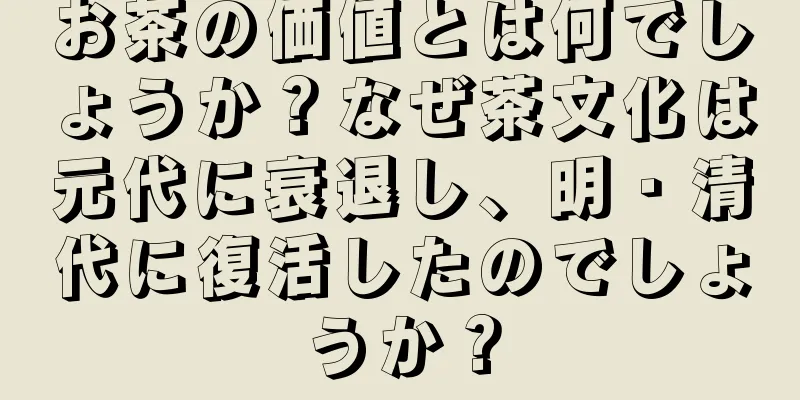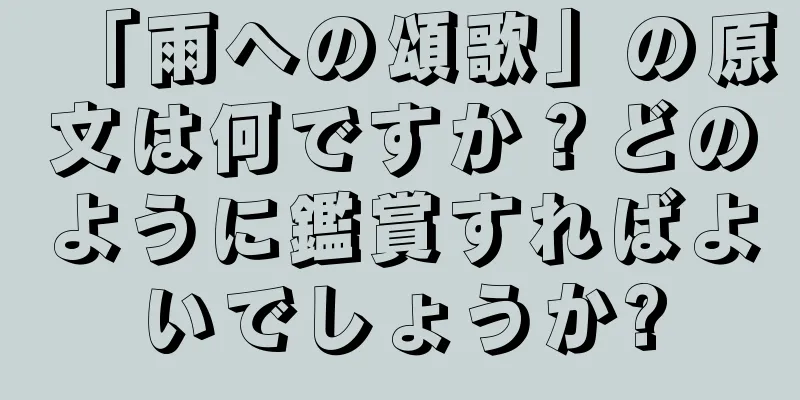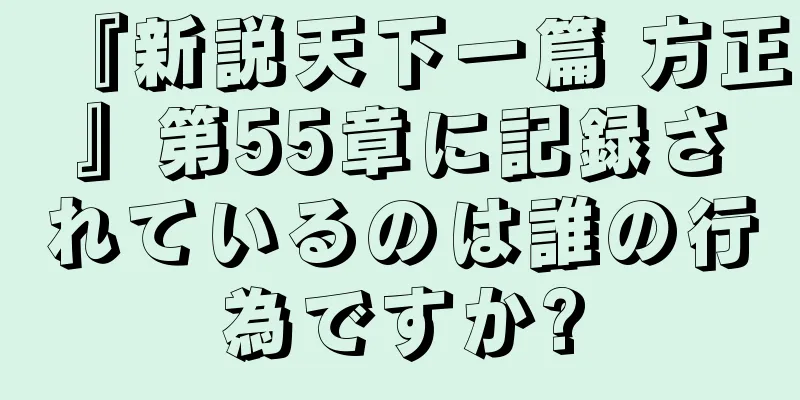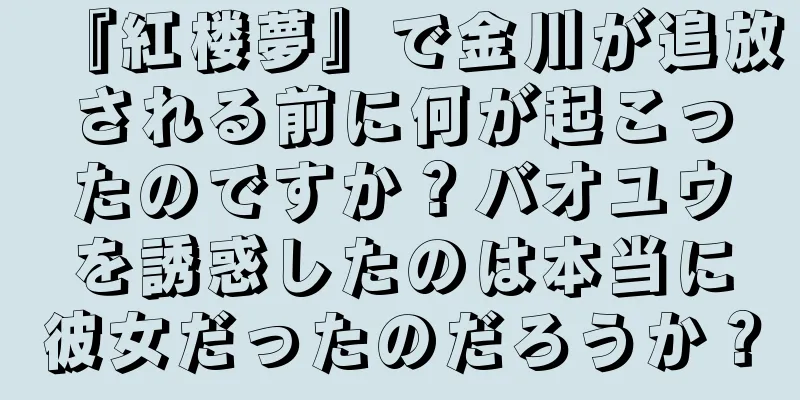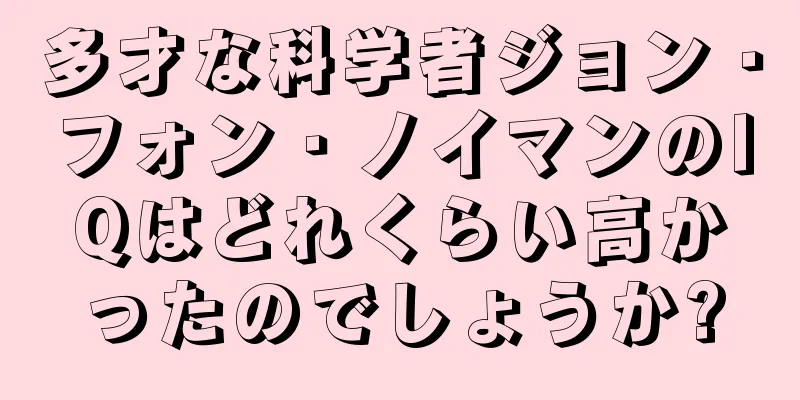前漢時代の有名な官僚である公孫洪の貢献は何ですか?
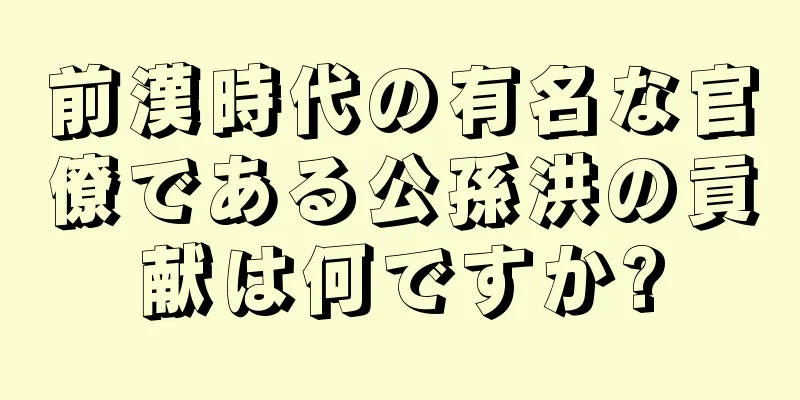
|
公孫洪(紀元前200年 - 紀元前121年)は、本名は洪、字は季、別名は慈青(『西京雑録』に記録)で、斉の淄川(現在の山東省寿光市南鶏台郷)の出身で、前漢時代の著名な官僚である。 彼は若い頃、役人として働き、海で豚を飼っていました。40歳になると、勉強を始め、継母の世話をしました。漢の武帝の治世中に、彼は中国国民の推薦を受けて二度医師として採用された。 10年のうちに、彼は金馬門の侍官から三公の長に昇進し、平金侯の爵位を授けられた。左内氏(左豊義)、于氏大夫、宰相を歴任した。漢の武帝の治世中の元寿2年(紀元前121年)、公孫洪は宰相の地位のまま亡くなり、衙侯に諡された。 公孫洪は前漢の建国以来、宰相として侯爵を賜った最初の人物であり、前漢における「宰相として侯爵を賜る」という慣例の先例となった。彼は在任中、優秀な人材を採用し、民生に配慮し、儒教の振興にかけがえのない貢献を果たした。彼はかつて『公孫洪』という十篇の論文を書いたが、現在は失われている。 公孫洪氏の主な業績は何ですか? 折り畳み理論 公孫洪は公陽の学者であった。彼は自身の理論的な著作を残していないが、彼の思想は主に『善人論』に反映されている。 公孫洪の最高の哲学的範疇は「調和」である。公孫洪は、どんな二つのものも相反しながらも統一されており、統一の根底は「調和」であると信じていました。社会や政治の分野では、統治者と人民は対立する二つの階級ですが、統治者が「和諧徳」であれば、人民も「和諧」し、世界に平和の調和した状況が実現します。社会の場にいる個人にとって、心と気、気と形、形と音はすべて互いに相反しますが、「心の調和」は「気の調和」につながり、「気の調和」は「形の調和」につながり、「形の調和」は「音の調和」につながります。同時に、公孫洪は、この対立と統一の関係を通じて人と天地を結びつけ、「音が調和すれば、天地の調和も応じる」という結論に達し、「人と自然の調和」という最高の境地を達成した。公孫洪は、「和」は社会だけでなく、自然界にも存在すると信じていました。「したがって、陰陽が調和しているとき、風雨は季節を迎え、甘い露が降り、穀物は収穫され、家畜は豊かに育ち、作物は繁茂し、赤い草が生え、山は不毛ではなく、湖は干上がっていない。これが究極の和である。」自然と人間社会において「和」が重要な役割を果たしているため、統治者はそれを最高の政治理想と見なすべきです。公孫洪は、君主が「和」を掴むことによってのみ、「ユニコーンや鳳凰が現れ、郊外に亀や龍が現れ、黄河に地図が現れ、洛河に書物が現れ、遠くの王たちが皆、正義を称えて敬意を表す」ようになり、平和と繁栄の状況を作り出すことができると信じていました。 公孫洪は「和」という哲学の範疇から出発し、漢の武帝の政治に応えて、国を治め、民の安全を確保するための8つの命題を提唱した。この八つの命題は、実は二つの問題について語っている。第一に、国は倹約し、税金や賦課を軽くし、人民の力を大切にし、人民のために良好な生産と生活条件を作り出すべきである。第二に、朝廷は職務に応じて人を任命し、功績に基づいて人を任命し、賞罰を明確に区別して、官吏が責任を果たし、人民が才能を最大限に生かせるようにすべきである。 公孫洪は、君主が国を治めるには、まず人民を納得させなければならないと信じていた。君主が「学識があり」、「理性的」、「礼儀正しく」、「愛情深い」場合にのみ、人民は「争わず」、「不満を言わず」、「暴力を振るわず」、「君主に親しく」なれる。これは、公孫洪の「和」における「君主」と「人民」の矛盾と統一の関係を具体的に詳述したものである。公孫洪はここで礼と義の重要性を強調し、「礼と義は民衆が従うものである」と信じていました。同時に、礼と義だけでは十分ではなく、賞罰も明確でなければなりません。「意志に従って賞罰する」ことによってのみ、「民衆は法律に違反しない」ことができます。公孫洪は礼と義を刑法と結びつけ、「法は義から遠くない」、「和は礼から遠くない」という結論に達した。 公孫洪の思想には、「能力に応じて官吏を任命する」、法律と道徳を融合させる、賞罰を明確に区別するなど、多くの法家的要素が浸透していた。しかし、公孫洪は単なる法家とは大きく異なります。仁義を否定した韓非とは異なり、彼は仁義を肯定し、徳政を重視した。彼は「天の徳は公平で、すべての人に優しい。それに従えば和が生まれ、それに逆らえば害が生じる」と信じていた。これは典型的な儒教の思想である。この観点から見ると、公孫洪は純粋な儒学者でも純粋な法家でもなかったが、両者を巧みに融合させた人物であった。 政治を折りたたむ 公孫洪は国境問題に関しては保守的な傾向があった。建元の時代に匈奴に初めて外交使節として赴いたとき、彼の言葉は漢の武帝の意に沿わなかった。また、元光の時代に西南に外交使節として赴いた後、西南夷の開拓事業に反対し、滄海、碩放、婺源の各県の設置に反対した。公孫洪は、常に辺境地域の人々の苦しみを第一に考えた。彼は漢の武帝に国境地帯の建設工事をやめるよう何度も進言した。武帝は常に反対したが、公孫洪は決して諦めなかった。元碩三年、検閲官に昇進したばかりの公孫洪は、再び武帝に西南、滄海、朔方、婺源の建設を中止するよう提案した。朱麦塵に反駁された後も、公孫洪は諦めず、一歩下がって朔方県の建設を支持すると表明したが、依然として西南夷県と滄海県の建設を中止するよう要求した。武帝は同意した。 公孫洪は、残酷な役人は残酷すぎると考え、もし彼らが郡知事に任命されれば、きっと民を残酷に扱うだろうと考えました。そのため、彼は漢の武帝が残忍な官僚である寧成を郡守に昇進させたことに反対した。 恩赦前には、遍歴の騎士郭傑は多くの殺人を犯した。後に状況は変わったものの、郭傑の信奉者たちは郭傑に敬意を欠いたため、依然として人を殺害した。当時の法律によれば、郭傑は起訴されずに釈放されるべきであったが、公孫洪は郭傑の罪は大逆罪であり、処刑されるべきだと進言した。東漢の荀岳は、騎士たちが民衆を威圧し、自らの権力を培っていると信じていた。騎士たちは道徳に違反し、法律を破壊し、社会不安を引き起こしていた。 儒教への貢献 漢の武帝の治世中の元碩5年(紀元前124年)、公孫洪は「五経博士」の弟子を設立するための措置を提案・起草し、儒教の経典と礼道徳に基づいて現職官吏の昇進方法と任命条件を制定した。内容は大まかに以下の4点にまとめられます。 1. 「三代の道」を守り、天下の「教育」を実現することを使命とする。まず中央官庁の学校をしっかり運営し、次に地方に普及させる。 2. 各博士官は50人の正式な弟子を持つものと規定される。礼部は、18歳以上で礼儀正しい者を博士課程の学生として選抜し、彼らに課せられた国家賦役と税金を免除した。 3. 「弟子のように指導を受ける」監査人を確立する。 「文学に優れ、年長者を敬い、政治や教育に厳格で、郷の人々に従順で、やる事もやらない事も正直である」優秀な若者を県、郡、鎮が推薦し、郡守と宰相の審査を経て礼部に報告し、監査役となる。監査員の定員はありません。 4. 定期的な評価と予約システム。一年後に試験が行われることが規定されており、一つ以上の古典を習得した者は文学と歴史の空席を埋めるために任命され、特に優秀な者は博士になることができた。知能が低い者や古典を習得できない者は学校から退学させられる。 儒教の経典や礼節に基づく昇進方法や任用条件は、主に「一芸(経典)以上に精通していること」「多くの条文を暗唱できること」を基準としており、位の高い者は左右内史や太行祖師に任用され、位の低い者は郡奉行祖師や辺郡奉行祖師に任用された。 |
<<: 前漢の有名な官僚、公孫洪の略歴 公孫洪はどのようにして亡くなったのでしょうか?
>>: 白馬公崔紅とは誰ですか?彼の息子である崔浩はどのような先駆的な仕事をしたのでしょうか?
推薦する
中国学史原典の鑑賞:『東経夢花録』第2巻
ロイヤルストリート方郷皇道は宣徳塔から南に伸び、幅は約200段で、両側に皇道の廊下があります。昔はそ...
『紅楼夢』で紫娟が宝玉の愛を試した後、薛叔母さんはなぜ小湘閣に行ったのですか?
『紅楼夢』では、バオ、ダイ、チャイの関係が常に注目の的でした。これについて言えば、皆さんも聞いたこと...
高翠蘭と朱八戒の関係は何ですか?彼女の結末は?
朱八戒は四師弟の中でも好色な男であることは誰もが知っています。彼は嫦娥を虐待したため、天宮の人間界に...
古代中国のトップ 10 の遺物: 東皇鐘の用途は何ですか?
東煌鐘の用途は何ですか:東煌鐘は天国への門であり、その所在は不明であり、その力は不明です。一般的には...
『東周記』第48章
冀政夫、史固、梁易允は協議し、秦軍の攻撃を待ち、趙惇に代わる反乱を起こすことを決めたと伝えられている...
賈宝玉の結婚に関しては、なぜ林黛玉ではないのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
武夷山はなぜ道教の聖地と呼ばれているのでしょうか?武夷山と道教の歴史的なつながりは何ですか?
武夷山はなぜ道教の聖地と呼ばれているのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見て...
中国史上最も有名な4人の反乱将軍の詳細な解説
1. 英布まず、英布についてお話しましょう。英布は秦後漢の有名な将軍です。秦の法律に従って入れ墨をし...
漢代の学者による『馬車返して進軍する』の原文、翻訳、鑑賞
「戦車を戻して前進せよ。」次回はInteresting History編集長が関連コンテンツを詳しく...
「竹石図」は清朝の鄭謝によって書かれたもので、竹の粘り強さを描写している。
鄭板橋は、本名を鄭謝、字は科柔、号は連安、板橋、通称板橋先生と呼ばれ、清代の書家、画家、作家で、文学...
さまざまな王朝における枯れた蓮についての詩は何ですか?詩人はどんな場面を描写しているのでしょうか?
どの王朝にも枯れた蓮を題材にした詩は数多くあります。次の『Interesting History』編...
山菜と龍娘の古代民話。山菜と龍娘はどのようにして出会ったのでしょうか?
観音菩薩の横には男女のペアがいるのをよく見かけますが、その名前を知っている人はほとんどいません。実際...
「水蓮花:春が満ち、柱が水位を増す」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
迪連花·春が満ち、水面が増す范成大(宋代)春になると水位が上昇します。風が吹く岸辺には、香り高い草や...
唐代の蘭陵公主の紹介:蘭陵公主李叔は歴史上どのような人物だったのでしょうか?
新世代監督の孫凱凱が監督し、張俊漢、尹旭、丁元浩、詹静怡、張玉曦が主演する全40話のオンラインドラマ...
第30章:孟銀鸞はシンバルを使って兜を掴み、焦将軍は鞭を使って敵を捕らえる
『海公小紅謠全伝』は、清代の李春芳が著した伝記である。『海公大紅謠全伝』の続編であり、海睿の晩年72...