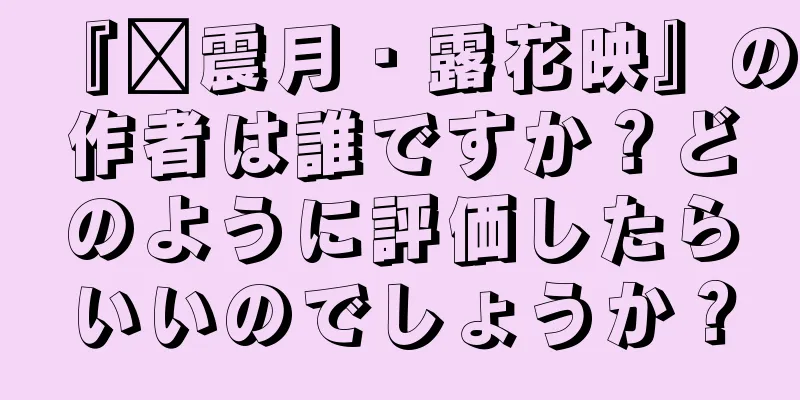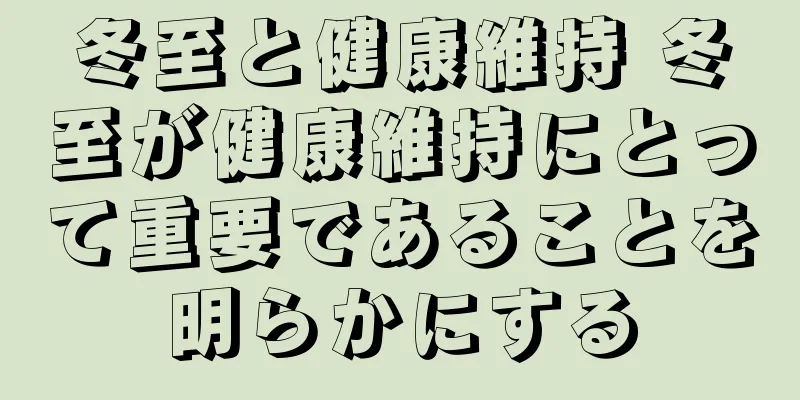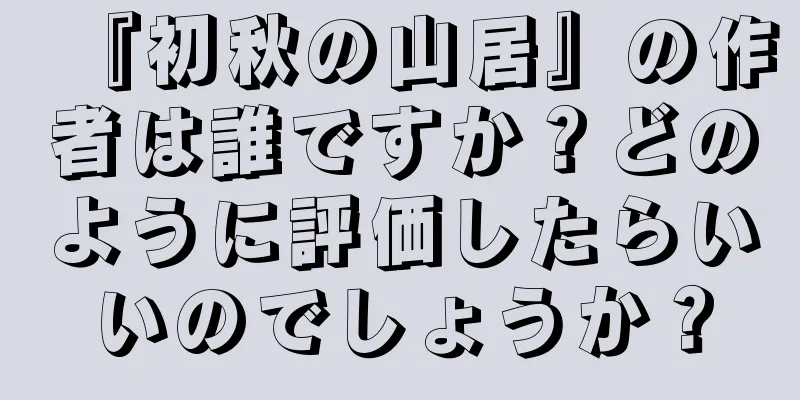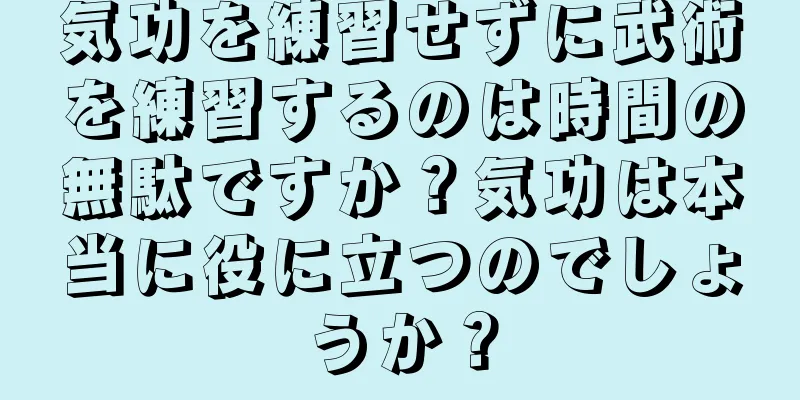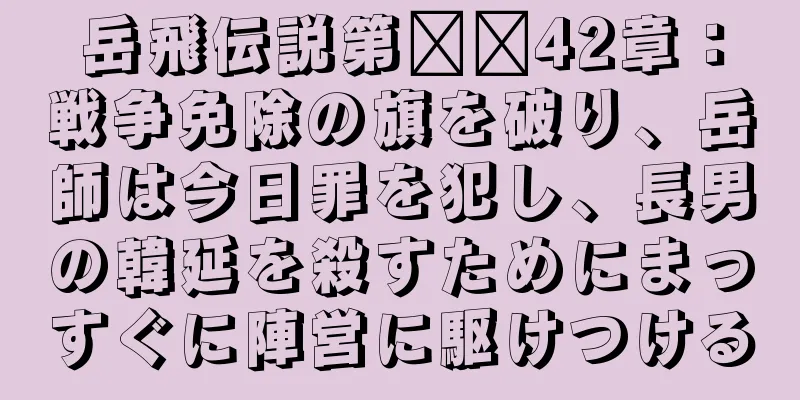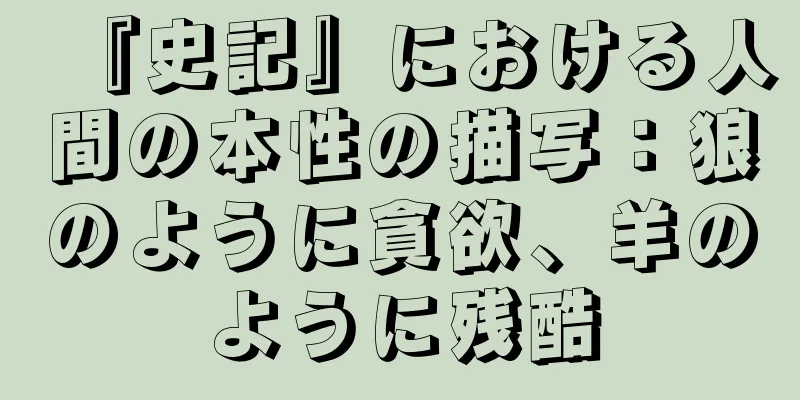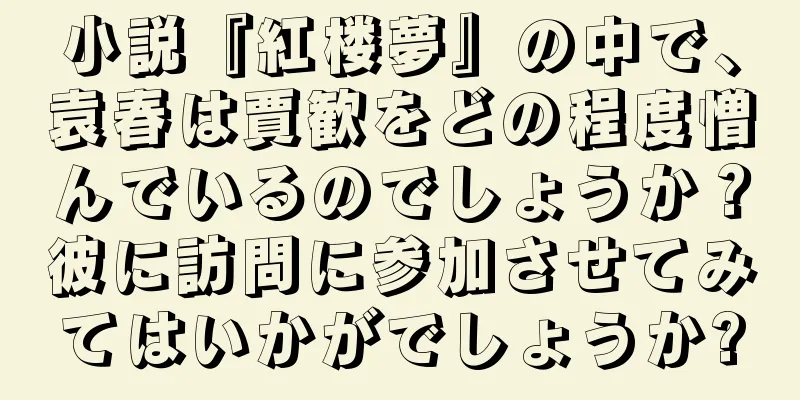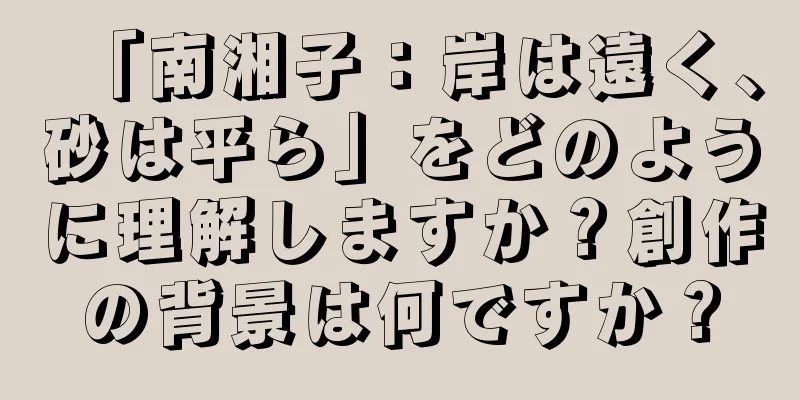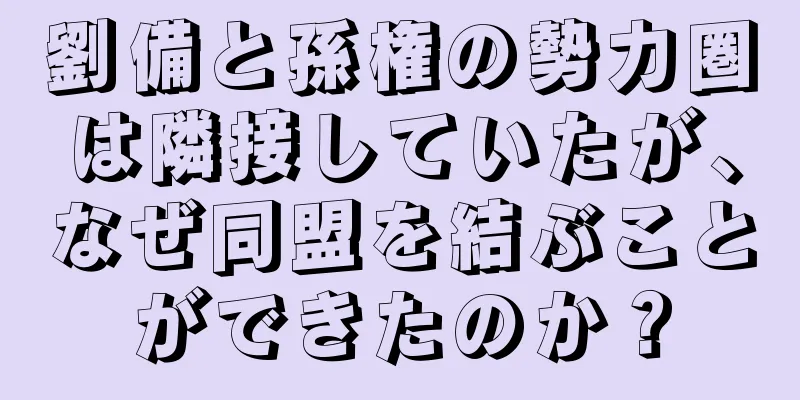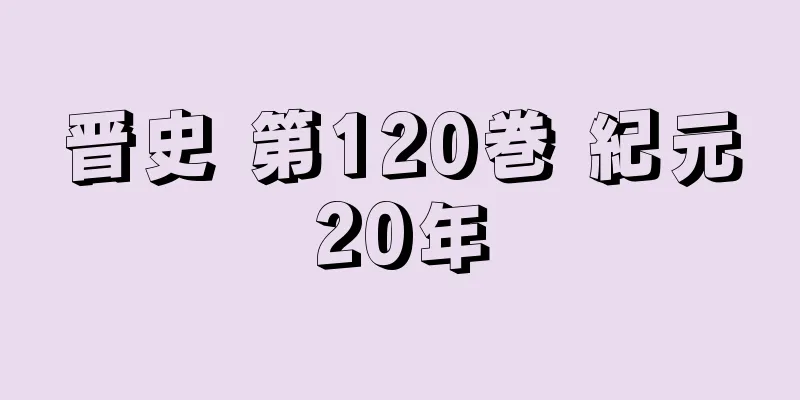「溥儀紛争」とは何だったのか? 「溥儀紛争」の具体的な経緯はどのようなものだったのでしょうか?
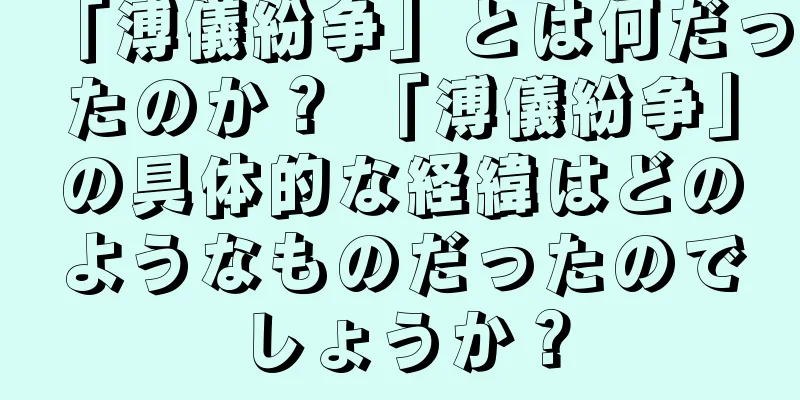
|
本日は、Interesting Historyの編集者が「溥儀紛争」について紹介し、皆様のお役に立てれば幸いです。 溥儀紛争は、北宋の英宗皇帝の治世中に起きた政治的事件であり、彼の実父である溥親王の趙雲朗が「親戚」と呼べるかどうかをめぐって起こった。皇帝、宮廷の役人、皇太后らが関与した。宋英宗の短い5年間の治世の間、普論は基本的にずっと続いた。それは英宗皇帝の治世中に大きな騒動を引き起こしただけでなく、後世にも大きな影響を与えました。溥儀に関する歴史的議論は複雑ですが、一般的に言えば、それは主に礼儀作法、法律、政治に関する考慮に基づいています。 宋英宗が即位した当初は権力が十分に集中していなかったため、宰相や普論を利用して「異論を妨害する」政策を実行した。溥儀発言後、朝廷の元々の権力構造は完全に崩壊し、多くの元大臣が首都から追放され、専制的な皇帝の権力は大幅に強化されました。英宗以来、宋代の皇帝の権力は文人によってますます制限されなくなりました。 母親の疑惑と息子の恐怖による皇帝と皇后の争い 嘉祐8年(1063年)3月、宋仁宗は「扶寧宮で急死」し、養子の趙叔が曹太后、すなわち宋英宗の援助を受けて無事に王位を継承した。本来は円満であるはずの母子関係は、宋英宗と太后の仲が悪かったこと、後代の宦官の扇動、太后の権力の譲り渡しを嫌がったこと、そして普論などの一連の出来事により、絶え間ない摩擦に悩まされた。 · 天皇と皇后の不和が紛争の種をまいた 英宗は養子であり、幼少期は宮中に迎えられ後宮で育てられたが、宋仁宗や曹太后との関係は実は親密ではなかった。一方、宋仁宗は実子が帝位を継承することを常に望んでいた。そのため、宋仁宗が病に倒れた後、宮廷の大臣たちは国家の安定を確保するためにできるだけ早く後継者を立てるよう何度も要請したが、その要請は却下された。韓起はまた、内廷に学校を建て、皇族の中から誠実で勉強熱心な者を選抜して入学させることを要求し、「これによって皇帝を動かし、後継者をできるだけ早く任命すべきだと示唆する機会を得たい」とした。しかし、宋仁宗は「後宮の側室の1人か2人が学校に入学するだろう」という理由でその要求を断った。 そのため、宋英宗は幼い頃に後宮で育てられたにもかかわらず、宋仁宗は彼にあまり注意を払わず、宋仁宗と親しい関係にはなかった。嘉祐7年(1062年)8月4日、宋英宗は初めて皇太子に立てられ、「紫禁城に召し出されました。当時、先帝は周囲の裏切り者たちに中傷され、少し混乱していました。宮殿の内外の人々、陛下の旧居の親族でさえ、誰一人として彼に手紙を書いて事情を尋ねる勇気はありませんでした。」この時点では宋仁宗の彼に対する態度はまだ非常に冷たく、周囲の裏切り者たちから英宗への批判を許し、食事さえも保証されなかったことがわかります。宋仁宗の支援がなければ、曹皇后は公然と援助する勇気はなく、ひそかに食料を送ることしかできなかった。 当時、宋英宗は隔離された宮殿で一人暮らしをしており、困難な状況にあったことが伺え、それが後に皇帝と皇后の対立の種を蒔くことにもなった。さらに、英宗は子供の頃から宮殿で育てられていたが、王位継承者の唯一の候補者ではなかった。英宗が仁宗の氏族長任命を固く拒否すると、貴族たちは燕元燕王の息子である雲初を推薦した。 「張仙はかつて夢の中で周の有公子が来て、景王の宮殿で生まれ変わると告げたと語りました。雲はちょうどその時生まれたばかりでした。」そのため、彼女は太后に愛され、宮殿で育てられ、成長するまで解放されませんでした。そこで、仁宗は言った。「宮殿には二人の息子がいた。弟はとても清純だったが、あまり賢くなかった。兄はまあまあだった。」賢くない方が雲初で、兄が英宗だった。 両宮殿の関係は、剣を抜く寸前まで来ている 将来に対するこの不確実性は、権力者が弱者を優遇する宮殿で宋英宗が前進することを困難にしました。このような状況下では、彼は当然、仁宗皇帝や曹皇后と親しい関係にはなく、むしろ実の両親と親しい関係にあっただろう。これはまた、後に溥儀が「親戚」を主張する根拠となった。宋英宗は即位後すぐに病にかかり、最初は「人のことがわからず、言葉も支離滅裂」となり、医者を呼んで治療を求めた。その後、「皇帝の病状は悪化し、泣き叫び、歩き方がおかしくなり、祭祀を行うこともできなくなった」ため、国政を執り行うことができなくなった。そこで朝廷の役人たちは皇太后に、後宮の東門にある小広間の幕の後ろに座り、同じ権限でこの件を処理するよう要請した。 嘉祐8年(1063年)6月、「皇帝の病気は回復したが、まだ正宮に入っていなかった」。大臣たちは何度も皇太后に権力を放棄して政務に参加するよう要請したが、皇太后は長い間権力を放棄することを拒否し、両宮殿の関係は次第に緊張していった。 「皇帝は当初、心配と疑念から病気になり、いつもと違う行動をとることもあった。特に宦官に対して冷淡だった」ため、周囲の人々は非常に不満を抱いた。英宗が重病にかかったとき、彼は不適切な言動で皇太后を怒らせることがよくあった。周囲の人々はその機会を利用して皇太后に英宗を廃位するよう進言した。例えば、内官の任守忠は裏切り者で、何度も両宮を偵察していた。この時点で、両宮殿の関係はほぼ争い寸前の状態に達していた。 宋英宗:皇太后は私に対して慈悲を持っていない 宋応宗はかつて韓奇らにこう言った。「太后は私に対して慈悲を持っていない。」大臣たちは舜の偉大な孝行を説いてこう言った。「親が慈しみ、子が孝行するのは普通のことで、言うまでもない。親が慈しみを示さなくても子が孝行している場合にのみ、称賛に値する。」それ以来、皇帝は皇太后の欠点について語ることはなくなった。大臣たちの仲介により、天皇と皇后の関係は徐々に緩和されていった。治平元年(1064年)5月、皇太后は「皇帝に権力を返上する書状を書いた」ため、国政を執り行わなくなった。この時点では、二つの宮殿はそれぞれ自分の地位を占め、自分の事柄を管理しており、表面上はすべて平和に見えました。 · 溥儀事件が勃発するまで、平和な状況は再び崩れた 治平元年(1064年)5月、宰相の韓奇らがこの案を初めて提案し、英宗皇帝は「盛大な儀式を行ってから議論しなければならない」と命じた。治平2年(1065年)4月の夏、皇帝は祭官と副大臣以上の者に、再び普安王の祭祀について協議するよう命じた。朝廷の役人たちは自分たちの利益のために激しく議論し、しばらくの間、正しい作法を決めるのが困難でした。これを聞いた皇太后は、皇帝に挨拶できなかった韓奇らを非難する手紙を書いた。英宗皇帝は皇太后の直筆の勅書を見て恐怖し、「直ちに直筆の勅書を発して議論を中止し、追悼の儀式も中止した」。そして「官吏に歴史上の言及を探し、儀式の経典に沿っているか確認するよう命じた」。 この時点ですでに英宗皇帝が権力を握っていたにもかかわらず、曹太后に対する恐怖心は依然として残っていたことがわかります。これはまた、当時、曹太后がまだ朝廷で強い影響力を持っていた一方で、英宗皇帝の皇帝権力が比較的弱かったことを示しています。そのため、溥儀の乱の最初の対決は英宗の妥協によって一時的に終結した。しかし、普王を祀るかどうかの議論は長い間決着がつかず、朝廷内の大臣の二派、宰相と検閲官がそれぞれの理由で言い争っていた。治平3年(1066年)正月に曹太后からのもう一つの直筆の手紙が届き、ようやくこの長く議論の的となっていた事件に大きな転機が訪れた。 曹太后 曹太后は言った。「私は歴史書をもう一度読んで、こんな話があることを知りました。皇帝は溥安王、喬王妃、湘韓妃、仙游郡の任妃を親戚として呼び、溥安王を溥安皇帝と称し、喬、湘、仙游を皇后と呼ぶでしょう。」曹太后の態度は急激に変わり、朝廷はしばらく恐れおののいた。彼がなぜそのような大きな譲歩をしたのかについては歴史書の中で多くの推測がなされているが、明確な記録はない。呂徽らは「韓起は宦官の蘇烈社、高居堅と共謀し、皇太后を欺いて自筆の降伏文書を送った」と主張した。 皇太后の譲歩は、この頃、英宗の皇帝権力が以前に比べて大幅に集中していたことを反映している。英宗はもはや曹皇后の権力を恐れていなかったため、溥儀における両宮の二度目の対決は英宗の勝利に終わった。英宗皇帝と曹太后の権力闘争は、普縁の最終決着により終結した。英宗は曹太后の支援を受けて帝位に就いたが、即位後すぐに過度の心配から病にかかり、曹太后はその隙をついて裏で国を治めた。 このような背景から、曹皇后の宮廷における威信は非常に強かったのに対し、英宗皇帝の威信は比較的弱かった。さらに、2つの宮殿の関係は調和的ではなく、常に対立が起こっています。溥儀の乱が勃発して初めて、英宗は、この争いを利用して曹操皇后の宮廷における権力を攻撃し、自らの権力を培い、名声を確立しようと努めた。皇帝と皇后の間のこの闘争は英宗の勝利で終わった。 英宗皇帝が即位して以来、朝廷内には溥儀事件を中心とした暗黒の渦が流れていた。皇帝と皇后の争いに加え、大臣たちも礼儀を武器に、皇帝の親戚を主張する派と皇帝の叔父を主張する派に分かれ、自らの考えを実現するために絶えず争いました。 · 検閲官と統治者 その中で、司馬光率いる太極派は、道徳の観点から「社会階層の維持における礼儀の実際的意義」を強調し、専制皇帝権力の正統性を維持するという目的を達成し、司馬光を皇帝の叔父と呼ぶことを提唱した。韓奇、欧陽秀らが率いる首相グループは、人情の観点から「礼儀作法の人間性を強調する」ことを始め、親族を親族として呼ぶことを提唱した。司馬光は、普王と祭祀について議論するずっと前、嘉祐8年(1063年)4月27日にこう言っていた。「祭祀は後世の人々やその子孫のために行うものである。したがって、人は何を奉っているかに集中すべきであり、個人的な利益を考慮に入れるべきではない。」 この碑文の中で、司馬光は、嬴宗が仁宗の養子として、小氏族の子から長氏族の子孫になったことを道徳の観点から論じました。身分的には最年長の氏族が若い氏族よりも尊敬されるため、喪制度では自分の親の喪期間は1年だけとされ、英宗皇帝に個人的な親族のことを考えて礼儀に反する行為をしないようにと忠告した。治平5年(1068年)、朝廷の役人が「親王普安儀、喬王夫人、湘韓夫人、仙游県仁夫人の合同の儀式について、関係官僚に協議するよう要請」した。しかし、当時、英宗皇帝は仁宗皇帝の死を悼んでいたため、「大吉」が過ぎてから協議するよう勅令を出した。 治平2年(1065年)4月、英宗は仁宗の喪を終えて、「両制の書状を諸士、侍臣、祭官に提出し、詳しく論じさせた」。翰林学者の王貴らは次のように報告している。「聖人が祭祀を定め、二上なし。敬愛が分かれば、これに専心することはできない……陛下は先帝の子息であり、即位して世に栄誉をもたらした……しかし、陛下が旗を掲げ、冠を被り、世に富み、子孫が代々王位を継承するのは、すべて先帝の徳によるものである」。つまり、英宗はもともと仁宗の息子であり、王位を継承する資格があった。ここに英宗の王位継承の正当性という問題が絡んでいる。 · 彼を「おじさん」と呼ぶ 普王は実の父親ではあったが、彼自身は小氏族に過ぎなかった。小氏族を大氏族に併合したという疑いを避けるために、彼は二人の父親を区別し、大氏族を敬い、小氏族を降格させなければならなかった。言い換えれば、司馬光は、王位継承の正当性の問題に直面したとき、血縁よりも家父長制の儀式を優先すべきだと信じていたのです。普王は英宗皇帝の父である仁宗皇帝の兄であったため、普王が英宗皇帝の叔父であることに異論はなかった。先代の漢の宣帝と光武帝は、父親を「黄皓」と呼んでいましたが、その例によれば、「この二人の皇帝は同じ氏族の出身であり、他の氏族の後継者ではなかった」、むしろ「彼らは先祖の後を継いだ孫であったため、父親を黄皓として尊敬したが、先祖を王家の父として尊敬することはなかった」ということです。 そのため、両制度の祭祀官たちは、于普王が皇帝を皇帝の名前ではなく叔父と呼ぶのは合理的であり、儀式の規範に沿っていると信じていた。これに対し、親族称号を支持する首相派も猛反撃を行った。韓其らはこう言った。「私は、自然から来るものを親族と呼び、人から来るものを礼と呼んでいる。物事は義によって支配され、時宜に適うが、親族は仁を基礎とし、礼はその根源を忘れてはならない。」韓其は、礼儀作法の根本である「人情」から出発し、社会は道徳によって規制されているが、古代から現代に至るまで「人情」が依然として社会の良好な道徳的雰囲気を形成する原因であると信じていた。 韓其らは言った。「私は自然から来るものを血縁と呼ぶと信じている。」 司馬光が礼儀作法の社会規範としての役割のみに焦点を当てていたのに対し、韓起はさらに一歩進んで人間性の問題を考慮し、普王の礼儀作法に対する判断をより人間的なものにした。現代の文献や「五年喪中」によると、「養子となった者は養父のために三年間喪服を着用する。養子となった者は両親のために喪服を着用する。」養子が養父母と実父母の両方を両親と呼ぶことが分かります。しかし、「産むことより大きな恩恵はなく、相続することより大きな義はない」。恩恵と義を満たすためには従わなければならないが、従うことは明確にすることができ、両親の名前を変えることはできない。しかし、王桂らが提唱する皇帝の叔父という称号には儀礼上の根拠がない。 両制度の祭祀関係者が言うように、実父を「叔父」と呼ぶことは、祭祀の乱れや人間関係の乱れにつながるため、天皇の叔父と呼ぶべきではない。しかし、英宗皇帝が普王の祭祀について議論したとき、欧陽秀は「現在、国は普王を祭祀するにあたって三つの祭祀のみを行っている。一つは親族と称すること、二つ目が庭園を造ること、三つ目が寺院を建てることである」と述べた。都の祖先の秩序を乱す意図はなく、道徳と人性に合致していた。この礼儀作法論争では双方がそれぞれの主張を展開し、最終的には首相派が勝利し、検閲官らは宮廷から完全に追放され、事態は一時沈静化した。 この論争では宰相派が最大の勝者となったかに見えたが、実際には、この論争の後、英宗はこれを機に、自分に従わない朝廷内の大臣を大量に粛清し、検閲官の権力を大幅に弱め、宰相派の大臣を大量に取り込んだことで、権力を自らの手に集中させ、即位以来の権力分散のジレンマを徐々に解消していった。 溥儀論争は 結論 溥儀紛争は長期間にわたり、多数の人々を巻き込み、前例のないほど大きな影響を与え、宋代の運命に大きな影響を与えました。英宗皇帝の時代になると、宋王朝は衰退し始めていました。この頃、皇帝と朝廷の役人たちは内部闘争に全力を注ぎ、派閥を形成して互いに抑圧し合い、改革の進展を遅らせ、貧困と弱体化の状況はますます深刻になっていました。 英宗の後を継いだ宋神宗は西寧改革を実行したが、それは宋王朝にとって単なる刺激に過ぎなかった。そして、神宗皇帝の死により、王安石の改革は中止を余儀なくされました。それ以降、宋朝の宮廷では改革はタブーとなりました。改革するか否かをめぐる宮廷官僚たちの争いは激しさを増し、宰相派と検閲派の争いは保守派と改革派の争いに発展しました。結局、宮廷内の不和は宋朝の国力を弱めることに繋がっていきました。 |
<<: 史上最盛期の馬産地!なぜ唐代初期に馬の飼育産業が前例のないほど発展したのでしょうか?
>>: 歴史上最も有名な短命の王朝はどれですか?元王朝の出現は中国の発展にとってどのような意味を持つのでしょうか?
推薦する
牛馬鬼と白黒無常はどちらも幽霊を捕まえますが、その違いは何でしょうか?
牛頭鬼と馬頭鬼は幽霊を捕らえることもできます。伝説によると、生前親不孝をしていた人は、死後、地獄の王...
『太平広記』第270巻の「女1」の原文は何ですか?
この巻はもともと宋版にはなかったものです。私の家蔵の本を調べたところ、11人が補ったことがわかりまし...
古典文学の傑作『太平楽』:居留部第5巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
紅楼夢第35話:白玉川が自ら蓮の葉スープを味わい、黄金英が梅の花のレースを巧みに編む
宝仔は林黛玉の厳しい言葉をはっきりと聞いたが、母と弟のことが心配だったので振り返らずにそのまま立ち去...
張陽浩の『山陝陽・洛陽郷愁』をどう鑑賞するか?どのような感情が表れるのでしょうか?
張洋浩の『山陝陽・洛陽の思い出』は、Interesting Historyの編集者が関連コンテンツを...
「泰山石」とは?歴史的な暗示はありますか?
「泰山石干堂」とは何ですか?歴史上の暗示は何ですか?次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をしま...
「崔容らを梁王東征に従え」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
蔵経の崔容らを梁王の東征に派遣する陳奎(唐代)黄金色の空はまさに殺戮の兆しを見せ始めており、白い露が...
『紅楼夢』における李婉と妙玉のやり取りは何ですか?なぜ彼女を嫌うのですか?
『紅楼夢』の李婉と妙豫の関係は?なぜ二人は李婉を嫌うのか?今日、Interesting Histor...
科挙制度はいつ廃止されましたか?古代科挙制度の廃止の経緯はどのようなものでしたか?
はじめに:光緒31年(1905年)、西太后は光緒32年から科挙制度を廃止すると宣告する勅語を出した。...
戦国時代の有名な発明家、魯班は何を発明したのでしょうか?
魯班は姓を冀、氏を公叔といい、春秋戦国時代の魯の人である。古代の有名な発明家として、彼の発明は世界中...
雍正帝は年庚瑤を釈放しなかったのに、なぜ岳仲啓の判決を「斬首・投獄」に変更したのでしょうか?
康熙帝と乾隆帝の治世中の勇敢な将軍として、岳仲旗は清朝の国境警備に多大な貢献をしました。しかし、彼の...
七剣十三英雄第135章:狄紅道は悪を殺し、ヒヒを殺し、白楽山は戦士と共にいる
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
済公全伝第116章:趙知事が事件について賢明な判断を下し、済禅師が棺を開けて2体の遺体を検査する
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
拷問器具「ギロチン」とは?鮑正はなぜ犯罪者を処刑するのにギロチンを使うことを好んだのでしょうか?
今日、『Interesting History』の編集者は、なぜ鮑正がギロチンを使って犯罪者を処刑し...
崑崙山はどこですか? 歴史上の崑崙山の起源と伝説
崑崙山の起源の伝説:崑崙山は、崑崙徐とも呼ばれ、中国の聖なる山、すべての祖先の山、崑崙丘、または玉山...