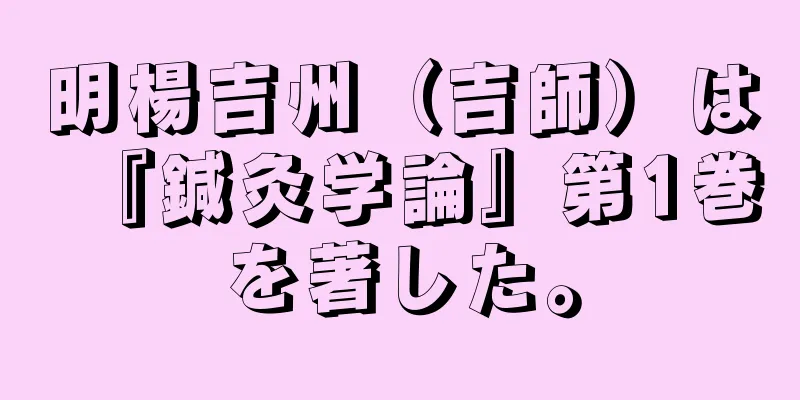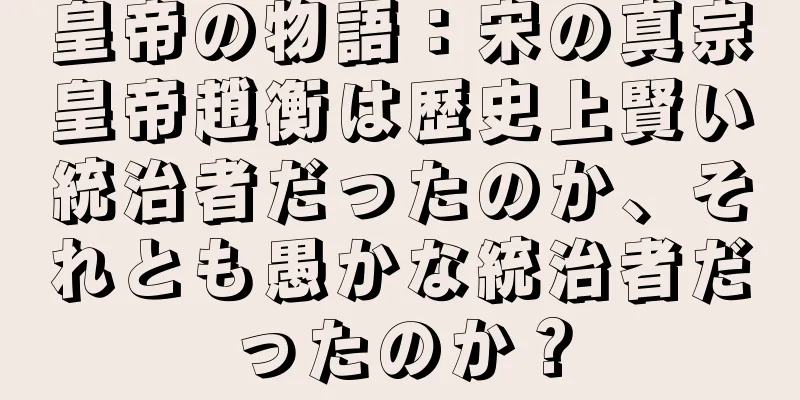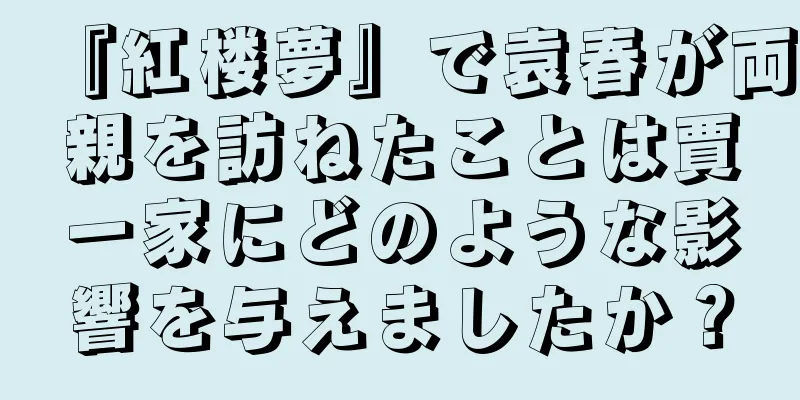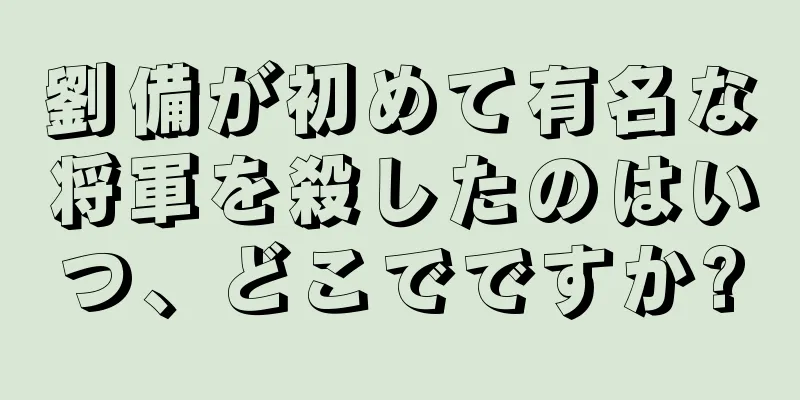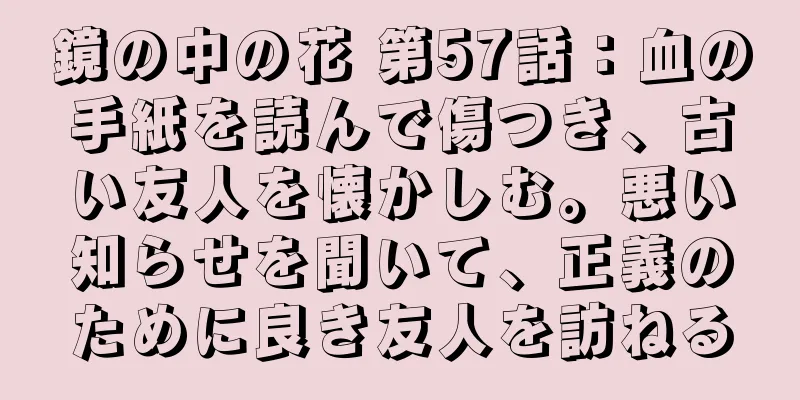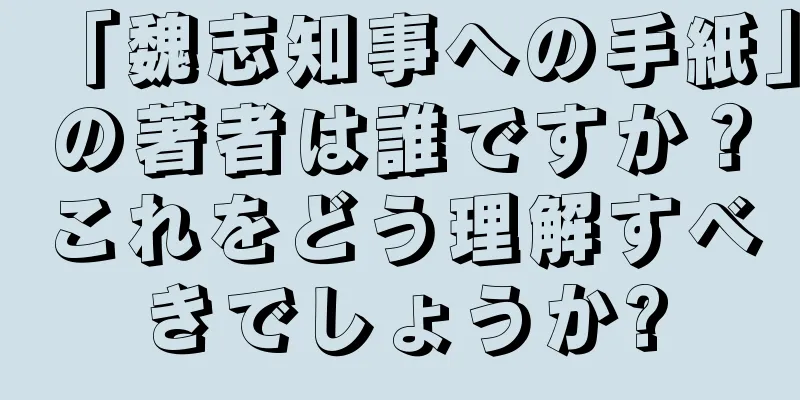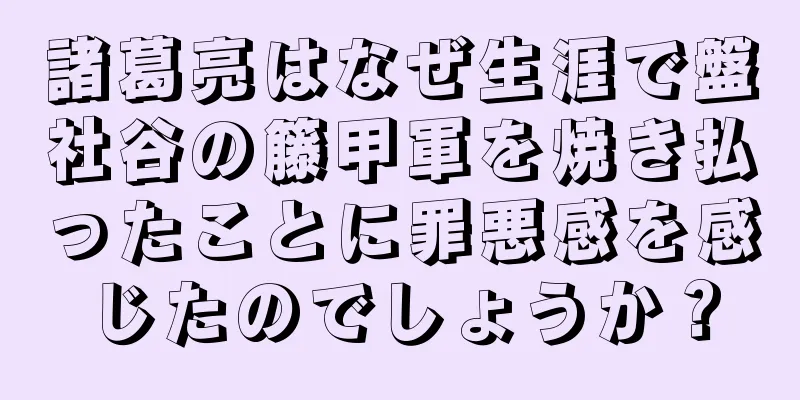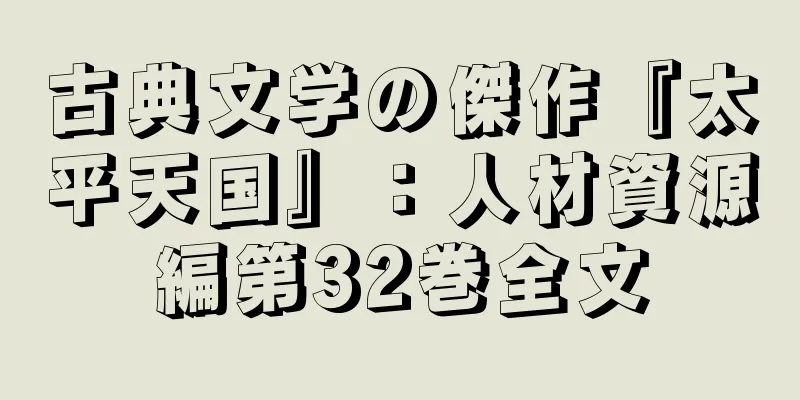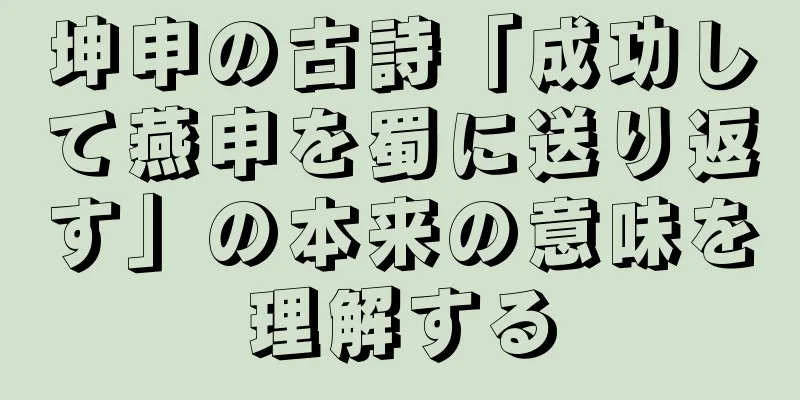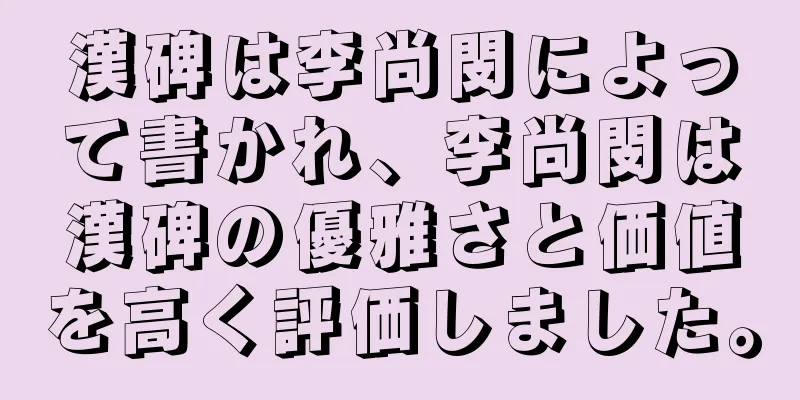三国志の武将が全員全盛期だったら、トップ5に入るのは誰でしょうか?
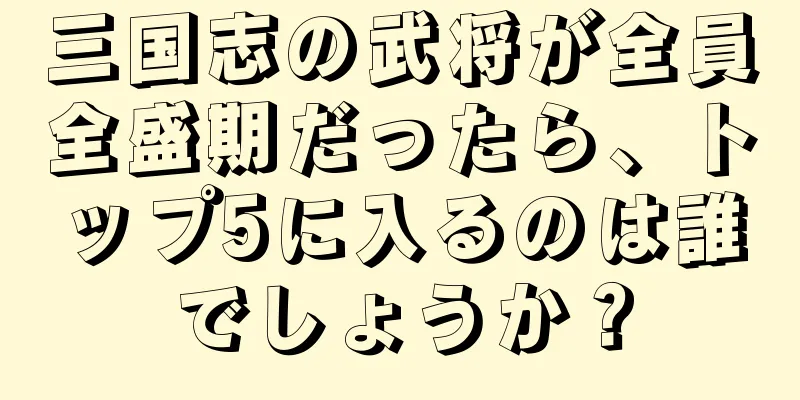
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、三国志の武将が全盛期ならトップ5に入るのは誰なのか、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。見てみましょう! まず呂布 三国志演義では、呂布は世界最高の将軍として認められています。呂布が2位であれば、誰も1位になる勇気はないと言えます。その理由は非常に簡単です。全世界で、1回の戦いで呂布を倒せる人はいません。呂布を倒したいのであれば、包囲戦術を使うしかありません! 虎牢関の前で、呂布はすべての王子たちに挑戦し、みんなが怒り狂うまで殴り倒しました。最後に戦いに出たのは張飛であり、王子たちの面目を保ったのです。しかし、張飛と呂布は50ラウンド戦っても勝敗は決まらなかったが、その後の展開から判断すると、関羽が自ら出陣して助けに入り、張飛と力を合わせて2対1で戦ったため、明らかに呂布をいじめていた。つまり、張飛が呂布に勝てたのなら、なぜ関羽が戦場に出たのでしょうか? 関羽はすべての王子たちの前で決闘のルールを破り、呂布を包囲する張飛を助けるために走りました。これは、張飛が当時すでに不利な状況にあったことを示しているだけです! その後、さらに驚くべきシーンは、グアン・ファイがルーブを包囲することができませんでした彼らは長い間囲まれ、戦い、休息せずに互いにブロックしてブロックしました」と「戦いは回転光のようなものであり、8人の人々のグループはすべてun然としました。 Bu、Liu Bei、Guan Yu、Zhang Feiの包囲にふさわしい将軍はいないはずですよね? 虎牢関の戦いに加え、呂布の濮陽の戦いでの活躍も並外れたものでした。当時、許褚は曹操に寝返ったばかりで、貢献したいという気持ちから、自ら呂布に挑戦しに行きました。その結果、わずか20ラウンドの戦闘の後、曹操は「呂布は一人では倒せない」と言い、6人の将軍に一緒に呂布を攻撃するよう命じました。これは衝撃的でした!劉備、関羽、張飛が呂布と戦ったとき、彼らは3人しか送りませんでした。今、曹操は6人の将軍に直接一緒に攻撃するよう命じましたが、これは誇張しすぎでした。これは、20ラウンド後に徐褚がすでに不利な状況にあったことを意味するだけです。この時点で呂布は強すぎました! 一般的に、呂布は虎牢関の戦いと濮陽の戦いで敗北しましたが、敗北は名誉あるものでした!彼は一度の戦闘で敗北したのではなく、敵の包囲で敗北したからです!三国志演義全体で、呂布だけがこれほど多くの猛将に包囲されるに値し、当然ながら世界一でした! 第二に、関羽 小説の中では、関羽は最強の将軍です!関羽の武術は老齢で大きく衰えましたが、黄忠や龐徳を倒すことはできず、最終的には徐晃に敗れました。しかし、それはすべて関羽が年老いていたためだと理解する必要があります。全盛期の関羽は非常に強かったのです! 曹操は、関羽が温酒を飲み、華雄の首を切る姿や、呂布と戦う三英雄の勇姿を目撃し、関羽を非常に尊敬していた。曹操は劉備を倒した後、関羽への攻撃を命じず、策略を用いて関羽を従わせ、自分に誠実に仕えさせたいと考えた。この目的を達成するために、曹操はまず夏侯惇に関羽を城外に誘い出すよう命じ、次に徐晃と徐褚に関羽の退却を阻止するよう命じ、野外で関羽を包囲して降伏するよう説得した。しかし、計画は変化に追いつくことができません。曹操は計画を立てていましたが、関羽は当時すでに全盛期でした。彼は冷酷になり、徐晃と許褚の連合軍を直接打ち負かし、世界に衝撃を与えました! 許褚は曹嬰で最高の将軍として知られ、戦闘力も非常に強かった。許晃は許褚と50ラウンドで引き分け、一流将軍の中でも最高とみなされていた。結果、二人とも関羽に敵わなかったが、これは関羽がいかに強かったかを示している!その後の白馬の戦いと延津の戦いで、関羽は顔良と文秀を殺し、再び皆を驚かせた。絶頂期の関羽は強すぎたよね?これらの関羽の記録から、彼の強さはトップ将軍のレベルに達するのに十分であることがわかります!しかし、なぜ彼を将軍の中で2番目にしたのでしょうか?次の停留所を見てみましょう! 関羽が曹操のもとを去った後、張飛が古城にいると聞いて、喜んで兄と再会しようとした。その結果、張飛は関羽が曹操に寝返ったと誤解し、甲冑を身につけて飛び出し、槍で関羽を刺し殺そうとした。張飛の奇襲に直面して、関羽はそれを簡単にかわしました。それは衝撃的でした!ご存知のように、三国志演義における奇襲は、実は非常に強力な動きです。関羽は顔良を殺し、趙雲は高蘭を殺し、黄忠は夏侯惇を殺し、関興は岳基元帥を殺しました。彼らは皆、奇襲を利用して敵の将軍を簡単に殺しました。この戦闘スタイルの最大の特徴は、自分の格闘技のスキルが相手よりも高くなければならないことです。そうでなければ、成功させるのは難しいでしょう。 二つの例を挙げると、関行は岳冀元帥よりも強かったため、岳冀元帥が関行に奇襲を仕掛けたとき、関行は結局それをかわしたが、関行は岳冀元帥に奇襲を仕掛け、結局彼を殺した。姜維の武術は徐志ほど優れておらず、徐志に奇襲を仕掛けたとき、一撃で殺すことはできず、徐志の馬を刺すことしかできなかった。結局、徐志は馬から落ち、蜀軍に殺された。自分の武術のスキルが相手より弱い場合、奇襲は成功しない可能性があります。自分の武術のスキルが相手より強い場合にのみ、奇襲は奇跡的な結果を達成できます。 つまり、張飛は突然関羽を攻撃したが、関羽は簡単に彼をかわした。張飛の武術は関羽よりわずかに劣り、全盛期の関羽の方が強かった!同様に、関羽は突然ヤン・リャンを攻撃して殺した。不当な勝利の疑いがあったが、本質的には関羽はヤン・リャンよりも強かった! 3番目は張飛 小説の中の張飛は、呂布と100ラウンド戦って勝敗がつかないという素晴らしい戦績を残しています。虎牢関での呂布との決闘で敗北した以外は、張飛は一度も負けていません。呂布より劣っていないと何人も言っていますが、実際に戦ったことはありません。呂布が生きていたとき、張飛だけが何度も呂布を挑発し、力の面では呂布とほとんど互角でした。これは張飛の超人的な強さを証明するのに十分です。さらに、その後の曹嬰との戦いでは、張飛は非常に良い成績を残しました。長板坡の戦いでは、張飛が一人で長い橋を占領し、曹嬰の将軍たちを怖がらせて戦う勇気がなかったのは驚くべきことでした。 多くの人が疑問に思うのは、張飛が3位なら馬超も3位、許褚も3位、典韋も3位だということです。なぜなら、馬超と張飛は200ラウンド戦っても勝者が決まらず、許褚と馬超も200ラウンド戦っても勝者が決まらず、典韋と許褚も200ラウンド戦っても勝者が決まらず、彼らの実力はどれもほぼ同じだからです。実際、少し分析してみると、これらの人々の間にはまだ実力の差があることがわかります。 夾岭関の戦いでは、馬超と張飛は200ラウンドにわたって戦いましたが、明確な勝敗はありませんでした。当時、張飛は50歳近くでしたが、馬超は30代でした。張飛はもう全盛期ではなく、馬超が全盛期であることは明らかでした。つまり、全盛期の馬超と老年の張飛は同率でした。張飛が全盛期であれば、馬超は間違いなく負けていたでしょう。 渭水のほとりで、許褚は馬超と裸で戦った。二人は二百ラウンド戦ったが、勝敗は決まらなかった。許褚は重量を減らすために鎧を脱ぎ、馬超の槍を奪うために武器を捨てたため、すでに不利な状況にあったことがわかった。さらに、馬超と許褚が激しく戦っていたとき、曹操は突然夏侯淵と曹洪に助けを求めました。これは、曹操の視点では許褚はすでに不利であり、馬超に敵わないことを示しています。 典韋と許褚が戦ったとき、許褚はまだ曹操に寝返っていなかったため、曹操は許褚のことを全く知らなかった。率直に言えば、許褚が典韋に決闘を挑んだのは、自分の武術を披露して曹操の注目を集め、評価を得るためだった。つまり、積極的な挑戦者として、徐褚は典韋を傷つけずに自分の武術の腕前を最大限に発揮する必要があり、そのために自分の武術のスキルを抑えていたのです。しかし、典韋は挑戦者であり、皆の前で面目を保つ必要があったため、全力で戦わなければなりませんでした。しかし、この状況でも、典韋は許褚に勝つことができず、許褚が典韋よりも強いことを示しただけです。 一般的に、ピーク時の強さで言えば、張飛は馬超より強く、馬超は許褚より強く、許褚は典韋より強いです! 4番目、趙雲 琅山の戦いで、劉備は退却中に許褚に奇襲された。趙雲は許褚と戦うために前に進み出たが、やがて許褚は「奮戦」の気配を見せた。その後、于禁と李典が到着しました。趙雲は劉備に先に撤退するよう指示し、後ろに残って許褚、于禁、李典を止めました。戦いの具体的な結果は原文には書かれていませんが、趙雲が背後から劉備に追いつき、劉備が高蘭を一巡で殺すのを助け、張郃を三十巡で倒したという事実から、許褚、于禁、李典は趙雲を止められず、趙雲はかなり楽に活躍したことがわかります。つまり、この戦いから判断すると、許褚の武術の実力は趙雲よりわずかに劣っていることになります! 馬超が劉備に降伏した後、劉備は馬超を優遇しようとしたが、劉璋の軍隊が攻撃した。趙雲は劉備の機嫌を損ねないように、自ら戦いを申し入れたので、劉備は部下に城壁で宴会を開くように命じ、趙雲の戦いを見ながら馬超をもてなす準備をした。しかし、宴会が開かれる前に趙雲は将軍を殺して戻ってきて、皆を驚かせた。これに対する馬超の反応は「馬超も驚いて、さらに敬意を表した」であり、馬超も趙雲の武術に驚いたことを示しています。彼の武術は趙雲よりわずかに劣っていました! 第五に、ヤン・リャン 多くの人は顔良の順位に同意していません。なぜなら、白馬の戦いで関羽が一撃で顔良を殺したため、顔良の兵士たちはあまり優秀ではないと思われるからです。しかし、実際には、関羽が顔良を殺したのは奇襲であり、正々堂々と戦ったのではないと疑われていました。もし二人が本当に正面から戦ったとしたら、関羽は間違いなく顔良をすぐに殺すことはできないでしょう!さらに、顔良は徐晃を20ラウンドで倒し、曹陣営の将軍全員に戦うことを恐れさせました。これは否定できない記録です。これをできる人は世界中に多くありません! 曹嬰の将軍たちの反応から判断すると、彼らは顔良と戦うにはあまりにも怖かったが、馬超と対峙したときはそのような態度をとらなかった。特に許褚は顔良と戦う勇気はなく、むしろ馬超に挑戦した。これは顔良が馬超より強いということしか意味しない! また、徐晃は顔良ほど優れてはいなかったものの、少なくとも一騎打ちで顔良と戦う勇気はあった。しかし、漢江の戦いでは、徐晃と張郃は力を合わせて趙雲を攻撃することを敢えてしなかった。これは、彼らが趙雲をどれほど恐れていたかを示している。つまり、趙雲の強さはまだ顔良より少し強かったのだ!顔良は5位にしかランク付けできない! |
推薦する
本草綱目第8巻䕡茹の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『水滸伝』で、鄭図が呂大から生き残りたいならどうすればいいでしょうか?
陸智深の初期の経験の中で、特に印象的なことが二つある。一つは渭州で三発のパンチで甄官熙を殺したこと、...
古代の蒸し器である釜が、なぜ商代から漢代にかけて普及したのでしょうか。
燕は食品を蒸すための容器で、曾と里の 2 つの部分から構成されています。つながっている部分もあれば、...
薛定山の西征 第21章:薛定山が蛮族の陣営を破り、蘇豹と華紅が脱出
清代の在家仏教徒である如廉が書いた小説『薛家将軍』は、薛仁貴とその子孫の物語を主に語る小説と物語のシ...
王冠の「清朝を祝う:雨を清らかさに調律する」:映画カメラのクローズアップ
王観(1035-1100)、通称は童蘇、通称は朱克、台州如皋(現在の江蘇省如皋)の出身。胡淵の弟子で...
「金門を訪ねて:春雨十分」は、魏荘によって書かれた作品で、誰かを恋しく思う心理活動を描いています。
「金門を訪ねて 春雨多し」は唐代の詩人、魏荘によって書かれたものです。次の『興味深い歴史』編集者が詳...
冷淡で無関心な皇帝であった朱元璋は、なぜ晩年に涙を流したのでしょうか。
後世の人々の目には、朱元璋は暴力的で残酷な人物として映った。明朝初期、彼は多くの功績のある官僚を殺害...
国語:晋語·有史が李季に神勝を誹謗するよう教えた全文と翻訳注釈
『国語』は中国最古の国書である。周王朝の王族と魯、斉、晋、鄭、楚、呉、越などの属国の歴史が記録されて...
黒竹渓谷デスバレーってどこにありますか?黒竹溝の死の谷にまつわる不思議な伝説とは?
長年にわたり、黒竹死谷では人々が行方不明になっており、どんなに探しても痕跡は見つかりません。専門家も...
『新説世界物語』第74条はどのような真実を表現しているのでしょうか。
『十碩心語』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『十碩心語』第74条に表現されている...
『紅楼夢』の賈聡とは誰ですか?賈家における彼の地位はどのようなものですか?
賈従は『紅楼夢』の登場人物。賈舍の息子で、小説にはほとんど登場しない。今日は、Interesting...
李尚銀の『風雨』:厳しい風雨を目の当たりにした作家の人生に対する思い
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
十六国時代の後趙の君主、石賁の略歴。石賁はどのようにして亡くなったのでしょうか?
石頌(339-349)、号は福安、桀族の人。上当武郷(今の山西省)の人。後趙の武帝石虎の息子、母は劉...
李存勗は包囲されて朱文と戦えなかった李可容をどのように慰めたのでしょうか?
李存勗は西突厥の沙托族に生まれました。彼の元の姓は朱戌であり、彼は何代にもわたって沙托族の族長でした...
皇帝の物語: 宋の高宗皇帝はなぜ生前に皇太子に譲位することを選んだのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...