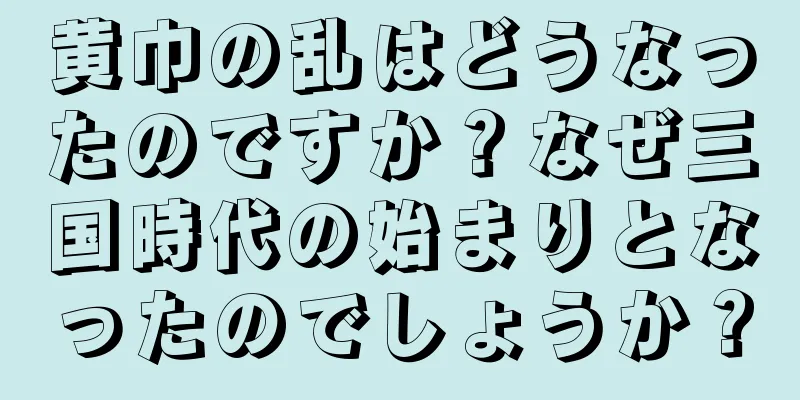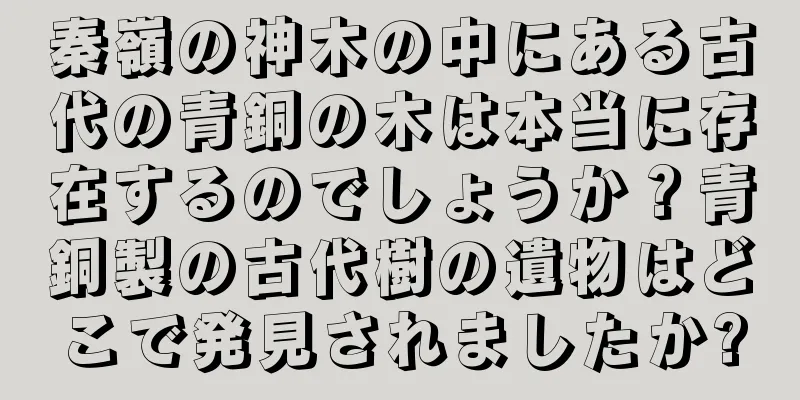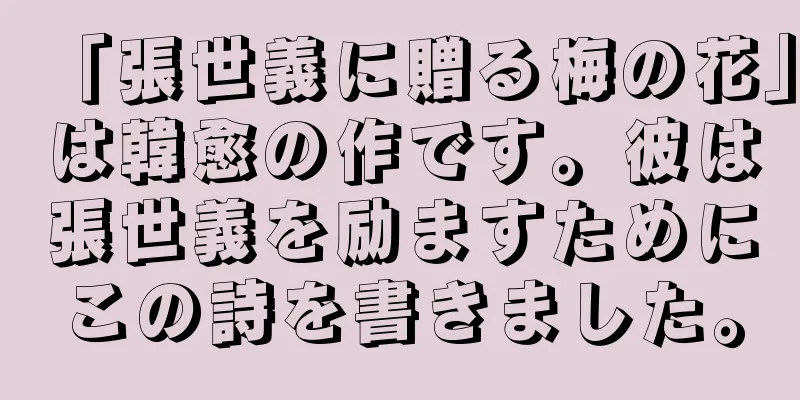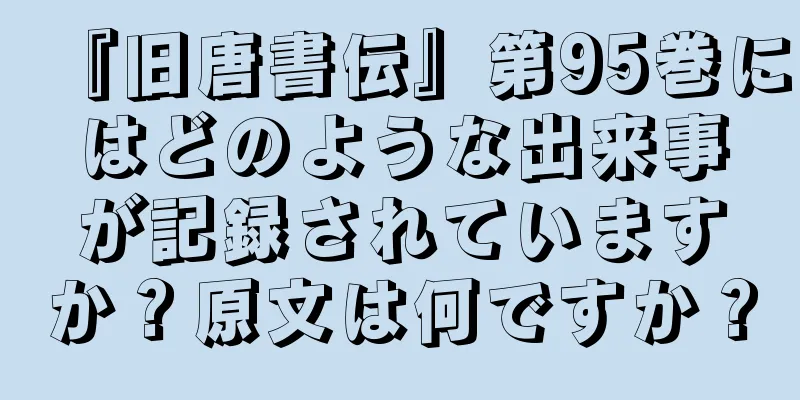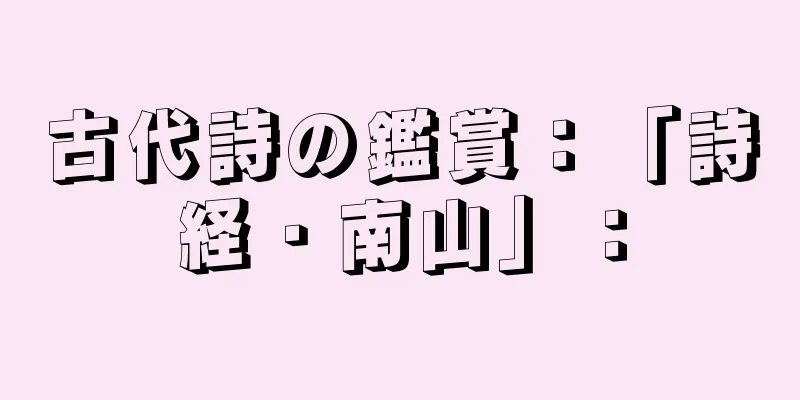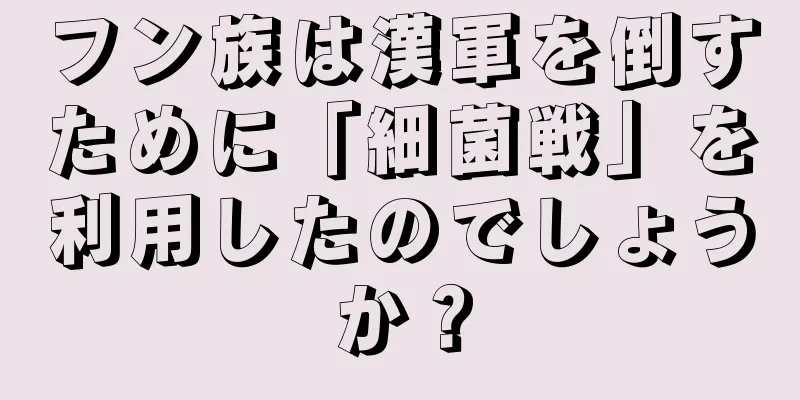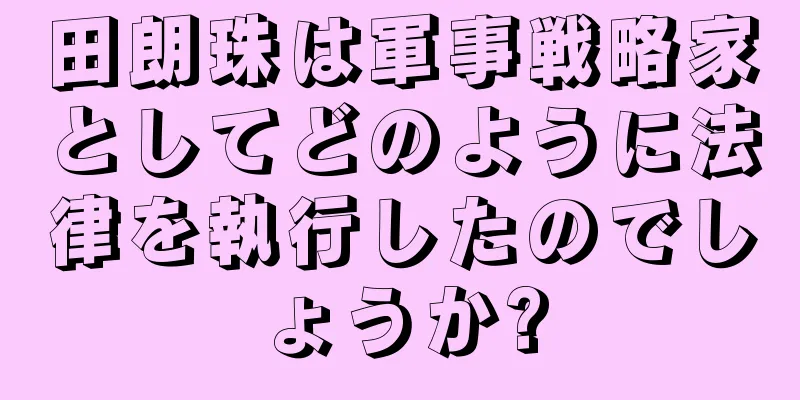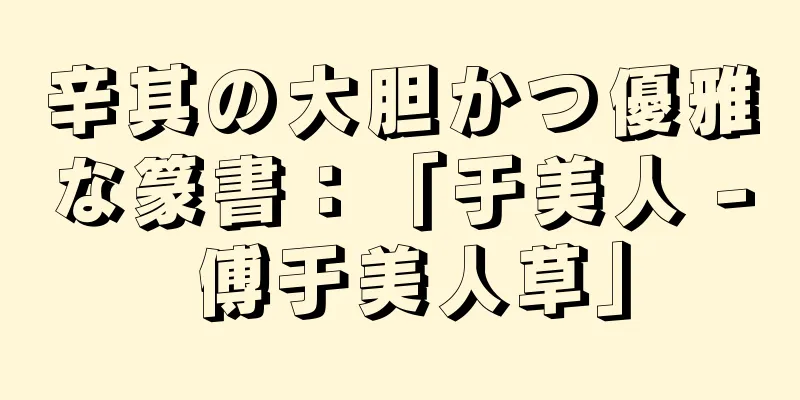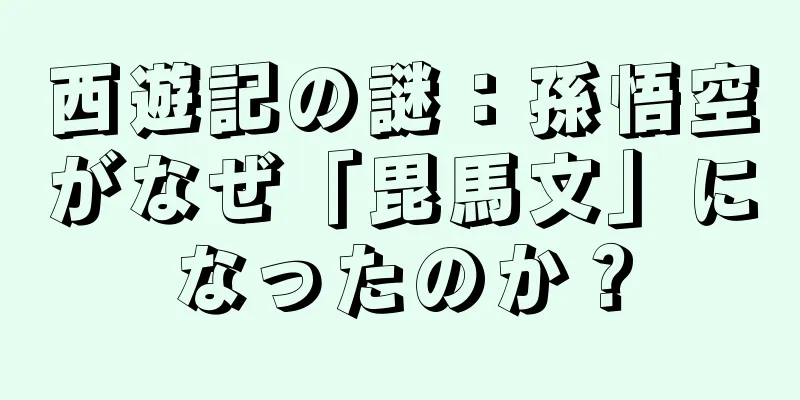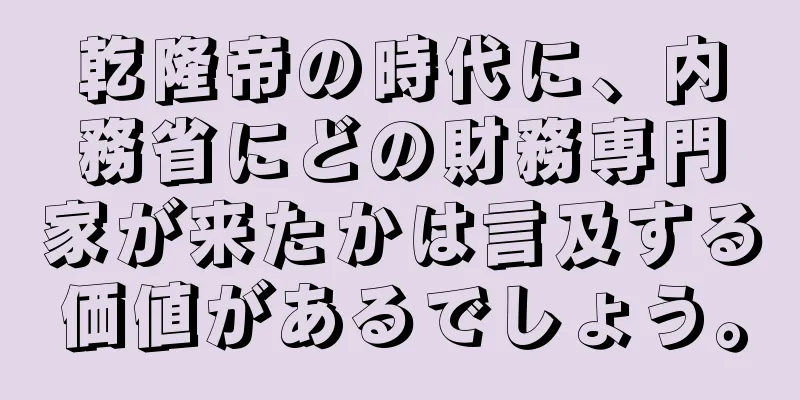諸葛亮はなぜ生涯で盤社谷の籐甲軍を焼き払ったことに罪悪感を感じたのでしょうか?
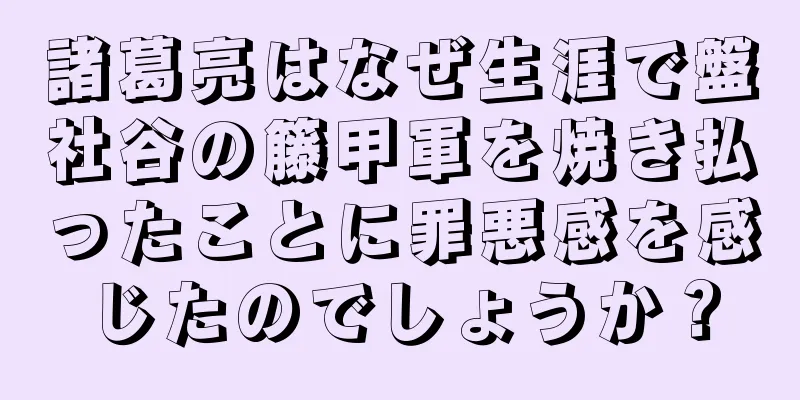
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮が敵を倒すために火を使ったことと、盤社谷が焼けたことでなぜ彼が泣いたのかについて、詳しく紹介します。見てみましょう! 三国志演義の諸葛亮は火の攻撃を得意としていました。これは孫子の兵法書に「火を用いて攻撃を助ける者は賢い」と書かれているからです。冷兵器の時代、優れた軍司令官が明らかな成果を上げるためには、当然自然の力に頼らざるを得ませんでした。本書で詳しく描かれている軍事戦略家として、諸葛亮は生まれつき火攻めに長けています。彼は山から出るとすぐに伯王と新野を焼き払い、曹の軍を恐怖に陥れた。しかし、諸葛亮の生涯において、彼に罪悪感を抱かせるような火災事件が起こりました。それはパンシェ渓谷での戦いであり、そこではヴァインアーマー軍が焼き払われました。 1. 盤社谷の滕家軍を焼き払う。 諸葛亮は白帝城の孤児の信頼を受け入れた後、しばらく休養して療養し、蜀漢政権の状況を再び安定させました。彼は蜀軍を再建し、内部の反乱を鎮圧し始めた。彼は5月に軍を率いて廬江を渡り、南中を征服した。この戦いで、彼は馬蘇の「城を攻撃するよりも心を攻撃する方がよい、軍事戦争よりも心理戦のほうがよい」という助言に従った。南伐の際、彼は敵国の民心を掴むことに重点を置き、孟獲を7回捕らえる劇的な行為を演出した。 敵のリーダーである孟獲を降伏させるには、優しさと力の両方を使う必要があります。相手をなだめるだけでなく、まずは力で相手を威圧しなければなりません。諸葛亮は孟獲を7回捕らえては7回解放し、最終的に孟獲は自ら降伏した。孟獲は言った。「殿様、これは天の力です。南の民は二度と反乱を起こすことはありません!」 この時点で、諸葛亮は南中を平定し、この反乱地域を蜀漢の安定した後方基地に変えました。彼は各民族の現地民衆の支持を得ただけでなく、大量の物資と人員も獲得し、北伐の基盤を築きました。 籐甲軍を焼き払う話は、孟獲を捕らえようとする最後の試みの最中に起こった。孟獲を生け捕りにしようとした最初の6回の試みでは、諸葛亮はさまざまな手段を使って孟獲を繰り返し失敗させた。他に選択肢がなくなったため、孟獲は呉国に助けを求めざるを得ず、諸葛亮と戦うために軍隊を派遣するよう呉国に要請した。五国の王五吐固は孟獲の要請を受け入れ、籐の鎧を着た3万人の兵士を率いて諸葛亮と戦った。 この本では籐甲冑軍について詳しく説明されています。この軍隊が対処しにくかった主な理由は、彼らが身に着けていた籐の鎧のせいでした。この種類の籐の鎧は、地元の人々が山の蔓を集め、油に浸し、半年後に取り出して乾燥させ、その後再び油に浸して作られています。 10回以上繰り返し浸すと、鎧にすることができます。身体に着用すると、川を渡るときに沈まず、水を通過するときに濡れず、剣や矢も貫通しません。この描写から判断すると、蜀軍と滕家軍が正面から戦えば、間違いなく不利な状況になるだろう。 案の定、蜀軍と籐甲軍の最初の戦いでは、蜀軍のクロスボウの矢は籐甲を貫通できず、すべて地面に落ちました。剣も槍も籐の鎧を貫くことはできない。その結果、蜀軍は敗北し、逃亡した。勝利後、籐甲冑軍は甲冑を身に着けて川を渡りました。中には籐甲冑を脱いでその上に座って川を渡る者もいました。諸葛亮は状況を知り、待ち伏せを計画し、その待ち伏せは盤社谷で行われた。 諸葛亮は盤社谷の場所を選ぶのに多大な苦労をしました。これは、孟獲が多くの失敗を経験した後、諸葛亮が待ち伏せ攻撃に長けているという教訓を学んだためである。パンシェ渓谷は長い蛇のような形をしており、険しい岩があり、木はなく、真ん中に道路があります。このような地形には隠れ場所がなく、当然待ち伏せには適していませんが、諸葛亮は逆にここで待ち伏せを仕掛けました。 彼は谷間に地雷を敷設し、竹の棒を使って接合部を貫通し、爆薬のコードを誘導した。また、魏延を派遣して敵を誘き寄せ、15回連続で敗北させ、7つの陣営を放棄させた。こうして、武吐は連続した戦いに勝利し、魏延によって盤社谷へと導かれた。山には木がないので待ち伏せはないだろうと考え、大胆に谷に突入した。 その結果、籐の鎧を着た3万人の兵士は、車両と薪を使った蜀軍によって谷間に閉じ込められました。その後、蜀軍は投げた松明を使って谷間の導火線に点火し、地雷を爆発させた。籐甲冑軍が着用していた籐甲冑が油に浸かっていたため、すべて発火してしまった。戦いの後、ウトゥグと籐の鎧を着た3万人の兵士はパンシェ渓谷で焼き殺された。孟獲も諸葛亮に捕らえられ、最終的に降伏し、諸葛亮の南征は終結した。 2. 諸葛亮は最後の手段として火攻めを行った。 この本には、諸葛亮が盤社谷で籐甲兵が焼き殺される悲惨な光景を見たとき、涙を流してため息をつき、そうすることは国のためになるが、自分の命を縮めることになると言わざるを得なかったと書かれている。後にこの戦いを総括した際、彼は部下たちに、この戦いは彼の徳を大きく傷つけ、彼にとって大きな罪であったと語った。しかし、諸葛亮は山から出てきた後、火の攻撃で無数の敵を滅ぼしました。なぜ彼はこの戦いにそんなにため息をついたのでしょうか? まず第一に、この戦いは諸葛亮の本来の意図ではありませんでした。この戦いはもともと諸葛亮の計画には含まれていなかった。彼は孟獲を6回捕らえては6回解放し、孟獲の領土をすべて占領した。論理的に言えば、この状況では孟獲は降伏するべきだった。孟獲が依然として降伏を拒否し、さらには呉歌国からの援助を得て決戦に臨むとは誰が知っていただろうか。このような状況下で、諸葛亮は南伐の最終的な勝利を収めるために、途中で諦めることはできず、孟獲と戦い続けなければなりませんでした。 第二に、諸葛亮は呉歌王国の悲惨な敗北に同情を感じた。南伐の際、諸葛亮の最大の敵は呉ではなく孟獲であった。孟獲は諸葛亮に抵抗するために呉国を戦争に引きずり込んだ。この戦いに、武歌王国は全国民を派遣した。王から兵士まで、誰もが戦いに出る準備ができています。しかし、この戦いの後、五格王国の健常者は皆、盤社谷で焼き殺された。 武歌の兵士たちの頭は砲弾で砕かれ、彼らの体に着けていた籐の鎧は燃え上がった。多くの人々が焼き殺されるという悲惨な光景は諸葛亮にとって恐ろしいものだった。これらの人々はここで死ぬべきではなかった。彼らは皆、参加すべきではなかった戦争に参加したために死んだのだ。さらに、武歌王国は一度に大半の有能な兵士を失い、すぐに窮地に陥りました。あの荒野では、そのような部族は滅びるしかなかったのです。諸葛亮はこの状況を思い浮かべて罪悪感を覚え、涙を流してため息をついた。 第三に、諸葛亮には火攻め以外に勝つ方法がなかったため、五歌王国は滅亡し、諸葛亮は罪悪感を抱くことになった。蜀軍が初めて呉歌国の籐鎧軍と遭遇したとき、敵の状況を理解していなかったため、大きな損失を被りました。しかし、諸葛亮は籐甲兵の籐甲が水を恐れないことを知り、「水に強い者は火に弱い」という原則に基づいて、すぐに火攻めの戦略を思いつきました。 しかし、前線の戦場で火攻めをすると、有利にはなるものの、壊滅的な結果を得ることはできません。そこで諸葛亮は、待ち伏せ戦術を使って一網打尽に敵を滅ぼすというアイデアを思いつきました。しかし、このようにして、籐甲冑軍の兵士は皆籐甲冑を着用していたため、一度火の攻撃を受けたら誰も逃げることができなかったことがわかります。しかし、諸葛亮には籐甲軍を倒す他の手段がなかった。この無力な気分の中で、諸葛亮は悲しくならざるを得なかった。 第四に、この戦いの結果は諸葛亮の南征の目的に反するものとなり、諸葛亮に罪悪感を抱かせた。今回の諸葛亮の南征の目的は「第一に心理戦、第二に軍事戦」であった。そのため、諸葛亮は地元の人々の心をつかむことに重点を置きました。捕らえられた孟獲とその部下たちを厚く扱っただけでなく、何度も孟獲を解放し、部隊を再編成して共に戦わせた。 このアプローチは良い結果を達成しました。戦闘中、孟獲は部下によって捕らえられ、諸葛亮のもとへ送られた。地元の人々は諸葛亮を憎まなかっただけでなく、自ら進んで諸葛亮を助けて困難を乗り越えようとした。しかし、今回の盤社谷の焼き討ちは諸葛亮を窮地に陥れた。滕家軍を倒さなければ、これまでの努力はすべて無駄になる。滕家軍を倒せば、武歌王国は滅亡する。 蜀漢の国と民のために、諸葛亮はついに籐甲軍を焼き払うことを選んだ。しかし、この戦いは諸葛亮の当初の意図に反するものとなり、諸葛亮は罪悪感を抱くことになった。この罪悪感のせいで、彼は涙を流し、ため息をついただけでなく、自分は罪を犯した、自分の命が縮むだろうと何度も口にした。しかし、これは諸葛亮の無力な選択であり、他に選択肢はなかった。 3. 天雷は地雷を破壊することができる。この戦いは上方谷の失敗を隠蔽した。 この戦いで諸葛亮は巧妙な作戦を立て、当時の秘密兵器であった地雷も使用しました。諸葛亮はまず敵の疑いを招かない盤社谷を奇襲戦場として選び、その谷に秘密兵器である地雷を仕掛けた。この武器は地中に埋められ、竹の筒に紐が通されていました。そして魏延を派遣して15回連続で戦いに勝利させ、7つの陣営を放棄させ、敵を傲慢にさせて敵を誘い出す戦略を使い、ついに籐甲軍を率いて盤社谷に侵入させた。 パンシェ渓谷でウトゥグ率いる籐甲軍が包囲されたときも、彼らは心配していなかった。谷には木がないので、当分の間、火事になる可能性はない。しかし、彼らが予想していなかったのは、谷間の鉱山が蜀軍の松明によって点火されたことだった。籐の鎧を着た兵士たちの頭や顔は砲弾で粉々に砕かれただけでなく、体に着けていた籐の鎧も燃え、彼らは全員谷間で焼死した。ラタンアーマー軍の失敗は、彼らが今まで見たことのない兵器地雷によるものだと言えるでしょう。 諸葛亮が地雷という秘密兵器を持っていたからこそ、盤社谷を焼き払う勝利を収めることができたのです。しかし、諸葛亮の秘密兵器の数は限られていることが本書から分かります。彼は黒油トラック10台分の鉱山だけを使い、残りは未使用のままにしました。当時、部下は「地雷はそんなに強力ですが、どうやって破壊すればいいのですか?」と尋ねました。諸葛亮も、天雷で地雷を破壊できると何気なく答えました。 諸葛亮が部下に対して出した答えは意図的なものではなかったかもしれないが、それでも現実となった。諸葛亮の最後の北伐の際、彼は上房谷で司馬懿を谷に誘い込み、火で焼き殺す計画を立てた。こうして関龍戦争の勝敗は決まり、諸葛亮は北伐の目的を達成することができた。 そこで諸葛亮は再び上房谷の鉱山を利用した。火攻めが始まったとき、司馬懿と息子は抱き合って泣きながら死を待った。しかし、人々が予想していなかったのは、予期せぬ出来事が起こるということでした。突然、雷が鳴り響き、激しい雨が降り注ぎ、諸葛亮の怒りは消えた。諸葛亮が事前に敷設した機雷は当然ながら無効となった。 諸葛亮は司馬懿が逃げる機会をとらえたのを見て、絶望してため息をつくしかなかった。結局、司馬懿は逃亡し、二度と諸葛亮と戦うことはなかった。諸葛亮は病気と未達成の野望のため、五丈原の軍営で亡くなった。諸葛亮は盤社谷で言ったことが実現するとは思っていなかった。天からの雷がついに地雷を破壊した。これが盤社谷を焼き払った原因と結果かもしれない。 |
<<: 歴史上の周瑜は実際どのような人物だったのでしょうか?彼はその歴史にどのような影響を与えたのでしょうか?
>>: 諸葛亮が魏延を使って街亭を守らせたとしたら、街亭が失われないことを保証できるだろうか?
推薦する
千奇の「春の夜竹閣の王維の辞世の詩に答える」:詩全体が新鮮で奥深く、余韻がたっぷりである。
銭麒(722?-780)、号は中文、呉興(現在の浙江省湖州市)出身の漢人で、唐代の詩人。偉大な書家懐...
『世界の物語の新記録』の第 6 章の教訓は何ですか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。それでは十碩心於・知識と鑑賞の第六章で表現...
カザフ人とウイグル人の関係と相違点
カザフ人とウイグル人の違いは、彼らの生活様式が異なり、言語にはいくつかの類似点があるものの、すべての...
『雷峰塔奇譚』第3章の主な内容は何ですか?
呉元外は友人の白振娘と出会い、ホテルで結婚するその詩はこう述べています。鬼として罪を犯し、また鬼と出...
『紅楼夢』の石向雲の結婚における「金色のユニコーン」とは、いったい誰のことを指すのでしょうか?
『紅楼夢』の石向雲はとても好感が持てる女性です。彼女は楽天的で、明るく、性格は素直です。では、本の中...
南宋の詩人趙定の傑作「建康元宵節に詠まれた鷺空」
以下、Interesting Historyの編集者が、趙丁の『山葵空・建康上元作品集』の原文と評価...
明代の五字詩「田園夜話」をどのように鑑賞すればよいでしょうか。この詩の作者はどのような比喩を持っているのでしょうか。
村人たちは夜中に話をしました。明代の李昌奇について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見...
『紅楼夢』で、宝仔が大観園を去ったとき、なぜ王夫人は彼女を引き留めようとしなかったのですか?
大観園の探索は『紅楼夢』における大きな出来事です。皆さんも聞いたことがあると思います。王夫人が大観園...
『紅楼夢』で賈家は新年をどのように祝いましたか?五荘頭家賃とは何ですか?
『紅楼夢』で賈家が新年をどのように祝ったのかまだ知らない読者のために、次の『興味深い歴史』編集者が詳...
秋の水のように滑らかな「燕陵腰刀」とはどんな武器でしょうか?
毛伯文が戦争に赴くとき、明代の世宗皇帝は彼に詩を授けた。「将軍は勇敢で、腰に雁の羽の剣を帯びて南へ戦...
『南遊記』第14章の主な内容は何ですか?
東岳寺の華光が賑わう華光は東岳寺の門に到着し、曹業の三聖人に会った。三聖人は華光に尋ねた。「あなたは...
『紅楼夢』で大観園が捜索されたとき、なぜ王希峰は小湘閣を調べなかったのですか?
大観園捜索は栄果屋敷で起きた一大事件でした。ご存知でしたか?次は、Interesting Histo...
唐代の魏荘の『往生記』をどう評価するか?詩人はどのような感情を表現しているのでしょうか?
過去[唐代]の魏荘を回想して、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう!...
『紅楼夢』で、青文はどのようにして賈家の中で徐々に消えていったのでしょうか?
青文の物語は『紅楼夢』の中でも注目度の高いストーリーである。彼女は才能と気概に溢れたメイドだったが、...
唐の太宗皇帝の長女、長楽公主李礼智の夫は誰ですか?
唐の太宗皇帝の長女、李麗志の妃は誰でしたか?唐代の王女、李麗志(621-643)は長楽公主という称号...