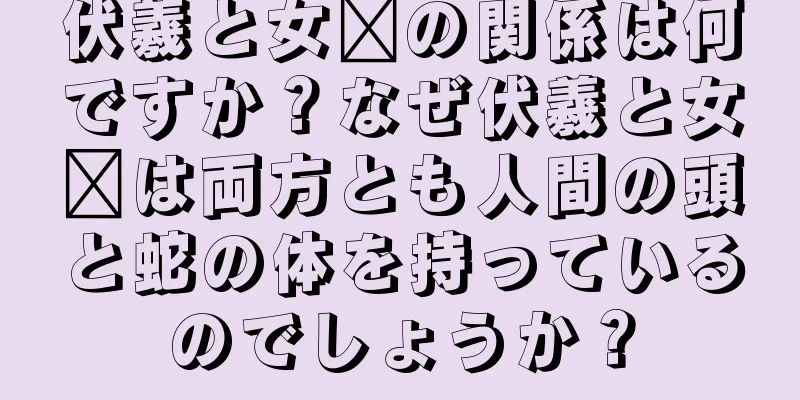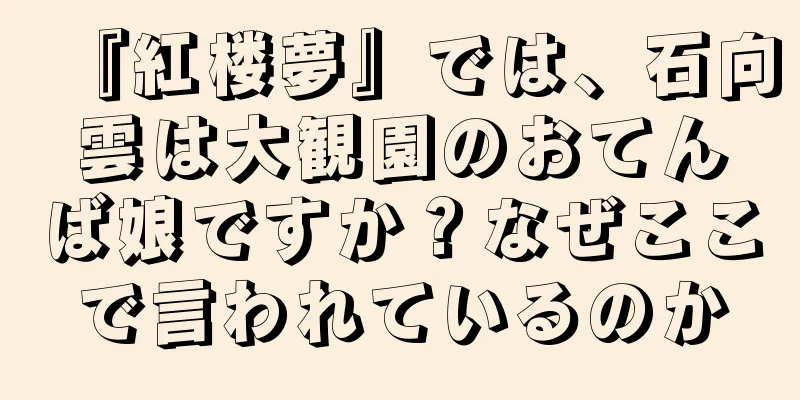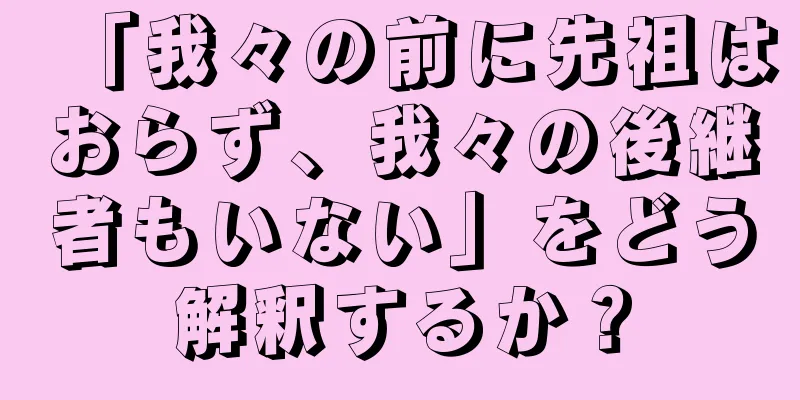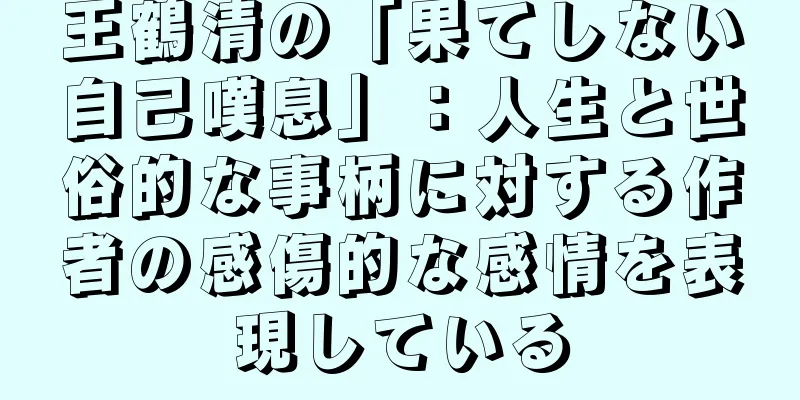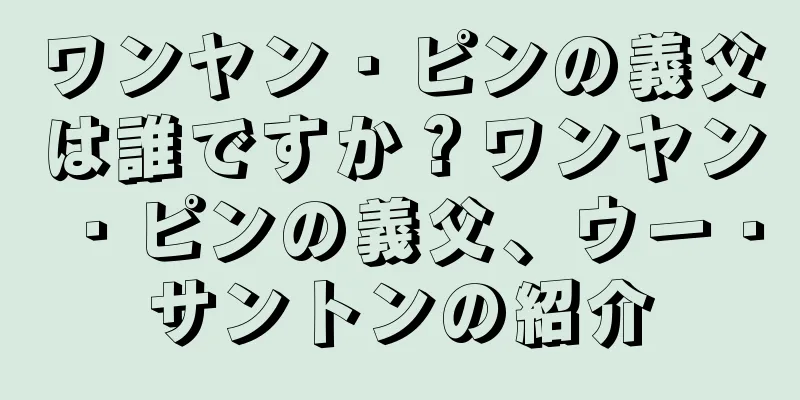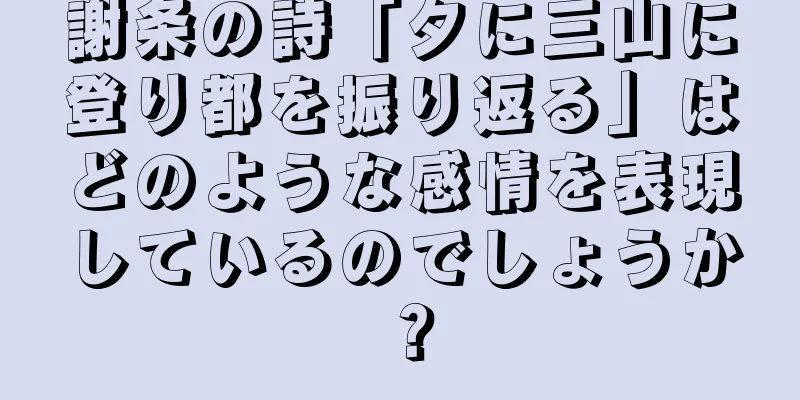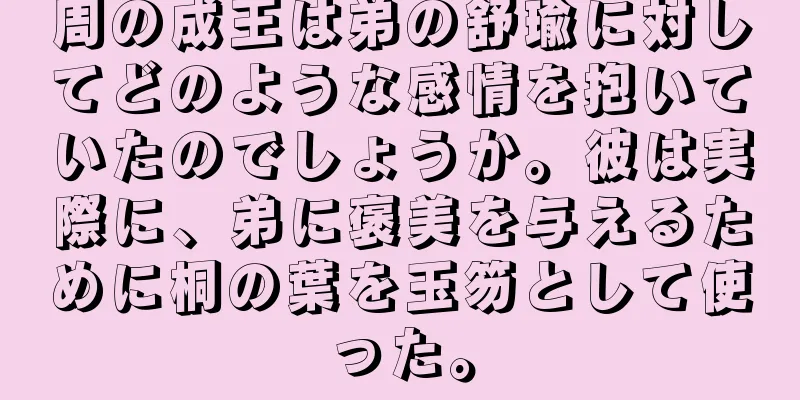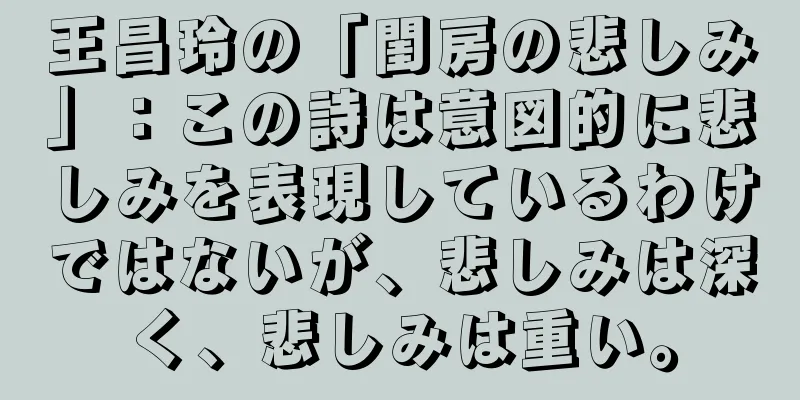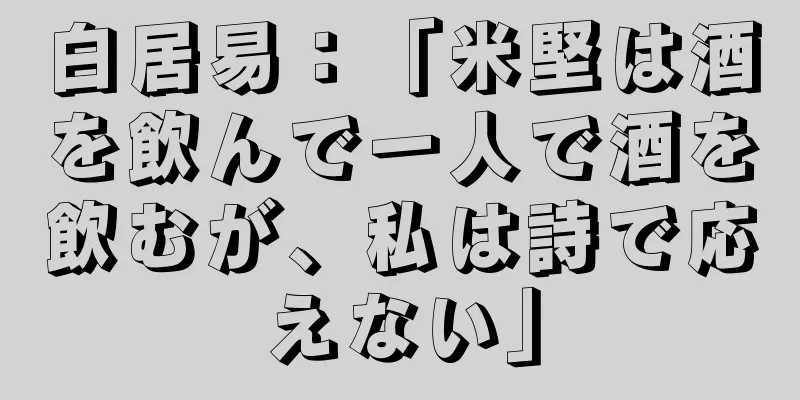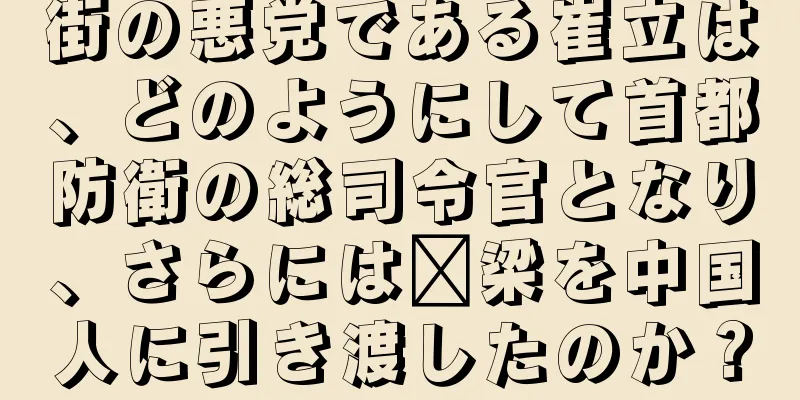「柳の花の詩三首」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?

|
柳の花の詩3つ 劉玉熙(唐代) 緑の帯に咲き、その香りを風に遠くまで広げます。 そのため、花が散ると、春の夜は美しい音色で満たされます。 風の助けを借りずに軽やかに飛び、地面に落ちることなく軽やかに落下します。 澄んだ空の下でのダンスは、無限の思考を呼び起こします。 晴れた日に雪が暗く降り、青春の黄昏に別れを告げます。 意図的ではないが、感傷的なようで、何千もの家族を残していった。 コメント 晩春になると、川岸や池のそば、小道の脇、中庭に垂れ下がる緑の柳がいつも見られます。柳の花穂は風に吹かれて空一面に舞い、軽やかに舞います。緑の柳の枝からは絶えず柳の花びらが上がり、独特の繊細さと魅力を放ちます。古代から現代に至るまで、文人や詩人たちは魅力あふれる柳の花を題材にした詩を詠んできました。 柳の花は一般に柳の花穂として知られ、ポプラの花としても知られています。春の香りがすべて消え去った晩春、柳の花穂は根も支えもなく雪のように風に漂い、詩人の連想や感情を呼び起こし、さまざまな気持ちを表現します。柳の枝を折って別れの贈り物にするのは、秦漢の時代に形成された中国の古代の旅行習慣です。西安の東郊にある八河にかかる有名な八橋は、漢民族が客人への別れの贈り物として柳の枝を折る場所です。この場所は「八六風雪」として知られ、「関中八景」の一つに数えられています。 古代の文人や詩人の詩や歌、また人々の日常生活の特別な場面の中には、別れを告げるために柳の枝を折る場面が常に詳しく描かれています。そのため、「柳を折る歌」の意味は古代人の詩歌には欠かせないものだったのです。 劉玉熙のこの詩集は、柳を題材にした詩を書いた以前の詩人たちの作風とは対照的であり、柳の花の性格と精神を表現している。これは、劉玉熙が改革運動の失敗に参加した後に降格され、その機会を利用して、達成されなかった野望に対する悲しみと憤りを表明したためである。彼は柳の花について、とても高貴で感傷的な方法で書きました。 劉玉熙 劉玉熙(772-842)は、愛称孟徳といい、唐代に彭城(現在の徐州)出身の漢人である。祖先は洛陽に住んでいた。唐代の作家、哲学者。漢代の中山景王の子孫であると主張した。かつては検閲長官を務め、王書文の政治改革グループの一員でもあった。唐代中期から後期にかけての有名な詩人で、「詩英雄」として知られています。彼の家系は代々儒教を継承してきた学者の家系です。彼は政治改革を主張し、汪書文の政治改革活動の中心人物の一人でした。その後、雍正の改革が失敗すると、彼は朗州(現在の湖南省常徳市)の司馬に降格された。湖南省常徳市の歴史学者で収集家の周新国氏の研究によれば、劉毓熙は、黃州司馬に左遷された際に、有名な『漢寿城春景』を著したという。 |
<<: 『荊門路の思い出』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
>>: 『桃源郷雪の悲劇』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
推薦する
荊族文化と現代荊族の民間文学の紹介
荊族の民間文学の発展は、時代の発展と密接に関係しています。 1840年のアヘン戦争後、キン族の社会は...
孔子家言集第42章 礼に関する質問 子貢著
子貢は孔子に尋ねた。「晋の文公は実際に皇帝を召し、君主に敬意を表するよう命じた。あなたが『春秋』を書...
ジン族の歴史 ジン族のトーテムの意味は何ですか?
モノコードはキン族に最も愛されている民族楽器の一つです。モノコードには長さ 80 cm の弦が 1 ...
中庸の教義とは何ですか?中庸の教義の本質は何ですか?
中庸の教義の本質とは何でしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!中庸...
『太平広記』第390巻の「二墓」の登場人物は誰ですか?
女官墓、陸環、趙東熙、丁永興、顔安志、女媧墓、李妙、賈丹、張氏、樊沢斉、景公墓、郭懿、寿安土棺、李思...
青銅器に最も多く刻まれている銘文です。伝わってくるのは愛と血の温もり!
今日は、Interesting Historyの編集者が青銅器についての記事をお届けします。ぜひお読...
韓馥はどのようにして、後漢末期の中原における覇権争いで排除された最初の太守となったのでしょうか。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
姓「彊」は周王朝の王族に由来します。姓「彊」を持つ現代の赤ちゃんにはどのように名前を付けるべきでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、Ji姓の赤ちゃんの命名に関する記事をお届け...
唐代の詩人杜甫の五字律詩:「江漢」の原文と鑑賞
『江漢』は唐代の偉大な詩人杜甫が書いた五字律詩です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので...
黄巾の乱の時、なぜ誰も皇帝を名乗らなかったのでしょうか?張傳はどのような社会を築きたかったのでしょうか?
なぜ黄巾軍には王や皇帝を名乗る者がいなかったのでしょうか。実は、とても単純なことです。張傅が築こうと...
『Strange Stories from a Chinese Studio - Miao Sheng』のストーリーは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「妙生」の原文は、中国のスタジオからの奇妙な物語から龔勝は閩州出身であった(1)。試験のために西安に...
宋代の詩『皇街を歩く』の劉勇の「春の庭で酒を飲む」をどのように理解すべきでしょうか?
皇城街を歩く:春の庭で酒を飲む [宋代] 劉勇、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらし...
「安氏:遠岸の残雨」の鑑賞、詩人劉勇は長年落ちぶれ、官僚として失敗した
劉雍(984年頃 - 1053年頃)は、もともと三弁、字は景荘であったが、後に劉雍、字は斉青と改めた...
王夫人は、華希仁が「虎を食べるために豚のふりをしている」ことを知っていたのに、なぜ騙されたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
中国の歴史における古代、中世、後期古代とは何ですか?
三つの古代とは、古代、中世、下古代のことである。しかし、さまざまな意見があります。 『韓義文志』には...