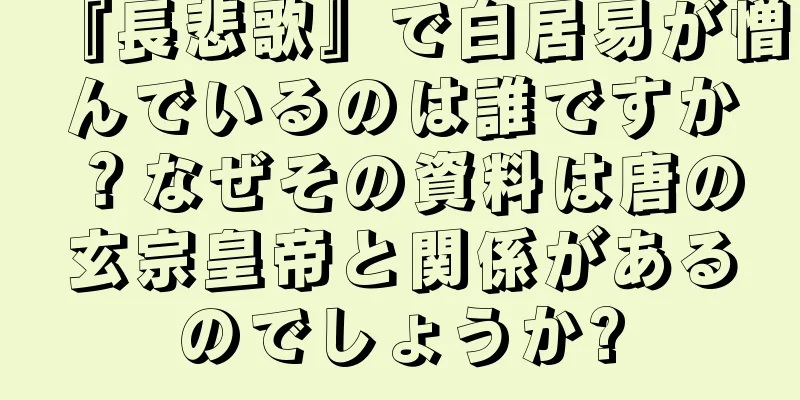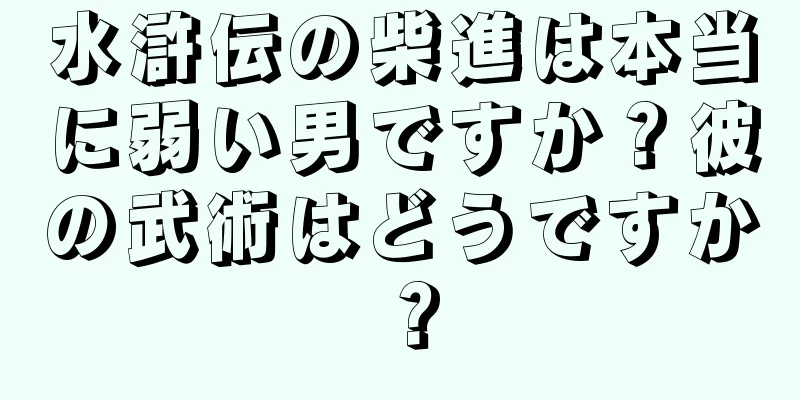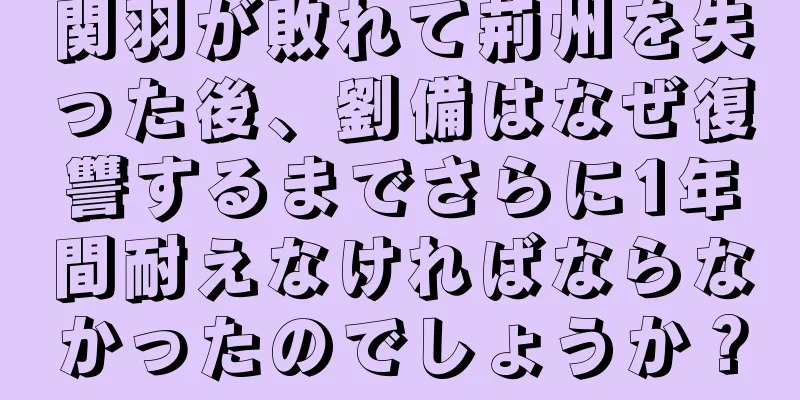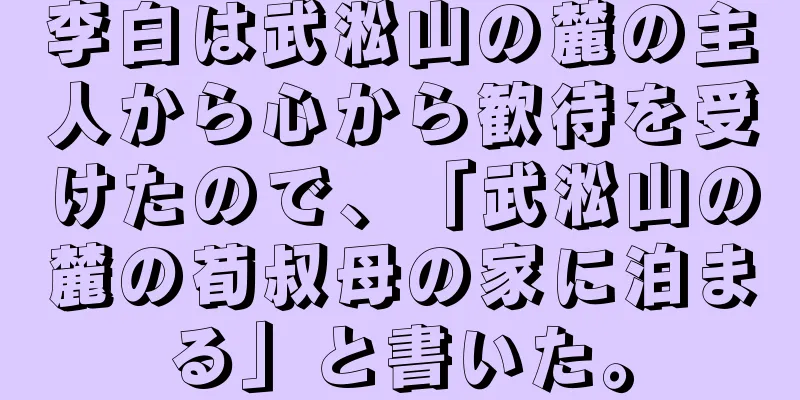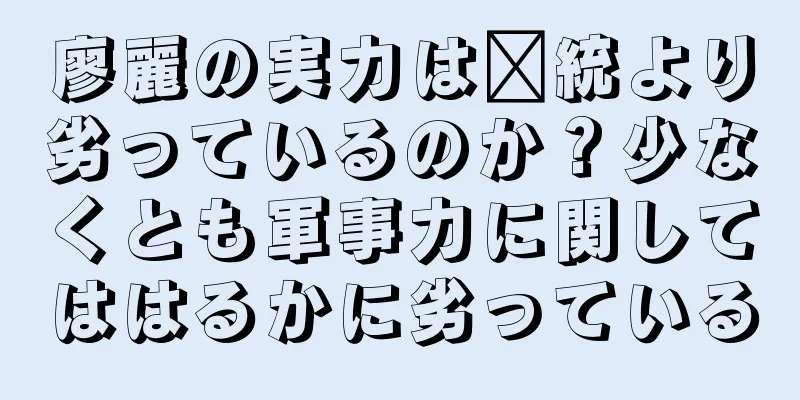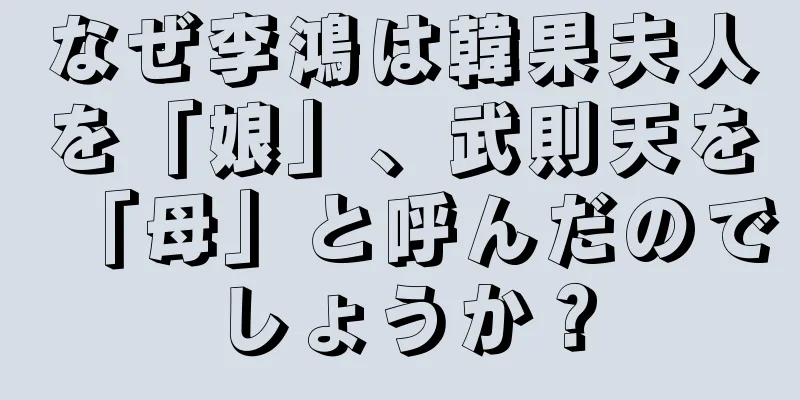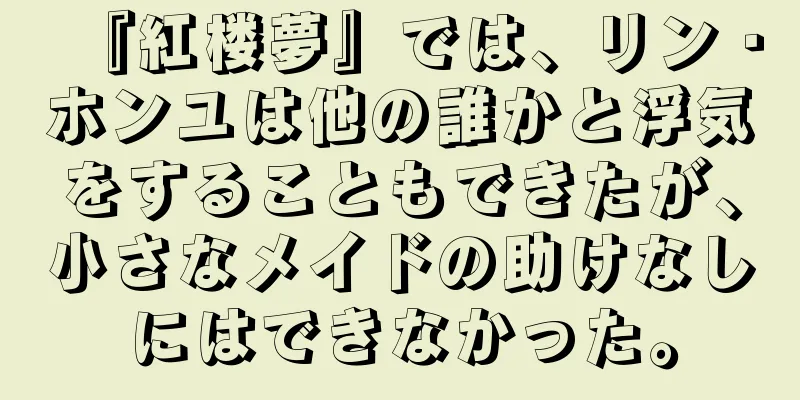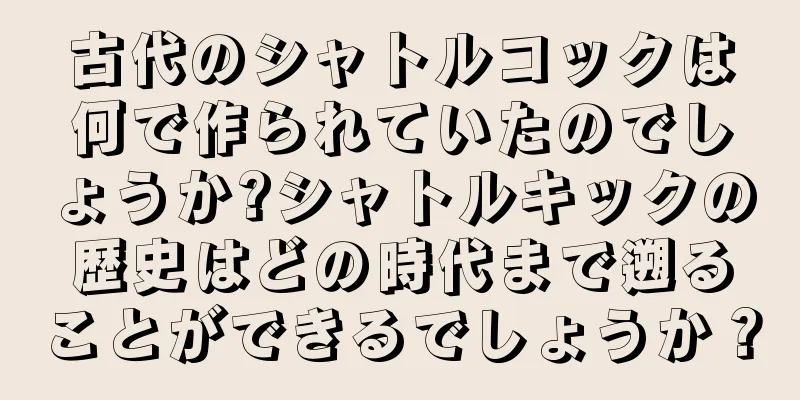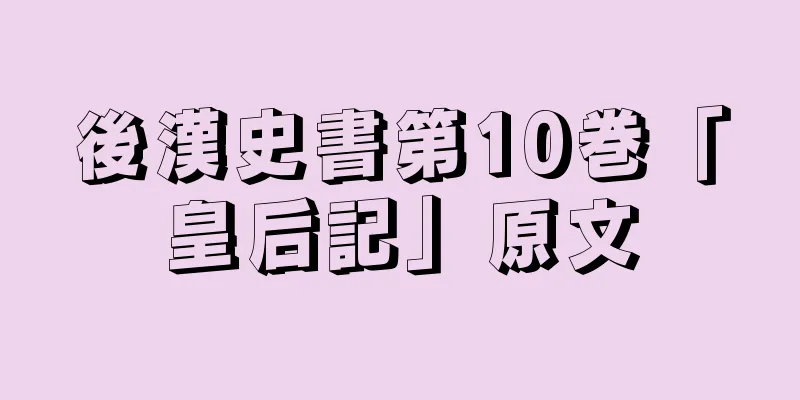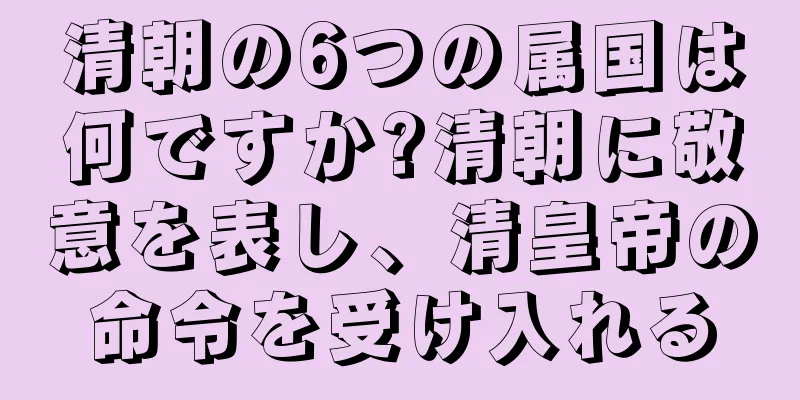「菩薩男 遥かな夕暮れに面した冷たい霧の窓」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
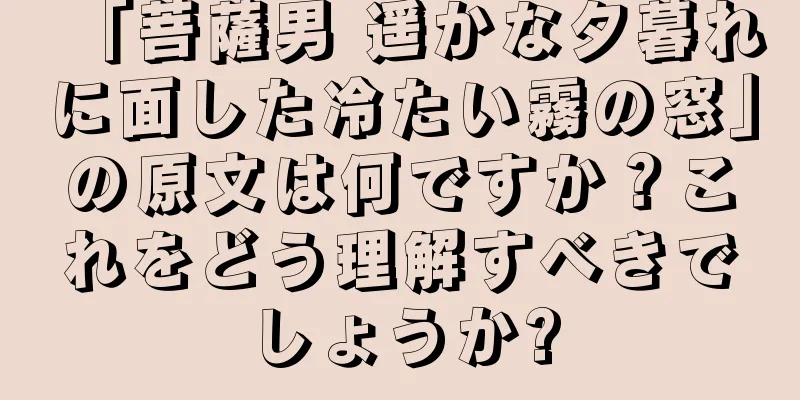
|
菩薩男:遠くの夕暮れに面した冷たく霧のかかった窓 那蘭興徳(清朝) 曇った窓は冷たく、夕暮れは遠くにあります。夕暮れは遠くにあり、曇った窓は冷たいです。カラスが鳴くと花が散り、花が散るとカラスが鳴く。 絹の袖が垂れ下がり、その絹の袖から薄い影が垂れ下がっています。風が赤い糸を切り、赤い糸は風によって切られます。 翻訳 霧のかかった窓は暗くなる夕暮れの空に面しており、夕方の空は窓の上の霧のかかった花に遠くから面しています。花は枯れ、カラスは鳴いています。カラスが鳴き始め、花が散る季節となりました。 絹の袖を垂らした姿は、とても痩せて見えました。その痩せた人物は袖を垂らしていた。そよ風が赤い糸を切り、その赤い糸はまるで春風のようにきれいに切られています。 感謝 この詩は2行ごとに回文で繰り返されます。 「霧のかかった窓は冷たく、遠くの夕暮れに面している。」最後の単語「夕暮れ」から逆から読むと、次の文は「薄暗い空は遠く、霧のかかった窓に面している。」となります。「花は散り、カラスは泣いている。」逆から読むと、次の文は「カラスは泣いていて、花は散っている。」となります。これは回文の一種です。この詩は一般的な詩集にはあまり選ばれませんが、その理由は非常に単純です。純粋な言葉遊びであり、芸術的価値や深い意味合いを含んでいないからです。これはまったくその通りです。回文詩のほとんどは単なる言葉遊びで、料理人が彫った見事な大根の花と同じです。どれほど美しくても、メインの料理の横にある飾りにすぎません。しかし、料理人が大根の花を彫ることをいとわないのには2つの理由があります。1つはテーブル全体の料理の値段を高くするためであり、もう1つは自分の腕を披露するためです。これは人間の本性です。普通の人よりも優れたスキルを習得した場合、それを披露せずにはいられません。披露する機会がなければ、環境からの刺激を受けて「披露したくてうずうず」することになります。 詩文の文体から見ると、前半で場面を設定し、後半で感情を表現したり、物語を語ったり、推論を作ったりするのが宋詩の基本的な構成パターンです。回文の歌詞は一般的にこのパターンで書かれています。前半部分の関連するオブジェクトとシーン(曇った窓、夕暮れ、散る花、カラスの鳴き声など)は、繰り返しの繰り返しの後に、曇った窓、夕暮れ、散る花、カラスの鳴き声に変わります。実際のアイテムは追加されていません。詩の後半では、登場人物の外見の変化を通して物語が語られます。絹袖薄影風切紅絹から絹袖薄影風切紅絹に変わり、同様に何も追加されませんでした。舞い散る花や鳴き声を背景に、風切紅絹、風切紅絹の変化を通して優美な姿を見せる女性に他なりません。これが回文の秘密です。 この詩は私たちの目の前にある風景を描写しています。あまり意味はありませんが、時代を超えたユニークな詩です。このことからも、詩人の洗練された文章力も伺えます。 背景 この詩が作られた正確な年は不明です。詩は清朝において社会的な交流の手段であり、文人や学者の間の会話の主な内容でした。詩のゲームを通じて誰もが簡単に社交界に溶け込むことができ、アイデンティティに関係なく誰もが参加できます。作者はこの詩を社交行事中に書いた。 |
<<: 『柳美仁:春の恋は梨の花が散るまで』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
>>: 『菩薩男:なぜあなたは簡単に去っていくのかと問う』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
推薦する
唐の皇帝高祖李淵の10番目の娘である南昌公主と、南昌公主の夫についての簡単な紹介です。
南昌公主(または南康公主)は唐の皇帝高祖李淵の10番目の娘である。生没年は不明である。蘇旭と結婚。南...
太平広記・第44巻・仙人・田さんの原作の内容は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
「鳳楽亭」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
フェンレパビリオン欧陽秀(宋代)秀が楚を治めた翌年の夏、人々は楚の水が甘くて飲み始めました。楚の人々...
『紅楼夢』で賈宝玉を大観園に住まわせた元春の目的は何だったのでしょうか?
『紅楼夢』を読んだ人なら誰でも、グランドビューガーデンについて知っているでしょう。本日はIntere...
古典文学の傑作『太平天国』:刑法第13巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
人生ののんびりとした楽しさを描いた4つの詩を振り返ると、詩人たちはどのような情景を描いたのでしょうか。
各王朝の文人や詩人は、人生のゆったりとした楽しさをよりよく捉えることができ、人生の味わいをじっくり味...
紅楼夢 第110話 月夜の大観園の幽霊と三華寺の神兆の兆し
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
西晋の時代、洛陽の貴族の間では贅沢が流行していました。富を競い合っていた最も裕福な男性は二人いましたか?
西晋の時代、洛陽の貴族の間では贅沢が蔓延しており、多くの富裕層や官僚が集まって互いに競い合い、富をひ...
古龍の武侠小説『陸小鋒伝』に登場する西門垂涎学の紹介
西門初学は、その卓越した剣術で武術界に名を残した。彼は生来、孤独で、笑うこともなく、剣に夢中だった。...
小説『紅楼夢』の薛叔母さんはなぜ賈家の誰も演劇に誘わなかったのでしょうか?
薛叔母は小説『紅楼夢』の登場人物で、王夫人の妹です。 Interesting History の編集...
もし『紅楼夢』の幽三姐が自殺していなかったら、彼女と劉香蓮の結末はどうなっていたでしょうか?
『紅楼夢』に登場する優姉さんは、とても意志の強い女性です。興味のある読者と『Interesting ...
洪秀全は自らを「真」と名乗ったが、皇帝になる勇気はなかった。一体何が起こっていたのだろうか?
1851年、洪秀全らは金田蜂起を起こし、自らを天王と称し、太平天国を建国した。太平天国では、洪秀全は...
第二奇談集第31巻:孝行息子は遺体を放っておかず、夫のために死んだ貞淑な女性は一緒に棺が運び出されるのを待つ
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
春秋戦国時代の祭祀や音楽はどのようにして崩壊したのでしょうか?礼儀作法の下での戦争とはどのようなものでしょうか?
今日は、おもしろ歴史編集長が、春秋戦国時代の祭祀や音楽がどのように崩壊していったのか?をお届けします...
『賈怡新書』第10巻の「王妃を立てる意味」の原文は何ですか?
昔、聖帝が皇太子を立てるとき、皇太子は朝服をまとい、東から階段を上り、皇后に向かって西を向きました。...