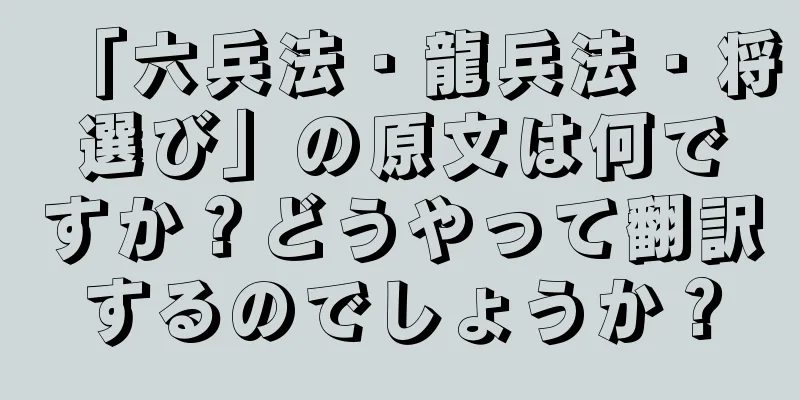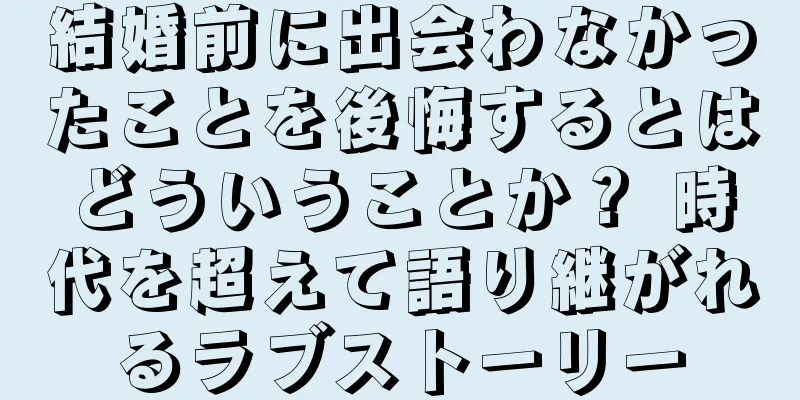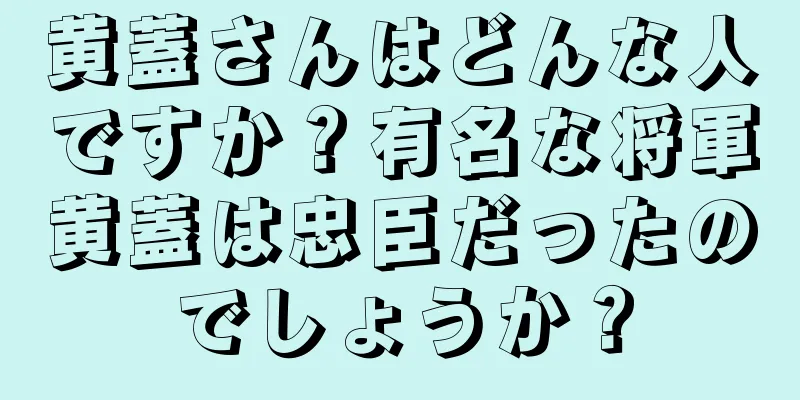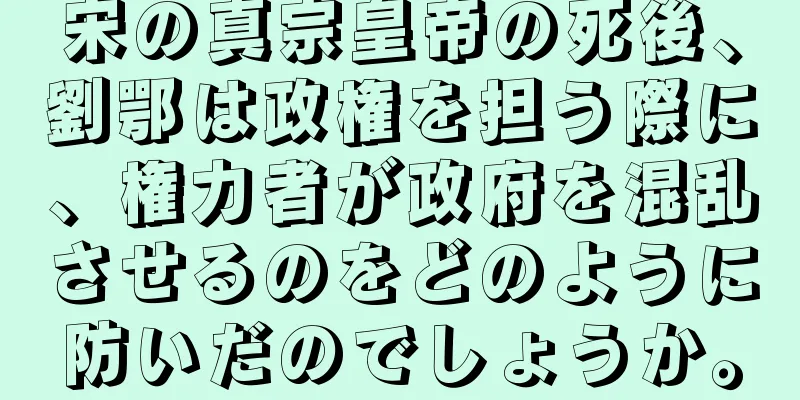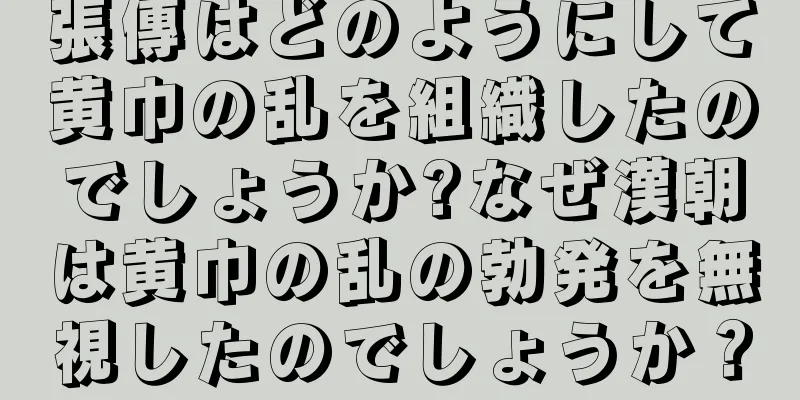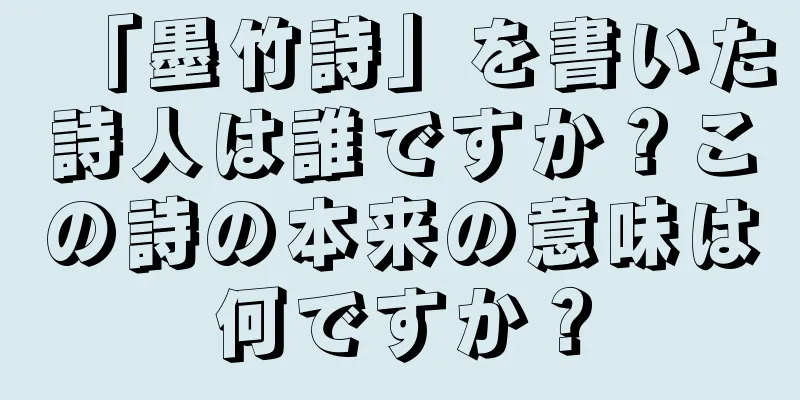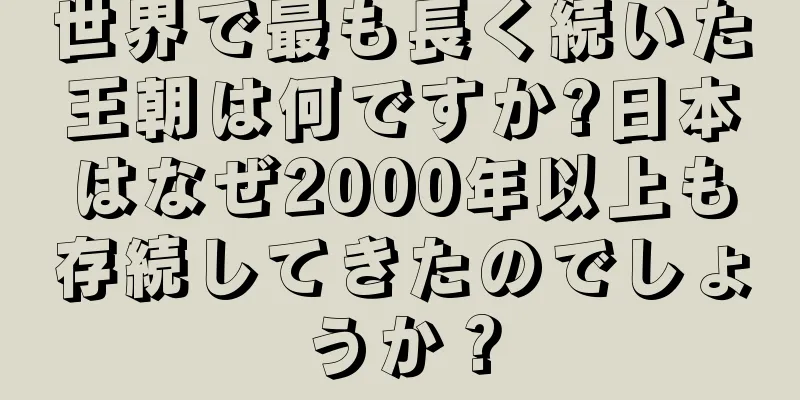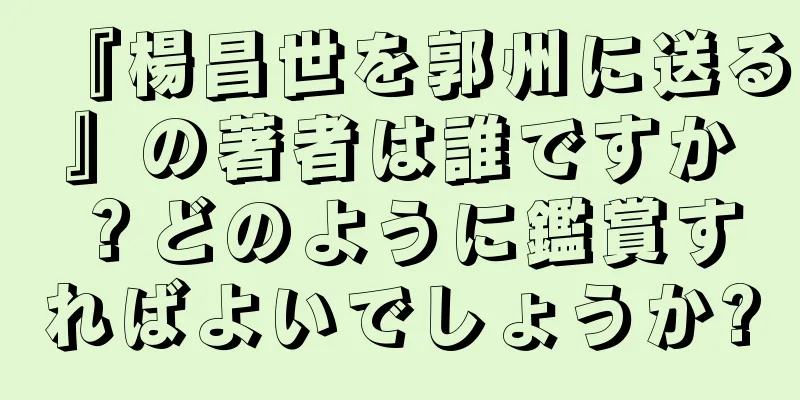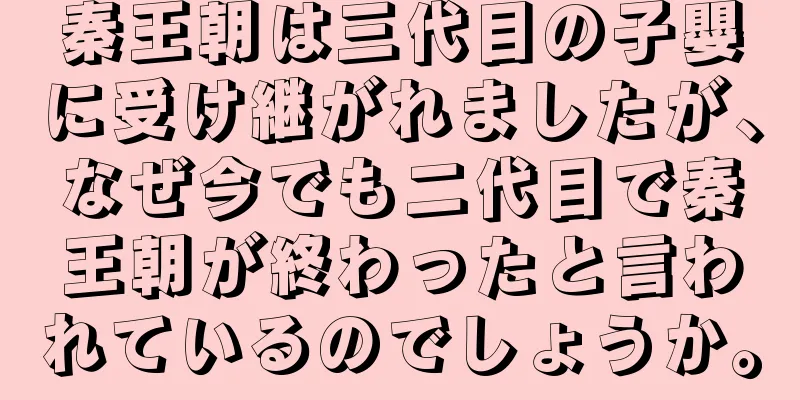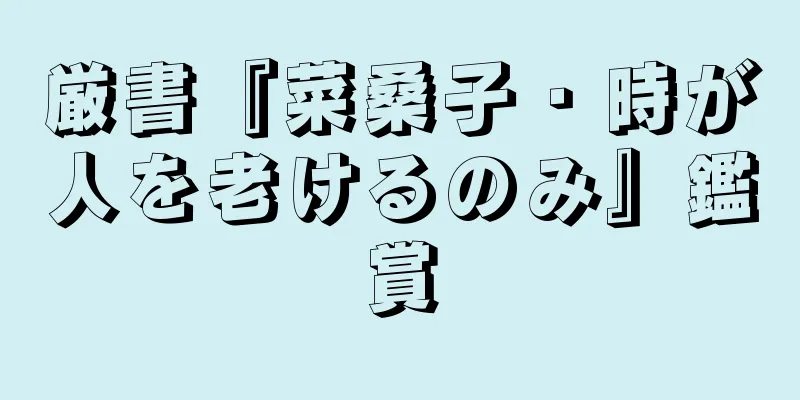薛安福の「清東園・西高亭」は停滞感や堅苦しさを感じさせず一気に完成した
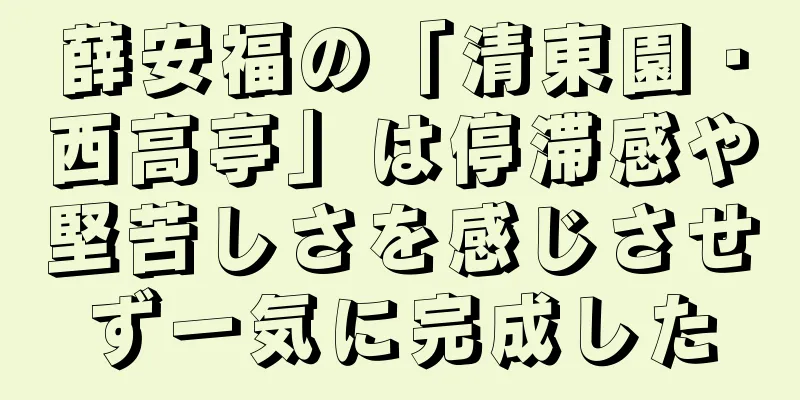
|
薛昊甫(1267-1359)は元代の紀書家であった。ウイグル人。彼の本名は薛超武であり、彼は自分の名前の最初の文字を姓として使用しました。私たちの祖先は内陸部へ移動し、淮孟路(現在の河南省沁陽市)に住んでいました。彼の祖父と父はともに丹公爵の称号を授けられた。彼の漢姓は馬、雅号は九高なので、馬挺夫、馬九高とも呼ばれています。趙孟頌の『宋学斎集序』によれば、彼はかつて劉晨翁(1234-1297)の弟子であったとされており、大まかに元代初期に生まれたと推測できる。江西省知事、瑞院副長官、太平路行政長官、衢州路行政長官を歴任した。薛昱甫は篆書に優れ、詩文でも有名であったが、詩集は失われてしまった。彼の詩は『黄元風雅后日』や『袁世宣』などの詩集に収められている。それでは、次の興味深い歴史編集者が、薛安復の『清東源・熙高亭世行』をお届けしますので、見てみましょう! 京東院·西開亭 薛安夫(元代) 邢は家賃を徴収できなかったので、歓は酒を届けに来た。酔っ払っても詩のインスピレーションは残ります。黄色い花がまた咲き、若々しい顔色も相変わらずみずみずしいので、忘れるにはいい時期です。国家を統治するなら、カニなしではいられません。 この歌の最初の 2 行は、重陽の節句に関する 2 つの有名な古代の物語を巧みに対比し、巧みな並行表現と密接に関連した内容を使用して、その後の物語と議論へと導きます。そのうちの一つは、慧洪の『冷宅夜話』に記録されている。北宋時代の潘大林は詩作が得意だったが、彼の家は非常に貧しかった。かつて、臨川の友人謝易が彼に手紙を書いて「最近、新しい詩を書きましたか?」と尋ねた。大林はこう答えた。「秋の風景はどれも美しいが、俗悪さに埋もれているのが残念だ。昨日、ベッドに横たわっていると、森の中の風雨の音が聞こえたので、壁にこう書いた。『重陽の節句が近づくと、街全体が風雨に覆われる』。突然、地代取りが来て催促したので、私は諦めた。この一文だけ送るつもりだ。」これが有名な「一文詩」の物語である。 2つ目は、肖童の『陶淵明伝』からの引用です。「九月九日、私は外に出て家の脇の菊の花の間に座っていました。しばらくすると、私の手は菊でいっぱいになりました。その時、志洪が酒を持ってきました。私はすぐにそれを飲み、酔って家に帰りました。」著者は、人生で潘大林のように「取り立て人」に失望したという同じ経験をしたわけではないかもしれません。ここでの「取り立て人によって台無しにされた喜び」は、日常生活のさまざまな世俗的な出来事の典型的な反映にすぎません。元の単語は「just in the mood」ですが、「失敗」という言葉が最初に出てくるのは、「喜びはワインを送ることから来る」ということを強調する目的があります。後者の文は、前の文の準備のおかげで、著者が飲酒を楽しむときの幸せで楽しい心の状態とより鮮明に対比されています。これは創作文を書く際に、まず批判し、次に賞賛するという手法です。したがって、3 番目の文は、「お酒を飲んでいると、詩のインスピレーションが残る」と指摘しています。家賃の請求など、不快なことで気分が落ち込むこともあるが、ワインに酔っている限り、その魔法の力のおかげで「詩的なインスピレーションは依然としてそこに存在する」。作者の手に負えない、抑えきれない情熱が余すところなく表れています。 最初の2つの文の失望と満足の対比が、世の中の優雅さと俗悪さの鋭い対立を浮き彫りにしているのに対し、真ん中の「黄色い花がまた咲いている」と「バラ色の顔は色あせていない」という2つの文は、赤と黄色の対比を通して、人間と自然の調和した状態を十分に表現しています。菊が咲くのは、陶淵明の「九月九日に菊を手に持つ」という故事に基づく。彼女の美しさが衰えていないという事実は、著者が絶望的で面白味のない歩く死体ではなく、人生に対する熱意に満ちた人物であることを示している。秋は一年の中でも何と素晴らしい季節であり、人生の中でも何と素晴らしい時期であり、「忘れるのにちょうど良い時期」です。著者の飲酒と詩に対する気分は、世俗的な雑念を排除し「忘れる」ことの結果です。忘れる根拠は、第一に「黄色い花がまた咲いている」ということ、第二に「若々しい顔が色褪せていない」ということである。前者は「西高亭」の美しい風景を表現し、後者は作者の高尚な野望と何かを成し遂げたいという願望の内面世界を表現したものです。 この時点で「気分に合う」というタイトルは完全に満たされており、この歌の美しさは、最後に「どんなに大きい県でも、カニは欠かせない」という奇妙で大胆な2つの言葉が付け加えられていることにあります。これもまた暗示です。欧陽秀の『帰郷記』第2巻には、「昔、邵慶に千坤という人がいた。彼の家は余杭の出身で、余杭の人々は蟹が好きだった。坤はかつて他の県に赴任しようとした。人々は彼にどの州に行きたいかと尋ねた。坤は『蟹はいるが知事はいないなら、それでいい』と言った」と記されている。この話は、奔放で気ままな文人たちに高く評価された。例えば、蘇軾には「王に護符の竹をお願いしたいが、蟹も知事もいないのではないかと心配だ」という詩がある。作者は、銭坤が蟹は持っているが建州は持っていないという状況を「建州がいても何の役にも立たない」と少し変えた。つまり、近くに建州があっても大したことではないということであり、官僚の束縛に対する軽蔑を表している。 「蟹」も重陽の名物です。馬志遠の詩「夜船 秋思」には「紫蟹を霜と分け合い、酒を煮て紅葉を燃やす。人生は有限だと思うのに、重陽の節句をいくつ無駄にしているのか」とあります。 『新世界物語』によると、東晋の狂人である畢卓はかつて「右手に酒杯、左手に蟹の爪を持ち、酒船に浮かんでいれば、一生これで十分だ」と自慢したことがある。この歌の「蟹は欠かせない」という部分は、「酒とともに喜びが訪れる」という表現を再確認し、補足している。最後の2つの文は、精神と気質において、畢卓の大胆な言葉とまったく同じです。 この歌は、著者の学者としてのかなり自由奔放で奔放な性格と、官僚制度の束縛に対する軽蔑を表現している。作品全体は暗示を多用し、緩慢さや堅苦しさを感じさせずスムーズに流れます。彼の作風は自由奔放かつ大胆であり、三曲スタイルの意味と哲学を深く理解しています。 |
<<: 薛安甫の『蔡紅秋:名声と成功は千里を越えるツバメのように忙しい』:作品全体が大胆で、鋭く、機知に富んでおり、言葉は真珠のようです。
>>: 陸志の「一歩一歩-洞庭陸橋寺壁銘」:3つの異なる対比を深く表現
推薦する
『西遊記』で、魏徴はなぜ景河の龍王を殺そうとしたのでしょうか?
『西遊記』では、景河の龍王は龍なのに、なぜ魏徴によって斬首されたのでしょうか。この点についてよく分か...
隋代の詩『船頭歌』をどのように鑑賞すればよいでしょうか?この詩の本来の内容は何ですか?
船頭の歌 [隋代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょ...
諸葛亮は生涯で5回も火攻めをしましたが、なぜ籐の鎧を着た兵士を焼き払うことに感情を表現したのでしょうか?
彼の功績は三国に及び、八卦陣によってその名が知られるようになった。諸葛亮は計算が得意で、軍を指揮する...
ルネサンス芸術の特徴を明らかにし、ルネサンスを評価する
中世は17世紀にヨーロッパ人によって発明されました。それは西暦600年から1500年までの期間を指し...
トゥ族の習慣 トゥ族の人々は日常生活でどのような習慣を持っていますか?
全国には192,573人のトゥ族がおり、虎竹トゥ族自治県、民和回族・トゥ族自治県、大同回族・トゥ族自...
「兵法書」における火攻めの条件は何ですか?火攻戦の技術と原理!
今日、Interesting History の編集者は、「兵法」の「火攻めの章」の分析をお届けしま...
安史の乱は8年間続きました。なぜ安禄山と史思明は息子たちに殺されたのでしょうか?
安禄山と史思明に非常に興味がある方には、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しているので、見てみましょ...
燕と黄の子孫という称号は、実は伝説に由来するものなのでしょうか?
神話の時代が終わり、伝説の時代が始まりました。この時代には真実がほとんどないとはいえ、それでもいくら...
なぜ西漢は匈奴と和平を望んだのでしょうか?
いわゆる婚姻同盟とは、一般的には中原王朝と国境地帯の少数民族指導者との婚姻関係を指す。この関係は...
「自分の気持ちを他人に伝えるのは難しい、だから青い空と明るい月にしか伝えられない」という有名なことわざはどこから来たのでしょうか。
まだ分からない:有名な言葉「私の気持ちを人に伝えるのは難しい、私が伝えることができるのは空の月だ...
賈宝玉が金伝児をからかっているとき、なぜ王夫人は寝たふりをしたのですか?
以下は、Interesting Historyの編集者がお届けする物語です。賈宝玉は金伝児と戯れまし...
古典文学作品『前漢志演義』第九章:趙高は胡海を建国する勅令を偽造した
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣評伝東漢志演義』というタイトルで、明代の中山の隠者...
75mm山砲は大砲です。解放前は重砲は輸入しかできませんでした。
解放戦争時代を映した映画では、75口径の山砲は小型山砲と呼ばれていました。この現象は映画「アセンブリ...
黄甫然の「春思」:詩全体は漢王朝を称え、唐王朝を称賛し、朝廷の好戦主義を風刺している。
皇甫然(717年頃 - 771年頃)は、雅号を茅正といい、安定県朝納(現在の甘粛省荊川県)の出身であ...
古代人はどのように税金を支払ったのでしょうか? 「税金」はどこから来るのでしょうか?
税金といえば、誰もがよく知っているはずです。税金は私たちの生活に密接に関係しており、税金を払うことは...