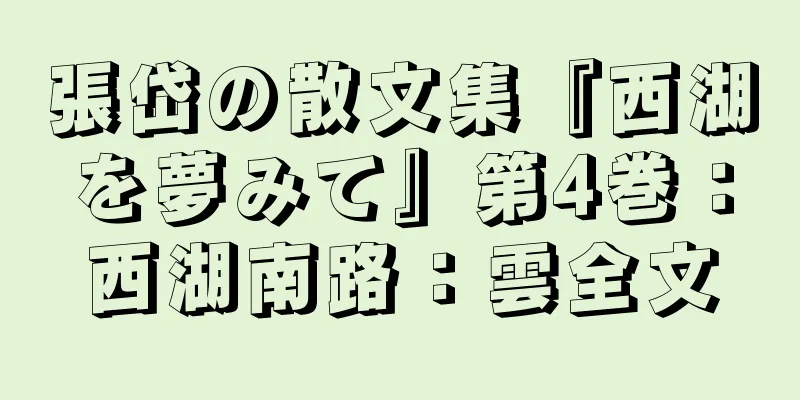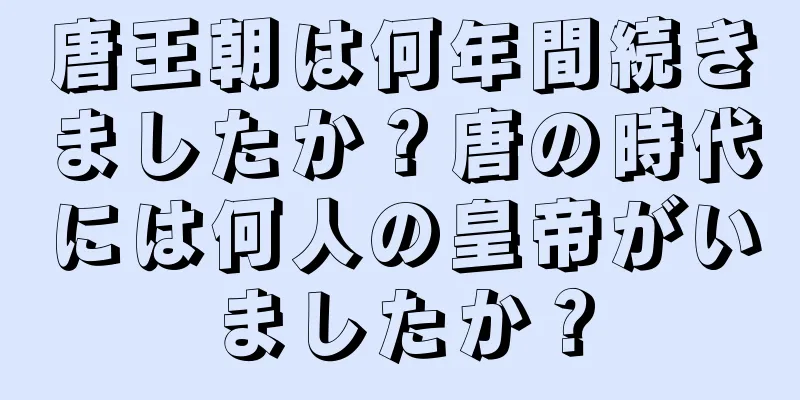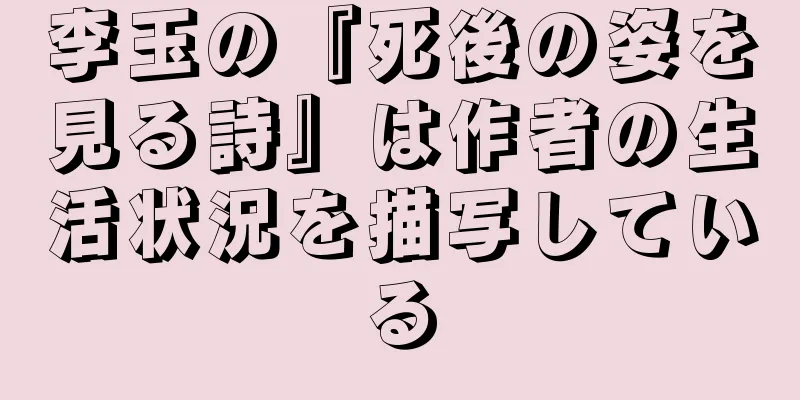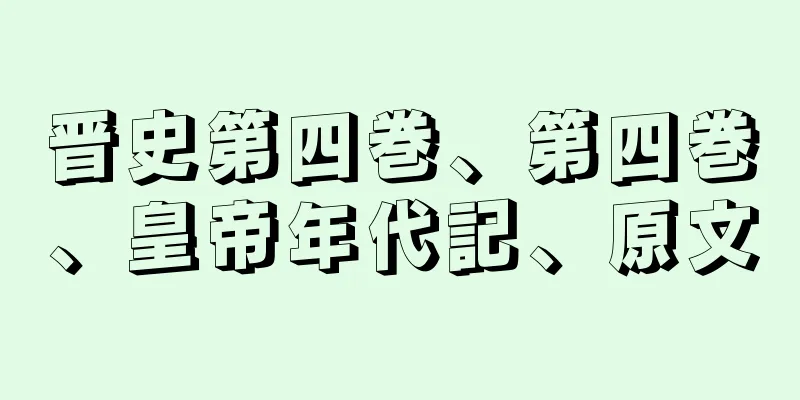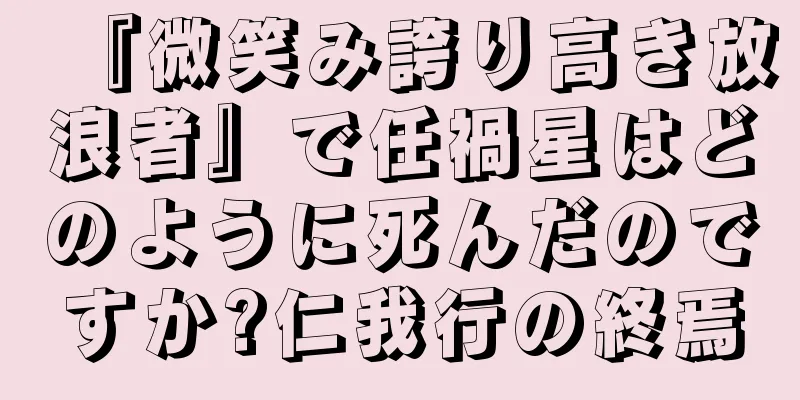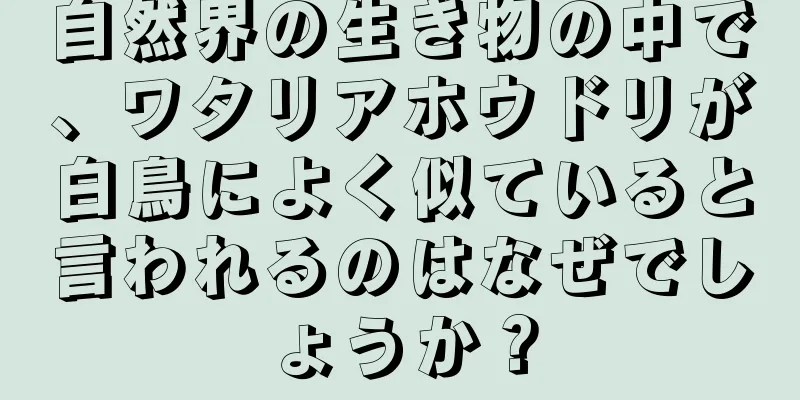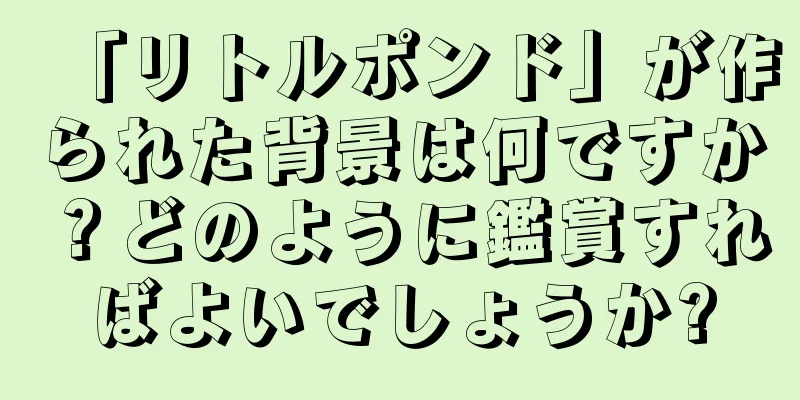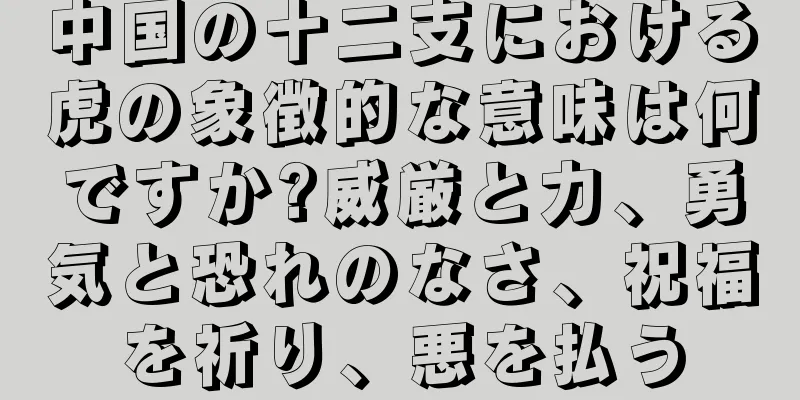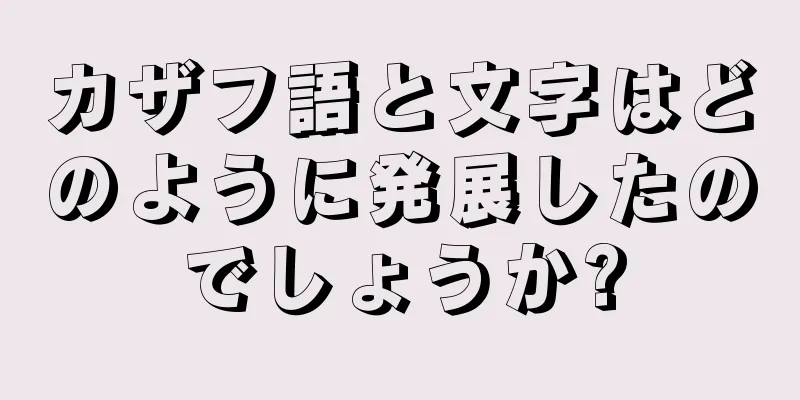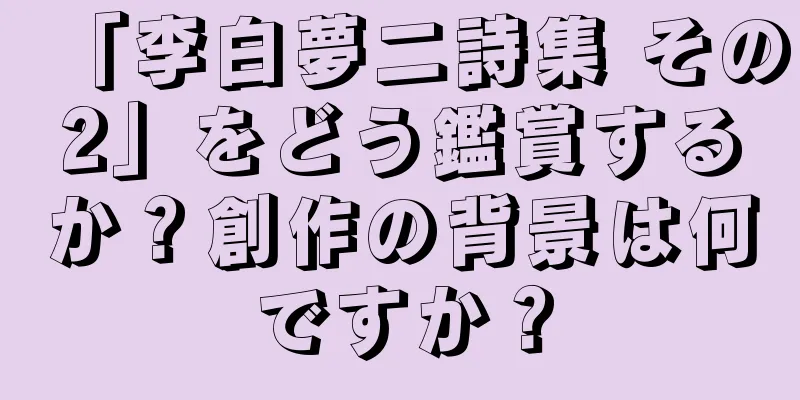劉炳忠の「南湘子・南北短長閣」:人生に対する前向きな見方を表現している
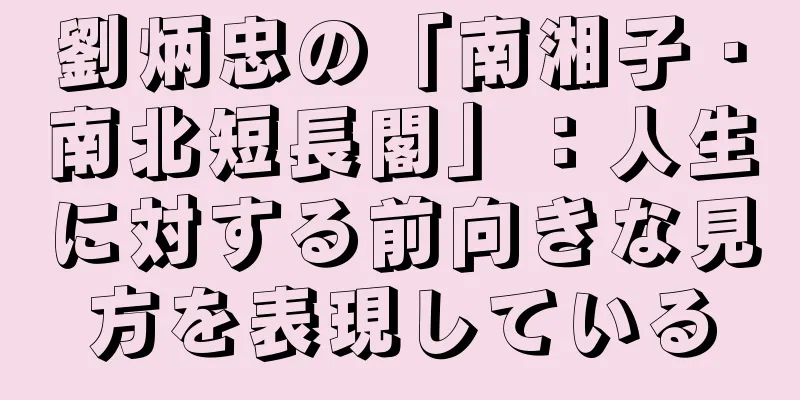
|
劉炳忠(1216-1274)は、本名は劉観、雅号は鍾会、号は蒼春三人で、邢州(現在の河北省邢台市)の出身である。彼は仏教を信仰していたため、名前を子聡と改め、官職に就いた後、名前を劉炳忠と改めた。元代の優れた政治家、作家。劉炳忠は元代初期の非常に特徴的な政治家であり、元代の政治体制や規則の確立に重要な役割を果たしました。同時に、彼は詩、作詞、音楽に精通した作家でもあります。彼は智遠11年に亡くなった。元の王朝の施祖は彼に太夫の爵位を授け、趙公の爵位を授け、諡号を文鎮としました。元朝の皇帝成宗の治世中に太師の称号を贈られ、諡号は文徴に改められた。元朝の仁宗皇帝の治世中に、彼は死後に常山王に任命されました。それでは、次の興味深い歴史編集者が劉炳忠の『南湘子・南北短閣』をお届けします。見てみましょう! 南湘子・南北短長亭 劉炳忠(元代) 南北に長い亭と短い亭があり、旅人は無情だが客人は情深い。私は何年も乗馬をしていますが、何を成し遂げたでしょうか? 私の短い髪には、数本の白い雪が垂れ下がっています。 私の寂しい家にはランプが一つだけあり、毎晩私が本を読むときにはそのランプが灯されます。窓の外には数本の竹が荒涼としていて、時折西風と雨の音が聞こえます。 伝説によると、李白の『菩薩行』では、旅人が故郷に帰りたいという願いを次のように表現している。「どこに帰る道があるか、長い楼閣と短い楼閣」。この詩の冒頭はここから借用されている。 「短亭・長亭」とは、短亭と長亭のことで、古代に道路脇に歩行者の休憩のために設けられていたあずまやのこと。于鑫の『江南哀歌』には「五里、十里ごとに長楼、短楼あり」とある。これは、十里ごとに長楼があり、五里ごとに短楼があるという意味である。古代の詩における「長端亭」のイメージは、常に放浪の観念と結び付けられてきました。この詩では、作者はさらにその前に「南北」という言葉を加え、この長い「旅」をさらに果てしなく憂鬱なものに見せたため、作者はそれを「無情」と呼んでいます。旅の長さ自体が実は人間の感情であり、それを「無慈悲」と呼ぶのは人間の感情の投影です。したがって、この「無慈悲な旅」は実際には「人間の感情」の現れです。「無慈悲」を「感情」と対比させることで、「感情」の激しさと深さをさらに強調します。この作品は、その後、長い期間の観点から「何年も」旅を続ける苦しみをさらに描写していきます。作者は別の詩『南湘子』の中で、「放浪者は世界を旅し、野の煙を離れた直後に砂漠に戻る。毎年寒食節に、彼は家を持たない」と書いている。これらの詩節は、毎年の「鞍馬」の旅の人生の脚注と見なすことができます。作者が耐え難い思いをしたのは、果てしない放浪の苦しみだけではなく、何も成し遂げられず人生を無駄にしてしまったという後悔でもあった。「何の功績も」という言葉は、詩人の後悔の深さを示しており、数少ない「雪茎」は、彼の悲しみをさらに際立たせている。道は長く、帰る日も遠く、慌ただしい旅の途中で、髪はすでに霜と雪に染まっていますが、出世はありません。放浪息子の悲しみ、後悔、混乱が一層一層極限まで押し上げられ、歌詞に浸透しています。 詩の後半は放浪者の孤独を描写することに焦点を当てています。最初の2つの文は、寒い夜に読書をしている場面を描写しています。宋代の黄庭堅の詩『東黄季譜』の一節「春風に酒一杯、河湖の夜雨に灯る十年」は詩人の作品の基礎になっているようだが、詩に書かれているのは作者の実際の生活の描写であるはずだ。 「ランプ」のイメージが興味深いです。それは旅人の孤独な家だけでなく、主人公の孤独な心も照らします。長い旅の間、彼に慰めをもたらし、耐え難い孤独と悲しみから逃れさせてくれたのは「本」だけだった。この「ランプ」によって、荒涼として冷たい詩的な情景全体に、突然、少しばかりの暖かさが加わります。燭台、ランプスタンド、燭台、ここでは測定用語として使用されています。同時に、夜にランプの下で読書をするプロットは、主人公の高貴で優雅な心を人々に示しています。詩の後半の「窓の外のいくつかの紳士竹」は、この心の象徴です。 「荒涼」という言葉は、寂しく寒い環境にありながら、優雅で魅力的な竹の性質を正確に表しています。古人は松、竹、梅、蘭を君子の四友と呼んでいたので、作者はここで竹を直接「君子竹」と呼んでいます。詩人がここで直接「君子竹」という言葉を使用したのは、時代に左右されずに堂々とした昔の君子の風格に対する尊敬と追求を表現するという深い意味があります。最後の行「時には西風が雨を散らす音とともに」は、竹を聴覚の観点から描写しています。西風がサラサラと音を立て、竹の葉がサラサラと音を立て、まるで風が雨を吹き飛ばしているかのようです。明らかに、行間から伝わってくるのは「竹紳士」の奔放で大胆不敵な精神であり、孤独や冷たさを恐れず、優雅な志を捨てない詩人の精神が伝わってきます。竹の音は「時々起こる」と余韻が続く。言葉は終わっているが、意味は尽きていない。 この詩と唐代や宋代の家から離れた気持ちを表現した作品との明らかな違いは、詩人が孤独や悲しみの感情に囚われていないことです。前半は放浪の苦しみについて語り、作者はそれを誇張しようと全力を尽くしていますが、これは単なる前置きです。後半では、「ランプ」を掲げて悲しみの雲を払い、読書をして志を明確にし、青竹について書いて自分の気持ちを表現し、人生に対する前向きな見方を示しています。王鵬雲が劉炳中の詩について「荘厳で広大でありながら、俗悪な感覚を失っていない」(『蒼春月譜追記』)と評したように、「悲しいが悲しくない」と言えます。 |
<<: 劉炳忠の『木蘭花漫・渾身后譜』:詩全体が叙情性と議論性を兼ね備えている
>>: 唐寅の「花の下で飲む」:4つの文章をセクションに分け、段階的に進めていく
推薦する
漢民族の礼儀作法:漢民族は祖先や年長者を尊重する習慣がありますか?
祖先を敬い、年長者を敬うのは漢民族の古くからの習慣です。先祖を敬うということは、彼らを崇拝するという...
趙明成は側室を娶った。宋代の碑文学者趙明成の詩のレベル
趙明成、通称徳福は山東省諸城の出身である。彼は宋代徽宗の治世に宰相を務めた趙廷之の三男であったが、後...
北宋の宰相樊志には息子がいましたか?樊志の息子は誰でしたか?
范之(911-964)、号は文粛、大明の宗城の人。五代後周から北宋初期にかけての宰相。彼は子供の頃か...
済公第184章:王三虎が大悲院の秘密を明かし、空中で雷鳴を響かせて鉄面仏を捕らえる
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
薛玄の妻は誰ですか?薛玄の妻、景武公主の伝記
薛軒、号は甘君、生没年不詳。東海潭県(現在の山東省潭城市)の人。前漢の宰相で、景武公主の夫。高陽侯の...
観音の地位がなぜそれほど高いのでしょうか?観音の起源は何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が観音の起源についてご紹介します。皆さんのお役...
七剣十三英雄第111章:元帥は勝利を報告し、武宗は軍事的功績に基づいて彼にさらに高い称号を授けた
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
「花影」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
花の影蘇軾(宋代)翡翠テラスには埃が何層にも積もっていて、何度子供たちに掃き掃除を呼びかけても、拭き...
家庭の子供たちの英雄の第33章(パート1):沈庭勲は義父から農業について学び、家事の手伝いをするように誘うのが楽しい
本日、Interesting History の編集者は、小説「家族の子供たちの英雄」の第 33 章...
クラゲに遭遇したら人間は刺されるのでしょうか?毒クラゲに刺されたらどうすればいいでしょうか?
クラゲは見た目は美しくおとなしいですが、実は非常に凶暴です。傘のような形の体の下にある細い触手は消化...
『紅楼夢』でタンチュンはなぜ悲劇の登場人物なのでしょうか?悲しみはどこにありますか?
『紅楼夢』の登場人物、丹春は金陵十二美女の一人です。今日は『おもしろ歴史』編集長が記事をお届けします...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第17巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
唐代末期の政治情勢が徐々に崩壊していく中、詩人たちはどのような感情を詩に表現したのでしょうか。
唐代末期、社会は混乱し、政治情勢は徐々に崩壊しつつありました。後期唐詩に影響を与えたのは、強い感傷的...
蘇軾は宋人宗によって将来の宰相とみなされていた。なぜ韓奇は蘇軾をすぐに宰相に任命すべきではないと提案したのか?
韓起はかつて蘇軾が勅撰者と日録者に任命されることに反対しました。それはなぜでしょうか?なぜ韓起は蘇軾...
尚官万児が山や川の澄んだ音を描写した詩にはどのようなものがありますか?長寧公主柳北池の鑑賞
上官婉児が山や川の澄んだ音を詠んだ詩を知りたいですか?どのように詠んだのでしょうか?今日は、Inte...