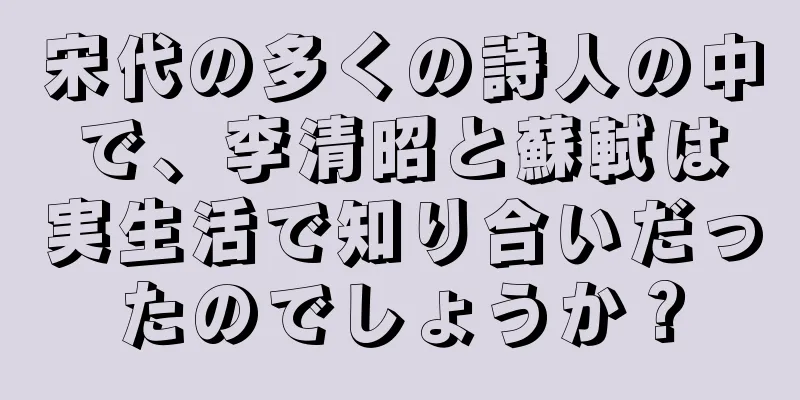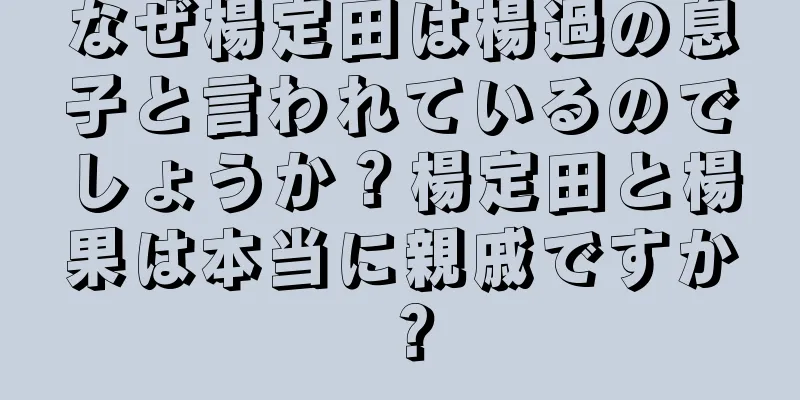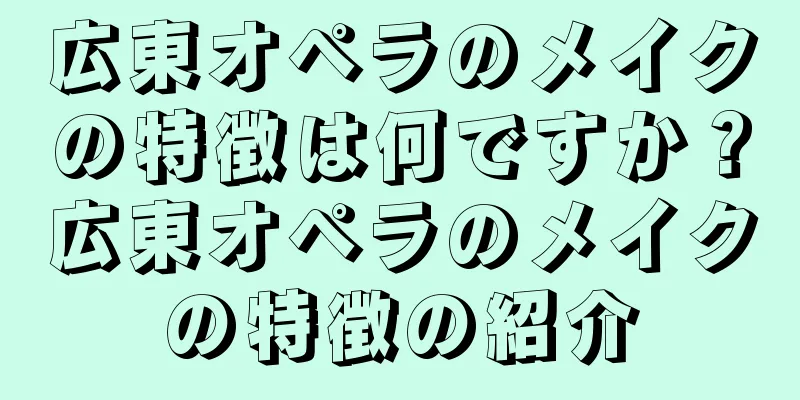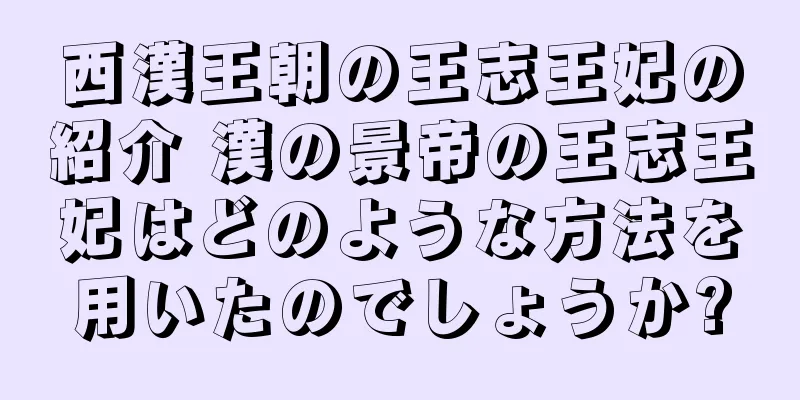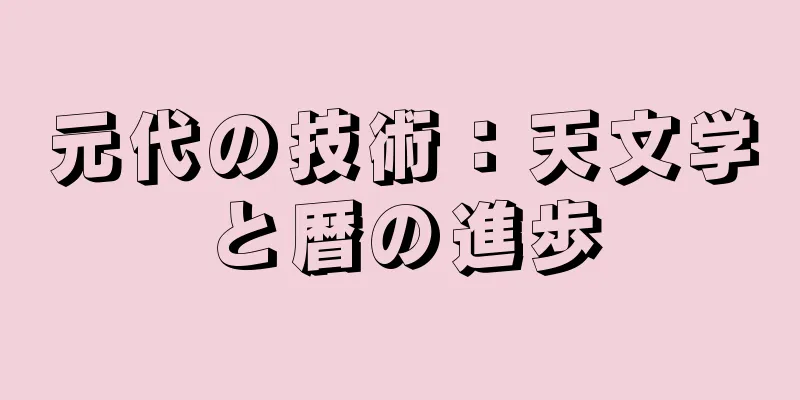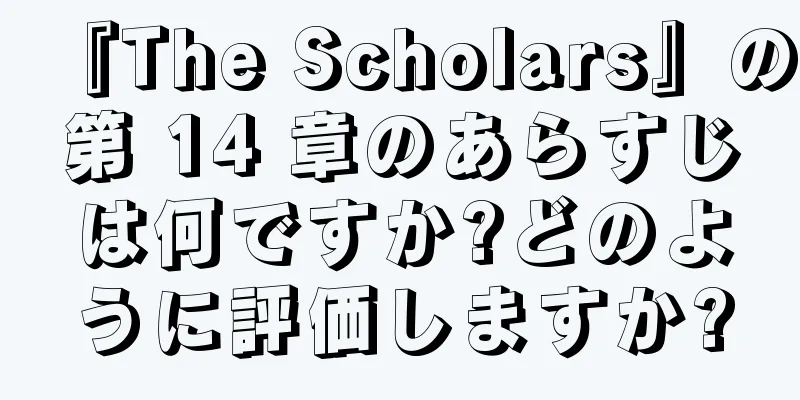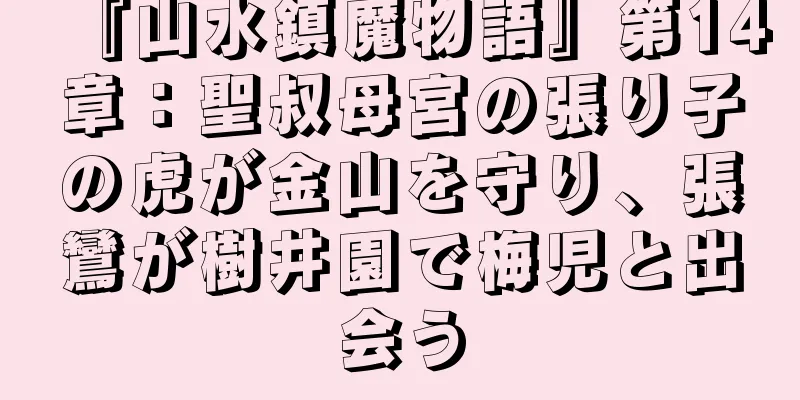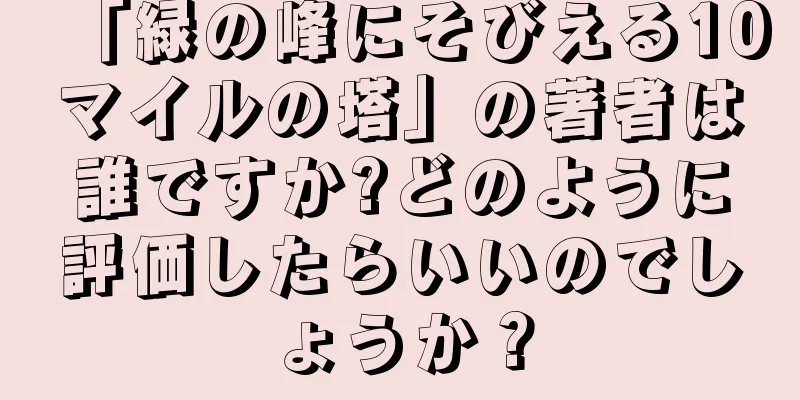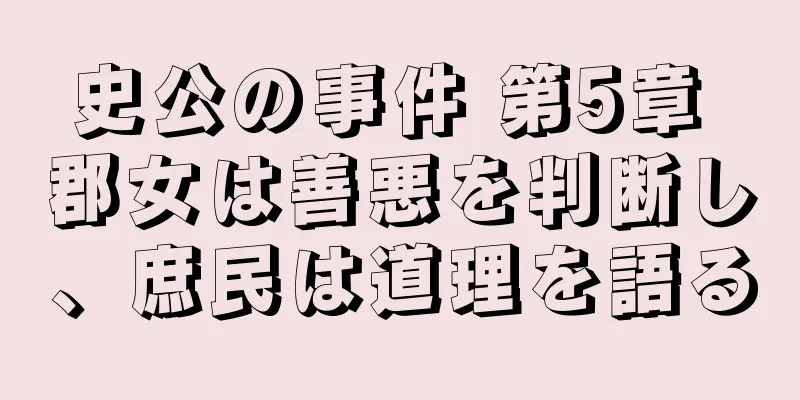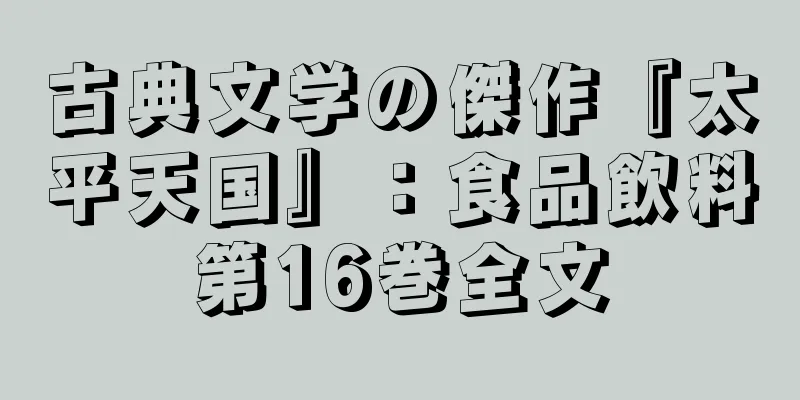蒋宗の「九月九日、長安から揚州に戻り、衛山閣に行った」:詩全体が情景と感情を表現している
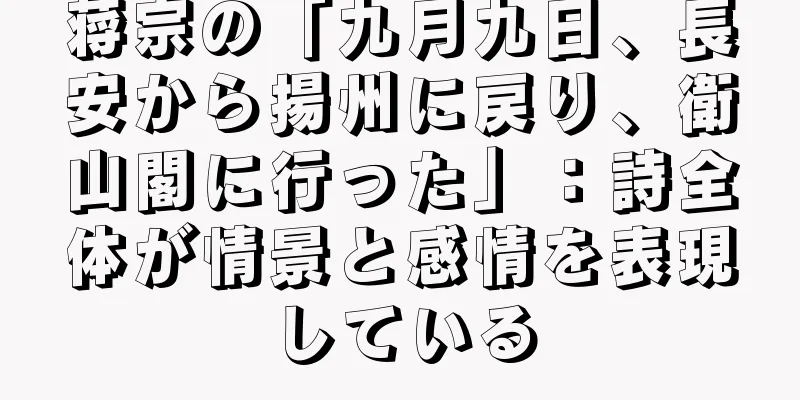
|
蒋宗(519-594)は、南陳王朝の有名な大臣であり作家でした。彼の雅号は宗麟であり、彼の先祖の故郷は済陽市高城(現在の河南省蘭嶼)であった。彼は貴族の出身で、子供の頃から頭が良く、文学の才能がありました。 18歳のとき、彼は宣恵武陵王の宮殿で武官として仕え、後に尚書の宮廷侍女に昇進した。彼の詩は梁の武帝に高く評価され、礼部大臣に昇進した。張尊、王雲、劉志林は当時の優秀な学者であり、年齢の差に関係なく蒋宗牙を尊敬し友人となった。侯景の乱の後、会稽に逃れ嶺南に住んだが、陳の文帝の天嘉4年(563年)にようやく建康に呼び戻され、中書記に任命された。陳后柱の治世中に宰相を務めたため、世間では「明江」と呼ばれた。在任中、「彼は常に権力を握っており、政務を執らず、皇帝と裏庭で宴会をしながら日々を過ごした」ため、「その結果、国政はますます悪化し、規律はもはや確立されなくなった」(陳書、蒋宗伝)。隋の文帝の治世中の開皇9年(589年)、陳王朝は滅亡した。蒋宗は商開府として隋に入朝し、後に江南に解放され、江都(現在の江蘇省揚州)で亡くなった。それでは、次の興味深い歴史編集者が、蒋宗の「九月九日に長安から揚州に戻り、威山閣まで歩く」を紹介します。見てみましょう。 長安から揚州に戻り、九月九日に衛山閣で詩を書いた。 蒋宗(南北朝) 私の心は南の雲を追い、私の体は北のガチョウを追います。 今日は故郷の塀の下の菊が咲いています。 この詩は作者が晩年故郷に帰省した際、微山亭を通りかかった際に詠まれたものです。この詩は、主に南雲と北雁を通して詩人の故郷への思いを表現し、故郷の柵の下の菊を尋ねることで詩人の切実な郷愁と帰還の願いを表現しています。詩全体は場面に応じた感情を表現しており、その感情は比較的微妙です。 詩の最初の行は「私の心は近くの南の雲を追う」であり、豊かな意味が含まれています。まず詩人は故郷を懐かしむが、懐かしさは戻ることができず、空を見上げてため息をつき、南に飛んでいく白い雲に気持ちを向ける。これは陸季の言う「南の雲を指してお金を送る」ということだ。しかし、雲は消えたようで消えておらず、郷愁はさらに痛くなり、私の心は南に漂う白い雲を追いかけることしかできない。蒋宗は郷愁に襲われると、いつも南に流れていく白い雲を見上げていた。詩「長安の使者に会い尚書沛に手紙を送る」では、「目は去る雲を追っても無駄、手は勝手に琴を弾く」と述べており、郷愁の気持ちが今も表現されている。 『季荘上書』で表現されている感情が無力感だとすれば、ここでは作者は故郷に帰る不安な気持ちを強調している。なぜなら、このとき詩人はすでに家に帰る途中だったからです。 2番目の文は「私の姿は北のガチョウに従う」です。前の文が故郷への悲しみと帰国の不安を表現した後、この文は南に到着した喜びを表現しています。詩人は、北から活発に飛んでくるガチョウとともに南にやって来た。故郷に帰りたいという願いが叶いそうなので私は幸せです。私の足取りは速やかなので私は幸せです。 「形は北の雁に従う」という5つの文字は、自由で優雅な印象を与えます。 最初の 2 つの文が組み合わさって最初のひねりが生まれ、対比を通して詩人の故郷に対する深い憧れが表現されています。この二つの文章は、リズムと言葉の選択の面ではバランスが取れており、詩人の優れた言語能力を示しています。また、勢いの面では、文章は流れる雲や流れる水のように活発で迅速であり、故郷に帰る詩人の気持ちをよく表現しています。 最後の2行は「故郷の垣根の下には今日、何本の菊が咲いているだろうか」という問いかけで、作者は郷愁を深めている。故郷に帰る途中、郷愁に襲われ、故郷が目の前に現れようとした時、詩人はふと故郷の垣根の下の菊を思い浮かべた。この思考過程は感情の発展の論理と非常に一致している。垣根の下の菊は具体的なもので、詩人が故郷にいるときによく見るものです。詩人に深い印象を残しました。この印象は詩人の潜在意識に埋もれているので、詩人の故郷への帰還の願いが実現しそうになったとき、突然潜在意識から飛び出し、詩人の故郷の印象がより鮮明になります。詩人はこの時、柵の下の菊を思い浮かべたが、柵の下の菊のことだけを思い浮かべたわけではない。以前からよく見ていた物には、他の多くの出来事や感情が結びついているはずなので、柵の下の菊を思い浮かべたとき、柵の下の菊に結びついている物も自然に自分と結びついていたのである。このように、詩人は、一つの特定の物体の思い出を通して故郷の全体的な印象を呼び起こすのです。この二行の詩が詩全体の感情を深めていることがわかります。この二つの文章のゆっくりとしたペースは、まさに感情の深まりを反映しています。 |
>>: 江宗の『雨雪の歌』:最後の連句は詩全体を要約し、兵士たちの郷愁というテーマを指摘している。
推薦する
なぜ劉表は曹操と天下を争うよりも、その機会を逃すことを選んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
サンチュケタワーとは何ですか?唐の順宗皇帝陵から出土した三階塔の紹介!
本日は、Interesting History の編集者が三楚鵝塔の紹介をお届けします。ご興味のある...
古代における花嫁の輿の要件は何だったのでしょうか?花嫁はなぜ輿に乗るのでしょうか?
古代の花嫁の輿には何が必要だったのでしょうか?なぜ花嫁は輿に乗らなければならなかったのでしょうか?こ...
古代ローマはどんな国だったのでしょうか?漢王朝とローマはどちらがより強かったのでしょうか?
今日は、古代ローマがどんな国だったのかを、おもしろ歴史編集長がお届けします。皆さんのお役に立てれば幸...
何卓の「魅惑の目:静かな川の秋の葦」:別れについての詩
何朱(1052-1125)は北宋時代の詩人。号は方慧、別名は何三嶼。またの名を何美子、号は青湖一老。...
あなたの先祖が誰であるか知っていますか?家系図なしで自分のルーツを辿るにはどうすればいいでしょうか?
あなたは自分の先祖が誰であるか知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Interesting Hi...
『紅楼夢』で西人(シーレン)と宝玉(バオユウ)の関係がなぜこんなにも良好なのでしょうか?
賈宝玉と最初にセックスしたのは誰ですか?紅楼夢第6章:賈宝玉の初体験と劉老老が栄果屋敷に入る皆が急い...
『西遊記』では観音は常に尊敬されてきたのに、なぜ紅坊主はあえて観音を軽蔑したのでしょうか?
『西遊記』では、観音は常に尊敬されてきたのに、なぜ紅坊はあえて観音を軽蔑したのでしょうか?これは多く...
李世民の『古屋を通り過ぎる二つの詩』鑑賞
【オリジナル】古い家を通るときの二つの詩著者: 唐 利世民[初め]緑の戦車は新豊で止まり、喬宜では角...
杜甫の有名な詩の一節を鑑賞する:たとえ私の体は紫色に覆われていても、早く家に帰る方が良い
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
詩の中の詩人の有名な詩句の鑑賞:私は何か感情的なものがあると予想し、それについて考えずにはいられなかった、そしてかつて聞いた
史厳(?-1107)、号は邦梅、河南省開封の出身。北宋時代の大臣。宋代神宗元豊二年(1079年)、科...
七剣十三英雄第156話:盗賊団は要塞を攻撃する際に軍隊を失い、病気を装う計画を元帥に提案した
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
『紅楼夢』の「桃葉渡し場の過去を思い出す」とはどういう意味ですか?この比喩の対象は誰ですか?
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の第一作であり、清代の作家曹雪芹が書いた章立ての小説である。 Int...
10世紀: 唐の滅亡から宋代初期にかけての五代十国時代
10 世紀は西暦 901 年から 1000 年までの期間を指します。この世紀は、唐王朝の崩壊後の大分...
秦克清を守るために、王希峰はどのようにして彼女のスキャンダルを隠蔽したのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...