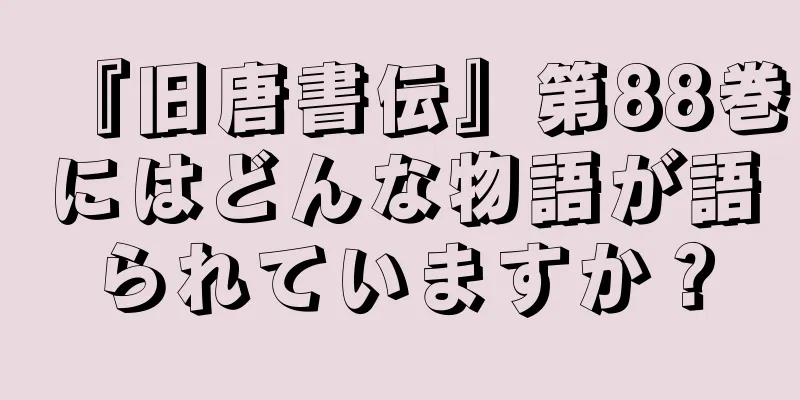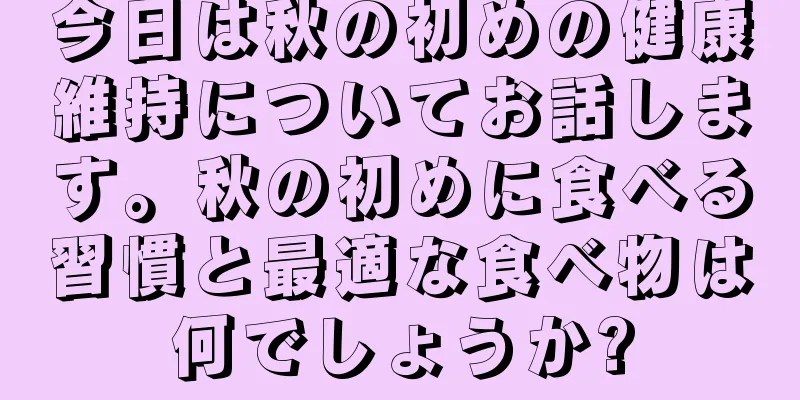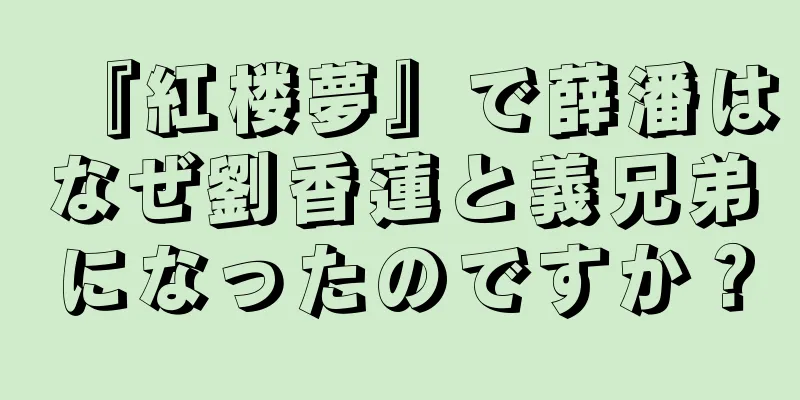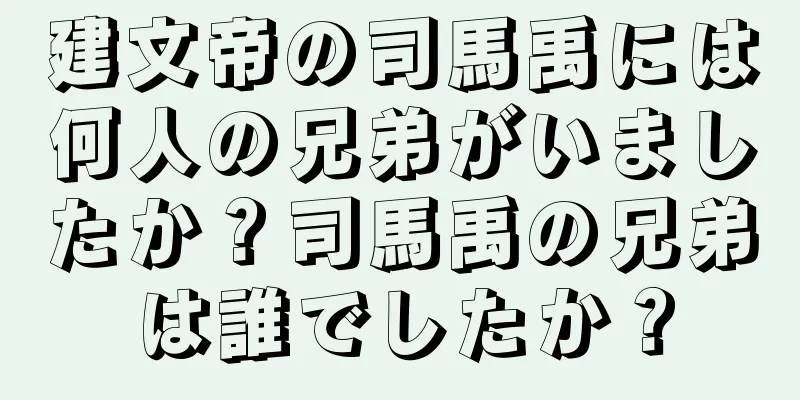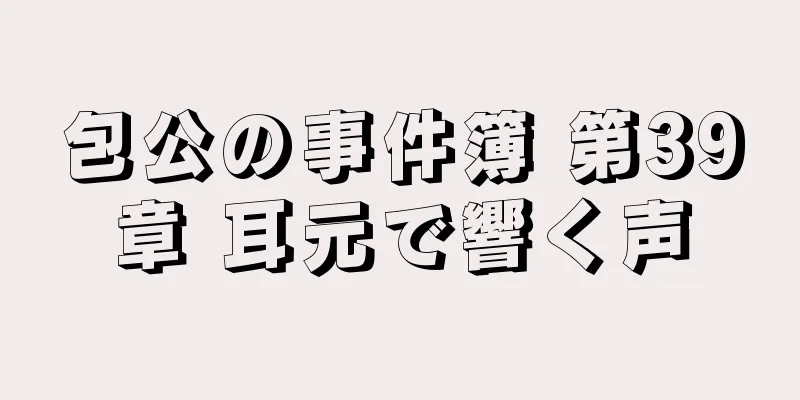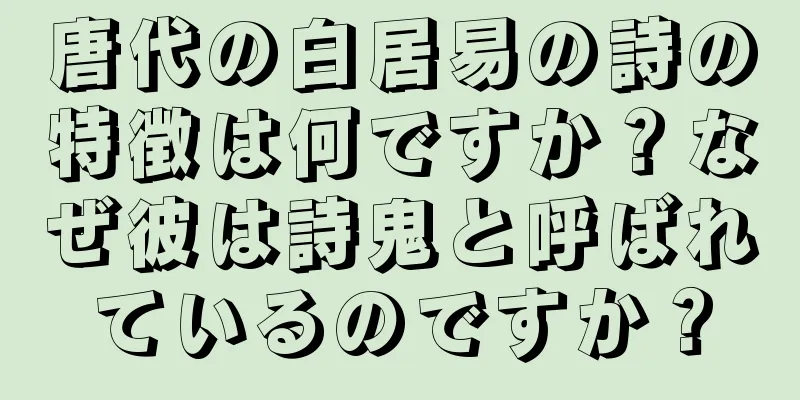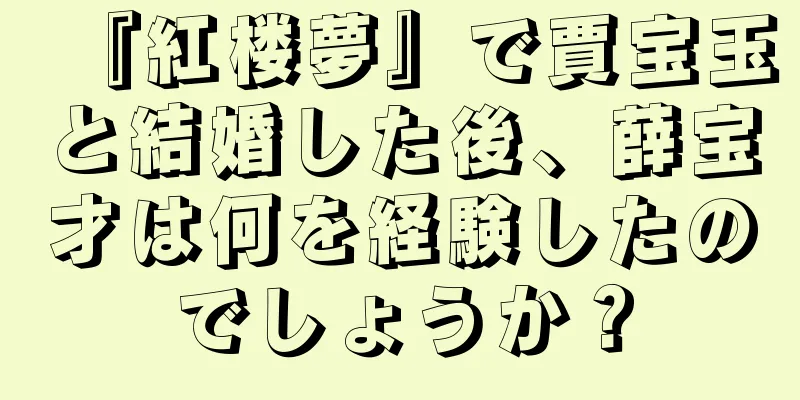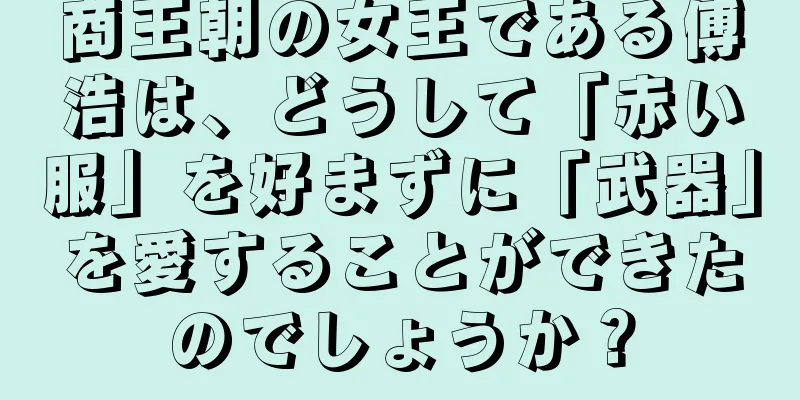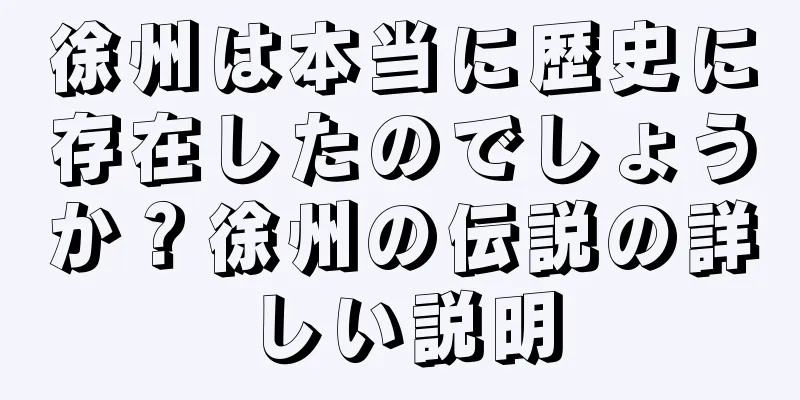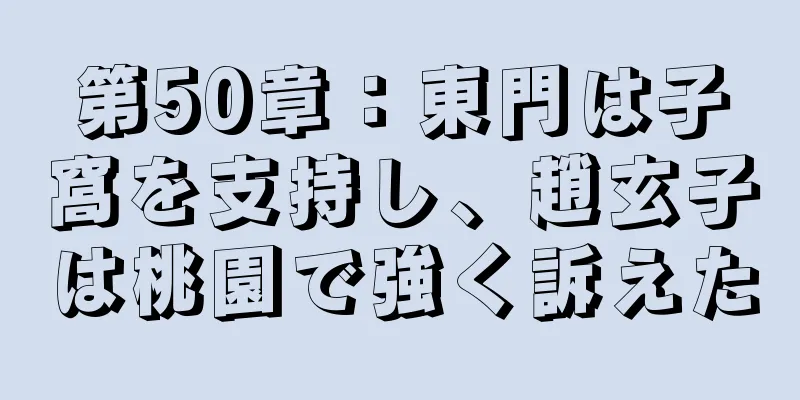「河北城塔に跨って書」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
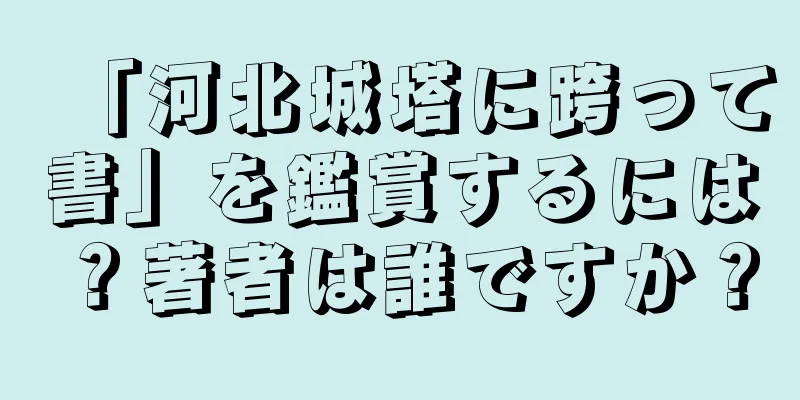
|
河北城の塔に書かれた 王維(唐代) 静義の富岩山の頂上には、雲と霧に囲まれた客殿があります。 高台にある街から夕日を眺めると、青い山々が湖に映ります。 岸辺の火のそばで孤独な船が眠り、夕方になると鳥たちが漁師の家に戻ってきます。 夕暮れの世界は寂しく、私の心は広大な川とともに安らぎます。 翻訳 富岩には住民の庭がいくつかあり、郵便局は雲の間にあります。 高い城壁に立って夕日を眺めると、遠くの水面に蒼山の山容が映ります。 岸辺には点々と明かりが灯り、水上には小さな船が数隻ぽつんと停泊しており、夕立に伴われて漁師たちが家に帰っていく姿が見られた。 この静かで広大な世界で、私の気分は広い川のようにゆったりとしています。 感謝 最初の連句「静義の富岩の頂上、客殿は雲と霧の中にある」は、詩人が城壁に登ったときに見た景色を描写しています。詩人は詩全体の舞台を雲と霧の中に設定しており、それによって広大さと変化の感覚が作り出されるだけでなく、絵全体が夢のような霞んだ感じに見えます。このようにシーンを設定すると、人物と風景の距離が広がるだけでなく、風景が鮮明になりすぎて近づきすぎてぼんやりとした美しさが失われることがなくなり、後に表示される実際のオブジェクトのための比較的空いた背景も提供されます。 「高台にある街から沈む夕日を眺めると、青い山々が湾に映る。岸辺の火のそばに一艘の船がとまり、夕方になると鳥が漁師のもとに戻ってくる」という二行連句は、最初の二行で全体像を描き、高さ、距離、壮大さ、広さを表現し、最後の二行で細部にまでこだわった装飾を加えています。絵画の構図法「大図から始めて、はっきりと開閉し、中間の細部を装飾として用いる」と同じように、二連句の構造の配置にも絵画の技巧が表れており、高い城の塔、やや低い沈む太陽、遠くの水辺、さらに遠くの蒼山の反射が散りばめられ、変化に富んでおり、絵画のような美しさを醸し出している。 首連句の2行では、詩人は広大な背景から視線を引いて、目の前の小さくて細かい場面に焦点を当てています。「留まる」は静かで、「戻る」は動いています。動きと静けさの組み合わせは、水面の遠く離れた静けさを表しています。 「岸辺の火」は「孤独な船」の孤独感を払拭し、いくぶん寂しく冷たい情景に温かみを与え、詩全体の風景が退屈で死んだようには見えないようにしている。 「夕暮れには世は寂しく、大河に心はゆったりと」という二行は、詩人の内なる自由と幸福感を表現し、山や川を楽しむ詩人の心情を示している。 この詩では、村と客亭を遠景、夕日と蒼山を中景、寂しい船と漁師の家を前景として、遠くから近くへ、点から面へ、そしてまた点へと、層が交互に並び、虚と実が組み合わさり、点と面がはっきりした山水画を形成している。 背景 この詩は唐の玄宗皇帝の開元15年(727年)頃に書かれたもので、当時詩人は中南山に隠遁して暮らし、毎日山河を楽しんでいた。詩人はかつて近くの城壁に登り、遠くに山と水、近くに平和で満足に暮らし働く人々を見て、深く感動し、この感動の詩を書いた。 |
<<: 「釜山の僧侶に食事を与える」をどう鑑賞するか?創設の背景は何ですか?
>>: 「劉思志を安渓に送る」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
推薦する
古典文学の傑作『太平天国』:官部第57巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
鏡の中の花 第85章:韻図では、彼は沈月を嘲笑し、毛沢東の詩の美しい行を引用して荘江を称賛した。
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
済公第165章:孫太来は怒りに耐えて腹心を招き、猛烈な英雄は誤って法源僧を殴打する
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
清朝時代の警備組織はどれほど詳細だったのでしょうか?剣を持った衛兵になるのはどれくらい難しいのでしょうか?
清朝の宮廷劇を数多く観た学生たちは、皇帝の前で剣を携えた衛兵の威厳に感銘を受けるに違いない。この称号...
『旧唐書』第36巻には、高宗と中宗の哲学者についてどのような話が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
韓国のキムチの何が特別なのでしょうか?栄養とは何か
キムチは韓国民族の代表的な伝統的発酵食品です。韓国のキムチは丁寧に作られており、評判が高く、冬から翌...
石公の事件 第67話: 善人が善い大臣を救う、天巴は過去を回想する
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
『紅楼夢』で、西仁が重病の母親を見舞うために帰宅したとき、王夫人は彼女に何をあげましたか?
Interesting Historyの編集者がお届けするXirenに関する記事を見てみましょう。紅...
『紅楼夢』における西仁と宝玉の密会がなぜ皆に知られるようになったのか?
『紅楼夢』の第六章では、希仁と宝玉が密かに愛し合う。今日は、Interesting History ...
『紅楼夢』の中で、賈正、黛玉、それとも宝仔にとって最も満足できる嫁は誰ですか?
賈宝玉の結婚は『紅楼夢』の主要なストーリーラインである。次回はInteresting History...
古典文学の傑作『論衡』第3巻:骨相章全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
なぜ唐の時代は外国人が官僚になることを許可したのでしょうか?唐王朝はどれほど強大だったのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が唐王朝がいかに強大だったかをお話しします。...
「文帝・景帝の治世」とはどういう意味ですか?文帝と景帝の統治の理由は何だったのでしょうか?
文帝と景帝の治世は紀元前167年から紀元前141年まで続き、西漢の第5代皇帝である漢の文帝、劉衡と第...
『黄帝内経』とはどんな本ですか?なぜ『黄帝内経』は今読めば読むほど悪くなっているのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、現在の『黄帝内経』がなぜますますひどくなっているのかをお伝えします。...
もし姜維が全盛期の趙雲と対戦したら、彼は依然として優位性を保ち、趙雲を倒すことができるだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...