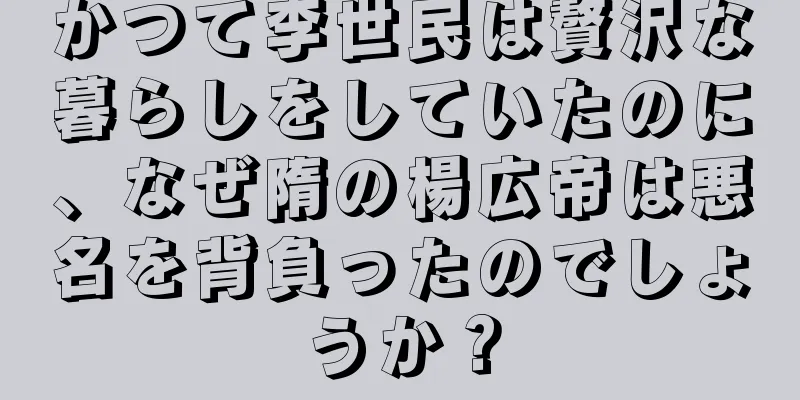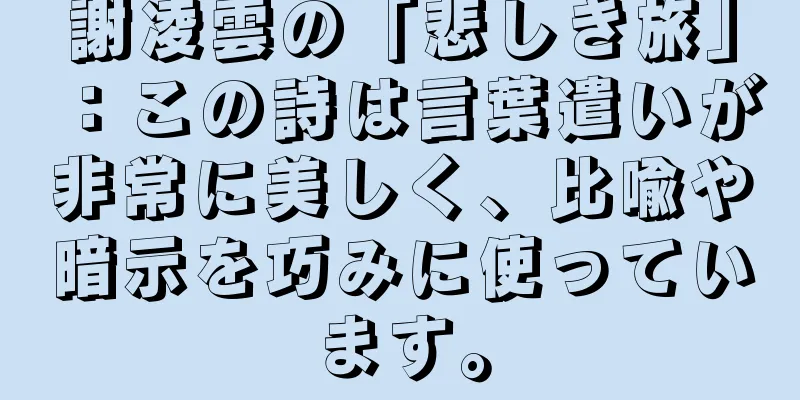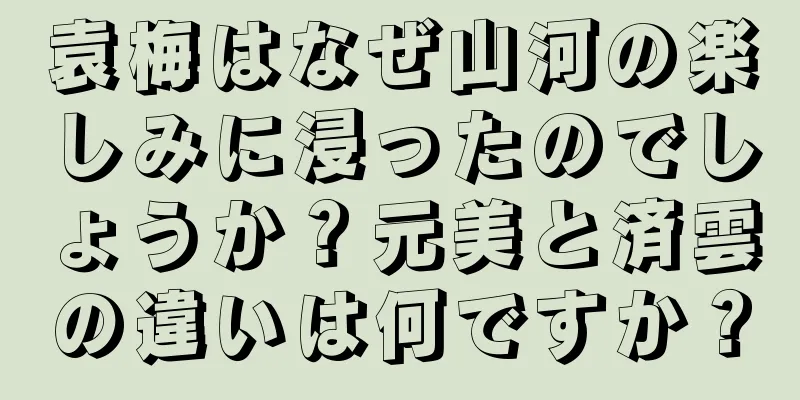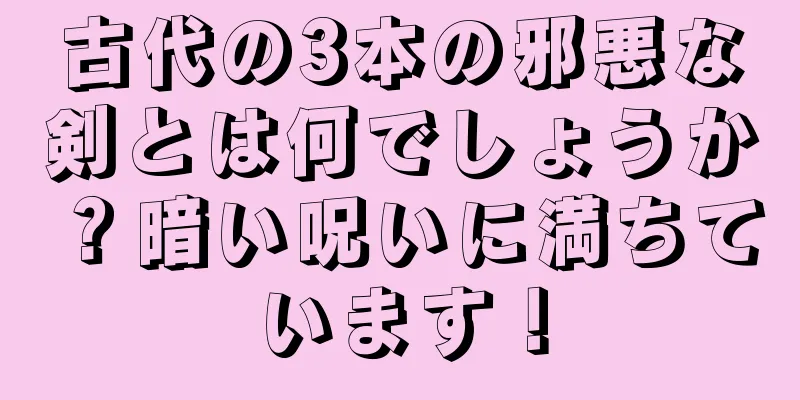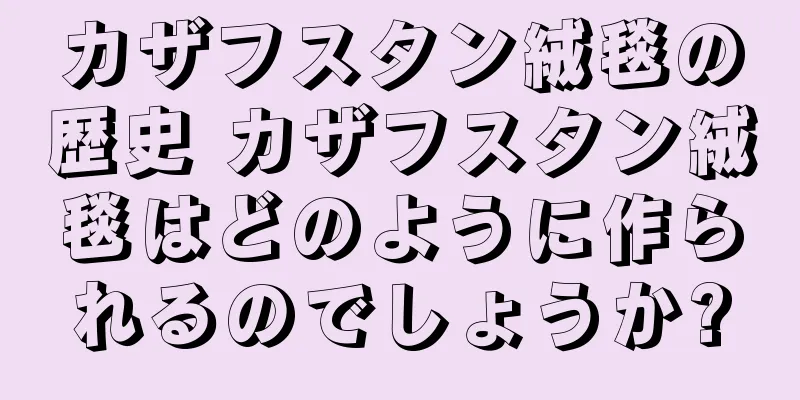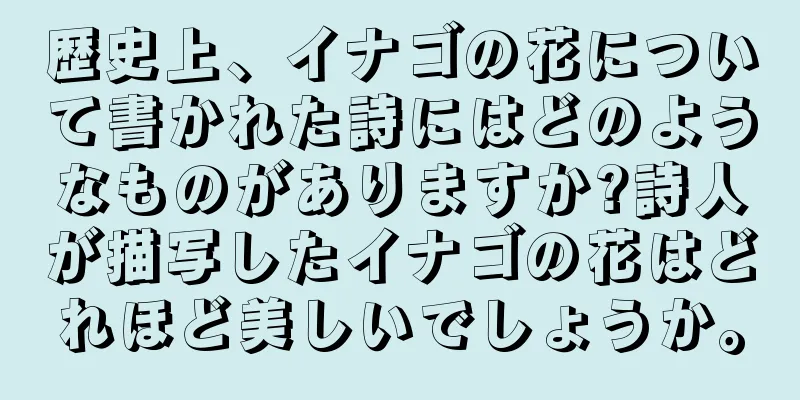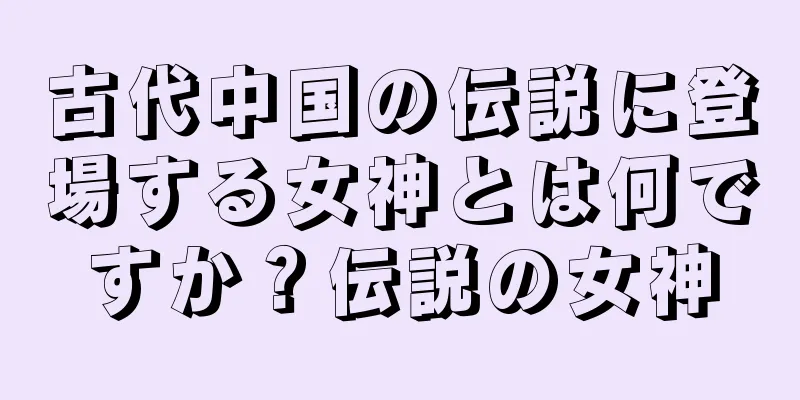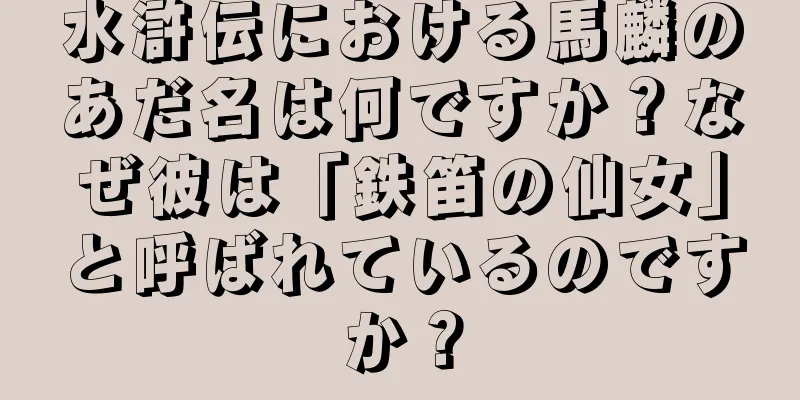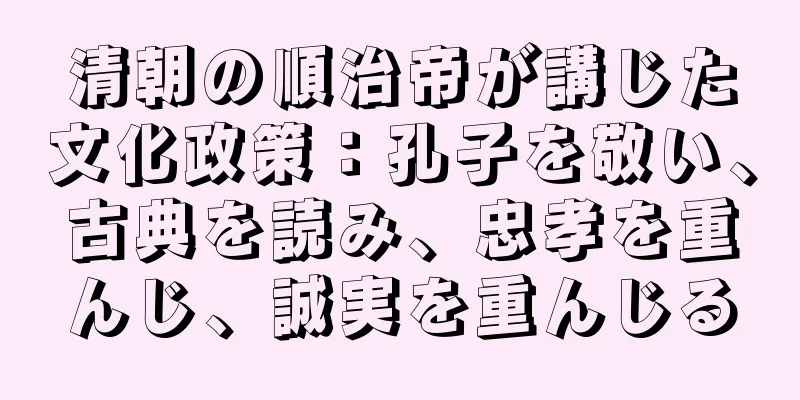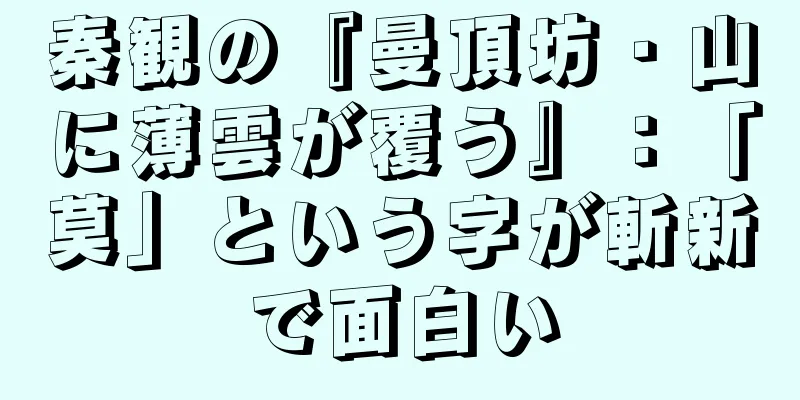「6つの戦略」の著者は誰ですか?主な内容は何ですか?
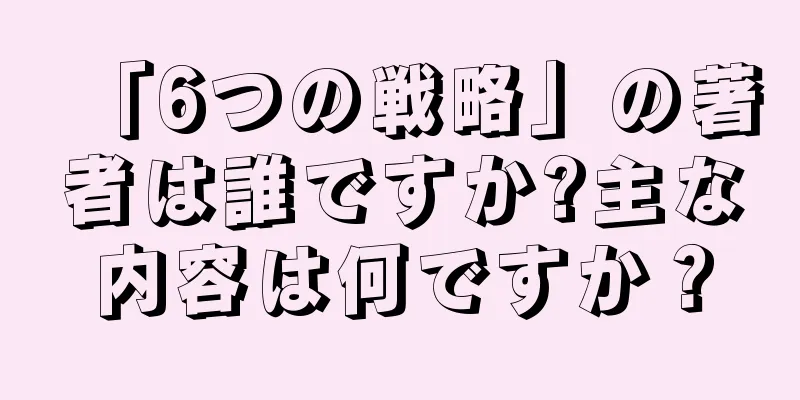
|
『六兵法』は、問答形式の古代の軍事書です。 「太公六計」とも呼ばれる。かつては西周の蒋王の作とされていた。書名の「韬」はもともと弓の鞘を意味し、その古字は「弢」で、深く隠すという意味で、戦略を意味するようになった。 「六策」とは、軍事問題を論じる6つの秘密の戦略と戦術を指します。 『韓・易文志』には儒学の範疇に「周史六策」が6章あり、唐代の顔世孤は「それが今の『六策』である」と評した。『隋・経季志』には「太公六策」が5章あり、軍事の範疇に含まれている。 1972年、山東省臨沂市銀雀山にある前漢初期の古墳から、本書の断片54点が出土した。1973年、河北省定県漢人第40号墓から『太公』の竹簡の断片が出土した。『六策』の伝統的な本と一致する内容のほか、他の章もある。両地の漢竹簡には「六策」の文字があるが、「六策」の名称は見当たらない。前漢の頃には『太公』とも呼ばれ、内容もより豊かになりました。現在の版は完全な巻ではなく、元の本の一部のみです。 『六兵法』は宋代、特に清代から偽書ではないかと疑われてきた。現在、一部の学者は、この本の内容、文体、近年発掘された文化財を分析し、大まかに言えば、この本は西周の蒋太公呂王という名の戦国時代後期の人物によって書かれたものであると結論付けています。現存するものには、『七兵経』、『四庫全書』、『四部叢観』、『百家論』、『百思想全集』、『平進観集』、清代順治八年(1651年)宋代写本、清代嘉慶十年(1805年)孫興延編纂本などがある。清代には孔童元、王仁君らによる全集や未完の版も存在する。 この本は全6巻、60章から成り、総語数は約2万語です。第一巻『文道』は、文氏、応挙、郭武、大礼、明福、劉寿、領土の防衛、国の防衛、賢者の進軍、賢者の選定、賞罰、兵法の12章に分かれており、主に戦争の前に国力を増強し、物質的にも精神的にも戦争に備える方法について論じています。例えば、内部的には、まず国を富ませ、人民を強くし、人民を教育訓練して団結させ、敵に対する憎しみを分かち合うようにしなければなりません。外部的には、敵の状況を把握しながらも、自らの秘密を守るように注意しなければなりません。この方法でのみ、あなたは無敵になれます。第 2 巻「五道」には、斉、文斉、文発、順斉、三易の 5 つの章が含まれています。一部のバージョンでは、三易の前に「氷道」の章が追加されています。この巻では、主に権力を奪取するための戦略と敵と戦うための戦術について論じています。戦う前に、まず敵と自分の長所と短所を比較し、自分の長所を使って敵の弱点を攻撃して勝利する必要があります。上記2巻は主に戦略的な問題の説明を扱っています。次の 4 巻では、戦争指導の原則と戦闘プロセスにおけるいくつかの戦術的問題の説明に重点を置いています。第三巻『龍涛』は、王弼、将軍論、将軍の選定、主将軍、将軍の権力、軍を励ます、陰府、陰書、軍事力、奇兵、五音、軍事遠征、農具など13章に分かれており、主に軍の指揮と部隊配置の術を論じており、戦争では敵を指揮し、将軍を選定し、厳しい規律を施行し、命令の発令方法と情報の伝達方法を決定する必要があると指摘している。また、天候、地形、武器や装備、物資の供給にも注意を払う必要があると指摘している。第四巻「虎の兵法」は、兵法、三陣、急戦、必攻、軍略、臨界、動静、鼓金鐘、路断、征地、火戦、空砦の12章に分かれており、主に広域での戦闘において注意すべき戦術などについて論じている。第5巻「豹戦術」は、森林戦、奇襲、強敵、強敵、山兵、沼兵、少数、危険地域の分割の8つの章に分かれており、主にさまざまな特殊な地形で戦う際に注意すべき戦術やその他の問題について論じています。第6巻「犬兵法」は10章に分かれており、分離と結合、軍の先鋒、兵士の訓練、戦闘の指導、兵士の均衡、軍の戦車兵、軍の騎士、戦車、戦争騎兵、戦争歩兵などについて論じています。主に兵士の訓練と選抜、そして異なる兵種が戦闘でどのように協力して軍隊の有効性を最大限に高めるかについて論じています。この本の内容は非常に広範囲で、戦争の概念、軍隊の構築、戦略と戦術など、軍事に関連する多くの側面をカバーしており、その中でも戦略と戦術に関する議論は特に優れています。 六秘伝は兵法から「戦わずして敵を征服する」という戦略観を発展させ、「戦いに長けた者は兵を配備する必要がなく、危険を未然に防ぐのに長けた者は危険を未然に防ぎ、敵を倒す者は敵が見えなくなる前に勝つ、戦いに長けた者は他人と戦う必要がない」と考えた(『龍の秘伝 兵力』)。この「完全勝利」戦略を達成するには、政治的には民心を掌握し、経済的には農業、工業、商業を力強く発展させ、軍事戦術では買収、麻痺、疎外などの方法を用いて敵を分裂させ崩壊させる必要がある。つまり、「戦わずして敵を倒す」という目標を達成するためには、民軍両戦略、つまり政治戦略と軍事戦略の緊密な連携が必要である。この本は、さまざまな戦闘形態におけるさまざまな戦術的問題について論じており、その長さ、広さ、分析の詳細さの点で秦以前の軍事書の中ではユニークなものである。特に、機動戦戦術の解明は軍事学史上大きな革新である。 「敵が集まった時に攻撃できる」「敵が逃げている時に攻撃できる」(全涛、呉鋒)、「敵の陣形が固まらず兵士が戦わないときは、前後左右から攻撃し、側面から攻撃すれば、敵は必ず恐れるだろう」「敵には戦略的な障害物や拠点がない。領土の奥深くまで進攻し、遠くまで追い詰め、食料を断てば、必ず餓死するだろう」(全涛、戦旗)などの戦法は、まだ足場を固めていない敵、孤立した弱い敵、領土の奥深くまで移動している敵を攻撃する際の戦闘原則を語っており、現代の戦争でも参考にできる戦法です。 『六策』には、軍の組織、将軍の選定と兵士の訓練、旗や太鼓、物資や装備、その他の軍事建設問題について論じた内容も大量に含まれています。例えば、『龍涛』の「王毅」は、古代の司令部の組織と分掌について論じることにほぼ専念している。また、本書は周の文王と蒋太公の会話の形式を借用し、問答形式を採用し、論じられた問題を大まかに分類しており、議論は広範かつ柔軟で、論理は比較的明確であり、伝統的な問答形式の軍事書の手本となっている。 『六兵論』は、秦以前の軍事戦略家や各哲学者の軍事論のエッセンスを吸収し、道教、法家、儒教などの哲学の観点と融合し、軍事弁証法の思想をより反映したものとなっている。かつて古学者からは偽書とされ、「言葉が下品だ」(姚継衡『古今偽書研究』)と偏見を持たれていたが、その理論的価値は軽視できない。 『六兵法』は秦以前の軍事思想の集大成であり、独自の体系と特徴を持つ軍事古典と言える。そのため、北宋元豊三年(1080年)、神宗皇帝によって「七経」の一つに指定され、軍事試験の必読書となり、封建軍事学の正統な地位を確立しました。 「6つの戦略」に関するこれまでの研究は、主にテキストの解釈と著者のバージョンの認証に焦点が当てられてきました。宋代の史子美の『講義録』、明代の劉隠の『直説』、清代の朱庸の『集説』など。この本は16世紀に外国語に翻訳され始めました。この本の日本語訳、注釈、解説、注釈は40近くあります。韓国語やベトナム語への翻訳も多数あります。近年では、本来の研究分野のさらなる発展・向上に加え、本書を総合的に評価したモノグラフも出版されている。主なものとしては、張烈の『「六兵法」の編纂と内容』(『歴史研究』第3号、1981年)、劉鴻章の『「六兵法」に関する予備的研究』(『中国哲学史研究』第2号、1985年)、孔徳奇の『六兵法の簡潔な紹介』(人民解放軍出版社、1987年版)などがある。 |
推薦する
徐晃は本当に孟達に射殺されたのか?いいえ、彼は一年前に病気で亡くなりました。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
杜牧の有名な詩の一節を鑑賞する: 山の柱と谷の溝はまだそこにありますが、弱い者が強い者を吐き出し、すべてを飲み込んでしまいました。
杜牧(803-852)は唐代の景昭萬年(現在の陝西省西安)の人であり、雅号は牧之で知られていました。...
『旧唐書』巻第七中宗・睿宗にはどんな話が書かれているのでしょうか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
秦王朝の王は誰でしたか?
秦王の治世の年表紀元前900年頃、東周の孝王は嬰非子に秦公(現在の甘粛省清水県の北東)の称号を与え、...
太平広記・巻76・道教・相小僧の具体的な内容は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
「孤延残喘」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「孤延残喘」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その背景にある物語は何でしょうか?次の興味...
朱元璋は、明朝の将来の建設の基礎を築くために、どのような蜂起計画を成し遂げたのでしょうか。
元朝の智正13年になると、元朝の崩壊の流れは不可逆なものとなり、全国で数え切れないほどの反乱が起こっ...
唐代の袁震の『薛涛への贈物』の原文、翻訳、注釈、鑑賞
袁震の『薛涛に贈る』については、下記に『おもしろ歴史』編集者が詳しく紹介しています。薛涛へ袁真(唐代...
恵州壁画は恵州様式の建築壁画ですが、一般的な壁画との違いは何ですか?
恵州壁画は恵州様式の建築壁画であり、壁画の一種です。いわゆる壁画は壁に描かれた絵画であり、人類史上最...
長い歴史の中で、漢代の皇后たちはなぜ常に「後宮から政務に干渉」することができたのでしょうか?
古代中国では、皇帝は国の象徴であり、世界を統治していました。女王は国の母であり、国全体の模範です。長...
ユグ族は漢字を使いますか?ユグ族はどのような言語と文字を使っていますか?
ユグル族は独自の言語を持っていますが、書き言葉はなく、一般的に中国語を使用しています。ユグ語には主に...
なぜ他の花ではなく、桃の花が幸運をもたらすのでしょうか?桃の花の幸運の由来
異性にモテることを「桃花運」と言いますが、なぜ他の花ではなく「桃花」なのでしょうか? 「桃花縁結び」...
市の考古学者が賈県で漢王朝の墓を発掘
市文化財局の考古学チームは先日、賈県で漢代の古墳を発掘した。昨日発掘された石の浮き彫りは考古学者たち...
『封神演義』で楊仁はなぜ二度死んだのですか?真実とは何でしょうか?
この質問は実はとても簡単です。楊仁は二度死にましたが、それは肉体の死と魂の死ではありませんでした。 ...
明朝中期から後期にかけて、皇帝は内務省の宦官に何をよく命じましたか?
西里監は明代に設立された官庁の名称である。明朝の内廷十二部の一つで、宦官や宮廷の事務を管理する部署で...