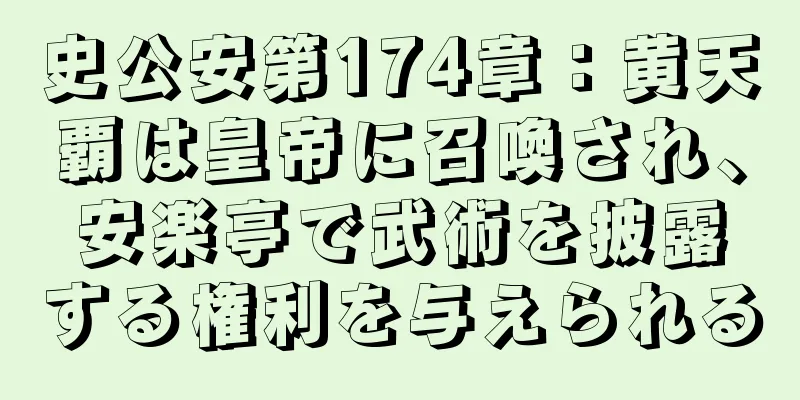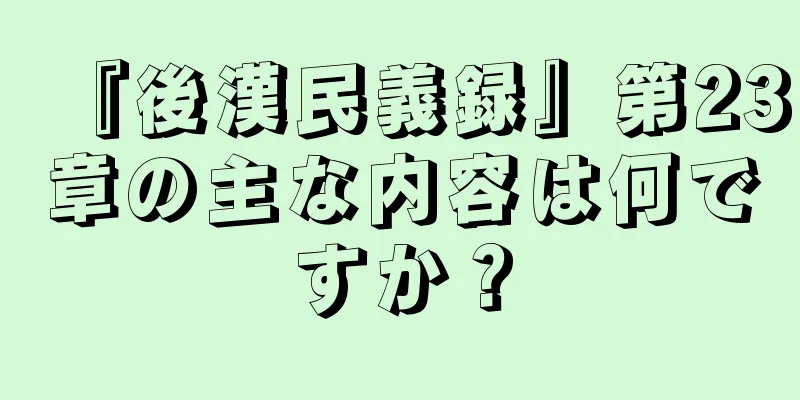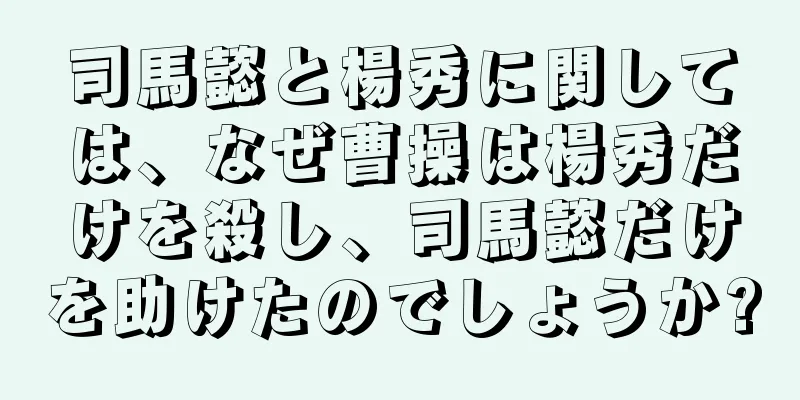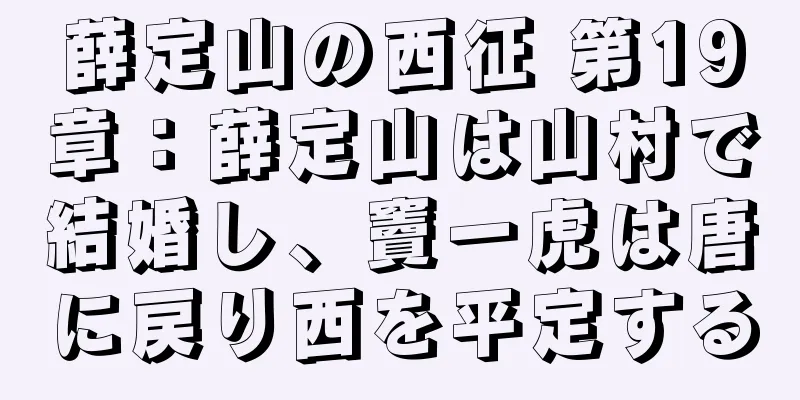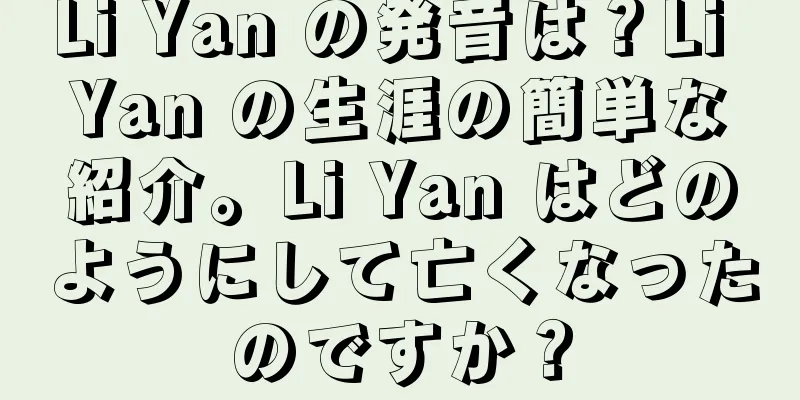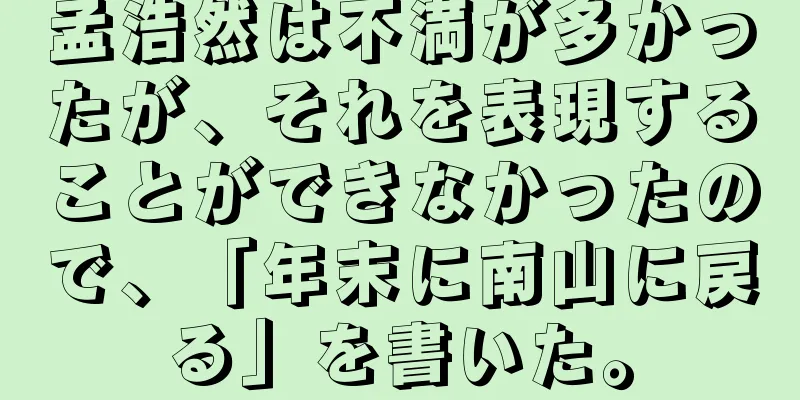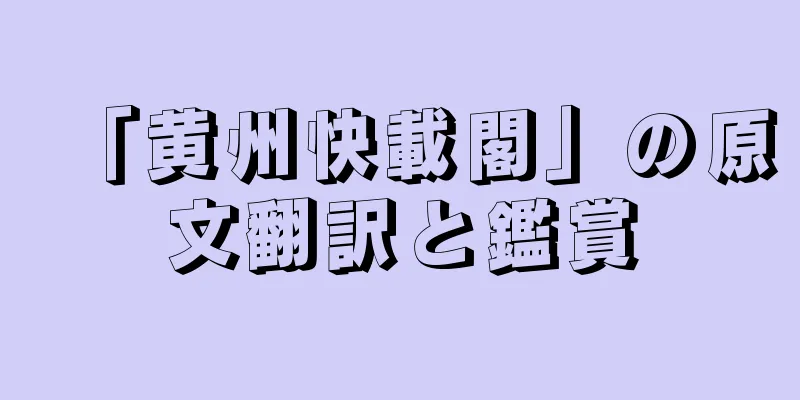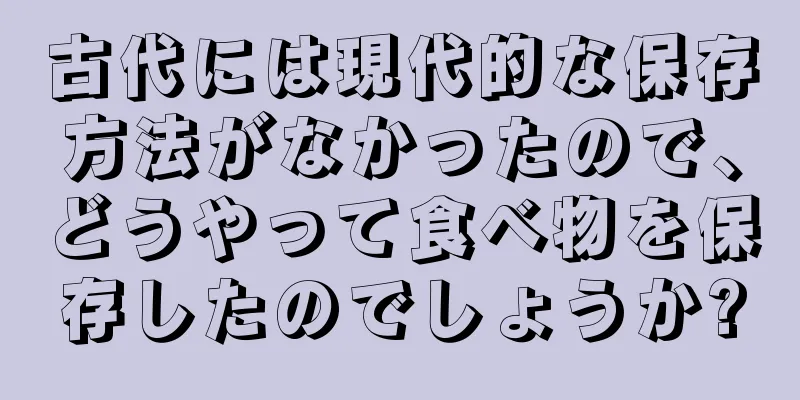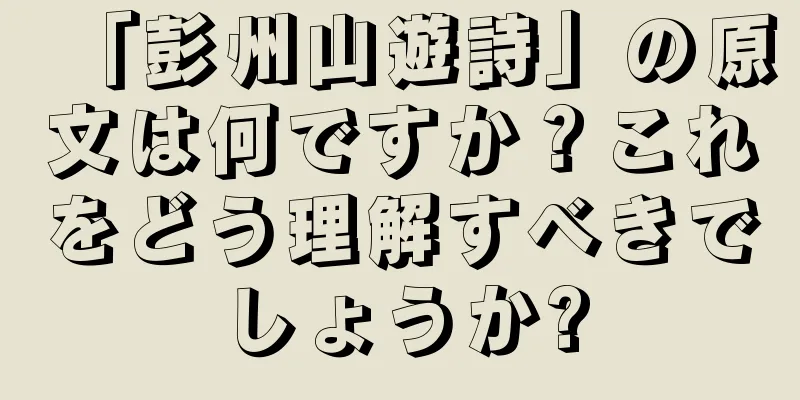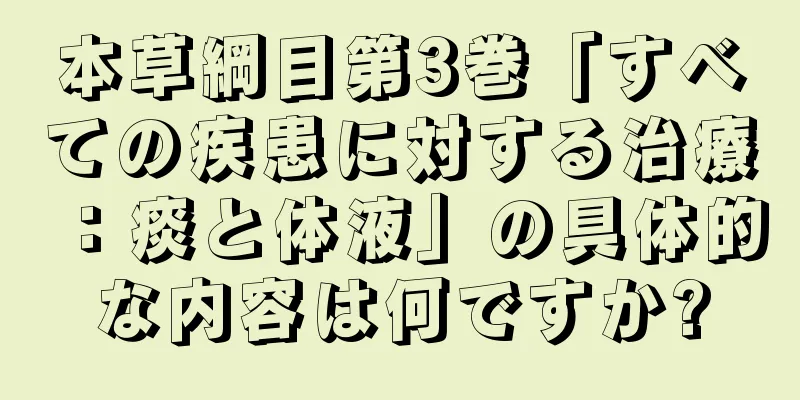老子の『道徳経』第 43 章とその続き
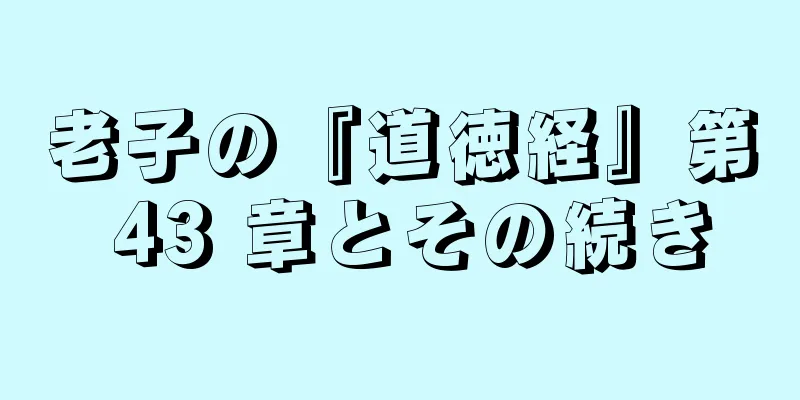
|
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古代中国で秦以前の哲学者が分裂する前に書かれた作品であり、道教の哲学思想の重要な源泉です。 『道徳経』は2部に分かれています。原典では上段を『徳経』、下段を『道経』と呼び、章は設けられていません。後に、最初の37章を『道経』、38章以降を『徳経』と改められ、81章に分かれています。そこで今日は、Interesting History の編集者が老子の『道徳経』第 43 章をお届けします。見てみましょう! [オリジナル] この世で最も柔らかいものは、この世で最も硬いものに打ち勝つことができる。無は虚空に入り、こうして私は何もしないことの利点を知ります。言葉のない教えと行動のない利益は、この世ではほとんど達成されません。 [翻訳] この世で最も柔らかいものは、最も硬いものを飛び越えることができる。目に見えない力は、隙間なく物事を貫くことができる。そこで私は「何もしないこと」の利点に気づきました。 「沈黙」の教えと「無為」の利益が一致するものは、世界でもほとんどありません。 [注記] 1. チピン: 馬の走り方を表します。 2. 目に見えない力は、どんなものにも隙間なく浸透することができます。無: 目に見える形を持たないものを指します。 3. 希:ある本では「希」が使われており、これは珍しいという意味です。 [拡張読書1] 王弼の『道徳経』の注釈 この世で最も柔らかいものは、この世で最も硬いものに打ち勝つことができる。 気はあらゆるところから入り、水はあらゆるところから経絡から出ます。 無は虚空に入り、こうして私は何もしないことの利点を知ります。 無は弱いが、すべてを知っている。何も枯渇することはなく、最も柔らかいものも壊れることはありません。このことから、何もしないことが有益であることがわかります。 言葉のない教えと行動のない利益は、世界でも稀です。 【拡張読書2】蘇哲の『老子解説』 この世で最も柔らかいものは、この世で最も硬いものに打ち勝つことができる。何もなければ疑問も生まれません。こうして私は何もしないことの利点を知りました。 硬いものを使って硬いものに抵抗すれば、壊れなくても粉々になります。柔らかいものを使って硬いものに抵抗すれば、柔らかいものは腐食せず、硬いものは損傷しません。物の中にそれを探すと、それは水です。存在と共に存在に入ると、両者は抵抗することができず、非存在と共に存在に入ると、非存在は労働を味わうことができず、存在は知覚を感じることができない。物の中に求めるなら、それは幽霊と神々です。したがって、聖人は何もすることができず、強者や権力者に命令し、大衆の間を行ったり来たりすることができます。 言葉のない教えと行動のない利益は、世界でも稀です。 |
推薦する
徐霞客の旅行記:白岳山旅行記の原文
冰塵の年(1618年)旧暦1月26日、私は叔父の荀陽とともに衛之秀寧へ行きました。西門から出てくださ...
皇帝の物語:歴史上の晋の景公はどんな人物だったのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...
「学者」第 2 章の紹介と評価
第2章:村の同級生である王小蓮と彼の教師である周孟は、山東省兗州県文上県に薛家集という村がある。この...
ダーウィンの生物進化論の主な考え方は何ですか?実は中国では2000年前にもこの考え方があったのです!
今日は、Interesting Historyの編集者が生物進化についての記事をお届けします。ぜひお...
『紅楼夢』で王夫人は迎春の結婚をどう見ているのでしょうか?
迎春は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。これは多くの読者が気になる問...
宝安族の「腰刀」がいかにして丁寧に鍛造されるか
荘子は偉大な人物でした。彼は中国の歴史に流れる哲学を寓話でよく説明し、あらゆる時代の人々が深い感銘を...
明らかに:孟姜奴が泣き崩れたのは本当に万里の長城だったのか?
世界建築の驚異である万里の長城について語るたびに、私たちは誇らしさを感じます。民間の四大恋愛伝説の一...
拓跋涛の母親は誰ですか?拓跋涛の母親、明元密皇后の簡単な紹介
拓跋涛(408-452)は、名を「佛」といい、鮮卑族の出身で、明元帝拓跋涛の長男で、母は明元密皇后で...
項子珍の『阮朗帰・紹興一茂大雪鄱陽路を歩く』:曲がりくねって奥深く、一層ずつ進んでいく
項子珍(1085-1152)は、法名は伯公、自称は項林居師で、臨江(現在の江西省)出身の宋代の詩人で...
宝仔と宝玉は新婚初夜をどのように過ごしたのでしょうか?
『紅楼夢』では、薛家が北京に来て賈邸に住んで以来、「完璧な縁」という言葉が栄果邸に徐々に広まっていっ...
康熙帝は賢明な統治者とみなすことができるが、なぜ彼は息子の教育に失敗したのだろうか?
清朝全体を見れば、康熙帝は清朝皇帝の中でも最も賢明な君主であったと言える。康熙帝の息子たちは康熙帝と...
『彩桑子:西湖の美を誰が鑑賞できるか』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
彩桑子:西湖の美しさを誰が理解できるだろうか?欧陽秀(宋代)西湖の美しさと永遠に続く景色を鑑賞できる...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源第46巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
蒋子牙の「太公六計」:「六計・犬計・兵法」の評価と例
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われてい...
英雄の旅における武術の達人のランキング:北海士は6位にしかランク付けできない
騎士の道の達人の中でトップ3は間違いなく石柏田、龍島達人、沐島達人です。これに異論はありません。最初...