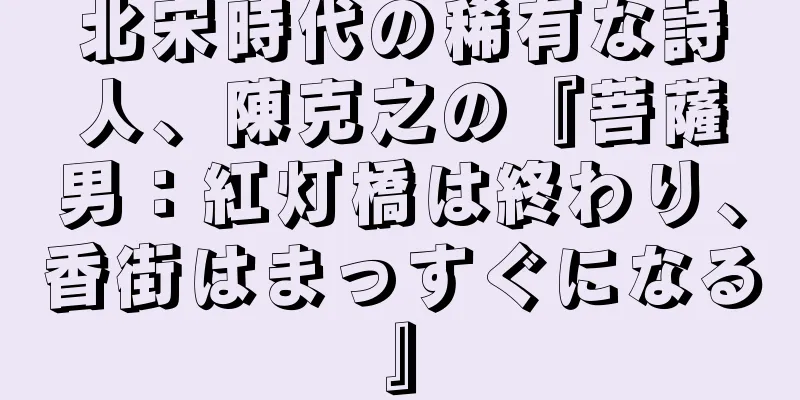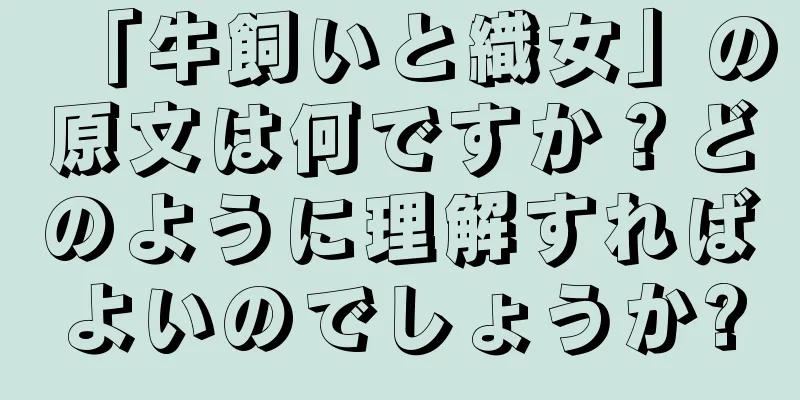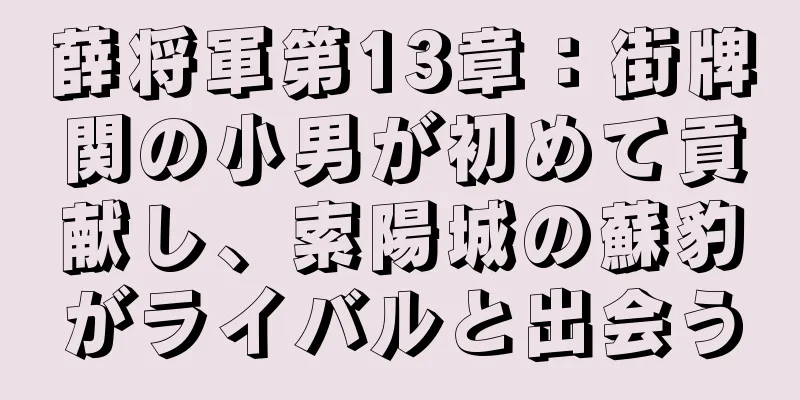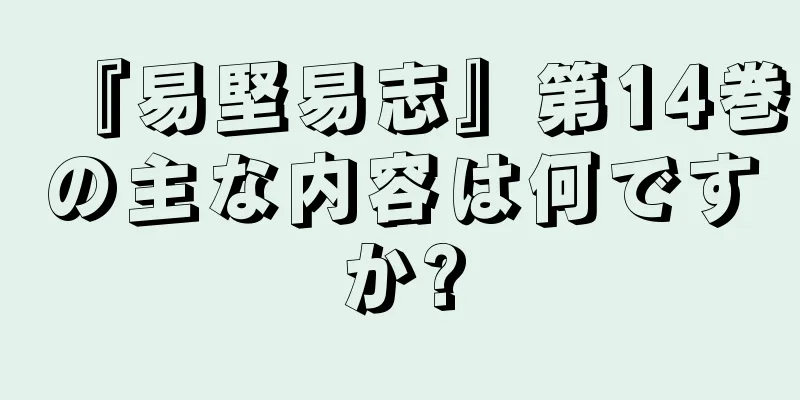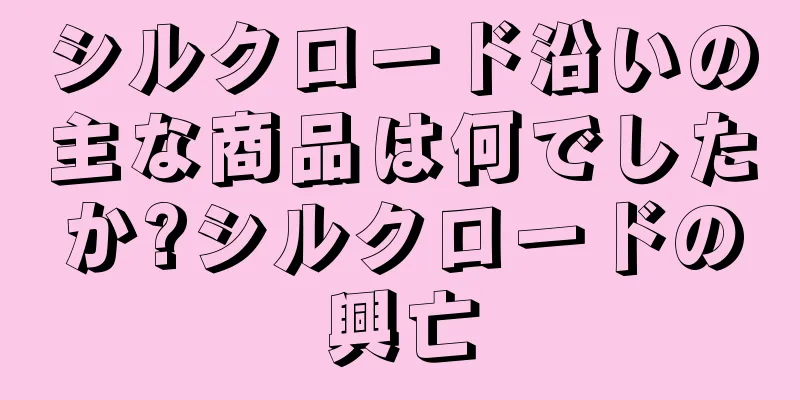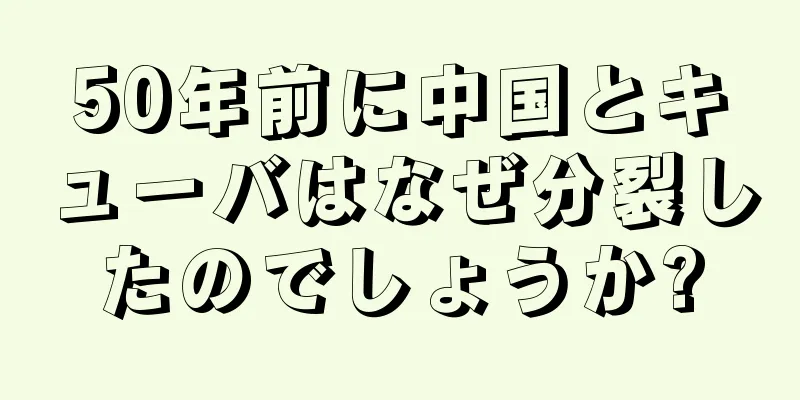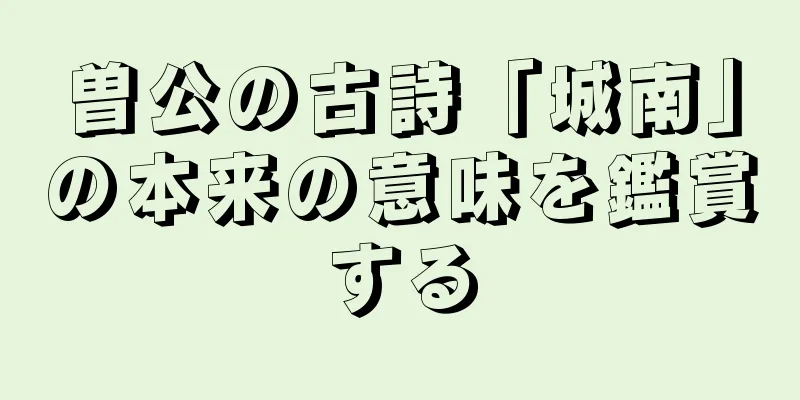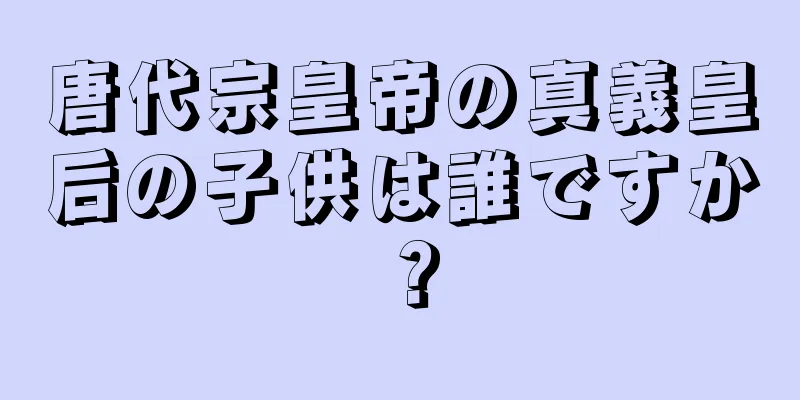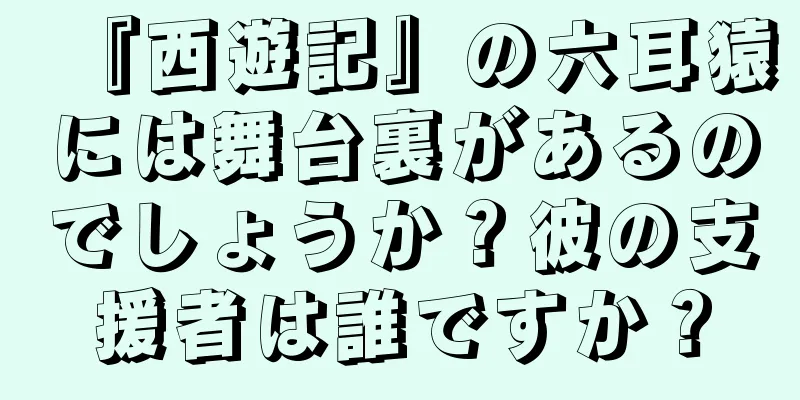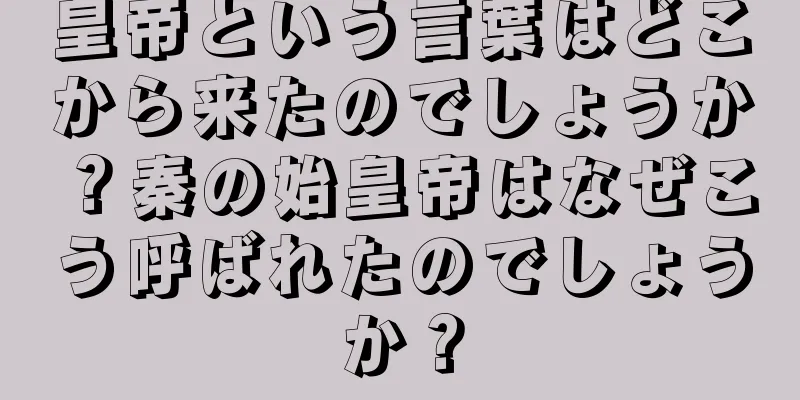古典文学の傑作『太平天国』:周君部第14巻全文
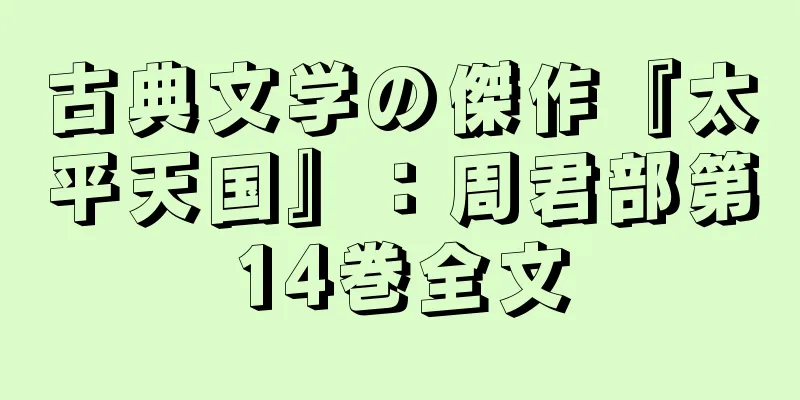
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が周君布第14巻の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! ○ 山南路 涼州 『絵本』には、涼州、漢中県とある。春秋時代から戦国時代にかけての楚の領土。秦・漢の時代には漢中県であった。 『蜀の記録』には、劉備が初めて漢中を占領したとき、「曹公が来ても何もできない」と言ったとある。 『漢書』には、項羽が沛公を漢王に任命し、沛公は南鄭に都を置き、巴、蜀、漢中の41郡を統治したと記されている。沛公が楚を攻めようとしたとき、宰相の蕭何は彼に助言した。「漢中王になることは悪であっても、死ぬよりはましではないでしょうか。それに、天漢の名は美しいものです。あなたが漢中王となり、そこの民を平定し、巴と蜀を制圧し、三秦を平定してください。そうすれば、天下を征服できるでしょう。」 揚州 『十省記』には揚州陽川県とある。春秋戦国時代には楚の領土であった。秦の時代には漢中県の領土であった。 「韓志」曰く:城谷は漢中県に属する。ここが現在の楊源県の地域です。 漢中に属し、安陽とも呼ばれる。彭谷の水源。現在は黄津県となっている。 上州 『十省記』には、商州は商洛県であると記されている。 『朝貢の禹』における涼州の地域。周は豫州の領土であった。戦国時代には秦の領土となり、秦が天下を統一すると兪氏の国となった。漢の武帝はここに商洛県を置いた。 『史記』:張儀は楚の淮王に言った。「陛下が本当に斉との条約を破棄できるなら、上虞の600里の土地を差し上げましょう。」そこで楚は斉との条約を破棄し、張儀を追って将軍を秦に派遣した。易は楚の使者に言った。「私は六里の領地を持っています。それを王に捧げたいのです。」楚の使者は言った。「私は上虞の六百里の土地と交換するように王から命令を受けましたが、六里など聞いたことがありません。」 皇甫密の『皇紀』にはこう記されている。「始皇帝の時代、四雄は尚山に隠れ、歌を作った。『山は高く雄大で、谷は深く曲がりくねっている。紫のキノコは明るく、飢えを癒すことができる。唐と禹の時代は遠い、どこへ行けばよいのか?』」 『韓志』によれば、商は洪農県に属していた。それは秦の宰相、衛阳の町でした。 ゴールデンステート 『十省記』には錦州安康県とある。 『朝貢の禹』における涼州の地域。周の時代には雍国の地で楚の臣下であったが、後に楚の領土となり、秦の時代には漢中県となった。 『皇紀』には、安康は桂胥、あるいは瑶胥と呼ばれていると記されている。 『後漢書』鄭洪は追悼文に「舜順は姚舜に生まれ、夏舜は新牛に生まれた」と記している。応容の「釈」には「舜は西域に住み、元々は桂邑と呼ばれていた」と記されている。 『韓志』によれば、西城は漢中県に属する。英邵は言った。「桂胥は舜が住んでいた北西部にあり、現在の西城県である。」 方州 『十省記』には、方州、方陵県と記されている。土地の所有権は錦州と同じです。それは古代ミの国でした。 『左伝』によれば、楚王は米を攻撃し、程大信は方渚で米軍を破った。 Du のメモ: Fangzhu は Midi にあります。坎厳は言った。「方霊は春秋時代の方珠と同じである。」 『韓志』によれば、方陵と上勇は漢中県に属する。 盛洪志の『荊州記』には、竹山県に白馬関がある、とある。孟達は新城の太守に任命され、白馬に乗りながらため息をつき、「劉封と沈丹は金城を支配していたが、守ることができなかった。どうして彼らが男と言えるのか?」と言った。 通州 『十省記』には通州通川県とある。土地の所有権は錦州と同じです。春秋時代・戦国時代には巴国に属した。秦は天下を統一し、巴県とした。漢王朝もそれに倣った。 『後漢書』には、宣漢は巴県に属していたと記されている。それが漢の当区地域です。 「八漢記」は言う。「河帝は当曲を東に分割し、そこに置いた。」 「通州」には、西魏の時代に、四方八方に通じる道路沿いにあったことから通州と改名されたとある。 (現在は達州として知られています。) 衢州 『十省記』には衢州臨山県とある。土地の所有権は通州と同じです。 『韓志』には「当区は巴県に属する」とある。 『于迪之』は言う:梁大同三年、衢州はこの地に建てられた。 左寺の『舒都』にはこう書かれている。「周囲は同梁と当曲に囲まれている。」 豫州 『十省記』には豫州、南平県とある。キューバという国。 『三巴記』には、郎江と白江が東西に流れ、漢字の「巴」のように3回曲がっていることから三巴と呼ばれるようになったと記されている。 『山海経』には、海の南西に巴国があると書かれている。昔、太豪は仙鳥を生み、仙鳥は承麗を生み、承麗は后昭を生み、彼らは巴の民でした。 (郭普曰く「彼は巴の祖先である。」) 李英の『易州記』にはこう記されている。「明月峡は巴県に位置し、東壁の高さは40フィートで、丸い穴が満月のような形をしているため、この名がついた。」 江津県の西側には湘草塔もあると言われています。昔、ここに塔があって、塔の下に香草を植えていた仙人がいましたが、一夜にして亡くなりました。後世の人々は、この場所を湘草塔と呼んだ。 福州 『十省記』には福州涪陵県とある。 『朝貢の禹』における涼州の地域。周は雍州の地であった。春秋時代には巴国に属していた。秦では巴県と呼ばれていました。漢代には涪陵県であった。 『八漢志』には、涪陵は八県の南境であり、もともと楚の上虞の地に隣接していたと記されている。 ラン州 『十省記』には、朗州、武陵県と記されている。 『朝貢禹記』の荊州の地域。春秋時代から戦国時代にかけては楚の領土であった。秦の時代には前中県であった。漢の高祖5年に武陵県に改名された。梁の襄東王は武陵県を荊州から分離し、梧州を建てた。陳天嘉元年、武陵を分割して元陵県が置かれた。隋の時代には、梧州は陳州、宋州、そして朗州と改名されました。 『史記』には、秦の恵文王14年に、呉衙以外の地域を楚の千中地域と交換することを求めたと記されている。 『武陵記』によると、後漢の梁宋は夷陵県を若城に移した。この県の東には張若城があります。 『晋書』には、潘静は武陵漢首の出身であると記されている。 20歳で郡の太守に任命された。太守の趙欣は彼をとても尊敬し、かつて「なぜあなたの郡は武陵というのですか?」と尋ねた。景は答えた。「私の郡は元々夷陵と名付けられました。陳陽県の境界に位置し、イ族と遼族と接しています。何度も攻撃を受けました。光武帝の時代に東の山に移り、ようやく無傷で治めることができ、名前を変えることにしました。戦争を止めるのは武だと言われています。『詩経』に高平を霊と呼んでいるので、そのように名付けました。」 『武陵記』によると、武陵県の領土は4,000マイル以上ある。 麗州 『十省記』には、溧州、溧陽県とある。春秋時代から戦国時代にかけて、この地域は楚の領土であった。秦の時代には前中県に属していた。漢代に前中は武陵県に改められ、荊州に属した。現在の県は武陵県凌陽県である。呉は武陵の西境を分割し、この県の領域である天門県を設置しました。晋では南邑陽県と呼ばれていた。隋は陳を征服した後、宋州を建国したが、すぐに麗州と改名された。麗水河の北に位置しているためこの名前が付けられました。 『禹記』には、岷山から揚子江が流れ出し、東に分かれて托河に入り、さらに東に流れて漓江に流れ込むと記されている。 (風水の名前です。) 『地理志』には、晋・宋の時代に、益陽からの亡命者によって荊州に隣接する南郡に南阳陽県が設立されたと記されている。 『十州志』には、慈理県は漢代の凌陽県の所在地であると記されている。 「絵本」にはこう記されている。「境界内にリンクリークと呼ばれる小川があり、それが名前の由来です。」隋の開皇18年に、凌陽は慈里県に改名されました。 王仲玄は孫文に「李よ、長く安らかに」という詩を贈った。 (丹江と漓江は溧陽県にあります。) 巴州 『十州志』には「巴州の土地所有は通州の土地所有と同じである」とある。漢代には巴県当曲県であった。 『四夷郡道記』:李徳と孫寿の時代に、10万人以上の遼部族の集団が南越から蜀と漢に入り、山や谷に散在して住んでいた。このため、彼らはこの地域全体に広がり、後に遼に占領されました。 碧州 『十省記』には、碧州は光寧県であると記されている。もともと漢代には当曲県の所在地であったが、後漢代には宣漢県に分割された。梁は玄韓を分割し、光寧を建国した。後魏は城寧を糯水県に分割した。 彭州 『十省記』には彭州、仙安県とある。ここは漢代の当曲県の地であった。 『周代地図記』には、武帝の天和4年、巴州の扶余県と龍州の龍城県が分離され、この地に彭州が置かれたと記されている。 冀州 『十省記』には冀州阜陽県とある。ここは漢代の当曲県の地であった。晋の恵帝永寧の時代には、李特が蜀の王となり、蜀の領土は彼のものとなった。梁武はこれを東坡県と改め、後に冀県と改めた。北東部の水源にちなんで名付けられました。 (万山に集まるからとも言われています。) 唐州 『十省記』には唐州淮安県とある。 『朝貢の禹』の豫州の地域。春秋時代の楚地方。戦国時代には晋に属し、後に漢に属した。秦は三十六の県を設置し、南陽県が設けられた。 『韓志』には、南陽県に毗陽県があり、毗江が東に流れて蔡に流れ込むと記されている。 「左伝。西暦4年」:斉軍が楚軍を攻撃した。楚王は屈嬌を師として遣わした。斉公は諸侯の軍隊を編成し、屈嬌とともに状況観察に赴いた。斉公は尋ねた。「この軍勢で、誰が抵抗できようか。この軍勢で、どの城も征服できないか。」斉公は答えた。「徳をもって諸侯をなだめれば、服従しない者はいようか。武力を行使すれば、楚の房城を城として、漢江を堀として使うことができる。大軍を持っても、役に立たない。」 『金泰康地理志』には、華から汾陽まで、南北に百里あり、方城と呼ばれ、万里の長城とも呼ばれていると記されている。 『周代地図録』には、胡陽県は光武帝の母方の祖父である范冲の領地であったと記されている。光武帝は妹にも胡陽公主と名付けた。 『韓志』には「胡陽は古代遼の国である」とある。(遼は「リージャオ」と発音する。) 鄧州 『十省記』には、鄧州、南陽県と記されている。 『朝貢の禹』の豫州の地域。戦国時代には漢に属していた。秦は36の郡を設置し、南陽もその一つであった。 「石明」とは:中国南部の日当たりの良い場所にあるため、この名が付けられたそうです。 『韓直』によれば、南陽県は万県、荀県を含む36県を管轄していた。秦によって建てられ、芒によって千嘴と称され、荊州に属した。 南陽に属し、鄧とも呼ばれます。祖国。ドゥウェイが統治する。英紹は言った。「鄧小平は侯爵だ。」 『史記』:蘇秦は漢の恵王に言った。「漢には西に益陽があり、東に琅と禹がある。」 『後漢書』には、当時、全国の耕作地の多くが実際には耕作されていなかったため、皇帝は各県にそのことを検討するよう命じたと記されている。当時、各県は使者を派遣して事の次第を報告させていた。皇帝は陳留の書記の文書にメモがあり、読んでみると「怡州と洪農は問うことができるが、河南と南陽は問うことはできない」と書いてあった。皇帝は書記に質問したが、書記は認めなかった。当時、献宗は東海公であったが、「皇城の河南には側近が多く、皇郷の南陽には近親者が多い。土地や家屋は規定外であり、参考にすることはできない」と言った。 『史記』には、秦が漢を征服した後、世界中の無法者を南陽に追放したと記されている。そのため、彼らの習慣は贅沢で豪奢であり、体力を重視し、貿易、魚釣り、狩りを好み、制御が困難です。湾は西は武関、東は淮海と繋がっており、大都市である。 「Tujing」によると、Jutan 郡は、その境界内にある Jutan 川にちなんで名付けられました。 盛洪志の『荊州記』には、「菊水、その源の傍らには芳しい菊が浸されており、そこから滋養液が流れ出る。その水は非常に香りがよく、甘く、それを飲むと長生きする」とある。 『後魏略史』には、孝文帝が南巡の旅の途中で新野に着いたとき、湖畔の菖蒲を見て「二菖蒲、新野の喜び」と歌ったと記されている。そして、それを記念して二菖蒲寺を建てた。 『楚地方記』には、漢江の北は南陽、漢江の南は南州と記されている。 香州 『十省記』には襄州襄陽県とある。 『豫公』の豫州の南境。春秋時代以降、楚の領土。秦南県の北境。漢代には南陽県であった。献帝の治世中、魏の武帝が初めて襄陽県を設置した。 『襄陽記』には、襄陽はもともと楚の従属都市であり、西には潭江が流れ、南には仙山が広がり、楚の北の港でもあると記されている。 『荊州地図写し』には、建安13年に魏武が荊州を平定し、襄陽県を置いたと記されている。湘山の南側に位置することからこの名が付けられました。 『楚郷記』には、蜀の関羽が于禁を含む七つの軍を攻撃して破ったと記されている。彼らの軍事力は非常に強大であったが、襄陽に駐屯していた徐晃だけが降伏を拒否した。曹公は黄に言った。「襄陽を救ったのは徐公だ。」その後、武帝は軍を西に進ませた。曹仁はそこに駐留していた。司馬玄王は魏の文王に言った。「襄陽は侵略者から身を守るための戦略的な場所であり、失ってはならない重要な場所だ。」 『南雍州記』には、雍嘉の乱の際、三県の貴族は樊と綿陽に逃れ、漢代に定住したと記されている。永州の設立は人々のニーズに基づき、人々に平和をもたらすことを目的としていました。そこで宋の文帝はそこに南容州を建設した。 『晋書』には、善堅、雅号は吉倫とある。私はかつて襄陽に駐在していました。その県には高陽池がありました。その池に行くといつも酔っ払って帰って来ました。人々は歌った。「善公はどこへ行ったのか?高陽池へ行った。夕暮れに逆さまに運ばれた。酒に酔っていて何も知らなかった。時々馬に乗ることができ、後ろ向きに白い草をつかむことができた。鞭を振り上げて葛強に尋ねた。汪州の少年と比べてどうか?」 盛洪志の『荊州記』には、襄陽県の延寿山から南の宜城まで百里余りあり、壁は彫刻され、建物は高く、家々が並んでいると書かれている。漢の宣帝の治世末期には、二千石級の大臣、地方長官、官吏が数十名おり、彼らの真珠楼閣と壮麗な天蓋が一列に並び、すべて大寺の下に隠されていました。荊州の知事が勤務中にそれを見て、その壮大さに驚きました。知事はそれを最高寺院と名付け、道に冠と天蓋を飾るように命じました。 「韓志」曰く:珠陽は南陽県に属する。古代の古国は現在、古城県となっている。マンはそれがイーヘだと言った。英邵はこう言った。「毗水は漢中の方嶺から流れ出て、東に流れて綿陽に至る。」(毗は「チュー」と発音する。) 『土井』にはこう記されている。古城県に霊という都市がある。 『韓志』によれば、ここは蕭何に「ザン」と発音される称号が与えられた場所である。 ジュンジョウ 『十省記』には君州武当県とある。 『朝貢の禹』の豫州の地域。春秋時代の楚地方。秦王朝は南陽県を設置した。 『韓志』によれば、武当は南陽県に属する。 『十州記』には、雲郷は古代雲国であったと記されている。左伝は言う。「楚の潘崇は荀を攻撃し、西学に到達した。」 『地誌』には次のようにも記されている。漢中県の東境には西県があり、そこは古代の西学である。 随州 『十省記』には、随州は漢東県であると記されている。春秋時代の水皇国。秦・漢の時代には南陽県に属していた。 左伝によれば、楚の武王が隋を侵略したとき、竇伯弼は楚王に言った。「漢の東の国の中で、隋は最も大きい国である。」 『韓志』によれば、隋は南陽県に属する。だからそれは李州だったのです。 『左伝』は言う:楚は徐を攻撃し、斉はそれを救うために黎を攻撃した。 (李一来) 崇陵とも呼ばれ、南陽県に属し、侯爵領となっている。旧蔡陽白水郷と上塘郷。漢の文帝の治世の元碩5年、長沙の王子麦は霊陵県霊道崇陵郷で崇陵侯の爵位を授けられた。その後、崇霊は雨に濡れていたため、皇帝に南陽への移住を要請する手紙を書いた。現在、棗陽には崇陵古城がある。 |
推薦する
明代史第177巻伝記第65号原文
王敖、年福、王洪、李冰、姚魁、王福、林聡、葉勝王敖は、字を九高といい、燕山の出身であった。永楽13年...
琵琶刑法とは何ですか?琵琶演奏に関する刑法の詳しい説明
琵琶を弾く刑罰とは何ですか? 琵琶を弾く刑罰は明代に発明された拷問で、主に金義衛と東昌が拷問の際に使...
「切り花の梅:秋の玉筵に漂う紅蓮の香り」は李清照によって書かれたもので、詩人の夫に対する深い思いを表現している。
李清昭は、宋代の雅流の女性詩人であり、易安居詩とも呼ばれています。学者の家に生まれ、文学的素養が高く...
『紅楼夢』で寧屋敷の客だった宝玉は、なぜ上の部屋に行って寝ることを拒否したのでしょうか?
秦克清は金陵十二美女の中で第12位にランクされています。 Interesting History の...
士公の事件第201話: 冷酷な呉成が良き友と出会い、七つの悪霊が訓練場で大混乱を引き起こす
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
涼山で第二の紛争が勃発した場合、反恩赦派は恩赦派を倒すことができるのでしょうか?
水滸伝の梁山泊の物語は好きですか?今日は、おもしろ歴史編集長が詳しく説明します〜涼山の重陽の菊祭りで...
西遊記の朱八戒が潜入捜査官だったとは思いもしませんでした!
西遊記は、三大派閥の争いを描いた物語です。仏典を求めて西へ旅するというのは、一見西への旅のように見え...
『西遊記』では、孔雀は強力な魔法の力を持っていますが、なぜ彼の子供が人間によって傷つけられるのでしょうか?
『西遊記』では、孔雀は強力な魔力を持っています。なぜ彼の子供たちは人間に傷つけられたのでしょうか?こ...
賈玉村は『紅楼夢』でどのように自分自身をパッケージ化し、人生の頂点に達したのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
大名姫の夫は誰ですか?大名姫の子供は誰ですか?
大明公主(1368年 - 1426年3月30日)は、明代の公主。明代の太祖朱元璋の7番目の娘であり、...
関羽に殺された顔良と文殊の真の強さは何だったのか?
どの王朝に最も強力で人気のある将軍がいたかといえば、三国時代です。これも三国時代の歴史の魅力です。諺...
『紅楼夢』の薛宝才は林黛玉よりどんな点で劣っているのでしょうか?
『紅楼夢』の薛宝才と林黛玉はどちらも才能があり美しい女性ですが、薛宝才は林黛玉よりどのような点で劣っ...
秋夕の唐代の詩を鑑賞するとき、杜牧はどのような芸術技法を使ったのでしょうか?
唐代の秋熙、杜牧については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!銀色のろう...
「已凉」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】緑の柵の外には刺繍のカーテンが垂れ下がり、真っ赤な血のスクリーンには折れた枝が描かれて...
バレンタインデーの伝説 中国のバレンタインデーの伝説
バレンタインデーの伝説:賢さと技巧を祈願する七夕祭りは、漢代に起源を持ちます。東晋の葛洪の『西都雑記...