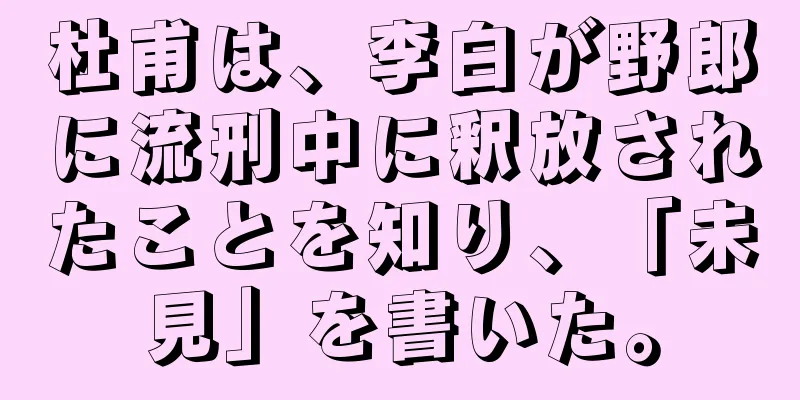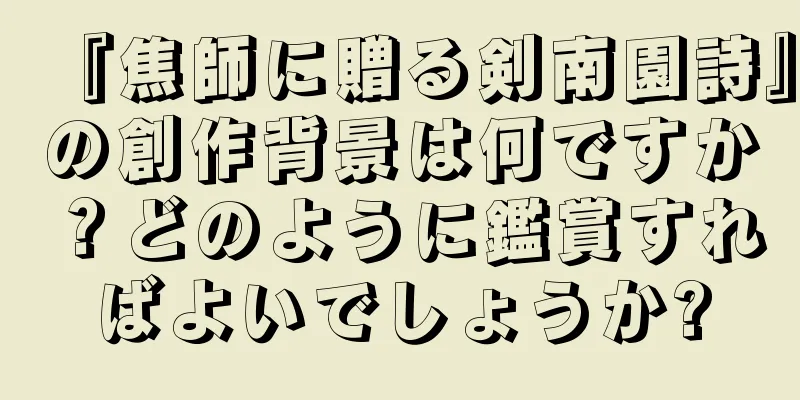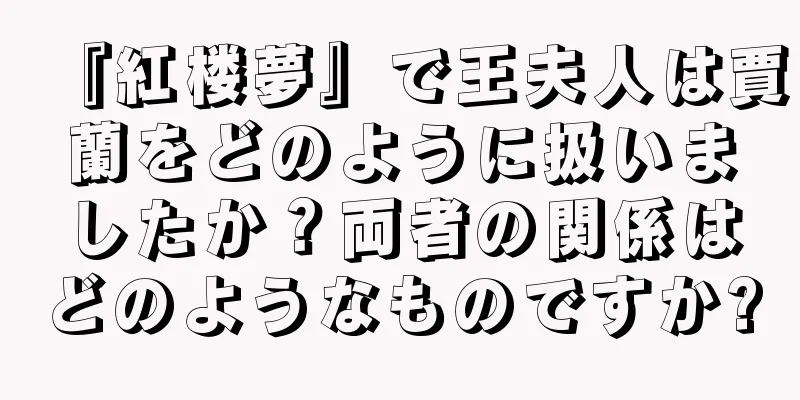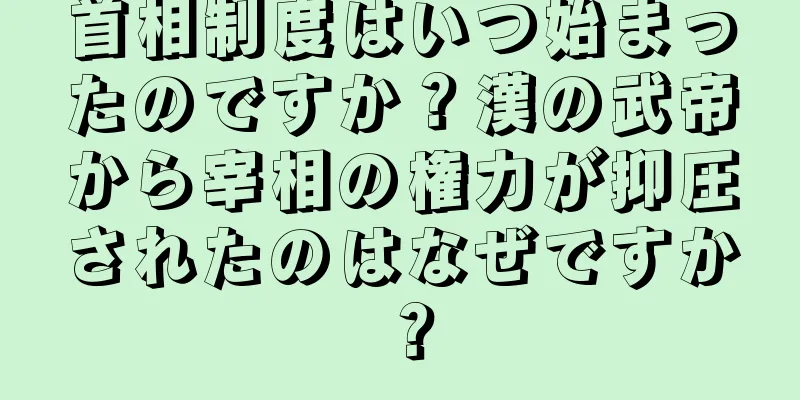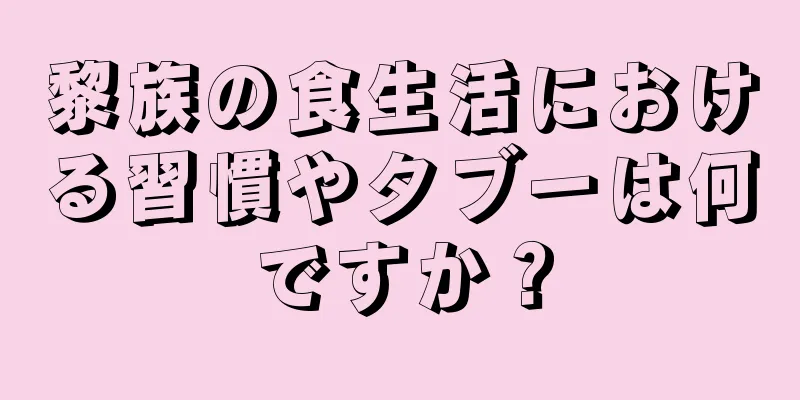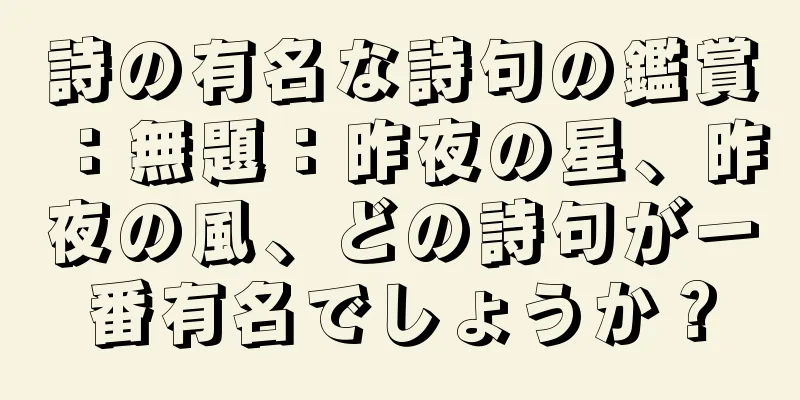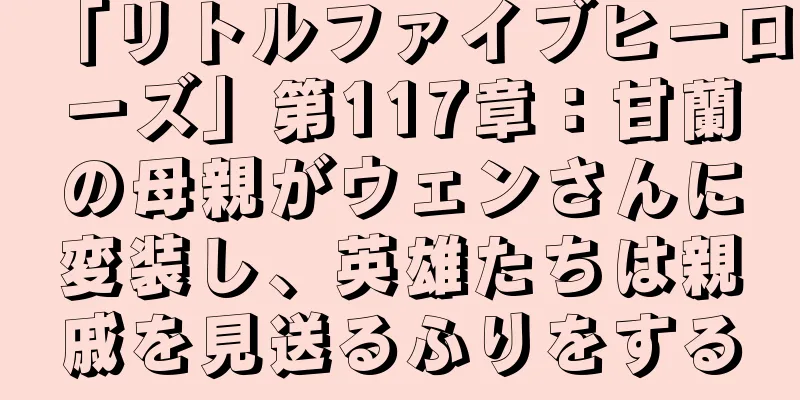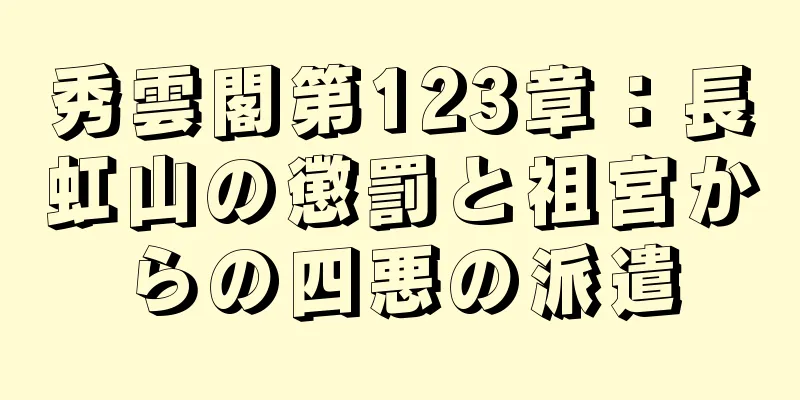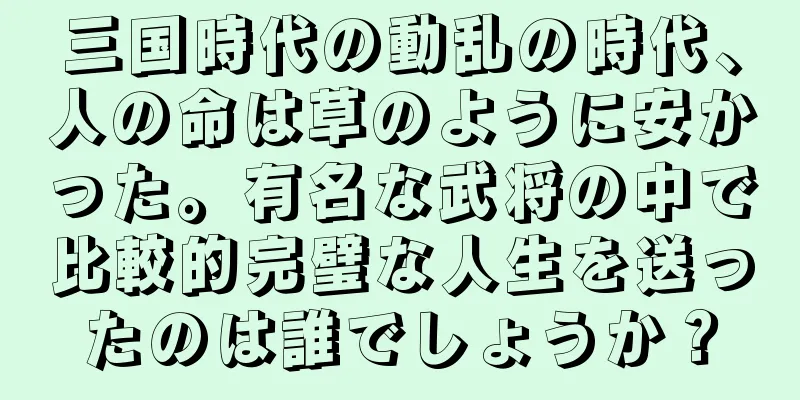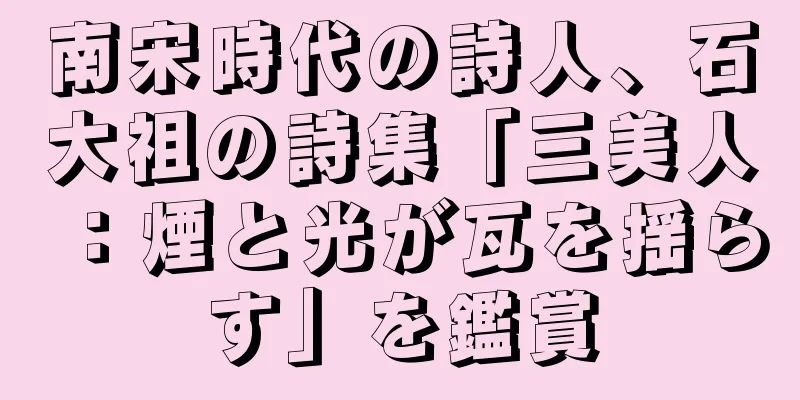古典文学の傑作『太平天国』:周君部第15巻全文
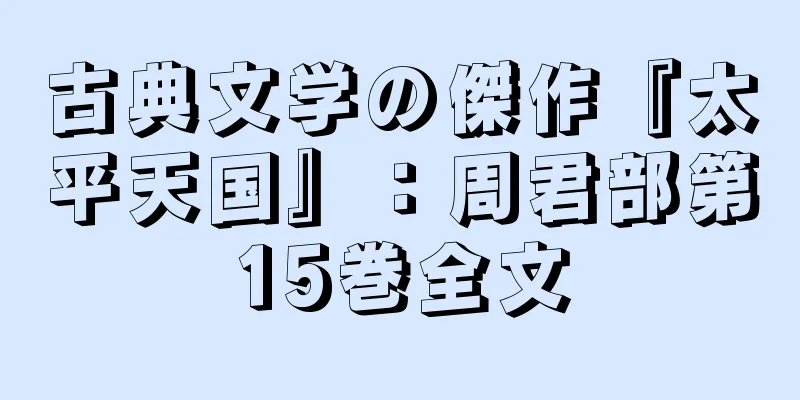
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が周君布第15巻の詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! ○ 淮南路 揚州 『元河県地図帳』には、揚州市広陵県と記されている。揚州は『朝貢禹記』に登場する九つの国のうちの一つです。春秋時代には呉に属していた。 7つの国は楚に属していました。秦が楚を征服した後、広陵となり、後に天下を統一して九江県に属した。漢代には江都国と呼ばれた。建武元年に揚州と改名された。 『左伝愛九年』には、武成杭運河が揚子江と淮河を繋いでいるとある。 『魏志伝』にはこう記されている。黄初六年、呉を攻めるために広陵城を訪れた。河畔の軍勢を眺め、波を見てため息をついて言った。「南北の境界は天だ。」 『隋書』には、伊寧元年、皇帝は江都宮の修復を命じ、江都への訪問のために龍船、鳳凰船、黄龍船、紅龍船、万楼船を用意したと記されている。彼は錦の帆と錦のテントを作り、「龍船に浮かぶ」や「春江月夜」などの歌を作曲して皇帝を楽しませ、そこに都を構えた。 『宋書』には、徐占之が揚州に豊亭、月関、垂台、秦市を建設し、娯楽や宴会の場としたと記されている。 また、揚州太守の王密が亡くなったとき、皇帝の補佐役は高帝が次に就くことになっていたが、劉懿らは皇帝の辞任を望まず、中央軍司令官の謝渾を揚州太守に任命し、丹渡の国を皇帝に治めさせることを提案し、この二つの案を皇帝に諮ったという。劉牧之は皇帝に言った。「揚州は重要な場所であり、他人に任せることはできません。以前、王彪に権力を与えたからです。今他人に与えれば、他人に支配されてしまいます。権力を一度失えば、取り戻すことはできません。」皇帝は同意した。 『県州記録』にはこう記されている。「広陵という都市が霊廟の上に築かれた。」 『二雅』には「大きな山を霊山という」とある。それは西蜀につながり、富岡山、崑崙山とも呼ばれている。鮑昭の『武城頌』には「草曲運河に引かれ、崑崙山に支えられている」とある。 『河図と地球』には、昆岡山は地球の水平軸であると記されている。この陵墓は崑崙と交差しているので、広陵と呼ばれています。 『韓志』には、高帝の6年に広陵国が建国され、景帝の4年に江都と改名されたとある。マンはそれを江平と名付けました。江都の易菲王と広陵の李胥王はともにここに都を置いた。 『漢書』には、広陵の李王が彼に勅を下して言った。「ああ、子胥よ、私はこの赤社を受け入れ、あなたの国を建て、南の地を与える。昔の人は言った。『長江の南、五湖の間は、人々が不注意で、揚州は強い。(宝、頼りになる)三代は従おうとしたが、それを正すことができなかった。』」 (堯夫は皇府の2番目のレベル内を意味する。正は政治を意味する。堯は堯の反対を意味する。) 『土京』には、江陽県はもともと漢代の江都県であったと記されている。川の北側にあったため、江陽と呼ばれた。 「韓志」曰く:江都は広陵国に属する。 海陵県、臨淮県とも呼ばれる。マンはそれがパビリオンにあると言った。 『十路記』には、六和県はもともと秦の唐夷県であり、春秋時代には唐であったと記されている。 「左伝」 襄王14年、楚王が永浦の戦いに参戦したため、子南は軍を率いて唐に向かった。 (雍、普、唐はすべて楚の都市です。) 滁州 『元河県記録』には淮陰県滕州と記されている。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋時代には呉と越の領土であった。戦国時代には楚に属していた。秦の時代には九江県に属していた。漢代には掖陽県の地であった。 『韓志』によれば、掖陽県は臨淮県に属する。マン氏は懐亭氏を監督すると述べた。潘水河の南側に位置するため、潘陽と呼ばれています。 また、広陵王徐が罪を犯し、勝利した臣下の秦が舒毗王の王位を奪ったとも言われています。 (張燕氏曰く:歙水池は歙陽県にある。) 『晋書』には、穆帝の治世に将軍荀献が北方へ遠征したと記されている。彼は、古い淮陰は水陸交通が良好で、好機を伺いやすい戦略的な場所であり、土地が肥沃で耕作に適しており、穀物を輸送する上で他に障害物がなかったため、そこに城を築いたと述べた。 『県州誌』には、北は清溪と臨淮に面し、平陽と石桂を要衝とし、田は水田が豊かであると記されている。 『呉越春秋』はこう言っています。呉が斉を攻撃しようとしたとき、広陵から運河を掘り、長江と淮河を結びました。つまり、状態と場所。 『史記』には、越は呉を滅ぼしたが、長江と淮河を制圧することができなかったため、楚は東に侵攻し、泗河に沿って領土を拡大したと記されている。 「韓志」曰く:徐邑は臨淮県に属する。ドゥウェイが統治する。マンは彼をウー・クアンと呼んだ。 『南兗州記』には、春秋時代には徐邑は風俗の良い場所であったと記されている。 『漢書』には、項羽は楚の淮王の孫である信を楚の淮王とし、襄邑を都としたと記されている。 『南兗州記』には、南兗州には塩屋が123軒あると記されている。この郡の人々は魚と塩の生産で生計を立てており、農業はほとんど行っていない。彼らは広大な海を利用して土地を肥沃にしている。公共および民間の商業輸送機関が、何千もの船舶を擁し、広範囲に渡って活動しています。このため、呉王は国を豊かにし、軍隊を強化して漢王朝に抵抗しました。 『土経』によれば、保応県はもともと安義県であり、漢代には平安県となり、広陵県に属していた。 『唐書』にはこう記されている。天宝の初めに、結婚後に尼僧となり、未亡人となった李という娘がいた。彼女の名前は真如であった。突然、誰かが空から降りてきて、彼に宝物をくれました。それで、Baoying という名前がつきました。 昊州 『十省記』には郝州中壢県とある。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋時代には中壢の国であった。戦国時代には呉に属していた。秦王朝は36の郡を設置したが、それらは九江県に属していた。漢王朝は中壢を建国した。 『春秋実録・成15年』には、叔孫喬如が中壢で呉と会い、呉との交流を始めたと記されている。中国とのつながりが始まります。 『趙二十四年』にも、楚王が艦隊を派遣して呉の国境を侵略し、趙と中壢を滅ぼしたと記されている。 『史記』には、楚の平王十年、呉の辺境の町毗梁の女性と楚の辺境の町中壢の少年が桑の木をめぐって争い、両家は怒り狂って互いに攻撃し合ったと記されている。楚は北良の民を攻撃した。北良の役人は怒り、軍隊を派遣して中壢を攻撃した。楚王はこれを聞いて激怒した。呉もまた軍を派遣し、光公を派遣して楚を攻撃させ、中壢を滅ぼした。 荘子と慧子は昊梁橋で泳いでいた時、一匹の魚がのんびりと泳いでいるのを見ました。荘子は言いました。「魚が幸せなのか?」慧子は言いました。「あなたは魚ではないのに、どうして魚の幸せがわかるのか?」荘子は言いました。「あなたは私ではないのに、どうして私が魚の幸せを知らないことがわかるのか?」 『史記』にはこう記されている。禹は土山で王子たちと会見し、そこには各国から集められた玉や絹があった。 『十省記』には、土山は臨淮県の西に位置すると記されている。 昭邑県は漢代にはもともと臨淮県であったとも言われている。 「韓志」曰く:懐陵県は臨淮県に属する。マンはそれを懐路と名付けた。 寿州 『元河県記録』には、寿州、寿春県と記されている。 『朝貢禹記』の揚州の地域。秦は天下を統一し、九江県を建てた。漢は淮南王国であった。 傅濤は『鄭淮論』の中でこう言っている。「戦国時代から晋の復興まで、600年以上続いた。」淮南を守ったのは9つの家があり、そのうち11人が兵を挙げたが、彼らは皆一瞬で亡くなり、災厄は世間に広がった。寿春を守る者は、南は荊と海の利益を享受し、東は三武の富とつながり、北は梁と宋とつながり、平地では700マイルを超えず、西は陳と徐を支えることができ、陸と水で1000マイルを超えず、外部には長江や湖などの障害があり、内部には淮河と肥河の堅固さがあります。龍泉池には数千エーカーの肥沃な農地があり、蜀と劉からの貢物はすべての蛮族に利益をもたらし、金属、石、皮革の道具が集められ、木、竹、その他の植物を育てる人々が住んでいます。彼らの習慣は肉体的な強さを重んじ、勇敢さに満ちています。彼らの人々は戦争に慣れており、欺瞞と策略を重んじているため、国を失うことがよくあります。 『史記』には、楚の高烈王が都を陳から寿春に移し、嬰と名付けたと記されている。 『項羽記』には、郝が嬴布を九江王に任命し、六つの都を置き、江と淮の全域を支配したとも記されている。 『韓書』は言う:「劉は古代の国であり、六安国に属していた。九堯の後に楚に滅ぼされた。」汴江が最初に受け取った渓流水と同様に、北東に流れて首春に至り、その後少壁江に流れ込みます。 (BiはBi、ShaoはJiと発音します。) 『左伝・文5年』には、楚成大信と鍾桂が軍を率いて劉を滅ぼしたとある。冬に鍾が帰国し、楚の謝公が遼を滅ぼした。 (遼は現在の安豊遼県である。)襄文忠は、柳玉遼が滅ぼされたと聞いて、「高瑶は強い人だったが、崇拝されなかった。彼の徳は確立されておらず、民の支持も得られなかった。なんと悲しいことだろう!」と言った。 『韓志』は次のように述べている。「寿春と合肥は北湖と南湖から皮革、アワビ、木材を産出しており、また大都市でもあった。」 (バオはアワビを意味します。) 「寿春記」曰く:三国時代、長江と淮河は戦争の戦場となり、数百里の範囲には人が住んでいなかった。金が呉を征服した後、その住民は故郷に戻り、郡は再び淮南県として設立されました。 『斉書』には、高祖がまず袁崇祖を首陽に駐屯させ、こう言った。「私は天下を取ったばかりで、魏は必ず劉昌を追い払う口実にするだろう。首春は敵が攻めてくるところなので、よく備えなければならない。」予想通り、彼は敗れて戻ってきた。 『十州志』には、霍丘県はもともと漢代には宋子県であったと記されている。 「韓志」曰く:宋子は侯爵である。廬江県に属する。マンはよく暗唱すると言いました。 『十省記』には、霍山県は清県とも呼ばれていると記されている。 『韓志』によれば、清県は廬江県に属する。天竺山は南にあります。 『史記』には、呉の和經王の治世4年、楚を攻撃し、霊を占領したと記されている。 滁州 『元河県記録』には、永陽県滁州と記されている。春秋時代の楚地方。漢代には泉郊県であった。 『韓志』によれば、泉郊県は九江県に属する。 『十州志』には、隋の時代には楚州と呼ばれ、楚河にちなんで名付けられたと記されている。 『県州記』には、後漢の時代に彭城の劉平が全郊の知事を務め、虎が皆川を渡ったと記されている。 賀州 『元河県記録』には賀州市溧陽県と記されている。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋時代、戦国時代には楚の一部であった。秦の時代には溧陽県であり、九江県に属していました。漢は淮南王国であった。 『県州記録』には、溧陽の西に鵝湖城があり、王道が石虎に抵抗するために築いたと記されている。 『韓志』によれば、溧陽は都衛の所在地である。九江県に属する。マン氏はそれが正義だと言った。 『十州志』には、南に漓江があり、漓陽と呼ばれるとある。 『淮南子』によれば、溧陽の都は一夜にして湖になった。 (漢の明帝の治世中に、麗陽は馬胡となった。) 『Shidaozhi』によれば、馬湖は郡の西10マイルにある。 『漢書』にはこう記されている。漢軍は江東城まで項羽を追撃し、呉江亭の長は船を停泊させて彼を待った。 瀘州 『元河県記』には、廬江県は古代の廬子王国であったと記されている。春秋時代の蜀の国の地。 『十路記』には、戦国時代、この地は楚の領地であったと記されている。秦王朝は36の郡を設置したが、それらは九江県に属していた。漢代の合肥県であった。 『左伝・陸西公四年』には「徐人が蜀を占領した」とあり、杜宇の記録には「蜀国は今の蜀県、廬江である」とある。 「上州鍾馗」:程唐王は桀を南朝に追放した。 「魏志」はこう言った。「清隆元年、万充は揚州の太守であった。彼は合肥城の西30マイルに新しい城を建てることを要求した。彼は碑文の中でこう言った。「合肥城は南は川と湖に接し、北は寿春に至っている。もし賊が攻めて包囲したら、水につけることができる。将兵が救出するとき、まず賊の大部分を倒して、それから包囲を解くことができる。賊にとってはそこに行くのは容易だが、兵士にとっては救出するのは非常に困難である。今、城の西30マイルに奇妙で危険な場所がある。我々は城を建てて守ることができる。これは賊を平地に誘い込み、その退路を塞ぐということである。」皇帝は同意した。 『廬江記録』には、民衆の声や地元の風習はいずれも淮河の左岸にある他の県よりも優れていると記されている。 『韓志』によれば、廬江県はかつて淮南県であった。文帝の治世16年に、12の県を管轄する独立国家として設立されました。 龍树とも呼ばれ、廬江県に属します。英邵は言った。「それは群樹の町です。」 廬江に属し、巨潮とも呼ばれます。英邵曰く、「春秋実録」:「楚の民が趙を包囲した。」趙。国。 『左宣昭25年』には、楚王が熊襄を遣わして郭超に陰謀を企てさせたとある。 (巣のための城壁を建設中。) 「県州記録」には、汝樹川は巣湖に源を発し、馬尾溝と呼ばれていると記されている。 『十省記』には、沈県はもともと漢代の君丘県であったと記されている。 「韓志」曰く、君丘は九江県に属していた。 (junの発音はjun、qiuの発音はchuの反対です。) シュジョウ 「説明」によると、蜀には蜀容、蜀龍、蜀州、蜀九、蜀成の5つの名前があるが、実際は同じである。 『左伝定二年』には、呉子が蜀九人を派遣して楚人を誘い出したとある。 『元河県記録』には、同安県舒州と記されている。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋時代の万国であった。 『十道記』には、春秋時代には楚の東の国境であったと記されている。戦国時代には楚に属していた。秦の時代は36の県を設置し、江夏県と名付けました。 『史記』には、万は万姓であり、九堯の子孫であると記されている。春秋時代に楚によって滅ぼされた。 「韓志」曰く:万は廬江県に属する。 『後漢書・郡州記』には、廬江県が蜀県から安徽省に移されたと記されている。 『魏志』にはこう記されている。正始二年、孫権は諸葛恪を万城に駐屯させ、国境の好機を伺わせた。 『呉志』はこう言っている。曹公は朱光を廬江の太守に任命し、万に駐屯させて広大な田畑を開いた。呂孟は言った。「万の地は肥沃だ。収穫が熟すと、人口は確実に増える。この状態が数年続くと、曹操の真意が明らかになる。できるだけ早く曹操を排除すべきだ。」そこで呂孟は自ら軍を率いて万に遠征し、曹操を打ち破った。 『宋書県郡記』には、晋の安帝が旧萬城に淮寧県を設置したと記されている。 『土経』によれば、同城は春秋時代の同州の国であった。漢代には丞陽県でもあった。 『左伝定二年』には、董が楚に反乱を起こしたとある。 (通とは小さな国という意味です。廬江市舒県に通郷があります。) 『韓書紀翁』にはこう記されている。元豊5年、彼は南方へと狩猟に出かけ、荀陽から川を下り、川の中の龍を射て捕らえた。船は数千マイルを旅して、丞陽から出航し、「唐隆丞陽の歌」という詩が作られました。 斉州 『十省記』には、斉州、斉陽県とある。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋戦国時代には楚の領土であった。秦王朝は36の郡を設置したが、それらは九江県に属していた。漢代の斉春県の地。 「韓志」曰く:斉春は江夏県に属する。 『史記』には、秦の始皇帝の治世16年に楚が滅ぼされ、楚王は捕らえられて斉に連れ去られたと記されている。 『地名録』には、水辺で豊富に採れる七菜にちなんで、七春と名付けられたと記されている。 『晋書』には、宣王母の禁名が淳であったため、武帝が秦陽に改名したと記されている。 『呉志』は言う。衛は廬江の謝季を斉春県の農事長官に任命したが、呂孟が攻撃して彼を打ち負かした。 『何斉伝』には、次のようにも記されている。「初め、金宗は西口の将軍であったが、民を率いて反乱を起こし、魏に渡った。彼は帰郷して斉春の知事となり、安楽を攻撃してその防衛を企てた。」全は恥じ、軍が解散したばかりの6月の盛夏に、斉太守の米芳、仙于丹らに斉春を攻撃し、宗を生け捕りにするよう突然命じた。呉は斉春県を再建した。 神州 『十省記』には神州益陽県とある。 『朝貢禹記』の荊州の地域。春秋時代の神国の地。秦の時代には南陽県の領土であった。漢王朝は荊州に属する平石県を設置した。漢の武帝は北将の魏志を益陽侯に任命した。魏の文帝は南陽を分割し益陽県を置いた。宋代の元嘉末期に益陽に泗州が設立された。周の武帝は神州の統治者でした。 「Yu Di Zhi」は言う:Yi Yangには3つの危険なパスがあります。 『十道記』には、三つの峠を平井関と呼んでいると書かれている。(長老曰く、この峠は山に阻まれ、溝がないので、平井と名付けられた。)その一つが五羊関と黄仙関で、安州盈山県境に位置している。 光州 『十省記』には広州益陽県とある。 『朝貢禹記』の揚州の地域。春秋時代の仙子王国。秦王朝は36の郡を設置したが、それらは九江県に属していた。漢代には西陽県であった。 『左伝・西暦五年』には、楚人が西安を滅ぼし、西安子は黄に逃げたとある。 (弦は益陽県にあります。) 『韓志』によれば、西陽は江夏県に属する。 別名:軚、江夏に属します。かつての仙子国。 (「タイ」と発音し、「ツ」の逆としても発音します。) 『土経』には、定城県は春秋時代の黄子の国であったと記されている。 『十三県記』には、定城は古代黄子国の南12マイルに位置していたと記されている。 『十州志』には、定城はもともと漢代の益陽県であったと記されている。 「韓志」曰く:易陽は侯爵である。汝南県に属する。宜山は北西にあります。かつての黄州は現在黄城県となっている。 『十州記』には、古市県はもともと秦丘であり、孫宋が領地を与えられた町であったと記されている。 銀城県は漢代には元々泗県であったとも言われています。 「韓志」曰く:斉思は汝南県に属する。つまり、江州だったのです。 「左伝」はこう言った。「樊江は周公の子孫である。」 安州 『十省記』には安州安鹿県とある。春秋時代に雲子という国があり、そこに雲夢湖がありました。その後、楚は雲を滅ぼし、その地である雲公に竇信を封じた。戦国時代には楚に属していた。秦が天下を統一すると、南君の城となった。漢代には安鹿県であった。宋の武帝が安禄県を建てた。唐の武徳4年、安州であった。 黄州 『十省記』には黄州遷安県とある。 『朝貢禹記』の荊州の地域。戦国時代には楚に属していた。秦では南君の地であった。漢代には西陵県であった。高啓が衡州を建国した。隋の開皇3年に黄州と名付けられた。 麻城県と黄陂県はもともと漢代には西陵県であったとも言われている。 綿州 『十省記』には綿陽県、漢陽県とある。 『朝貢禹記』の荊州の地域。春秋時代の雲国の地。戦国時代には楚に属していた。秦が天下を統一すると南州地域となった。漢代には安禄県の領土であった。晋の時代には敦陽県が設けられ、江夏県に属した。唐の武徳4年に綿陽県が設置された。 『禹の文書・貢物』には「綿河を渡る」とある。 (漢代は面と呼んだ。) 『三国志』には、魏が初めて荊州を征服したとき、敦陽は重要な町とみなされていたと記されている。 『晋書』には、永嘉6年、王惇は陶幹を荊州太守に推挙し、綿陽に駐在させたと記されている。 『宋書県郡記』には、晋の時代に臨漳山に敦陽県が置かれたと記されている。 『荊州記』には次のように記されている。「林棠山の南峰は武林峰と呼ばれ、赤壁とも呼ばれる。」 『呉志』はこう言っている。曹公が荊州に近づいたとき、孫権は周瑜と程普を左右の指揮官として派遣し、一万人を率いて劉備とともに進軍させ、赤壁で会った。 『永初山河記』には、綿陽口は古代には滄浪江であると信じられており、屈原が漁師と出会った場所である、と記されている。 |
推薦する
東漢と西漢の違いは何ですか?なぜ姻戚関係にある人が常に権力を握るのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が東漢と西漢の違いについての記事をお届けします。ぜひお読みください〜国名...
呂桂孟の「ムーランの裏池への三つの頌歌:白蓮」:詩人自身の見解を直接表現している
呂帰孟(? - 881年頃)、号は呂王、号は天水子、江湖三人、伏里献生。常熟(現在の江蘇省蘇州)の人...
なぜ項羽は鴻門の宴で劉邦を殺さなかったのですか?
『鴻門の宴』は、項羽が劉邦を殺そうとして鴻門で宴会を開いた物語です。まだ知らない読者のために、次の興...
四聖心 出典:巻六:雑病之解:薊理根源全文
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
『紅楼夢』の邢叔父とは誰ですか?彼と邢秀燕との関係は?
邢秀燕は『紅楼夢』に登場する邢忠とその妻の娘であり、邢夫人の姪である。 Interesting Hi...
孟浩然の詩「雲門寺の西6、7マイルのところに伏公庵があると聞いて、薛覇と一緒にそこへ行った」の本来の意味を鑑賞
古詩:「雲門寺の西6、7マイルにある最も人里離れた場所が伏公庵だと聞いて、薛覇と一緒にそこへ行きまし...
唐代の書家張旭の詩:「山行客宿」の鑑賞
以下、Interesting History の編集者が張旭の「客を山に留める」の原文と評価をお届け...
陳朱の「江城子・中秋初雨晩晴」:風雨に負けない精神を表現
陳卓(1214-1297)は6月13日午後10時に生まれた。号は向孫、字は紫微、号は千之、号は本堂、...
ウズベクの民話と物語詩
ウズベキスタンの民俗文学はウズベキスタン文学の重要な部分を占めています。最も広く流布しているのは民話...
清朝の十二皇帝は死後どこに埋葬されたのでしょうか?
清王朝は、ヌルハチの台頭から黄太極が1636年に国名を清と改め、1912年に清皇帝が退位を余儀なくさ...
「正義のために親族を殺す」ことがなぜ最も恐ろしい美徳とみなされるのでしょうか? 「正義のために身内を殺す」というのは褒め言葉でしょうか、それとも批判でしょうか?
「正義のために身内を殺す」ことがなぜ最も恐ろしい美徳なのか?「正義のために身内を殺す」ことは褒め言葉...
南宋時代の詩人朱淑珍の『秦夷を偲ぶ・正月六日月』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
「秦夷を偲ぶ・正月六日の月」は南宋時代の詩人朱淑珍が書いたものです。次の『興味深い歴史』編集者が詳し...
もし関羽に個人的な感情がなかったら、本当に曹操を止めることができたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
燕と黄の子孫である私たちの祖先には、どんな物語があるのでしょうか?
Interesting Historyの編集者がお届けする、炎帝と黄帝の伝説的な物語を見てみましょう...
涼山の英雄の中で第4位にランクされた公孫勝がなぜ最初に涼山を去ったのでしょうか?
公孫勝は涼山の英雄の中で4番目にランクされ、別名は如雲龍です。なぜ彼は涼山を最初に去ったのでしょうか...