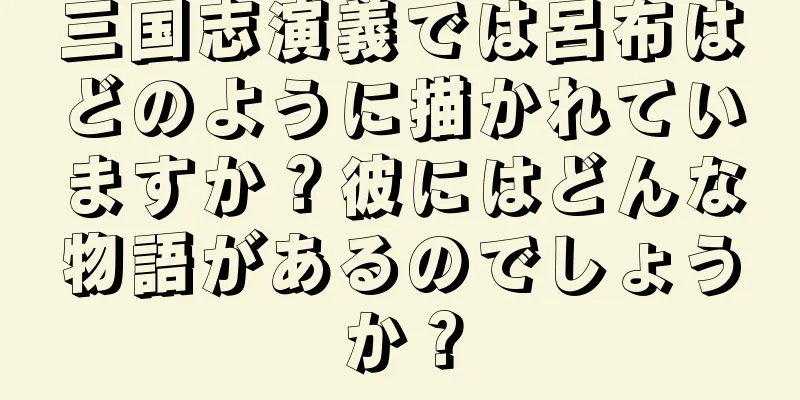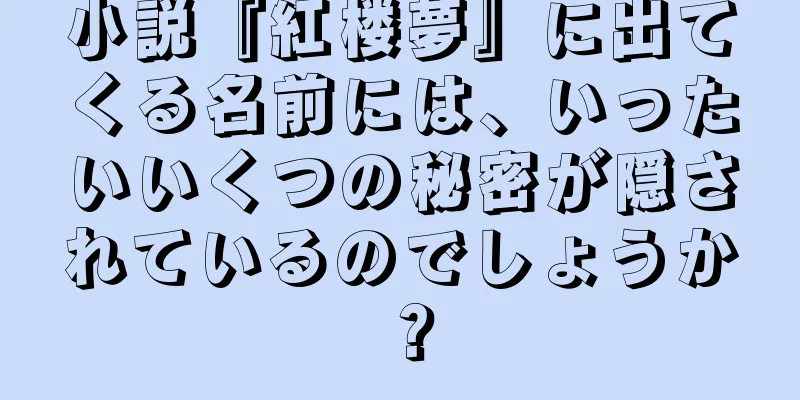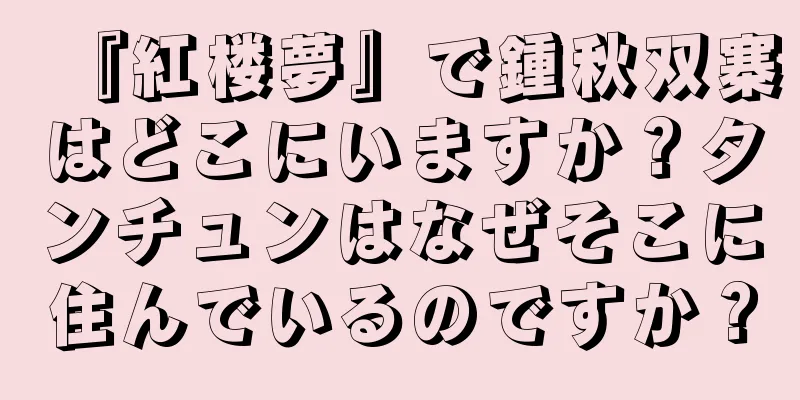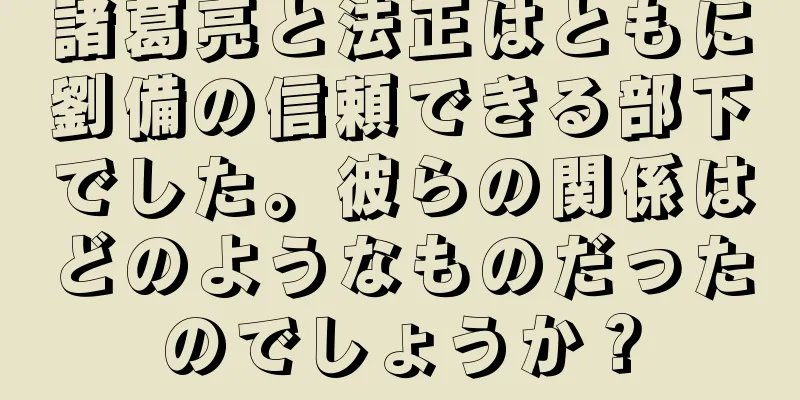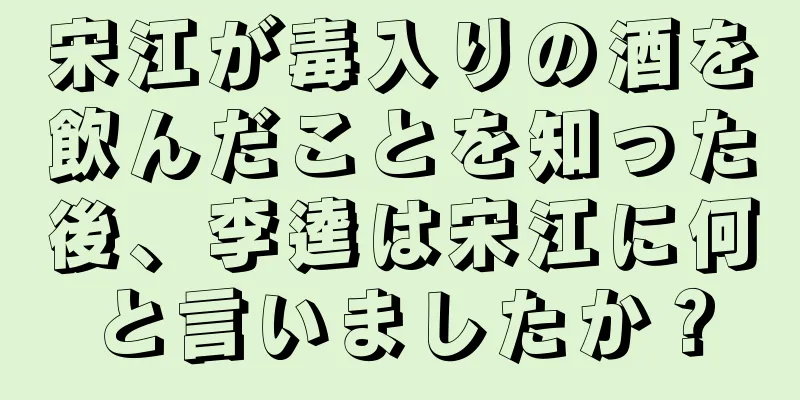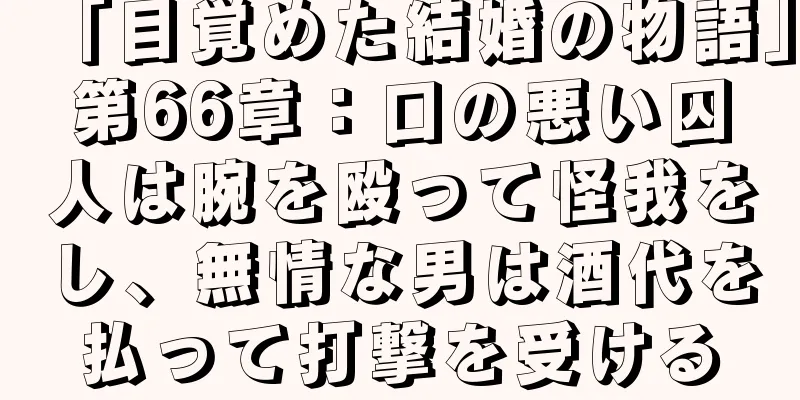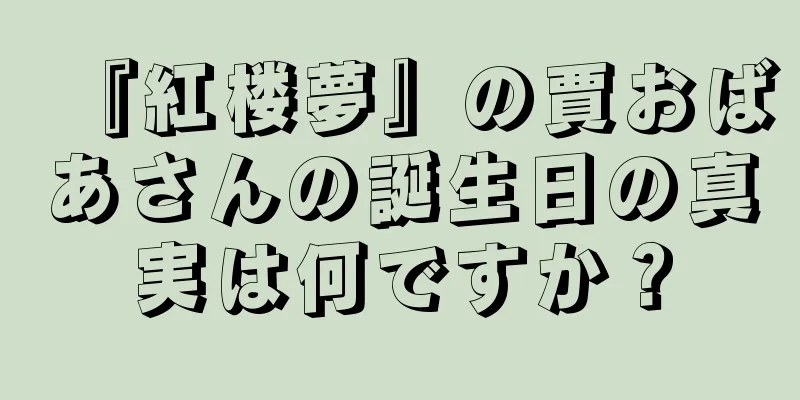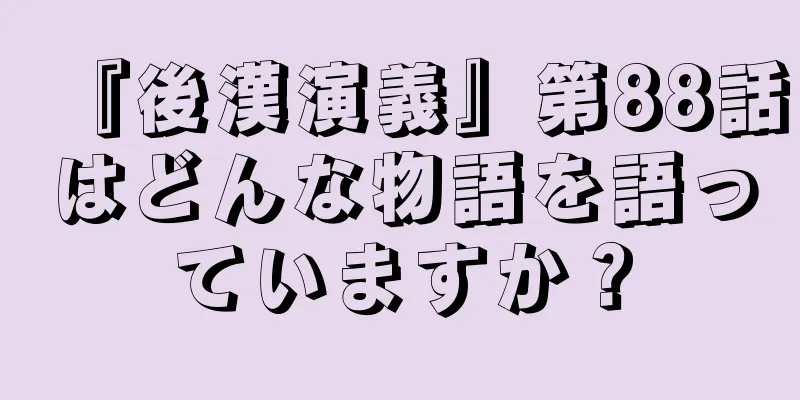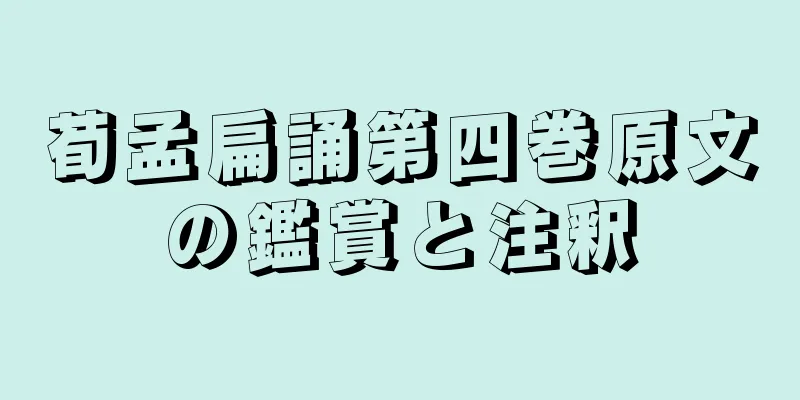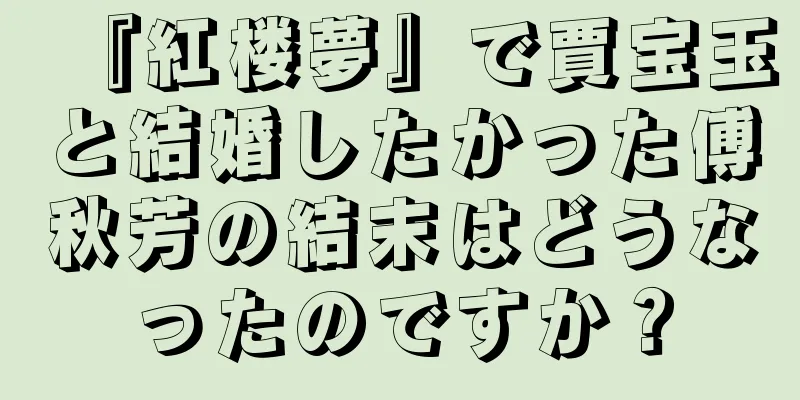明楊吉州(吉師)著『鍼灸学論集』第2巻:玉龍譜全文
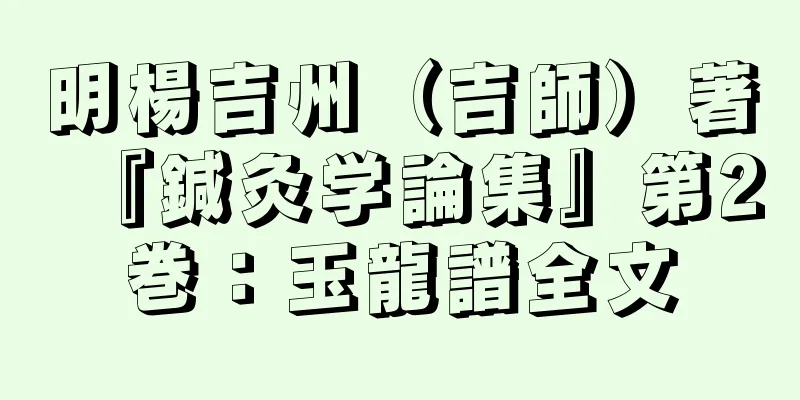
|
『鍼灸学事典』とも呼ばれる『鍼灸事典』全10巻。明代の楊其左によって書かれ、万暦29年(1601年)に出版された。楊氏は、家宝の『衛生鍼術秘伝』(略称『衛生鍼術秘伝』)を基に、明代以前の鍼術書20冊以上を参考に、著者自身の鍼術臨床経験を加味して本書を編纂した。本書は、鍼灸理論と施術法を比較的包括的に論じ、経穴の名称と位置を調べ、歴代の名医の鍼灸症例を記録しており、明代以前の鍼灸研究のもう一つの集大成であり、鍼灸の学習と研究のための重要な参考書である。それでは、次の興味深い歴史編集者が第2巻「玉龍譜(ジュイン)」の詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 鍼治療においては、迅速な方法が最も奇跡的です。危険から回復するには、補液と排液の技術を明確に理解する必要があります。まず病気を上部と下部に分けて、経穴の高さを決定します。頭が病気なら足で治療し、左側が病気なら右側で治療します。男性のエネルギーは早く頂点に達し、遅く底に達するので、摂取する際には原則を理解しなければなりません。女性のエネルギーは早く底に達し、遅く底に達するので、使用する際には適切な時期を知っておく必要があります。正午前は朝で陽に属し、正午後は夕方で陰に属します。男性と女性の場合、上部と下部は腰によって決定されます。手足の3つの陽経は、手から頭へ、頭から足へ通じています。手足の3つの陰経は、足から腹部へ、胸から手へ通じています。陰が上昇し、陽が下降する、出入りのメカニズム。それに対抗することは、浄化し、歓迎することであり、それに従うことは、補足し、従うことです。春夏は痩せ型の人には浅めのピアス、秋冬は太めの人には深めのピアスがおすすめです。また、気の太さも考慮し、鍼をどのくらい浅く、または深く刺すかを決定します。 古典にはこう記されている。「滋養の気は経絡を巡り、昼夜を問わず身体を50周し、夜明けに手の太陰で防御の気と出会う。」衛気は経絡の外側を流れ、昼は陽に25度、夜は陰に25度進み、夜明けに手の太陰で容気と出会います。衛気の運行は昼と夜に分かれているだけで、上部と下部の区別はありません。男性と女性の内臓、経絡、気、血液の循環は同じです。 「現在の朝と夕方の区分の根拠は何だろうか。しかし、このような賦は現代人には重んじられているので、参考までに記しておく。」 補気・排膿法の魔法は呼吸と指にあります。男性の場合、親指は前に動かして左に曲がり、息を吐いて養い、後ろに動かして右に曲がり、息を吸って排泄し、針を上げると熱くなり、針を上げると寒くなります。女性の場合、親指は後ろに動かして右に曲がり、息を吸って養い、前に動かして右に曲がり、息を吸って排泄し、針を刺すと熱くなり、針を上げると寒くなります。左と右が違いますし、胸と背中も違いますし、お昼前はこんな感じで、お昼以降はその逆になります。したがって、爪で切ることは針を刺す方法であり、振って後退することは針を抜く方法であり、動かして前進することは針を促す方法であり、従って抑制することは気の循環を促進する方法です。こすると病気が治り、叩くと欠乏を補うことができ、腹部を一周し、触れると閉じたツボのような感覚になります。強い圧力をかけることを「押す」、軽い圧力をかけることを「持ち上げる」といいます。鍼治療には14の方法が必須です。補おうとする者にとっては、一退三退で真の気は自然に還り、浄化しようとする者にとっては、一退三退で邪気は自然に避けられる。補うには、不足しているものを補い、排除するには、過剰にあるものを排除します。過剰になると腫れや痛みが生じ、これを「過剰症」といいます。一方、不足すると痒みやしびれが生じ、これを「過剰症」といいます。気が速ければ効果も早く、気が遅ければ効果も遅い。生きている者は衰弱し、死んだ者は衰弱する。気が来るのを待たなければ、必ず死ぬ。 この技術は4巻にわたって詳細に説明されています。 針を刺す前に、指で針を強く押して患者に咳をさせ、咳をしながら針を刺す必要があります。患者が補充を必要とするときは、息を吐きます。針が最初に皮膚に刺入すると、天菜と呼ばれます。しばらく止めて針を肉に刺入すると、人菜と呼ばれます。再び止めて、腱と骨の間に針を刺入すると、迪菜と呼ばれます。これは極点であり、補充してから長時間止めますが、患者の気があるところまで針を引き戻さなければなりません。気が深く締まるまで待ってから、針を病変部に戻し、前後に動かして、気を経絡に流します。すべてこれにかかっています。気を抜くときは、患者が息を吸い、まず針を天に突き上げます。その後、しばらく停止し、針を地面に届くまで進めます。気を抜くときは、しばらく停止してから針を引き抜き、患者に戻します。気が深く締まるまで待ってから、針を逆にして患者に向けます。方法は前と同じです。鍼治療後に患者が気絶した場合は、気力とエネルギーが弱っているためです。針で気力を補充し、口と鼻からの呼吸を再開させ、熱いスープを与え、しばらく待ってから、前と同じように手順を繰り返します。 肝経のツボを刺してめまいを感じる場合は、肝を補うツボであり、針を刺すとすぐに目が覚めます。他のツボも同様です。鍼治療後にめまいを感じる人は、足三里穴または人中穴を補う治療をすべきです。めまいのほとんどは心臓から来ます。心臓が怖くないのなら、めまいはどこから来るのでしょうか?まるで、毒を治すために骨を削ったが顔は変わらなかった関公のようです。 気の調節方法は、針を地面に刺した後、人体を元に戻します。気を上げたい場合は、針を右にひねります。気を下ろしたい場合は、針を左にひねります。補いたいときは、まず息を吐いてから吸い込みます。排出したい場合は、まず息を吸ってから吐きます。気が来ない場合は、手を使って気を追い、爪でつまみ、針で振って、ひねって、こすって、叩いて、気が来るまで続けます。昇龍虎の法則を使い、前を押すと気が後ろに行き、後ろを押すと気が前に行きます。痛みのある部分に気を流し、気取り法で針を真上に刺し、気が戻らないように下に引きます。関節が詰まって気の流れが悪ければ、龍虎亀鳳凰法で経絡を開き、気を繋ぎます。大節法で動かし動かします。脈を追って切る方法も有効です。これが不死になる不思議です。 龍虎亀鳳凰の術も4巻に注釈されている。 また、針を抜く方法は、病気が治まれば針の気が少し緩みます。病気が治まっていないと、針の気が根付き始め、押したり回したりしても動かなくなります。これは邪気が針を吸い取っているからです。本当の気が戻ってくるまで、針を抜いてはなりません。抜くと病気が再発し、再度補ったり抜いたりする必要があります。回復するのを待ちます。針が少し緩んだら、針を少し抜いて振って止めます。補気の場合は吸入により病を取り除き、ツボを素早く押圧します。瀉気の場合は呼気により病を取り除き、ツボを閉じないようにします。毛穴を引き締めてから息を吸い込むので、「針をゆっくり刺し、あまりに急いで刺すと血液を傷つけ、針をゆっくり抜き、あまりに急いで抜くと気を傷つける」と言われています。 「以上が大まかなポイントです。」 『初等医学古典』にはこう書いてある。「針をいきなり抜いてはいけません。3、4回抜いてください。ゆっくり抜くと血は出ません。いきなり抜くと血が出ます。」 『内科経補遺』の注釈には、「気が動くと、すぐに針を抜く。これは激しい抜き方である」とある。しかし、これは違います。一般的に、経絡に血栓がある場合、大便をしたいのであれば、激しく排出する必要があります。通常の補気や瀉血が必要な場合は、これに従ってください。区別することも重要です。 』 甲府には八つの病気治療法がある。一つは火で山を焼くこと。これは頑固な痺れ、冷え、麻痺を治療するために使用される。浅い治療から始めて深く行く。九陽法を用いて三回前進後退する。ゆっくりと持ち上げて強く押す。熱が来たら針を閉じて刺す。寒を取り除くのに正確である。 2つ目は「頭天亮」と呼ばれ、筋肉の熱と骨の蒸しを治療するために使用されます。最初に針を深く挿入し、次に浅く挿入します。6つの陰経と3つを外側に、3つを内側に使用します。しっかりと引き上げてゆっくりと押します。風邪が来たら、針をゆっくりと上げます。熱を下げることができます。丁寧にこすりつけることが病気を治す最善の方法です。 3つ目は、陰は陽の中に隠れていて、最初は寒くて次は熱く、浅くて次は深いということです。九六法によれば、最初に補ってから浄化するという意味です。 4番目は、陽は陰の中に隠れていて、最初は熱く、次に冷たく、深く、次に浅い。69の方法を使用すると、最初に浄化し、次に補充することを意味します。補熱にはすぐに熱が入り、瀉熱にはすぐに寒が入ります。糸を撚り、針をゆっくり回すようなものです。方法が浅ければ浅い方法を使い、方法が深ければ深い方法を使いましょう。この2つは同時に使うことはできません。 5日目は紫烏で、臼を搗き、姑横隔膜の気を流し、針をツボに刺した後、気を均等に調整し、針を上下に動かし、9回入れて6回出し、左右に回して10回バランスをとります。六番目は、空気を取り入れる秘訣です。腰、背中、肘、膝、全身の痛みには、針を9つのポイントに刺し、針を9つのポイントに移動して補充し、針を所定の位置に置き、5〜7回息を吸い込み、空気が上下するのを待ちます。また、龍と虎の戦いを行うこともできます。左の9つのポイントと右の6つのポイントをねじります。これも痛みを止める針です。七番目は気を保持する秘訣です。腫瘍、障害物、腫瘤には、純粋な陽を使用して針を7分の10まで刺します。次に、針をまっすぐに挿入し、気が来たら深く刺し、針を持ち上げて止めます。八番目は抽出と追加という秘訣です。麻痺、傷、ハンセン病の場合は、九陽に気を流すためのツボを選び、持ち上げて押して探り、基本的に気を循環させます。針をまっすぐに刺し、次に下に押して、陽を戻し、陰を逆にし、神秘的なポイントを指して、胸を活性化します。反応がない場合は、この方法をもう一度繰り返します。風習や祭りのときに運気を上げたいなら、飛龍経絡を使ってエネルギーを循環させるといいでしょう。方法は4つあります。1つは、青龍を使って尾を船の舵のように振り、前進も後退もせず、ゆっくりと左右に動かす方法です。 2 つ目は、ホワイト タイガーが鐘を鳴らす手のように頭を振り、四角形に戻り、次に円に戻り、さらに左右に揺れ、振動します。 3つ目は、洞窟を探検するカメです。まるで地中に入って、一度後退して3回前進し、四方八方に穴をあけて掘っているかのようです。 4つ目は、鳳凰が源を迎え、翼を広げる儀式です。針を地面に刺し、針を空に持ち上げ、針が自然に揺れるのを待ってから、針を元の位置に戻します。上下左右に飛び回ります。病気が上部にある場合は、息を吸って退却させ、病気が下部にある場合は、息を吐いて前進させます。 上記のテクニックは、あくまでも大まかな概要にすぎません。全体のプロセスについては第 4 巻を参照してください。 長い間片麻痺に悩まされてきた人に対しては、経絡を開いて気を繋ぐ、つまり呼吸の回数を調節する方法があります。手足の三陽経絡は、上が9本、下が14本で、経絡の幅は4インチです。手足の三陰経絡は、上が7本、下が12本で、経絡の幅は5インチです。経絡を出し入れし、呼吸も同様です。気血を動かし、瞬時に循環させ、上部と下部を結びます。寒さを温め、熱を冷まし、痛みを止め、腫れを取り除きます。まるで水路を開いて水を流すように、効果がすぐに現れるのに、どうして危険な状況を回避できないのでしょうか。しかし、病気の原因は3つあり、すべて気と血に関係しており、鍼灸は8つの方法に分かれており、陰陽と切り離せないものです。経絡は昼夜を問わず循環しており、呼吸も絶えず行われています。これらが調和していれば、身体は健康になります。そうでなければ、病気が発生します。たとえば、すべての国、地域、山、海、野、川、谷では、季節ごとに風と雨のバランスが取れていれば、水路は妨げられることなく、人々は安全で繁栄します。時には、風と雨が一箇所に偏って干ばつや洪水を引き起こし、水路が干上がって災害をもたらすこともあります。場所が干ばつや洪水の影響を受けるのと同じように、人の気と血は三つの病気の影響を受けます。鍼灸は経絡を開き、気血のバランスを整え、邪気を消し、体を強くすることができるので、最も早くて奇跡的な方法であると言われています。 ああ、玄啓は遠く、陸扁は亡くなって久しい。この道は奥深く、数語で表現しきれない。優雅で緻密であり、長い修行を経てのみ習得できる。それは単に世間でよく使われる言葉ではなく、凡人の一般的な技能である。それを得る者は科挙に合格したようなもので、心は喜び、それを使う者は弓矢で的を射たようなもので、目は満足である。この技術は古代の賢者から後世に受け継がれてきました。鍼灸師がそれを習得しようと決意し、その奥深い神秘を真に理解し、その精妙さを十分に活用することができれば、幸運にも鍼灸の恩恵を受ける人々が鍼灸に出会えば、世界中の慢性疾患はすべて簡単に治癒するでしょう。 |
<<: 『西遊記』の朱八戒は本当に好色で貪欲な人物なのでしょうか?それは彼の変装に過ぎない。
推薦する
愚か者とは何か:なぜ愚か者は馬鹿と呼ばれるのか?
「二百舞」は強い感情的意味合いを持つ軽蔑的な言葉で、愚かな愚か者を表現するときによく使われます。例え...
『紅楼夢』で、なぜ丹春は宝玉に勉強して役人になるよう説得しなかったのですか?
丹春は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の一人であり、賈宝玉の異母妹である。以下の記事はIntere...
『紅楼夢』では、賈家は裕福な家庭です。彼らの生活はどれほど優雅なのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
呉文英の「秋花・七夕を愛でる」:風景描写、物語性、叙情性を融合
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
南宋時代の詩人陳雲平の『清平月:鳳城の春』
以下、Interesting Historyの編集者が、陳雲平著『清平楽風成春前』の原文と評価をご紹...
三国志演義のイケメンベスト10、1位は誰でしょうか?
いつからか、私たちの世界は外見を特に重視する時代になった。携帯電話、テレビ、新聞、雑誌をつけると、「...
「越に帰る前に虞丈の君主に別れを告げる」は唐代の獨孤紀によって書かれたもので、去ることへの惜しみの気持ちが込められている。
独孤記(本名は智之)は唐代の官僚、随筆家。唐代における古散文運動の先駆者。彼の古散文は蕭英石の古散文...
漢史第77巻 諸葛・劉・鄭・孫・呉・何の伝記原文
蓋寛饒は、字を慈公といい、渭県の出身であった。経文に通じた者は郡文官に任じられ、孝行で誠実な者は朗に...
清明節気に関する諺は何ですか?
清明節のことわざ全集:清明節の間に脱脂綿を脱がなければ、年をとっても何も成し遂げられない。清明節に柳...
『遷安県折々の詩 第二』の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
遷安県で時々詠まれる二つの詩 - 第二杜牧(唐代)秋の音が心を乱し、孟沢の葦は深い雨に覆われている。...
「香り高い草を通して王子様を思い出す、柳の木が茂る建物の外では私の魂は打ち砕かれる」という有名な一節はどこから来たのでしょうか?
「草香をたたえ、王子を偲ぶ、楼外の柳は天高く、魂は砕け散る」という有名な詩はどこから来たのでしょうか...
張岱の散文集『西湖を夢みて』第4巻・西湖南路・小蓬莱全文
『西湖夢想』は、明代末期から清代初期の作家、張岱が書いた散文集で、全5巻72章から成り、杭州周辺の重...
ミャオ族の頭飾りの紹介 ミャオ族の頭飾りの特徴は何ですか?
ミャオ族の男性の頭飾りは主に巴沙、従江県、九干外囲などの地域で見られ、これらの地域では大人の中には頭...
清朝の太祖ヌルハチの側室、普茶群代の簡単な紹介
フカ・グンダイ(?-1620年)は満州人で、清朝の初代建国者ヌルハチの2番目の妻でした。彼女は後に初...
司馬炎は少数民族をどのように扱ったのでしょうか?太康の統治の具体的な現れは何ですか?
司馬炎は少数民族に対する待遇として宥和政策と征服政策を組み合わせた政策を採用したが、一部の役人はこの...