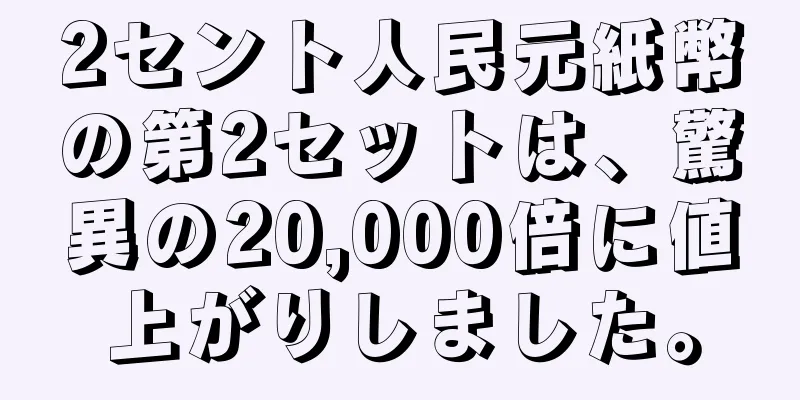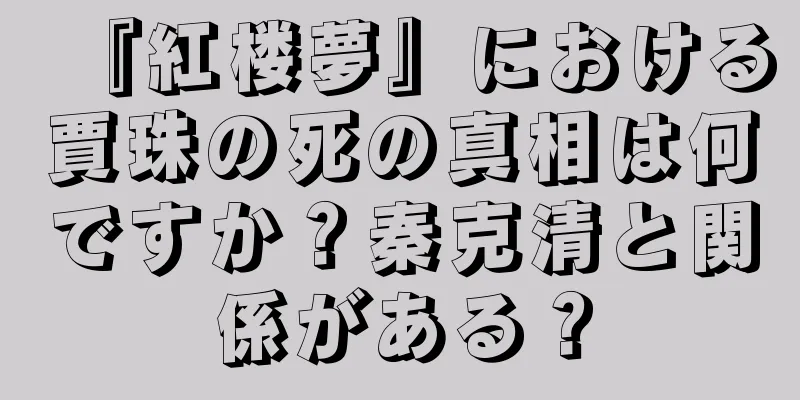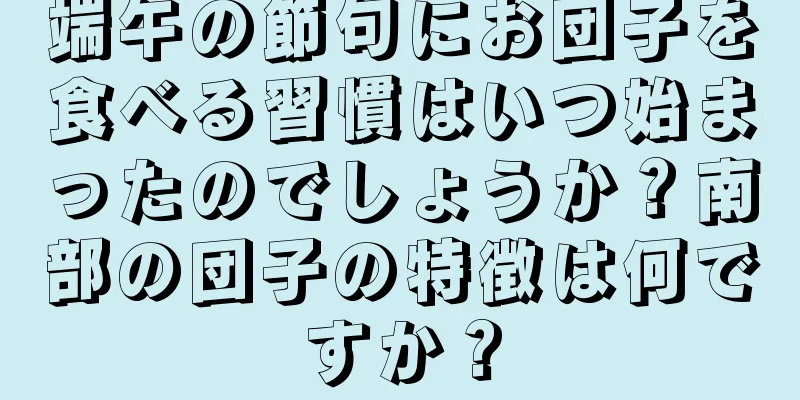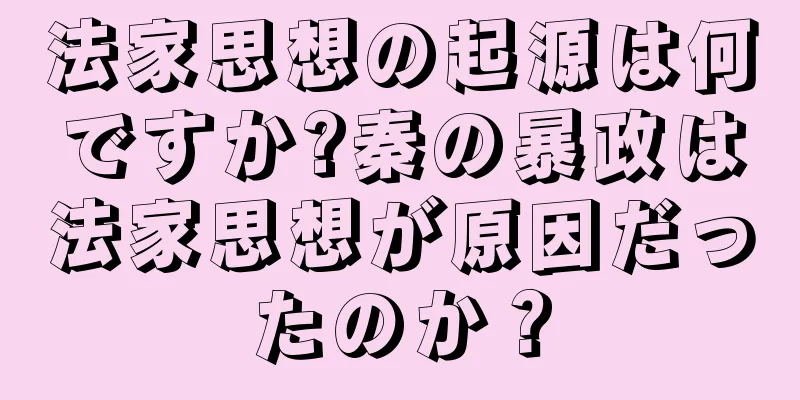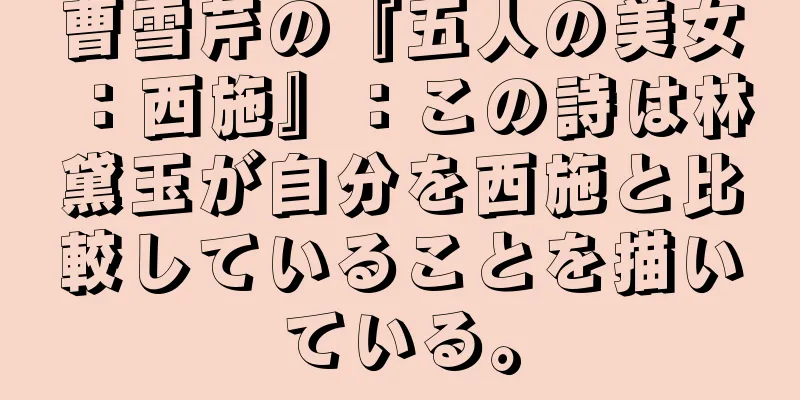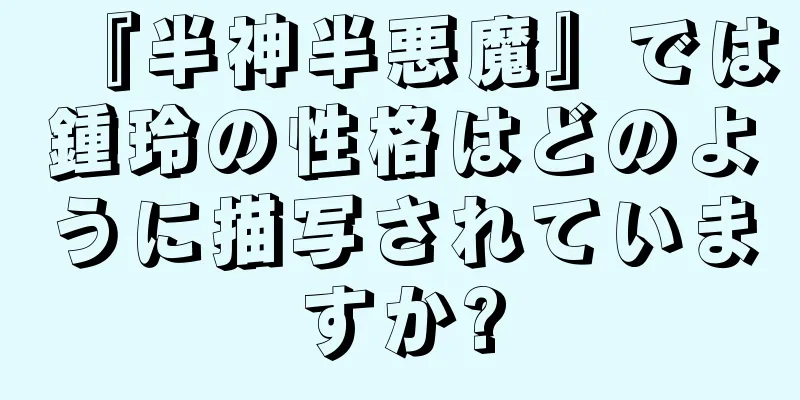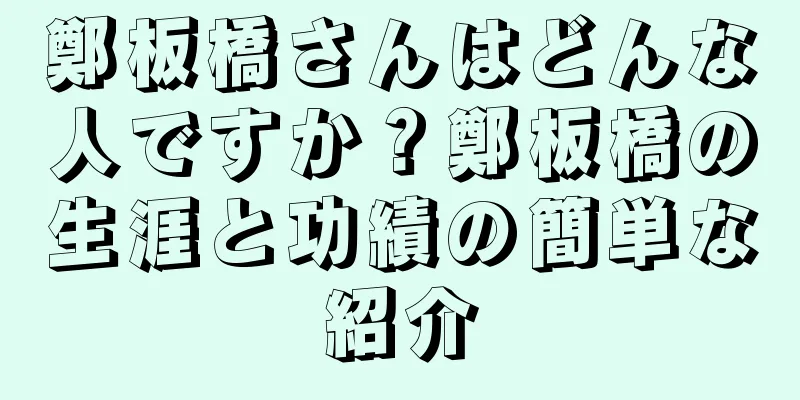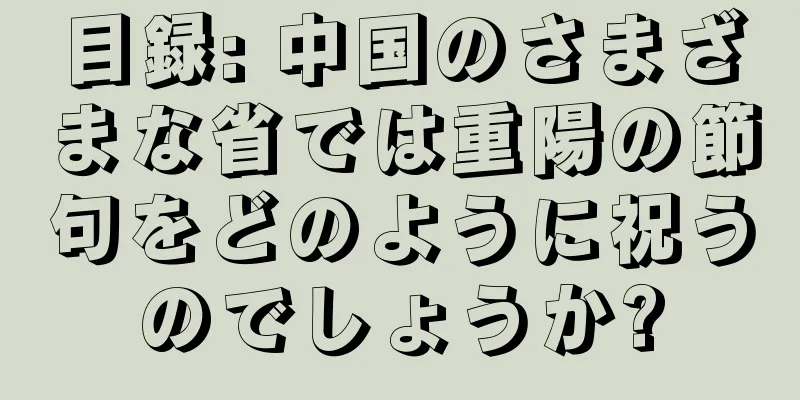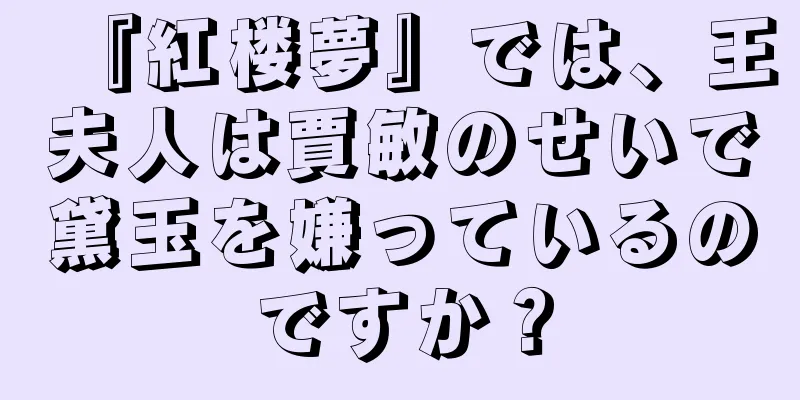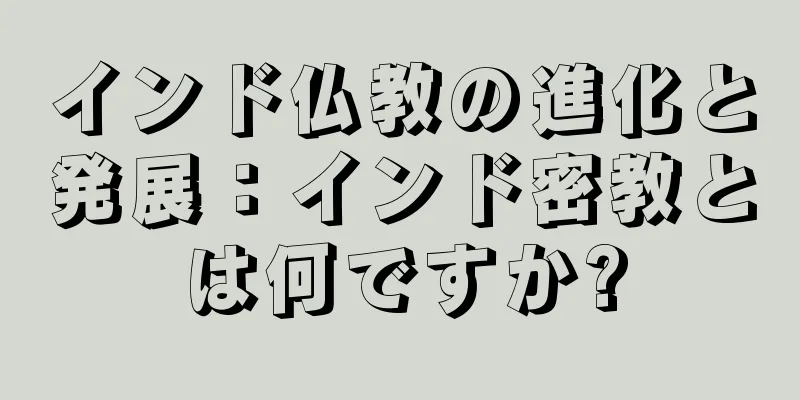安倍晴明とは誰か:日本で最も優れた陰陽師、安倍晴明の簡単な紹介
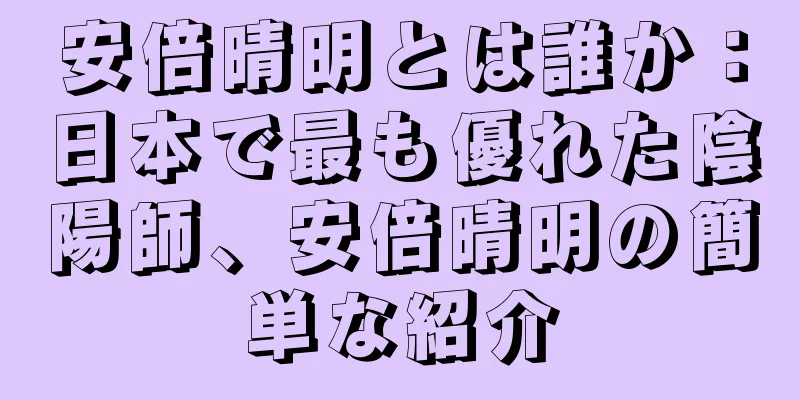
|
安倍晴明(あべ はるあき、延喜21年2月21日 - 寛弘5年10月31日)は、平安時代中期に活躍した陰陽師であり、鎌倉時代から明治初期にかけて陰陽師を統べた土御門家の祖である。安倍晴明は、当時の科学技術と呪術の最先端であった「天文道」と、占術を主とする「陰陽師」の関連技術に卓越した知識を持ち、平安貴族から信頼された偉大な陰陽師でした。 彼の生涯もまた神秘化されており、多くの伝説的な逸話を生み出している。生前、道真師匠(蘆屋道満)のライバルであった。また、阿倍晴明は平将門の子である平将国ではないかという伝説もある。生前、天皇や有力な大臣たちから高く評価され、79歳で「宝生院」の称号を授けられた。彼の死後、数世代にわたる子孫の努力により、彼は第四位の天文学博士から政府の最高位に昇進した。江戸時代には「源義経は知らぬが、治明公は知る」という有名な言葉が広まったほどです。それ以来、阿部春明は「春明さん」と呼ばれ、日本中で有名になった。 阿部氏に伝わる系図によれば、阿部晴明は大膳府下級貴族阿部益基の子で、摂津国阿倍野(現在の大阪市阿倍野区)に生まれたとされる。阿倍仲麻呂の子孫とされる。生年は不明だが、寛弘2年(1005年)9月に85歳で亡くなったという記録から、延喜21年(920年)生まれと考えられる。 45歳で亡くなったという説もある。 (土御門家の記録では年齢が異なる)幼少期の詳しい記録はないが、陰陽師の賀茂忠行・保憲父子に師事し、保憲に重んじられ天文学を教えた。 安倍晴明の実際の記録は、天暦2年(960年)に村上天皇がまだ有志の学生(天文学博士の下で天文学を学び、陰陽師寮に所属していた学生の称号)であった晴明を占術に任命した際に現れます。清明は晩年に成功を収めたが、彼の占いの才能はすでに貴族社会で認められていた。その後、天文学の博士号を授与された。 979年、59歳の晴明は皇太子(後の香山天皇)の命を受け、天狗を封印する儀式を行うために那智山へ赴いた。この頃から晴明は花山天皇の信頼を得るようになったようで、晴明が陰陽術の儀式を行った様子が詳しく記録に残されている。花山天皇の退位後、晴明は一条天皇や藤原道長からも厚い信頼を得ていたことが、道長の日記『御堂関白記』や他の貴族の日記からも窺える。 晴明は、左京権傅、関倉院別当、播磨守などの要職を歴任した高名な陰陽師で、藤原道長の信頼と実行力の高さから、四位下から宝生院まで昇り詰め、平安時代の陰陽師にとって越えられない頂点となった。また、晴明の二人の息子、義昌と義平も天文学博士や陰陽師(陰陽寮次官)に任じられ、晴明の代に安倍家は主君忠行の賀茂家に匹敵する陰陽師の家となった。彼は白狐の息子なので、人々は彼を「白狐王子」と呼んでいます。 阿部晴明の両親について 安倍晴明の父は、大膳大夫の下級貴族であるあべのますき(阿部ますざい)であると一般に信じられていますが、彼の母については多くの伝説があります。最も一般的な伝説は、彼の母は葛の葉という名前の白いキツネ(日本の稲荷神信仰の影響を受けている)であったというものです。 『風喰抄』によれば、阿部吉在は悪右衛門から白狐を救い出した。その白狐は和泉国の神田の森で長年修行していた狐仙人の「九蔵」であった。その後、彼女は人間に変身し、易才と恋に落ち、清明を出産した。清明が5歳のとき、思いがけず母親の本当の姿であるキツネを見てしまい、別れの時が来た。葛野は泣いている子供を残して森へ戻りました。 「会いたくなったら会いに来て…泉の奥、神太の森、葛の葉の間で…」この歌は何度も歌われました。それは母親が子供に残した最後の言葉でした。その後、春明は歌の指示に従い、森の秘密の場所で再び母親に会い、彼女の強力な霊力を受け継ぐことができました。 しかし、安倍晴明には両親がおらず、万物から変化したという伝説もあります。 現代の研究によれば、安倍吉在は実際には身分の低い芸者か山姥と結婚していたとされています。この不名誉な事実を隠蔽するため、あるいは安倍春秋を意図的に神格化するために、葛の葉の白狐伝説が生まれ、人々の心の中に安倍春秋に対する地位と神秘性が定着しました。 晴明が生きた平安時代は、表面的には文明的で平和な時代でしたが、内部では貴族の間で汚い権力闘争に満ちた時代でした。当時の政府の統治能力の無さは下層階級の人々の生活に苦しみをもたらした。このような悲惨な状況の中で、社会の底辺にいる人々は「なぜ自分は生きているのか」という疑問を抱き始めました。有能なトップや権力を失った人たちも、「政情は悪化しているが、どうすれば救えるのか」という疑問を抱いている。このように、さまざまな負の感情が時代を覆い尽くし、それに伴って怨霊も出現しました。人間に害を及ぼす怨霊と戦うのが陰陽師の仕事でした。さらに、当時の日本の京都は、前例のない自然災害と人災に見舞われていました。大地震、火災、洪水などの災害が相次ぎ、人々はパニックに陥り、幽霊や神についての憶測が飛び交いました。これは、高官たちが信じるだけでなく、庶民の間でも広まりました。貴族たちは方角や日付の吉凶を固く信じていました。外出するときはいつも、正しい日と方角を選びました。病気や災害に遭遇すると、幽霊のせいか、夜に百の幽霊がさまようような不浄なものに遭遇したのだと言いました。そのため、当時の貴族たちは陰陽師のさまざまな禁忌をよく知っており、その作法や掟を厳格に守っていました。起床、洗面、食事といった日常生活の些細なことにも、それに応じた禁忌がありました。 (この慣習は明治維新まで続いた)朝廷の行為の吉凶もこの原則に基づくものでなければならない。そのため、当時の陰陽師は国内に陰陽師寮という専属部門を持っていただけでなく(陰陽師寮は中務省管轄の6つの部門の一つで、天文、気象、占術、暦の作成などを担当していた。役人のほかに、陰陽師、陰陽師博士、陰陽師学生、暦博士、暦学生、天文博士、天文学生、陰陽師博士、宿塵丁などがいた)、国の政策の実施にも影響を与えていた。この時代の陰陽師は、もはや単なる禁忌や呪物に基づく信仰ではなく、一定の政治的意味を持っていた。そのため、平安時代には陰陽師は「国家官僚」として政治の舞台で活躍していました。さらに興味深いのは、陰陽師が皇室によって独占されていたため、民間にも「民間陰陽師」が生まれたことです。もちろん、これらは話題から外れているので、今のところ議論されません。 安倍晴明は歴代最高、最も傑出した、最も偉大な陰陽師です。彼の能力はどの世代のどの陰陽師よりも優れています。非公式の歴史書『今昔物語』の記述によると、晴明が生まれたとき、侍女に憑りつかれた霊を見たという。 『宇治拾遺物語』や『古事談』の記録によれば、晴明の正体は修行中に幽霊や精霊を操る能力を身につけた高僧の生まれ変わりだという。 それから、彼の正確な出生地についての疑問もあるが、歴史上、そこには「不明」という大きな赤い印が押されている。主な伝説は3つあります。 1) 大阪説:大阪市阿倍野元町には阿倍治明神社や治明公を埋葬した地があり、祭りも行われている。 「阿部治明生誕地・遺跡」の石碑があり、その横には治明が製造用の水を沸かしていた井戸跡が残っています。山水と太福はそれぞれの著作の中で、先祖の阿部治明の出生地は大阪であると主張している。土御門泰福と三水吉右衛門は、それぞれ当時の将軍徳川家継と後水尾天皇に事態を報告した。陰陽五行学に強い関心を持っていた家継と、土御門家に好印象を持っていた後水尾天皇が初めて手を組んだ。天皇は自ら宣旨を発し、晴明に大臣の最高位である従一位を贈り、土御門家と親交の深かった一条家を大阪の安倍晴明神社に派遣して晴明に尊号を授けさせた。幕府は自費で大規模な慰霊祭を催し、幕府の重要官僚を慰霊祭に参加させた。それ以来、大阪は安倍晴明の生誕の地であることを誇りに思うようになった。 2) 茨城説:晴明の最古の伝記『伯耆抄』の「由来」によると、晴明の出生地は常陸国筑波山麓の猫島、現在の茨城県真壁郡明野町の猫島とされている。猫島はかつて高松家の領地でした。また、高松家は1711年に『晴明伝』も収集した。晴明が生まれる前に朝廷から京都から常陸国へ陰陽師を派遣するよう命じられたという記録がある。陰陽島の研究ですが、猫島が晴明の生誕地であるという確証はありません。 3) 香川曰く、「讃岐国日記」には晴明が讃岐国河東郡井原荘に生まれたと記されている。また、丸亀藩の官誌『西讃府志』には晴明が讃岐国香川郡遊佐で生まれたとの記録がある。興味深いことに、讃岐国の遊佐は常陸国の猫島と深い関係があります。遊佐という地名は常陸国出身の遊佐氏に由来しています。 阿部治明の経歴について 次に起源についてですが、現存する資料によれば、氏の起源は孝元天皇の子である大彦命に遡ります。『古事記』には「大屋本彦国久留命(孝元天皇)は原口宮で天下を治めていた。…この天皇には全部で五人の息子がいた。屋本彦国命が天下を治めていたとすれば、その弟の大彦命の子である建沼河別命が阿倍臣らの祖先である」と記されています。晴明流安倍氏の祖は大彦信行の11代孫、阿倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ、別名阿倍内麻呂)である。倉梯麻呂は大化の改新の際、左大臣を務め、その子の阿倍三国は文武天皇の御代に右大臣を務めた。『竹取物語』には、かぐや姫のために火鼠の皮を手に入れたと記されている。倉橋麻呂の娘、大足姫は孝徳天皇の妃で、有間皇子を産んだ。彼女は天智天皇の敵であり、蘇我赤大姫の陰謀により殺害された。このことから、安倍晴明は高貴な生まれで、優れた経歴を持っていたことがわかります。しかし、伝説によれば、なぜ安倍家は父の代までには衰退していたのでしょうか?これは確かに不明です。 阿部家系図によれば、春明の父は大膳大夫(天皇の食事を担当する宮内省の役人)阿部桝在であった。阿部公以来8代目当主。鎌倉時代以降の伝説では阿倍保名と呼ばれており、近代では春女の父は平将門であったとする研究もある。阿部春明の母は白狐の化身であったという古い伝説があるが、最近の研究では彼の母親は山の住人であったことが分かっている。平安時代、都市以外で暮らす人々は非常に少なく、総称して「山の民」と呼ばれ、その地位は高くありませんでした。安倍晴明は自分が貧しい家庭出身であるという事実を隠すために、故意に真実を隠したのかもしれない。しかし、辺鄙な地域に住む人々は、常に自然と触れ合い、天と地の間の霊的なエネルギーを感じているため、都会の人々に理解できない能力を自然に持っています。したがって、安倍晴明の強力な超能力の一部は母親から受け継いだものであることは間違いありません。もちろん、伝説は様々で、流浪の巫女(安土桃山時代の「出雲阿国」に代表される日本各地を旅した巫女)だったという説や、橘文子の子という説もあります。しかし、母親は平民であったと一般に考えられているため、彼女に関する記録は残っていない。 晴明の複雑な生涯に比べ、比較的はっきりしているのはその子孫である。『古今上文集』『栄花物語』『甲陽』によれば、長男の安倍吉平は陰陽師の博士を務めたとされている。次男の阿部吉政は陰陽の長となった。しかし、それでも伝説が残るのは避けられません。もう一つの説は、実の娘であるサヤとの間に生まれた安倍徳威が、芦屋道満に殺されたというものです。 最後に、この謎の人物の生涯を見てみましょう。安倍晴明は、921年(藤原氏摂関政治の最盛期)に生まれました。彼は子供の頃から天文学と占星術が大好きでした。これも運命的なものだったのかもしれない。960年、40歳の時、彼は「陰陽師リアオ」の天文学の弟子となり、後に天文学博士となった。晴明は大膳大夫、天文博士、上渓権助、倶利伽羅院別当、播磨守、左京権大夫などの高官を歴任し、非常に有能な官吏であったと歴史の記録に残されており、天皇からもたびたび賞賛されていた。ある時、天皇は晴明を左大納言に昇進させようとしたが、晴明は丁重に辞退した。皇帝は落胆せず、代わりに清明に家を与えた。清明はそれを受け入れるしかなかった。 1000年、晴明は「法性院」の爵位を授かり、貴族となった。 1001年(寛弘3年)には従五位より上の従四位より下の位である権大納言・天文博士に任じられ、後世も陰陽師の最高位を従四位と定めた。残念ながら晴明の幼少期から中年期までの記録は残っておらず、残っている肖像画も中年以降の姿しか描かれていない。おそらくこれが、この現象が非常に神秘的である理由の一つでしょう。 アニメキャラクター そのため、歴史上、彼の青年時代に関する小説や伝記は数え切れないほど存在します。 『今昔物語』巻第24第16帖には、晴明が賀茂忠行の所で陰陽術を学んでいたとき、忠行に同行していた牛車が鬼の姿を見たと記されている。忠行は晴明の超能力を発見し、「瓶から水を注ぐ」などのあらゆる魔法を晴明に教えた。しかし、春明の師匠は忠之の子・保則であったという説もある。土御門神道の創始者です。占星術や予言は信じるべきものではないが、少なくとも阿部治明は人の心を理解し、政治情勢を分析する鋭い感覚を持っていることがわかる。彼が開発した完璧な天文暦は、数学と天文学における彼の並外れた才能を十分に証明しました。阿部春秋は生涯に数え切れないほどの著書を著したが、今日まで残っているのは『湛地流家』のみであるが、陰陽師の占術に関する重要な文献である。これは、この魅力的で神秘的な人物が後世に残したもう一つの謎なのかもしれません。 |
<<: 李冀って誰ですか?なぜ王子を殺そうと企んだのですか?
>>: すべてのマヤの集落は紀元前300年以前に大規模な施設を建設した。
推薦する
『紅楼夢』で石向雲はなぜ林黛玉をそんなに嫌っているのですか?彼らの間に何が起こったのでしょうか?
石向雲は『紅楼夢』に登場する金陵十二美女の一人で、四大名家の一つである石家の娘です。次回は、Inte...
『紅楼夢』における王希峰の悲劇の核心は何ですか?家族に搾取される
『紅楼夢』の王希峰の悲劇の核心は何ですか?実は彼女は母方の家族に利用され、息子を産むことができず、他...
『紅楼夢』でタンチュンは遠く離れた場所に嫁いだ後、何を経験したのでしょうか?
「紅楼夢」は封建社会のさまざまな悲劇を集めた作品です。まだ知らない読者のために、次の興味深い歴史編集...
王維の古詩「趙堅書記を日本に送還」の本来の意味を鑑賞
古代詩「春の日、私は裴迪と一緒に新昌里に行き、呂宜人に会いに行ったが、彼に会えなかった」時代: 唐代...
もし王允が西涼軍の降伏を受け入れていたら、後漢末期の歴史は変わっていただろうか?
王允が西涼軍の降伏を拒んだのは、確かに大きな誤りだった。戦略思考と全体的な戦術思考のない指導者は、最...
艾心洛洪礼には何人の娘がいましたか?洪礼の娘は誰でしたか?
清朝の皇帝高宗、愛新覚羅洪歴(1711年9月25日 - 1799年2月7日)は、清朝の第6代皇帝であ...
『紅楼夢』の青文はなぜネギの筒のような赤い爪をしているのでしょうか?
青文は賈宝玉の部屋にいる4人のメイドのうちの1人です。メイドでありながら、宝玉の部屋で裕福な女性のよ...
「Yan Ge Xing」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
ヤンの歌高史(唐代)開元26年、元容に従って国境を越えた客人が帰国し、「顔歌行」を作曲して人々に披露...
正義の宋江が降伏を選んだ理由の詳細な説明
宋江はなぜ降伏したかったのか?この事件は水滸伝の英雄たちの悪夢とも言える。涼山では宋江は英雄的な人物...
『紅楼夢』に、酔って牡丹の布団の上で眠る石向雲が登場すると、どんな感じになるのでしょうか?意味は何ですか
石祥雲は『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人であり、石家の娘です。次の興味深い歴史編集者が詳細...
魏晋南北朝の衣装:魏晋南北朝の貴婦人の衣装
人間の衣服の進化の歴史は、ある意味では、人間の文化の知覚的発展の歴史でもあります。古代中国の衣服は、...
道教の神である鍾馗には歴史上の原型があるのでしょうか?この人本当にいるの?
鍾馗をご存知ですか?今日は、Interesting History編集長が詳しく紹介します。 「鍾馗...
三国志演義の第一章に登場し、最終章で大活躍できるのは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
羅斌王の「埔里金の夕べ」:この詩は大まかな筆致と詳細な描写を組み合わせている
羅斌王(626?-687?)は光光としても知られ、梧州義烏(現在の浙江省)の出身です。唐代の大臣、詩...
李米順の「春の日」:詩人は風景を使って孤独と耐え難い悲しみを表現している
李米淳(1085-1153)、字は思志、別名は雲熙翁、雲熙居士、普賢居士など。祖先の故郷は福建省連江...