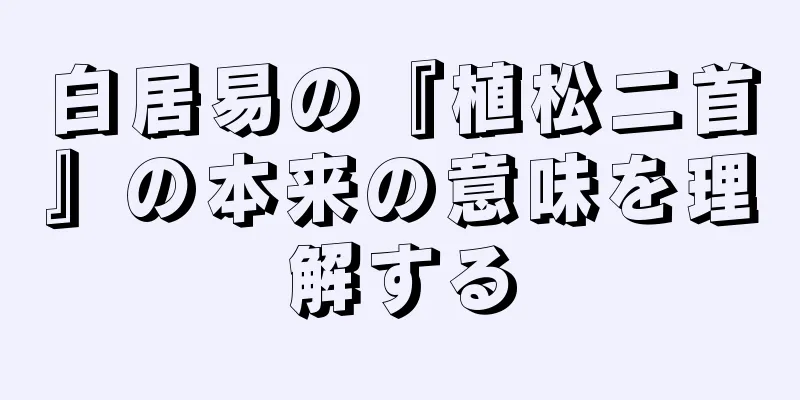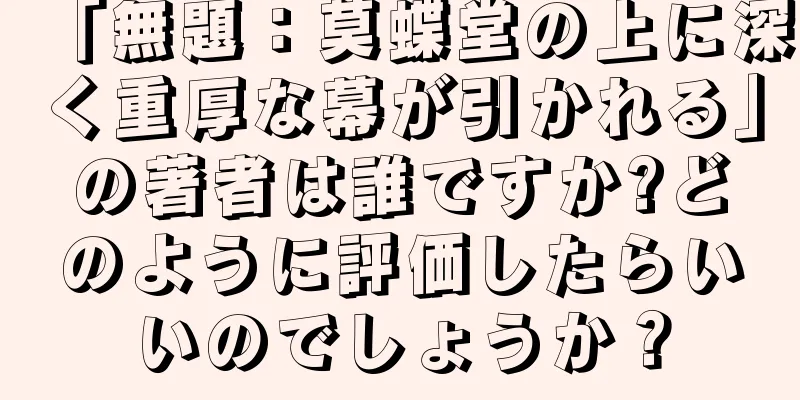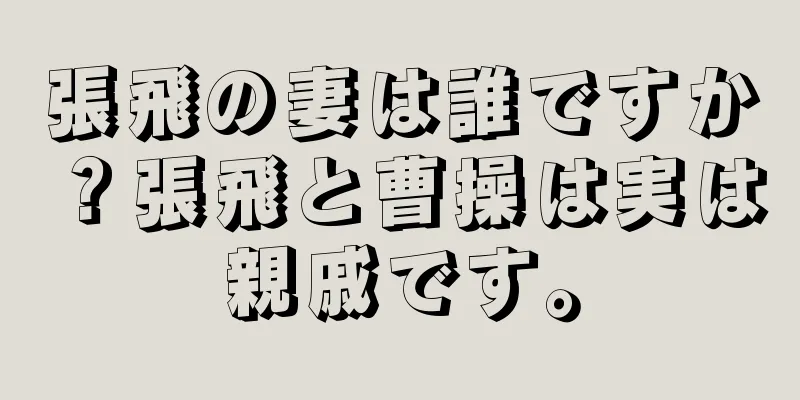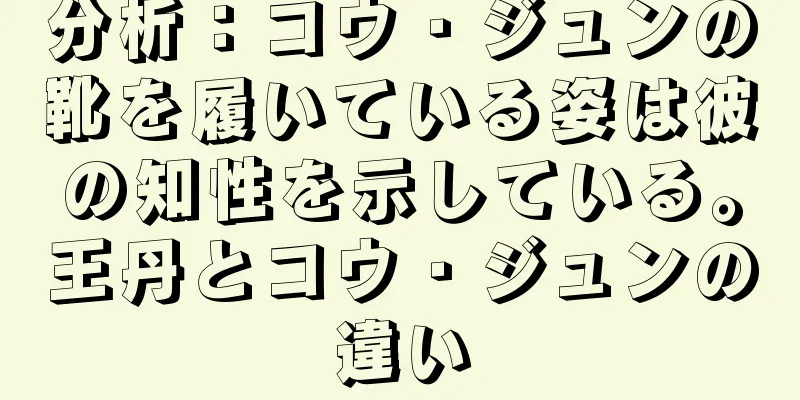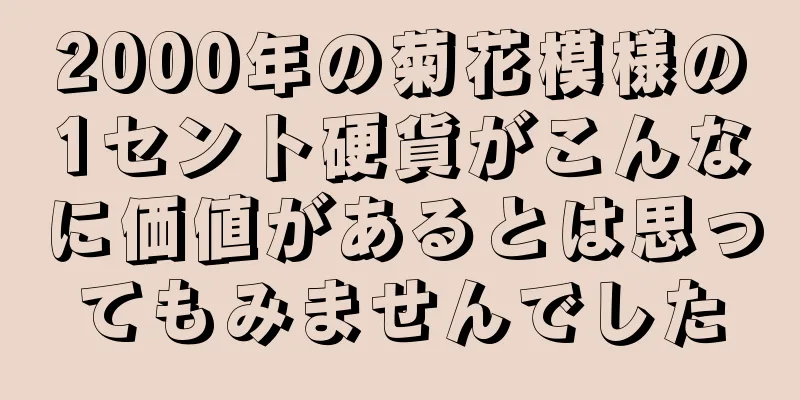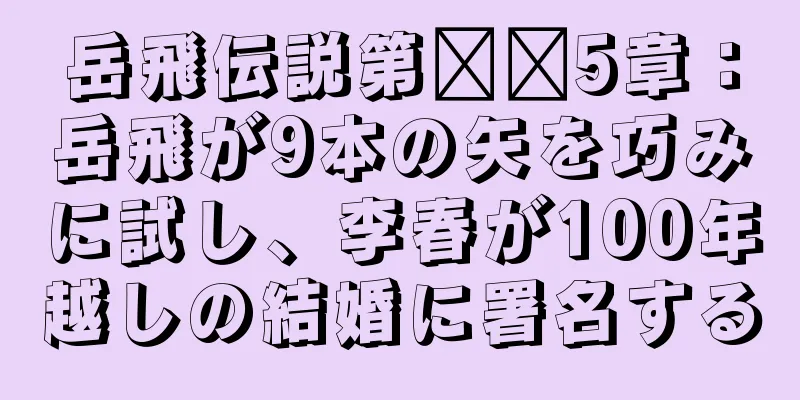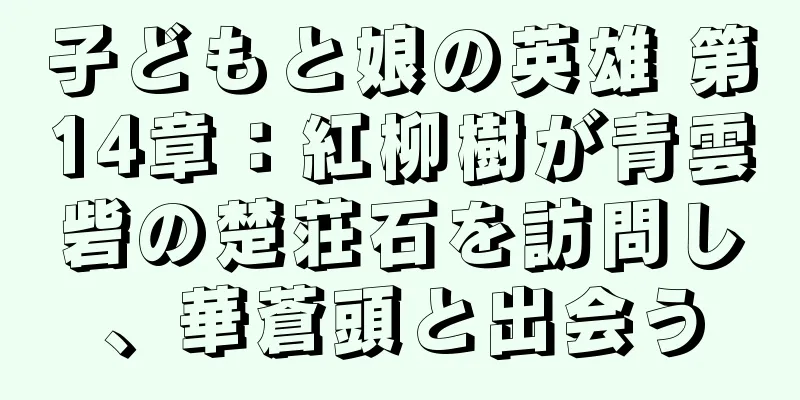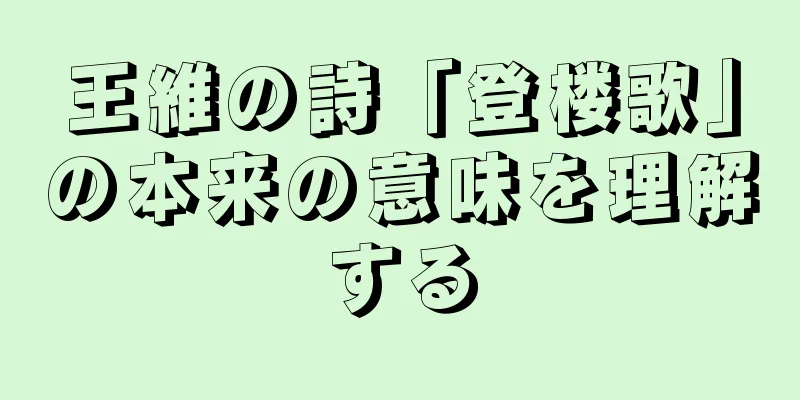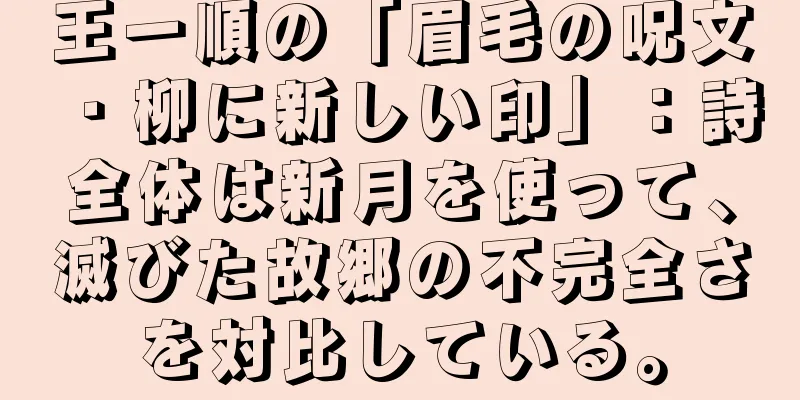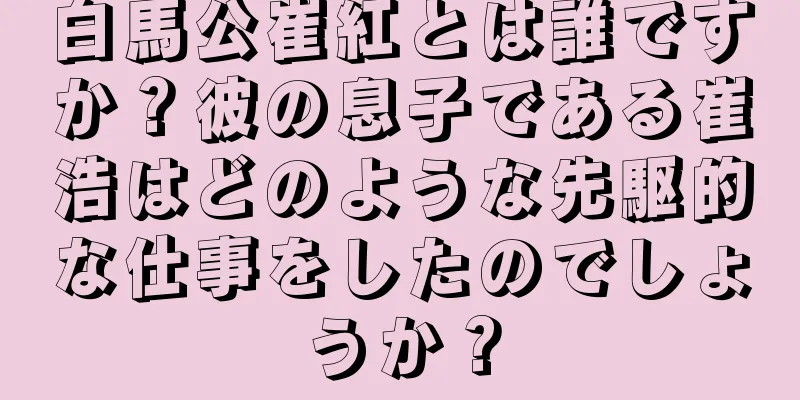鄭板橋さんはどんな人ですか?鄭板橋の生涯と功績の簡単な紹介
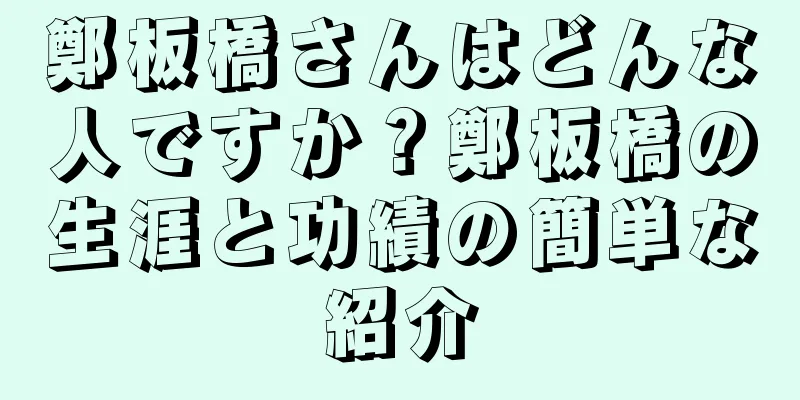
|
鄭板橋は板橋先生とも呼ばれ、中国最後の封建王朝の画家です。詩や書道にも優れ、「詩、書、画の三奇」と呼ばれ、歴史上有名な「揚州八奇人」の重要な代表者でした。他の画家と比べると、鄭板橋先生は蘭、竹、石しか描いていません。このような独特の個性を持つ鄭板橋がどの王朝に属していたのか、また、鄭板橋とはどんな人物なのかを知りたいですか?その答えは以下で明らかにします。 鄭板橋はどの王朝に属していましたか? 鄭板橋は学者の家に生まれ、康熙年間末期に科挙に合格して学者となり、雍正年間10年に尉人となり、乾隆年間初年に進士となった。 鄭板橋(1693-1765)は、本名を鄭謝といい、別名を科柔、連安、板橋といい、板橋氏とも呼ばれた。江蘇省興化の出身で、祖先は蘇州に住んでいた。彼は康熙帝の時代に学者となり、雍正帝の時代には侍人となり、乾隆帝の時代には進士となった(1736年)。山東省樊県と渭県の県令を務め、政治的に顕著な功績を挙げた。後に揚州に住み、絵画を売って生計を立てた。「揚州八奇人」の重要な代表者であった。鄭板橋は生涯を通じて蘭、竹、石だけを描き、自らを「四季を通じて色褪せない蘭、常緑の竹、永遠に負けない石、永遠に変わらない人」と称した。 彼の詩、書、画は「三奇」と呼ばれ、清代を代表する文人画家である。 代表作に『剪竹新竹図』『清光残光図』『蘭竹香図』『甘谷菊花春図』『蘭棘群』など。また『鄭板橋全集』も著した。 鄭板橋はそんな人だ 鄭板橋は、本名を鄭謝(xiè)といい、雅号は克柔、連安、板橋とも呼ばれ、板橋氏と呼ばれた。彼は江蘇省興化市出身です。 「揚州八奇人」の代表的人物であり、詩、書、画という三つの特異な才能で有名な書家、画家、作家。彼の生涯は、「学問と教育」、「揚州での絵画販売」、「科挙合格と進士」、「官旅」、「山東省での官僚勤務」、「再び揚州での絵画販売」の5つの段階に分けられます。 また、鄭板橋は書道にも優れており、官字と楷書を混ぜた書体を使用しており、「六点半書体」と呼び、「板橋体」とも呼ばれています。彼の絵画は主に蘭、竹、岩を題材としており、蘭と竹は彼の魂となっている。鄭板橋の書道芸術は中国書道史上特異である。板橋が23歳の時に書いた『欧陽秀小書「秋音譜」』と30歳の時に書いた『樊之小書詩』から、板橋が若い頃に欧陽洵に書道を学んだことが推測できる。書体は端正で力強いが、やや堅苦しい。これは、当時の書道界では端正で優美な官書が流行し、科挙の標準書体として使われていたことに由来する。 この点について、鄭板橋はかつてこう言った。「小楷書は均整がとれすぎている。長い間書道を練習していると精神が傷つくのではないかと心配だ」。40歳で科挙に合格した後、彼はほとんど書かなくなった。鄭板橋の書風の中で最も高く評価されているのは「六半韻」で、これは「漢八韻」(官書の一種)と楷書、行書、草書を組み合わせた独特の「板橋風」である。 「六点半」書道は、鄭板橋が自身の創作書道に付けたユーモラスな名前です。波状の線を多く含む「八点書体」と呼ばれる一種の官書体があり、いわゆる「六点半書体」は基本的に官書体ですが、楷書体、行書体、篆書体、草書体などの他の書体が混在しています。 『曹操行書詩巻』(写真上、揚州博物館所蔵)は、「六点半」様式の代表作といえる。 この書は曹操の「海を観る」という詩です。非常に大きく、各文字の平均面積は10平方センチメートルを超えています。文字は官書体で、篆書と楷書の要素が強く、文字は長く平らで、主に四角形ですが、少し揺れています。そのシンプルさと大胆さは、曹操の詩の荘厳で壮大なスタイルに似ています。鄭板橋はかつて「潘同崗に贈る」という詩の中で、彼の書道を賞賛した。「筆の並びは雲間に舞い上がり、霧を払い、空に広がる。一、二行の数字、北斗七星と北斗七星が星を並べている。」 鄭板橋の書道作品の構成も非常に特徴的で、石の大きさ、長さ、四角さ、厚さ、密度をランダムに組み合わせ、「ランダムに石を敷き詰めた街路」のように、自由な作風の中に規則性を持たせています。何気ないストロークのように見えますが、全体を見ると跳ねるような躍動感のあるリズムが生まれます。 例えば、乾隆27年に制作された横巻の『行書論』は、乾隆帝が70歳を過ぎて晩年に制作された傑作です。大体のところ、蘇東坡は宣城の諸葛家の奇峰筆を好んで使い、書くときにとても満足していた。その後、他の筆に替えたが、筆記面が手のひらに合わなくなった。 板橋自身は台州鄧の羊毛筆を好んで使用しており、その筆致は優雅で軽快で、常に満足のいくものであった。そこで彼は、台州鄧の羊毛筆の書法を宣城諸葛奇峰と比較し、最後にこう言った。「どうして蘇東坡の真似をしようというのか。蘇東坡は書くとき、細く書くよりも太く書く方を好み、これも蘇東坡の考えだ」。作品全体には、字の大きさが異なり、太い筆と細い筆、傾いた姿勢があり、点、筆、持ち上げる、押す、曲げるといった動作は、耳に響く音楽、空を飛ぶ鳥、水中を泳ぐ魚のようで、恣意的な姿勢のリズムの中に力強さと気概が表れている。清代の何紹基は、彼の字は「蘭や竹にインスピレーションを受けたものもあり、特に興味深い」と述べた。この作品の構成、構造、筆遣いからは、彼の「奇妙で古代的な形と優美な筆遣い」による蘭、竹、そして婁の精神を認識せずにはいられません。 |
<<: 維新の四将軍の一人、韓時忠とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は韓時忠をどのように評価したのでしょうか?
>>: 韓世忠の墓はどこにありますか?韓世忠の寺院と墓の紹介
推薦する
劉邦が即位後「多くの功臣を殺害した」と多くの人が信じている理由は何ですか?
前漢(紀元前202年 - 紀元後8年)は、中国史上、12人の皇帝が統治し、210年間続いた王朝です(...
『易堅志』第5巻の主人公は誰ですか?
李明偉マスター・ミンゲイは、彼は孤独であり、その結果を告白しました。そして、この郡の張は他の人のため...
曹操が「軍農制度」を実施した後も官渡の戦いで食糧不足に悩まされたのはなぜでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清朝時代には「明式家具」と呼ばれる家具がありました。「明式家具」の特徴は何ですか?
清朝時代には「明式家具」と呼ばれる家具がありました。「明式家具」の特徴は何でしょうか?「Intere...
南宋時代の詩人朱淑珍の『江城子・春を観る』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
『江城子 春を観る』は南宋時代の詩人朱淑珍によって書かれたものです。次の『興味深い歴史』編集者が詳し...
四聖心の源泉:第 5 巻:さまざまな病気とその説明(パート 1):咳の根本原因
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
儒教の古典『春秋古梁伝』の桓公七年の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
リー族の力スポーツは何ですか?
黎族の人々は勇気と勇敢さを重んじているため、黎族の若者は、個人の強さを反映し、個性を際立たせることが...
「帰つばめ」という詩をどう理解したらいいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
帰ってきたツバメの詩張九齢(唐代)カモメは小さいですが、春を満喫するためにやって来ます。泥が安いこと...
木星は年に何回月と合になりますか?現代ではいつ上演されるのでしょうか?
木星と月の合とは、木星と月が偶然同じ経度に移動し、互いに最も近づく天文現象を指します。木星と月の合は...
趙霊芝著『脱ぎたいけど寒さは消えない』の美しさとは?
趙霊芝の「脱ぎ捨てたいが、寒さは去らない」の美しさを知りたいですか?この詩は感情を表現し、風景を繊細...
唐代の詩「長湘詩」第1部をどう解釈するか? 李白は詩の中でどのような比喩を表現したのか?
恋慕、第一部、唐代の李白、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けします、見てみましょう!長安で、...
「双鳳伝説」第72章:宿敵を討つため、老将軍は力を見せて助けを求める。二代目王が指揮を執る
今日、興味深い歴史の編集者は「双鳳物語」第72章の全内容をお届けします。この本は清朝の薛喬珠人によっ...
『紅楼夢』の薛叔母さんはやはり高貴な女性なのに、なぜ小湘閣に行って街中で悪態をついたのでしょうか?
『紅楼夢』の薛おばさんはやはり高貴な女性なのに、なぜ小湘閣に行って街中で悪態をついたのでしょうか?こ...
『十朔新于文学』第32条に記録されているのは誰の行為ですか?
まだ分からないこと:『新説世界文学物語』第32条に記録されているのは誰の行為ですか?それはどのよ...