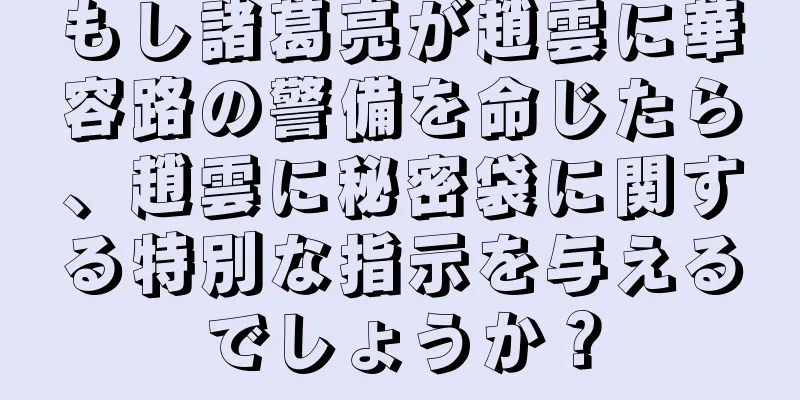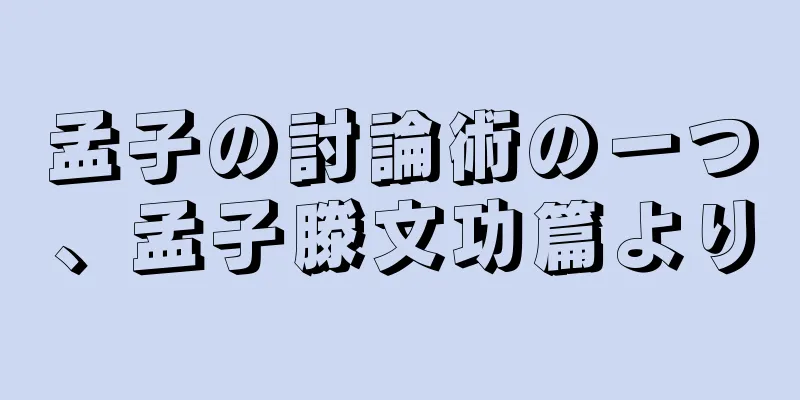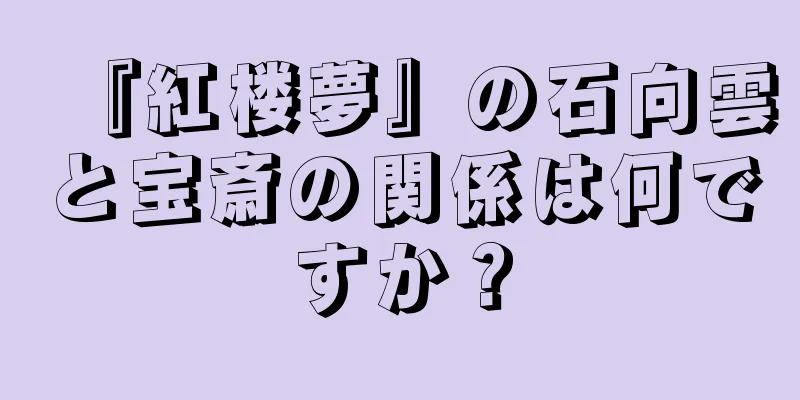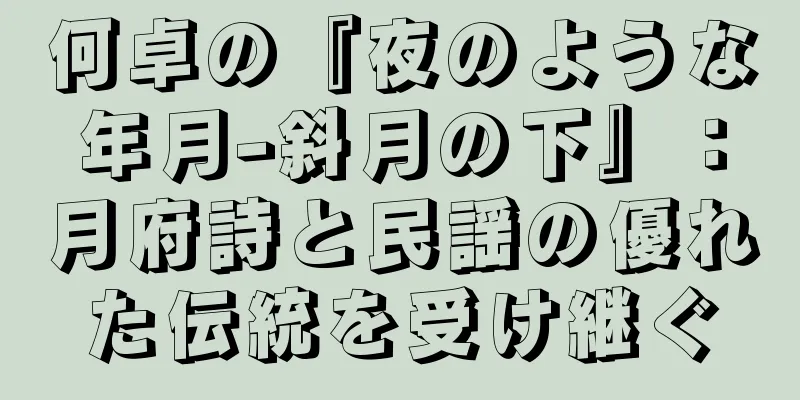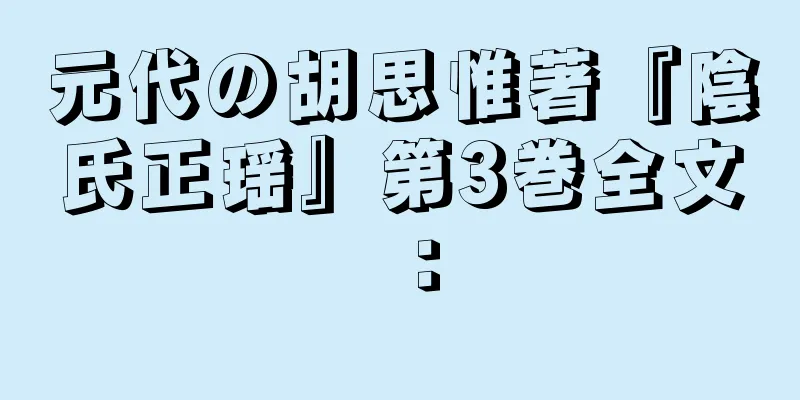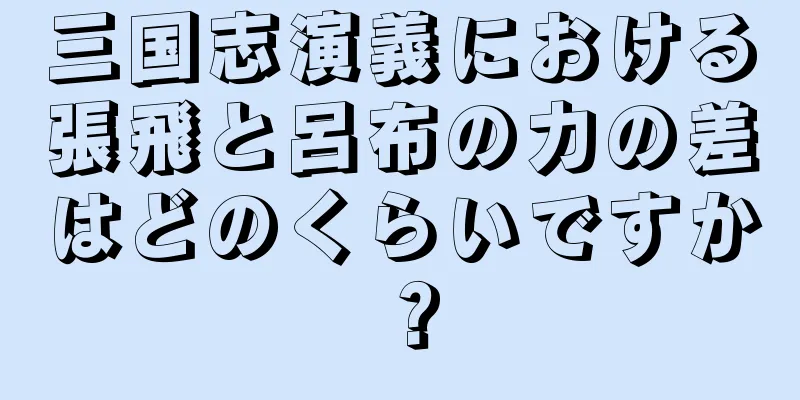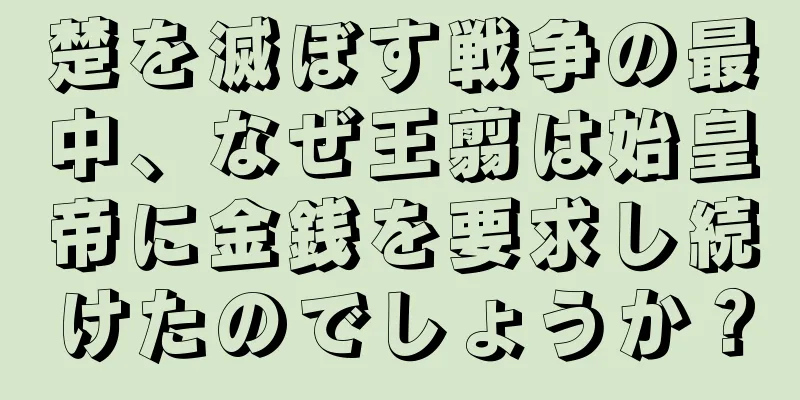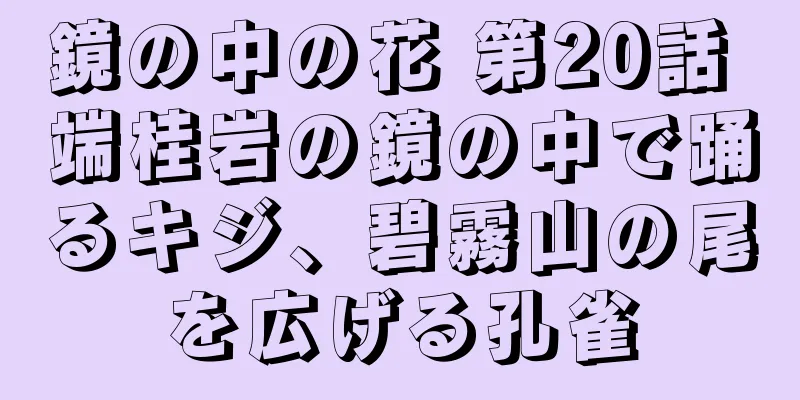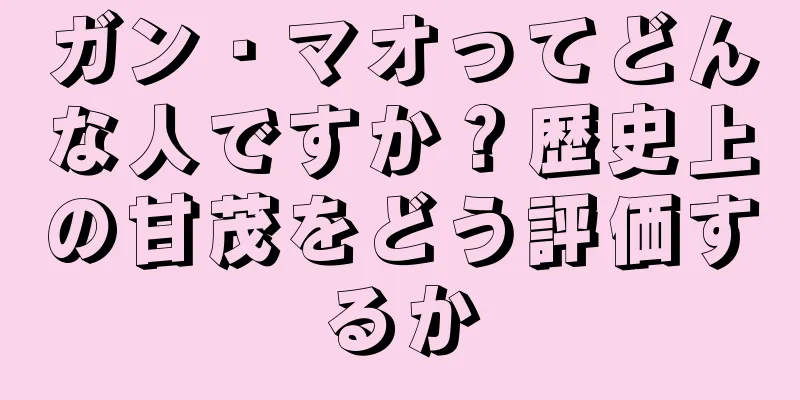古代人はなぜ日本を「扶桑」と呼んだのでしょうか?
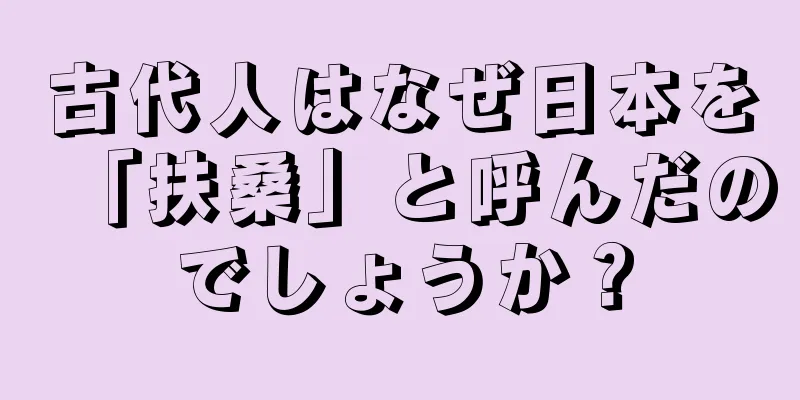
|
扶桑は古書に記された木の名前です。この木は『山海経』に初めて登場しました。伝説によると、太陽が昇る場所である扶桑の下で太陽が昇るので、「扶桑」は太陽を指すために使用されることもあります。ハイビスカスの木は高さ40メートル以上にも成長し、葉は桑の葉に少し似ており、春には花と葉が一緒に咲くと言われています。日光を好み、主に山間の谷間に生育します。秋の葉は鮮やかな赤色になります。漢や唐の時代の人々が考えていた「扶桑樹」は、主にこの巨木を指していました。 扶桑は古代の書物に記録されている国名でもある。『梁書扶桑国伝』には、「扶桑は漢代より東に2万里以上離れている。中国の東に位置している。その地には扶桑の木が多いので、その名が付けられた」と記されている。歴史書には扶桑の人々が扶桑の実を食べ、木の皮で作った布で衣服を作り、扶桑の皮で紙を作ったとも記されている。位置的には扶桑は日本とほぼ等しいため、後世の人々は扶桑を日本の同義語として使用しました。 「日本」の文字どおりの意味から判断すると、「本」という言葉は植物や木の根の意味を持ち、「日本」という名前は太陽と太陽の木の根の場所を意味します。日本列島の古代の国々の中には、太陽がある神聖な木がある場所を意味する「扶桑」と自らを名乗った非常に古い国や民族がありました。この日本の概念は、古代中国と日本が共有する宇宙構造の概念を反映しています。 日本の古代名——倭国 韓国ドラマ「大長今」では、日本人は「倭寇」と呼ばれています。歴史に詳しい人なら、この言葉が明代にも存在したことを知っています。この名前は日本の古代の名前に関連しています。古代人は日本を倭国、または倭奴国と呼んでいました。そして「傀」は盗賊や国を侵略した者を指す一般的な用語でした。 日本人を「倭」あるいは「倭人」と呼ぶことは、古代中国において日本を指す一般的な呼び方であった。この記述は『山海経』で初めて見られ、その後の『漢書地理』には「楽浪海には倭人がおり、百余の国に分かれている」と記録されている。これは日本の九州北部を中心とする多くの小さな部族国家を指しているのかもしれない。倭国と中国との外交関係は早くから確立されており、漢の光武帝の治世中元2年(西暦57年)には倭国は漢に使者を派遣して朝貢し、光武帝は印璽も授けている。この金印は1784年に日本の福岡市志賀島で発掘されました。「漢代の倭王」と刻まれており、歴史書の記録を裏付けています。しかし、一般的には「倭奴国」は九州北部の博多近郊の奴郡のことを指すと考えられています。その後、便宜上、日本は「倭」と略されるようになり、646年の大化の改新以降は「大倭国」と呼ばれるようになりました。 |
<<: 広田三原則:第二次世界大戦中の日本外交の失敗した試み
推薦する
清代の『修雲歌』第48章の主な内容は何ですか?
湖の真ん中の亭が幽霊について語る 江月鎮 ピアノを弾く華氏玉慧龍仙は女性兵士の一団を率いて赤水河の黄...
太平広記・巻43・仙人・薛玄真の原作の内容は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
燕叔:幼い頃から天才児として知られ、14歳で皇帝から壬氏と同じ地位を与えられた。
顔朔は子供の頃から頭が良く、勉強熱心だった。5歳で詩を作ることができ、「神童」として知られていた。景...
趙雲が馬超と一対一で戦った場合、馬超の相手にならないと言われているのはなぜですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「清平月:留まれない」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】あなたを引き留めることができず、彼は酔った蘭の船に乗って去りました。湧き水の緑の波の上...
『紅楼夢』で邢秀燕が賈の屋敷に入ることで6つの問題が説明される
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
諸葛亮の生涯の目標は漢王朝を支えることだったのに、なぜ漢の献帝に忠誠を尽くさなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『蔡喬作』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
木こり孟浩然(唐代)木こりたちは木々が密集している山奥へ入って行きました。橋は崩壊し、いかだは積み重...
王秦若の行政スタイルはどのようなものですか?北宋の官僚としての王秦若はどのような人物でしたか?
王欽若(962-1025)、号は定果、臨江軍新渝(現在の江西省新渝市)の人。北宋初期の政治家、宋真宗...
楊静志の「項寺に贈る」:この詩は友人に贈る一流の詩となった
楊敬之(820年頃生きた)は、雅号を茅霄といい、郭州洪農(現在の河南省霊宝)の出身である。安史の乱の...
十六国時代の後趙の君主、石虎の略歴。石虎はどのようにして亡くなったのでしょうか?
後趙の武帝石虎(295-349)は、号を基龍といい、桀族の出身で、上当の武郷(現在の山西省毓社北部)...
本草綱目第3巻「すべての疾患と外傷の治療」の元の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
那藍星徳の「清平楽・潭琴峡壁銘」:詩人の「英雄的孤独」の感情
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...
唐王朝はどれほど自信があったのでしょうか。外国人が宮廷の役人として働くことさえ認めていました。
最も戻りたい王朝をみんなに選んでもらうとしたら、間違いなく多くの人が唐王朝を第一候補に挙げるでしょう...
『清代名人逸話』第8巻には何が記録されていますか?
◎ 丁汝昌の『1894年の日清戦争』北洋海軍提督の丁汝昌は、1894年から1895年にかけての日清戦...