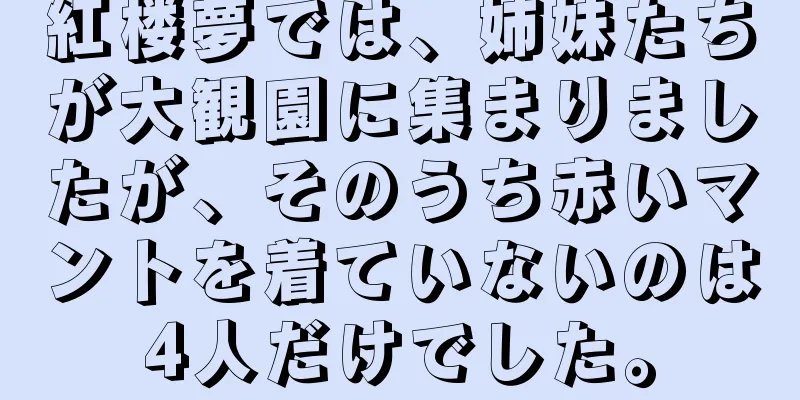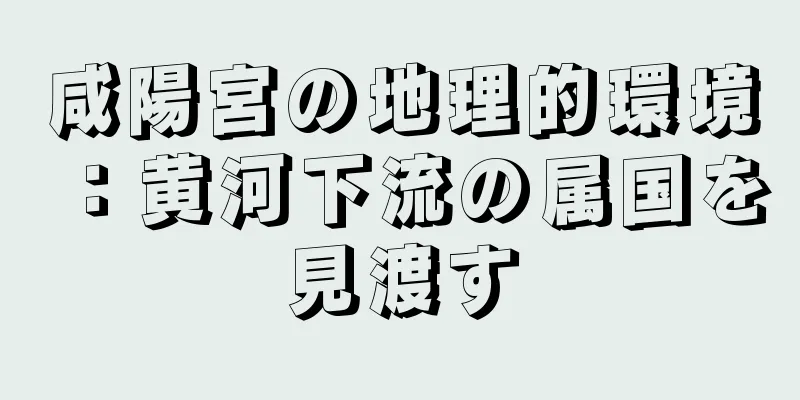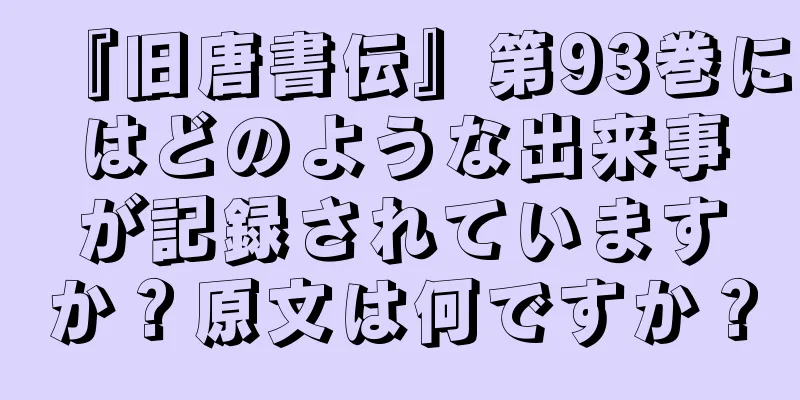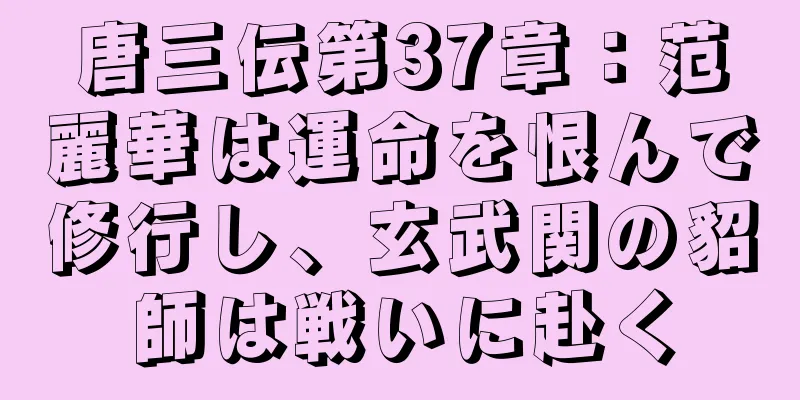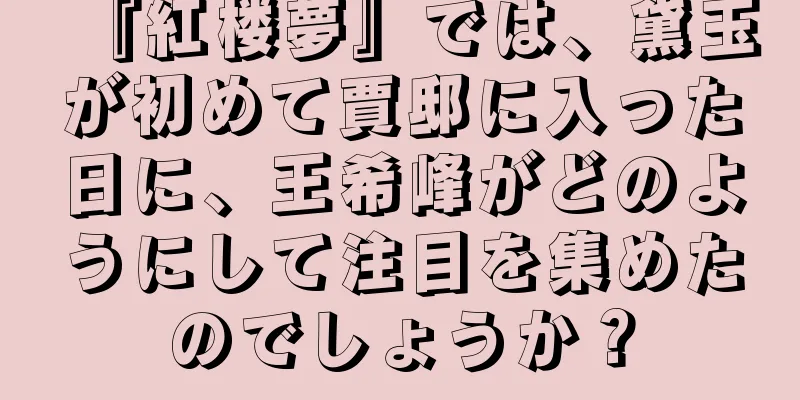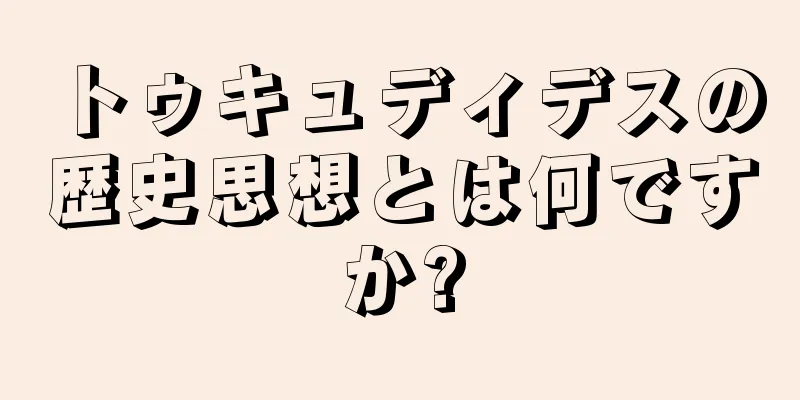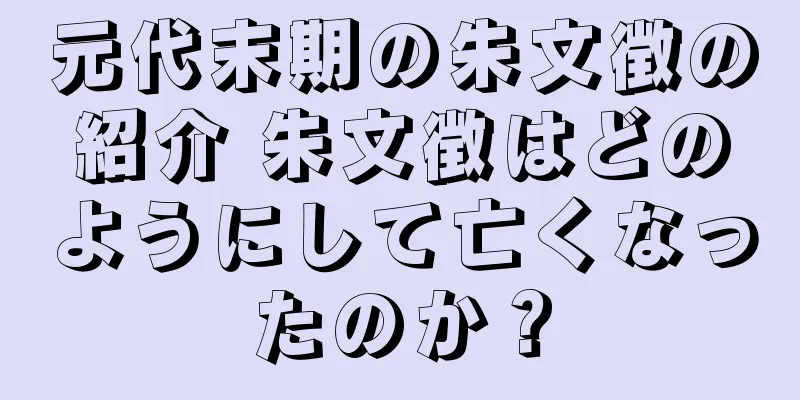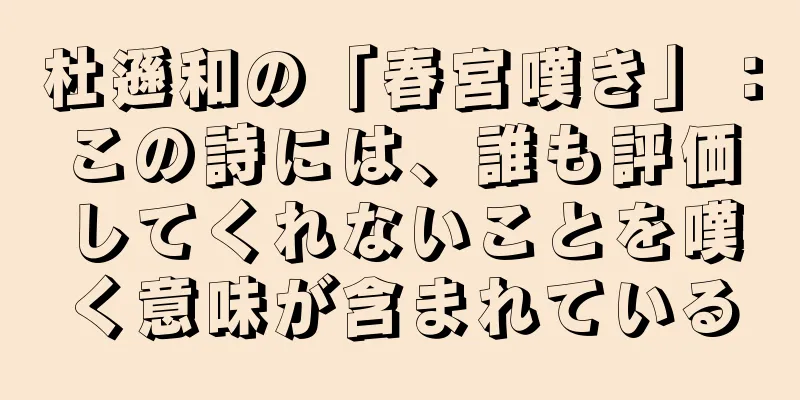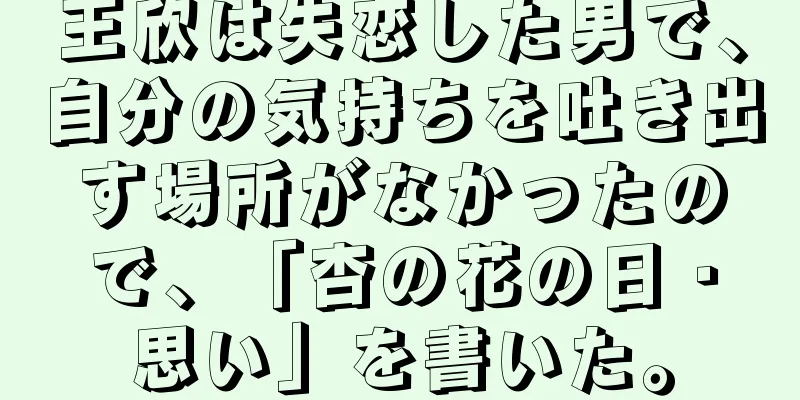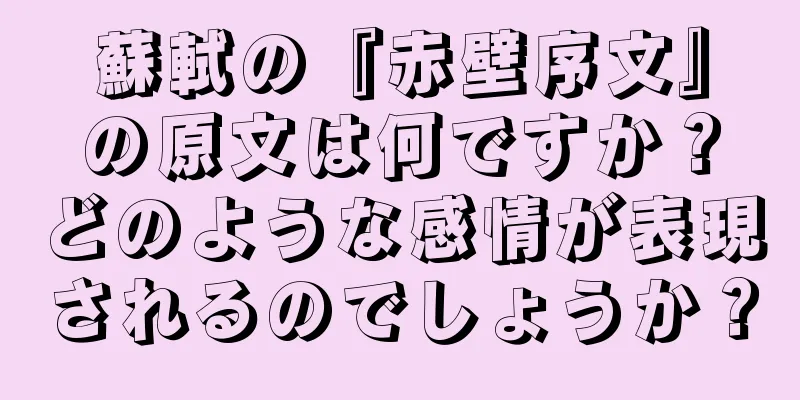諸葛亮の生涯の目標は漢王朝を支えることだったのに、なぜ漢の献帝に忠誠を尽くさなかったのでしょうか?
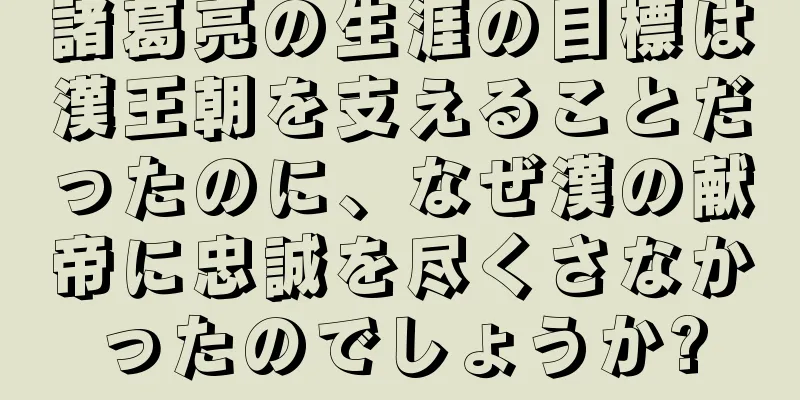
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、漢王朝に忠誠を誓っていた諸葛亮が漢の献帝のもとに行かず、劉備に協力した理由について詳しく紹介します。見てみましょう。 明代の馮夢龍はかつて孟子について詩を書いた。その詩の2行は「当時、周の皇帝はまだ存在していたのに、なぜ人々は魏や斉のことを言っているのか」である。彼は、孟子が忠誠と信義を重視していたので、当時まだ権力を握っていた周の皇帝に忠誠を尽くして仕えるべきであり、魏や斉などの属国の間でロビー活動を行うべきではなかったと疑問を呈した。 諸葛亮が生きた時代は、東漢末期でした。当時、軍閥たちは権力をめぐって争い、各地で戦争が激化していました。しかし、当時は漢の献帝がまだ権力を握っており、漢の朝廷もまだ存在していました。諸葛亮の生涯の目標は漢王朝を支えることでした。ではなぜ彼は漢の献帝の宮廷に行き、官吏として仕えて忠誠を尽くすのではなく、劉備に従って何千マイルも離れたところまで漢王朝を支えるために旅立ったのでしょうか。 1. 当時、曹操は漢王朝の朝廷を支配していました。 東漢末期の董卓の反乱の後、漢王朝の威信は最低に落ちました。当時は各地で軍閥同士が争っており、漢朝の権威など誰も気にしていなかった。特に董卓が殺害された後、関中も戦争に陥った。軍閥の乱闘の中で、漢の献帝は誰も気にしない政治的看板となっていた。 当時の漢の献帝は、戦国時代の周の皇帝よりもさらに悲惨な状況で、財力も領土も軍隊もありませんでした。漢の献帝が長安から洛陽に逃げたとき、いわゆる大臣たちは自分で薪を集めて料理をしなければならず、中には餓死した者もいた。漢の献帝のいわゆる漢王朝の朝廷も存続に問題を抱えていた。 しかし、当時最強の軍事力を持っていた袁紹は、漢の献帝を迎えるつもりはなかった。部下たちは皇帝を利用して諸侯を統制することを提案したが、袁紹はまったく興味を示さなかった。これは、袁紹がすでに漢王朝に代わって自らの政権を樹立する意図を持っていたため、漢の献帝とその一味が自力で生き延びるのを何もせずに見守っていたためである。 この時、曹操は部下の進言を採用し、率先して漢の献帝を徐都に迎え入れた。彼が重視したのは漢王朝を支えるという魅力であり、その結果、皇帝に仕えて不忠を罰するという正当な名誉を得て、大きな政治的利益を得た。しかし、曹操は漢の献帝を迎えるにあたって独自の計画を持っており、他人の利益になるようなことは何もしませんでした。彼は、正義の人という評判を得ることに加え、この政権内での地位も得たいと考えていた。 曹操は、漢の献帝から、初めに書記の称号と帝剣を振るう権限を与えられ、後に三公の一人である司空に任命されました。このようにして、曹操は漢王朝の軍事力と政治力を掌握した。このように、曹操は最初から漢の献帝の朝廷の実権をしっかりと握っていました。軍事力がなければ、他人に依存していた漢の献帝は無力でした。 曹操はこの時点ではまだ満足せず、自らの権力を獲得しようと漢の献帝に忠誠を誓う人々を何度も殺害した。彼はこれらの人々、たとえ王族の親族であっても、慈悲を示さなかった。彼はまた、自分の娘を漢の献帝と結婚させ、彼を完全に支配した。この朝廷では、曹操が関羽に返答したように、「漢は我々である」というのは全く真実である。このため、劉備、孫権らは曹操を名ばかりの漢の裏切り者だと非難した。 諸葛亮は漢王朝を支援したかったため、漢の献帝の宮廷に行き、皇帝への忠誠心を示したが、それは自殺に等しいものだった。曹操の厳しい統制の下、漢の献帝の傀儡として個人の自由さえ奪われた諸葛亮は、何も成し遂げられないばかりか、命も危険にさらされていた。このことは後に曹操が漢の献帝に忠誠を誓う大臣たちを繰り返し虐殺したことで実証された。 したがって、諸葛亮が漢王朝を支持するために漢の献帝の宮廷に行き支持することは不可能であり、また支持すること自体が不可能であった。彼には、漢王朝を支援し、漢の献帝の状況を外部から変えようとする勢力のもとに避難するしか選択肢がなかった。 2. 諸葛亮は、自分の運命に満足する、無関心な性格の男でした。 諸葛亮は『出陣の志』の中で、彼の本来の野望は「乱世にあって命を守り、諸侯の間で名声や富を求めることではない」と記している。これは謙虚な発言ではなかった。諸葛亮は大きな野望を抱いていたが、タイミングにも満足していた。彼は『息子への証言』の中で、「無関心でなければ、自分の野望を明確にすることはできない。穏やかでなければ、遠大な目標を達成することはできない」という有名な言葉を残しています。諸葛亮の考えは、孔子の格言に要約できます。「貧しければ、自分の面倒を見るべきだ。富めば、世を助けるべきだ。」 この場合、諸葛亮は簡単に官界に入り込み、その泥沼に巻き込まれることはないだろう。諸葛亮は、国内で世の中の変化を観察しながら、農作業や勉強をしながら、身の安全を確保し、適切な時期を待っていました。そのため、諸葛亮は漢の献帝の宮廷に行き、曹操に支配されていた漢の献帝のために働くことはなかった。 劉備が諸葛亮を隠遁から呼び戻すために来たとき、諸葛亮と会う前に彼の茅葺き小屋を三度訪れた。諸葛亮と劉備は気質も野心も似ていたため、すぐに意気投合しました。諸葛亮が劉備と会うとすぐに「龍中の策」の戦略案を提示したのはそのためです。これは諸葛亮と劉備がともに漢王朝を支えたいという思いを持っていたためであり、諸葛亮は劉備の誠実さに心を動かされ、劉備陣営に加わって劉備のために働くと同時に、漢王朝に忠誠を尽くし、漢王朝を支えたいという自身の願いも実現した。 3. 諸葛亮は漢王朝への忠誠心と劉備への忠誠心を統合した。 劉備は庶民の出身であったが、漢の王族の血統を政治的資本として利用した。実際、劉備は劉秀を手本として漢王朝の復興を試みた。諸葛亮は劉備の野心と行動を見逃すことはできなかった。 しかし、当時の知識人たちはすでに、漢王朝を復興することはできず、曹操を突然排除することはできないという共通認識に達しており、それは魯粛の発言でもあった。当時、多くの人々が漢王朝を捨て、自らの主人を探しに行きました。これらの人々の中には曹操に寝返った者もいれば、孫権に寝返った者もいたことがわかります。彼らは皆、王朝を変えてそれぞれの主君に仕えたいという願望を抱いていました。 諸葛亮も確かにこれを見ていた。しかし、彼は依然として漢王朝に忠誠を誓い続けました。彼が最終的に劉備を選んだのはこのためでした。彼は漢王朝復興の希望を劉備に託した。これは劉備が漢の血を引いており、漢王朝を支持すると主張していたためである。 劉備は生涯を通じて漢王朝の旗の下で戦い、最終的に彼が樹立した政権もまた漢王朝であり、歴史上「季漢」と呼ばれています。諸葛亮が劉備に尽くしたのはまさにこのためであり、劉備に仕えることは漢王朝に仕えることであり、劉備が国を再建するのを助けることは実は漢王朝を再建することであると信じていたからである。 このようにして、諸葛亮は漢王朝への忠誠心と劉備への忠誠心を兼ね備えた。漢の献帝と劉備の関係については、諸葛亮にとっては問題ではなかった。漢の献帝と劉備はともに漢の血を引いており、同じ漢王朝を支えていたため、どちらが皇帝になるかは漢王朝の内政であり、国が外部の者の手に落ちることは決してありませんでした。 結論: 当時の実情から、諸葛亮は漢王朝に忠誠を誓っていたが、曹操の傀儡となった漢の献帝の下に仕えることはしなかった。なぜなら、そこで忠誠を尽くすということは、実際には曹操に忠誠を尽くすということだからです。荀攸の最期はその良い例です。荀攸は曹操に多大な貢献をしたが、曹操の公爵昇格に反対を表明した途端、曹操に殺されてしまった。 そのため、諸葛亮は外部環境において漢王朝を支えるために一生懸命働くことしかできなかった。彼が劉備を助けるために出向いたことは、漢王朝に対する忠誠心の表れであった。劉備は漢の血を受け継いでおり、漢王朝を復興させた。劉備を助けることは漢王朝への忠誠を意味した。そのため、諸葛亮は漢の献帝に仕えなかったにもかかわらず、漢王朝の継続を維持した。諸葛亮が蜀漢政権の存続と発展、そして漢王朝の復興のために尽力したことも歴史に記録されています。 |
<<: 古代の墓にある永遠の光はなぜ何千年も燃え続けるのでしょうか?永遠のランプはどのように作られるのでしょうか?
>>: 十八羅漢の順位と物語の詳しい解説:十八羅漢とは誰ですか?
推薦する
『紅楼夢』では、宝仔はどこへ行くにもいつも赤い麝香の珠の紐を持ち歩いています。それはなぜでしょうか。
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人で、林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。これは今日...
『詩経・大雅・列文』原文、翻訳、鑑賞
リーウェン匿名(秦以前)主の偉大な徳と祝福が私たちに与えられています。私にとっての恩恵は無限であり、...
饕餮:古代神話の「龍の九子」の一人。食べることが大好きで、世間では貪欲な邪悪な獣とみなされている。
饕餮(タオティエ)は、老饕餮や袈裟(パオシャオ)としても知られ、古代中国の神話や伝説に登場する凶暴で...
なぜ項羽は劉邦によって自殺に追い込まれ、韓信の悲劇的な人生が始まったと言われるのでしょうか?
紀元前203年9月、項羽は東へ移動し、彭城に向かった。その年の10月、劉邦の軍隊は、韓信、英布、彭越...
『新唐語』第9巻の「忠勇」の原文は何ですか?
李玄通は定州に送られ、劉黒太に捕らえられたが、劉黒太は彼の才能を評価し、将軍にしようとした。彼は言っ...
蘇軾の「江南を観て、潮然台で書いた」:大胆さと優雅さを兼ね備えた詩
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
『西遊記』で幕引き将軍が現世に降格された本当の理由は何だったのでしょうか?
以下は、Interesting History の編集者による短い紹介です。『西遊記』で幕末の将軍が...
『紅楼夢』で、王夫人はなぜ青文を追い払おうとしたのでしょうか?本当の密告者は誰だったのでしょうか?
『紅楼夢』では、麝香月は宝玉の部屋の一流メイドであり、易虹院の四大メイドの一人です。 Interes...
孫子の兵法を分析すると、秦の穆公が鄭国への攻撃を主張して失敗したのはなぜでしょうか?
秦の穆公といえば、何を思い浮かべますか?次のInteresting History編集者が、関連する...
なぜ文周は趙雲より順位が低いのですか?三国志の24人の将軍の順位は正確ではない
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝 第9章 林師匠が雪山寺に、陸羽侯が干草小屋を焼く
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
「菊」が生まれた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
菊李尚閔(唐代)淡い紫、温かみのある黄色。タオ・リンの塀の美しさと、ラオ・ハンの家の香り。いつになっ...
陳良の『雨美人:東風が吹く薄雲』:歌詞は憂鬱と悲しみに満ちている
陳良(1143年10月16日 - 1194年)は、本名は陳汝能で、同府、龍川とも呼ばれ、学者たちは彼...
なぜ李おばあさんはみんなに好かれていないのですか?なぜ江雲軒で泣いているのですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、李馬がなぜみんなに不評なのかをお伝えします...
周の武王はなぜ封建制度を導入することを決めたのでしょうか?規則に従うことを拒否する王子はまだたくさんいます。
周の文王が亡くなった後、その子の季法が跡を継ぎ、周の武王となった。次は興味深い歴史エディターが詳しく...