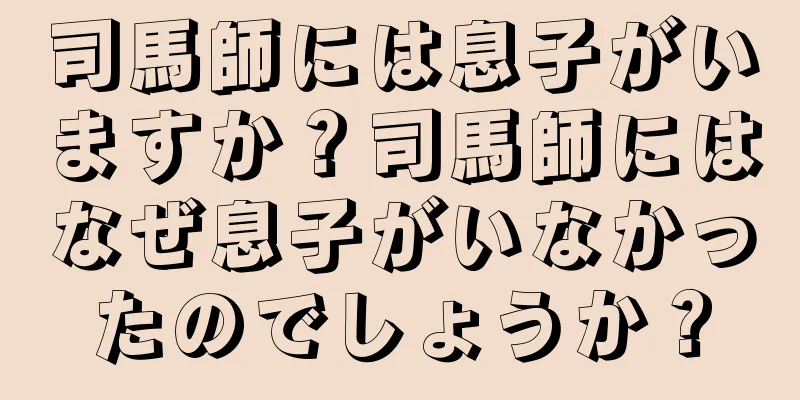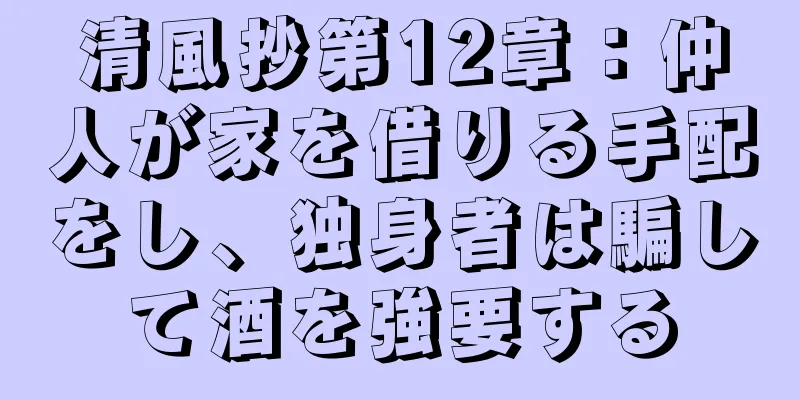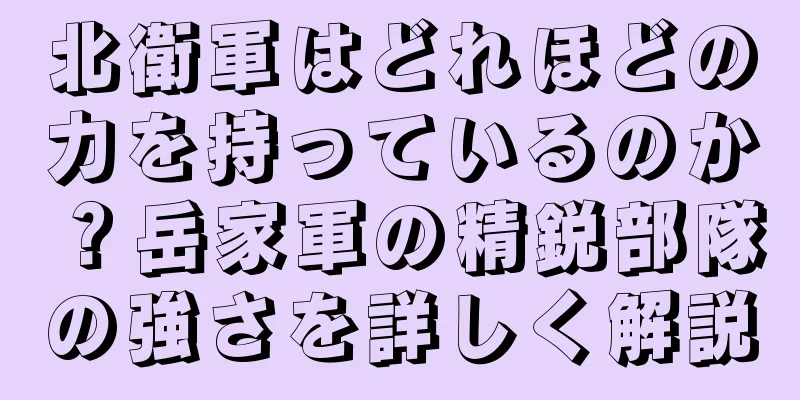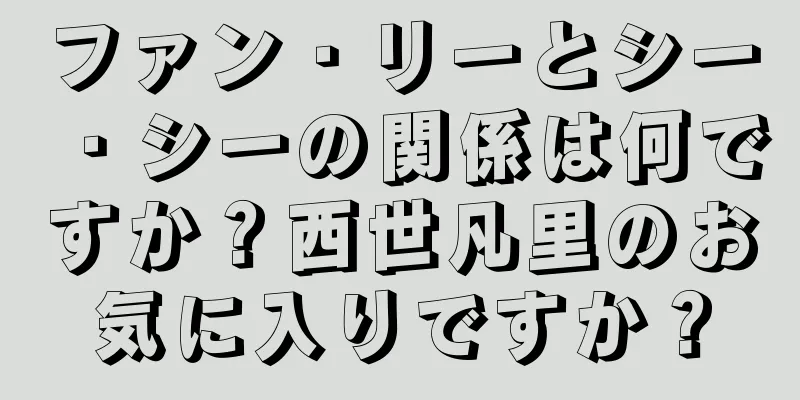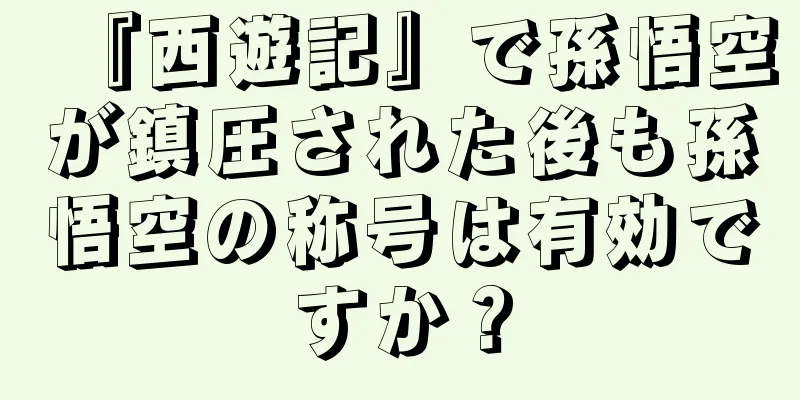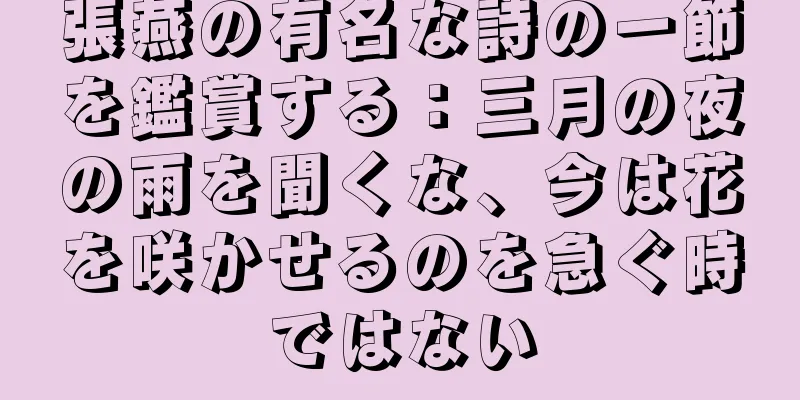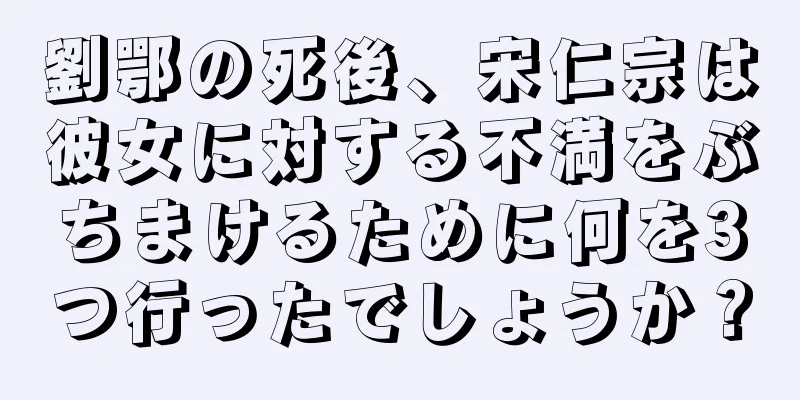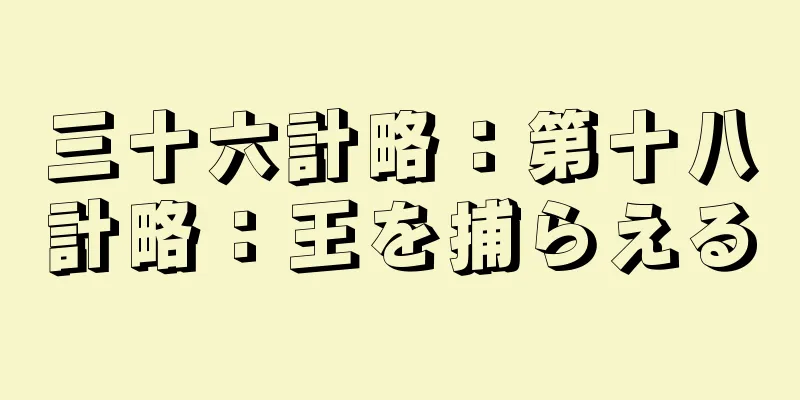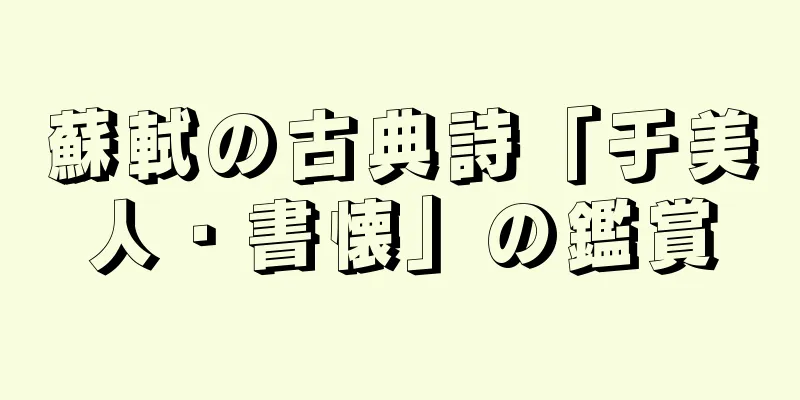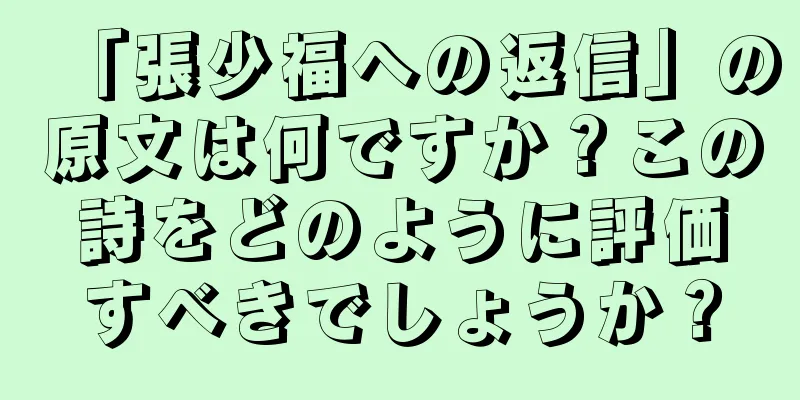十八羅漢の順位と物語の詳しい解説:十八羅漢とは誰ですか?
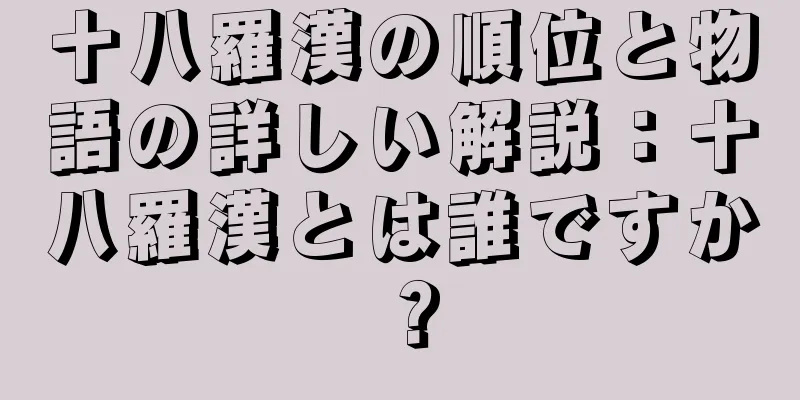
|
十八羅漢の簡単な紹介:十八羅漢とは、仏教の伝説の中で、永遠にこの世に住み、法を守護する 18 人の羅漢を指します。十六人の羅漢と 2 人の尊者から構成されます。彼らは皆歴史上の人物であり、釈迦牟尼の弟子です。十六羅漢は主に唐代に人気がありました。唐代の末期には十八羅漢が登場し始めました。宋代には十八羅漢が主流でした。十八羅漢の出現は、中国文化における 18 という数字の伝統的な好みと関係があるのかもしれません。 阿羅漢は、サンスクリット語の名前(Arhat)で、阿羅漢とも呼ばれます。阿羅漢は、仏陀の悟りを開いた弟子であり、上座部仏教の修行を通じて得られる最高の成果です。阿羅漢の境地に達すると、三界の煩悩をすべて断ち切り、観と修行の二つの迷いを取り除き、輪廻から永遠に解放されます。この意味で、阿羅漢の段階は「無量果」または「無学果」とも呼ばれ、極限に達し、すべてを学んでおり、これ以上学ぶものは何もないことを意味します。 「Arahant」という言葉はサンスクリット語の音訳であり、3つの意味があります。 一つ目は「殺盗」、つまり煩悩の泥棒をすべて殺すということです。仏教では、衆生の無知や迷いによって生じるあらゆる煩悩、疑い、執着などを心の「泥棒」と呼び、人々の心の平穏を乱し、修行を妨げる有害な感情であると考えています。しかし、阿羅漢はこれらすべての「心の泥棒」を排除しました。 「 2つ目は「供養に値する」ことであり、これは、阿羅漢の段階に達すると、生死の輪廻につながる「汚れた」法をすべて断ち切り、心身が清浄になり、人々や神々から崇拝されるべきであることを意味します。 3つ目は「無生」で、これは阿羅漢が永遠不変の涅槃の境地に入り、もはや生死の輪廻を経ず、生も死もない境地に達したことを意味します。 ” 「十六羅漢」から「十八羅漢」へ 十六羅漢像は先ほど登場しました。主に唐代の玄奘三蔵法師が翻訳した『南天密陀羅漢説法録』を根拠としています。仏典によると、釈迦は涅槃に入らずに、現世に留まり、世間の供養を受け、生きとし生けるものすべてに福徳の場をつくり、仏教を広め守るようにと教えました。 十八羅漢の出現に関する一つの説は、それが主に画家の創作に関係しており、古典的な根拠はなかったというものである。そのため、最後の2人の阿羅漢の名前についてはさまざまな意見があります。元代と明代以降、多くの寺院で十八羅漢像が彫られるようになり、十六羅漢像よりも十八羅漢像の方が人気が高まりました。 2つ目の説は、古代中国人は「9」が縁起の良い数字だと信じていたため、「18武術」や「18学者」など、「16」は「18」(「9」が2つ)ほど良くないと考えていたというものです。 「18」は縁起の良い数字です。中国文化では、「十八代目」、「十八侯爵」、「十八武道」、「十八学者」など、多くの数量表現で「18」が使われています。仏教には「十八論」「十八界」「十八変」「十八地獄」など多くの「十八」があります。「十六羅漢」が「十八羅漢」に変わったのは、明らかにこの「十八」複合体と関係があります。歴史上、少林寺の十八羅漢も松山の少林寺に現れました。カンフー羅漢の潘国静は、現代の少林寺十八羅漢の一人です。 この事件を最初に記録したのは宋代の蘇軾です。蘇軾の父、蘇軾は唐宋時代の有名な8人の散文作家の一人で、雲門派の4代目元通禅師の弟子でした。母の程夫人は名家の出身で、蘇軾と結婚した後、仏教に帰依しました。蘇家は禅岳師が描いた十八羅漢像を祀っていました。 宋代の智槃は『仏祖記』の中で、第17番目と第18番目の阿羅漢は迦葉尊者と達磨尊者であるべきだと信じていました(『弥勒経』に記録)。 清朝の乾隆年間、乾隆帝とチャンキャ・フトゥクトゥ・リンポチェは、十八羅漢の最後の二人は、龍を征服する阿羅漢(迦葉)と虎を征服する阿羅漢(弥勒)であるべきだと信じました。龍と虎を征服することは中国人の好みに非常に合っており、皇帝によって任命されたため、その時から十八羅漢が定義されました。 チベット人は、ガサヤバ尊者は龍を鎮める阿羅漢であり、ナダミダラ尊者は虎を鎮める阿羅漢であると信じています。 十八羅漢の順位と名前の由来: 最初のものは、サンスクリット語でピンドラ尊者(一般に「座る鹿阿羅漢」として知られる)です(ピンドラバラドヴァジャ)。彼はかつて鹿の車に乗って宮殿に入り、王に仏教を実践するよう説得した。 2番目はサンスクリット語でカナカヴァツァ(「祝福の阿羅漢」、「喜びに満ちた阿羅漢」、すべての善悪を知る者)です。この世の善悪醜をすべて知っているので、昔、古代インドの弁論家で、議論をするときいつも笑っていたので、幸福な阿羅漢と呼ばれていました。 3番目はサンスクリット語でKanakabha^radvaja(東大陸に住む鉢を持った阿羅漢)です。鉢阿羅漢は鉢を持って施しを乞う修行者です。だから私はいつもボウルを手に持っています。 尊者ピンドラ 4番目は尊者須菩提(ウッタラクルに住む塔を持つ阿羅漢)、サンスクリット語(スヴィンダ)です。仏塔を持つ羅漢は、釈迦に受け入れられた最後の弟子です。彼は釈迦を懐かしむため、しばしば手に仏塔を持っています。 5番目は、サンスクリット語でナクラ尊者(ジャンブドヴィーパに住む瞑想する阿羅漢)です(Nakula)。瞑想阿羅漢は戦士として生まれたため、大きな力を持ち、どんな重い物でも動かすことができるため、強大な阿羅漢としても知られています。 6番目は、サンスクリット語で「バドラ」と読み、仏陀の従者(川を渡り、沐浴を担当し、タミル・ナードゥ島に住む阿羅漢)であるバドラ尊者です。彼は賢い人で、水面をすくうトンボのように川を渡ります。 7番目はカーリカ尊者(象に乗る阿羅漢、仏陀の従者、僧伽大陸に住む)です。8番目はドゥラブッダ尊者で、パティナ大陸に住んでいます。サンスクリット語(カリカ)。象乗り阿羅漢は仏陀の従者であり、もともと象の調教師でした。 8番目はヴァジュラプトラ(笑う獅子の阿羅漢、「金剛の息子」の意、パッタナ大陸に住む)サンスクリット語(Vajraputra)です。笑う獅子阿羅漢はもともと狩猟者でした。仏教を学んだ後、動物を殺すのをやめました。ライオンたちが彼に感謝しに来たので、この名前が付けられました。 9番目は、サンスクリット語でジヴァカ(幸福な阿羅漢、「触れられない者」または「男根を断たれた者」を意味する。僧侶になる前は宦官であり、湘蘇山に住んでいた)である(ジヴァカ)。幸福な羅漢は出家する前は乞食だったとも言われています。ある時、彼は自分の心を明かし、人々に仏が心の中にいることを悟らせたので、幸福な羅漢と呼ばれました。 10番目はサンスクリット語でパンタカ(パンタカは「道端で生まれた」という意味で、私生児である)です。両手を広げた阿羅漢は路上生活者です。瞑想後によく手を上げてストレッチをするため、両手を広げた阿羅漢と呼ばれています。 11番目は、ホーラ尊者(瞑想する阿羅漢、釈迦牟尼の実子、釈迦牟尼の十大弟子の一人となり、「秘密の修行の第一人者」として知られ、ビリヤンチュ島に住んでいた)サンスクリット語(Ra^hula)です。観自在羅漢は釈迦牟尼の実子です。釈迦の十大弟子の中で、仏教の教えにおいて第一位に位置づけられています。 12番目は、広範渡坡山に住むナガセナ尊者(耳かき阿羅漢、意味は「龍軍」、通常は「比丘ナガセナ」と呼ばれる)です。サンスクリット語(Na^gasena)。耳かき阿羅漢は耳清浄の理論で有名で、耳かき阿羅漢と呼ばれています。 耳かきをする羅漢 13番目は広溪山に住む桀佗尊者です。サンスクリット語(An%gaja)。布袋羅漢は背中に布袋を背負っていることが多く、いつも笑顔を浮かべています。現在では布袋弥勒とも呼ばれています。 14番目はヴァナヴァシ尊者(山に住むバナナ阿羅漢)。サンスクリット語(Vanava^-si)。彼は出家後、バナナの木の下でよく修行し、ある日ついにバナナの木の下で悟りを開いたため、バナナ阿羅漢と呼ばれました。 15番目は、アジタ尊者(ヒガラ峰に住む仏陀の侍者、長い眉を持つ阿羅漢)、サンスクリット語(Ajita)です。象乗り阿羅漢と同じく、長眉阿羅漢も仏陀の召使いです。伝説によると、生まれたときから眉毛が2本長かったため、長眉阿羅漢と呼ばれています。 16番目は、尊者ユダパンタカ(門番の阿羅漢)であり、尊者パンタカの弟で、サンスクリット語(Cu^l!apanthaka)で「小さな道端の学生」(私生児でもある)を意味します。門番の阿羅漢は、義務に忠実なパンタカの弟です。 17番目は、龍を鎮める阿羅漢である迦葉尊者です。龍を鎮める阿羅漢は、古代インドで龍王が仏典を盗んだのに、龍王を鎮めて経典を取り戻した功績が大きいため、龍を鎮める阿羅漢と呼ばれています。 18番目は虎を鎮める阿羅漢、弥勒菩薩です。鎮虎阿羅漢は、寺の外で空腹の虎によく遭遇し、菜食の食事を虎に分け与えたことから、このように名付けられました。 |
<<: 諸葛亮の生涯の目標は漢王朝を支えることだったのに、なぜ漢の献帝に忠誠を尽くさなかったのでしょうか?
>>: 周瑜の美人罠は最初から成功の見込みがなかったと言われるのはなぜでしょうか?
推薦する
三十六計:第十三計:蛇に警戒させる
第13の戦略: 蛇に警告する草をかき回すと、その中に隠れていた蛇が驚きました。後に、相手に気づかれる...
重要な将軍に褒賞を与えるとき、劉備はなぜ趙雲を最後にしたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
日本の侵略者と戦った明代の有名な将軍、胡宗賢の簡単な紹介。胡宗賢はどのようにして亡くなったのでしょうか?
胡宗賢の簡単な紹介胡宗賢(1512-1565)は漢民族であった。名は如真、号は梅林。徽州鶏西(現在の...
「貧しい人は水に行ってはいけない、金持ちは売春をしてはいけない」ということをどう理解しますか?そこにはどんな真実が含まれているのでしょうか?
「貧乏人は水に入るべきではない、金持ちは売春をするべきではない」ということわざをどう理解しますか?そ...
なぜ満漢宴会は北京の「十大馬鹿事」の第一位に挙げられているのでしょうか?
当時の北京人によって、清朝の宮殿での満漢宴会が北京の「十大馬鹿事」の第一位に挙げられたのはなぜでしょ...
「漢民族」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか?歴史上、漢民族が権力を握った王朝はたった3つしかありませんでしたか?
「漢民族」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか?歴史上、漢民族が権力を握った王朝はたった3...
「忠勇五人男物語」第57話の主な内容は何ですか?
若い英雄が高家店の泥棒にいたずらをして、山西ガチョウの薬酒を飲ませたアイ・フーたちが決心したとしまし...
蒋子牙の「太公六計」:「六計・犬計・兵法」の評価と例
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われてい...
王容に関する逸話や物語は何ですか?後世の著名人は彼をどう評価したのでしょうか?
王容(234年 - 305年7月11日)、雅号は俊崇とも呼ばれる。彼は臨沂琅牙(現在の山東省臨沂市白...
銭奇の「古口書斎から楊不韵への手紙」:著者は楊不韵を書斎に招き、雑談をする。
銭麒(722?-780)、号は中文、呉興(現在の浙江省湖州市)出身の漢人で、唐代の詩人。偉大な書家懐...
昭王32年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記されているか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
歴史上、大晦日に関する詩にはどんなものがありますか?詩人はどんな場面を描写しているのでしょうか?
大晦日の夜は、祭りの喜びと新年への期待が最高潮に達します。歴史上、大晦日に関する詩は数多くあります。...
劉邦の軍事力はどれほど優れていたのでしょうか?淮王は彼に武安侯の爵位を授けた。
劉邦(紀元前256年12月28日 - 紀元前195年6月1日)、字は冀、沛県豊義中洋里(現在の江蘇省...
『紅楼夢』で賈正はなぜ趙叔母さんに恋をしたのでしょうか?彼らはどうやって出会ったのですか?
工部省副部長の賈正は、賈夫人と賈岱山の次男であった。以下の記事はInteresting Histor...
北宋の六大盗賊の一人である王福は、最終的にどのように死んだのでしょうか?王福の結末
王福(1079-1126)は、北宋時代の開封県湘府県(現在の中国河南省開封市)の人。号は江明。本名は...