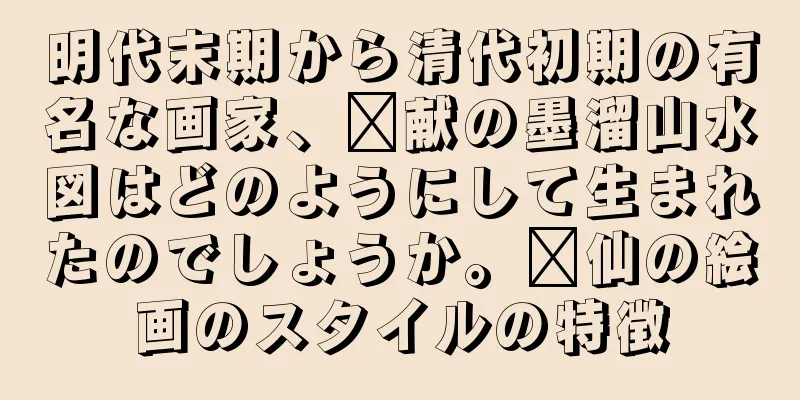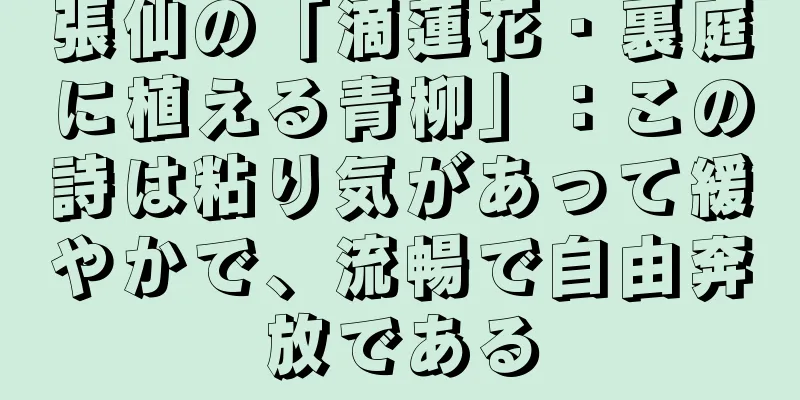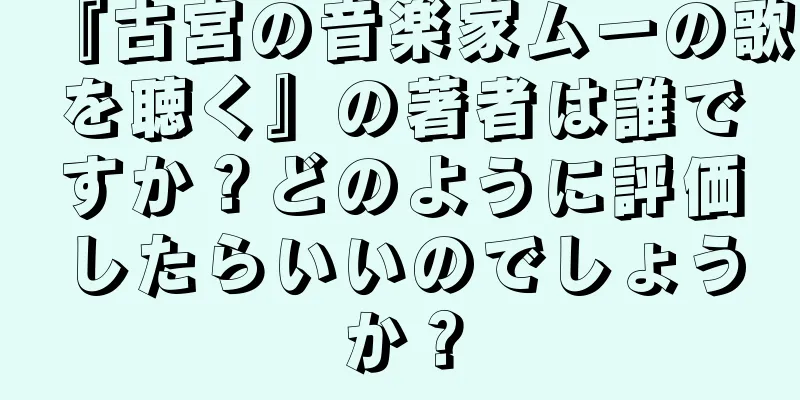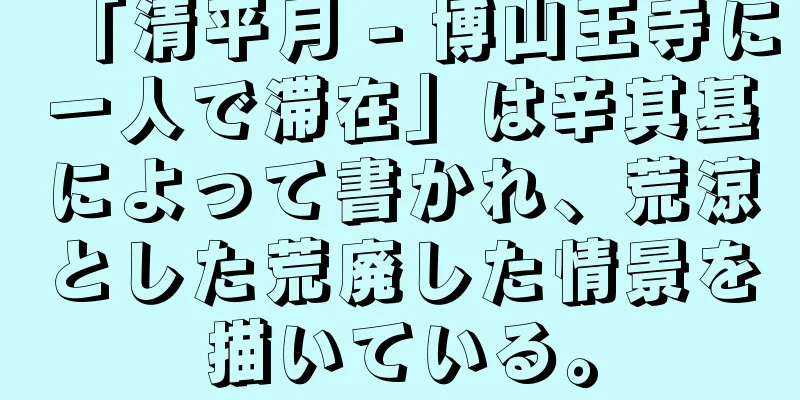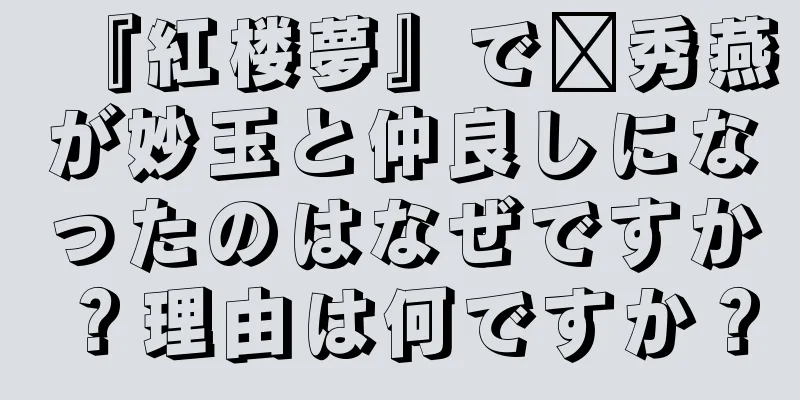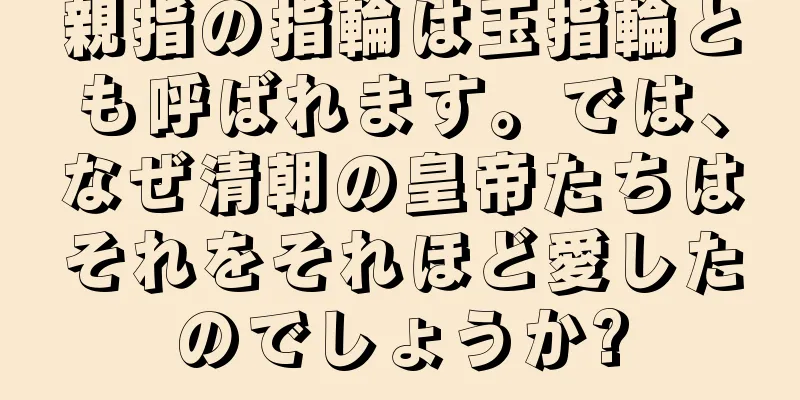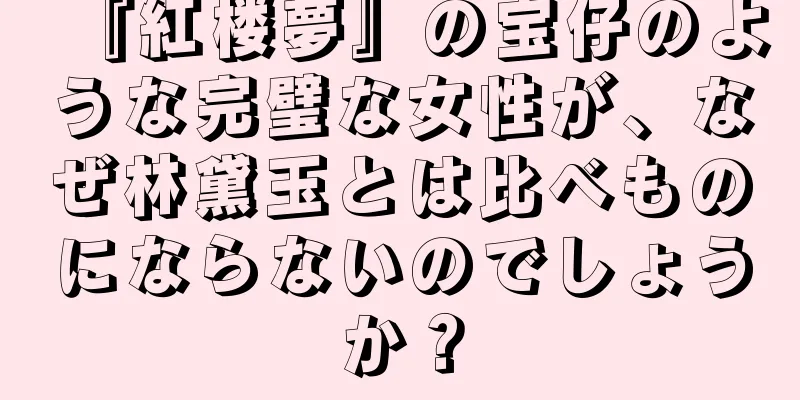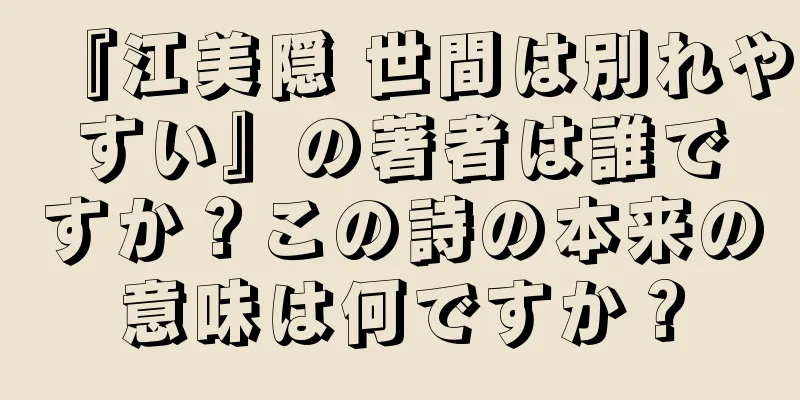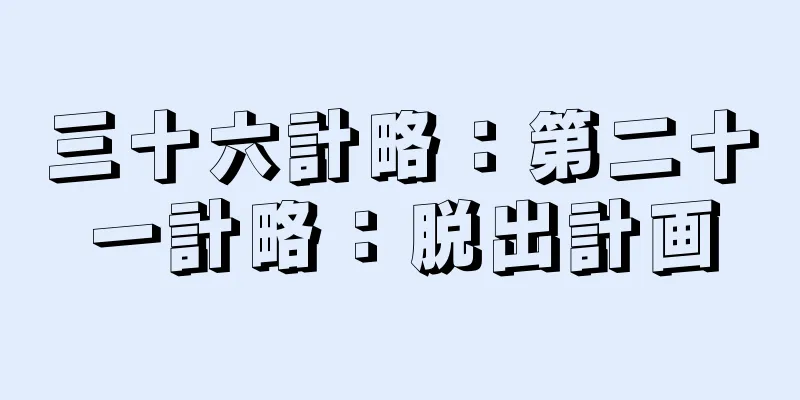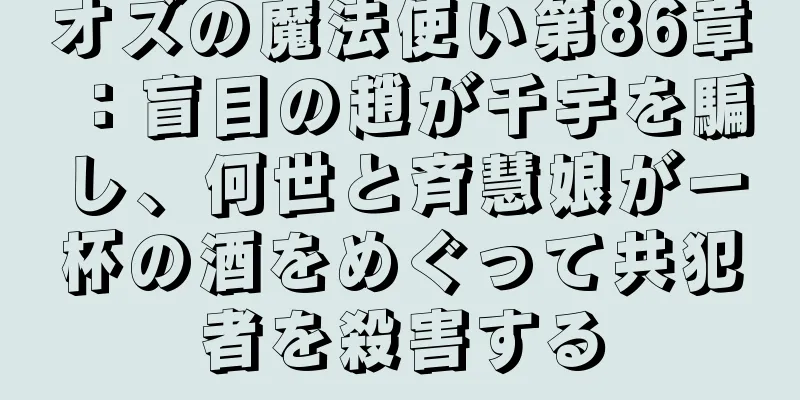抗日戦争中に何人の国民党の将軍が敵に降伏したか?
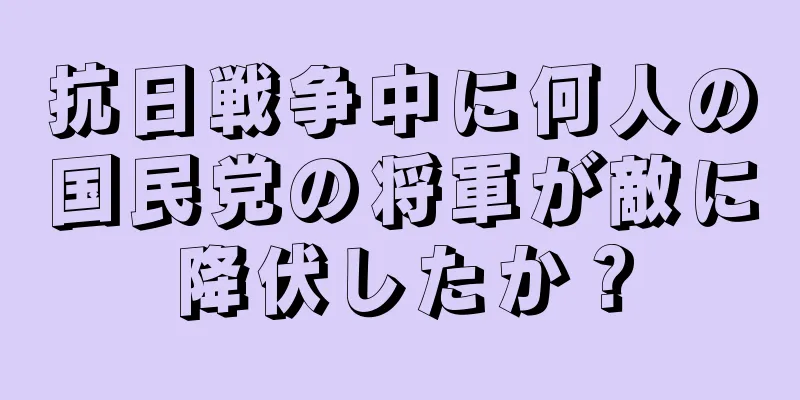
|
はじめに:岡村安治氏は、「平和的抵抗」とは「蒋介石を中心とし、黄埔陸軍士官学校出身の青年将校を中心に構成された中央直轄軍の抗日意志」を指すと述べた。 西北軍の将軍46名が敵に亡命し、これは敵に亡命した国民党の将軍総数のほぼ半数を占めた。 抗日戦争中の国民軍の敵への降伏の問題は常に懸念事項であった。インターネット上には、「抗日戦争で敵に投降した国民軍兵士の数は、実際には殺した敵の数を上回っており、これは大きな「奇跡」だ」と国民軍を揶揄する書き込みもあった。ネットユーザーの中には、「抗日戦争の際、国民党の将軍は数百人が敵に降伏したが、共産党からは一人も降伏しなかった」とさえ言う者もいる。では、国民党軍は何人、誰の軍だったのだろうか。国民党軍の敵への投降問題について、葉剣英は、孫良成が敵に投降した1942年から1944年6月まで、「抗日陣営の将軍は合計67人が敵に投降した」と述べた。①その後、学者の王観と楊樹標はさらに、1939年から1945年の間に、少なくとも99人の国民党の高級将軍が敵に投降したと計算した。 敵に投降した将軍たちの中で、最も高い軍階級を有していたのは、河北・チャハル戦区副司令官、ゲリラ総司令官、第39軍集団副司令官を務めた孫良成将軍だった。孫良成が所属していた西北軍は、降伏した将軍が最も多かった軍でもあった。孫自身の8人の将軍に加え、第128師団の指揮官である王金寨と9人の将軍、孫典英、龐炳勲と11人の将軍、呉華文と数人の部下が次々と部隊を率いて降伏した。敵に降伏した北西軍の将軍は46名で、敵に降伏した国軍の将軍総数のほぼ半数に相当した。 ②北東軍で敵に降伏した将軍の数は、北西軍に次いで多かった。鮑文月(元東北警備指揮部参謀長、軍事委員会弁公庁副部長、中将)ら東北軍の3人は西安事件後、上海に住んでいたが、孤独に耐えられず敵に投降した。魯粛戦区の第89軍副司令官潘干成らは部隊を率いて敵に降伏した。東北軍の将軍計11名が敵に降伏した。 ③敵に投降した他の国民軍の将軍は、主に地方軍、軍事統制委員会、山西綏遠軍、広東派、中央軍の出身者であった。 敵に降伏した中央軍の将軍のうち、香港で汪に単独で降伏した元武漢守備隊司令官の葉鵬と、河南で部隊を率いて降伏した第一戦区旅団長の何凱先を除き、衡陽の戦いの後、周清祥ら5人だけが方献啓とともに日本に降伏せざるを得なかった(そのほとんどは後に帰国した)。彼らは敵に降伏した将軍の総数のうちわずか8%を占めた。 ④この99人のほかに、東北抗日連合軍と八路軍の師団長、連隊長数十人が敵に投降した。例えば、抗日連合軍第1軍の補給総監であった胡国塵と政治部長の安光勲は、それぞれ1937年と1938年に日本軍に投降し、楊靖宇の軍隊を排除する方法について助言を与えた。八路軍河北・山東国境軍区司令官の邢仁福は、1943年にまず蒋廷文に降伏し、その後1944年に日本に降伏した。 1943年2月、新設された第4師団の指揮官である呉華文は部隊を率いて日本軍に降伏した。写真は、呉華文氏(左から2番目)が南京で朱民益氏などの汪傀儡政権の高官らに歓迎されている様子。抗日戦争中、敵に降伏した国民党軍の総数は約50万人で、そのほとんどは雑多な兵士だった。中央軍で敵に降伏した国民党の将軍はごくわずかだった。彼らの中には挫折して裏切り者になった者もいれば、部隊を率いて敵に降伏した者もいた。太平洋戦争勃発後、日本軍が敵陣後方の国軍への圧力を強めた際に、敵に降伏する事例が多数発生した。ゲリラ地帯であった河北・チャハル戦区と山東・江蘇戦区の崩壊により、山東・江蘇戦区遊撃隊副司令官の李長江、江蘇第8保安旅団司令官の楊中華の軍勢4万人、河北・チャハル戦区の孫良成の軍勢3万人、孫典英の率いる軍勢1万人が傀儡軍となった。 ⑤ 次々と敵に降伏した将軍たちによって、どれだけの国軍が連れ去られたかを正確に知ることは不可能である。 葉剣英は1944年に「傀儡正規軍は約38万人、傀儡地方軍は約40万人、全国の傀儡軍総数は約78万人で、そのうち62%が国軍によって敵に投降した」と述べた。⑥おそらくこれに基づいていると思われるが、『ケンブリッジ中華民国史』には「50万人以上の軍隊がこれらの離反将軍に従い、日本軍はこれらの傀儡軍を使って占領地を防衛し、共産ゲリラと戦った」と書かれている。⑦上記の情報から、さまざまな理由で敵に投降した軍の将軍は主に「雑多な部隊」であり、中央軍の大規模な投降は衡陽での1回だけであったことがわかります。 1939年11月、岡村安治は『日華事変の早期解決に関する意見』の中で、「敵の抗日勢力の中核は、四億の中国人民でも、官僚の意志でもなく、地方雑兵を含む二百万の敵抗日軍でもなく、ただ蒋介石を中心とし、黄埔陸軍士官学校の青年将校を主体とする中央直轄軍の抗日意志にある。この軍が存在する限り、迅速かつ平和的な解決は木の中の魚を探すようなものである」と判断を下した。⑧ 岡村の判断が妥当かどうかは意見が分かれるところである。 汪兆銘は傀儡の軍事・政治大臣である鮑文月を伴って傀儡軍を視察した。注:「Ye Ye Jianying:「中国共産党の日本に対する抵抗戦争の紹介(1944年6月22日)、党の設立以来重要な文書を選択しました。 45”、党の歴史の研究、2000年、「日本に対する抵抗の多くの操り人形の奥行きの分析」 Uan People's Publishing House、1987、p。 |
<<: 「帝国の華」として知られる日本のスパイとは誰ですか?
推薦する
『紅楼夢』のタンチュンは遠方から嫁いだ後、何を経験したのでしょうか?結末は?
丹春の遠方への嫁入りは『紅楼夢』の筋書きである。次に、Interesting Historyの編集者...
「太白峰登山」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
太白峰に登る李白(唐)西の太白峰に登り、沈む夕日を眺めましょう。太白は私に話しかけ、天国の門を開いて...
後梁の創始者朱文には息子がいましたか?なぜ彼は養子に王位を譲ったのでしょうか?
梁、唐、金、漢、周、そして南部の10の分離独立政権、すなわち前蜀、後蜀、呉、南唐、呉越、閩、楚、南漢...
【張鈞伝】原文と翻訳、張鈞は荊昭の出身である
チャン・ガンの経歴張鑫は荊昭の出身であった。父の武威は三元県の県令であり、その功績により死後普社とい...
科挙の秘密を探る:成績一位の学者が必ずしも宮廷試験で一位になるとは限らない?
科挙で1位になった人は「元」、省挙で1位になった人は「界元」、都挙で1位になった人は「会元」と呼ばれ...
「庚緒の乱」:嘉靖年間にモンゴルのハーン、アルタンが明朝を侵略した
「庚緒の変」についてご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。『興味深い歴史』編集者がお教えします。元...
水滸伝では、宋江と呉容はどれほど陰謀を企んでいるのでしょうか?
水滸伝に登場する玉の一角、陸俊義は、武術の世界では最高峰であり、棒術では他の追随を許さない人物です。...
孫光賢の「環西沙・刺繍のカーテンから漂う香りを風が運ぶ」:この詩は女性の嫉妬を描いている
孫光賢(901年 - 968年)は、孟文と号し、宝光子と号し、陵州桂平(現在の四川省仁寿県湘家郷桂平...
劉宗元の「孟徳への別れ」:この詩は別れの気持ちを直接表現し、誠実で感動的な芸術的構想を生み出している。
劉宗元(773年 - 819年11月28日)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の...
「長安星・九江河畔の家」は崔昊によって書かれた。詩人は人生の一場面を捉えた。
崔昊(704-754)は汴州(現在の河南省開封市)の出身で、祖先の故郷は伯陵安平(現在の河北省衡水市...
『文心语龍』原文の鑑賞 - 神思第26章
古代人は「肉体は海や川の上にあり、心は衛宮の下にある」と言いました。これが精神的に考えるという意味で...
楊家将軍物語の八賢王:八賢王の本当の原型は誰ですか?
宋元時代以降、楊家の将軍を題材にした小説やドラマが数多く作られてきました。これらの伝説の物語には、常...
『紅楼夢』の薛叔母さんはなぜ香玲を人身売買業者に売ったのですか?
甄英蓮は古典小説『紅楼夢』の登場人物です。彼女は『金陵十二美女』第二巻の娘で、賈家では香玲として知ら...
北京語:金宇・鄭樹展は耳を押さえて痛みに叫ぶ 全文と翻訳ノート
『国語』は中国最古の国書である。周王朝の王族と魯、斉、晋、鄭、楚、呉、越などの属国の歴史が記録されて...
なぜ魏延は諸葛亮の最後の命令に背き、楊毅と戦ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...