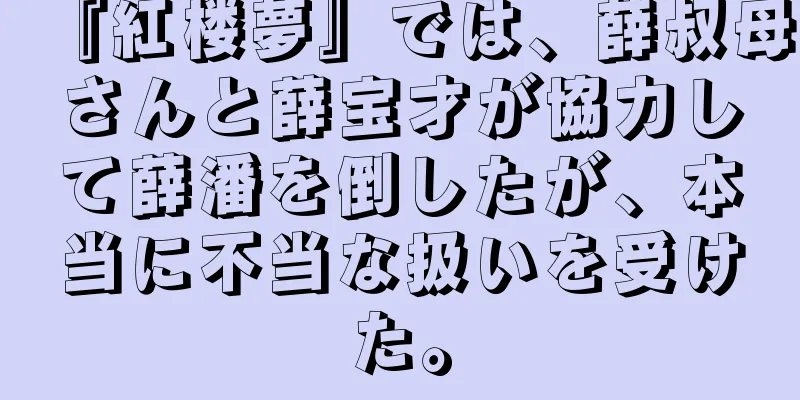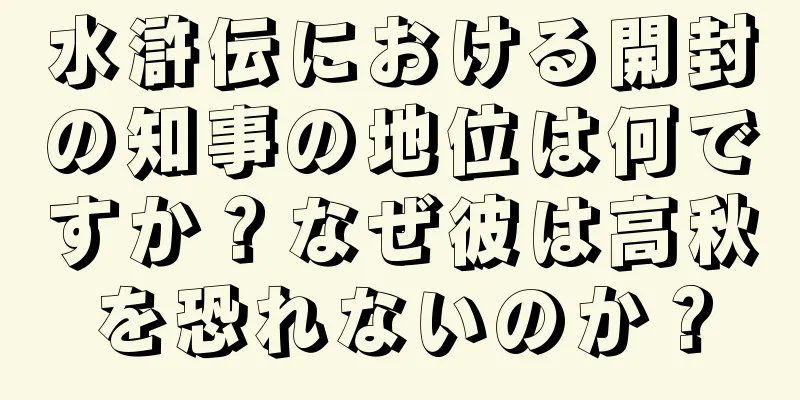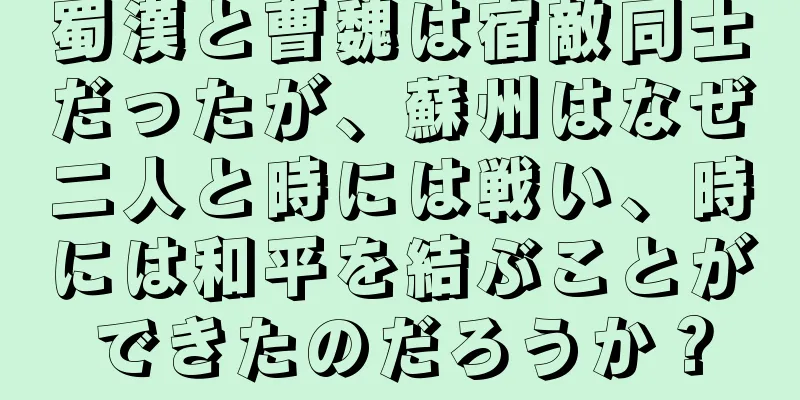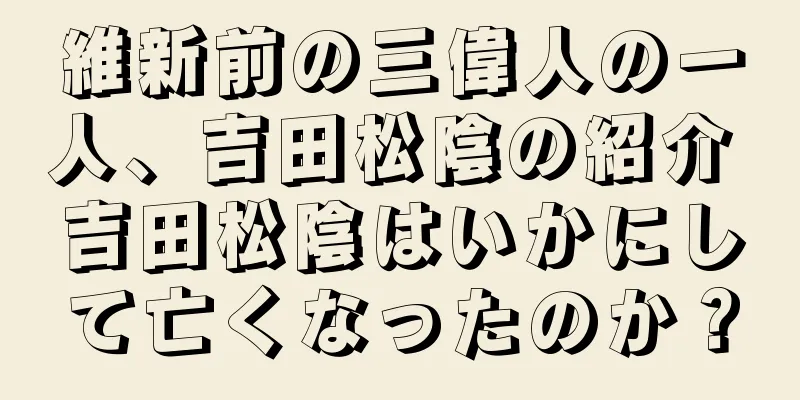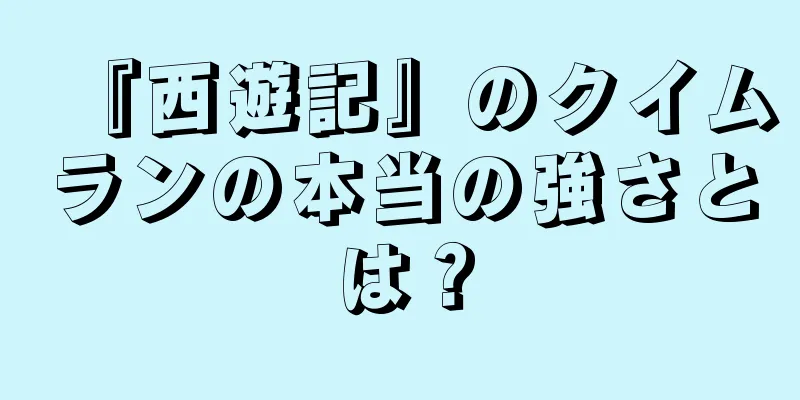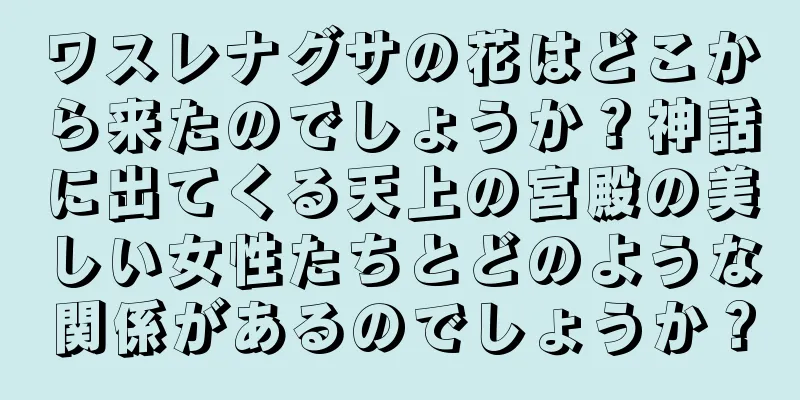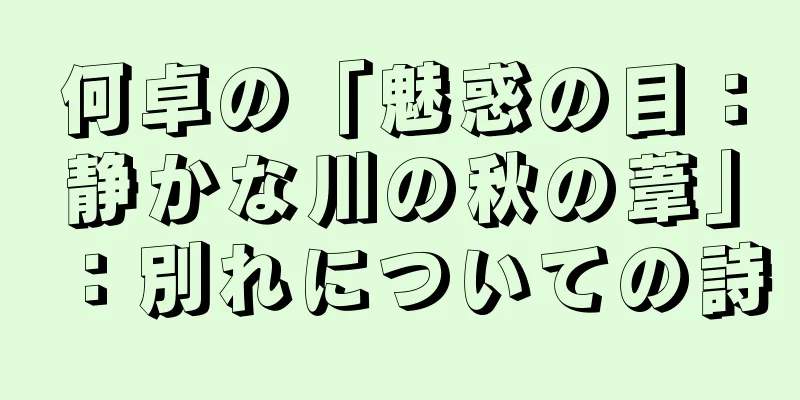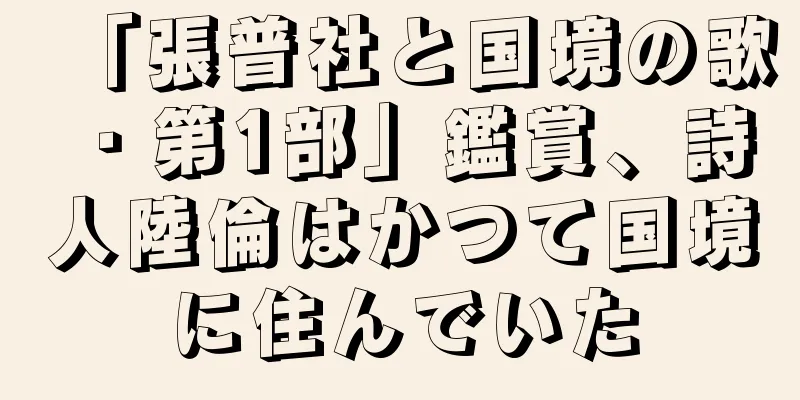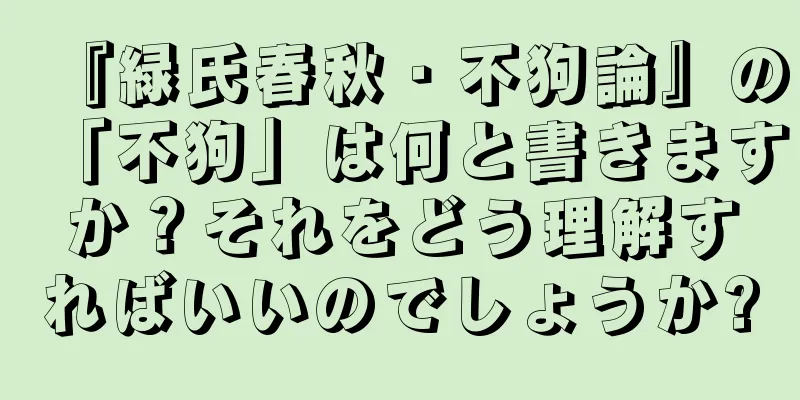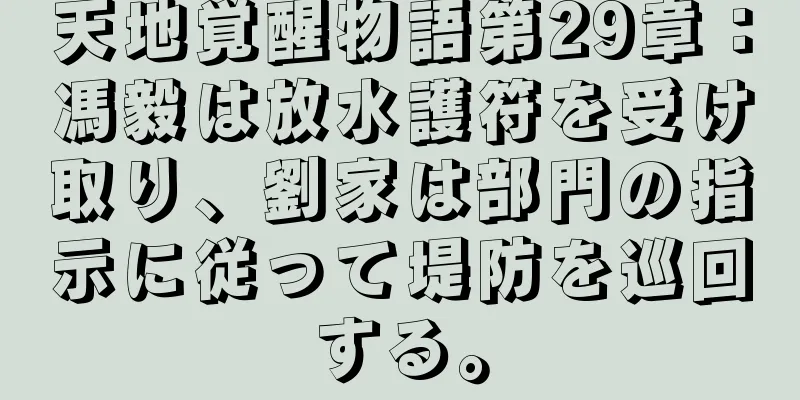「清平月 - 博山王寺に一人で滞在」は辛其基によって書かれ、荒涼とした荒廃した情景を描いている。
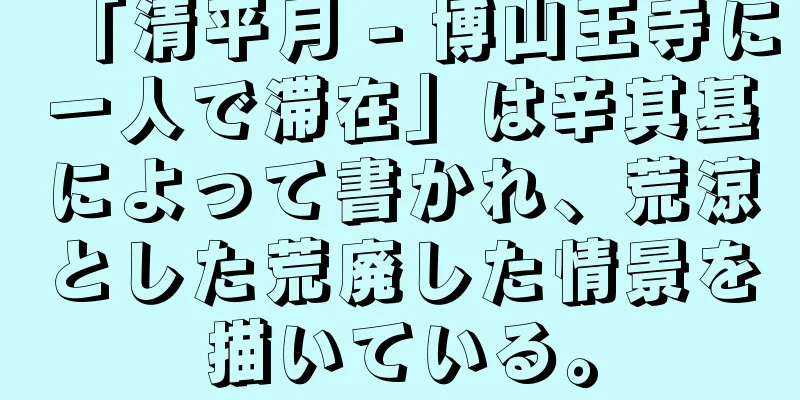
|
辛其基は、字を有安、号を嘉宣といい、南宋時代の大胆で奔放な詩人の代表者であり、「筆をもって天下に平和をもたらし、馬に乗って天下の運命を決する」人物であった。曲史の編集者と一緒に、辛其記の『清平楽:博山王寺独居』について学びましょう。 辛其基(1140-1207)は、死後「中敏」と名付けられ、山東省済南市礼城の出身である。南宋時代の大胆で奔放な詩派の代表者として、辛は後に「詩の中の龍」と称えられ、彼の詩集『家宣長端集』は今日まで伝えられている。辛其基は宋の領土回復に生涯を捧げ、偉業を成し遂げたいと願っていたが、彼の運命は不運に満ちており、その野望は達成するのが困難であった。南宋の抗金戦争の指導者として、官職での挫折の後、彼は国の興亡に対する情熱と国家の運命に対する憂いを詩で表現しました。彼の文体は、深遠で勇壮で力強く、満たされなかった野望に対する彼自身の悲しみと憤りが混じっています。 「三国志を知らなくても彼の言葉はわかる」というのは、世間からの彼に対する高い評価と言えるでしょう! 辛其季(1140年)は北方の占領地で育った。1161年、万延良が南方を侵略した。22歳の辛其季は反乱を起こし、宋朝に戻った。南に帰った後、彼は何度も任命されたが、また解任され、ほとんどの時間を怠惰に過ごした。彼が最後に官吏を務めたのは、65歳の時で鎮江の知事を務めたときだった。彼は約15ヶ月の在職後に再び解任され、1207年に心の中に憎しみを残したまま亡くなった。 辛其基は大きな野望を抱いていたが、働く機会を与えられなかった。しかし、朝廷に任命されるたびに、彼は常に「大業の復興に自信と希望を抱いて官職に就いた。職務を遂行する一方で、朝廷の北伐に助言や提案を惜しみなかった。しかし、その後の長い年月、江西省、湖北省、湖南省、両淮地域の地方官として勤務することは予想外だったが、中原復興に参加する機会はなかった。 春熙12年(1185年)、辛其基は江西省にやって来て、上饒で隠遁生活を送ることを選んだ。この時期、辛其基は普通の農民のようで、毎日ただ本を読んだり書いたり、農作業をしたりしていた。彼は暇な時には、ただ心を落ち着かせるために、その地域を旅していました。この頃、彼はすでに45歳でしたが、旅行が好きで、訪れた場所ごとに多くの美しい詩を残しました。その中で、「清平楽:博山王寺に一人で泊まる」という詩はとても興味深く、言葉遣いも美しく、ほんの数語でとても生き生きしています。 清平楽:博山の王寺に一人で泊まる 空腹のネズミがベッドの周りを回っており、コウモリがランプの周りで踊っています。屋根の上の松風が激しい雨を運び、その雨が破れた障子を通してささやきます。私は生涯ずっとこの国の北と南を旅してきましたが、今では白い髪と灰色の顔で帰ってきました。布のキルトの下で秋の夢から目覚めると、目の前に広大な景色が広がっています。 辛其氏は、空腹のネズミがベッドの周りを走り回り、コウモリが薄暗い石油ランプの周りを飛び回っていると話した。強い風が松の木の音と混じって、うねる波のようにうなり、激しい雨が降り注いで屋根を激しく打ち、窓の障子が風に引き裂かれ、まるで独り言を言っているかのようにカサカサと音を立てた。彼は北の辺境から揚子江の南部まで旅した後、今は山奥に隠遁して暮らしている。彼は年老いていて、頭髪は真っ白だ。冷たい秋風が薄い掛け布団を吹き抜け、私は突然目が覚めた。夢の中の広大な風景がまだぼんやりと私の目の前に残っていた。 辛其の詩は、「鉄騎兵、虎のように千里を呑み込む」という英雄的な精神、「人混みの中で何百回も彼を探し、振り返ると、薄暗い光の中に彼がいた」という優しさ、「枝の明るい月がカササギを驚かせ、涼しい風が真夜中にセミを鳴かせた」という新鮮さと美しさなど、豊かな多様性を反映しています。彼の様々なスタイルの作品は高い芸術的成果を達成しており、この「清平月:博山王寺独居」も例外ではありません。 この「清平楽」は辛其記の詩の芸術的なスタイルを代表している。詩全体はわずか8文46語だが、荒涼とした荒廃した情景を描いている。 この詩の最初の部分は、作者が見たもの、聞いたもの、そして当時の心境を描写しています。この短い文章はとても興味深く、感動的です。ベッドの下の空腹のネズミが走り回って人々を落ち着かせず、コウモリが薄暗い石油ランプの周りを飛び回っていました。その時、外では再び強い風が吹き始め、この強い風は松の木の音を伴い、波が押し寄せるような音を伴っていました。一瞬にして激しい雨が降り始めました。巨大な雨粒が屋根にぶつかり、窓の紙は破れ、まるで誰かが夜雨の中で独り言を言っているかのように、口笛のような音を立てました。これらの文章は生き生きと書かれており、真夜中の雨とは違うことを感じさせます。 この詩の後半で、辛其記は「私は生涯、国の南北を旅し、今は白髪と老いた顔で帰ってきた」と本音を述べている。この2行は、彼の人生の大半の経験を要約し、「白髪と老いた顔」で彼の老齢を強調し、深い感情を暗示している。それにもかかわらず、「秋の夜の夢」から目覚めた後、彼が考えていたのは依然として祖国の「広大な川と山」でした!彼の思想領域は実に高尚です。辛其基は43歳で罷免された。大きな打撃を受けたが、悲しむことはなく、国と人民のことを心配し続けた。彼は本当に素晴らしい人です!こんな兄がいて幸せです! この詩が言葉で表現した絵や感情は、線や色を使って表現すれば十分に表現できる。これは作者が抽象的な文字記号で捉え、表現した風景の具体性の高さを示している。また、それぞれの文章は物や観光名所であり、それらを組み合わせると接続詞さえ省略でき、珍しい風景画を形成します。この絵を通して、作者は悲しい気持ちと、祖国の美しい山や川への愛情を表現しています。 王国衛は「有安の奉仕は気質と境地に基づく」と語った。深く強い愛国心はまさに辛其記の「気質」である。結局、彼が趙全を批判し、友人を激励したのは、彼が深い愛国心と北伐と戦う強い決意を持っていたからであり、彼の気持ちは誠実で、野心は強かった。詩人は、ジャンル本来のスタイルを失うことなく言葉の中に暗示を用いており、その雰囲気は穏やかで落ち着いている。詩全体が響き渡り、明瞭で感動的である。 |
<<: 陸游著『蘇忠清:称号を求めて千里を旅した』は尽きることのない愛国心に満ちている
>>: 張若旭の「春河月夜」は、思想と芸術において山や川を単に模倣する以上のものである。
推薦する
お堀の発展の歴史!古代において堀はどのような役割を果たしていたのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が堀の開発史をお届けします!興味のある読者は編...
古典文学の傑作『太平天国』:帝部第20巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
なぜ明王朝は日本軍の侵略に抵抗できたのに、清王朝はできなかったのでしょうか?
明代中期(特に嘉靖年間)以降、中国南東部沿岸では倭寇の脅威がますます深刻になっていった。しかし、斉継...
沼地の無法者第94章:天文大臣蔡が失脚、宋公明が渭水を渡る際に兵を失う
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...
林黛玉と賈宝玉が仲良くしているとき、賈おばあさんはなぜ冷静を保っていたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『秋長安図』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
長安の秋景色杜牧(唐代)建物は霜の降りた木々に寄りかかっており、空は鏡のように澄み渡っています。南山...
李白の古詩「中都の明福兄弟に別れを告げる」の本来の意味を理解する
古代詩「中都の明福兄弟に別れを告げる」時代: 唐代著者: 李白私の兄は詩と酒において陶氏の後継者であ...
薛宝琴の郷愁詩十首の意味は何ですか?
レッドクリフへのノスタルジア(パート1)赤い崖は埋もれ、水は流れず、空っぽの船に名前と苗字だけが残っ...
リス族の食 リス族の食文化の特徴は何ですか?
リス族の文化は非常に豊かで、特に食文化は独特です。リス族は山岳地帯で暮らすことを選んだ民族であり、そ...
「青空は死んで、黄空を確立すべきだ」ということわざはどこから来たのでしょうか?この文はどういう意味ですか?
「青空は死に、黄空は確立すべき」という言葉はどこから来たのでしょうか?この文章はどういう意味でしょう...
秀雲閣第44章:袁富虎の講義録が亭雲閣の大臣の宮廷に返還される
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
なぜ司馬昭は劉禅を殺さなかったばかりか、彼を安楽県公にしたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『晋書』第127巻の原文は何ですか?
◎ 慕容徳慕容徳は、号を玄明といい、黄帝の末子であった。彼の母である公孫は、昼寝中に太陽が臍に入って...
宋代の作家蘇軾:「承天寺夜遊」の翻訳と創作背景
『承天寺夜遊び記』は、中国宋代の作家蘇軾が書いた古代の随筆です。文章は月夜の美しい風景を描写し、黄州...
楊吉の『揚子江千里』:この詩は新鮮で流暢で、自然で完成度が高い
楊季(1326-1378)は、元代末期から明代初期の詩人であった。名は孟仔、号は梅安。彼はもともと嘉...