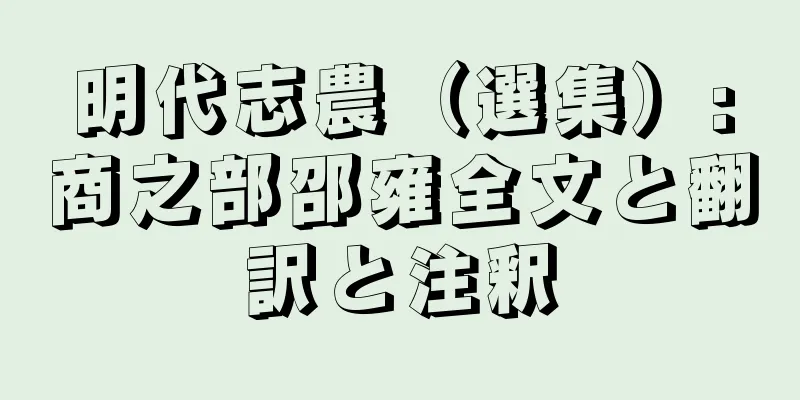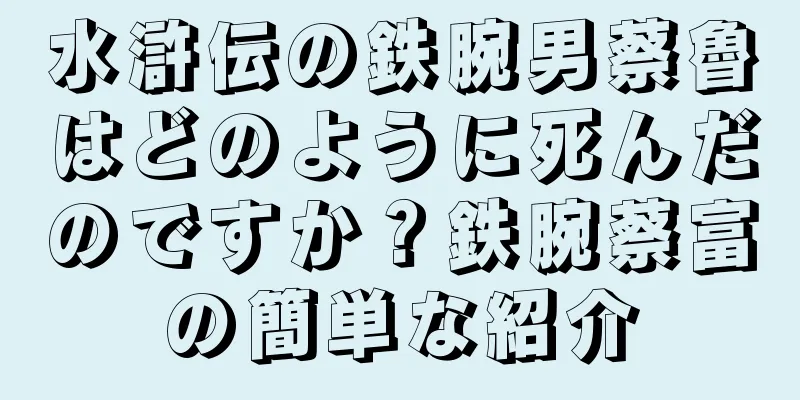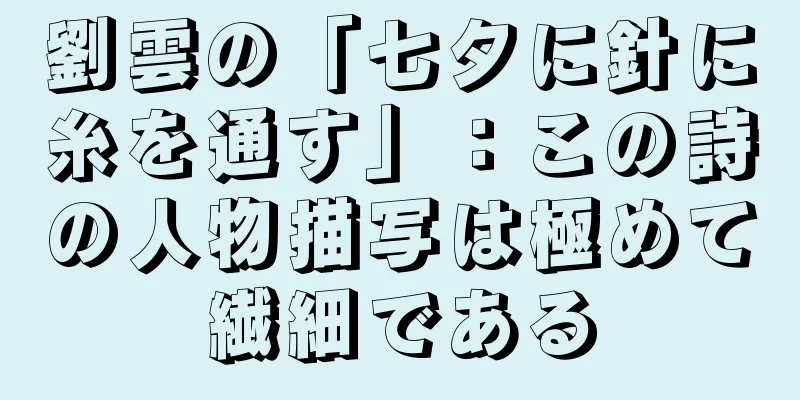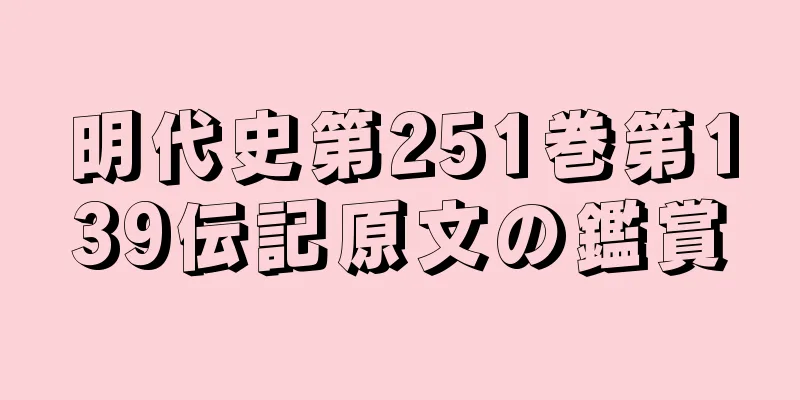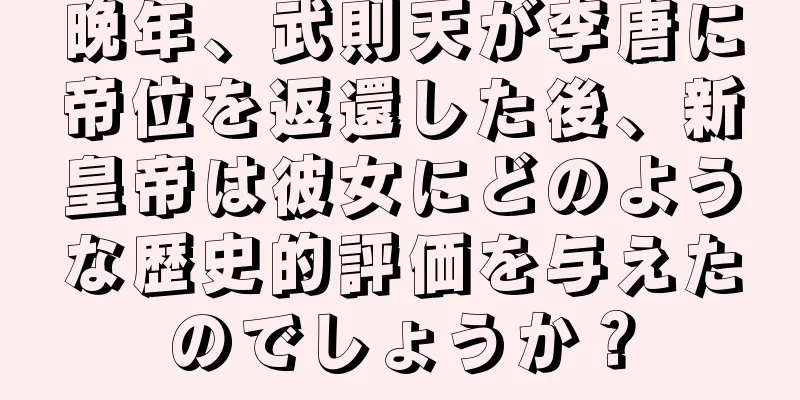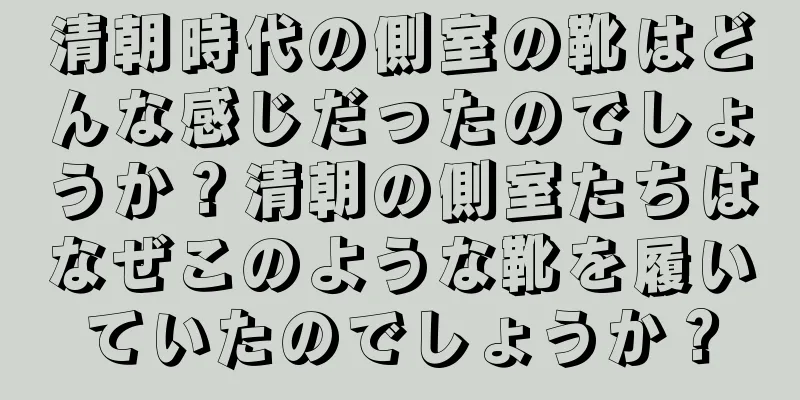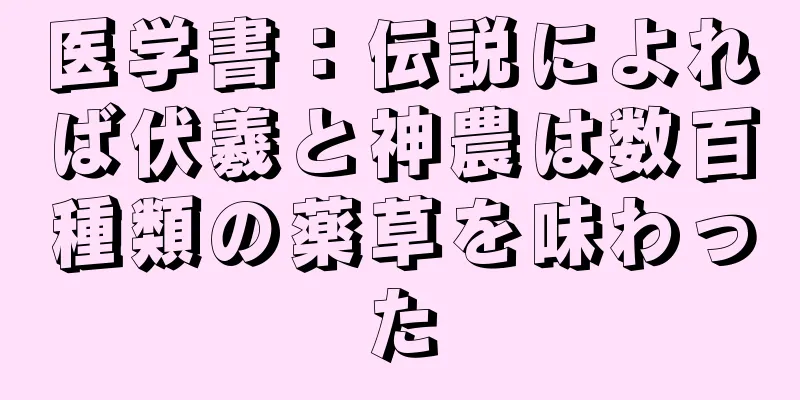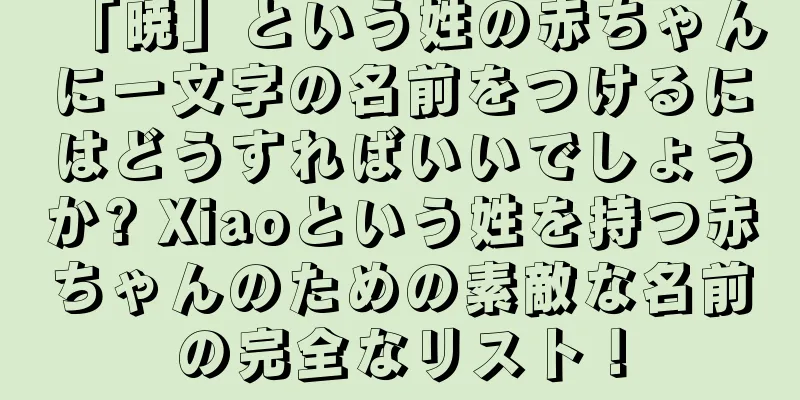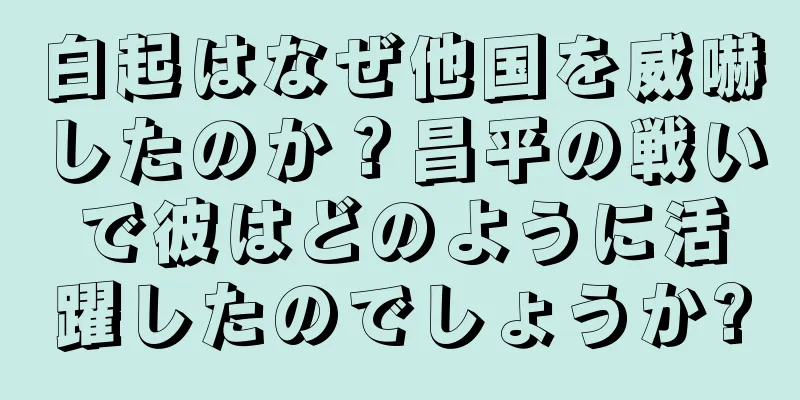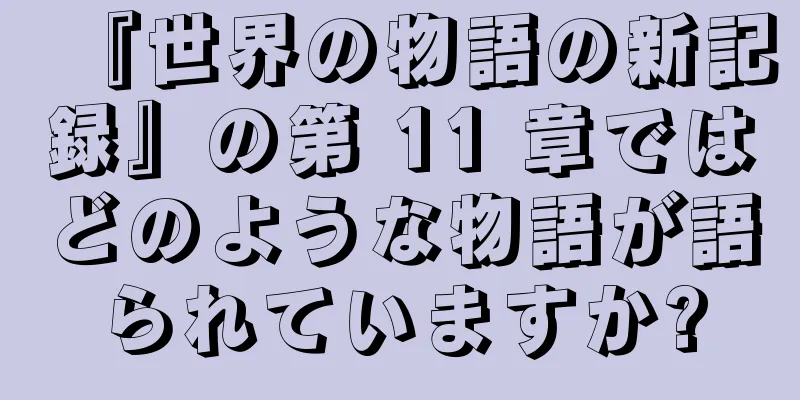清朝はなぜ女性に足を縛ることを厳しく命じたのでしょうか?西太后の纏足禁止令の結果はどうなったのでしょうか?
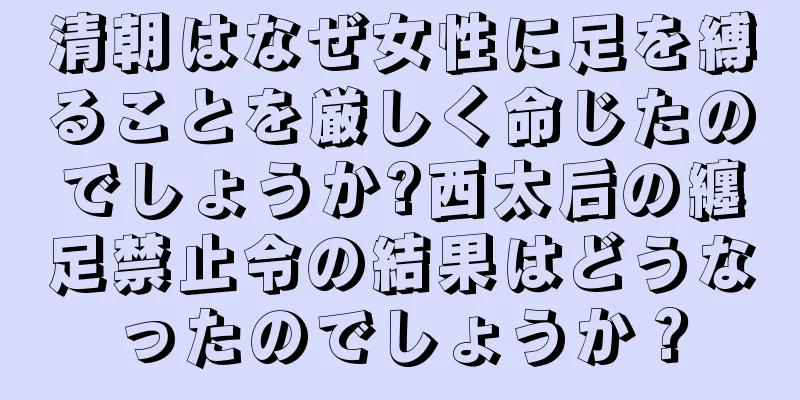
|
本日は、Interesting Historyの編集者が、西太后の纏足禁止令に関するお話をお届けします。皆さんにご理解いただければ幸いです。 多くの人々の目には、西太后は良いことをせず、悪いことばかりする悪いイメージがあるのではないかと思います。しかし、実際の西太后はそうではありません。おそらく、清朝政府がまだ弱すぎたため、人々は彼女にそのような印象を抱いているのでしょう。実際、西太后は良いこともしました。古代のある時代には女性が足を縛る習慣があったことは知られていますが、これは非常に悪い習慣でした。西太后はこのような行為を禁止する命令も出しましたが、西太后が命令を出したとしても、なぜ最終的に完全に禁止されなかったのでしょうか。 三つ編みと纏足は、中国の後進性と無知さの象徴と長い間みなされてきた。一つは男性に関するもので、一つは女性に関するものであり、一つは頭に関するもので、一つは足に関するものであり、一つは500年近い歴史があり、もう一つは1000年以上続いている。ただ、中国では男性はみんな三つ編みをしなくてはならないが、女性は足を縛る必要がない。西太后は足を縛らなかった。 彼女は満州八旗出身だったからです。有名な歴史教授の毛海建は、著書『悲惨な皇帝 咸豊一珠』の中で、中国史上のすべての皇太后の中で、西太后が最も多く、最も劇的な伝説を持っていると述べている。近年の歴史家による詳細な研究により、彼女は歴代王朝の中で最も明確な経歴を持つ皇太后となった。西太后は官僚の家系の出身で、青旗に属していました。清朝時代、八旗の女性は纏足を厳しく禁じられていました。 纏足がいつ始まったかについては諸説あるが、一般的には宋代に流行したと考えられている。しかし、古代中原地方で流行した悪しき風習であったことは確かである。北方の遊牧民である契丹族、女真族、モンゴル族などの少数民族は纏足をしていなかった。 清朝は満州人によって樹立された政権であり、満州人の支配者たちは漢族女性の纏足の習慣に非常に嫌悪感を抱いていた。黄太極は関に入る前に、1638年に「異国の衣服を着たり、髪や足を縛ったりする者は厳重に処罰される」という勅令を出した。「異国」とは明王朝のことだった。 1644年に清軍が峠に入った後、一方では人々に三つ編みを強制し、他方では漢民族の少女たちに纏足をしないように命じた。順治から康熙帝の時代にかけて、清朝政府は女性の纏足を禁じる数々の禁止令を出した。孝荘皇后はかつて「足を縛った女性を宮殿に連れてくる者は斬首せよ」という命令を出した。これは満州族女性に対する最も重い縛足刑罰であった。 清朝初期、髪を束ねることと纏足することは漢民族の大切な伝統であり、人々の心に深く根付いていたため、満州政府が三つ編みを生やし、纏足を廃止するよう命じたことは、漢民族から強い抵抗を受けた。清政府はその後、「頭は残しても髪は残さず、髪は残しても頭は残さず」というスローガンを掲げて、残忍な取り締まりを開始した。強い圧力の下、三つ編みは奨励されたが、纏足の廃止は実現しなかった。 実際、当時清政府は纏足を廃止する法令を何度も発布したが、効果はほとんどなかった。 1668年、左検閲長官の王羲は纏足禁止の解除を求める書簡を書き、康熙帝から許可を得た。清政府は漢人女性が纏足を実践しているという事実を黙認せざるを得なかった。清朝政府の態度も無力感から出たものだった。まず、清軍が峠に入ったばかりで、漢民族の抵抗闘争が相次いでいた。強制的な組紐は彼らを疲れさせ、纏足問題に費やすエネルギーはもうなかった。第二に、女性は性質が弱く、社会的地位も低いため、新政権にとって脅威となることも少なかった。さらに、強制的な組紐は深刻な民族対立を引き起こしていた。多くの漢民族学者は清朝の朝廷に不満を抱いていた。民族紛争緩和の観点から、清朝政府は妥協せざるを得なかった。 西太后は自分では足を縛ることはなく、また、縛ることに対して断固とした反対の姿勢を示しました。清朝末期の改革派は纏足に反対し、康有為らは纏足反対協会を設立して大きな反響を巻き起こした。西太后は改革派を弾圧したが、康有為や梁啓超が主張した纏足反対の旗を掲げ続けた。八カ国連合軍の中国侵攻後、西太后は外国人の力を痛感し、首都に戻ってから一連の改革を実行した。 1902年、西太后は纏足を禁止する勅令を発布した。1905年には別の勅令を発布した。「漢族の女性の多くは纏足をしている。これは長年の慣習であり、万物の調和を害するものである。今後、貴族とその家族は女性たちを優しく説得し、各家庭にこれを知らせ、徐々に古い慣習をなくしていくことを望む。」一時期、全国の役人が応じ、大きな成果が得られた。 しかし、西太后は非常に権力があり絶対的な権威を持っていたにもかかわらず、千年にわたる纏足の伝統は彼女の一言で終わらせることはできませんでした。西太后の無力さを物語る物語があります。 かつて、ある外国大使の妻が西太后との談笑中にこう言った。「清朝の女性は纏足のせいで世界中で笑いものになっています。」西太后はこれを聞いて非常に不快に感じた。当時、ヨーロッパ諸国の女性は皆、ウエストを細く見せるためにコルセットを着用する習慣がありました。これもまた、中国の纏足と同じように、身体に深刻なダメージを与える悪い習慣でした。多くの女性が、過度のコルセット着用により身体の変形に苦しみ、さらには死亡しました。西太后は目の前にいる大使夫人を見ました。彼女は背が高くて力強いのですが、腰がとても細いです。彼女はコルセットをしているに違いないと推測し、尋ねました。「外国人は腰にコルセットをする習慣があると聞きました。ここには外国人がいませんから、女性の方は腰にコルセットを何で巻いているのか見せていただきたいです。」 それを見た彼女は感動してこう言った。「外国人女性はこのような拷問を受け、鉄の棒で腰を縛らなければならない。なんと哀れなことでしょう!」そして彼女に着替えるためのゆったりとした満州族の衣服を渡した。その後数日間、大使の妻は西太后に会いに来なかった。西太后はすぐに人を遣わして調べさせ、大使の妻の体調が優れないことを知った。西太后は誇らしげに言った。「やはり、一度解かれた腰帯を元の形に戻すには時間がかかります。まだ笑われているのですね。苦しんでいるのだと思います!」 実際、足を解放することも一種の苦痛です。なぜなら、足を縛ることで足の骨や腱がねじれているからです。足を解放することは、二度苦しみ、二度罰を受けるようなものです。 1927年に発行された「婦人雑誌」には、次のような話が載っている。足に縛られていた桂英は、留学生と結婚した。進歩的な考えを持つ夫は、救世主のような口調で、彼女に足の縛りを解くように頼んだ。桂英は夫のためにおしゃれな女性になりたかったので、夫の言うことに従った。しかし、足を解く感覚があまりにも不快で、ある時、彼女はひどく痛がった。歴史的伝統を変えるのはとても難しいです! |
<<: 歴史上、どの王朝に「派閥争い」がありましたか?北宋時代の「派閥闘争」の中心人物は誰だったのでしょうか?
>>: 歴史上の「貴族の家系」とはどのようなものだったのでしょうか? 「貴族」はなぜ歴史の舞台から退いたのか?
推薦する
「十二塔」:桂正塔・財宝と食料、そして金銀の損失
『十二塔』は、明代末期から清代初期の作家・劇作家である李毓が章立てで書いた中国語の短編集です。12巻...
漢書第82巻の王尚、石丹、伏羲の伝記原文
王尚は、字を紫微といい、涛県立霧の出身で、後に都陵に移住した。商の武公とその兄弟は、宣帝の叔父である...
宋代の詩の最も美しい60行:宋代の詩から選ばれた有名な行
暗い瞬間、一日中沈黙が続いたが、その後私は階下に降りていった。 —劉勇「屈雨観」時間が経っても、悲し...
李商胤は李和、李白とともに「三里」の一人として知られています。李商胤にはどんな美しい詩がありますか?
李商隠は唐代末期の有名な詩人です。李白、杜甫、王維などの巨匠が詩芸を比類のない高みにまで高めた後、李...
石公の事件 第6章:石公の銀事件の裁判、生姜と酒で肺を腐らせるという決断
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
朱后昭は明朝の孝宗皇帝朱有堂の息子です。なぜ彼の皇太子としての地位は揺るぎないものだったのでしょうか?
皇太子は皇位継承者であり、皇帝の後継者でもあるため、皇帝は当然皇太子に対して非常に高い要求と期待を抱...
『紅楼夢』では、賈宝玉と青文が長い間一緒に暮らしていましたが、二人の間に親密な行為はありましたか?
『紅楼夢』では、清文と賈宝玉は絶対に性的関係を持っていません。彼女は腐敗した者たちと付き合うことを拒...
『梁書』には海南島のどの国が記されていますか?特徴は何ですか?
梁は、中国史上、南北朝時代に南朝の第三王朝として存在した謎の王朝です。蕭延が斉に代わって皇帝になりま...
「Wild Ambition」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】西丘陵の白い雪の下には三つの都市が駐屯し、南浦の清流には数千里に渡る橋が架けられている...
グリーンピオニー完全ストーリー第50章:羅洪勲の敵
『青牡丹全話』は清代に書かれた長編の侠道小説で、『紅壁元』、『四王亭全話』、『龍潭宝羅奇書』、『青牡...
ニームの花について記述した歴史上の詩にはどのようなものがありますか?詩人はニームの花をどのように称賛しているでしょうか?
ニームの花を描写した詩は歴史上数多く存在します。Interesting History の次の編集者...
『星香子・丹陽拾遺』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
星香子・丹陽が古代の物語を伝える寿司江村と手をつないで、スカートには梅の花と雪が舞っています。愛は無...
『紅楼夢』で賈宝玉はなぜ西人を蹴ったのですか?
『紅楼夢』の中で、宝玉は「女性は水でできている」と言ったことがあります。これは人々に清々しい気持ちを...
小白龍は唐僧の弟子ですか?聖典を求めることができる人数に制限はありますか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
『新世界物語』第 12 章「政治問題」はどのような真実を表現していますか。
『世碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『世碩心於・政事・第12号』に表現さ...