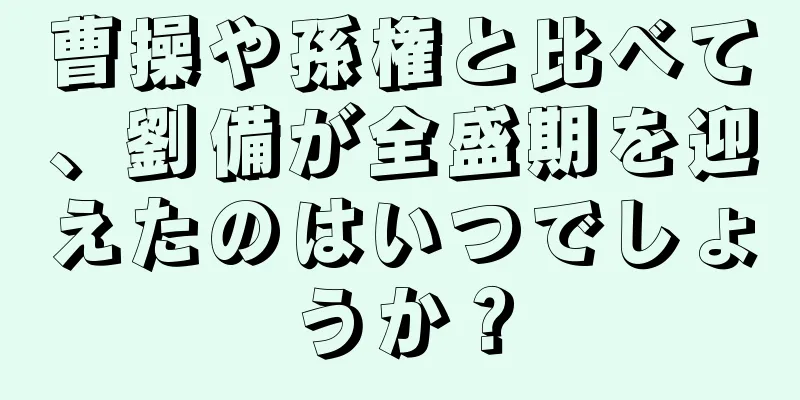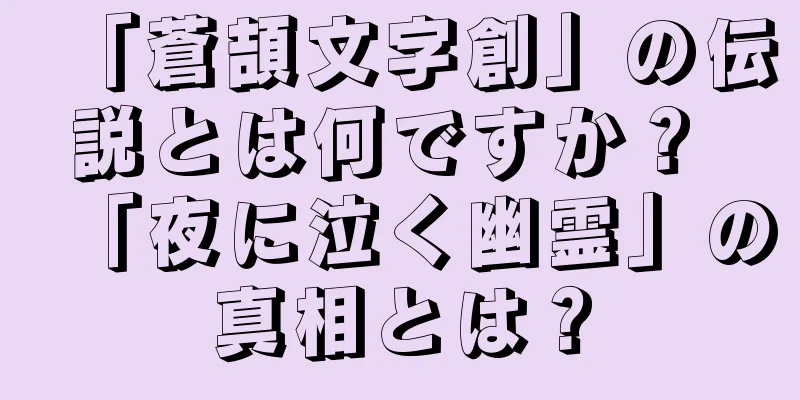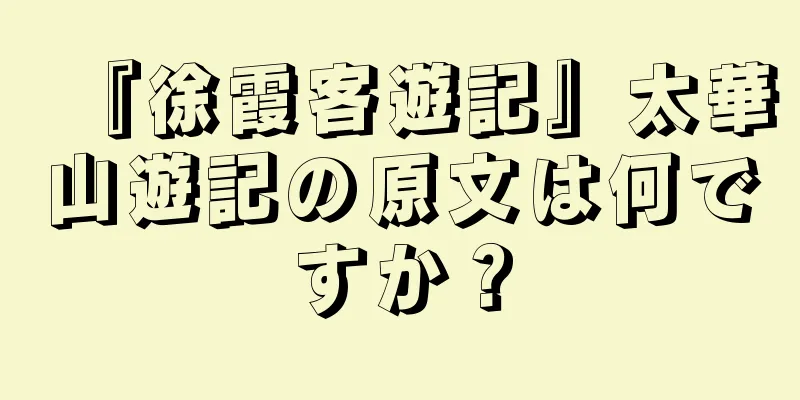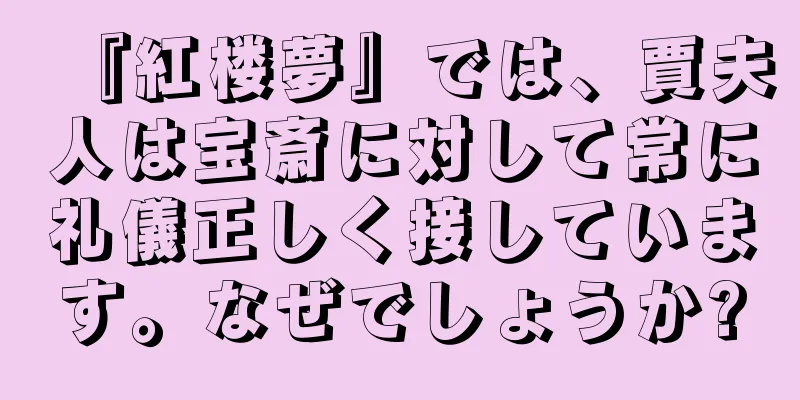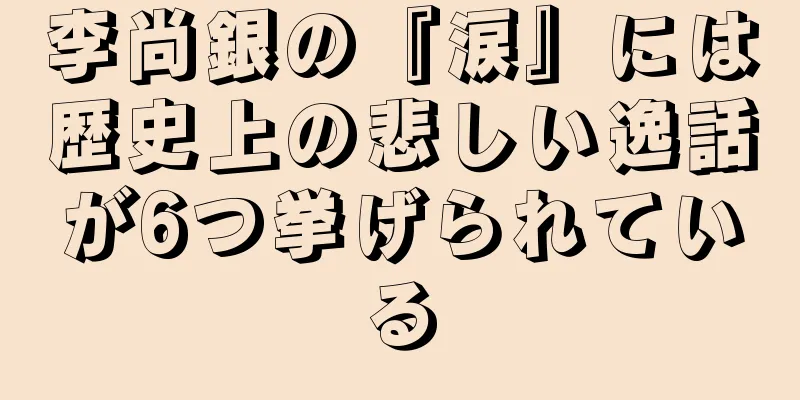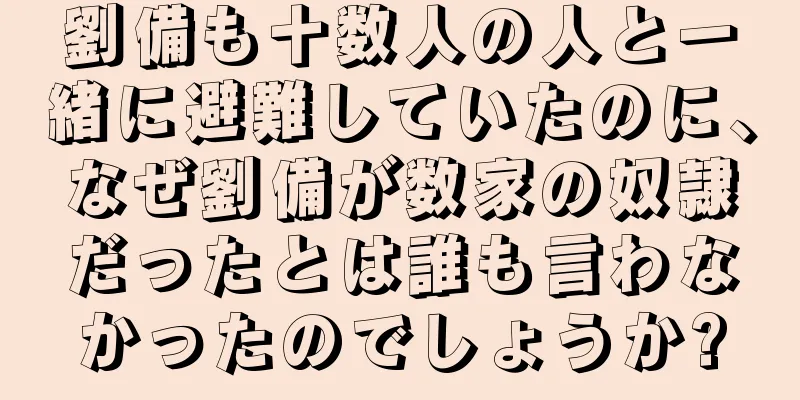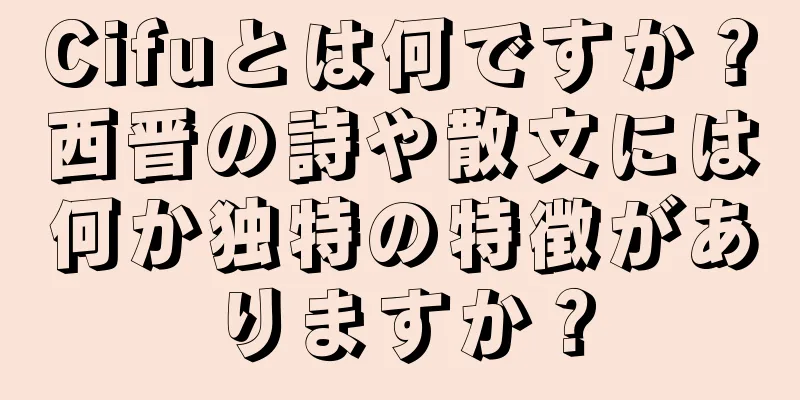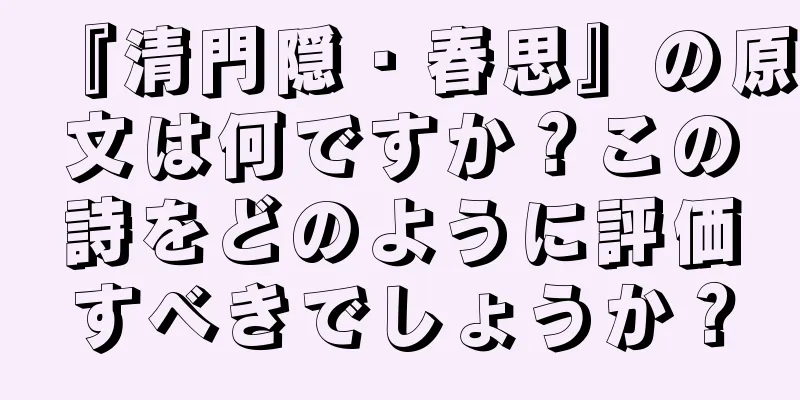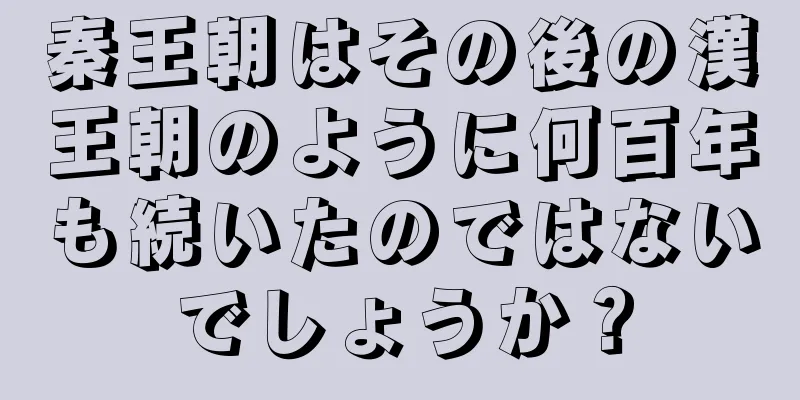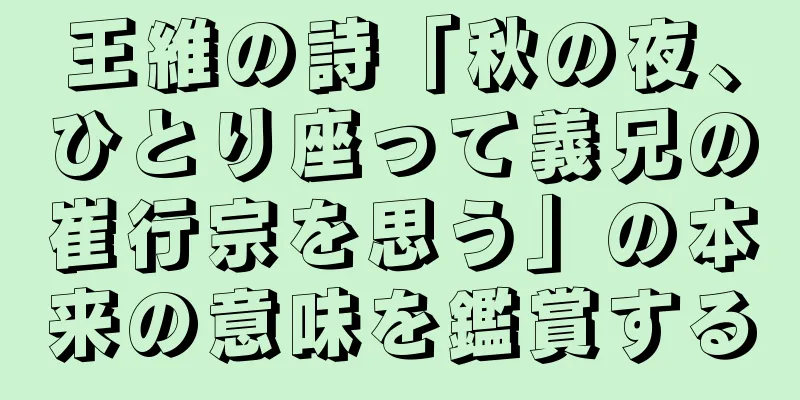東漢から西晋までの人口調査?人口減少が最も深刻だったのはいつですか?
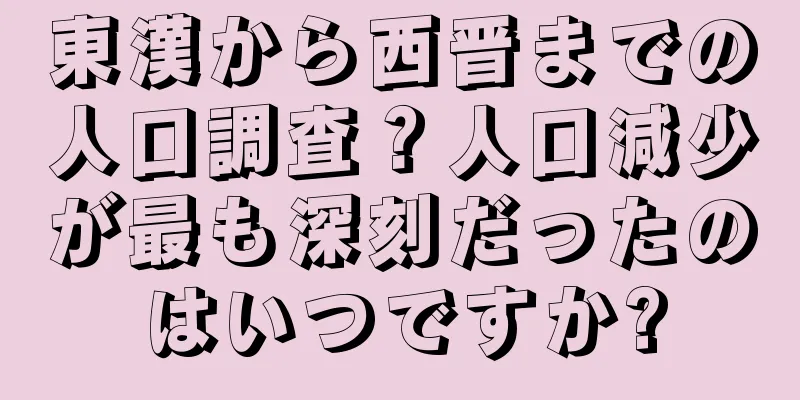
|
今日、Interesting History の編集者が皆さんのために用意したのは、東漢から西晋までの人口調査です。興味のある方はぜひご覧ください。 後漢末期、黄巾の乱をきっかけに国全体が混乱し、何年も戦争が続きました。激動の時代から私たちがよく注目するのは、軍略や陰謀、そして数え切れないほどの名場面です。しかし、歴史の一時期において、社会の最も基本的な単位である「人々」についてさらに深く探究するならば、東漢末期から西晋初頭にかけての人口問題に注目しなければなりません。人口問題を理解することで、当時の人口の増減を理解し、人口の増減の理由を分析し、その時代における実際の状況を理解することができます。 東漢と西晋の人口調査データ 漢の光武帝の中元2年(57年)、東漢は人口調査を実施した。当時、国内には4,279,634世帯、総人口21,007,820人が住んでいた。桓帝の治世中の永寿3年(157年)の人口調査によると、国内には16,707,960世帯、56,486,856人の人々がいた。東漢の時代は、生産性の向上や領土の拡大など、さまざまな政策によって、世帯数は4倍近く、人口は2倍以上に増加したようです。学者の研究によると、永寿3年の人口を基準にすると、有力地主に占領または保護されていた大量の従者、一族、客人、家臣、奴隷、その他、漢地域に移住した他の民族はほとんど戸籍統計に含まれておらず、そのため、データから東漢のピーク時の人口は6500万人であったことがわかります。 次のデータセットを見てみましょう。晋の太康元年(280年)の人口調査データによると、国内の世帯数は2,459,840(東呉の530,000を含む)、人口は16,163,863人(東呉の2,562,000を含む)に過ぎなかった。東漢永寿三年のデータによれば、世帯数は西晋の約6.7倍、人口は西晋の約3.4倍であった。 もちろん、中国は西晋初期にほぼ百年にわたる戦争を経験していたため、貴族の家に保護された小作人や家臣、また定住世帯、軍人世帯、官人世帯、逃亡世帯、行方不明世帯、潜伏世帯、漢地域に住む少数民族など、戸籍統計に含まれない人々もいた。そのため、学者たちは西晋の280年の国の人口は約3000万人だったと推定しています。 曹薇人口調査データと計算 実際、魏の最後の皇帝である曹桓の治世中、魏が蜀を征服した後、景元4年(263年)に人口調査が行われました。当時、魏国+蜀漢地域には90万世帯以上、総人口は500万人以上という結論に達しました。当時は、魏と蜀漢の戦争が続いていたため、民衆の死や戸籍の隠蔽が深刻だったようです。 『後漢書』によれば、景元4年、魏・蜀漢には合計943,423戸、5,372,891人(5,372,881人という説もある)がいた。 『通典世乎典』によれば、曹桓時代の人口調査では、蜀漢を除く魏国の世帯数は663,423、人口は合計4,432,881人であった。 『同店世火店』のデータから『徐漢書』のデータを引くと、西暦263年の蜀漢には合計28万世帯、940,010人(または94万人)の人口がいたことになります。魏が蜀漢を滅ぼした後、蜀漢の人口は推定値か、意図的に切り上げられたようです。あまり正確ではないかもしれませんが、歴史書に記録されている人口データの唯一の根拠です。 蜀漢の人口については別の言い伝えもあり、『三国志』には108万2千人という記録がある。 人口減少が最も深刻だった時期 一部の学者は、東漢から西晋にかけてのこのような大規模な人口減少は、主に漢の献帝から三国時代初期にかけて起こったと指摘している。 東漢末期の状況については、以下の史料から概要を知ることができます。 1: 『張繡伝』によれば、張繡は曹操に従って袁譚を討った後(西暦205年)、その所領は2,000戸にまで増加した。しかし、当時、全国の人口は急激に減少し、10軒のうち9軒は空き家となり(10軒のうち1軒はまだ空き家だった)、最も大きな領地を持っていた張秀を除いて、多くの将軍の領地は1,000未満であった。 2:「後漢書」によれば、漢の献帝の時代には皇帝が追放され、民の死体が荒野に晒されたこともあった。世界中の盗賊間の抗争は30年以上続いた。曹丕が王位に就いた頃には、東漢時代の人口ピーク時と比べると、生き残ったのは一万人に一人だけだった。 (データは歪んでおり、当時の急激な人口減少の傾向を理解するためにのみ使用されています) 3:「晋書・善導伝」によれば、初平元年から建安25年(延康元年)まで、計30年間にわたり、民衆は流浪し、ほとんどが死亡した。この時代は極めて残酷で混乱した時代であった。 上記の歴史資料は、当時のものから抽出すると、すべて建安時代を指し示しています。実際、その期間の急激な人口減少には主に3つの理由がありました。 理由1: 殺害 『三国志 董卓伝』には、二休会活動中に董卓が活動会場で大規模な殺人を行ったと記されている。 『三国志荀攸伝』には董卓の都での混乱以来、人々が東へ移住し、その多くが彭城一帯に住むようになったと記録されている。数年後、曹操は陶謙を攻撃し、彭城などで大規模な虐殺を行った。死体はスラバヤ川に投げ込まれ、川は干上がりました。虐殺された街は廃墟となり、通りを歩く人は誰もいませんでした。 『三国志 武帝紀』の裴の「献帝日常記」は曹操の追悼文を引用し、官渡の戦いで曹操が淳于瓊を含む8人の将軍を殺害し、袁紹が逃亡し、7万以上の首が斬首され、数え切れないほどの物資と財産が押収されたことを指摘している。 もちろん、これらは氷山の一角に過ぎません。これらの点は主に、後漢時代の殺人の3つの形態を説明するために要約されています。活動や集会を利用して人々を殺害し、都市を虐殺し、軍事行動に従事する。 曹植はかつて『白馬篇』の中で次のような詩を書いた。 鋭い刃の先に身を投げて、どうやって自分の命を救えるでしょうか? 両親を大切にしないのに、どうして子供や妻を大切にできるでしょうか? 戦士として登録されると、個人的な利益を考慮することはできなくなります。 国のために命を捧げ、死を故郷への帰還とみなせ! 理由2: 空腹 『三国志 司馬朗伝』には、曹操と呂布が濮陽で膠着状態にあったとき、司馬朗が家族を連れて故郷に帰ったことが記されている。その年、大飢饉が発生し、民衆の間で人食いの悲劇さえ起こった。 『三国志 董卓伝』には、もともと三府一帯には数十万戸の世帯があったが、李傳らが兵士に食糧の略奪を許したため、民の食糧配給が奪われたと記されている。この2年間、人々は食べるものが無く、人食いに頼らざるを得ませんでした。 『三国志 袁術伝』には、袁紹が皇帝を名乗った後、傲慢で贅沢な生活を送っていたが、兵士や民間人は裸のまま放置されていたと記されている。もともと繁栄していた江淮の地域には食べ物さえなく、「人食い」が蔓延した。 『三国志陸羽伝』には、袁紹と公孫瓚が戦っていたとき、長年の戦争により幽州と冀州地方で深刻な飢饉が発生したと記録されています。 『三国志 夏侯淵伝』には、初期には兗州と豫州が混乱していたと記されている。国内の深刻な食糧不足のため、夏侯淵は末息子を餓死させ、亡くなった兄の一人娘を生き延びさせることを選んだ。 『三国志 武帝紀』には『衛略』が引用されており、王忠が幼い頃、三府の混乱で飢えに苦しみ、人肉を食べて生き延びたと記されている。 『三国志・顔文伝』の『衛洛勇士伝』から引用された内容から、興平年間に数十人からなる人を殺してその肉を食べた犯罪集団が現れたことがわかります。 実際、飢饉は建安時代だけでなく、三国時代にも国家にとって大きな問題でした。太和2年、曹植は魏の飢饉を目の当たりにして『喜雨詩』を書いた。 空はなんと広大で、あらゆる生き物を包み込み、育んでいるのでしょう。 それを放棄すれば枯れてしまうが、利益を得ると繁栄する。 青雲は北から進軍し、虞叔は南西へ進軍した。 真夜中に雨が降り、長い雷鳴が私の中庭を取り囲みました。 肥沃な土壌には良質の種が満ちており、秋には豊かな収穫が得られるでしょう。 理由3:主にペストによって引き起こされる病気 『三国志 司馬朗伝』には、建安22年に司馬朗が夏侯惇、臥覇らを従えて居巣地方に赴いたと記録されている。当時、軍隊で伝染病が流行していました。司馬朗は自ら下町に赴き、兵士たちに薬を届けて検査していたため、感染してしまいました。病気にかかった後、司馬朗は47歳で亡くなりました。 『三国志 王燕伝』には、建安21年に王燕が軍に加わって東呉を攻撃したと記録されている。彼は建安22年の春、41歳で病死した。また、建安17年に阮羽が亡くなり、建安22年には徐干、陳林、劉震らが疫病で亡くなった。 建安22年に発生したこの大疫病は、『三国志 関寧伝』の注釈にも記載されており、「多くの人が亡くなり、郡は彼らを埋葬するよう命じた」と記録されている。 曹植はかつて中国全土に蔓延した疫病について次のような文章を書いている。「建安22年、疫病が蔓延した。どの家にもゾンビのような痛みがあり、どの部屋にも泣き叫ぶ悲しみがあった。家族全員で亡くなった人もいれば、一族全員を失った人もいた。疫病は幽霊や神が引き起こしたものだと考える者もいた。この災難に遭ったのは、すべて粗末な服を着て山菜を食べ、茅葺き屋根の家に住む人々だった。宮殿に住み、食べ物を高く、ミンクの毛皮や寝具を厚く敷く人々は、そのような人は少なかった!陰陽が狂い、寒さや暑さが季節外れだったため、疫病が発生したのだ。愚かな人々は魔除けのお札を掛けたが、これもまたばかげている。」 最も恐ろしいのは、「すべての家族がゾンビの痛みを抱え、すべての部屋に涙の悲しみがある。殺される家族もあれば、全滅する家族もある」ということだ。 味わうのです、じっくりと味わうのです。 東漢末期の人口急減の「余波」 三国時代、最も人口が多く、最も強大な力を持っていた国は魏でした。三国時代は漢末期に比べて人口が増減したと推測できるものの、時折起こる戦争や「人口負債」により、増加率は依然として低かった。明の魏皇帝、曹叡の治世中の公式文書から貴重な情報を得ることができます。 『三国志』陳群の伝記には、清隆年間に曹叡が大規模な宮殿を建てたことが記されている。陳群は碑文の中で、我が国は今、戦乱の余波にあり、人口はまだ比較的少ないと指摘し、我が国の国土は漢の文帝・景帝の時代の大県ほどではないと指摘した。 『三国志』の蒋済伝にも同様の記録がある。荊楚の時代に曹叡は強制的に人を徴用して労働させたため、民衆の反感を買った。蒋済は追悼文の中で、現在国内には十二の州があるが、その数は漢代の大県の人口ほど多くはない、と指摘している。 『三国志 杜書伝』にも、魏は今や10か国に領土を持つが、つい最近まで混乱していた国を占領したと記されている。国の総人口を計算すると、当時の1か国の人口にも満たない。 質問:人口の急激な減少は後遺症を残すでしょう。人口動態の影響を軽減し、悲劇の再発を防ぐことができる要因は何でしょうか? 著者の答え: 戦争を止め、食料と衣服を提供し、医療を提供する。 |
<<: なぜ中国人は「適応」が得意なのか?中国の「柔軟性の文化」はどのようにして生まれたのでしょうか?
>>: 魏晋の時代に美男子が出現したと言われています。魏晋の時代に美男が流行ったのはなぜでしょうか?
推薦する
古代の埋葬制度はどのようなものだったのでしょうか?私たちはなぜ若い男の子や女の子を死者と一緒に埋葬することを選んだのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が古代の埋葬制度がどのようなものであったかをお...
李白は『廬山観瀑図』でどのような芸術技法を用いたのでしょうか?
李白は「廬山の滝を見る」でどのような芸術技法を使ったのでしょうか?この詩は李白が50歳くらいの頃、廬...
『緑氏春秋・不狗論』の「不狗」は何と書きますか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『禄氏春秋』の「武狗論」は何を書いているのか? どのように理解するのか? これは特に多くの読者が知り...
「漁師の誇り:過去30年間穴はなかった」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
漁師の誇り:30年間穴なし黄庭堅(宋代)私は30年間視力を失っており、視力が回復した今でもまだ混乱し...
趙端礼の『水龍音・月詠』:読むと三度ため息が出る、素晴らしい詩と言える
趙端礼(1046年 - 1113年)は、袁礼とも呼ばれ、字は慈英、汶州清豊県(現在の河南省濮陽市)の...
士公の事件第214章:いじめっ子が主人を奪って失い、賢者は密かに指名手配犯を救出しようと企む
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
米芳と傅士人は二人とも関羽を裏切った。後世のほとんどの人がなぜ米芳を非難したのか?
219年は三国志の名将関羽にとって最も栄華を極めた年であった。この年、主君の劉備は自らを漢中王と称し...
二十四史第114巻明史第二伝
◎ 妾 2 ○孝宗皇帝の張小康皇后 武宗皇帝の夏小静皇后 世宗皇帝の陳小潔皇后 張飛皇后 小烈芳皇后...
胡家将軍第19章:桃花潭は怪物を捕らえるという約束を守れるか?新唐国の王女は夫を探している
『胡氏将軍伝』は清代の小説で、『胡氏全伝』、『胡氏子孫全伝』、『紫金鞭物語』、『金鞭』とも呼ばれてい...
姓「張」の2文字の名前の選び方は? 2020年、姓が張の赤ちゃんのベストセレクション!
今日は、Interesting Historyの編集者が、姓「張」の2文字の名前の選び方を教えてくれ...
『紅楼夢』で賈元春が死んだ原因は何ですか?賈家と関係があるのでしょうか?
賈元春は『紅楼夢』の中では最も登場回数が少ない人物ですが、『紅楼夢』の中で最も地位の高い女性です。次...
司馬懿による権力掌握は曹芳の治世中に起こったのに、なぜ曹丕のせいだと言われるのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「胡家将軍」の主人公は誰ですか?どのように鑑賞しますか?
『胡氏将軍伝』は清代の小説で、『胡氏全伝』、『胡氏子孫全伝』、『紫金鞭物語』、『金鞭』とも呼ばれてい...
太平広記・巻105・報復・張嘉有の原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
『紅楼夢』で薛宝才は王希峰をどう呼びましたか?彼女はなぜ馮夜頭と呼ばれるのですか?
『紅楼夢』の登場人物間の複雑な関係の中で、王希峰と薛宝才は血縁関係の面で非常に近い。皆さんも聞いたこ...