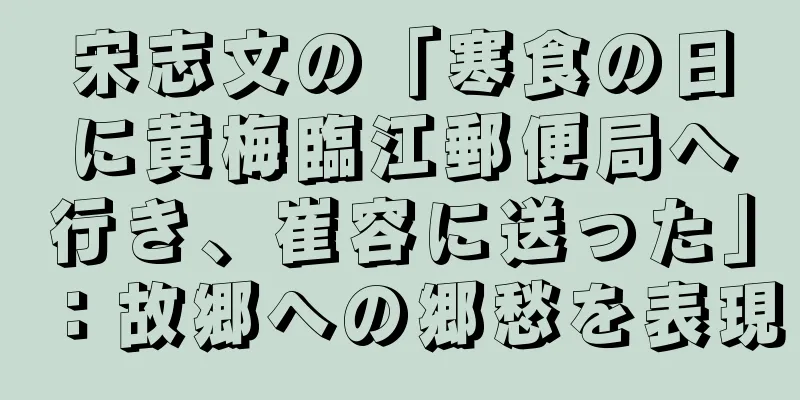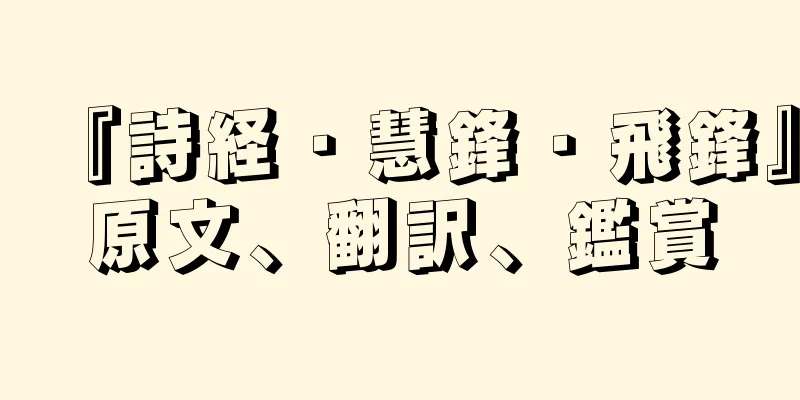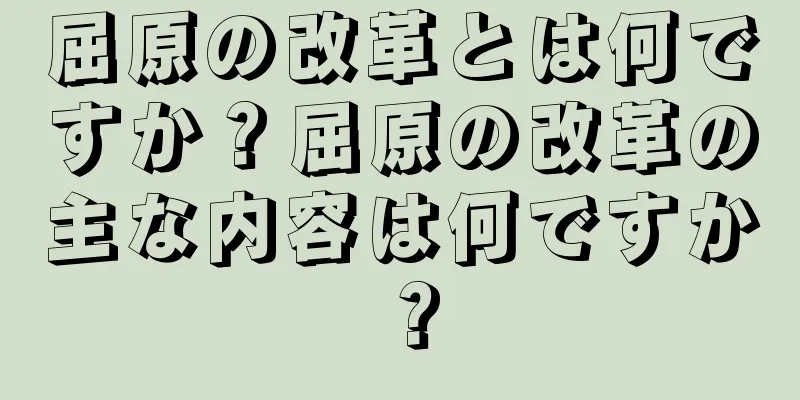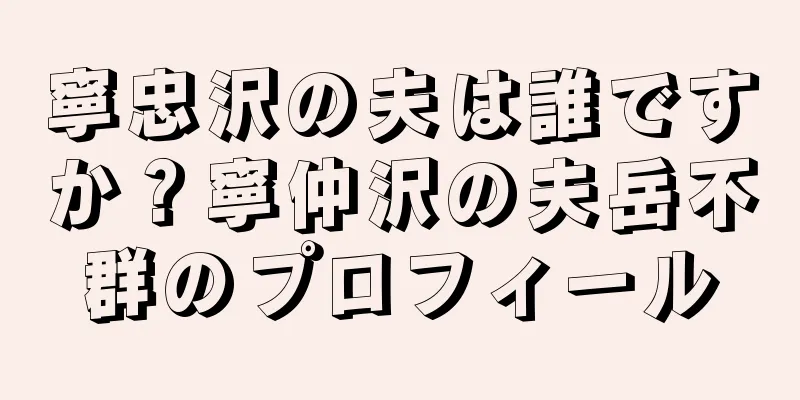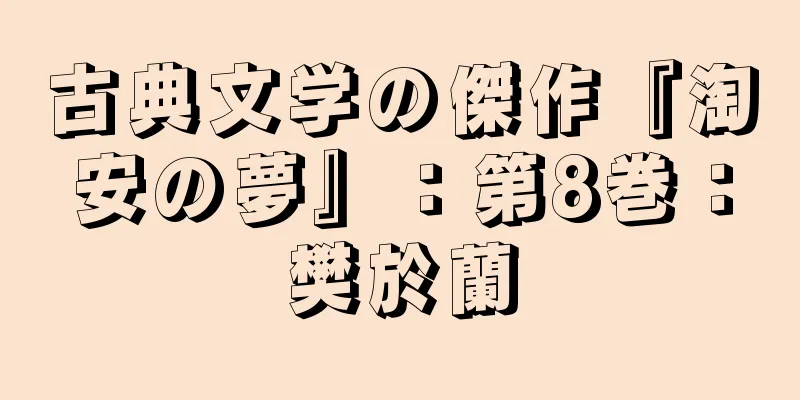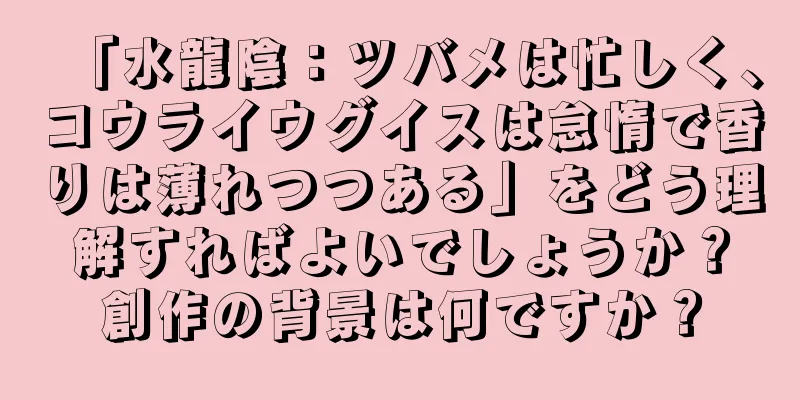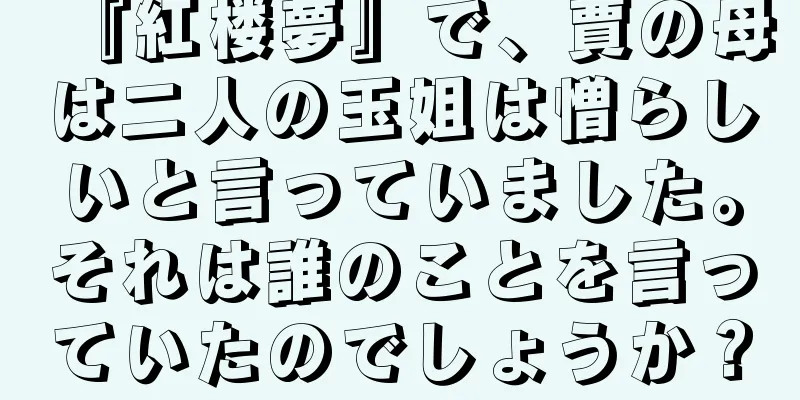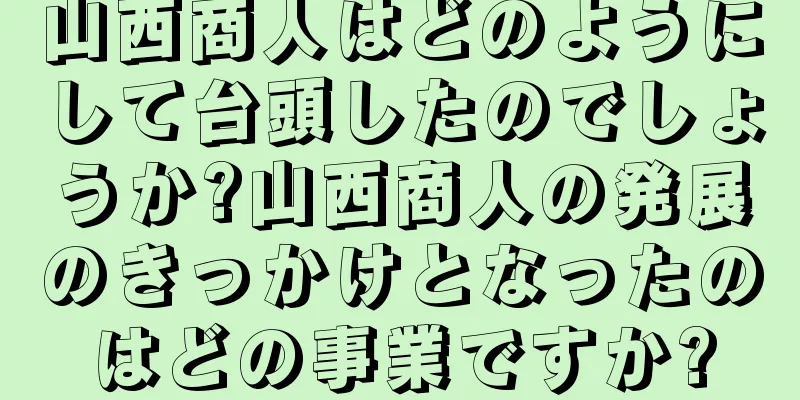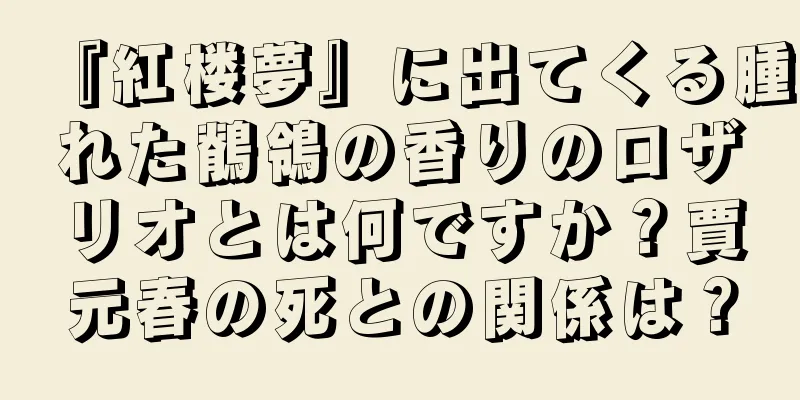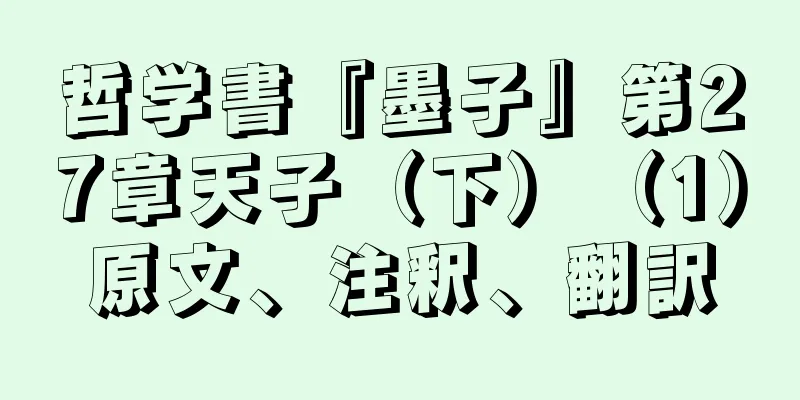ワインの神とワインの祖先は誰ですか?ワインを作ったのは誰ですか?
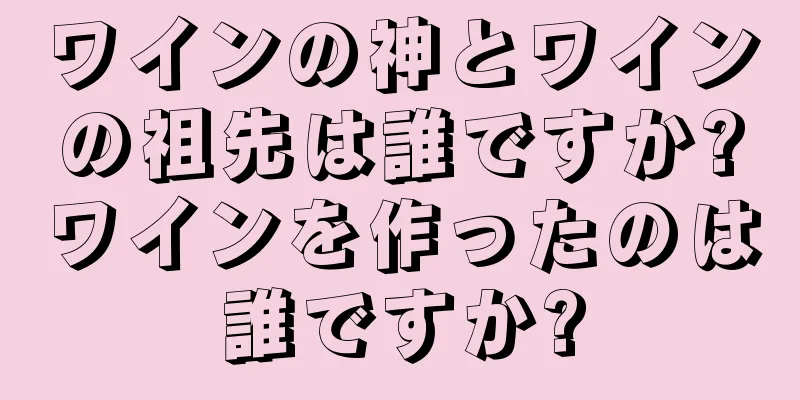
|
今日は、Interesting History の編集者が「ワイン」を作ったのは誰かを教えてくれます。興味のある読者は編集者をフォローして見てください。 諺にもあるように、「良い友達に出会ったら、一杯飲んでも足りない」のです。 中国ではワインには長い歴史があり、今では生活に欠かせないものとなっています。人々は、ビジネスを話し合うとき、結婚するとき、お祭りを祝うとき、お互いにコミュニケーションをとるときなどにワインを飲みます。ワインの役割が非常に重要であるのに、ワインの本当の作り手は誰なのでしょうか? 現在では、杜康が酒を発明し、後世の人々から酒の神として崇められたという言い伝えが広く流布している。 杜康の生涯には2つのバージョンがある。 一説には黄帝時代の大臣であったとも言われています。伝説によれば、当時は農耕文明が発達し、食べ物が余りすぎていたため、良い保存方法がなかったため、食べ物を洞窟に保管していたそうです。しかし、洞窟に貯蔵された食料は湿気により腐ってしまうため、食料を担当する役人として彼はこの問題に頭を悩ませ、あらゆる方法で貯蔵方法を探しました。ある日、杜康は木の穴を見つけ、そこに食べ物を入れようとしました。しばらくして、杜康がもう一度確認してみると、木の穴から液体が染み出ているのを見つけました。彼は勇気を出してそれを味見し、おいしいと感じたので、部族に持ち帰ってみんなに食べてもらいました。このようにして、杜康はワインの製法を発見し、彼の作ったワインは高粱酒と呼ばれるようになりました。 もう一つの説は、杜康は夏王朝の君主であり、夏斉(別名邵康)の孫であるというものです。邵康の叔父である太康は、放蕩と不道徳のため、后羿に国を奪われました。太康は亡命生活を始め、歴史上「太康の国喪失」として知られています。太康の死後、后羿は太康の弟である鍾康を傀儡として君主としました。少康は父が殺された後、虞国に逃げて酒を醸造し、その後同姓の部族や夏王朝の他の大臣を団結させて国を復興させました。これは歴史上「少康の復興」として知られています。私はこの意見に同意します。 ワインの祖先は夏王朝の官僚であった 酒の祖先は五帝の末裔である易帝と呼ばれた。易迪は中国で最初の酒造家と言われており、彼の酒造業は『禄氏春秋』と『戦国兵法』の両方に記録されています。易迪は女性でした。彼女は酒を造って夏羽に味見させました。夏羽はそれを味見した後、「将来、酒のせいで国を滅ぼす者が出てくるだろう」と言いました。夏羽は易迪と距離を置き始め、酒のせいで国を滅ぼしたくないという思いから、自分自身に「禁酒令」を発令しました。易帝の酒は「老」と呼ばれ、現在四川省では「老盒」と呼ばれています。時代の流れから考えると、イーディこそがワインの真の創始者だと思います。 |
<<: 「秦と晋の友情」という歴史的な暗示とは何ですか?淮英と文英の正体は何ですか?
>>: 青島は済南よりも有名ですが、なぜ済南が山東省の首都なのでしょうか?
推薦する
デスワームは本当に存在するのか?目撃証言がなぜこんなにも似ているのでしょうか?
モンゴルのゴビ砂漠には、死の虫のようなものがいると言われています。この死の虫は本当に存在するのでしょ...
古代詩の鑑賞:詩歌集:木を伐る:木こりのチャリンという音と鳥のさえずり
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
『梁書』に記されている王冀とはどのような人物でしょうか?王冀の伝記の詳細な説明
南北朝時代の梁朝の歴史を記した『梁書』には、6巻の史書と50巻の伝記が含まれているが、表や記録はない...
劉備が廃位された後、彼の母である何太后と唐妃はどうなったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
トゥ文化 トゥ語と文字の歴史は何ですか?
トゥ族は独自の国語を持っており、それは「チャハン・モンゴル語」とも呼ばれ、アルタイ語族のモンゴル語族...
李白の「楊潘児」の美しさとは何でしょうか?博山炉の沈香が燃え、二重の煙が紫色の雲に上がる
李白の『楊潘児』の美しさとは何でしょうか?これは多くの読者が関心を持っている問題です。次に、興味深い...
歴史上の牛軀如月とは誰ですか? 嘉慶帝の側室の簡単な紹介
牛軀緑月の紹介名前: 牛軼如月夫:嘉慶帝妹:牛軼璜万秀息子:艾新儒羅面宇職業: 妾タイトル: ル・フ...
『世界物語新説 賞賛と報奨』第 112 話の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの著名人の言行や逸話を記録しています。では、...
「天家慈」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
農民の詩袁真(唐代)牛のひずめがカチャカチャと鳴り、畑は乾いていて、乾いた地面が牛のひずめをカチャカ...
太平広記・巻39・仙人・劉演をどのように理解しますか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
Liという名前の女の子にぴったりな名前は何でしょうか?エレガントで優美な女の子の名前を厳選しました!
今日は、Interesting Historyの編集者が女の子の名前についての記事をお届けします。ぜ...
荀夢邊居第五巻:マイクロ原本鑑賞と注釈
司守謙作「子供のための片居」、明代街は高くそびえ立ち、宮殿は雄大です。楚の客は蘭を縫い、襄妃は竹のた...
『新説世界物語』第112章「讃美」には誰の言葉や行いが記録されているのでしょうか?
『十朔新于』は、魏晋の逸話小説の集大成です。では、『十朔新于・讃・112』には誰の言葉や行いが記録さ...
「ザクロ」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ザクロ李尚閔(唐代)ザクロの枝は優雅で、ザクロの果実は豊富で、ザクロの皮は軽くて透明で、ザクロの種は...
中国三大鬼祭りの一つ、漢夷節の由来。漢夷節とは?
旧暦の10月1日は「十月潮」と呼ばれます。私の国では、昔から、親孝行をし、自分のルーツを忘れないよう...