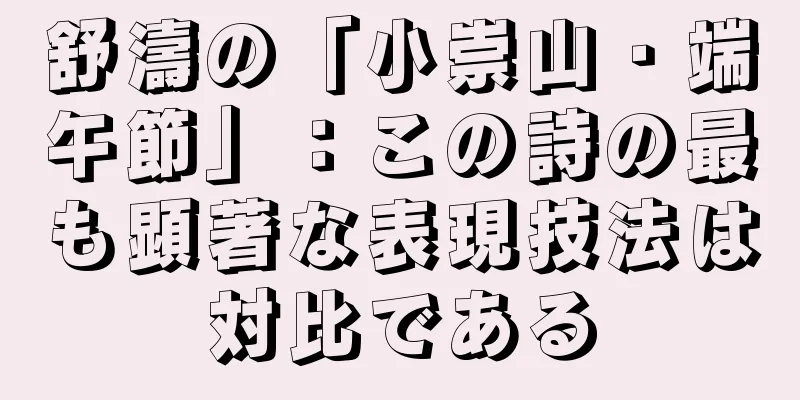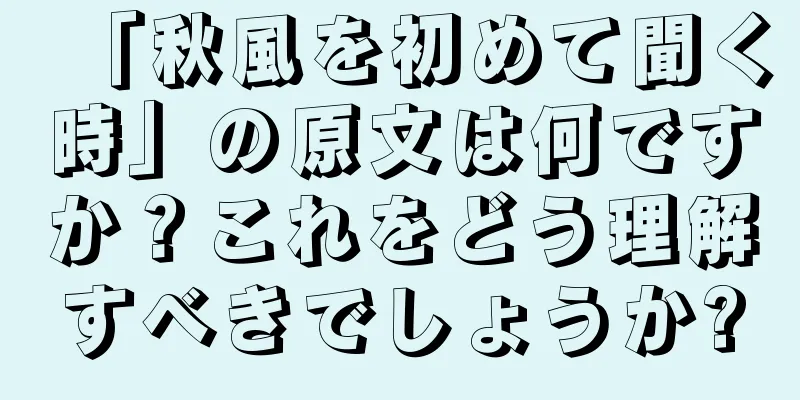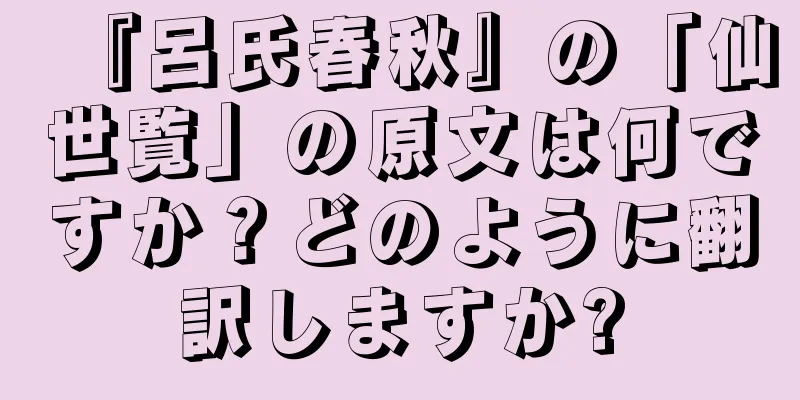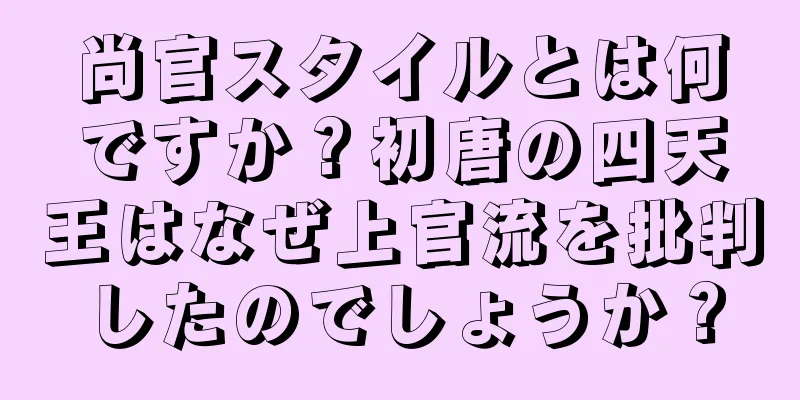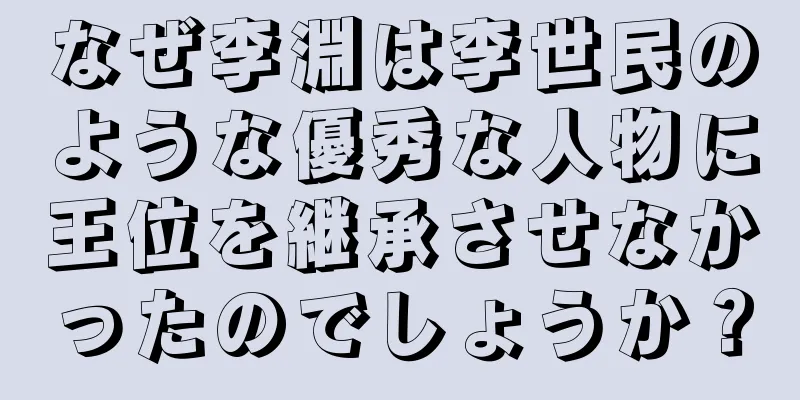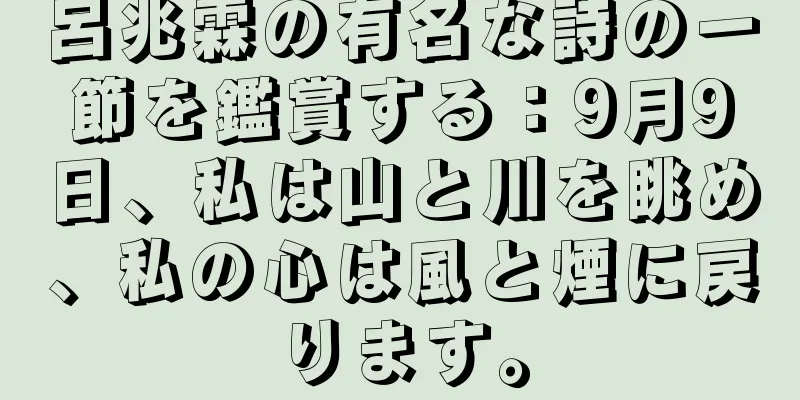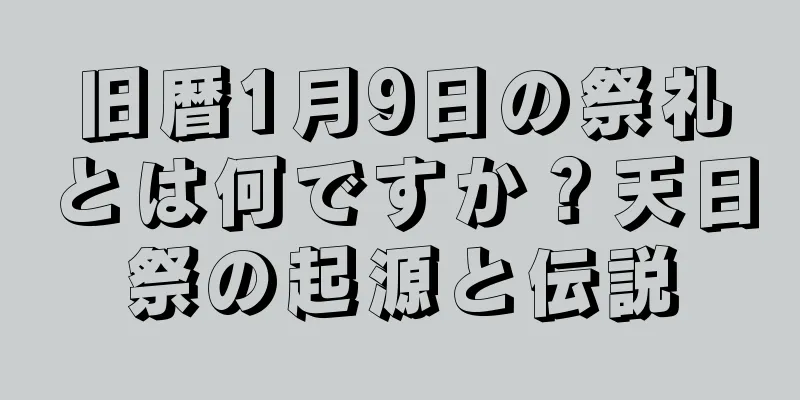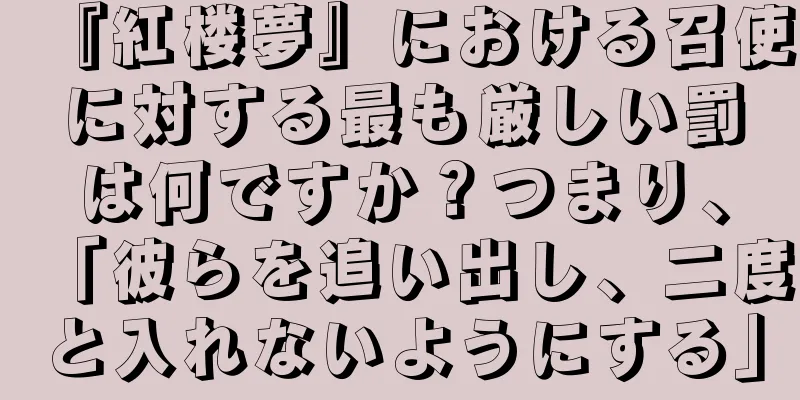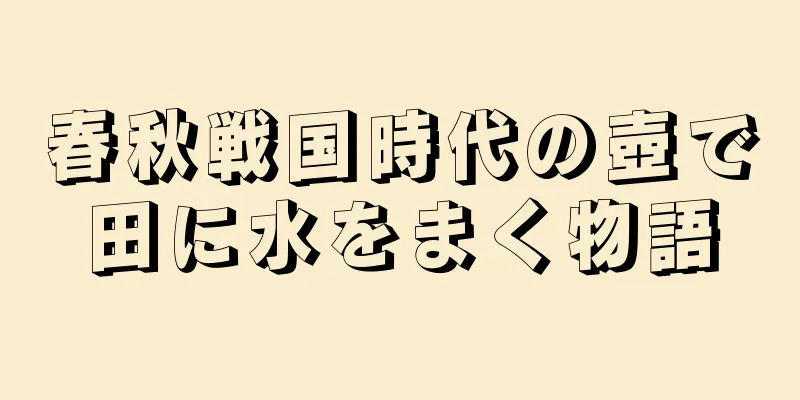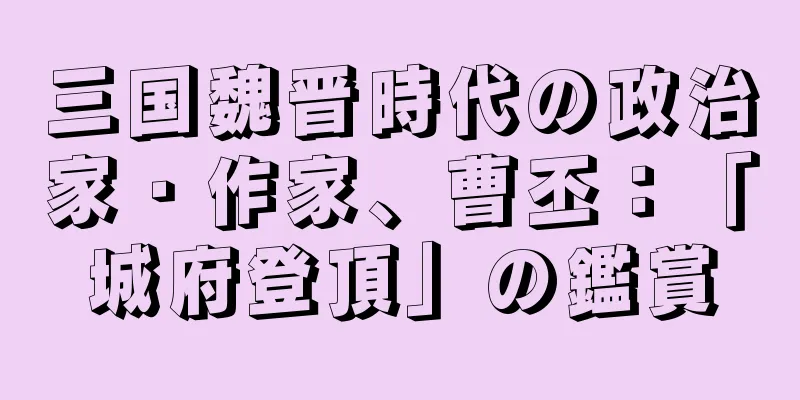端午の節句は邪悪な日だという言い伝えの起源は何ですか?邪悪な日理論は誰と関係があるのでしょうか?
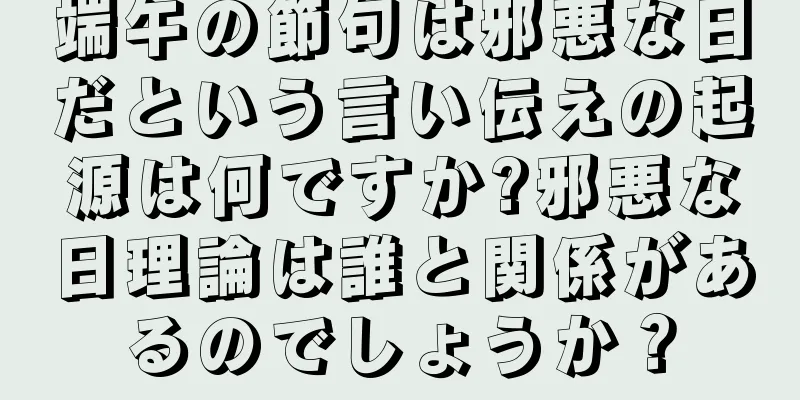
|
「端午節は屈原のせいではない」と言い、端午節は「邪悪な月と邪悪な日」から始まったと信じている。漢代の北方では、5月5日は「凶月凶日」であると信じられており、「5月に生まれた赤ん坊を育てない」という風習がありました。つまり、5月5日に生まれた赤ん坊は、男女を問わず、成人まで育てることができませんでした。育てれば、男の子は父親に危害を加え、女の子は母親に危害を加えることになるからです。 「5月に就任すると、役職を免除されても昇進しない」「5月に家を建てるとハゲになる」などの諺もある。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 東漢の王充は『論衡』の中で、「5月5日に生まれた子供を育てない」という風習について、「年が明けて太陽が最も強くなる5月。この月に子供が生まれると、その精液は熱く激しくなり、両親を圧倒し、両親はそれに耐えられず苦しむ」と説明しています。この風習は戦国時代から広まっていたと一般に考えられています。この習慣は、後漢の王充の『論衡』、英紹の『風素通』、後漢書など多くの書物に記録されています。 5月5日は不吉な月と日であると信じられており、関連する文化活動が生まれ、「五毒を避ける」や「端午節を避ける」などの独特の風習が形成されています。 悪い日 不吉な日。昔、我が国の北部の一部の地域では、「5月5日」は不吉な日だと信じられていました。例えば、王充は『論衡・毒論』でこう述べています。「毒とは太陽の熱であり、すべての人を毒する。太陽の火は常に有毒である。」 「太陽のエネルギーを持って生まれたこの世のあらゆるものは有毒である。」この文章は、太陽がすべての「毒」の源であると言っているように思われます。もう一つの例は、『論衡』の「5月5日に生まれた子供は勃起しない」という説明である。「年が明けて5月は太陽が最も高くなる月です。この月に子供が生まれた場合、その精液は熱く激しくなり、両親を圧倒します。両親はそれに耐えられず、苦しむことになります。」この記事は、端午節の「邪悪さ」の理解を「太陽が最も高くなる」ことに帰しています。 カスタム 5月5日の風習は、後漢の范業の『後漢書』や嬴紹の『風俗通義』に何度も言及されており、5月5日のタブーは北方でますます広まっていった。 『礼書 月例令』には「この月(夏至)は昼が最も長く、陰陽が争い、生死が分かれる。君子は断食し、性交を控え、外出するときは身を覆い、焦らず、色欲を表に出さず、食べ過ぎず、食べ過ぎず、怠けず、欲望を抑制し、心を静める。官吏は犯罪行為を控え、陰陽の結果を確定させる」とある。人々の印象では、5月は「陰陽が争い、生死が分かれる」特別な月であることが分かる。 古代の北方の人々は、疫病の幽霊や五毒(ヒキガエル、サソリ、ヤモリ、ヘビ、ムカデ)などの不吉な要素は、気候が大きく変化する5月5日にすべて現れると信じていました。そのため、この日に生まれた子供は不吉とみなされていました。『風俗意義』には、「5月5日に生まれた子供は、男の子は父親に危害を加え、女の子は母親に危害を加える」という諺があります。 『史記 孟昌君伝』によると、後の孟昌君となる田文は5月5日に生まれた。父の田英は「5月に生まれ、背丈が一家の大男と同じ子は、両親に殺気をもたらす」と言った。5月5日に生まれた子は家族や両親に悪い影響を与えると考え、捨てようとした。母は耐えられず、密かに彼を育て、後の孟昌君を成功に導いた。 王充の『論衡思為』にも次のような記録がある。「一月五日に生まれた子供を育てるのは禁忌である。一月五日に生まれた子供は父母を殺してしまうので、育ててはならない。育てれば、両親が災難に見舞われる。」遼の王定の『汾交録』には、遼の義徳皇后が5月5日に生まれたと記されている。彼女の父親は母親に言った。「この娘は非常に高貴だが、安らかに死ぬことはないだろう。また、昔の人は5日目に女の子を産むのを避けた。彼女の運命はすでに決まっている。私たちに何ができるだろうか?」 5月はすべてが不吉であるように思われ、5月5日に子供を出産することは差し迫った災難の兆候と見なされます。 5 月に対する恐怖とタブーに加えて、古代の北方の風習では、5 月に家を建てたり、畳を干したりすることも避けていました。『風俗行』には、「5 月に家を建てると、禿げる」とあります。唐代の段承世も、「邑陽雑注・光志」の中で、「5 月に 2 階に行くのはタブーです。5 月は脱皮すると言われています。2 階に行って自分の影を見たら、魂が去ってしまう」と述べています。不吉な月と不吉な日という考え方は広く浸透しており、5月は政治家や役人にとっても不吉な月だと人々は信じています。風水堂の失われた文書には、「5月に就任した役人は、退任するまで昇進しないと言われている」と書かれている。5月に就任した役人は、退任するまで昇進しないと言われている。どの王朝の役人も5月に就任することを恐れていた。 『日直録』第6巻には「唐代の新規則によれば、1月、5月、9月は禁忌月である。現代の人々はこの規則に従い、就任するのにふさわしくないと考えている」とある。また、潘容弼の『地経随氏集聖』にも、井戸毒の害を避けるために5月5日に湧き水を汲むことは禁忌であると記されている。 『六氏春秋』の「夏至記」の章には、5月は性行為を控え、断食をすべきであると記されている。五日が死者の日であると信じる伝説も数多くあります。例えば、『史記 孟昌君伝』には、歴史上有名な孟昌君が5月5日に生まれたと記録されています。父親は「5月に生まれた子供は家長よりも背が高くなり、両親に悪影響を与える」と信じ、母親に彼を産まないよう頼んだ。風蘇堂の失われた文書には、「5月5日に生まれた子供は、男の子なら父親に悪影響を与え、女の子なら母親に悪影響を与えると言われている」と記されている。 『論衡』の著者である王充は次のようにも記している。「正月と五月に生まれた子供を育てるのは禁忌である。正月と五月に生まれた子供は父母を殺してしまうので、育てることはできない。」東晋の名将、王真異は五月五日に生まれたため、祖父は彼を「真異」と名付けた。宋徽宗の趙季は5月5日に生まれ、幼い頃から宮殿の外で育てられました。古代、我が国の北部の人々にとって、5月5日を不吉な日とみなすのは一般的な現象であったことがわかります。 |
<<: 端午の節句にお団子を食べる習慣はいつ始まったのでしょうか?南部の団子の特徴は何ですか?
>>: なぜ端午節は蘭沐浴節とも呼ばれるのでしょうか?蘭浴祭はどの植物に関係しているのでしょうか?
推薦する
『三朝北孟慧編』第65巻の主な内容は何ですか?
景康時代には40巻ある。景康元年11月26日定海に始まり、辛卯年30日に終わります。 26日、定海瓊...
賈玉村の『紅楼夢』の結末は何ですか?なぜ誰かが報告されたのですか?
賈玉村は『紅楼夢』の重要な登場人物であり、この小説に登場する最も初期の男性キャラクターの一人である。...
西遊記の続編で武田はどうやって悪魔になったのですか?阿修が亡くなった後、仏陀が4つの言葉を言ったからです。
『西遊記』の続編で、武田はなぜ鬼になったのか?阿修が亡くなった後、仏陀が4つの言葉を言ったからだった...
劉和は前漢の王位継承者ではなかったのに、なぜ皇帝になったのでしょうか?
海渾侯劉和は、前漢史上最も在位期間の短い皇帝であったが、長い間歴史家からは認知されていなかった。西漢...
『紅楼夢』で賈屋敷で捜索押収作戦が勃発したのはなぜですか?誰の刺繍入り春バッグでしょうか?
大観園の探索は、『紅楼夢』の最初の 80 章の中で最も重大な出来事です。次回はInteresting...
マバ族はどの時代に生きていたのですか?マバ族の生活はどのようなものですか?
129,500年から135,000年前に生きていたマバマンは、中国の猿人と現代人の中間に位置する古代...
「孤延残喘」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「孤延残喘」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その背景にある物語は何でしょうか?次の興味...
光と影の古代芸術を探る:影絵の起源
影絵は、古くからある独特な演劇形式です。精巧な革を使って人間や動物の姿を作り、舞台裏からの光で白いス...
唐の時代に女性はどんなスポーツに参加できましたか?唐代の女性はポロをするのが大好きだった
唐代の女性はどのようなスポーツに参加できましたか? 男性の武道精神に影響され、唐代の女性もスポーツを...
劉勇の「玉蝶・目をそらすと雨が止み雲が切れる」鑑賞
オリジナル外を見ると雨は止み、雲も晴れています。私は静かに手すりに寄りかかりながら、秋の景色を眺めて...
姜子牙の「太公六計」:「六計・犬計・車」の評価と例
『六兵法』は『太公六策』『太公兵法』とも呼ばれ、秦以前の中国の古典『太公』の軍事戦略部分と言われてい...
ウイグル人の習慣と習慣 ウイグル人の葬儀習慣の紹介
ウイグル族の葬儀は壮大かつ厳粛な儀式です。ウイグル族がイスラム教に改宗した後、葬儀はイスラムの儀式に...
袁梅の「私が見たもの」:この詩はのんびりとした気楽な詩のように見えますが、実際には私の気持ちを表現しています
袁眉(1716年3月25日 - 1798年1月3日)、号は子才、号は建寨、晩年は蒼山居師、綏遠師、綏...
「一を聞いて十を知る」という慣用句はどういう意味ですか?その背後にある歴史的な物語は何ですか?
「一を聞いて十を知る」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか。その裏にはどんな物語があるのでし...
石公の事件 第6章:石公の銀事件の裁判、生姜と酒で肺を腐らせるという決断
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...