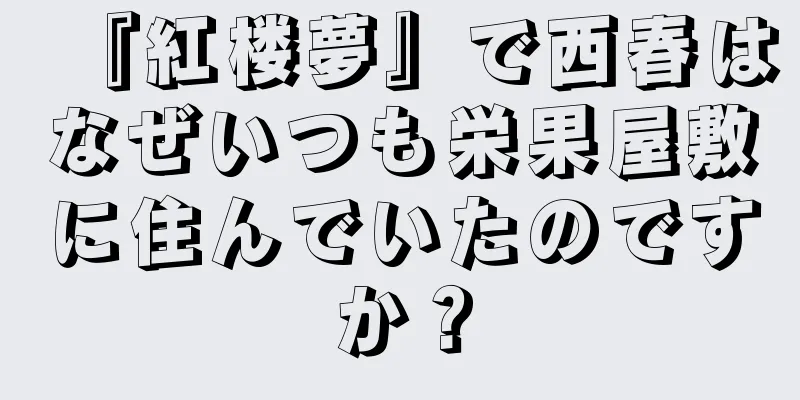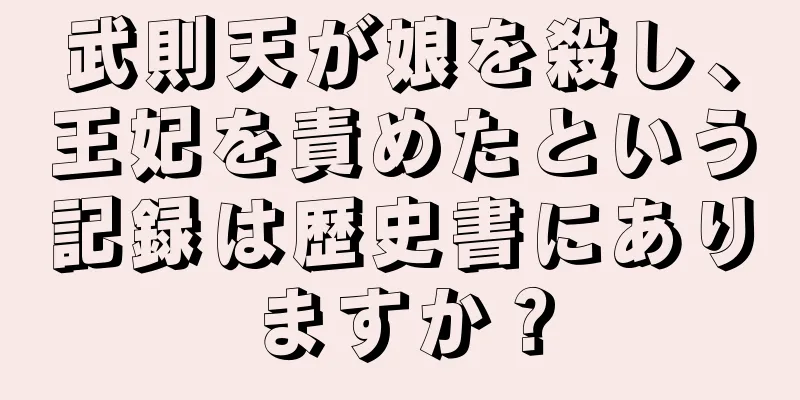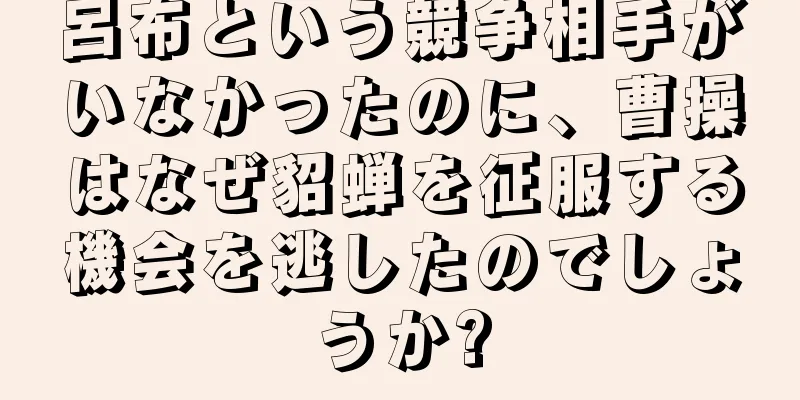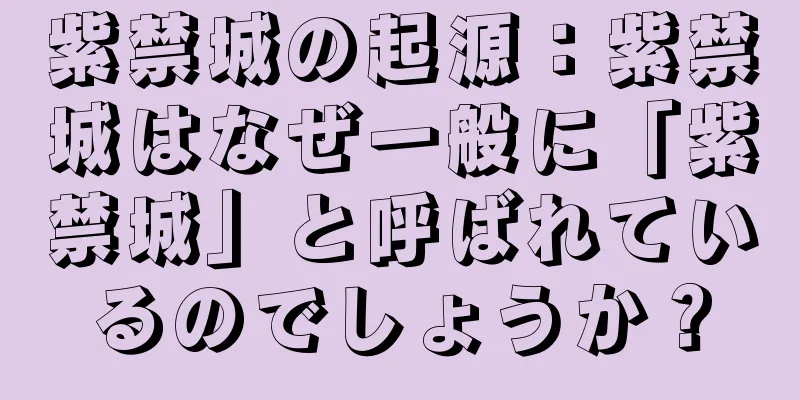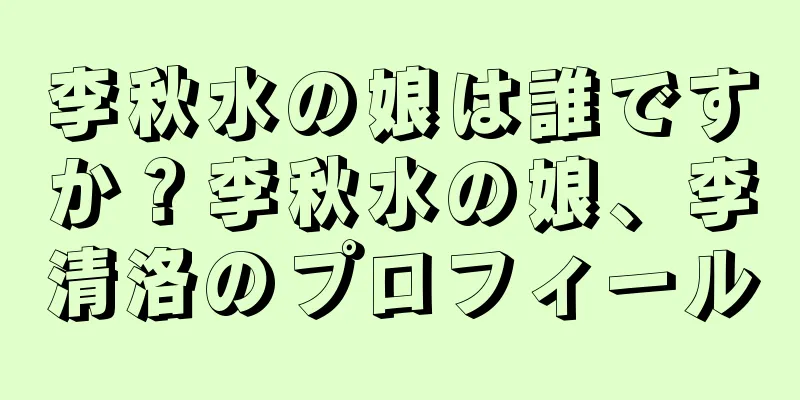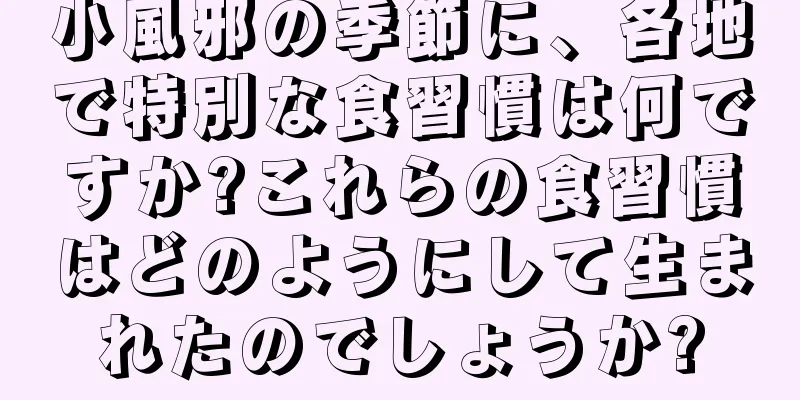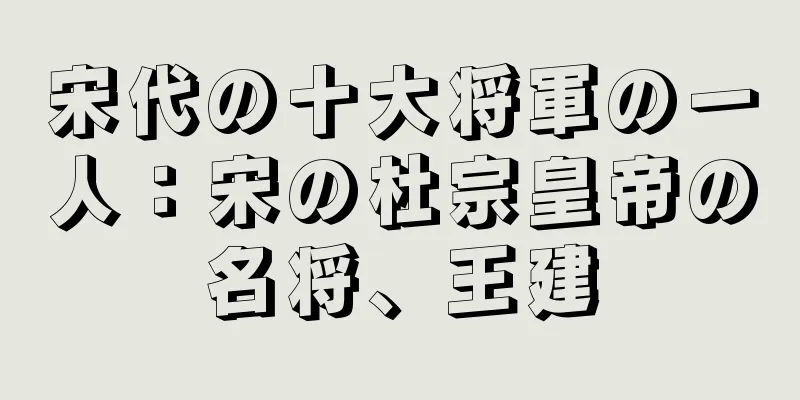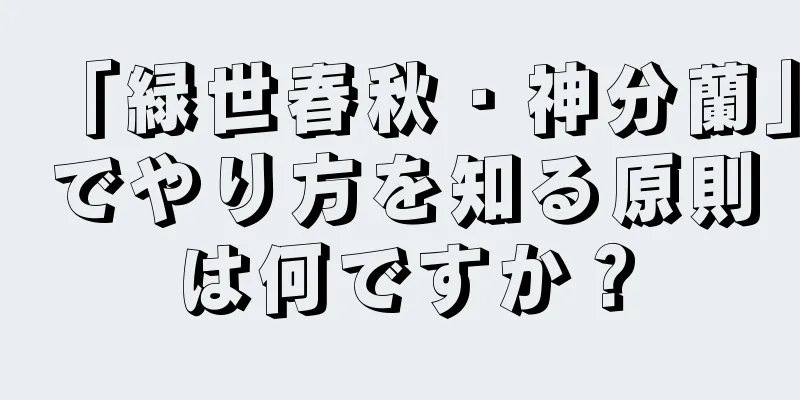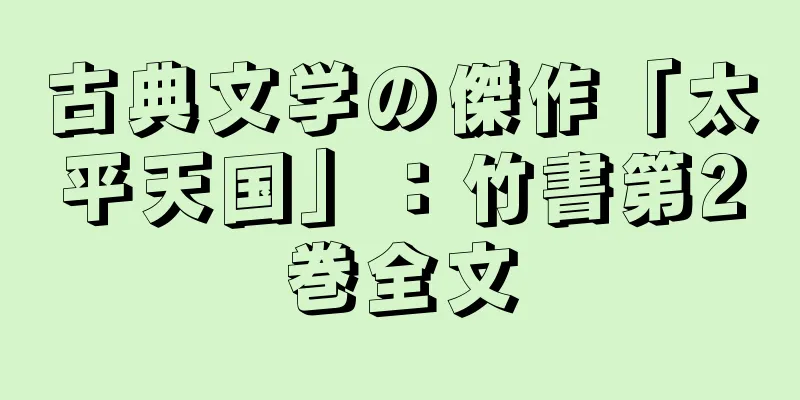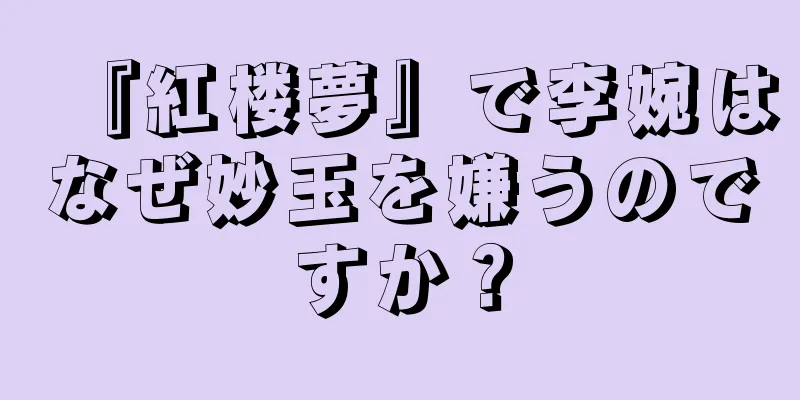皇帝は皇族の女性たちにどのような称号を与えたのでしょうか?
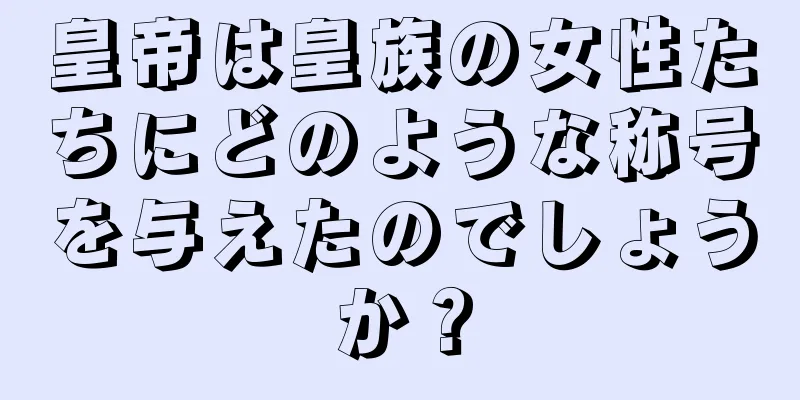
|
古代の女性の地位はそれほど高くなかったが、王族の女性など例外もあった。女性の家族構成員はそれぞれ異なる身分を持ち、皇帝から与えられた称号も異なっていました。大きいものから小さいものの順に、長女、公主、郡の公主、郡の公主、郡の公主、郡の公主でした。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 1. プリンセス 王女は古代中国の王族の女性の称号です。漢代には、彼女たちの地位は王子と同等であり、公主の称号を与えられたのはごく少数でした。 長女は、通常、皇帝の嫡女、功績のある皇女、皇女の姉妹、皇女の叔母である。東漢以来、皇帝の娘は公主、皇帝の姉妹は長女、皇帝の叔母は大長女と呼ばれている。寵愛を受けた長女は、普通の側室よりも高い地位を持っていました。周の時代、皇帝の娘は王冀と呼ばれていました。宋の徽宗皇帝の時代に、蔡靖の提案により、宋の朝廷は周の「王冀」の称号を真似て、「公主」の名前を「帝冀」に改めました。その後、長女は「帝冀」と呼ばれるようになりました。 2. プリンセス 王女は、皇帝の娘、王の娘、一族の娘に対する古代中国の称号です。略称は「王女」です。「王女」に対応する男性の称号は「王」です。 「公主」の語源は『公陽評』に「皇帝が領主の娘を娶る場合、領主と同じ姓の女性を亭主としなければならない」とあることから公主と呼ばれるようになった。 「王女は皇帝の娘と同じではありません。逆に、王族の女性の中には王女の地位を与えられる人もいます。王女と結婚することを「王女と結婚する」と言い、王女と結婚することを「側室と結婚する」と言います。」 3. プリンセス 王女は古代中国の封建社会において王族の女性に与えられた称号でした。 「君主」という言葉は「君公主」という言葉から派生したものです。「君公主」という言葉は東漢時代に生まれました。一般的に皇女の位は「仙公主」でしたが、少数ですが「君公主」もいました。時代の変化とともに、皇女には皇帝の娘、皇太子の娘、太子の娘、皇帝の側室の娘、太子の娘など、さまざまな身分を持つようになりました。唐代になって初めて、皇太子の娘に対する特定の称号として公主が使われるようになりました。 「君主」という言葉は、南宋臨川王劉益卿が編纂した『新世界・高貴な女たち』に初めて登場し、そこには「韓玄武(桓文のこと)が蜀を征伐し、李施の妹を妾とした」とある。南梁の劉小表は『嫉妬記』の中で「韓が蜀を征伐し、李施の娘(李施の妹という説もある)を妾としたので、君主(南康県の公主)は激しく嫉妬した」と記し、引用している。ここでの君主とは、晋の明帝司馬紹の娘、司馬興南のことである。君主は君公師の略称である。 4. プリンセス ジュンジュンは古代中国と朝鮮王朝において高位の女性に与えられた称号であり、郡名に基づいていました。唐・宋時代には皇帝の側室や官吏の母や妻に与えられた称号であったが、明・清時代には王族の女性にのみ与えられた。 公主の称号は、西漢の時代に漢の武帝が祖母に平原公主、略して平原公主の称号を授けたことに由来します。漢の武帝は祖母の荘児を平原公として尊崇した。平原は当時の郡の名前であり、郡女を封建制にするという慣習の始まりでした。唐代:一級の内廷女官の母には四級の郡女官の称号が与えられ、二級の内廷女官の母には四級の郡女官の称号が与えられた。四級の文武官の母または妻には郡女官の称号が与えられた。北魏:皇后の実母、義母、継母にはすべて皇女の称号が与えられた。 宋代:中三大夫、大江君、団連氏、雑学氏以上の者の母または妻に君君の称号が与えられた。宋の徽宗皇帝の時代には、叔仁、叔仁、仁仁、公仁にこの称号が与えられた。同時に、君君は側室の低い称号の一つでもあった。晋代:侯爵の母または妻には郡夫人の称号が与えられた。晋の章宗皇帝の成安2年(1197年)、この称号は郡侯夫人に改められた。元代:第四位の官吏の母または妻には公主の称号が与えられた。明代:王子の孫娘には王女の称号が与えられた。清代:満州語では多老格格と呼ばれた。和朔王の妾の娘と多老北楽の嫡女にも郡夫人の称号が与えられた。 5. 郡領主 カウンティプリンセスは王族の女性に与えられる称号です。東漢の皇帝の娘は皆、郡公主の称号を与えられた。隋と唐の時代では、王子の娘だけが郡公主の称号を与えられた。郡主の一般的な称号には、楽安、清平、蓬莱、栄安、栖霞、寿光などがあります。 東漢:公主は郡の名にちなんで名付けられたため、郡公主と呼ばれた。劉松:王の娘は郡公主と呼ばれていましたが、もはや公主と呼ぶことはできませんでした(晋の時代を除く)。郡公主は独立した称号になりました。晋の時代:王子の娘は郡姫と呼ばれた。北魏:王子の娘は郡姫と呼ばれた。唐代:王子の娘は郡姫の称号を与えられた。宋代:王子や公爵の娘には郡姫の称号が与えられた。北宋の正和3年(1113年)、宋の徽宗皇帝は公主の称号を「帝姫」に、郡公主の称号を「祖姫」に改めたが、この制度は北宋の滅亡後に廃止された。 晋:王子の娘は郡姫と呼ばれ、同時に皇帝の娘も郡の名を冠して郡姫と呼ばれた(王子の娘の郡姫と同じではない)東漢と同様に、皇帝の娘の称号として30の郡名が定められた。晋の皇女の号は、楽安、清平、蓬莱、栄安、栖霞、寿光、霊仙、首陽、忠秀、恵和、永寧、清雲、静楽、富山、龍平、徳平、文南、富昌、順安、楽首、静安、霊首、大寧、文喜、秀容、易芳、振寧、嘉祥、錦祥、華源であった。 明代:王子の娘は郡公主と呼ばれた。清朝:王子または皇太子の娘は郡公主と呼ばれました。 6. カウンティレディ 「仙君」は古代中国において王族の王女や高位の女性に与えられた称号である。郡主の称号は西漢時代に始まり、郡名を称号として与えられた君主を指します。当時、漢の武帝は異母妹に君主の称号を与えました。彼女の称号は秀城であったため、彼女は秀城君と呼ばれました。秀城は当時の郡名であったため、彼女は郡主と呼ばれました。 唐代には、郡夫人の称号は第五位の官吏に相当した。第3位または第4位の皇妃の母親には郡夫人の称号が与えられ、第5位の文官または武官の母親にも郡夫人の称号が与えられた。宋代には、官吏またはその妻の母親に郡夫人の称号が与えられました。晋の時代には、文官第四位の邵忠大夫や武官の懐遠大将以上の官吏の母親やその妻には、郡女の称号が与えられた。元代には、五位以下の官吏の母または妻に郡夫人の称号が与えられた。明代の王子の曾孫は郡女と呼ばれた。清朝時代には、北子の娘は郡夫人の称号を授けられました。 7. 翔君 項君は古代中国の女性の称号であり、晋の武帝が楊虎の妻に万歳項君の称号を授けたことに始まります。唐代には、爵位を持つ四位の官吏の母または妻に項君の称号が与えられたが、宋代には廃止された。晋の時代、第五位の文官である朝烈大夫と、武官である玄武将軍以上の母親や妻には、項君の称号が与えられた。章宗の成安2年(1197年)、この称号は項君に改められた。明代には、郡公の玄孫に「香君」の称号が与えられた。清代には、貞国公、扶国公、北妾の娘が「香君」と呼ばれた。 |
<<: 解華は中国絵画のジャンルの一つです。晋の時代の顧凱之は何と言ったでしょうか?
>>: 「南風は我が意を知る」は古代に広く流布していたが、これは南朝時代のどの民謡から来ているのだろうか。
推薦する
「7月29日チョンラン邸宴会記」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
7月29日チョンラン邸での宴会で書かれたもの李尚閔(唐代)目の前の池には小雪のように露が降り、月が池...
カザフ族の美しい「ドンブラ」にはどんな神秘的な伝説があるのでしょうか?
ドンブラは新疆ウイグル自治区のイリに住むカザフ族の愛用楽器です。その起源については伝説があります。伝...
史公の事件 381章: 徳の高い大臣が未亡人に同情し、報酬を求める。指揮官は盗賊の逃亡を知る
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
本草綱目第8巻セダムの原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
蕭何はどうやって韓信の才能を知ったのでしょうか?なぜ彼は比類なき愛国者と言われているのでしょうか?
紀元前206年半ば、秦王朝が滅亡してから半年も経たないうちに、項羽は世界を18の地域に分割し、秦王朝...
万延宗弼の紹介 有名な晋の将軍、万延宗弼はどのようにして亡くなったのでしょうか?
万延宗兵(? - 1148年11月19日)は、本名は武初、別名は武主、武初、黄武初で、女真族である。...
宋代の大臣が劉鄂に武則天に倣うよう勧めたとき、なぜ彼女は記念碑を破り捨てて自ら皇帝を名乗ったのでしょうか?
古代中国では女性の地位は非常に低く、政治に参加し歴史に名を残す女性政治家はさらに少なかった。古代から...
李清昭の恋愛詩で有名な詩句は何ですか?有名な詩や詩節の内容はどこから来ているのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が李清昭の恋愛詩の有名な一節を紹介します。興味...
南宋の官僚にはなぜ二つの時代があったのでしょうか?彼らの目的は何ですか?
南宋時代の官僚である洪邁によれば、ほとんどすべての指導者には2つの年齢があり、1つは「実年齢」、もう...
現在最も広く受け入れられている説によれば、秦の子嬰王は誰の息子でしょうか?
秦の王子嬰は誰の息子でしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!胡海の...
史公の事件 エピソード514:ハオ・スーユが張琦を誘い、張桂蘭が張歓と戦う
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
清代史草稿第16巻原文の鑑賞
◎仁宗皇帝紀仁宗皇帝は天の祝福を受け、福徳に恵まれ、天下を平定し、教徳、武勇、孝徳、勤勉、倹約、聡明...
三国志演義のトップ10武器ランキングでは、呂布の「方天華壷」は3位に過ぎない。
TOP10. 曹操 - 七星剣リストに載っている理由: 貴重な刀の価値の鍵は敵を殺すことではなく、自...
『満江紅』の作者は岳飛ですか?論争の的となっている分野は何ですか?
「文江紅」に非常に興味がある方のために、「Interesting History」の編集者が詳しい記...
なぜ『紅楼夢』では西仁は青文ほど優れていないのでしょうか?彼女の強みは何ですか?
青文と希仁は『紅楼夢』の中で最も重要な二人の侍女であり、『金陵十二美女』の中でそれぞれ第一位と第二位...