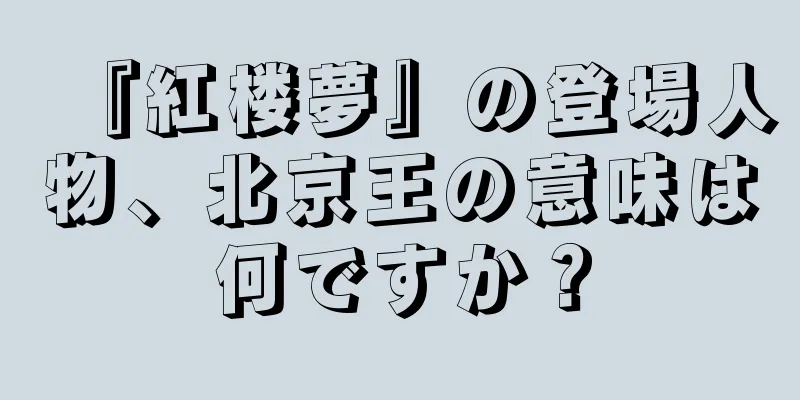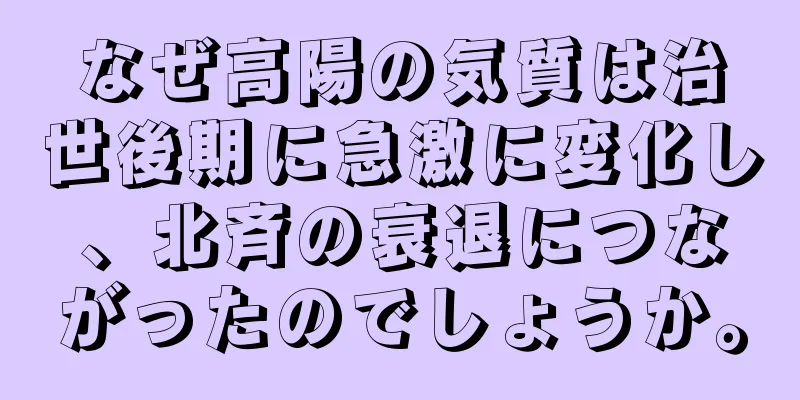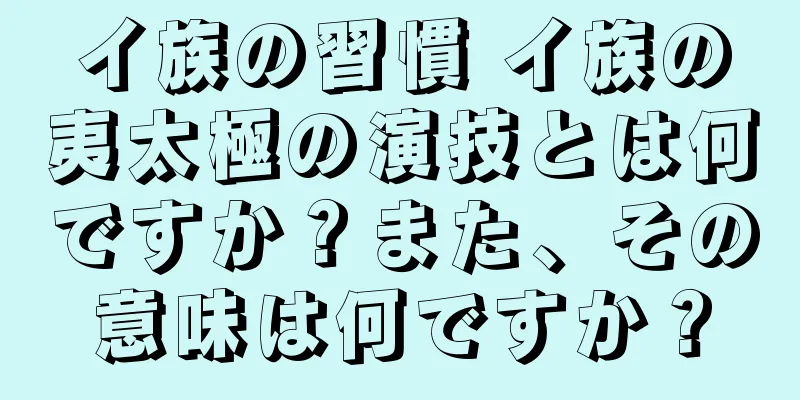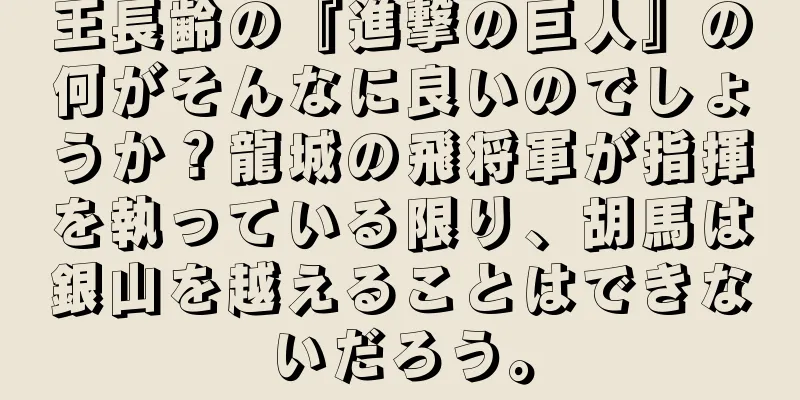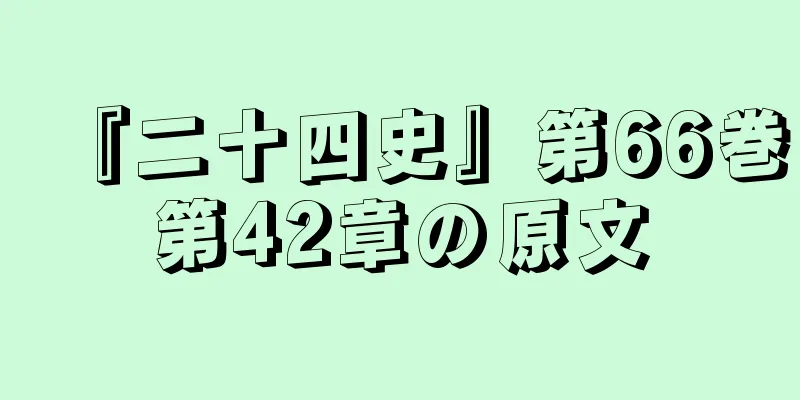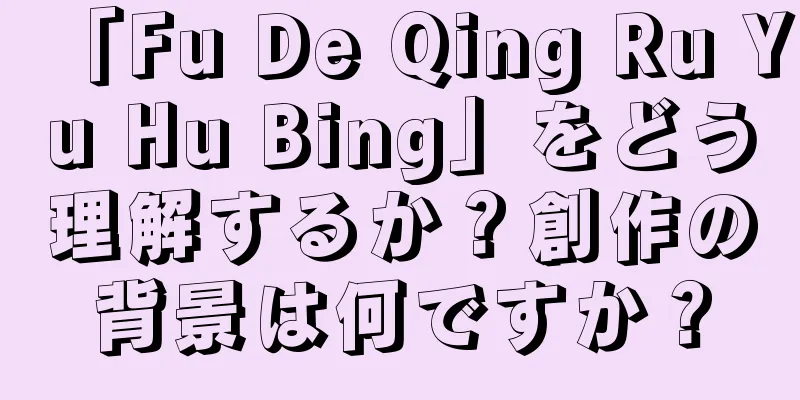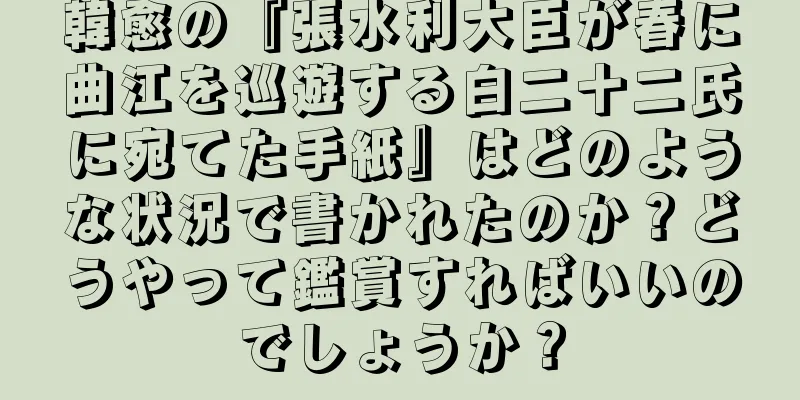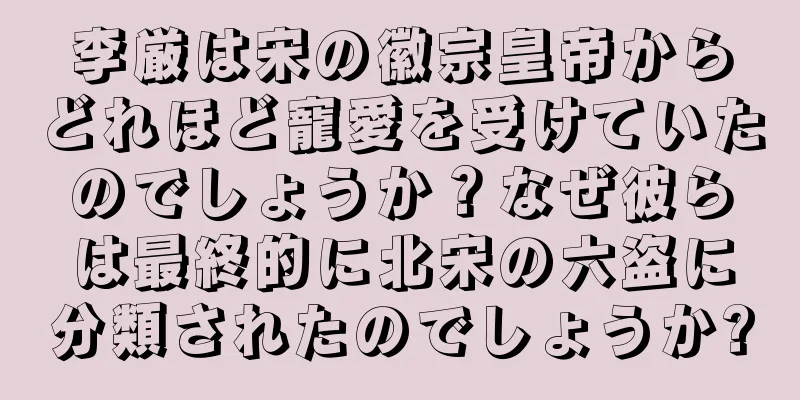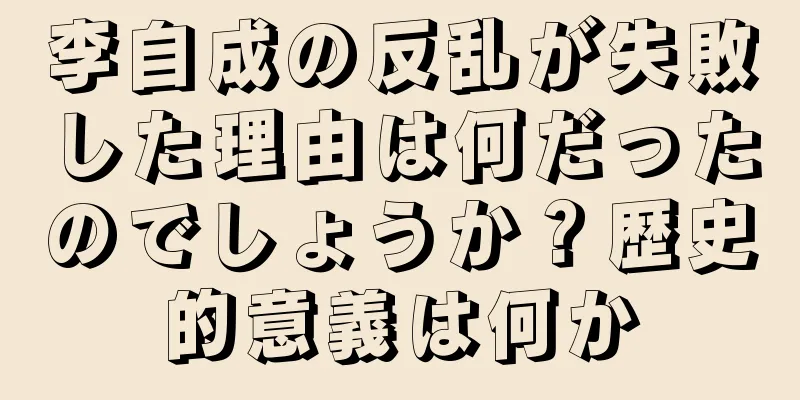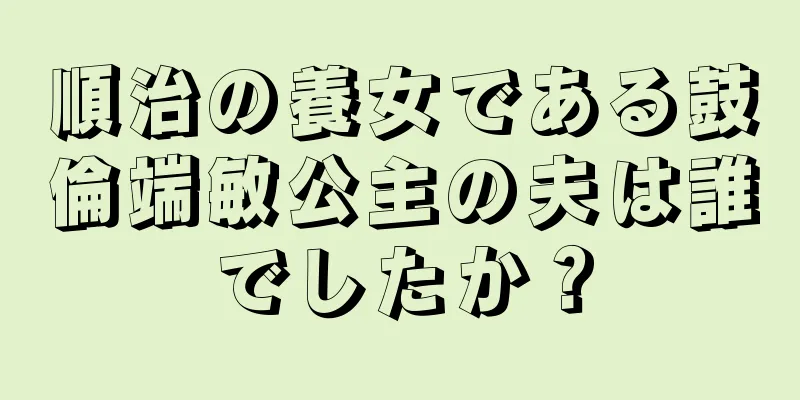唐の時代に勉強を始めてから科挙を受けるまでにどれくらいのお金がかかったのでしょうか?
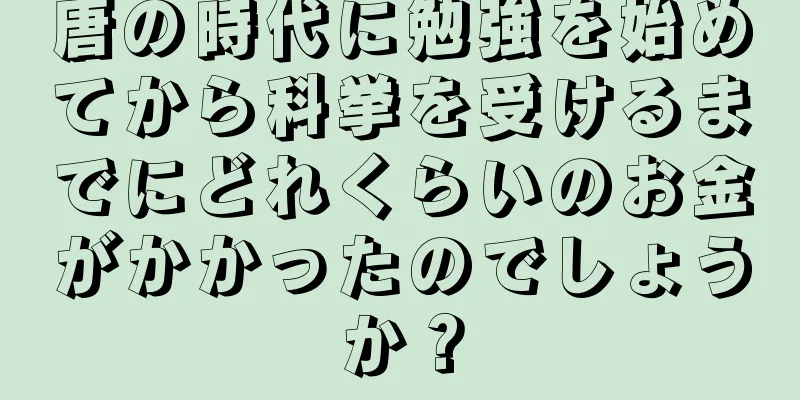
|
古来より、学者は国家の屋台骨であり、特に科学技術が爆発的に発展した現代社会においては、科学技術の人材を多く抱えることによってのみ、国家は急速に発展することができるのです。 2000年以上前の春秋時代には、法家の代表的人物である管仲が、国の繁栄には人材が第一であると明言していました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 戦国時代、関仲を尊敬する支下官僚たちは、関仲の国治思想をもとに編纂した『管子』の中で、天下四民論を提唱した。 『管子小光』には「学者、農民、商人、職人の四階級の人々が国家の基礎である」とある。 学者、農民、労働者、商人の「四つの階級」のうち、「学者」が第一位となったのは、当時の権力層が学者の重要性を認識していたことを示しているだけではない。同時に、社会発展の観点からは、「学者」が国家の柱としての核心的地位を反映しているとも言えます。 実際、西周の時代、3000年前にはすでに「官立学校」の設立が流行していました。貴族の子弟のための基礎科目である「六芸」は、国家のために有能な人材を育成するための教育システムです。 春秋時代の偉大な思想家であり教育者であった孔子は、「階級の区別なく教育する」という教育思想の下、「私立学校」の設立を強く主張し始めました。これにより、貴族による教育制度の独占が崩れ、勉強は貴族階級の特権ではなくなりました。社会に暮らす他の階級の人々も「私立学校」に入学して教育を受けることができるようになりました。 著者は、春秋戦国時代から2000年以上の時を経て現代社会に至るまで、中国の教育制度において指導と教育は依然として最優先事項であると考えている。なぜなら、文化、知識、技術は国の繁栄の3つの原動力だからです。才能のない国は底なしの奈落に落ちてしまう。明日は太陽が昇らないばかりか、永遠に沈んでしまうだろう。 古代教育の歴史には、2つの大きな発展の飛躍がありました。1つ目は孔子が「私立学校」の設立を提唱し、貧しい人々でさえも学ぶ権利を得たときです。2つ目は隋代に初めて科挙制度が創設され、唐代に科挙制度が引き継がれたときです。 私教育から科挙への移行は、教育意識の継続的な発展の兆候であっただけでなく、学者の地位の向上の重要な象徴でもあったと言っても過言ではありません。 学者の科挙への道 1. 科挙制度の歴史的起源:周代の「村選」 古代から現代まで、歴代の王朝の学者を見てみると、彼らは常に社会から大きな注目を集めてきた集団でした。これは主に、文化的知識を習得した学者が社会の発展において非常に重要な役割を果たすだけでなく、古代の君主たちの統治の道具としても機能するためです。周代の学者のほとんどは有力者や貴族階級の子弟であったが、「村選」制度が確立されてからは、地元の人材も宮廷の役人として働くことができるようになった。 つまり、いわゆる「村選」とは、「村の長老」が村の賢者を推薦し、地方官僚による審査を経て、地方から直接政府に行けるというものである。しかし、この人材推薦の方法は周王朝の貴族階級から抵抗を受けた。したがって、下層階級の賢者は政府に入ることができるように見えますが、実際にこの目標を達成できる人はほとんどいません。 2. 春秋時代に世襲貴族制度は揺らいだ 春秋時代、「礼楽の崩壊」により貴族の子弟による世襲貴族制度が崩壊した。簡単に言えば、父親の官職を直接継承できる貴族階級とは別に、多くの下層階級の人々が歴史の舞台に登場し始めたのです。 著者は、「儀式と音楽の崩壊」は表面的にはマイナスの影響のように見えるが、根本から分析すると、実は一種の進歩であることが分かると考えている。 貴族や大臣の世襲称号が揺らぎ始めると、社会の底辺に生きる学者たちが試験や推薦を通じて徐々に奴隷制度の中核権力層に入り始める。著者は、貴族の世襲制から下級の学者が試験に合格して宮廷の官吏として仕えるようになったことは、社会発展の必要性であり、科挙制度誕生のきっかけでもあったと考えている。 3. 漢代の推薦と採用の制度 「徳が高く、正直で、率直に話し、助言を与えることができる人」というのが漢王朝の統治者の人事哲学でした。 この目標を真に達成するために、推薦制度と徴兵制度が創設されました。これら 2 つの人材選択システムも多くの障害を設けていますが、「村選択」システムよりも進歩的です。民衆の中にいた多くの才能ある人々が漢王朝の政治の舞台に立つようになりました。 実際、科挙制度の誕生を真に促進し、あるいは科挙制度の成熟を予兆した官選制度は、魏の文帝が創設した九階制であった。 この官選制度は「九位制度」とも呼ばれ、その名の通り、実際に封建領主が有用な人材を選抜するために制定した制度です。 九階制の重要な地位は、主に漢代の推薦制度を継承し、隋唐代の科挙制度に先行したという事実に反映されていると筆者は考えている。 科挙制度は南北朝時代に始まったが、周の「村選」、漢の推薦制度と採用制度、魏晋の九階制がなければ科挙制度は生まれなかったであろう。 これは実は古代政治の進歩であるだけでなく、社会の発展の必然的な結果でもあります。奴隷制度と封建制度の間には本質的な違いがあるものの、両者とも中央集権的なシステムへと絶えず発展していることは否定できない。つまり、封建君主は、帝国の権力を継続的に強化する過程で、官選制度の発展と成熟も促進したのです。 4. 隋唐の科挙制度 著者は、歴史記録と古代王朝における官選制度の発展過程に基づけば、科挙制度の出現が一朝一夕で起こったものではないことが明確に理解できると考えている。推薦制度から科挙制度に至るまでには400年以上の歳月を要したが、科挙制度形成の鍵となったのは隋唐の時代であったと言っても過言ではない。 隋の官僚選抜制度は漢の官僚推薦・採用制度を継承したものではあるが、世界中から多くの学者を集めた科挙制度がすでに隋の時代に登場していたことは否定できない。 開皇末期、隋は科挙制度を実施し、学者、明経、進士の3つの科目を開設した。この観点から、科挙制度と進士号はともに隋代に誕生したと筆者は考えている。 5. 科挙制度の形成期 科挙制度を真に全盛に導いた王朝は、隋の次に唐の王朝である。 『新唐書』には、289年続いた唐代に科挙制度が268回行われ、計7,448人の進士が入学したことが正確に記録されている。しかし、正確に故郷が記録されている唐代の進士の総数は約846人である。 この点が唐代において進士の学位がいかに貴重であったかを示していると筆者は考えている。 唐代の学者が科挙に合格して進士になれば、鯉が龍門を飛び越えるように地位が一変するだけでなく、一人の成功が家族全体の繁栄をもたらすという現象が起こると言っても過言ではありません。だからこそ、唐代の文人は努力を惜しまず、何度も科挙に挑戦し、挫折に直面してもさらに勇気を奮い起こしたのです。 進士試験は確かに唐代に多くの優秀な人材を輩出したと言える。同時に、社会の下層階級出身の学者たちは、より多くの社会的経験と思想を持っているだけでなく、統治者が貴族階級と戦うための道具でもあります。もちろん、彼らの熱意を考えれば、科挙によって選ばれたこれらの官吏たちも、啓蒙的で進歩的な進士集団を形成していた。 彼らの指導と影響を受けて、唐代の学者たちは科挙に対して異なる態度をとっていました。 実際、唐代の多くの有名な詩人は科挙を経て官職に就きました。もちろん、成功する人がいるところに失敗する人もいますが、これらの失敗した唐代の文人たちは科挙を受けるという決意を捨てませんでした。 著者は、唐代の289年の歴史において、唐代の進士集団は政治の舞台で最も優れていただけでなく、最も活気のある文人集団でもあったと信じている。 科挙に合格したこれらの人々が唐代の歴史の発展に大きな影響を与えたと言っても過言ではありません。 「進士」を養成するには多額の費用がかかり、北京に行って試験を受けるのにも多額の費用がかかる 古代史上最も栄華を極めた封建王朝である唐王朝は、極めて強大な国力を有していただけでなく、人材の選抜にも多大な労力を費やしました。著者は、封建制度の根源から分析すれば、どの封建王朝でも貴族一族と皇帝権力の争いがあったことは容易にわかる、と考えている。 李唐は関龍貴族から始まった。李淵は反乱を起こした際に関龍貴族の支援を受けた。そのため、唐の成立後、多くの要職は基本的にこれらの貴族の手に握られていた。さらに、皇帝が下した多くの決定は、実際には関龍の貴族によって深く支配されていました。この前提の下、従順な官吏を育成することが唐代の統治者にとって重要な課題となった。 実際、隋の時代に科挙制度が生まれたのもこの理由によるものでした。 唐代の進士の数は宋代に比べてはるかに少なかったが、科挙によって選ばれたこれらの官吏は唐代の政治構造や勢力均衡において非常に重要な役割を果たした。 しかし、皆が勇敢に一枚板の橋を渡ろうとしているとき、科挙を受ける学生たちのことなど誰も気に留めていなかった。 勉強を始めてから科挙を受けるまで、そして故郷から長安までの旅費など、何の援助も受けられなかったどころか、すべて自費だったと言っても過言ではありません。彼らにできる唯一のことは科挙に合格することだった。なぜなら、この方法でのみ、彼ら自身と家族の運命を変えることができたからだ。 唐代の学者の科挙受験費用 唐代は封建社会の最盛期であったが、当時の社会の生産性は依然として遅れており、交通は非常に不便であった。そのため、唐代に科挙を受けるために北京へ行きたい学生は、基本的に長い旅をしなければならなかった。この過程では多くの旅費が発生し、学生の故郷が長安から遠いほど、旅費も高くなります。 唐代の学者、劉推は、試験を受けることの悲しみと費用を次のように記録しています。 「私の家は九曲の南にあり、長安から4,000マイル近く離れています。助けてくれる人もいないし、世の中に有力な親戚もいません。1日に60マイルを旅しなければならず、往復に半年かかります。1年に3か月は両親に仕え、さらに2か月は道中で食べ物や衣服を乞う休暇を取らなければなりません。」 この一節から、劉推が試験を受けるまでの旅は4,000マイルに及んだことがわかると著者は考えています。彼の家族は比較的貧しく、裕福な親戚もいなかったため、彼は大変な苦労をしながらしか旅をすることができませんでした。故郷から長安まで行き、そしてまた家に帰るまでに半年もかかった。 彼はほとんどお金を持っていなかったので、「道中で食べ物や衣服を乞う」必要さえありましたが、それは学者にとって大きな恥辱でした。 「さらに、予測できない病気、寒さ、暑さ、風、雨が一年中発生します。風と雨で髪は白くなり、畑は不毛になります。」天候の変化により病気になった場合、最長 1 年間、道路上で遅延が発生します。 この悲しい一節は、道中の困難さを明らかにするだけでなく、莫大な経済的圧力も表していると著者は考えています。 清朝の科挙試験に失敗したある学者は、絶望を感じてこう書いた。「銀貨数百枚を費やしたが、土でできた牛が海に沈むようなもので、何の知らせもない。」彼は疲れる旅にもかかわらず試験を受けるために北京に行ったが、合格する見込みがなく「数百銀貨」を費やしてしまったため、やはり泣いていた。 唐代の下級学者にとって、旅費、船賃、ホテル代、医薬品、衣服、靴、帽子などの費用は、非常に大きな出費でした。特に貧しい家庭出身の受験者の場合、長安に到着する前にほとんどお金が残っておらず、試験を受けるために路上で物乞いをしなければならなかったこともあった。 著者は、このような困難にもかかわらず唐代の学者たちが科挙に希望を持ち続けた理由は、理由をさらに深く分析すると、「一生懸命勉強して良い仕事を得る」というのは単なる不十分なスローガンであることがわかります。 「本には何千ブッシェルもの穀物が詰まっている。本には黄金の家が詰まっている。本には房のように多くの馬が詰まっている。本には翡翠のように美しい女性が詰まっている」というのが、科目レベルの試験の究極の目標です。 |
<<: 霊岩閣の24人の英雄の中で、有名な秦瓊がなぜ最下位にランクされているのでしょうか?
>>: 李隆基が皇帝になった後、なぜ李衡に帝位を返上するよう求めなかったのか?
推薦する
呂睿の「瑞鶴仙・濡れた雲が雁の影に張り付く」:この詩は非常に繊細で深い意味をもって書かれている。
呂叡(?~1266)、字名は景思、号は西雲とも呼ばれる。会稽(現在の浙江省紹興市)出身で、宋代の官僚...
孟浩然の別れの詩「江南の杜世思に別れを告げる」への感謝
「夕暮れ時に帆船を停泊できる場所はどこでしょう?水平線を見ると心が痛みます。」この詩を読んだことがあ...
『紅楼夢』で賈牧が黛玉に文学を学ばせた意図は何だったのでしょうか?
諺にあるように、女性の美徳は才能のなさにあります。以下の記事はInteresting History...
『紅楼夢』における李婉の最終的な運命は何でしたか?彼女の判決はどうですか?
李婉は小説『紅楼夢』の登場人物です。彼女の名前は公才で、金陵十二美女の一人です。次は、興味深い歴史の...
劉禅が蜀漢に降伏しなければならなかった3つの理由は何ですか?
蜀漢の最後の皇帝である劉禅について語るとき、多くの人は「期待に応えられなかったことに失望した」と感じ...
鍾書の「南克子・回顧昔」:詩人の俗世への執着を表現している
鍾舒は北宋時代の僧侶であり詩人であった。彼の礼儀名はシリであった。彼は安州(現在の湖北省安鹿市)出身...
水滸伝における李逵の最後の運命は本当に彼自身のせいだったのでしょうか?
李逵は『水滸伝』の重要人物であり、「黒旋風」の異名を持つ。 Interesting History ...
「衛県役所の弟に送った最初の手紙」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
魏県役所から弟に宛てた最初の手紙鄭謝(清朝)読んだらすべてを暗記できるというのは、最も役に立たないこ...
漢の武帝はどのようにして収入を増やし、支出を減らしたのでしょうか?前漢の金融改革は後世にどのような影響を与えたのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が漢王朝の財政改革についての記事をお届けします。ぜひお読みください〜課税...
三十六計略:第一計略:真実を隠す
もともとは誰にも知られずに真っ昼間に海を渡ることを意味していました。あらゆる欺瞞手段を用いた極端な欺...
リス族の食 リス族の食文化の特徴は何ですか?
リス族の文化は非常に豊かで、特に食文化は独特です。リス族は山岳地帯で暮らすことを選んだ民族であり、そ...
陸游の『沈園二詩』は唐婉への憧れを表現している
陸游は、字を武官、字を方翁といい、上書右丞の陸典の孫である。北宋滅亡の頃に生まれ、南宋の愛国詩人であ...
カザフ人はなぜミルクティーを飲むのが好きなのでしょうか?ミルクティーはどんな感じですか?
ミルクティーは新疆の少数民族の日常生活に欠かせない飲み物です。カザフスタンの人々はミルクティーが好き...
古代の軍馬はどのように名前が付けられたのでしょうか? 「Red Hare」という名前はどのようにして生まれたのですか?
古代の軍馬はどのように名付けられていたのでしょうか?「赤兎馬」という名前はどこから来たのでしょうか?...
王時珍の『迪連花・何書魚辞』:この詩は李清昭の『迪連花』に対する応答である。
王時珍(1634-1711)は、元々は王時珍と呼ばれ、子珍、易尚、如亭、于陽山人とも呼ばれ、王于陽と...