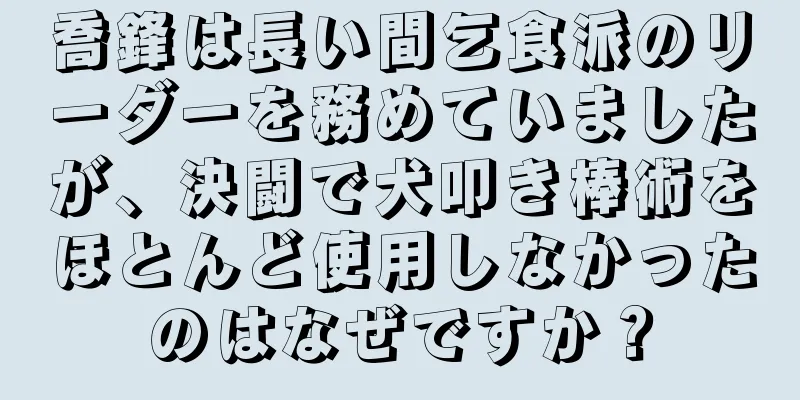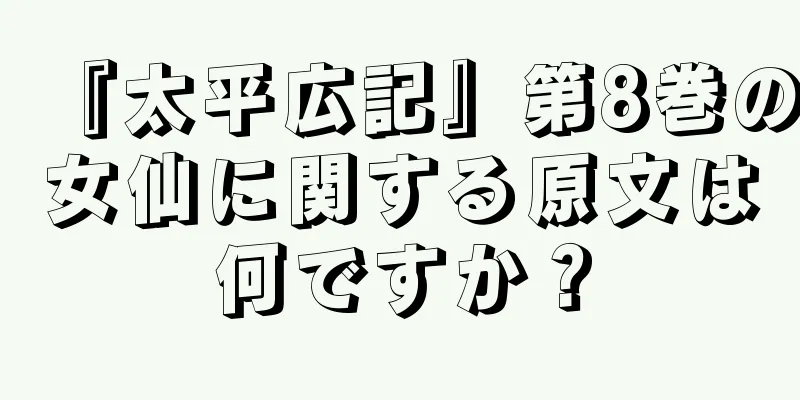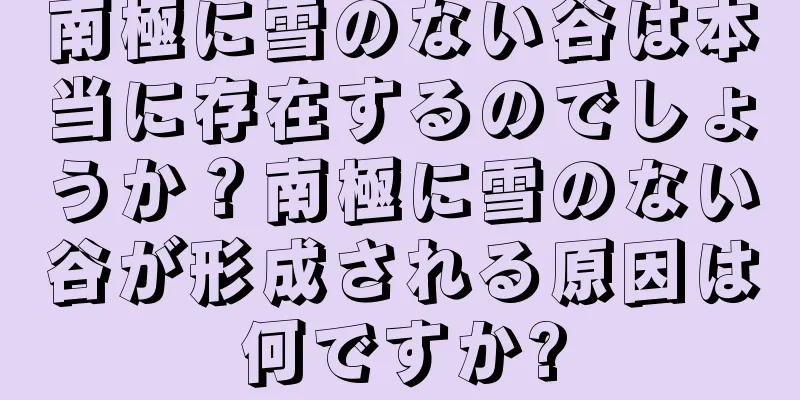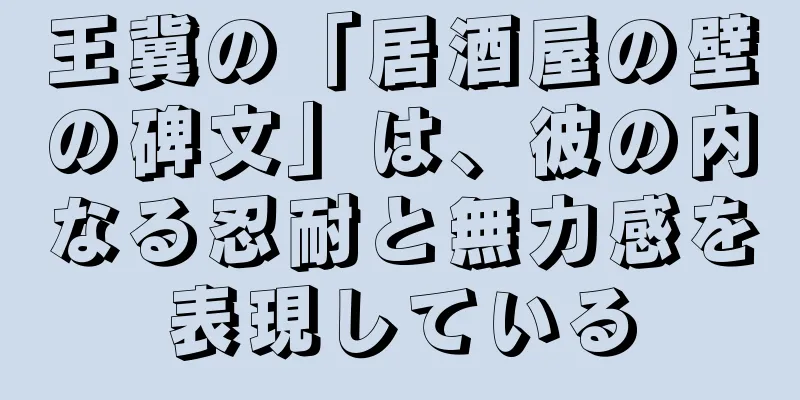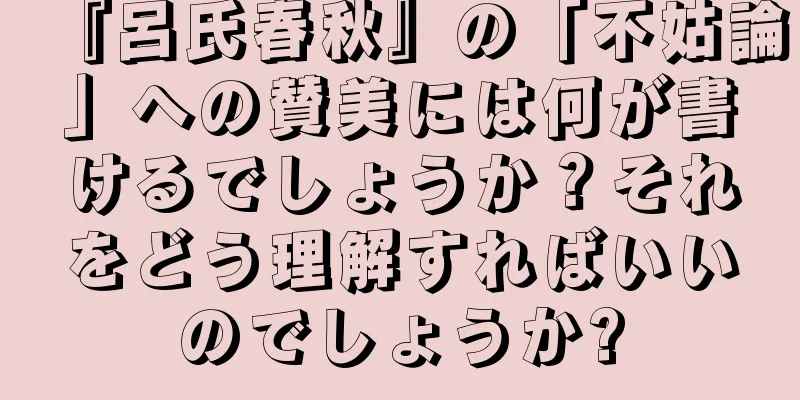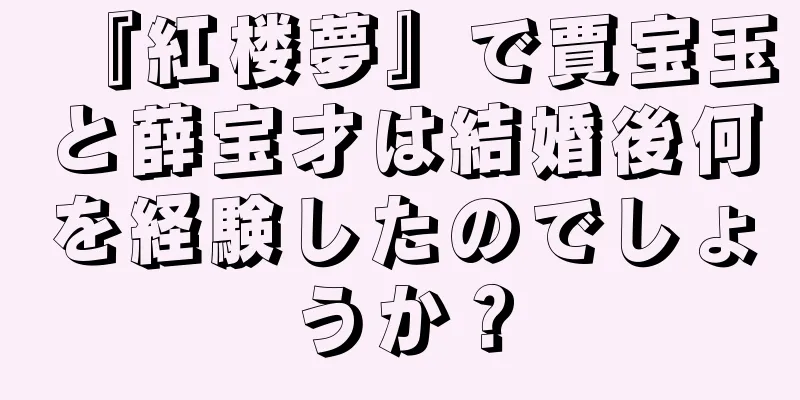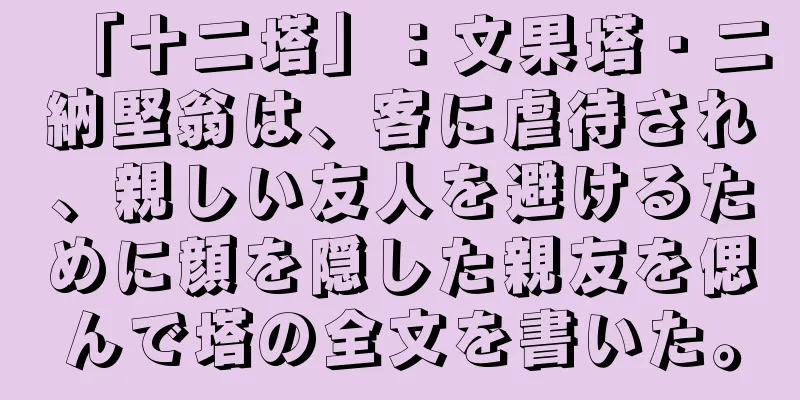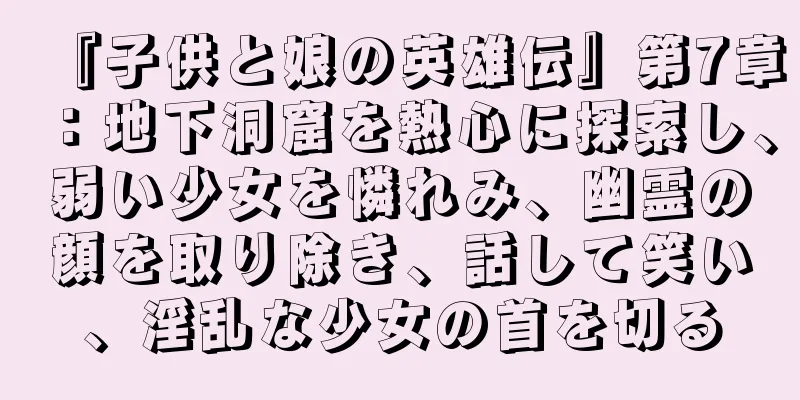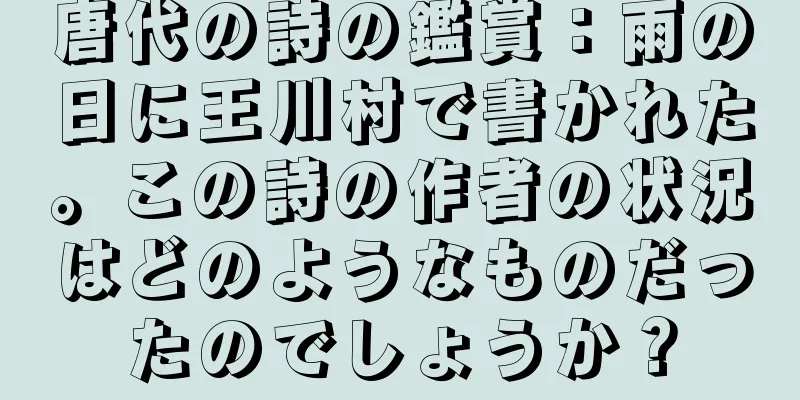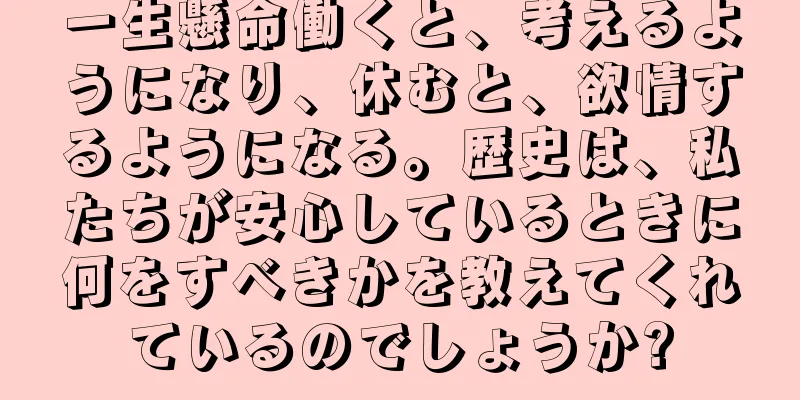実際の歴史では、東呉の将軍太史慈は張遼の手で殺されたのでしょうか?
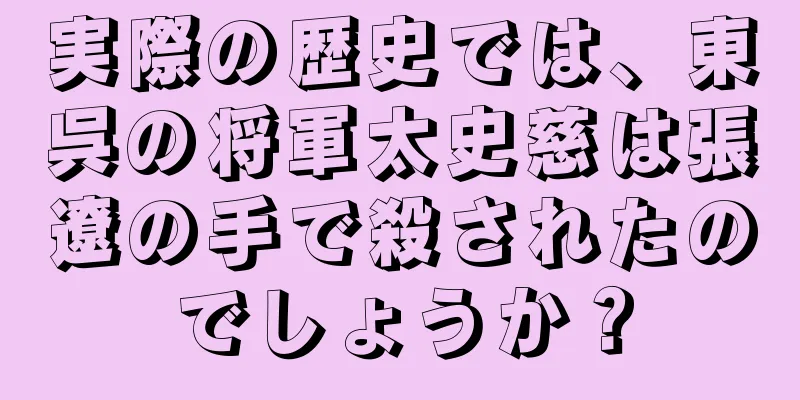
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、小説の中で太史慈が張遼の手でどのように殺されたかについて詳しく説明します。彼らは実際に現実に何か交わりがあったのでしょうか?見てみましょう! 『三国志演義』の作者は劉を称え、曹を抑圧する傾向が明らかで、本全体が劉、関、張の建国から始まり、諸葛亮の北伐で終わるほどである。これら以外の功績はほとんどがさりげなく触れられている。曹操陣営の登場人物としては、関羽の友人である張遼と徐晃も作者の承認を得ている。しかし、著者は関羽の言葉を使って、東呉のいわゆる「江表の虎臣」を、ただのネズミの集団であると表現している。しかし、東呉の将軍たちの中で、著者は依然として太史慈の勇敢さを賞賛していたが、彼は張遼の手によって殺された。では、実際のところはどうなのでしょうか? 著者がこれらを一緒に書くきっかけとなった交差点は何でしょうか? 1. 三国志演義の太史慈と張遼。 三国志演義では、曹操が陶謙を攻撃しているときに太史慈が登場します。当時、曹操は陶謙の部下が父を殺したと言い訳し、軍を派遣して徐州を攻撃した。陶謙は北海と青州に助けを求めざるを得なかった。北海の孔容は陶謙の救援の手紙を受け取った後、軍隊を派遣することに同意したが、数万の黄巾軍に包囲された。この時、太史慈は母の命により孔容を助けに来た。彼は包囲を突破し、劉備に孔容の援軍を要請し、北海の包囲を解いた。戦争後、太史慈は揚州太守の劉瑶から退去を要請された。 この戦いで、太史慈は数万の敵軍の中で一人で戦い、彼の力は止められないものでした。彼が再びコートに登場したとき、彼はリトルオーバーロードとして知られる孫策と対峙した。孫策が父の旧軍を率いて江東を占領したとき、彼は劉瑶の部下として孫策と戦った。神亭嶺の戦いでは、彼と小将軍が孫策と配下の12人の将軍と対峙した。太史慈と孫策は一対一で決闘し、戦いは数百ラウンド続いたが引き分けに終わった。 その後、劉瑶の無能さにより、彼は敗北し、太史慈は孫策によって生きたまま捕らえられました。孫策の説得により、太史慈は孫策に降伏し、江東の有力な将軍となった。彼は孫策に従って燕白湖を攻撃した戦いで目覚ましい活躍を見せ、大きな軍事的功績を残した。しかし、その後、太史慈は赤壁の戦いに一度登場したが、その活躍は以前ほど目立ったものではなかった。孫権が合肥の戦いを開始して初めて、彼は再びその勇猛さを見せた。 張遼は曹操軍の重要な将軍であった。彼はもともと呂布の部下であり、八大将軍のリーダーであった。呂布が敗北した後、張遼は劉備と関羽の支援により曹操に降伏した。張遼は曹操の軍隊の中ですぐにその能力で頭角を現した。多くの戦いで、彼が先頭に立っているのがわかります。白浪山の戦いでは、張遼が敵陣に突入し、敵の主将である達屯禅于を殺害した。張遼は合肥を守りながら、東呉の攻撃を何度も撃退し、敵を威嚇した。 張遼は忠誠心と正義感にあふれた人物です。彼は関羽の友情に感謝し、さまざまな方法で彼を守った。土山で三協定が結ばれたとき、関羽の命を救うために立ち上がったのは張遼だった。関羽は曹操の陣営にいた頃は曹操の陣営の将軍たちを軽蔑しており、張遼と徐晃とだけ仲が良かった。張遼は曹陣営の様々な勢力の間で調停を行い、関羽が多くの衝突を避けるのを助けた。また、白馬の戦いや五関六将遠征の際も張遼から何度も援助を受けた。 曹操は当然張遼と関羽の関係を知っていた。将軍を配置する際、張遼を特に淮南の前線に配置し、合肥の戦略的な位置を守り、東呉の攻勢を阻止するようにした。関羽が襄樊を攻撃し、状況が非常に危険な状態になったときでさえ、曹操は張遼を救出に動員しなかった。そのため、張遼の後半生における軍事的功績はすべて東呉に関係したものであった。小遼津の戦いで、張遼は孫権率いる10万人の呉軍を破り、孫権をほぼ捕らえた。 歴史的に、孫権と劉備の同盟が安定していた時期に、彼らは淮南に戦略目標を設定しました。孫権は合肥に対して数回の攻撃を仕掛けたが、小用津の戦いで敗北した。赤壁の戦いの際、孫権は周瑜を孫・劉連合軍の指揮下に派遣し、赤壁の曹操主力と戦わせたが、自らは軍を率いて合肥を攻撃した。 『三国志演義』では、著者は太史慈と張遼の衝突を、赤壁の戦いの後に孫権が開始した攻勢の中に位置づけています。 しかし、孫権が対峙した相手は張遼であった。この戦いでは、太史慈と張遼が一対一で戦い、二人は70ラウンドか80ラウンド戦いましたが、明確な勝敗は出ませんでした。しかし、他の将軍たちの成績が悪かったため、孫権は陣地へ撤退しなければならなかった。このとき、太史慈は戦略によって勝利しようとした。彼には、張遼の馬飼いである侯曹の兄弟である葛定という同郷者がいた。太史慈は、侯曹を内部者として利用し、内外の勢力の助けを借りて張遼を倒そうとした。 張遼が準備をして、その夜、誰も鎧を脱いで眠ることを許さないという命令を出したとは誰が知っていただろうか。このように、葛定らが混乱を起こしたとき、張遼はすぐに混乱を鎮め、彼らを捕らえて殺した。張遼もこの状況を利用し、故意に城門に火を放ち、太史慈を誘い出そうとした。その結果、太史慈は数本の矢に撃たれて敗北した。キャンプに戻って間もなく、彼は負傷により死亡した。 2. 歴史上における太史慈の死因。 実際、歴史上、太史慈と張遼の間には大きな交流はありませんでした。太史慈が張遼に殺害されるという筋書きも、史実を基に作者が芸術的に加工したものである。歴史上、張遼は部下による反乱を経験しており、その筋書きは三国志演義と似ていました。その時、張遼の部下たちが突然反乱を起こし、各地で反乱を叫んだ。張遼は反乱を起こしていない者全員に座り込んで動かないように命じた。すぐにキャンプ内の混乱は収まり、少数の反乱者は直ちに捕らえられました。この事件から、張遼の軍を指揮し、緊急事態に対処する能力がわかります。著者はこの出来事を芸術的に処理し、本に書き記した。 歴史を通じて、太史慈の能力は誰からも認められてきました。当時、遠く北にいた曹操でさえ、太史慈の名声を知っていた。彼は太史慈に特別な手紙を送ったが、手紙には特に何も書かれておらず、ただ漢方薬の当帰が少し入っていただけだった。ここでの意味は、当然、太史慈が北に戻って自分の指揮下に入ることを望んでいるということです。しかし太史慈はそれを無視し、問題は放置された。 しかし、歴史上、太史慈と張遼が出会うことは困難でした。曹操が陶謙を攻撃していたとき、張遼は呂布に従い、袁術、袁紹らの軍勢の間をさまよっていた。太史慈は徐州の戦いの後、揚州へ行ったが、張遼に会うことはできなかった。孫権が王位に就いた後、彼は太史慈を南に派遣してその地域を守らせた。建安13年、曹操は赤壁の戦いを開始した。三国志演義で太史慈が亡くなった戦いは、建安13年12月の赤壁の戦いの後に起こりました。しかし、このとき太史慈はすでに亡くなっていました。 『三国志』には、太史慈が建安11年にわずか41歳で亡くなったと記録されています。歴史の記録によると、太史慈は死ぬことを非常に嫌がり、「この世の男なら七尺の剣を持って皇帝の位に就くべきだ。今、私の願いは叶わなかったが、どうしたらいいだろうか」と言ったそうです。この記録から、太史慈は戦場で死んだのではないことがわかります。太史慈は壮年期に亡くなったこと、また亡くなった場所が江東南部の非戦乱地域であったことを考えると、重病で亡くなったに違いない。 したがって、『三国志演義』において、太史慈が張遼に殺害されるという描写は、作者による芸術的な加工である。太史慈と張遼は歴史上ほとんど交流がなく、太史慈は赤壁の戦いよりずっと前に亡くなっていたため、赤壁の戦いの後に張遼と戦うことはさらに不可能でした。 3. 張遼の死因。 三国志演義では、張遼が太史慈を待ち伏せして矢で殺した。しかし、この本の中では、彼自身も同じ運命を免れることはできない。曹丕に従って東呉を攻撃したときも、東呉に待ち伏せされた。曹丕の逃亡を援護していたとき、東呉の将軍丁鋒に腰を撃たれ、徐晃に救出された。張遼は許昌に戻った後、矢傷により死亡した。これは太史慈の死を彷彿とさせ、報復とも言える。 しかし、歴史上、太史慈が張遼に射殺されなかったのと同様に、張遼も丁鋒の矢で死亡しなかった。彼の死因は太史慈と同じで、二人とも病気で亡くなった。張遼は病死する前は曹魏の切り札であり、曹丕によって孫権を脅迫するために利用されていた。これは張遼が合肥に駐留していた間に孫権の攻撃を何度も打ち破り、東呉の君主や大臣たちが彼を恐れたためである。 特に湘水争いの後、孫権は劉備との荊州紛争を解決し、東呉最大の軍事力を集中させ、合肥に対して最大規模の攻勢を開始した。この戦いは孫権自身が指揮し、10万人の軍隊を率いて合肥を占領しようと決意した。当時、合肥を守っていた曹操軍はわずか7,000人余りで、張遼、李典、楽進の3人の将軍によって守られていました。 しかし、曹操軍の将軍たちは曹操が残した戦略に従って行動し、張遼と李典が戦い、楽進が城を守った。張遼が攻撃を仕掛けると、彼は孫権の陣営に突入し、孫権を殺戮しながらその地を攻めた。呉軍の士気が下がり、城を占領できずに撤退した後、張遼は軍を率いて再び呉軍を攻撃した。今度は、偶然にも孫権の私兵を襲撃し、孫権を生け捕りにするところだった。この戦いで張遼は孫権に深刻な精神的トラウマを残し、孫権は二度と張遼と対峙することはなかった。 歴史の記録によると、張遼は曹丕が皇帝になった直後に病気になった。曹丕は彼の状態を非常に心配し、自ら医者を派遣して治療させ、非常に優遇した。しかし、曹丕の主な目的は張遼を利用して東呉を威嚇することであった。張遼は死ぬ前の期間、健康状態が悪かった。しかし、曹丕は依然として淮南の前線を守らせ、曹休とともに船に乗せて前線の巡視に当たらせた。 孫権はこれを非常に警戒し、張遼は病気ではあるが抵抗することはできないので、皆で用心すべきだと部下に伝えた。張遼は死ぬ前に呉軍の呂範に勝利した。しかし、張遼は重病のため江都で亡くなった。彼の死後、曹丕は非常に悲しみ、涙を流して彼に康后の爵位を授けた。 結論: 張遼と太史慈は歴史上交わるところがなかったが、『三国志演義』では作者が芸術的に処理し、彼らの偉業を融合させた。実は、赤壁の戦いの前に、太史慈は東呉南部ですでに病死していた。孫権に従って合肥を攻撃することは不可能であり、張遼の矢に当たって死ぬことはさらに不可能であった。 同様に張遼も病死しており、丁鋒将軍の矢で死んだということはあり得ない。張遼は合肥に駐屯していた間、孫権の攻撃を何度も撃退した。さらに、小遼津の戦いで張遼は孫権の自信を完全に打ち砕き、孫権はもはや張遼に立ち向かう勇気を持たなくなった。張遼が死ぬまで、孫権は部下たちに病気の張遼と戦わないように警告し続けた。張遼は曹丕からも軍事的功績を賞賛され、古代の72人の名将の一人に数えられた。 |
<<: 三国志演義で、王朗はなぜ諸葛亮の手で死ぬほど怒ったのですか?
>>: 曹植は「天才」として知られていましたが、なぜ曹丕に負けたのでしょうか?
推薦する
北涼における聚屈孟勲の貢献 聚屈孟勲の政治的施策は何でしたか?
聚曲孟勲(366-433)は、臨松緑水(現在の甘粛省張掖市)出身の匈奴民族の一員であった。十六国時代...
『淮南子』の斉素詹篇にはどんな物語が語られていますか?
自分の本性に従って行動することを道と呼び、自分の本性を得ることを徳と呼びます。本性が失われたときには...
明王朝はなぜ最も偉大な王朝なのでしょうか?明王朝は世界にどのような影響を与えましたか?
明王朝はなぜ最も偉大な王朝なのでしょうか?明王朝は世界にどのような影響を与えたのでしょうか?興味のあ...
『紅楼夢』では、秦忠が亡くなる前に、親戚や友人が彼のベッドサイドに見舞いに来ていたのでしょうか?
秦中は『紅楼夢』第7話に初めて登場しました。当時、秦中は妹の秦克清の助けを借りて、賈宝玉に会うことが...
薛剛の反乱 23章: 酔って捕らえられた童成虎、二人の英雄が阻止して強奪
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
『史記』の著者、司馬遷の簡単な紹介。司馬遷が『史記』を書く決意をした物語
『史記』の著者は誰ですか?歴史記録の著者司馬遷(紀元前145年 - 紀元前90年頃)は、雅号を子昌と...
漢歓后宮はどこに建てられたのですか?漢歓后宮に関する伝説は何ですか?
漢歓后寺は、通称張飛寺と呼ばれ、四川省閘中市古城区西街59号に位置し、国家重点文化財保護単位である。...
唐代の歴史に李牧は本当に存在したのでしょうか?彼は李俊賢と同一人物ですか?
はじめに:ドラマ「武美娘伝」では、武美娘と李牧は幼なじみの恋人同士でした。ドラマ「則天武后」では、唐...
劉芳平の「春の嘆き」:詩には嘆きの言葉はないが、目に見えない形でそれが表れている
劉芳平は唐代玄宗皇帝の天宝年間の詩人。洛陽(現在の河南省洛陽)出身で、生涯は不明。彼は詩作において黄...
貴族の女性の地位はどのくらい高いのでしょうか?貴族の女性の特権とは何ですか?
皇后妃の地位はどのくらい高いのでしょうか?皇后妃の特権とは何でしょうか?皇后妃の称号は、唐、宋、明、...
『紅楼夢』で、なぜ元春は黛玉を諦めて木と石の結婚を支持しなかったのでしょうか?
賈宝玉の結婚は『紅楼夢』の主要なストーリーラインである。 Interesting History の...
劉易清の『雪歌』は女性詩人謝道雲の卓越した詩才を示している
劉易清(号:季伯)は南北朝時代の作家で、宋の武帝劉毓の甥である。劉毓は『冥界記』と『奇蹟記』を著した...
李青昭の最も古典的な詩の一つ:「切り花の梅 - 赤い蓮の香りは消え、玉の敷物は秋」
以下、興味深い歴史の編集者が、李清照の「切り梅・秋の玉座に残る紅蓮の香り」の原文と評価をご紹介します...
『紅楼夢』における青文はどのようなキャラクターですか?彼女はどれくらい葛藤しているのでしょうか?
「紅楼夢」は古代中国の長編小説で、中国古典文学の四大傑作の一つです。今日は、Interesting ...
高石の『辺境の歌』は、国に貢献したいという作者の野望を表現している。
高史は、名を大夫といい、繁栄した唐代の有名な辺境詩人であった。彼の詩は題材が幅広く、内容が豊かで、非...