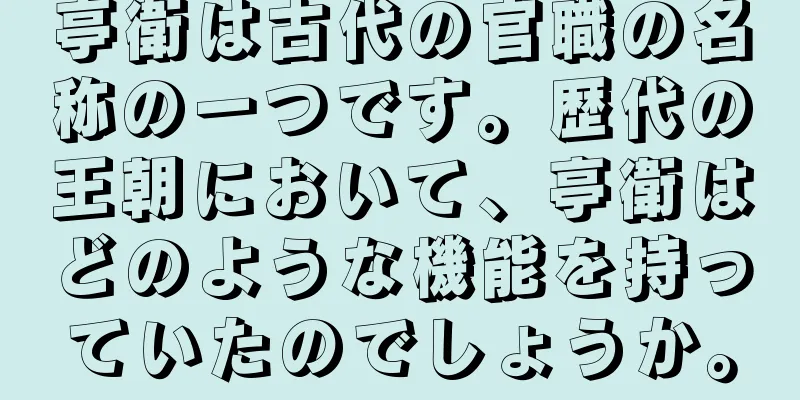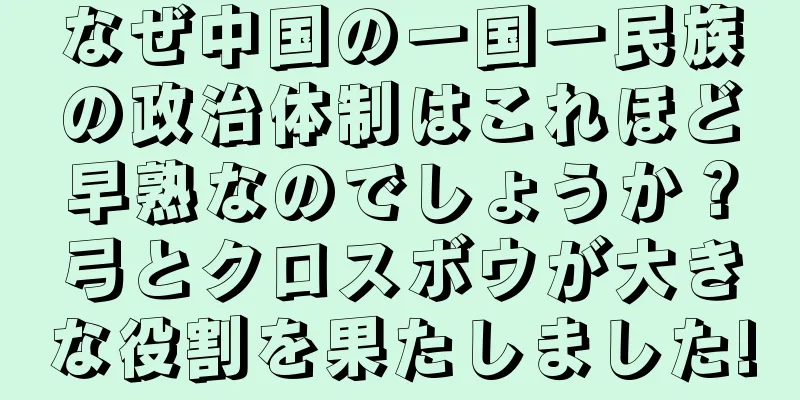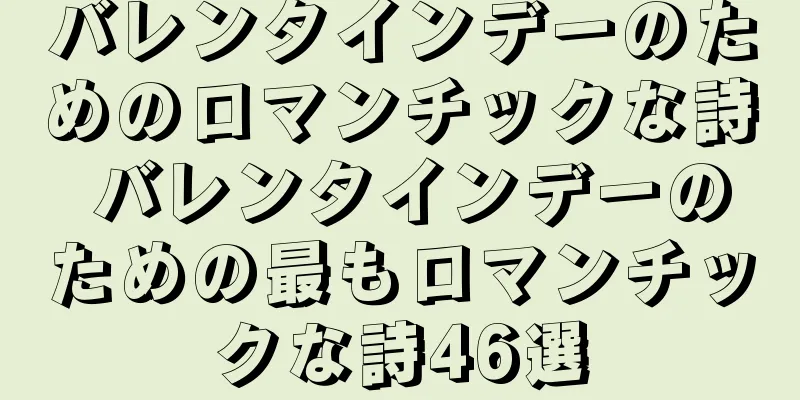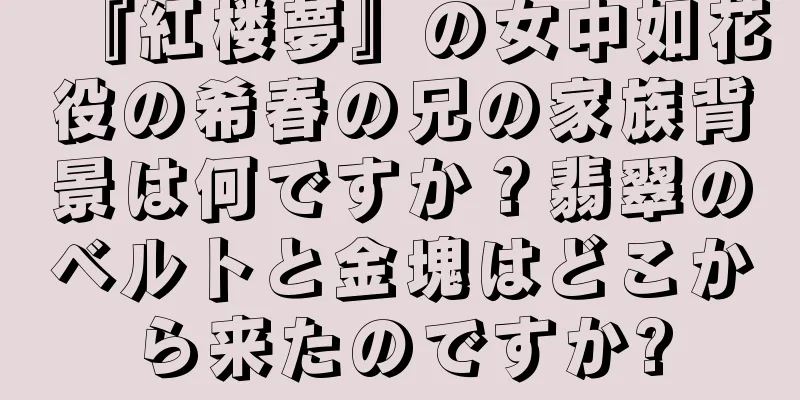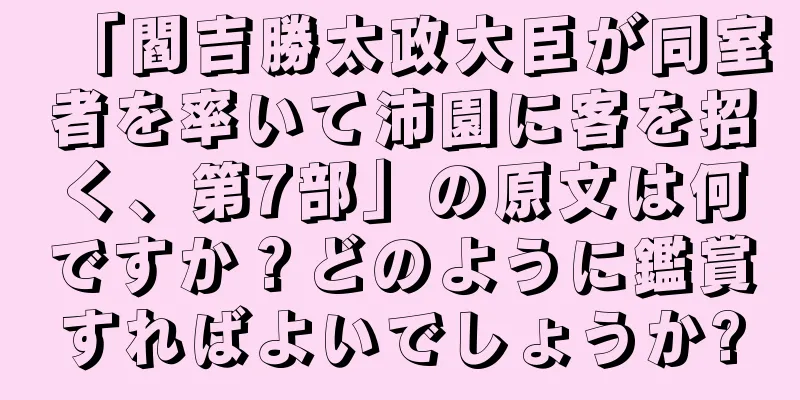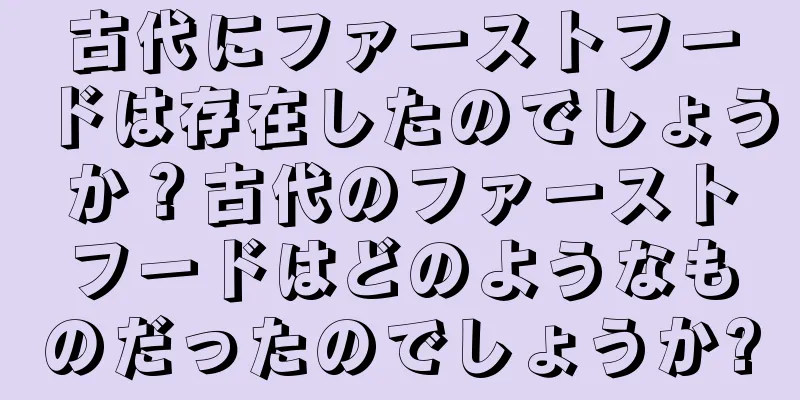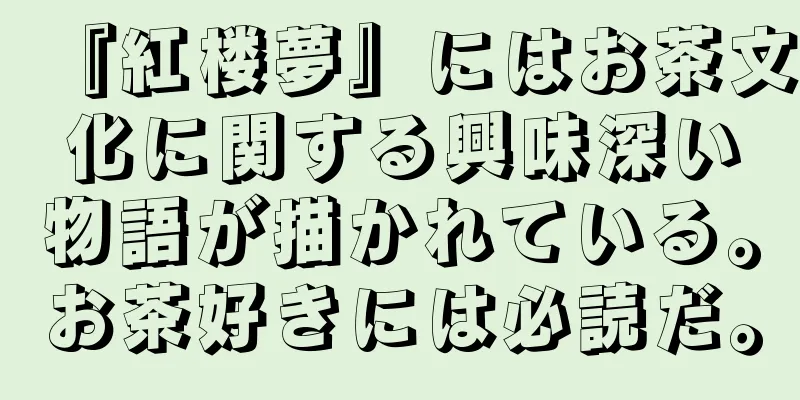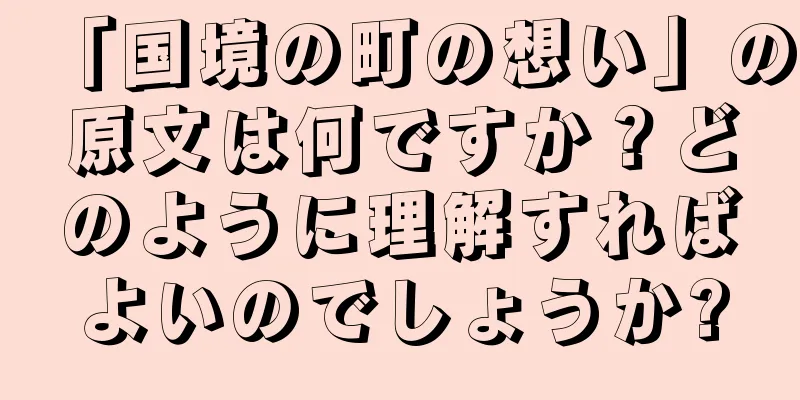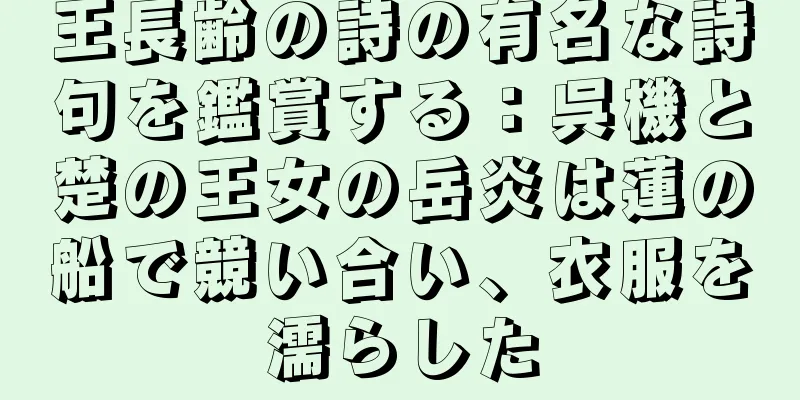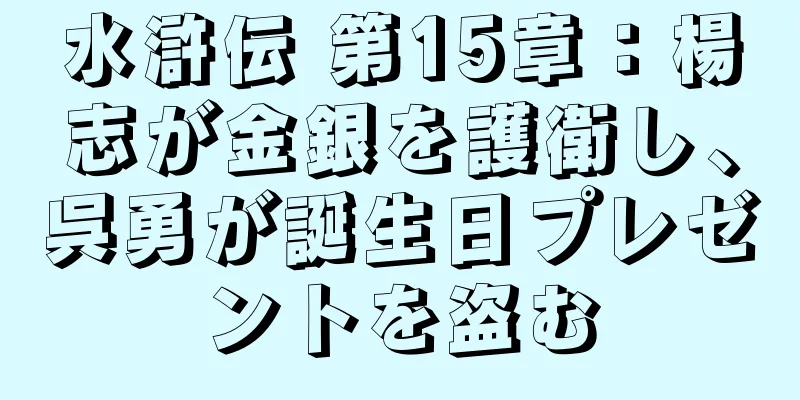『景潭道済古砦』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
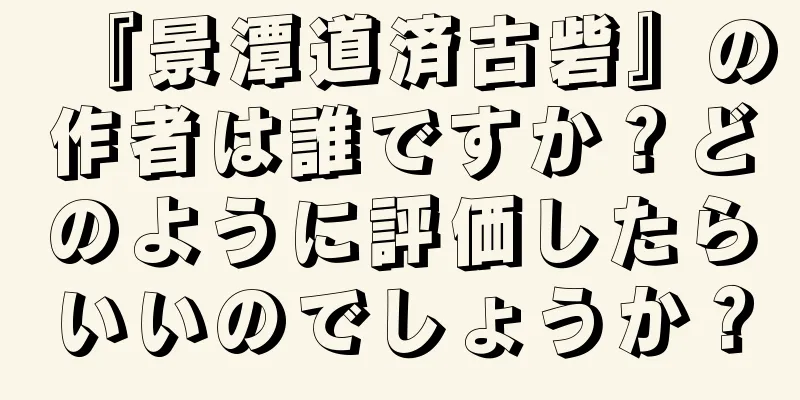
|
景潭道済の要塞 劉玉熙(唐代) 万里の長城は崩壊し、キャンプ地は荒れ果てて雑草に覆われている。 モリングにはたくさんの男女がいて、彼らは今でも白い鳩の歌を歌っています。 翻訳 劉宋時代の万里の長城は崩壊し、秋には放棄されたキャンプには雑草が生い茂ります。 モリング市の多くの男女は、深い哀悼の意を表すために今でも「白い象徴の鳩」を歌っています。 背景 宝暦2年(826年)秋、劉毓熙は賀州知事の職を解かれ、建康(現在の江蘇省南京)を経由して洛陽に戻った。詩人は南朝劉宋時代の名将譚道済の古城に登り、過去を悼み現在を嘆きながらこの詩を書いた。 感謝 詩人は譚道済の古城を見て、譚道済の不当な殺害を思い出し、感極まった。そのため、最初の2行は「万里の長城は崩壊し、陣営は荒れ果て、秋の野草に覆われている」と悲しみを表現し、譚道済の無実の殺害の深い悲しみと痛みに同情の涙を流した。しかし、悲しいながらも、譚道済を高く聳え立つ万里の長城に例えていることからも、譚道済を称賛し、賞賛する意味も込められていることがわかります。この二つの文は、風景を描写するとともに、詩人の深い悲しみを表現しています。次の「寂れた野営地、秋の野草」という文章では、目の前の荒涼とした荒涼とした光景を背景に、詩人の悲しく苦しい思いが表現されています。詩人は心の中に特別な悲しみと悲嘆の感覚を持っていたため、古い要塞に登ったとき、特に敏感に感じました。何百年も前の不当な扱いを受けた犠牲者たちの怒りの抗議がすぐに彼の耳に響きました。詩人の心の中で歴史と現実が共鳴するということは、詩人が特に強い歴史意識を持っているということではなく、むしろ詩人が歴史を使って現実を批判し、蓄積した憤りを表現し、友人を悼む必要があるということである。この詩人の友人である王書文は中唐の政治家であった。彼は唐の皇帝順宗の支援を受けて雍正改革を主導し、利益を促進し不利益を排除し、「人々を非常に幸せにしました」。その後、彼は残念ながら献宗皇帝によって「死刑」に処せられました。詩人はこれもまた自己破壊的であると信じている。 3番目と4番目の文では民謡を詩に取り入れています。著者自身の注釈によると、「歴史によれば、当時の人々は『江州で譚道済を不当に殺した白字鳩はなんと哀れなことか』という歌を歌った」とのこと。宋代の文帝は譚道済殺害の罪状を長々と列挙したが、歴史は公平であり、人々の同情は被害者の側に向けられている。このバラードはその最良の証拠です。 詩全体の含意は、歴史は王書文の無実の「不法殺人」に対して公正な裁きを下し、人々の同情は王書文の側にあるということだ。この詩では、心の中の不満を吐き出すために古代人の酒杯が使われているが、それを声に出して言いたくないというところに美しさがあり、それが詩全体を奥深く、限りない感情に満ちたものにしている。 |
<<: 「田植えの歌」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
>>: 「堤防上の三つの詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
推薦する
山西省の名前の由来は何ですか?山西省の歴史の起源を探る
おもしろ歴史編集長が山西省の起源をまとめて、皆さんに詳しく解説しています。ぜひご覧ください。山西省は...
「彭公の場合」第228章:夫婦は再会し、夫を見つけるために武術で競い合うために会った。
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
MSGを発明した国はどこですか? MSGはどのようにして生まれたのでしょうか?
約 100 年前、日本の東京大学に池田菊苗という化学の教師がいました。彼は遅く帰宅したので、妻が残り...
「南湘子:なんて良い主人」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
Nanxiangzi·良いホスト新奇集(宋代)素晴らしいホストですね。彼は理由を尋ねずにそこへ行った...
火焔山の土地神である孫悟空でさえ彼に道を譲りました。火焔山の土地神は非常に強力ですか?
火焔山の土地神である孫悟空でさえ彼に道を譲りました。火焔山の土地神は非常に強力ですか?興味のある読者...
部門38:「文心语龍」原文の鑑賞
出来事の分類については、書くこととは別に、出来事を使って意味を分類したり、過去を使って現在を説明した...
「心臓の火星」は単なる天文現象ですが、なぜ古代の皇帝たちはそれをそれほど恐れたのでしょうか?
古代中国では、多くの王朝に天文学や占星術を学ぶ場所がありました。皇帝の目には、空の星が幸運や不運を予...
唐の乱を引き起こした安禄山は1年も経たずに亡くなりました。なぜ安史の乱は6年間も続いたのでしょうか?
正確に言うと、安史の乱は8年間続いたわけではなく、合計7年2か月続きました。しかし、安禄山は757年...
唐三伝第37章:范麗華は運命を恨んで修行し、玄武関の貂師は戦いに赴く
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、『唐物語』と略され、『唐代前編』、『唐代物語』、『唐代全物語...
なぜ漢王朝は王女と結婚するのではなく、結婚したのでしょうか? 「平和な結婚」の本来の意味は何ですか?
婚姻同盟とは何かご存知ですか?次はInteresting Historyの編集者が解説します。漢代を...
『賈怡新書』第7巻の「玉成」の原文は何ですか?
唐は人が網を張っているのを見て、祈った。「天から来る者、地から来る者、四方から来る者、皆私の網に掛か...
漢代の封土令の内容と機能の分析
「使節使令」は、漢の武帝が中央権力を強化するために施行した重要な法令である。以前の教訓から、趙匡の君...
古代の言葉と現代の解釈:「陳其」という用語は歴史の中でどのように使われるべきでしょうか?
『密月伝説』では、后宮の美女たちは、夫人、愛人、美人、八男、主史、下史を問わず、誰かに会うたびに自分...
『清代名人故事』第9巻の統治の項目には何が記されていますか?
◎劉文正の遺作に書かれた劉文正公の名は同勲。山東省諸城の出身。彼の事績は国史に記録されているが、生没...
毛文熙の『甘州編・秋風強し』:読者は戦争の緊張感を感じる
毛文熙は、字を平桂といい、高陽(現在の河北省)あるいは南陽(現在の河南省)の出身で、五代前蜀・後蜀の...