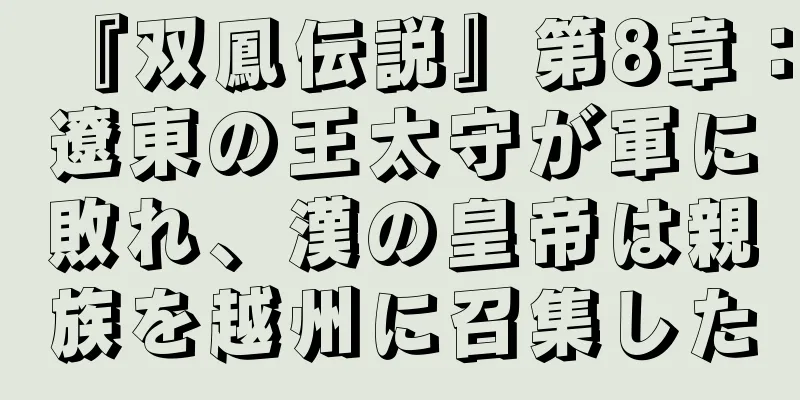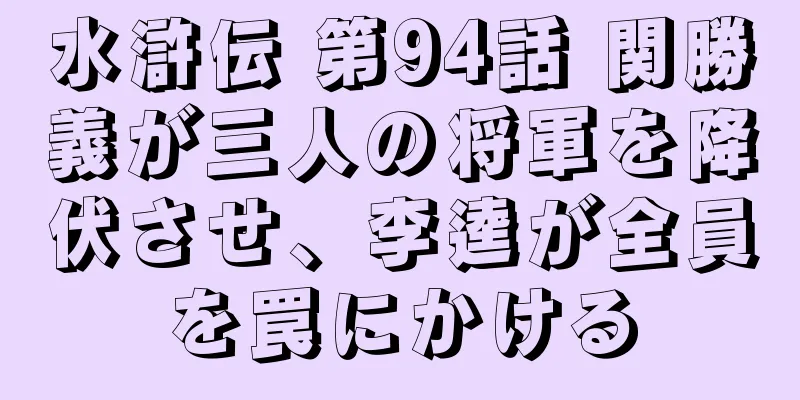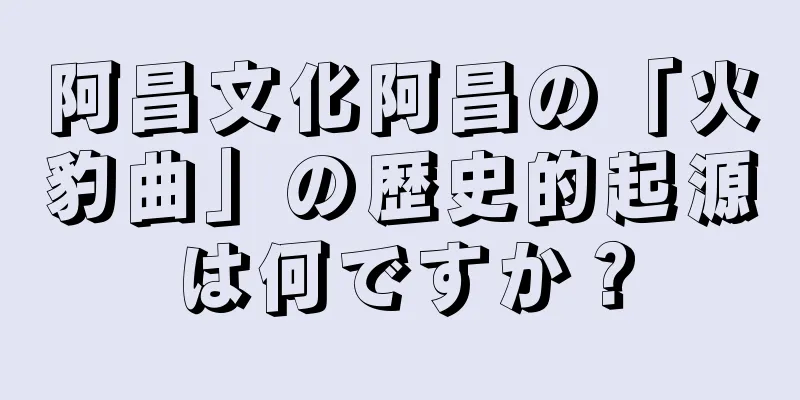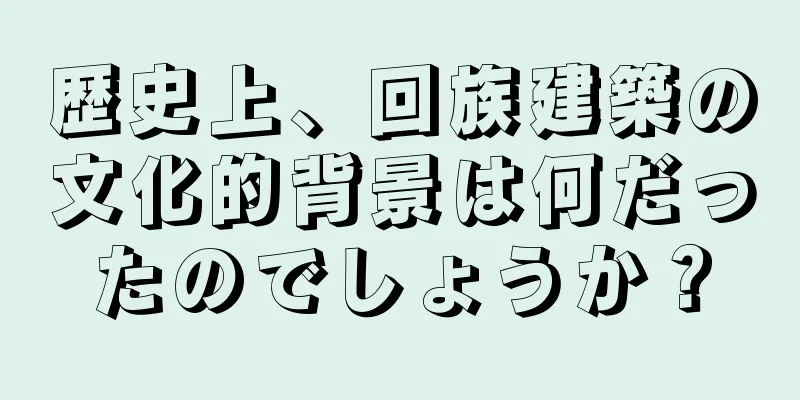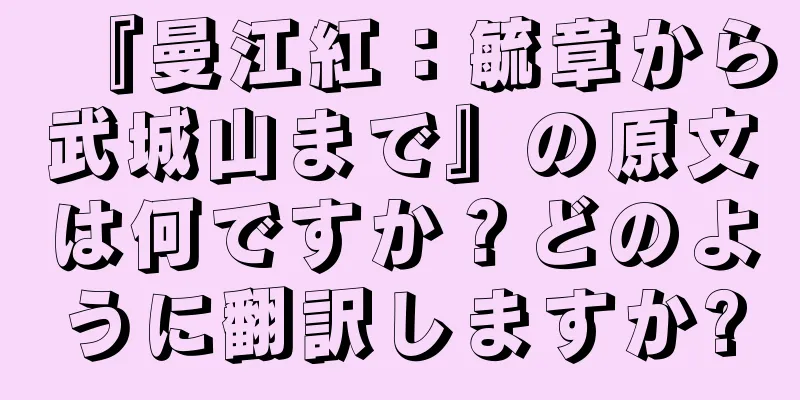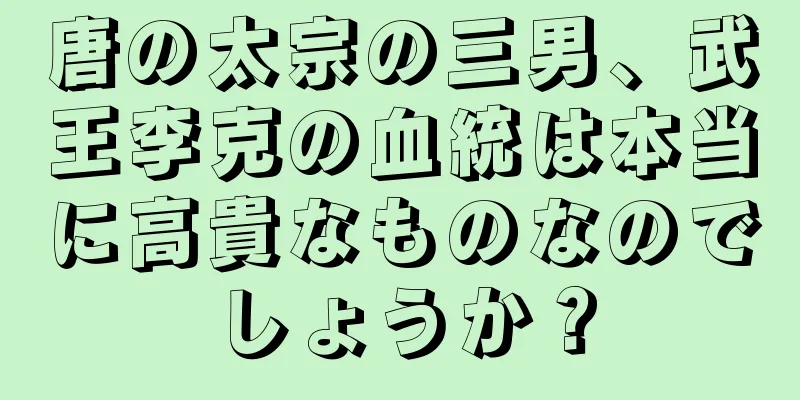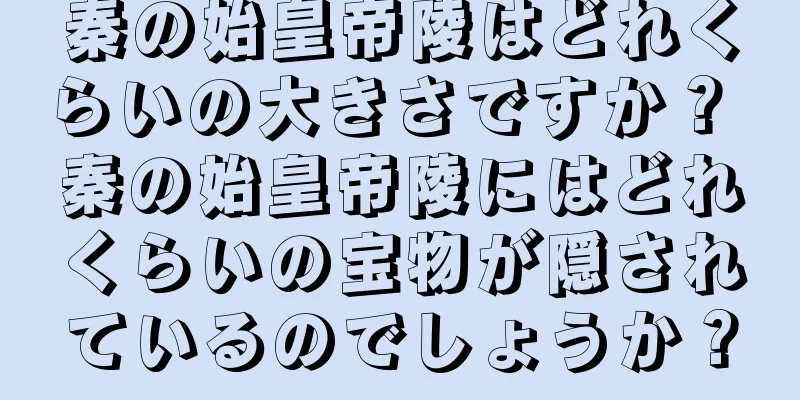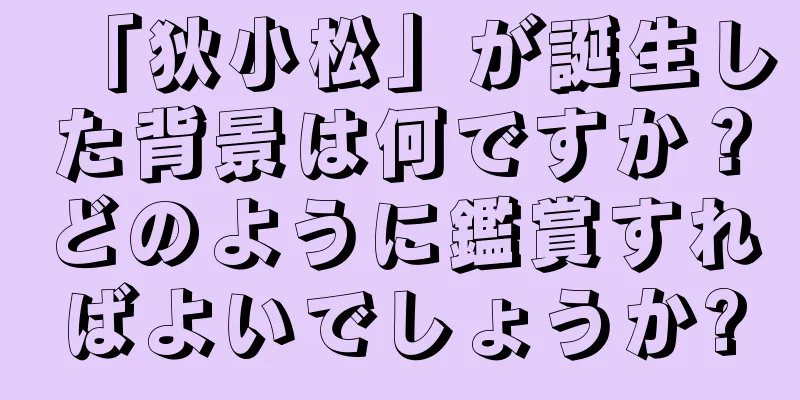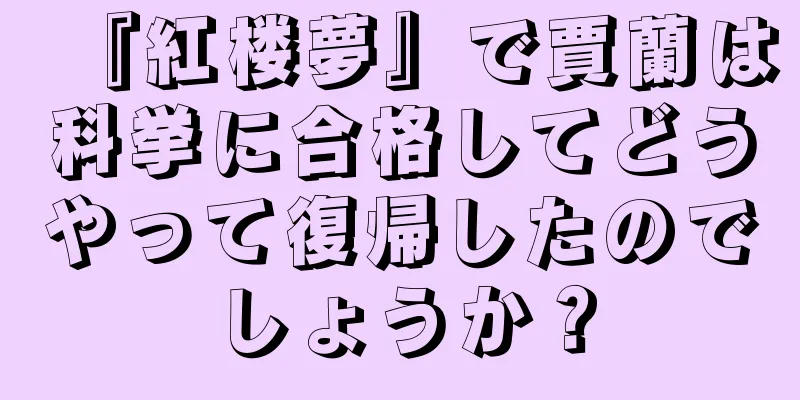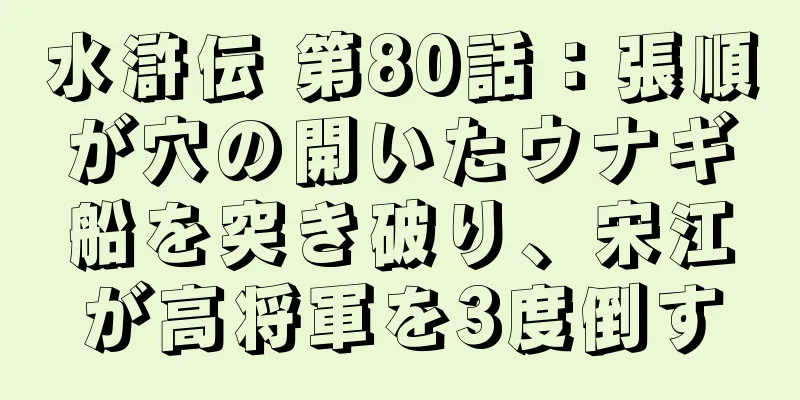王安石の『飛来峰登頂』鑑賞:作者の先見の明が表れている
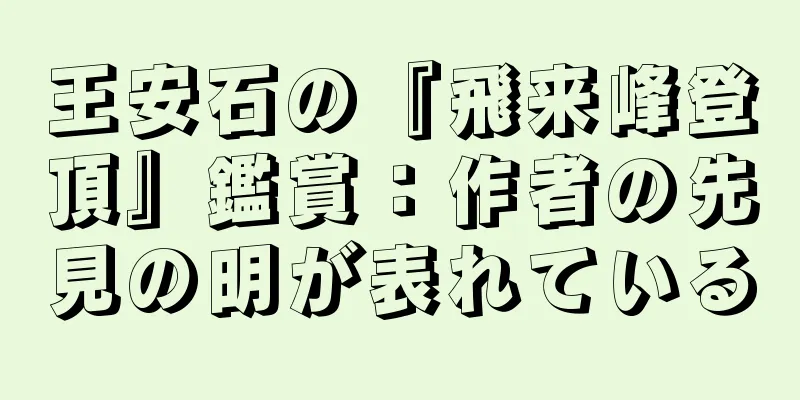
|
飛来峰登山 時代: 宋代 著者: 王安石 飛来山には高さ1000フィートの塔があり、鶏が鳴くと太陽が昇ると聞きました。 (飛来山は飛来峰とも呼ばれます) 私は最高レベルにいるため、視界を遮る雲を恐れません。 (ただ一つの理由:自分の運命) カテゴリーラベル: 哲学詩 作品鑑賞 この塔は紹興市の南にある飛来山(宝林山、塔山とも呼ばれる)にある迎天塔を指します。 文①と文②は風景を描写しています。文①は現実のもので、文②は想像上のものです。現実と想像が組み合わさって、素晴らしい風景が生まれます。 「千勒」はその高さを表します。 ③④文章は風景、感情、理性が組み合わされています。これは、作者の先見性、未来への自信、そして困難を恐れず革新を決意する政治的野心を表現した哲学的な詩です。 ----------------------------------- ユニークで満足できる場所:「飛来峰の登山」と「西林の城壁の碑文」について 唐文喜 清代の済雲は「東坡と半山は旗を対峙させているが、他の点では人々を満足させるような長所があるようだ」(『蘇軾文仲公詩評』第23巻)と述べている。済雲は、蘇軾と王安石は新法に対する政治的見解が異なり、対立しており、相容れないと思われたため、この2人の優れた人物には他の点でも人々を満足させる共通点があるのではないかと期待した。 実際、蘇軾と王安石は15歳も年齢が離れていましたが、二人にはユニークなだけでなく偶然にも多くの共通点がありました。例えば、二人とも21歳で科挙に合格して進士となり、65歳で亡くなりました。王安石は半山、蘇軾は東坡と呼ばれ、名前の意味は似ています。蘇軾は黄州の職を解かれ、汝州に赴任した際、南京を通過する途中、一ヶ月間王安石のもとに滞在した。蘇軾が『静公への手紙』で明らかにしたところによると、二人はかつて金陵で土地を購入し隣人となり、森の下で一緒に暮らすことに同意したという。二人はよく一緒に詩を歌い、似たような考えを持っていました。 『西清詩談』によると、王安石が江山にいたとき、蘇軾に自分の最近の作品『蔡の娘に』を見せた。それを読んで蘇軾は言った。「私は今、李洛の文章構造しか見ていません。」王安石はまた言った。「あなたがお世辞を言っているのではなく、私も誇りに思っています。」宋代の人の記録によると、王安石が中山にいたとき、都から人が来た。王安石は尋ねた。「蘇軾は最近何か詩を書きましたか?」訪問者は言った。「蘇軾が最近廬山を訪れ、『西林壁銘』という詩を書いたと聞きましたので、それを朗読しました。」これを聞いた王安石はうなずいて同意した。二人とも論文で有名で、唐宋時代の八大散文作家の一人です。等々。これらの類似した偶然の出来事から、半山と東坡は伝説上の人物のペアであるように思われます。証拠として、王安石の『飛来峰登頂』と蘇軾の『西林壁銘』という二つの詩を挙げます。 「飛来峰に登る」:「飛来峰には高さ1000フィートの塔があります。鶏が鳴くと太陽が昇るのを見ることができると聞きました。最高地点にいるので、雲が視界を遮っても怖くありません。」 西林の壁に刻まれているのは、「横から見れば山脈、正面から見れば峰、距離や高さによって見え方が変わる。私は廬山の中にいるので、その本当の姿を見ることはできない」というものです。 『飛来峰登頂』は王安石が30歳の時に書いた作品です。黄有二年(1050年)の夏、浙江省殷県の県令としての任期を終えて故郷の江西省臨川に帰る途中、杭州に立ち寄ってこの詩を書いた。この詩は彼が初めて官僚になったときに書かれたものです。当時の彼は若く、活力に満ち、並外れた野心を抱いていた。飛来峰に登頂したことは、彼にとって自分の気持ちを表現し、高尚な志を表明する良い機会であった。これは「万字文」の先駆けであり、新法施行の前兆であるとも言える。 『西林壁銘』は蘇軾が47歳の時に書いたものである。元豊7年(1084年)4月、蘇軾は黄州を離れて汝州に赴任した際、江西の廬山を訪れ、この詩を書いた。この詩は彼の廬山への旅を要約した最後の詩です。 『東坡志林』第七条には「これが私の廬山詩の終わりである」とある。この詩は蘇軾の入念な構成の結果であることがわかる。それはまた、世界を貫き、人生の深い意味を悟った彼の傑作でもある。この 2 つの詩は、34 年の間隔を置いて、次々に書かれました。1 つは飛来峰に登ったことを、もう 1 つは廬山を訪れたことを描写しており、この 2 つの詩は 1,000 マイル離れています。しかし、二つの詩を読み比べてみると、行間には似たような手がかりがあるようにいつも感じます。 「飛来峰登山」はよく組織化され、よく配置されています。最初の文は飛来峰の地形について説明しています。この山頂は杭州西湖の霊隠寺の前にあります。杭州地図帳によると、この山頂は天竺から飛来したため、この名前が付けられました。山頂には高さ 1,000 フィートの塔もあり、その高さを物語っています。この文は登山の危険性を説明しています。次の文章は、そのビジョンの広大さを説明しています。文章を続けて、古典的な引用を使って、「玄宗記」は言います。「淘都山に淘都という大きな木があり、枝は3千里離れています。その上に天の鶏がいます。太陽が初めて昇り、この木に輝くと、天の鶏が鳴き、世界中の鶏がそれに従います。」これに基づいて、「鶏が鳴いて太陽が昇るのを見たのを聞いた」という7つの言葉は、木が数千マイル先まで見通せるだけでなく、その声が遠くまで聞こえることも意味しており、非常に印象的です。準備段階の文章ではありますが、決して軽視してはいけません。実際の場面の言葉で高らかに歌い上げます。さらに、作者の出来事の使い方は非常に独創的です。例えば、「太陽が先に昇ってこの木を照らし、鶏が空で鳴く」という喩えは、本来は「太陽が先に昇り、鶏が後に鳴く」という意味ですが、王安石は「太陽が昇ると聞き、鶏が鳴くのを聞いた」とは言わず、「鶏が鳴くのを聞いて、太陽が昇るのを見た」と言ったので、「鶏が先に鳴いて、太陽が後に昇った」という意味になります。詩人はしばしば物事を微妙な方法で使います。他の意味があるかもしれないので、リズムを平坦にしたり、物事の使い方を間違えたりすることはできません。この文章は、感情的な言葉に直行し、「恐れを知らない」という言葉を厳しい言葉として使っており、印象的です。 「浮かぶ雲が視界を遮る」という古典的な名言。呉暁如教授の研究によると、西漢の人々は浮雲を比喩的に裏切り者や邪悪な人物を表すためによく使っていた。例えば『心于神為片』には「故に、善人を隠す邪悪な臣下は、太陽を遮る浮雲のようだ」とある。王氏の文章はこの考えを利用している。彼には「史を読む考」という題名の七字詩があり、その第二連は「当時は世がまだ暗く、人々はまだ誤りを受け入れ、当時の混乱した慣習は真実をさらに混乱させた」とある。偉業を成し遂げようとするとき、最も恐ろしいのは「浮雲が目を遮ること」と「真実が塵に変わること」であり、王安石が後に新法を推進したのもまさにこのためであった。この詩には詩人の善意が表れている。結びの文では「最高水準にある」という言葉を使って詩的な雰囲気を高め、先見の明のある精神を示しています。移行と結論の 2 つの文は、素晴らしい愛情表現であり、時代を超えて有名な一節でもあります。著者の最後の仕上げは結論にあります。状況からすると、語順は「私は最高レベルにいるから、雲が目を遮っても怖くない」となるはずですが、作者は逆に、まず結果を語り、次に原因を語っています。原因と結果の逆転は、詩の焦点が移っていることを示しています。これは詩を書く一般的な方法ですが、作者の深い構想も反映しています。詩全体から判断すると、「高いところにいるから、視界を遮る雲を恐れない」という心境は、空から高い山頂に登ることによってのみ引き起こされるが、「鶏の鳴き声を聞き、太陽が昇るのを見る」という前兆がなければ、そのような心境は引き起こされない。 「飛来峰千尺塔」に登ることでのみ、日の出を見て、天空の鶏の鳴き声を聞くという物語を体験することができ、空から飛ぶ高い峰で日の出を見て、天空の鶏の鳴き声を聞くことでのみ、世間と真実の混乱を恐れず、高く立って遠くを見る勇気と精神を養うことができます。思考は首尾一貫していて密接に関連しており、シームレスで一気に完成し、始まりと終わりを考慮して全体を形成します。 「西林寺壁銘」は蘇軾が廬山を訪れた際に西林寺の壁に書かれたものである。西林は晋の時代に江州の太守であった陶凡によって建てられた西林寺で、廬山の重要な景勝地の一つです。蘇軾の『東坡志林』第七条「廬山遊記」には、「私は十日余り山の北と南を行き来し、それは珍しい経験だと思った」「最後に宗老と一緒に西林に旅し、別の詩を書いた」とあり、この詩に言及している。彼は廬山への旅について七つの詩を書いたが、これが最後の詩となった。この詩は廬山の全体像を描写しています。作者は西林寺を拠点としており、詩全体は水平方向と上空からの眺めを描写しています。最初の文は廬山の水平と側面の景色を描写しています。廬山をまっすぐに見ると、奇妙で素晴らしい景色が見えます。要約は正確かつ的確で、描写は繊細かつ鮮やかです。これは基本的に廬山の山頂の方向です。南山玄の『干通録』によると、廬山には7つの主要な山脈があり、すべて廬山の東に面し、峰に合流しています。そのため、姚寛の『西溪叢語』には、「蘇東坡の『横から見れば山のよう、前から見れば峰のよう』という一文には長い歴史があることを知っている」とあります。次の一文は、廬山の山岳地形を遠くから描写し、絶えず変化する廬山を見下ろして、最初の一文の未完成の景色を埋めています。導入と展開の二つの文章が、真実味を失わずに情景を描写し、表現しにくい情景をあたかも目の前にあるかのように見せていることがわかります。それは風景の描写であり、感情の描写でもあります。かつて、この二つの文に対する注釈の中には、無理があるものもあった。例えば、石元之の『石の蘇軾詩注』第21巻では、『華厳経』から「一粒の塵の中に、大小の仏の様々な違いがあり、塵の数ほどある。その平らさ、高さ、深さは皆異なっている。仏はそこに行き、それぞれに法輪を回す」という言葉を具体的に引用している。これは、「距離、高さ、深さはすべて異なっている」という文の由来を証明している。例えば、『冷斎夜話』には、この詩に対する黄庭堅のコメントが記録されている。「この老人は、四方八方に般若を語り、余計な言葉は一切使っていない。筆先に舌がなかったら、どうしてこれほど素晴らしいものが生まれ、後世に伝わらなかっただろうか。」これは、「痒いところに手が届くが、的を射ていない」別の種類の賛辞である。このような詩評や注釈は読む価値がない。注釈者たちはずっと前からこれを否定し、「このような詩はすべて瞬間的なひらめきの産物だ。仏典を念頭に置いてから詩を詠んだのでは、意味が薄れてしまう」と信じている。(王文高『蘇文忠詩集注』第23巻) 移行と結論の2つの文は感情表現として使われている。著者は論理的な文章で詩の中に哲学を取り入れ、人々の主観的認識には限界があるという共通の概念を表現している。たった14語で人間の本質と人生の真実のすべてを表現しているため、この詩は出版されるや否や暗示となり、エリート層から庶民まで幅広く引用されました。詩全体を見ると、第二連句の概念は第一連句の風景描写と完全に融合し、敷き詰められている。アイデアは幻想的で壮大な想像力から生まれ、一方、理性に対する深く時代を超えた関心は、自然に新鮮で適切な機知に富んだ発言を刺激します。そのため、歴代の評論家たちはこの詩の哲学の深さを称賛し、非常に高い評価を与えてきました。例えば、最も有名な評論家は『宋代詩精華』第2巻で「この詩には、これまで誰も触れたことのないような新しい考えがある」と述べています。現代の『唐宋代詩探』では、この詩は「現在の情景を描写するのに優れており、物質世界を超えた原理も見事に伝えており、両者がシームレスに融合している」と述べています。禅の詩とは比べものにならないほどで、その評論は極めて正しく、当然のことのようです。 二つの詩を比較すると、二つの詩は構想、構成、文の構造が似ているだけでなく、一致しているという結論を導き出すことができます。詩の題名から判断すると、王の詩では動詞「登」が、蘇の詩では動詞「题」が使われており、どちらも地名を目的語として用い、動詞-目的語構造の句を形成している。どちらの詩も形式から判断すると、風景を描写した七字四行詩である。全体の意図と構想から判断すると、王の詩は風景の描写を通じて彼の崇高な志を表現し、すべての文章は首尾一貫しており、蘇の詩は風景の描写を通じて真実を表現し、すべての単語は繊細であり、どちらも詩の文脈に感情と理性を組み込んでいます。構成の観点から見ると、最初の連句は風景を描写し、2番目の連句は感情を表現しています。表現スタイルから判断すると、2つの詩で使用されているいくつかの単語はほぼ同じです。例えば、王の詩では「恐れない」を前文と次文のつなぎとして使っていますが、蘇の詩では「知らない」を前文と次文のつなぎとして使っています。それぞれの考察は極めて安全です。例えば、どちらの詩も「ただ」を結論の導きとして使っています。また、王の詩「最高レベルにいる」も蘇の「この山にいる」と同じです。この観点から見ると、2 つの詩の類似点と一致点は非常に類似しており、まったく同じであると言えます。偉大な心は同じように考えます。なんと似ているのでしょう。世界にこのような素晴らしい人々や詩があるのは素晴らしいことではないでしょうか。 |
推薦する
清代の画家朱達が描いた「水樹図」の芸術的価値はどのようなものでしょうか?
清代の画家朱達が描いた「清華水樹図」の芸術的価値を知りたいですか?この絵は八大山人の一貫した画風を継...
中国の神話では、水蓮はどのようにして人工的に火を起こしたのでしょうか?
古代我が国には、人類の生活が原始的な集団から初期の氏族共同体へとどのように進化したかについての伝説が...
岑神の古詩「南西別夜」の本来の意味を理解する
古詩「南渓荘」時代: 唐代著者: セン・シェン家は緑の山々を背景に建てられており、窓は緑の野原に面し...
鏡の中の花 第53章:過去の王朝を論じ、南北を分け、古い歴史を書き、過去と現在を結びつける
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
『世界物語新説 賞賛と報奨』第 111 条の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
有名な古代書物『新世界物語』は、主に後漢末期から魏晋までの著名人の言行や逸話を記録しています。では、...
「西湖を夢みて」の原文は何ですか?この古代のテキストをどのように理解すべきでしょうか?
【オリジナル】私は死後28年間、西湖を離れていた。(1) しかし、西湖は毎日私の夢の中に現れ、そして...
三勇五勇士第52章:愛と結婚の約束をくれた方さんに感謝し、手紙を書いてくれた寧さんに感謝する
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
『何新浪:陳振州子華を送る』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
新郎おめでとう:陳振州子華さんにお別れ劉克荘(宋代)神州路の北を望む。平張さん、この公的な問題にどう...
フオ家はどのようにして壊滅的な災害に見舞われたのでしょうか?漢の宣帝を廃位するためにクーデターを起こそうとした
宣帝がまだ平民だったころ、彼にはすでに二度処刑された下級官吏の徐光漢の娘である徐平君という妻がいた。...
「春園異変」をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
スプリングガーデン王維(唐代)夜中に雨が降ったら軽いサンダルを履き、春の寒いときにはぼろぼろのローブ...
『韓非子』の五蘊とは、どのような5種類の人々を指しますか?
『韓非子』の五蘊とはどのような人物でしょうか?これは多くの読者が知りたい質問です。次の『興味深い歴史...
『魯陽雑録』の記録によると、唐代に鯉を食べることが禁止されていたのはなぜですか?
李は唐の姓であったため、唐代には鯉を食べることは禁じられていました。鯉を捕まえたら放さなければなりま...
呉三桂は清朝に降伏したのに、なぜ30年以上経って再び反乱を起こしたのでしょうか?
確かに中国の歴史上、国を裏切り敵に降伏した人物は数多くいるが、呉三桂のように何度も国を裏切った人物は...
唐代の重要な軍事書『太白陰経』全文:陰謀術数
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
岑申の『山荘春歌二首』はどのような状況で書かれたのでしょうか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
坤申の「山屋春二首」は、Interesting Historyの編集者が関連コンテンツをお届けします...