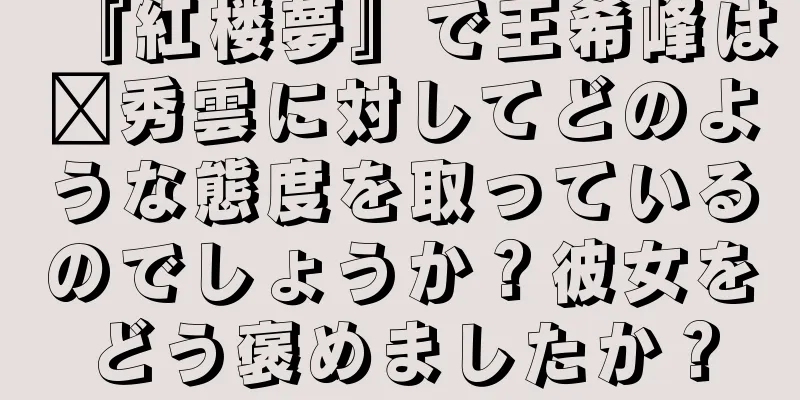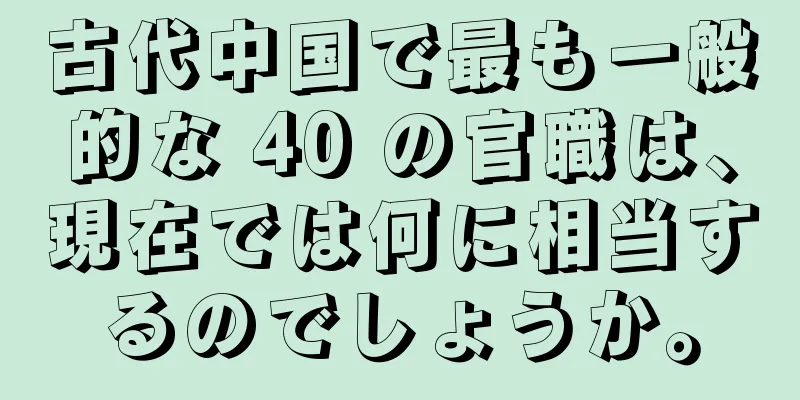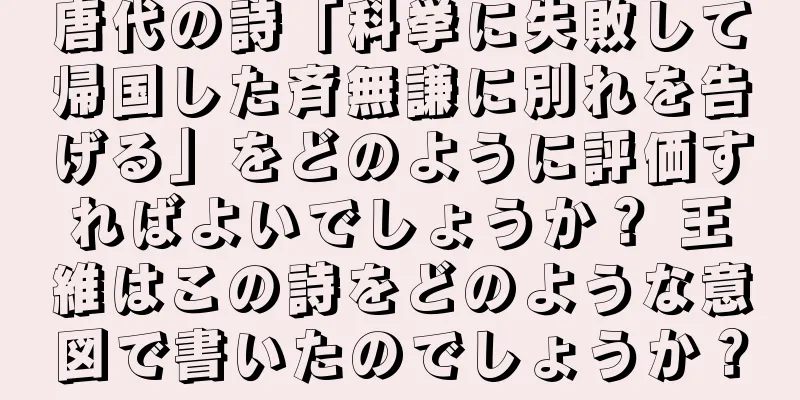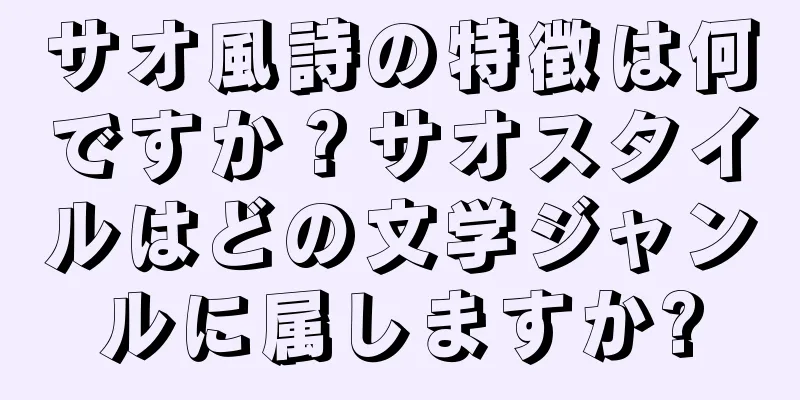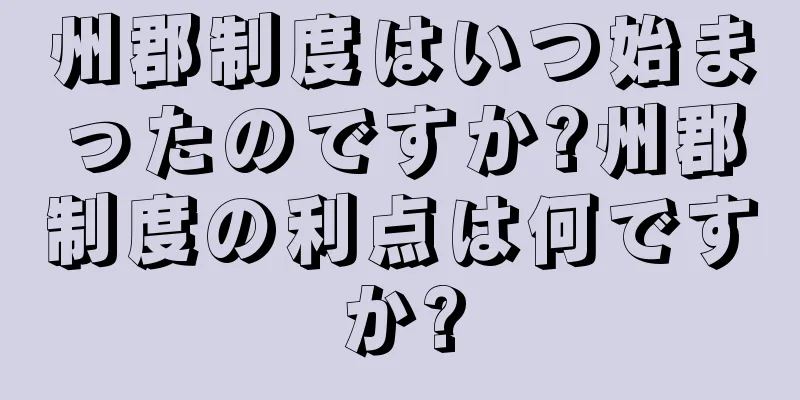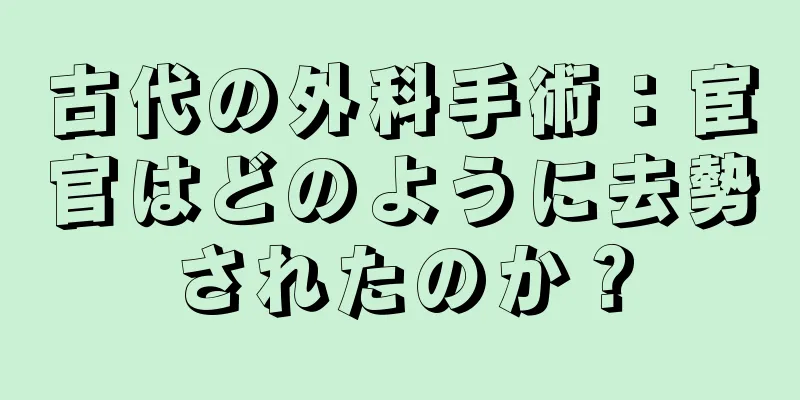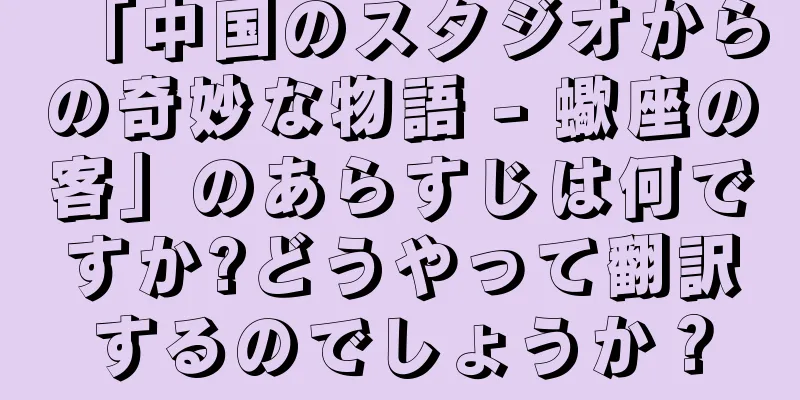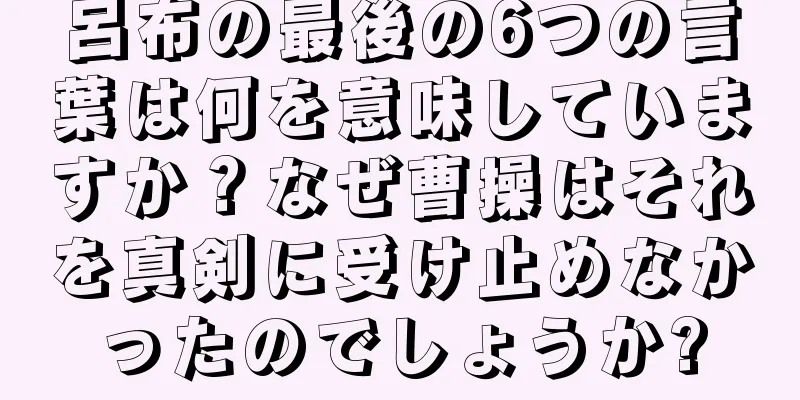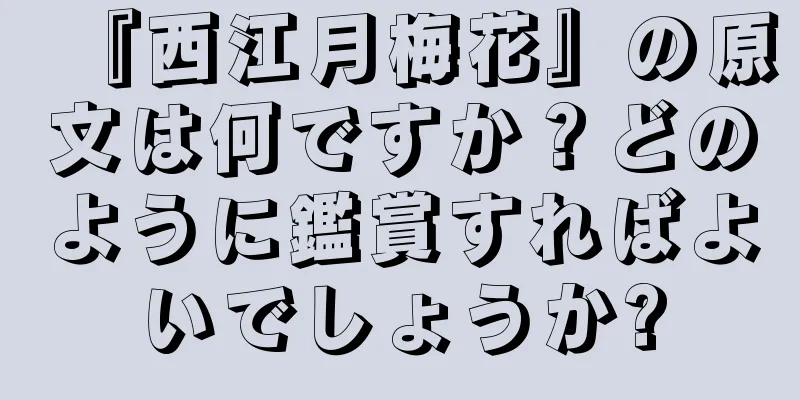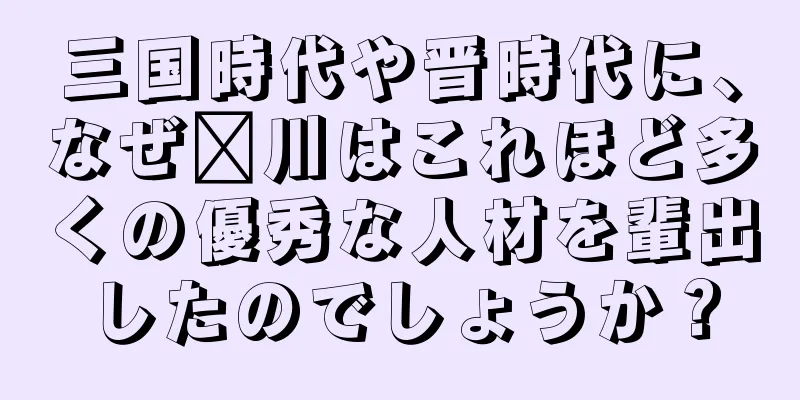清代の詩『鶉空』の「別れの悔い」を鑑賞する。この詩をどのように理解すべきか?
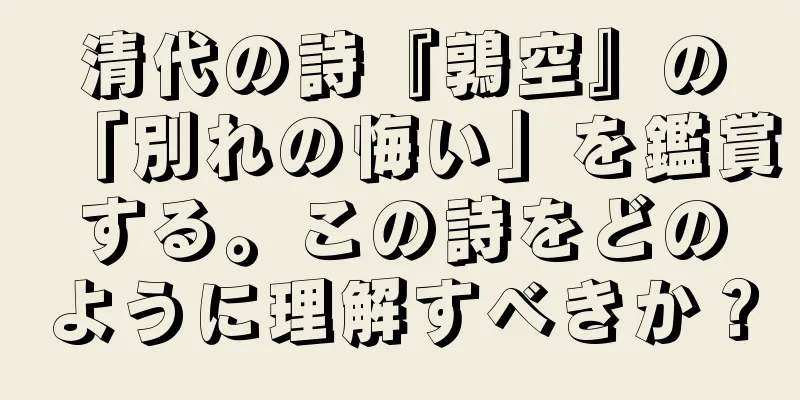
|
ヤマウズラ天:礼遍[清代] 納藍星徳、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう! 彼女は彼に背を向けて恥ずかしそうなふりをしながら、手で梅の花をつまんだり肩をたたいたりした。別れの悲しみを恋人に伝えたいけれど、彼が来れば悲しみは消えてしまう。 雲は軽く、水面はゆったりと流れています。笛の音が空っぽの建物を閉ざす。いつになったら私たちは、崩れた岸辺の柳に囲まれた船に乗って、月明かりの下、春の小川を一緒に航海するのでしょうか? この短い詩は、女性のイメージと心情を通して「別れの憎しみ」を表現しています。すべて平易な言葉で書かれており、装飾は一切ありません。非常にシンプルで美しく、一種の短歌です。最初の部分は、過去の情事を思い出し、繊細で用心深く内気な女性のイメージを描いています。感情は微妙ですが、言葉や文章の選択は、意図的に作られたという印象を与えません。 「女性に背を向けて、恥ずかしがっているふりをしている」の「インイン」という言葉は、実に生き生きとしていて精巧で、詩の中のヒロインの美しく感動的な優雅さと態度を凝縮しています。 『十九古詩集 河畔の青草』に「娘は上の階で優雅に、窓辺では明るく澄んでいる」という一節があります。ここでの「英英」という言葉の使用は、歌詞のヒロインが『十九古詩』の繊細で軽やかで輝く女性と同じイメージを持っていることを反映しています。 「梅の花を押して肩を打つ」は、ナランの詩のスタイルを最もよく表す言い換えです。女性は繊細な手で梅の花を摘み、恋人の肩に投げつけた。怒りと恥ずかしさが入り混じった表情は、とても魅力的だった。最初の4行は、李游の詩「刺繍のベッドに艶かしく寄りかかり、赤い毛皮を噛んで、微笑みながら恋人に吐きかける」(『一ヘクタールの真珠:朝の化粧後』)に描かれた場面と非常によく似ていますが、香りと優雅さに新鮮さを感じ、優美さにハンサムさを感じます。 詩の後半では、見聞きした光景、薄い雲、ゆったりとした水面、耳に響く笛の音などが描写され、別れの悲しみがさらに強調されています。 「フルートが空っぽの屋根裏部屋に鍵をかける」は、空っぽの屋根裏部屋に残るフルートの音を表現しています。 「ロック」という言葉は、まるで停滞しているかのような、終わりのないフルートの音を表現しています。笛の音と梅の花は、詩の中では昔から寂しさを表すイメージとして描かれてきました。梅の花を眺め、笛の音を聞くことは、古来から多くの人々の心を動かしてきました。唐代の崔道栄に「梅の花」という詩がある。「数枚の花びらが雪に覆われ始め、一輪の花は描きにくい。香りは独特の魅力があり、澄んでいて寒さを感じない。横笛は悲しく聞こえ、斜めの弦は病んでいるようだ。風が私の気持ちを理解しているなら、どうかそれを壊さないでください。」笛の音はいつも冷たく空虚で、この時は別れが迫っていて、二度と会う機会がない。悲しくないわけがない。結びの文では、想像上の言葉を使って月夜の春の美しい情景を描き、この想像上の情景を使って詩人の分離感と憎しみをさらに表現しています。 「いつになったら、壊れた岸から柳が垂れ下がる小舟に乗って、月明かりの下の春の小川を一緒に航海するのだろう?」想像上の美しい風景は、別れの痛みをさらに耐え難いものにします。 昔は今とは状況が違っていました。旅行は不便で、一度別れたら一生二度と会えないかもしれません。時間、距離、生死、どんなに強い愛でも、このような困難に直面しなければなりません。皇帝となった李玉でさえ、「別れの悲しみは春の草のように、どんどん遠ざかっていく」と言うだろう。もしそれが那蘭だったら、彼はさらに無力だろう。 |
<<: 清代の詩『臨江仙・寒流』の鑑賞:この詩をどのように理解すべきか?
>>: 清代の詩『迪連花・有道洛陽増哲』を鑑賞する、この詩をどのように理解すべきか?
推薦する
曹操は陳林を見て非常に怒ったが、なぜまだ陳林に重要な任務を任せたのだろうか?
『三国志演義』の誇張表現のせいで、曹操は裏切り者で疑り深い人物だったと考える人が多い。しかし、実際に...
『太平広記』巻73、道書IIIの原文は何ですか?
周献哲、王昌業、徐忠、鄭俊成、宜仁、李楚世、羅玄素、趙曹、崔玄良周 仙哲唐代の則天武后の治世中、宰相...
『新唐語』第9巻の「忠勇」の原文は何ですか?
李玄通は定州に送られ、劉黒太に捕らえられたが、劉黒太は彼の才能を評価し、将軍にしようとした。彼は言っ...
「桃の花切手」は全部で何枚ありますか?切手の価格に影響を与える要因は何ですか?
「桃花切手」は全部で何枚あるのでしょうか?切手の価格に影響を与える要因は何でしょうか?『Intere...
『紅楼夢』で、賈屋敷に住む気前の良い林黛玉の月々の手当はいくらですか?
『紅楼夢』に登場する賈家の娘たち、応春、丹春、希春、岱玉、宝仔などの月々の手当は、二人の側室、趙叔母...
伝統的な寺院の祭りの起源: 古代の寺院の祭りはどのようにして始まったのでしょうか?
寺の縁日の由来:寺の縁日、別名「寺の市場」や「お祭り会場」。これらの名称は、寺社の縁日の形成過程にお...
世界第8番目の不思議:秦の始皇帝陵の地下宮殿はどのように建てられたのか?
なぜ排水施設が先に建設されたのか?秦嶺地域の地下水データによると、地下水の第1層は地表から約15メー...
解華は中国絵画のジャンルの一つです。晋の時代の顧凱之は何と言ったでしょうか?
境界画(jièhuà:「境界を描く」という意味。「華」は入音と発音される)は、中国絵画の非常に特徴的...
李曽波の『秦元春:李玉岱公を送る』:現実に対する極度の憤りが込められている
李曽伯(1198-1268)、号は昌如、号は克斎。彼はもともと潭淮(現在の河南省沁陽市付近)の出身で...
宋代の詩人、楊万里の『桑茶洞』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
楊万里の『僧刹坑道にて』について、次の『Interesting History』編集者が関連内容を詳...
『水滸伝』に登場する108人の英雄のうち、宋江によって一族を滅ぼされたのは誰ですか?
『水滸伝』では宋江は「胡宝儀、時雨、孝義の黒三郎」と呼ばれています。このことについてよく分からない読...
黎族の人々はなぜ自分たちの一族の紋章を体に刻むのが好きなのでしょうか?
李のタトゥーに関する文献は数多く残っており、明・清の時代には記録の数も増え、内容もより詳細になり、タ...
歴史上、帰路の旅を描いた詩は何ですか?そこにはどんな感情が込められているのでしょうか?
歴史上、帰路を描いた詩は数多くあります。Interesting History の次の編集者が、関連...
胡家将軍第34章:龐煕との天頂山の戦い、そして道士少年の魔法
『胡氏将軍伝』は清代の小説で、『胡氏全伝』、『胡氏子孫全伝』、『紫金鞭物語』、『金鞭』とも呼ばれてい...
李世民が冥界に入ったとき、彼は非常に恐れ、地獄の王が彼に頭を下げました!李世民の正体は何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が李世民の正体についてお話しします。気に入って...