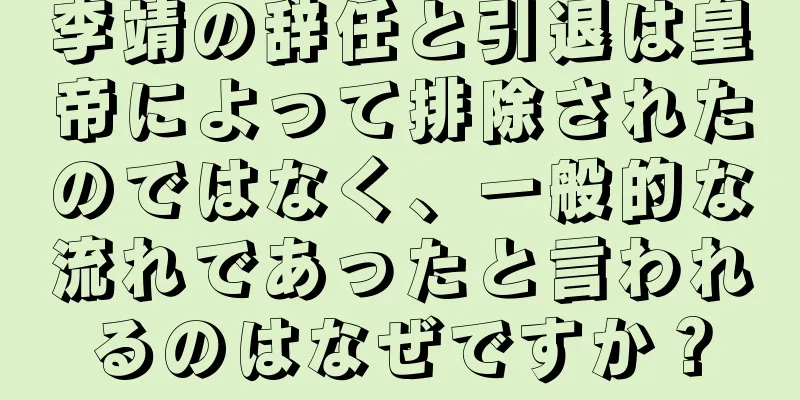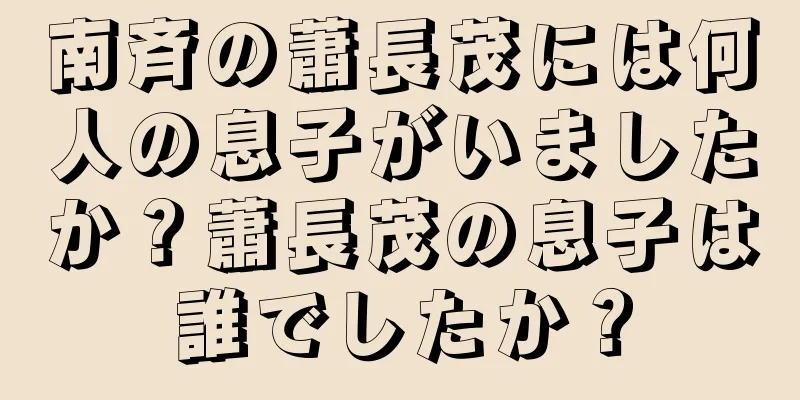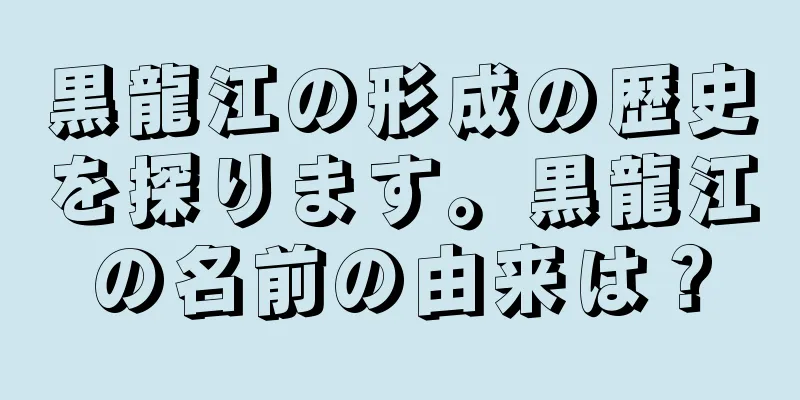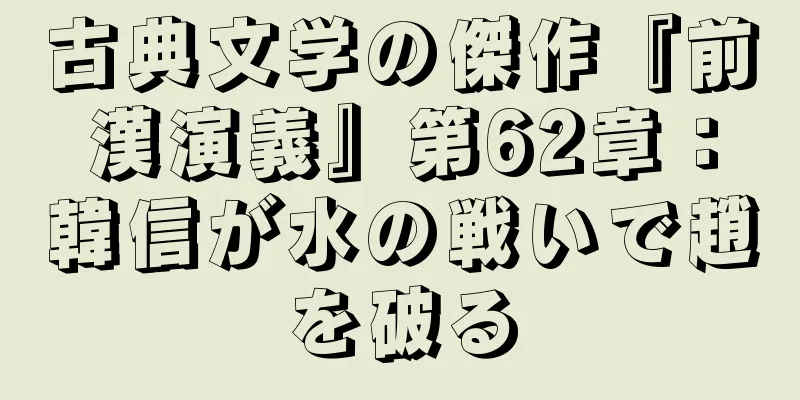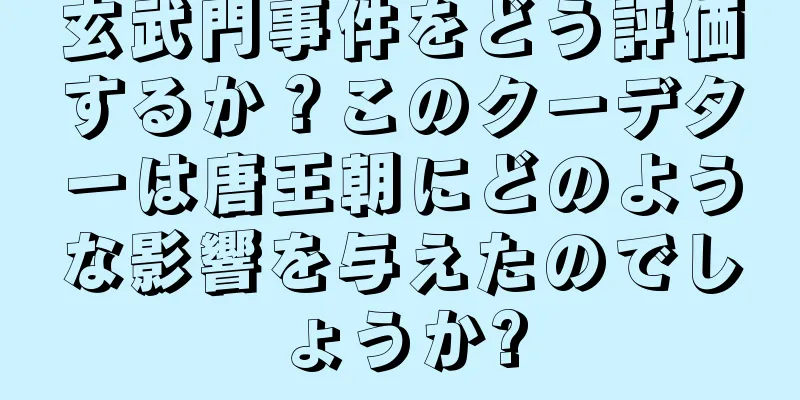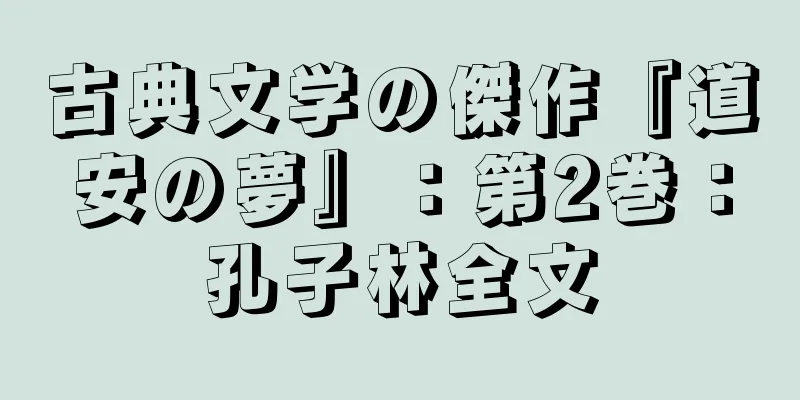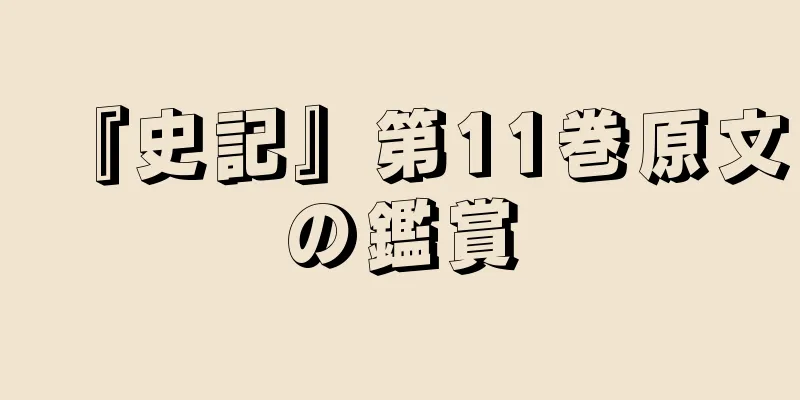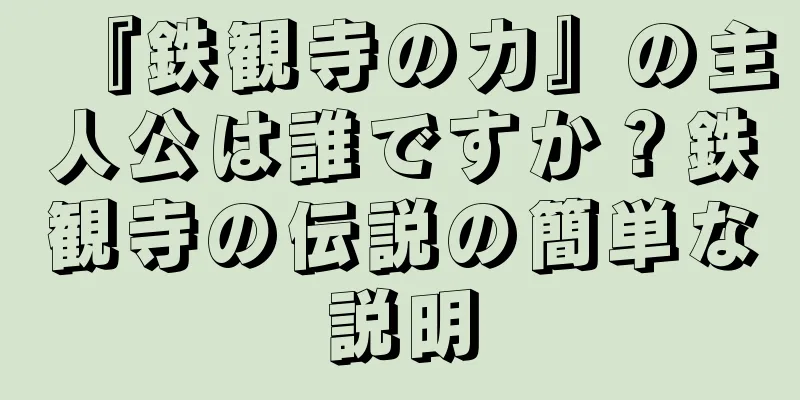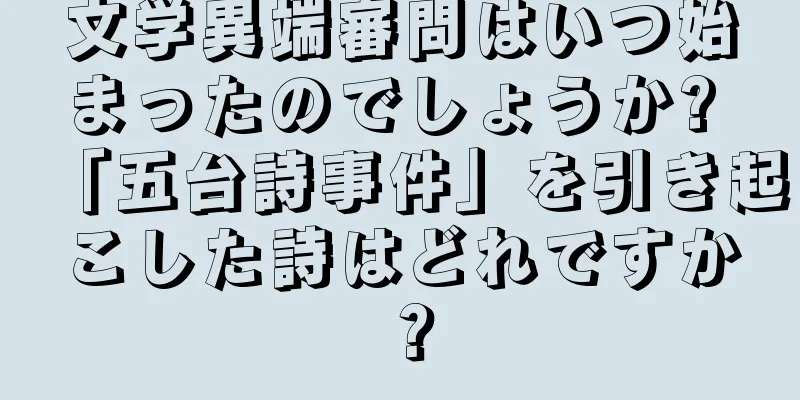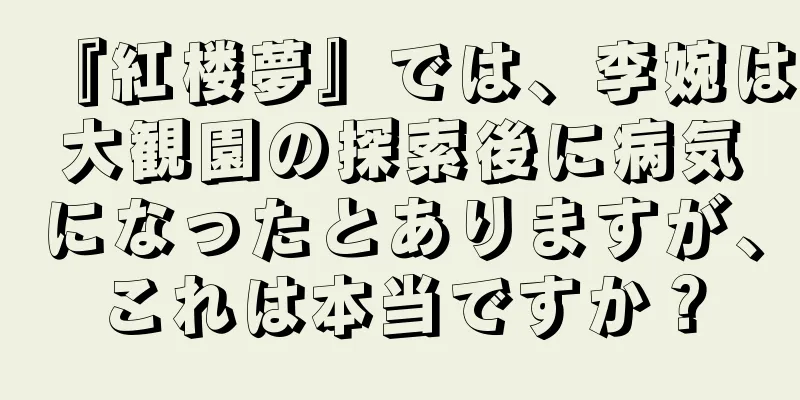夏の暑さが終わり、涼しい季節が訪れることを願う張磊の七字詩
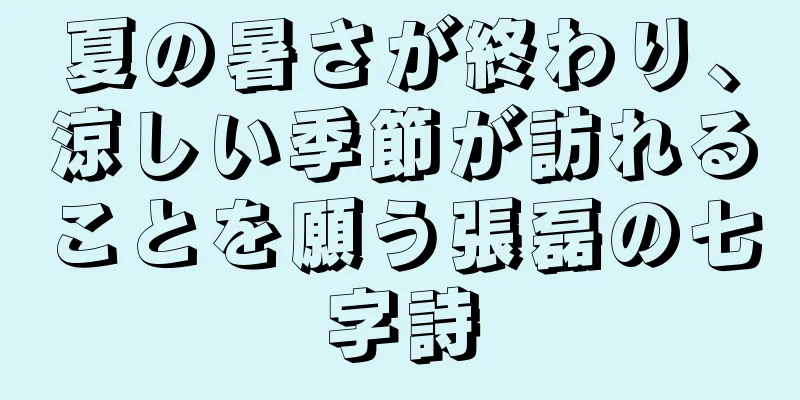
|
古代の詩人の多くは、劣悪な宿泊環境による灼熱に耐えられず、自分の気持ちを表現するために詩を書いた。杜甫はかつて、真夏の夜は短くて寒いと嘆き、涼しい空気を入れるために窓を開けなければならなかった。魏英武は家の暑さに耐えられず、山の中で一人座ってリラックスしながら創作を楽しむしかありませんでした。興味のある読者とInteresting Historyの編集者はぜひご覧ください! 白居易は暑さを恐れていなかったようです。心を静めれば暑さが消え、部屋を空にすれば涼しさが生まれると感じていました。心を静め、自然に涼しくするこの実践は、学ぶ価値があります。北宋の時代に、大暑の暑さを恐れた詩人がいました。彼は一日中家にいて、自分の気持ちを表現する詩を書きました。猛暑の季節には、張磊の七字詩を愛でながら、西風が吹くのを辛抱強く待ち、夏の終わりと涼しい季節の到来を楽しみにしています。 趙応之の「大暑について」(北宋:張磊)への返答 入ってくる車を迎えるために長い間ドアを閉めたままにしていたが、暑さがさらに怖かったので、小部屋は空っぽだった。緑の苔には鳥文字が、緑の枯れ葉には昆虫文字が刻まれています。井戸から冷たい泉が湧き出て何の役に立つのか?涼しさを招こうとする白羽の計画はすでに失敗している。西風が吹いてグリーンパーチを切って釣りができるまで待つのは耐えられない。 張磊は北宋時代の作家で、蘇軾の弟子であった。黄庭堅や秦貫ほど有名ではなかったが、彼もまた非常に才能があった。東坡氏の関与により、詩人は公務で障害に遭遇し、名声や富に無関心になり、群衆と一緒にいるよりも家で読書や執筆をすることを好むようになった。 趙英之は彼の友人であり、二人はよく一緒に詩を詠み、酒を楽しんだ。これは贈り物と返事の詩です。作者は夏に対する気持ちを表現し、涼しい季節が早く来ることを願っているのです。 最初の連句は詩人自身の状況を説明しています。「長い間、扉は閉ざされていた」は、詩人が長い間多くの社交行事を断り、隠遁生活を送っていたことを示しています。しかし、親しい友人たちが私を訪ねて来てくれると、やはり感謝しています。彼は暑さを恐れて一日中東屋の中に隠れていたが、そのおかげで客を迎えたり本を読んだりするのに都合がよかった。 詩人はその後、夏の暮らしを描写しました。平日は中庭に人がほとんど来ないため、中庭は苔で覆われ、いたずら好きな鳥たちは見知らぬ人をまったく恐れず、みんな中庭に来て餌を探したり散歩したりしていました。枝の緑の葉も垂れ下がり、虫が這った跡が残っていた。鳥篆書や昆虫文は鳥や昆虫の痕跡を鮮やかに描き、苔や緑の葉は夏の青々とした植生を表現しています。 2番目の連句は少しいらだたしい感じがします。庭には澄んだ泉があるのに、天気が暑すぎるので「役に立たない」と詩人は不平を言います。白い羽根の扇は爽やかに見えますが、それ以上の涼しさはもたらしません。 この二つの文章は明らかに詩人の暑さに対する恐怖を反映しているが、詩人はそれを泉水と白雨のせいにしている。とてもユーモラスで、また厳しい夏に苦しむ古代人の苦悩を表現している。 古代人はエアコンも冷蔵庫もなく、現代人のような快適な生活は送れなかった。詩人は、秋の始まりとともに友人たちと涼しさと美味しい料理を楽しめることを願いながら、常にイライラを抑えて暑さの苦しみに耐えなければならなかった。 「西風が吹くのを待ち、青スズキを切って魚を釣るなんて、どうしたら耐えられるだろうか」最後の2つの文章は、作者の切実な期待を表しており、また語呂合わせでもある。「bleak」という言葉には意味がある。詩人は、自分の官職がより順調になり、国と国民のためにもっと貢献できることを望んでいる。 張磊の七字詩は、暗示や伝説を一切使わず平易な言葉で書かれているが、その描写は繊細で生き生きしている。特に二連句「緑の苔に鳥の印が宿り、緑の枯れ葉に虫の字が宿る」はイメージが豊かで、夏の万物の活力を表すとともに、室内でのゆったりとした生活を楽しんでいることをより繊細に表現しています。 耐えられないほどの暑さでなければ、詩人はおそらく1年間外出しなくても心配しなかっただろう。彼は高い東屋で夏を過ごし、古い書類の山に浸り、鳥や昆虫の書道に魅了されていましたが、満足していました。詩人はポーチから外を眺めながら、秋の到来を望み、さらには公職の復活を期待していた。しかし、人々は暑さに苦しみ、物事はすでに秋を恐れている一方で、涼しい西風はゆっくりと道を歩いているようです! |
<<: 唐代の詩人、李毅の七字四行詩を3つ読んでみましょう!
>>: 『金色』は李尚鴻の有名な詩であり、唐代の詩の最高傑作でもある。
推薦する
南宋代宋慈著『西源義録』全文:巻一:総説
『西元集録』は法医学書で、『西元録』、『宋特星西元集録』とも呼ばれ、全4巻である。南宋の宋慈(恵夫)...
白居易の詩「張元朗中医師に送る新昌新居四十韻」の本来の意味を鑑賞する
古詩「新昌の新居について書いた四十首、張医師に送る、袁朗中」時代: 唐代著者: 白居易毛崇は3度昇進...
孫尚香は東呉に戻った後、なぜ劉備のもとに戻らなかったのですか?
個人的には、三国志演義で羅貫中が言及した女性は、貂蝉、徐庶の母、孫尚香など、基本的にみんなバッドエン...
宋代の蘇秀の道中詩を鑑賞します。曽冀は詩の中でどのような場面を描写しましたか?
蘇秀道忠、宋代の曽記、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介をもたらします、見てみましょう!蘇秀...
有名な抗金将軍、劉啓とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は劉啓をどのように評価しているのでしょうか?
劉琦(1098年 - 1162年2月25日)、号は辛叔、秦州城邑(現在の甘粛省景寧)の出身。呂川軍太...
二科派暗景記 第2巻: 道士が一手で世界を救い、女性チェスプレイヤーが2つのゲームで自分の人生を決める
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
もし関羽が彼らの古い友情を無視していたら、曹操は本当に華容路で死んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古典文学の傑作『論衡』第20巻、遺品
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
『紅楼夢』で秦克清の死を知った宝玉はどう反応しましたか?なぜそんなに異常なのでしょうか?
金陵十二美女の最後の秦克清は『紅楼夢』の比較的早い時期に登場しました。以下の興味深い歴史編集者が詳細...
儒教古典の原典の鑑賞:『論語』第8章「太伯」
孔子は言った。「太伯は最高の徳を備えた人物と言える。彼は三度も国を明け渡したが、民衆は彼を称賛する理...
金川が井戸に飛び込んだ後、薛宝才はなぜ急いで王夫人を慰めたのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
フビライ・カーンの統治時代、中国の領土はどれくらい広かったのでしょうか?
ボルジギン姓を持つクビライ・ハーン(1215-1294)はモンゴル人であり、チンギス・ハーンの孫であ...
唐代の李傅野の「山外に新年をおく」は時の流れを嘆く
「大晦日を山の外に留める」は唐代の李傅野によって書かれたものです。次の興味深い歴史編集者が、関連する...
「Yan Ge Xing」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
ヤンの歌高史(唐代)開元26年、元容に従って国境を越えた客人が帰国し、「顔歌行」を作曲して人々に披露...
薛剛の反唐事件 第17章:薛定山の家族全員が拷問を受け、范麗華は処刑場から逃亡した
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...