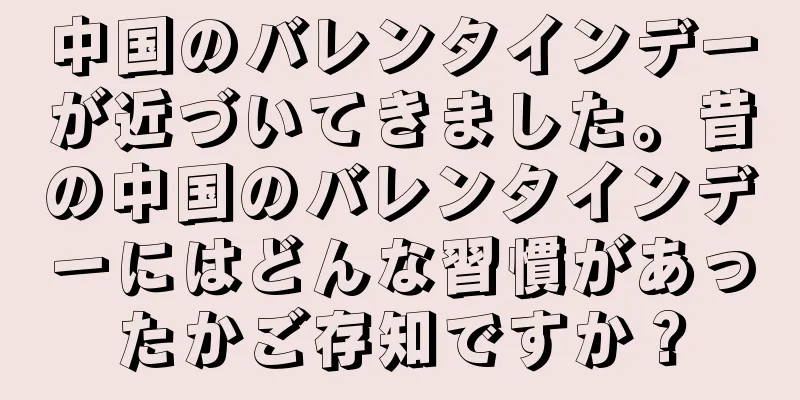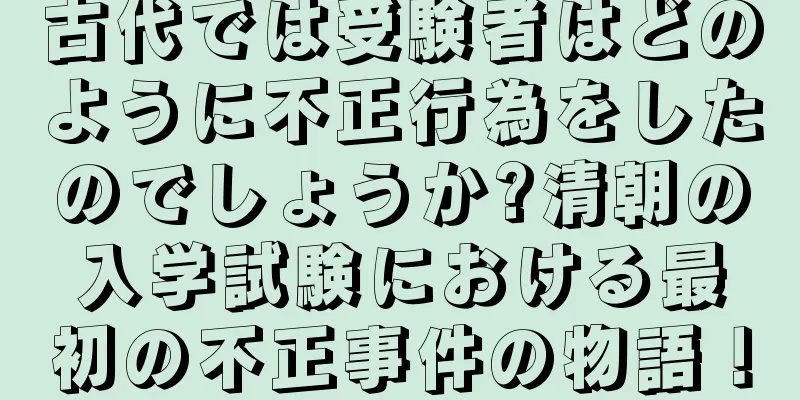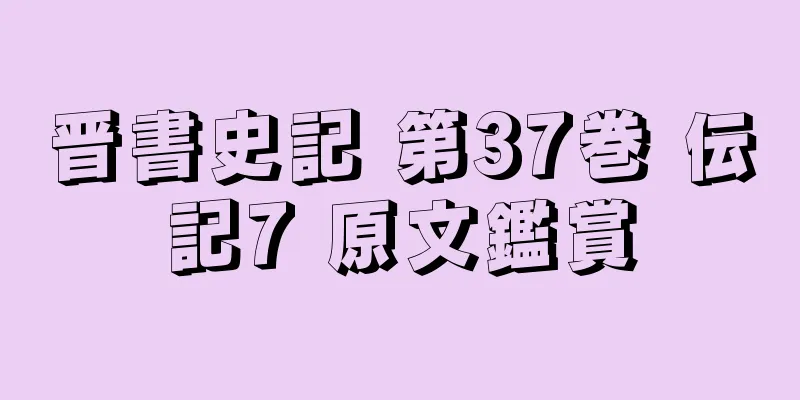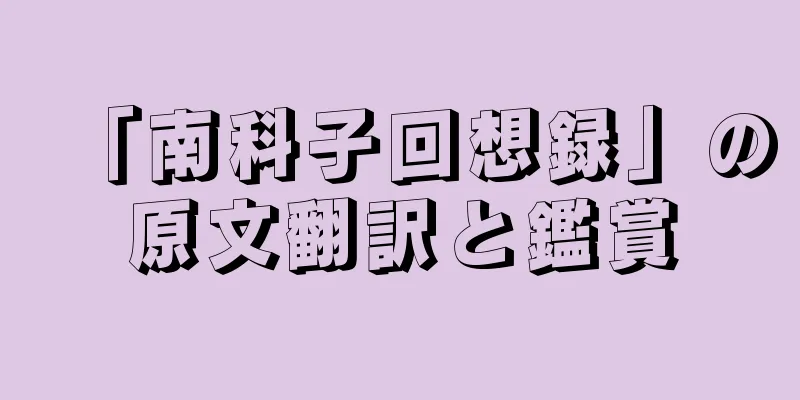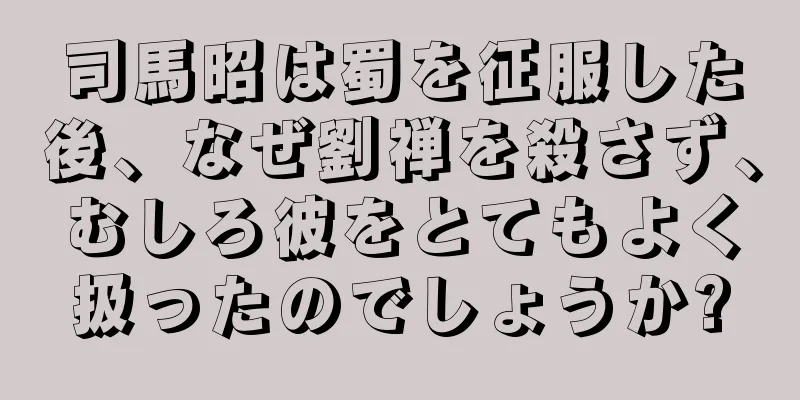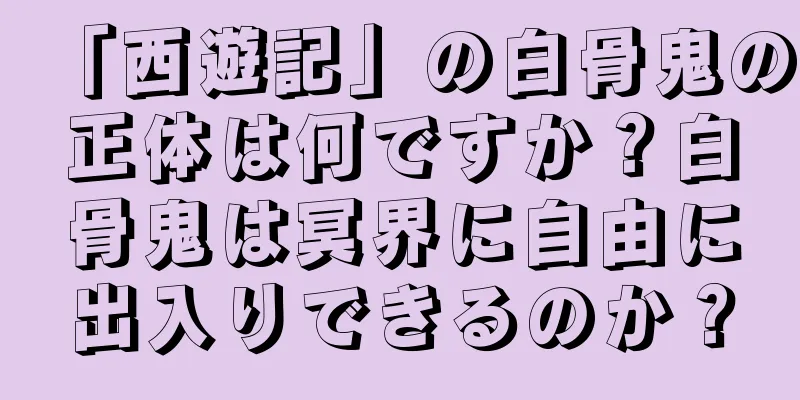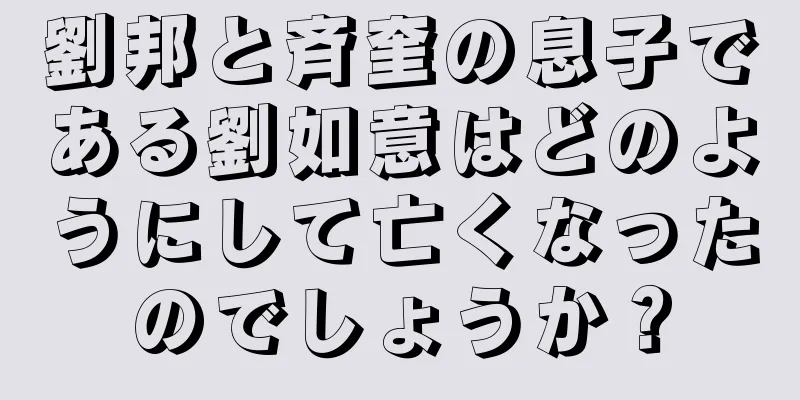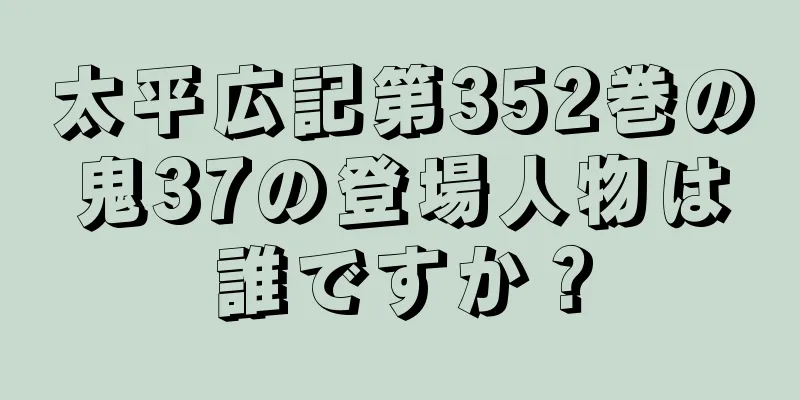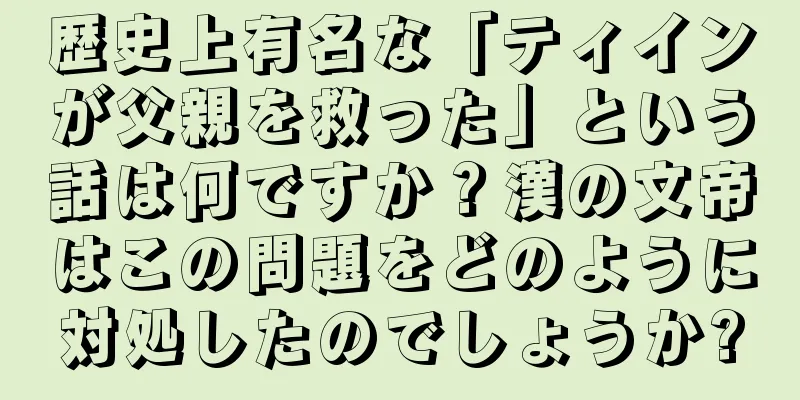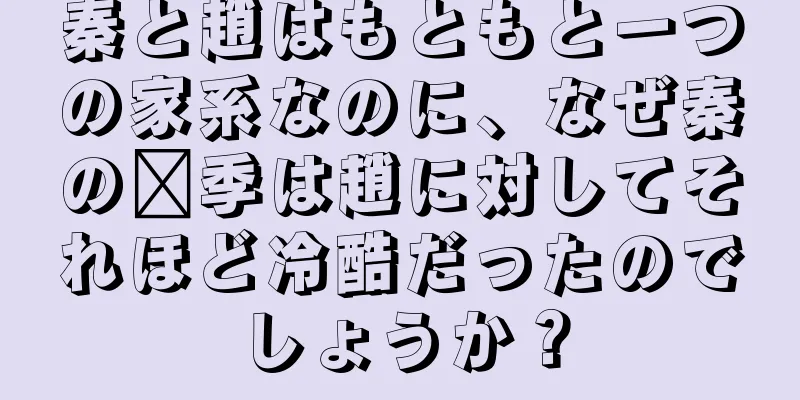唐代の王建の「窓辺の機織り」には労働者階級の人々への深い共感が込められている
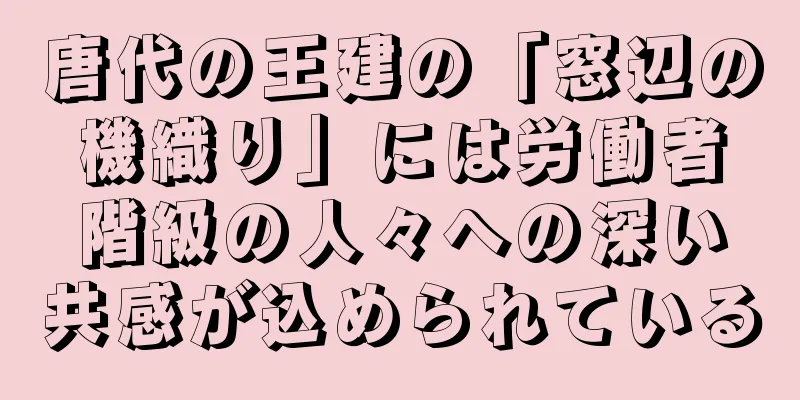
|
王堅(本名は鍾楚)は中唐の詩人である。768年に生まれ、835年に亡くなった。彼の生涯は中唐時代全体にわたる。彼は月夫詩に優れ、張季と同等の名声を博し、世間では「張王月夫」と呼ばれた。興味深い歴史の編集者と一緒に、王建著『窓辺の機織り』について学びましょう。 貧困に生まれ、生涯苦難の中で生きてきた彼は、世の中の苦しみや貧しい人々の生活の厳しさを理解していました。これは彼の創作に豊かなテーマを与えただけでなく、彼の積極的な写実主義のスタイルの基礎を築きました。これらの詩作品のほとんどは月夫を題材にしており、彼の親友である張季と同じくらい有名で、世間では「張王月夫」として知られています。それらの多くは七字歌の形式をとっており、民謡的特徴に富み、言葉遣いが簡潔明瞭、簡潔で、長さが比較的短いため、現実を反映しやすく、社会の矛盾を集中的かつ鮮明に表現しやすい。 王建の代表作の一つである『窓辺の機織り』は、一生懸命働いても何も得られない「貧しい少女」のイメージを描き、当時の社会現象を鮮やかに反映しており、一定の積極的な意義を持っている。 窓辺で織る [唐代] 王建 ため息を何度もつく。庭には通行人が食べられるナツメヤシの木がある。 貧しい少女は裕福な家庭のために機織りをしていますが、義理の両親は壁で隔てられているという理由だけで彼女を助けることができません。 水は冷たく、手はこわばり、絹はもろいですが、使い続けるうちに心が痛みます。 織機の下では虫が鳴いていて、二日間で馬が一頭半完成しました。 役人の頭の上には衣服の破片が散らばっており、着る服がない。 窓際に立って、指も動かさずに服をいっぱいにしている売春宿の売春婦たちを羨ましく思う。 詩の最初の 2 行は、「ため息に次ぐため息、庭には通行人が食べるためのナツメヤシがある」です。なぜため息やうめき声が何度も聞こえるのでしょうか。庭のナツメヤシは熟していたのに、通行人に盗まれて食べられてしまったのです。ここでは詩でよく使われる比喩技法が使われており、「庭のナツメヤシが盗まれる」という表現は、労働の成果が理由もなく盗まれ、人々に占拠されるという醜い現象を描写しており、次の文章につながって、それがこの詩で主に描写されているすべてである。 一体何が問題なのでしょう?「貧しい家庭の娘が裕福な家庭のために機織りをする」です!この文章は明快で分かりやすいです。問題の理由を非常にうまく説明しており、読者の興味をそそります。読者は、なぜ詩人がこのような単純な問題にそれほど注意を払い、それを書き留めるためにそれほどの努力を払ったのかを知りたいのです。 「義母と義父は私たちの間で何の役にも立たない」ここでの義母と義父とは、織り手の義理の両親のことを指します。つまり、二人の間には壁があるだけなのに、義理の両親は高齢で、誰の助けも得られない。彼女は、できるだけ早く仕事を終わらせるために、自分で残業して織りをするしかない。これが第一の苦しみ、助けてくれる人がいない苦しみだ。 「水は冷たく、手は硬く、絹はもろくて切れ、絹を結んだりほどいたりして心は折れる。」寒い冬、水は凍るような冷たさです。絹を取り出すと、冷たい水で手が荒れます。しかし、絹は寒くなるともろくなり、切れやすくなります。一箇所繋いでまっすぐにしたと思ったら、またそこで切れてしまいます。このように忙しく行ったり来たりするのはとてもイライラします。これは二番目の種類の苦しみ、つまり多忙な仕事による苦しみです。 「織機の下で草虫が鳴き、二日で馬一頭半が完成する。」草虫とはコオロギのことで、「クク」とは虫の鳴き声を意味する擬音語です。それは陰鬱な夜で、他の皆は眠りに落ち、織機の下のコオロギだけが鳴いていた。まるで監督が織り手たちに、もっと頑張って規定の二日間で布を一枚半織るという仕事を終わらせるように促しているかのようだった。これが3番目の苦しみ、つまり重労働による苦しみです。 上の5つの詩節は、詩人が心血を注いだ詩節です。手伝い手が少ないことによる苦労、劣悪な労働環境、多忙な仕事、過重な労働など、織り手が耐えてきたさまざまな苦難を詳細に描写しています。そのような努力が相応に報われるのであれば、それはすべて価値のあることですが、現実は常に自分の望みに反するものです。 「役人にお金を払うと、頭はだらしなく覆われ、服が戻ってくるまで着るものがありません。」ここで支払うということは、支払うことを意味します。散らばっているというのは、残りの部分を意味します。彼女が苦労して織った布は政府に無償で渡され、最終的に残ったのは端切れだけで、おそらく義母と彼女の服を作るには十分ではなかったでしょう。ここでは、織り手たちへの抑圧といじめの根本原因、そして誰が働いても得をせず、誰が働かずに得をするのかという社会の現実を指摘しながら、残酷な真実が容赦なく暴露されている。 「窓際に立って、十本の指も動かさずに箱いっぱいに服を詰め込んだ売春宿の売春婦たちを羨ましく思う。」上記が残酷な現実に直面した描写だとすれば、この文章は抑圧された織女の哀れで怒りさえ感じる告発である。売春婦、娼婦、売春宿の女。織工は、絹や繻子の服を着た売春宿の売春婦たちをどうしようもなく見つめていた。彼女たちは、一生懸命働く必要も、苦労に耐える必要もなかった。何も心配する必要もなく、美しい服が詰まった箱を簡単に所有できるように見えた。しかし、自分を振り返ってみると、私は苦労して機織りをし、苦労して働き、苦難と寒さに耐えているのに、まだ一文無しで、食べ物と着るものに困っています。私の懸命な努力では現状を変えることはできません。これは何と大きな痛みであり、何と耐え難い絶望感を私に感じさせます。 最後の2行は、まともな女性が売春宿の娼婦を羨むという、道徳倫理に反する心理状態を描いている。「まだ服がないので着ない」と「10本の指を動かさずに箱に服が詰まっている」という対照的な表現は、「いじめられ侮辱されている」織工のイメージを描き出すために使われている。詩人は彼女を通して、社会の底辺にいる人々が一生懸命働いても見返りがないという社会現象を深く批判している。詩人の支配者に対する憤りと労働者に対する深い同情が言葉から伝わってくる。 この詩は、詩人が見たものをそのまま記録した、有名な出来事を題材にした詩であり、言葉遣いは適切で分かりやすく、考えは深く、好き嫌いは明確で、描写は繊細で正確、生命の息吹に満ち、一定の批評性があり、王建の七字歌の特徴をよく反映している。 この詩を読むと、人々はいつも白居易の『炭売り』、梅勝宇の『陶工』の「十本の指は泥に染まらず、大きな建物に住んでいる」、張毓の『蚕女』の「絹や繻子に覆われている者は養蚕者ではない」を思い出す。炭を焼く人は炭を燃やさず、家を建てる人は住む家がなく、蚕を養う人は布の服を着なければならず、布を織る人は布がない……「国が栄えれば民が苦しみ、国が滅びれば民が苦しむ」という言葉は、おおよそ真実であり、これは孤立した現象ではなく、人類の文明発展の歴史のあらゆる段階に共通する社会現象であると私は考えています。 貧しさと質素さの夢が残酷な現実によって閉じ込められてしまったら、どんなに強い人でも覆ることはできないでしょう。 |
<<: 王安石の『梅花図』は静けさの中に悲しみと憤りが込められている。
>>: 欧陽秀の「漁師の誇り:5月のザクロの花は華やかで美しい」は、楽しい雰囲気で心の孤独感を浮き彫りにしている。
推薦する
太平広記・巻52・仙人・陳伏秀の原作の内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
高奇の『牛飼い歌』は、重税に対する作者の不満を表現している。
高奇は、字を季迪、号を茶軒といい、武淑の清丘に隠棲していたため、清丘子と名乗った。元代末期から明代初...
太平広記・巻13・仙人・蘇仙公をどう理解するか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
鍾会の罠がなかったとしても、鄧艾は死んだとなぜ言えるのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「彭公安」第116章:地獄の生き王を捕らえた報復 3人の英雄が5人の幽霊を捕らえるよう命じられる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
『清尚元・嘉夢駅』の著者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
清尚縁·嘉孟駅にて執筆陸游(宋代)夕暮れ時に川辺で酒を飲むと、雪が消えてもまだ肌寒い。山間の宿は寂し...
東周書紀第57章:呉塵は夏季と結婚して晋に逃げ、程英は孤児を宮殿に隠した。
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
趙雲は何に驚いたのでしょうか?趙雲は本当にその時姜維を倒せなかったのだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
第88章:崔判事が王明を導き、王可心は冥界を旅する
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
明代『志農(抜粋)』:軍事情報部・韓時忠全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
李存勗は包囲されて朱文と戦えなかった李可容をどのように慰めたのでしょうか?
李存勗は西突厥の沙托族に生まれました。彼の元の姓は朱戌であり、彼は何代にもわたって沙托族の族長でした...
梅耀塵の「夕雲」:この詩は斬新な比喩と連想を用いている
梅耀塵(1002年5月31日 - 1060年5月27日)は、聖宇とも呼ばれ、宣州宣城(現在の安徽省宣...
この1元硬貨は、100元札を何枚も重ねた価値に相当します。
諺にあるように、希少性は物事に価値をもたらします。 1元硬貨も希少になり、価格も非常に高騰しています...
孟浩然の「朱達を秦に送る」:人々の想像力を刺激できる
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...
デアン族の習慣は何ですか?デアン族の牛を尊重する習慣
秋の収穫期になると、梁河県徳安村の村人たちは、最初の香り高い新米を牛に与えます。特に老人や老婆は自分...