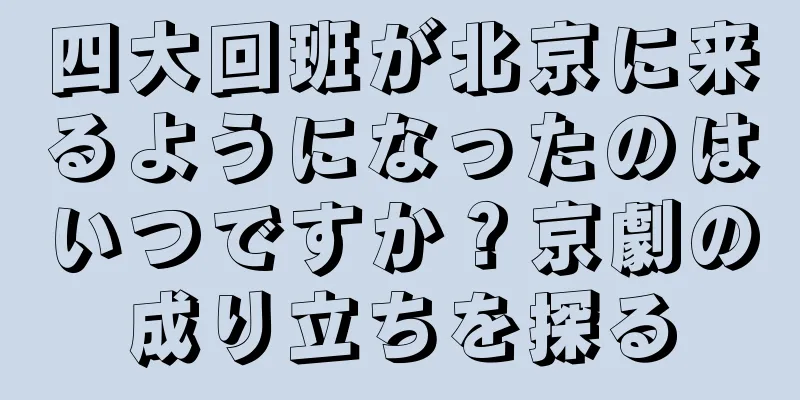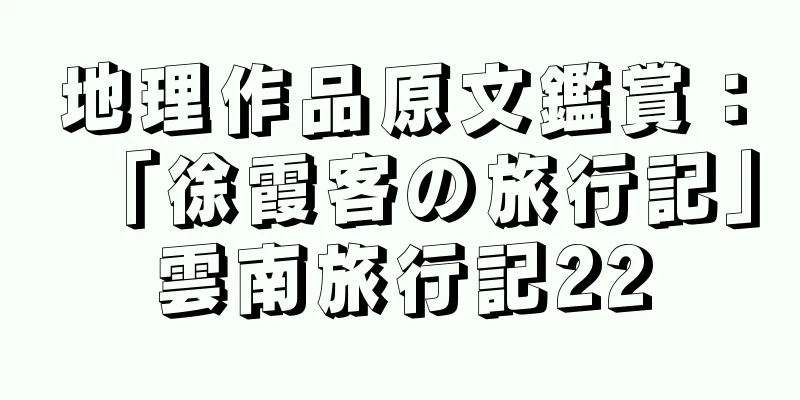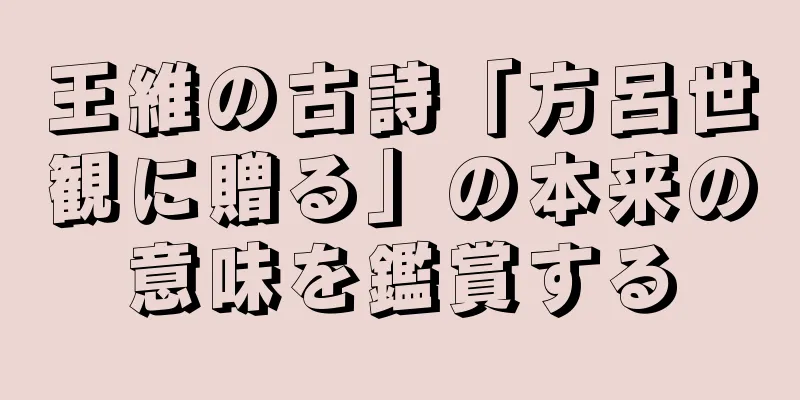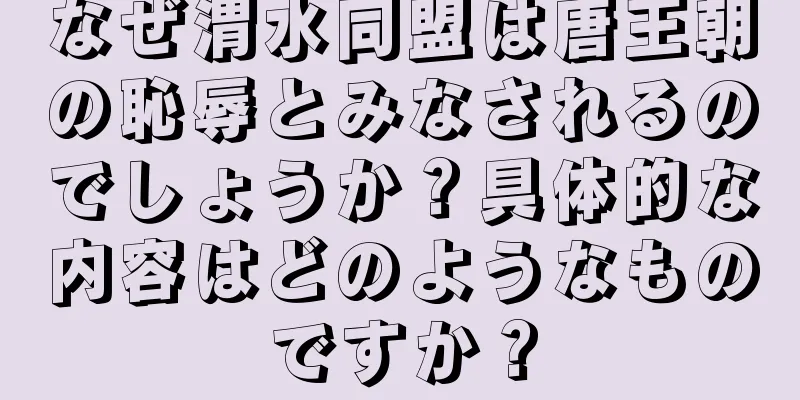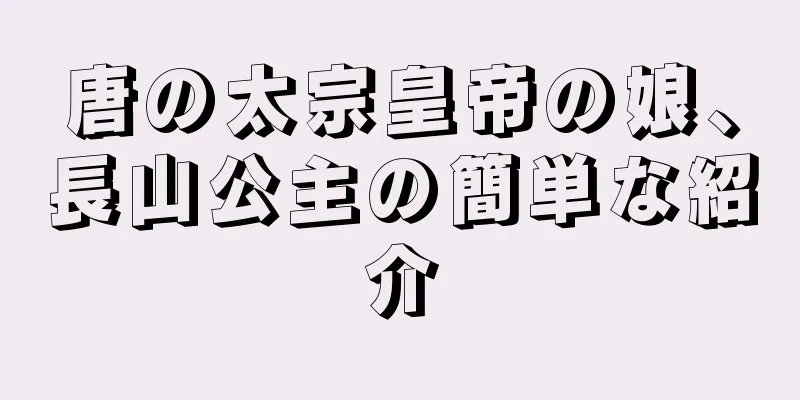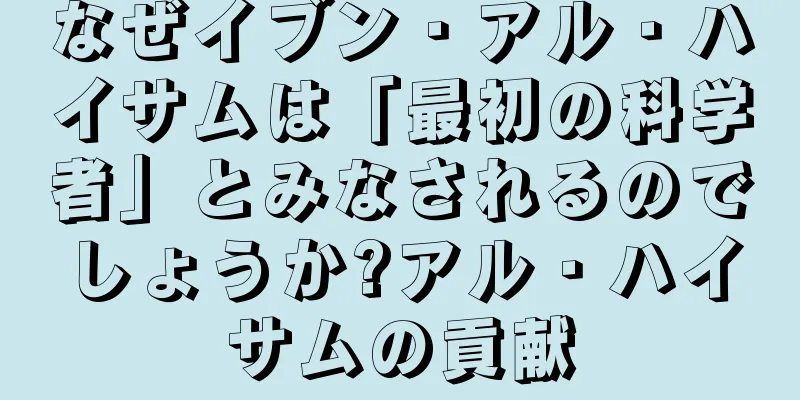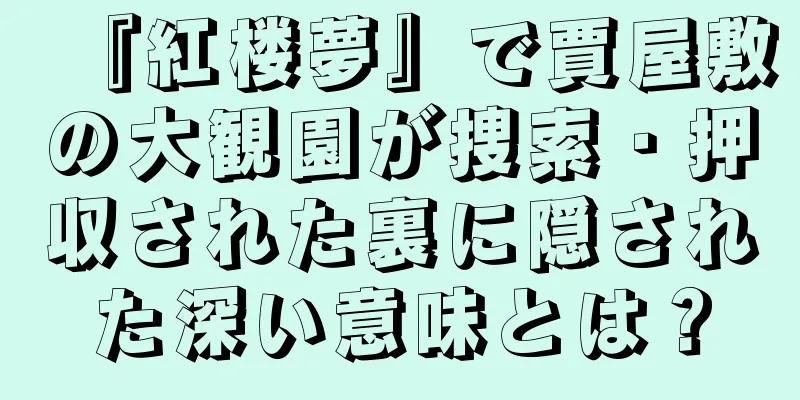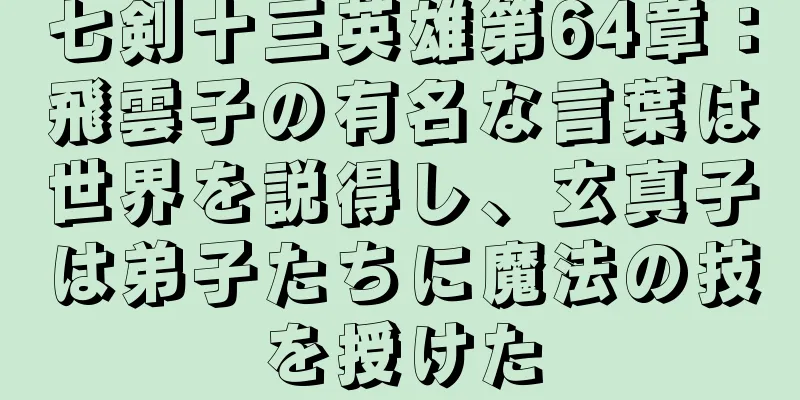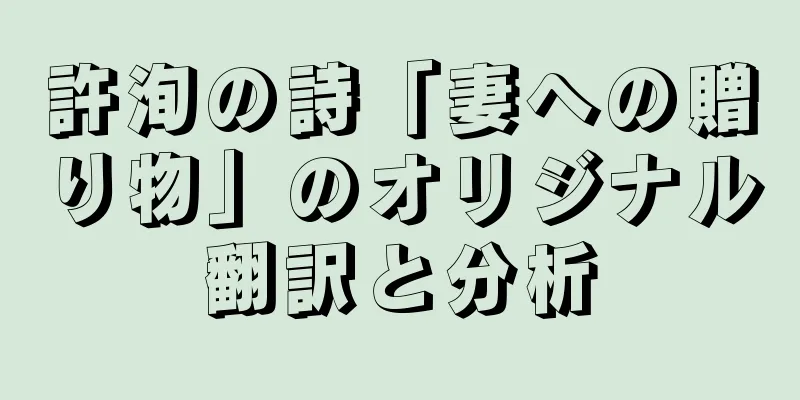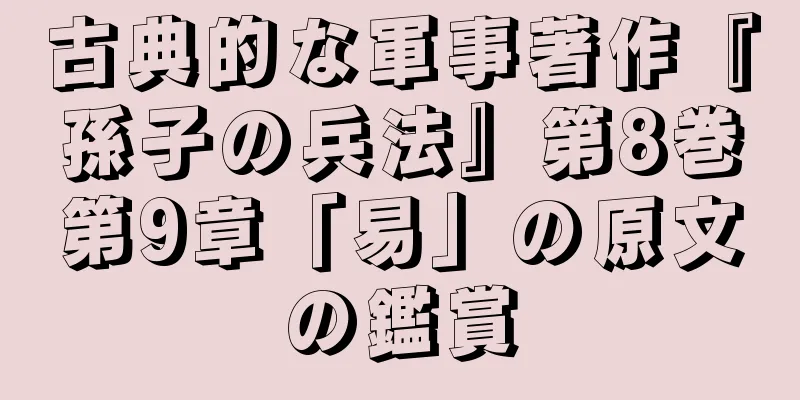司馬昭は蜀を征服した後、なぜ劉禅を殺さず、むしろ彼をとてもよく扱ったのでしょうか?
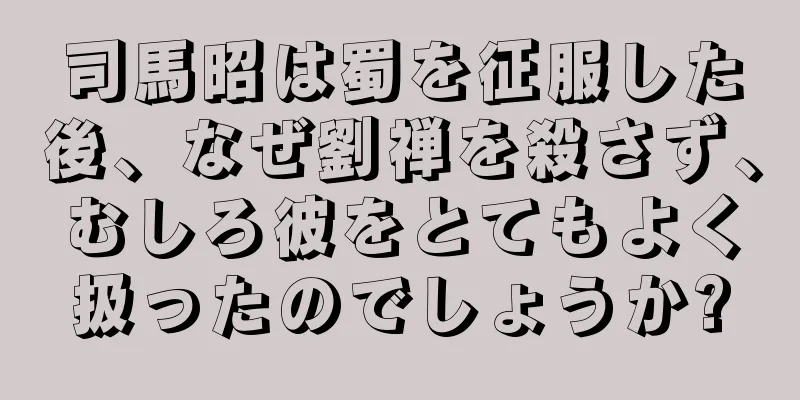
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、司馬昭が降伏した後、劉禅を殺さなかっただけでなく、彼を好意的に扱い、安楽公に任命した理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 魏の景元4年、司馬昭はあらゆる困難を乗り越え、蜀を滅ぼす戦争を起こした。苦戦の末、劉禅は途方に暮れ、魏軍に降伏するしかなかった。降伏後、劉禅は洛陽に移され、司馬昭から好意的に扱われた。なぜ司馬昭は、自分の敵であり、魏の宿敵であった劉禅を殺さず、非常によく扱ったのでしょうか? 1. 劉禅の性格は司馬昭に安心感を与えた。 後世の人々が蜀漢の滅亡の理由を論じたとき、劉禅の個人的な理由が蜀漢の滅亡の重要な理由であると考えられました。歴史書には、諸葛亮の時代に、賢臣の諸葛亮の援助により劉禅が立派な君主になったと記されている。しかし諸葛亮の死後、劉禅は黄皓らの策略にかかり、悪徳皇帝となった。 劉禅は政治的才能に欠けていたため、諸葛亮と蒋万、費毅が亡くなり、遺された蜀漢の統治を任された劉禅は、圧倒されてしまいました。彼は軍事面で姜維を頼りにしていたが、姜維はあまりにも攻撃的であり、蜀漢が長年かけて蓄積した力を無駄にしてしまった。彼は内政を黄昊に頼っていたが、黄昊は権力を乱用し、腐敗したため、朝廷は混乱した。 魏軍が蜀を滅ぼす戦争を開始する前に、姜維はその知らせを知り、劉禅に報告して漢中方面の守備を強化するよう要請した。しかし、劉禅は黄昊の言葉を聞いて反対し、その結果、空っぽになった漢中は魏軍によって簡単に突破されてしまった。鄧艾が陰平を突破したとき、諸葛瞻とその息子を派遣して鄧艾に抵抗させたが、惨敗した。 鄧艾の軍隊が成都に到着する前に、パニックに陥った劉禅は喬周のもっともらしい主張を聞いて自発的に降伏した。援軍として戻ってきた姜維の主力軍は、降伏を要求されたという知らせを聞くと、怒り狂って剣を抜き、石を切りつけた。しかし、このような愚かで無能な皇帝に遭遇したとき、私たちは何ができるでしょうか? 劉禅が降伏した後、彼の愚かさと無能さは司馬昭の前に完全に露呈した。最も有名な物語「故郷を懐かしく思わないほど幸せ」はこの時に起こった。当時、司馬昭は劉禅を試すために、わざと蜀の人々に宴会で蜀の歌や踊りを披露するよう命じた。劉禅の部下は皆泣いていたが、劉禅は笑い続け、冗談を言い続けていた。 司馬昭はこれを見て、賈充に劉禅は冷酷だと評し、姜維はおろか諸葛亮ですらこのような君主を長く助けるのは難しいだろうと言った。彼はわざと劉禅にまだ蜀へ行きたいかと尋ねた。劉禅は「私はここで幸せです。シュウを恋しく思いません」と答えた。司馬昭は劉禅の調査を通じて、劉禅には野心など全くなく、自分や政権に何の脅威も与えない人物だと悟り、彼を釈放した。 2. 劉禅の忠実な部下はもう存在しない。 劉禅は野心がなかったが、結局は国の王様だった。漢王朝を支持すると信じる人々にとって、劉禅は今でも心の中の旗印となっている。したがって、もし劉禅がこれらの人々によって支配されていたら、司馬昭に対する反乱が起こり、司馬昭の統治が脅かされる可能性もあった。 しかし、劉禅が洛陽に到着したとき、この可能性はもはや存在しなかった。これは劉禅が降伏した後、蜀で大規模な騒乱が起こったためである。この騒乱は、最初は鄧艾と鍾会の功績をめぐる争いから始まったが、その後、事態は制御不能となり、血みどろの虐殺へと発展した。 鍾会は蜀を滅ぼす作戦の最高司令官であり、主戦場での戦闘任務を担当していた。彼は10万人以上の軍を率いて漢中を攻撃し、関を占領し、姜維に蜀軍の主力を率いて江閣まで撤退させた。鍾会は蜀軍の主力を拘束すると同時に、鄧艾に戦う機会も作った。鄧艾は陰平を抜けて蜀国の中心部に侵入し、綿竹の蜀軍の最後の主力部隊を破り、劉禅を降伏させた。 鄧艾の独断的で独裁的な振る舞いは、鍾会の嫉妬と司馬昭の疑惑を招いた。姜維は偽りの降伏戦略に訴え、鍾会に鄧艾を排除させ、すべての軍事力を掌握させてから反乱を起こすよう唆した。時が熟すると、姜維は鍾会を排除し、蜀漢政権を復活させた。こうして鍾会はまず鄧艾とその息子を捕らえ、洛陽に送り込んだ。しかし、反乱は失敗し、彼と姜維は部下によって殺害され、鄧艾も混乱の中で死亡した。 こうして蜀を攻めていた魏軍は総指揮官を失い、完全に混乱した軍となってしまった。軍の監督官である魏管の暗黙の承認を得て、蜀で大規模な略奪が行われた。この混乱の間、劉禅の皇太子劉玄を含む、蜀漢政権に忠誠を誓う多数の大臣が虐殺された。 忠実な部下の多くが殺害された後、劉禅は司馬昭によって洛陽に移されました。蜀を去った後、漢王朝の再興を望む少数の人々でさえ、劉禅が国を復興するのを助けることはできなかった。このように、愚かで無能な劉禅は、国を復興するための忠臣の助けもなく、もはや司馬昭にとって脅威ではなくなり、司馬昭は劉禅の根を絶つ必要もなくなった。 3. 劉禅の状況は東呉の促進に利用できる。 劉禅が降伏した後、かつては無能で誰からも軽蔑されていた君主は、誰もが争う人気者になった。これは主に劉禅の個人的な象徴的意義であり、彼の実際の価値を超えています。姜維の目には、劉禅は蜀漢復興の希望である。鄧艾の目には、彼は東呉に対する世論戦争を遂行するための強力な道具に映った。 鄧艾は劉禅の降伏を受け入れた後、彼を威嚇するどころか、親切に扱った。鄧艾は劉禅を騎将軍に任命し、降伏した蜀の官吏全員に褒美を与えた。後に鄧艾は司馬昭に、なぜこのようなことをしたのかを説明したが、それは主に呉への次の攻撃に備えるためであった。 鄧艾は司馬昭に報告し、蜀漢を呉攻撃の拠点として軍事的準備を整え、下流に下って東呉を攻撃することを提案した。東呉に対する宣伝攻勢を開始するために、劉禅を厚遇し、扶風王として封じ、蜀に留めておくことを提案した。そしてこの事態は東呉の君主と大臣たちに公表され、彼らの抵抗の意志を弱めました。 司馬昭は鄧艾の独裁政治に疑問を抱いていたが、鄧艾とその息子を排除した。しかし、司馬昭は依然として鄧艾の報告の合理的な提案を採用した。司馬昭は劉禅を王にせず蜀に留めたが、洛陽に移した後は安楽公に任じ、東呉に対する世論工作の道具として利用した。 東呉を攻撃する機が熟したとき、司馬炎は呉を滅ぼす戦争を開始しました。呉王孫昊は前線で何度も壊滅的な敗北を喫し、絶望的な状況に直面した後、劉禅の例に倣って金軍に降伏した。劉禅の前例があったからこそ、東呉の君主や大臣たちは自発的に降伏することを選び、それによって金軍の戦闘の困難さが軽減され、軍の死傷者も減少した。この観点から、司馬昭が劉禅を優遇したことの影響が明らかになった。 結論: 蜀漢の最後の王、劉禅は降伏した後も司馬昭に殺されず、むしろ司馬昭から厚く遇された。主な理由は、劉禅が愚かで無能な君主であり、忠臣や勇敢な将軍が蜀漢の滅亡を招いた混乱の中で全員殺されたことであった。このように、劉禅は司馬昭とその政権にとって脅威ではなく、司馬昭が彼を根絶する必要もなかった。 司馬昭は劉禅を殺さなかっただけでなく、劉禅を厚く扱った。これはまた、次の戦略的動きへの準備でもあった。蜀漢の滅亡後、東呉を滅ぼし天下を統一することが司馬の主な戦略目標となった。劉禅を優遇する目的は、東呉に宣伝を広め、東呉の君主と大臣たちの抵抗を弱め、軍事作戦に便宜を図ることであった。呉を滅ぼす戦争では、劉禅の前例により、東呉は最終的に戦わずして降伏することを選んだ。 |
<<: 蜀漢には5人の虎将軍がいました。劉備のグループの中で、最も高い官職と最も権力を持っていたのは誰ですか?
>>: 馬超はかつて許褚と激しい決闘をしましたが、勝者はどちらでしたか?
推薦する
四龍四鳳ブロンズプランとは何ですか?その精巧さに専門家も驚嘆!
四龍四鳳の青銅図案とは?その精巧さに専門家も驚愕!次のInteresting History編集者が...
ゼロからスタートした皇帝である朱元璋の気質が晩年で大きく変わったのはなぜでしょうか。
権力には常に欲望が伴います。歴史上の皇帝を見てみると、生涯を通じてただ一人の人だけを愛するほど忠誠心...
夏金貴の母親は彼女をとても大切に育てたのに、なぜ彼女を傷つけるのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
清朝の老人保健に関する論文『老老衡眼』第3巻:靴下
『老老衡厳』の著者は清代の学者曹廷東で、老年期の健康維持に関する論文集で全5巻からなる。周作人はこれ...
マオドゥン・チャンユはどのようにしてカーンの王位を継承したのでしょうか?
マオドゥン・チャンユはどのようにしてカーンの王位を継承したのでしょうか?北方匈奴部族同盟のリーダーで...
孟子:梁慧王 第二章第四節 原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
古典文学の傑作『太平天国』:官部第33巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で、賈夫人が賈正に対して不公平で偏見を持っているというのは本当ですか?
周知のように、「紅楼夢」における賈牧と賈正の関係は、常に愛情深い母と孝行な息子の関係であった。賈祖母...
金王朝の地図: 両金王朝時代の中国領土の紹介
金王朝の領土西晋は曹魏の領土を継承し、統一後は孫武の領土を奪取した。その領土は北は山西省、河北省、遼...
水滸伝の武松と武二という名前はどのようにして生まれたのでしょうか?なぜ後からそう名乗らなかったのですか?
武松は、史乃安の古典小説『水滸伝』の重要な登場人物です。彼は家族の2番目の子供であり、「武二郎」とも...
呂不韋はどうやって死んだのですか?彼はどのようにして単なるビジネスマンから秦の宰相になったのでしょうか?
歴史上、呂不韋は毒を飲んで自殺した。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう...
古代の学者はどのような特別な待遇を受けていたのでしょうか?古代の学者の待遇についての詳細な説明
古代では学者は高貴な身分でした。裕福な実業家でさえ学者に敬意を払う必要がありました。では古代の学者は...
涼山の英雄たちのリーダーとして、宋江はどのような人々を恐れていましたか?
宋代末期の統治者は無能であったため、多くの人々が様々な理由で涼山に集まり、山を占領して王となり、宋代...
王維の古詩「送興貴州」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「邢貴州に別れを告げる」時代: 唐代著者 王維景口ではシンバルの音が騒々しく、洞庭湖では風と波...
秦の六国統一に貢献した武将の中で、より有能だったのは誰でしょうか?
戦国時代後期、秦の統一戦争の時代、秦国には多くの名将がいて、人材を登用し、一歩ずつ統一を果たしました...