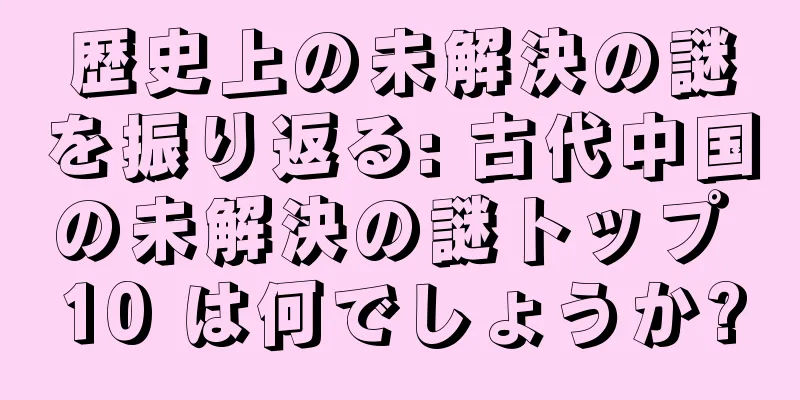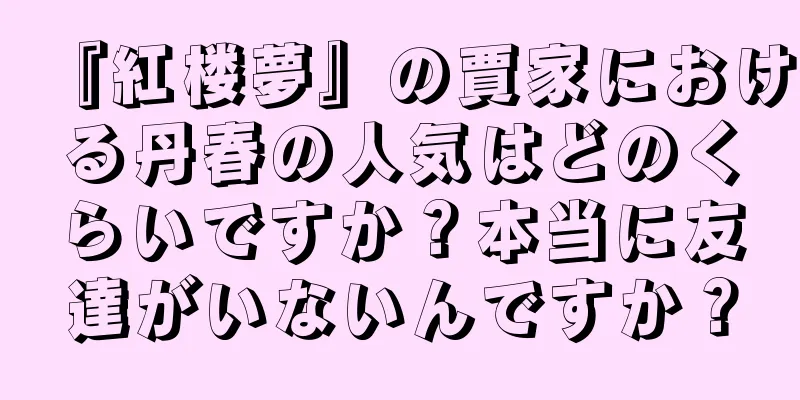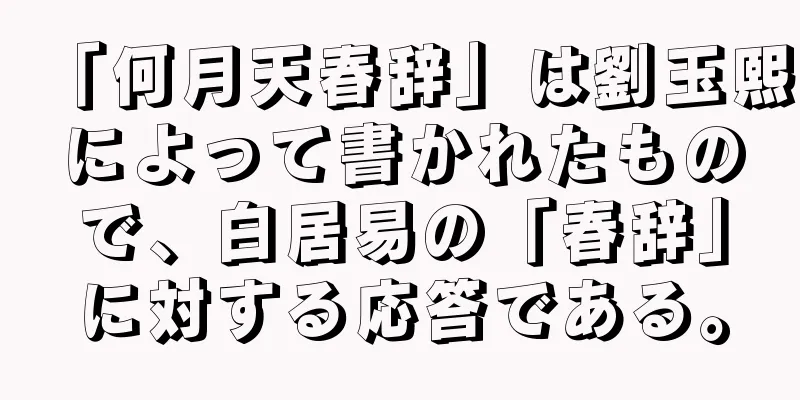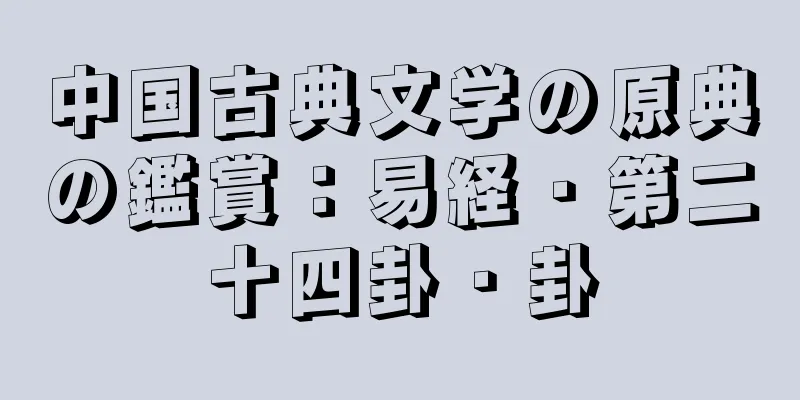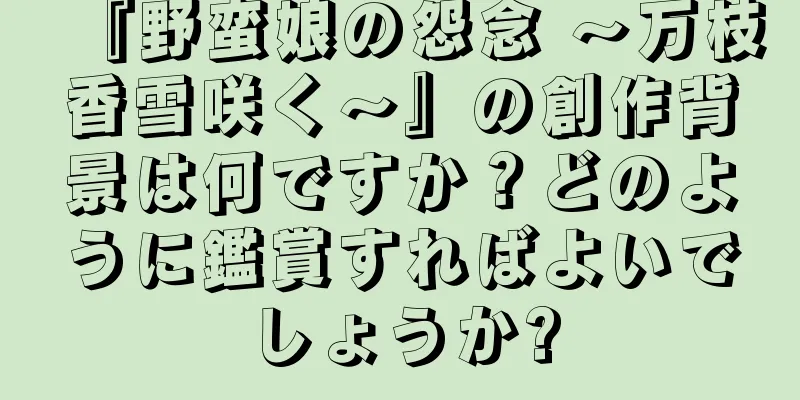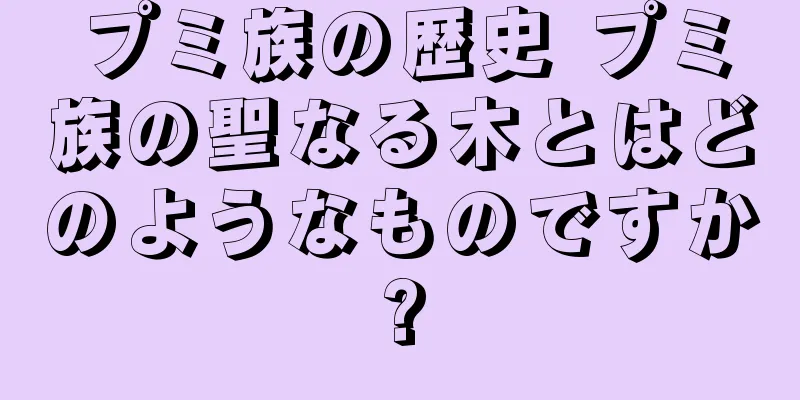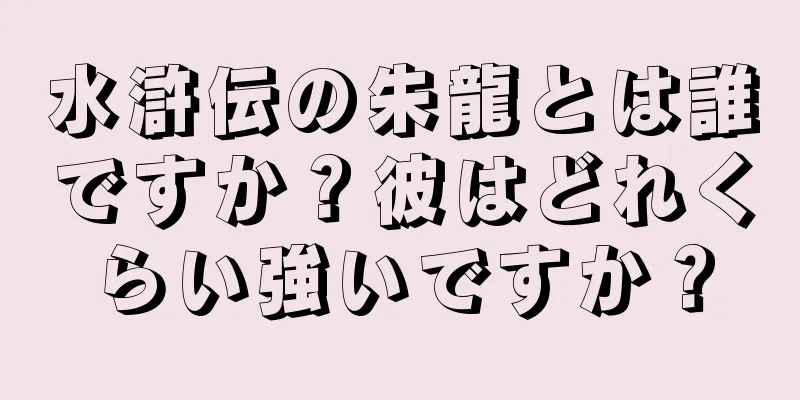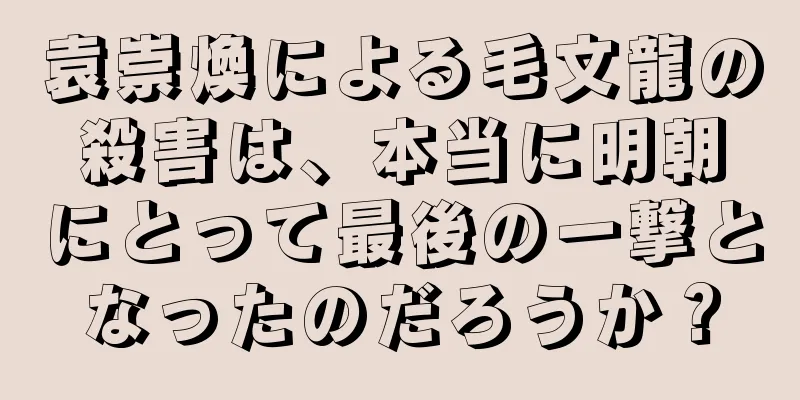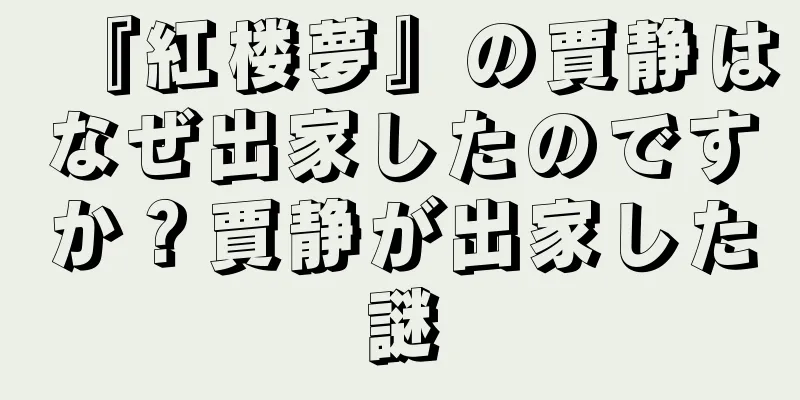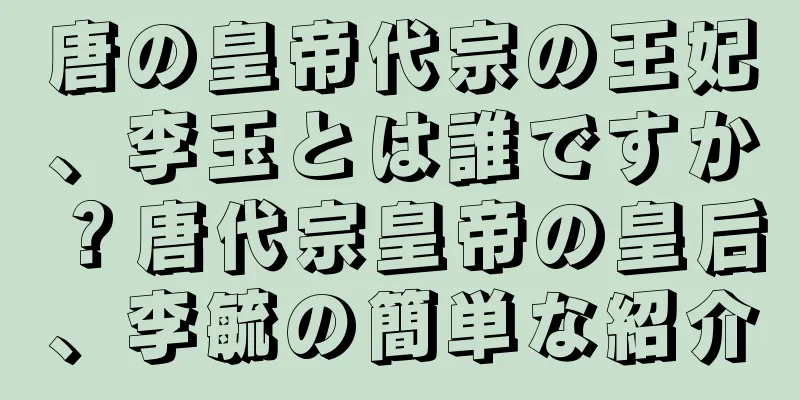白居易の有名な詩句を鑑賞する:散り散りの赤い杏の花、新緑の睡蓮は均等に成長する
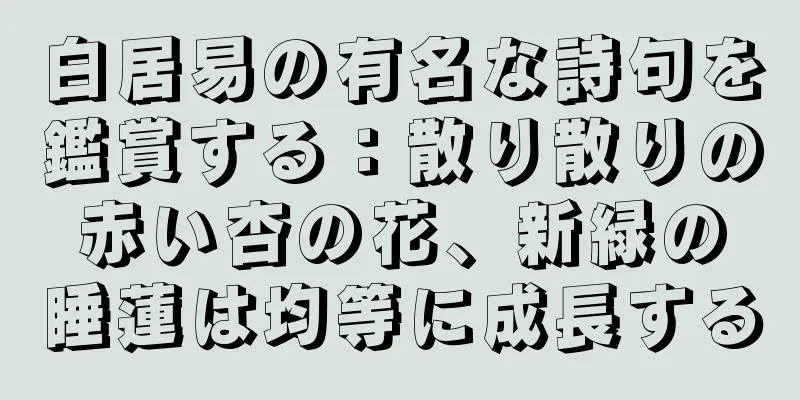
|
白居易(772-846)は、字を楽天といい、別名を向山居士、随隠仙生とも呼ばれた。祖先は山西省太原に住んでいた。曽祖父は下桂に移り、白居易は河南省新鄭で生まれた。 彼は唐代の偉大な写実主義詩人であり、唐代の三大詩人の一人でした。白居易と袁真は共同で新月傳運動を提唱し、世間では「袁白」と呼ばれ、劉玉熙とともに「劉白」とも呼ばれた。 白居易の詩は幅広い主題を網羅し、形式も多様で、平易で庶民的な言葉で書かれていることから、「詩魔」や「詩王」として知られています。彼は翰林学士、左残山博士を務めた。 846年、白居易は洛陽で亡くなり、香山に埋葬されました。 『白居易全集』『長悲歌』『炭売り老人』『琵琶歌』などの詩集は現代まで伝わっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が白居易の「南湖早春」をお届けします。見てみましょう! 風は吹き去り、雲は消え、雨は止みます。湖畔には再び太陽が輝き、暖かく明るくなります。 赤いアプリコットの花がランダムに散らばり、新しい緑のウォーターアップルが均等に広がっています。 白雁は重い翼を低く飛ばし、コウライウグイスの舌は乾いていて言葉は完全ではない。 揚子江南岸の春が悪いというわけではないのですが、私の気分は年々悪くなっています。 【注意事項】 1. 南湖:蓬莱湖、別名鄱陽湖。 『太平環于記・江州』には「蓬里湖は徳化県の南東にあり、都昌県とを分けている」とある。詹方勝の『入南湖詩』には「蓬里は三つの川を治め、鹿月はすべての山を治める」とある。 2. 早春:早春。 3. 風が戻る:春のそよ風が大地に戻る。 4. 雲は風によって吹き飛ばされます。 5. 反射: 太陽の光が再び輝きます。 6. 混沌:無数。山野のあちこちで光り輝いているという意味です。 7. ブロークンレッド: アプリコットの花のつぼみが開き、赤い部分が見えてきました。 8. Fa: 開花。 9. ウォーターアップル:水に浮かぶウォーターアップル。 10. 翼を低く: 非常に低く飛ぶ。 11. 白ガチョウ:湖のそばの白いカモメ。 12. 舌の渋み:流暢でない発音を指します。 「Se」は、難しい、まだ滑らかで優雅ではない呼び方を表現するときに使われます。 13. オリオールズ:キイロアメリカムシクイ。 14. ブダオ:言うまでもない。 【感謝】 白居易が江州に流刑された時に残した作品です。これも作者が江州にいた頃に残した作品です。 「南湖の早春」では、最初の6つの文章は早春の南湖の明るく感動的な風景を描写し、最後の2つの文章は追放された後の作者の憂鬱で憂鬱な気分を表現しています。 この作品は、春の初めを最も特徴づけるいくつかのイメージを強調しています。春の雨がちょうど上がったばかり、太陽が輝いていて、山杏が満開で、水リンゴが緑を競い合っており、白雁が低く飛んでいて、コウライウグイスがさえずっています。ちょうど大雨が降ったばかりで、地面も湖も雨に洗われ、その美しさに新鮮さが加わっていました。早春はまだ少し冷たい空気が残っていますが、太陽が照り返すと、景色は美しいだけでなく、暖かくて明るくなります。野生の杏が咲き、水リンゴが育ち、すべてが繁栄しています。赤と緑が互いに引き立て合い、色彩のコントラストが鮮明です。早春の最も特徴的な風景であり、この絵画に欠かせない装飾です。山々一面に生える野生の杏は赤い斑点が点在し、まったく秩序がなく、自然の生命力の強さを示しているため、「混沌」という言葉で表現されています。湖の睡蓮は果てしなく咲き、水面に整然と敷き詰められた緑の芝生のようであるため、「平ら」であると言われています。 「平」という字には二つの働きがある。一つは睡蓮の清楚さを表現すること、もう一つは平らで広大で果てしないという意味の「普」という字と一緒に使われることで、人々に湖の広大さと睡蓮の豊かさを想像させる。 4つの文章の中で、雲、雨、太陽、野生の杏、水リンゴのイメージの描写は、いずれも早春の兆しを完璧に反映しています。しかし、これがすべてだとすると、最も重要な動物がまだ行方不明になっているため、何かが完璧ではないようです。 5 番目と 6 番目の文、「白いガチョウは重い翼を低く飛ばし、コウライウグイスの舌は乾いていて、言葉はうまく伝わらない」は、この欠点を補っています。雨がまだ乾いていないため、白雁の翼は重くなり、低く飛ばなければなりませんでした。また、雨のせいで、ムクドリの舌は少し硬くなり、制御不能な感じがしました。しかし、片方は雨に濡れても踊り続け、もう片方は舌が痛くても歌い続けました。理由はただ一つ、ちょうど訪れた春がとても美しく魅力的だったからです。彼らの踊りと歌は早春の魅力をさらに引き立てます。 古人は「色彩豊かに早春を描き、特に中連句が目覚ましい」(『唐宋詩集』巻23)と述べ、三連句の重要な役割を指摘している。この連句によって、「南湖早春」の絵画が完成した。詩の最後の2行は作者の憂鬱な気分を表現している。こんなに美しい春を前にして、詩人は依然として興味を失っており、気分も落ち込んでいます。それは、詩人が心の中で大きな痛みを感じていることを意味します。当時、国は内外の難局に直面し、国力は日に日に衰えていましたが、詩人はただただ見ているしかありませんでした。降格された下級官吏にとって、たとえ優秀な人材や良いアイデアがあったとしても、それは何の役にも立ちません。国や国民を心配し、体調も優れない詩人が、どうして美しい春の景色を鑑賞する気分になれようか。同時に、春の景色が美しく、国や山河が美しいほど、国が滅び、家族が破滅するという恐ろしい結果を人々は心配するだろう。したがって、「長江以南の春は良くないとは言わないが、年々老いと病気で気分が落ち込んでいる」というのは、まさに、祖国と国民を憂慮する詩人が、爽やかで心地よい早春の風景を前に、将来を思い、前を向いたときのどうしようもないため息である。 早春なので他の季節と景色が違いますし、中春や晩春とも違います。詩人は、雨が止んで空が晴れ、反射した光が湖面に輝く夕方という特定の角度を選び、野生の杏、水リンゴ、白雁、黄岩など江南風の風景を描くことに焦点を当て、南湖の早春の魅力を生き生きと表現しました。まだ季節は早く、大地は目覚めたばかりで、野生の杏の花が咲き始めたばかりです。花は多くなく、湖や山の景色の中に点在しているため、「破紅」と呼ばれ、「ランダムドット」は、杏の花が無造作に咲き、至る所に点在している様子を鮮やかに描いています。 「混沌」とは、乱雑で無秩序なことではなく、自然で気取らないことです。詩人たちは西湖の春の景色について、「花が乱れてだんだん目を眩ませる」(『銭塘湖春の旅』)、「峰が乱れて水面を囲む」(『湖上春』)などと詠んでいます。「混沌」の中に、人工的な気取りのない、自然の面白さが感じられます。睡蓮は新芽を出し、葉を水面に平らに広げています。「平和」と「無秩序」が映し出され、春の無限の生命力を人々に示しています。この光景は水郷でしか見られません。季節が進み、春の色が濃くなるにつれて、睡蓮が湖面に伸びて広がり続けることを人々に感じさせます。一見静的な風景について書いた後、詩人は湖上のガチョウの影とオリオールの鳴き声を描写します。静と動、風景と音が互いに補完し合っています。厳しい冬が過ぎたばかりで、雁はまだ冬の怠惰な状態から回復しておらず、高く飛ぶのが得意ではなく、湖の上を低くゆっくりと飛んでいます。詩人は「重い」という言葉を使って、この時期の彼らの怠惰で不器用な状態を生き生きと表現しています。冬の間ずっと閉じ込められていたため、オリオールの舌は乾燥してしまい、最初に歌い始めたときも美しい歌声を出すことができませんでした。白雁は翼が低く、黄雁は舌が乾いていて、どちらも早春の特徴があり、とても興味深いです。彼らは詩人が描いた絵に動きの感覚を与えるだけでなく、音も与え、人々に彼らがもうすぐ翼を広げて高く飛び立ち、大声で歌うだろうと感じさせます。希望と活力に満ちた早春の風景を読者にお届けします。 白居易は「記事は時代に合わせて書き、詩は出来事に合わせて作る」と唱え、詩や散文の難解さや難解さを否定した。彼の詩は各家庭で朗読され、国内外に広まった。「少年は『長恨歌』を暗唱でき、胡少年は『琵琶歌』を歌える」という言葉は、彼の詩の分かりやすさと切り離せないものである。白居易が詩の洗練に気を配っていなかったと考えると、実際の創作とはかなり異なるものになります。時には彼の作品があまりにも自然すぎて、創作に注いだ苦労に人々が気づくのは難しいこともあります。この詩「南湖の早春」は、彼の詩作の技量と創意工夫をよく表しています。 詩人は雨上がりの晴れた最初の日という独特な角度から詩にアプローチしています。彼の詩は簡潔で生き生きしています。彼は冒頭から新鮮で鮮明な絵を描きます。暖かい風が吹き返し、雲が散らばり、雨が止んで空が晴れます。特に嬉しいのは、太陽の反射光が湖に輝き返し、すべてが暖かく明るく見えることです。詩人の気分もそこに暗示されています。連句の最初の 2 行は 14 語で構成されており、非常に多くの事柄が含まれており、その特徴が鮮明に表現されています。詩人は詩的な場面を素早く展開した後、湖の風景を巧みに描写します。野生の杏が初めて芽吹くとき、詩人は「ランダムな点」を使ってその自然の魅力を表現しています。リンゴの葉が新しく生まれたとき、詩人は「平らな広がり」を使ってその成長シーンを表現しています。どちらも非常に興味深いです。「ランダムな点」と「平らな広がり」は、もともと静的なものを動的にし、人々に春の継続的な成長の力を見せているようです。黄鵬は「まだ語り終わっていない」とよく言われるが、白雁が「まだ重く飛んでいる」というのは詩人の創作である。「重く」という言葉は、春先に白雁が翼を広げて高く飛ぶのが難しい状況を生き生きと描写している。詩人は何回考えた末に、白雁が頭を下げるほど印象的な「重く」という言葉を選んだのだろうか。白雁の「まだ重く飛んでいる」ことはまだ理解できるが、黄雁の「未完成の言葉」は絵では表現できないが、詩では伝えることができる。春は明るく美しく、詩人は影や人物を描き、色を塗ることも忘れません。野生の杏と水リンゴの「砕けた赤」と「新鮮な緑」が互いに引き立て合い、白いガチョウと黄色いワシが春の風景に彩りを添え、絵に躍動感と音を添えています。詩人が描いた鄱陽の早春には、動と静、音と色、視覚と聴覚と触覚があり、人々に全方位的な全体的な感覚を与え、人々に色鮮やかで生き生きとした春の光景を見せている。これは詩人の詩語の訓練と作文の配置に対する配慮と切り離せない関係にある。 風景の選択や言葉の使用は、結局のところ、外面的で表面的なものです。深く鑑賞すれば、この詩「南湖早春」は「風景の描写はすべて感情の表現である」と言えるほどで、詩人の精神と感情が実際に彼が描写する風景に注ぎ込まれていることに気づくのは難しくありません。風が戻り、雲が消え、雨が止み、空が晴れる。すべてがとても自然で、人々の願いと一致しています。風は人々の心の闇を吹き飛ばし、夕日に照らされた湖のように人々の気分を明るくすることができるようです。湖の穏やかな色彩は人々に暖かさを感じさせます。野生の杏や水リンゴも人々に春の無限の生命力を示しています。この早春の時期に、詩人も春の希望と暖かさを感じなければなりません。この詩は詩人が江州に流刑になったときに書かれたものです。その少し前、詩人は人生で大きな苦しみと挫折を経験したばかりでした。元和10年(815年)夏、宰相の武元恒が殺害された。忠臣の白居易は怒りに燃えて朝廷に嘆願書を出し、朝廷が殺人犯を逮捕し、国辱を洗い流すよう求めた。しかし、政敵から権力を濫用したと濡れ衣を着せられ、その年の秋に江州に左遷された。冬が過ぎて春が戻った今、彼の傷は徐々に癒え、長江南の春の景色は彼に心地よい驚きと安堵感を与えた。しかし、彼の心の暗雲はまだ晴れていない。飛べない白いガチョウも、まだ言葉を話せない黄色い岩も、すべて彼自身の影を運び、彼はそこに感情を託している。都から遠く離れた流刑地に春が戻ってくるのを見て、詩人の心は複雑だった。嬉しくて待ち遠しいけれど、心の中に溜まった悲しみを完全に取り除くのは難しかった。詩全体を見ると、詩人は心から揚子江南方の春の風景を愛し、それを隠し切れないでいる。「老齢と病気のため、年々気分が落ち込んでいる」と嘆いているが、春の風景が濃く深くなるにつれ、詩人の気分もますます明るくなるだろう。 |
<<: 張燕の有名な詩句の鑑賞:皿の上の透明な露は鉛の水のようであり、別の夜、西風がそれを吹き飛ばす
>>: 王維の詩の有名な一節を鑑賞する:九つの天の門が宮殿に開かれ、世界中の人々が皇帝に敬意を表します。
推薦する
『太平広記』第300巻の神代の原文は何ですか?
河東県の副長の妻である杜鵬菊、三人の衛兵、李曦、葉静能、王長齢、張嘉有ドゥ・ペンジュ景隆の末期には、...
『紅楼夢』で王希峰が仕掛けた毒のある恋の罠はなぜ批判されたのか?
『紅楼夢』の王希峰は賈睿に嫌がらせを受け、侮辱されたと感じたため、恋の罠を仕掛けたが、なぜこれが批判...
唐代の詩人、王維の『渭成曲』の原訳、注釈、鑑賞
王維は唐代の有名な詩人で、「詩仏」として知られています。それで、王維が袁児を安渓に送り出すために書い...
六朝の三人の英雄は誰ですか?中国美術史上有名な「六朝三傑」の紹介
六代の三大画家とは、中国絵画史上六代時代の有名な画家、東晋の顧凱之、南宋の陸旦偉、南梁の張僧有の3人...
第62章: サンリンタウン
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
賈家とは全く関係のない人物です!彼は長年、賈邸に住んでいたが、彼の財産が捜索されたとき、誰もそのことに言及しなかった!
本日は、Interesting History の編集者が Grand View Garden の謎...
劉備はなぜ、白帝城で諸葛亮に息子を託した時、馬謖は重要な任務に適さないと諸葛亮に告げたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
魏晋詩の鑑賞:七段詩、曹植は詩の中でどのような芸術形式を使用しましたか?
漢代の曹植の七段詩については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!豆を煮る...
李世民が貞観王朝を建国。どのようにして中国の黄金時代が到来したのでしょうか?
ほとんどすべての中国人は、古代中国の歴史の中で最も繁栄した時代は唐の時代であったことを知っています。...
『紅楼夢』の張華とその息子と賈家との関係は何ですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説で、四大古典の第一作です。今日は、Interesting...
前漢の有名な官僚、公孫洪の略歴 公孫洪はどのようにして亡くなったのでしょうか?
公孫洪(紀元前200年 - 紀元前121年)は、本名は洪、字は季、別名は慈青(『西京雑録』に記録)で...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 三仙人』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
中国のスタジオから生まれた奇妙な物語の中の「三人の仙人」の原文ある学者が試験のために南京へ行き、宿遷...
『紅楼夢』で賈おばあさんは林如海に対してどのような態度を取っているのでしょうか?なぜ嫌いだと言うのですか?
賈祖母は石太君とも呼ばれ、「紅楼夢」の主人公の一人です。以下の記事は、Interesting His...
張郃が殺された後も、曹魏のどの有名な将軍が蜀漢の北伐に抵抗できたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清朝の最盛期の人口はどれくらいでしたか?急速な人口増加の理由は何ですか?
清朝は中国で人口が急激に増加した時代でした。宋、元、明の時代の人口増加を基礎として、前例のない倍増現...